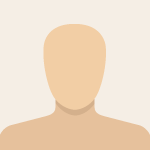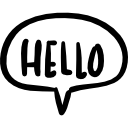Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- <h1>プロローグ</h1>
- かつて神は遠い存在ではなかった。
- それは思想や宗教の伝えるように崇高なだけのものでなく、もっと身近で飾らない、血のかよった存在だった。彼らも人が人を愛するように仲間を愛し、人が人を憎むように仲間を憎みもした。地上の歴史と同じように、神々の歴史も愛と憎悪に満ちていた。未熟な人間は自らを落としめて神を崇めてはいるが、神にもまた未熟な時代があったのだ。
- 語り部さえ知らぬ遥かなる昔、神々の大いなる戦いがあった。
- 野望に満ち、地上に降り立った邪悪神。その野望を阻むべく、天界より遣わされた精霊たち。その戦いも、わずかに神話として形をとどめるに過ぎない。歴史が語るのは、いつも断片だった。
- その頃、世界を形成する八つの大陸はヨモック、ヒナータ、ウビロス、ヒウケビロス、ミヨイ、タミアラ、オネスト、カーン。ふり返ればこの時代こそが、剣と魔法の時代の始まりだった。それまで人々は剣を持ち、魔法は神のものだった。もし、邪悪神が天界を追放されてこなければ、人間は科学という魔法を手に入れるまで、魔法というものを知るすべもなかっただろう。邪悪神は天界への憎悪を地上の箱庭ではらすかのように、魔の法を操り、破壊の限りを尽くした。
- その恰好の餌食となったのが、ウビロスの時の皇帝フヒド=ワラーだった。世界征服の野望を持つ彼の心は、苦もなく邪悪な波動と共鳴した。魔皇帝フヒド=ワラーは邪悪神の地上の姿と化したのだ。
- 果敢にも、その魔の手に立ち向かった者たちがいた。天界の七惑星の神々に仕えし民たちである。彼らは天界の神々の加護を受け、邪悪神の封印に挑んだ。
- その戦いの歴史は正史には残されていない。
- しかし、唯一残る書物がここにある。ブディドの初代大神官タミアラ=バドーの遺した書である。
- それにはこう記されている。
- ---我が祖先、天界の下僕なり。邪悪なるものを払わんと天界より降りて浄化を試みん。されど悪しきとも神なれば、完全なる浄化は不可能なり。操られし皇帝を抹消せしめしが辞世にて復活をいい残せし。その言葉、危惧残るものなり。魂の三体の封印。一つは岩塊の柱に呪縛させ、一つは肉体に宿りしまま結界の魔宮に封印す。そして残る一つを封印石ヒーロルにて封印を施すものなり。もはや人間になりたる子らに伝えん。その名、フヒド=ワラーなり。その記憶、失われんことを祈るものなり。我ら邪悪神グルの永遠なる眠りを見届ける民なり。
- <h1>第1章 乱心の傭兵</h1>
- <h2>魔物の叫ぶ夜</h2>
- 荒れ狂う吹雪の中、老人と少年は疲れ果てていた。
- 冷たい強風が唸り、吹雪は幻惑のように白い波紋を広げている。
- 旅に暮らす二人にとって、山で道に迷うことも、吹雪に曝されることも珍しいことではなかったが、今度ばかりは少し様子が違っていた。昨日の夕刻から歩き詰めで、陽はとっくに落ち、もう、どのくらい彷徨っているのか感覚も定かでない。まだ、宵のうちなのか、もう明け方を迎える頃なのか、それさえもわからなかった。
- 老人は旅の荷物を詰めた大袋を担ぎ、二、三歩歩くたびに振り向いて、少年がついてきているか確かめながら先を歩いた。振り向いた時の老人の目を見るたびに、少年は安心して新しい勇気を揮い起こした。老人の目はあきらめていなかった。永遠に続くかとも思われる吹雪を抜けて、必ず明日の太陽をその目で見る決意に溢れていた。
- どれくらい歩いただろう、寒さや疲れをほとんど感じなくなった頃、老人は吹雪の変化に気がついた。探していた音が聞こえたのだ。
- 強風が魔物の叫びのような奇妙な音をあげている。
- 「魔物の叫びだ……」
- 老人は冷たい強風が吹き荒ぶ中、希望を含んだ声で低く言った。
- 魔物の叫びとは、旅人の言葉で《吹雪の中の小屋》を示している。吹雪に迷ったら、耳を澄ませて魔物の叫びを聞け---。旅人の知恵からくる言葉だった。視界は遮られ、役には立たなくても、音の変化なら聞き取れることができる。小屋に当たった風は、ただ吹き荒れる風とは違って複雑にくねった音を届けた。吹雪の音に混じるわずかな音だが、生死の淵に置かれた旅人には希望の音だった。
- 二人は魔物の叫びを頼りに吹雪の中を進んだ。
- 積もり始めた雪に足を取られながら進むと、やがて一軒の炭焼き小屋に辿り着いた。
- 鍵はかかっていなかった。冬になるまでに使い切れなかったのか、小屋の中には炭と藁が少しばかり残っていた。老人はすぐに大袋を降ろすと、火打ち石を使って炎を起こし、土間の中央で炭を燃やした。それから少年のために、冷たい土間に藁を束ね、寝床をこしらえた。
- 「よし、これで寝床はできたぞ」
- 老人は炎の横にでんと腰を降ろし、震える手を少しだけ少年に伸ばして言った。
- 「キタラを取ってくれ」
- 少年は大袋を探りキタラを取り出した。老人はキタラの名演奏家だった。キタラは心の拠り所であり、街角で奏でることでパンを得た。老人の弾くキタラは、二人の生活の糧そのものだった。無事に吹雪から逃れて小屋に辿り着いたことを旅人の神に感謝し、一曲奏でるのかとも少年は思ったが、考えてみれば、未だ寒さに震える指先でキタラを弾けるはずもなかった。
- 老人はキタラを受け取ると、震える両手で持ったまま、何かを深く考えているようだった。老人は長い間そうしていた。
- そして表情を変えず、ふいにキタラを振り上げた。
- 「あっ……?」
- 少年は老人の気がおかしくなったのかと思った。
- 止める暇もなかった。老人は渾身の力で、硬く冷たい土間にキタラを投げつけた。
- 砕ける木切れや弦の音が反響した。飛び散った木片に混じり、一片の薪ほどの包みが中から飛び出した。羊皮紙にくるまり、細い麻紐でしっかりと結わえつけられている。老人はその包みを開けてみろと、目で伝えた。
- 少年が包みを拡げると、中から鞘に納まった銀の短剣が出てきた。鞘にも鍔にも細かな装飾が施された物で、掴には尾白鷲を象った彫り物がある。一目見て高価なものであるとわかった。もう何年も老人と旅をしてきた少年だが、老人の奏でるキタラの中に、こんな物が隠してあったなどとは少しも知らなかった。
- 「それは、お前のものだ。これからは、肌身離さず持っているんだ」
- 「キタラ……。壊しちゃったね」
- 少年には高価そうな銀の短剣より、美しい調べを奏でるキタラの方が価値のあるものに思えていた。
- 「いいんだ」老人は悲しい目をしていたが笑顔を見せて答えた。
- 少年はしばらく銀の短剣を眺めていたが、腰紐に通した小袋にしまうと、やはりもう一度、キタラの残骸に視線を移した。
- 「さあ、眠るがいい。大丈夫だ。火は見ている。お前はゆっくり休め」
- 老人はそう言って少年に背を向けると、木屑となったキタラを炎にくべ始めた。
- 少年は老人の容体を案じながらも、それを口にしなかった。何か話し掛けても「平気」だとしか答えないことを知っていたのだ。老人は少年には優しかったが、頑固で偏屈で厳格だった。どのようなことがあっても少年に自分の弱さを見せることはなかった。藁の上に横になった少年に、老人は背を向けたまま言った。
- 「出会いに気を配れ。お前の目で見たものを信じ、自分の心に感じたものを追うんだ。運命は決して平坦ではないが、お前なら歩んでいける」
- なぜ、突然そのようなことを言い出したのか、少年にはわからなかった。
- 外ではまだ、魔物の叫びが聞こえている。炎に弾けるキタラの木片が音をたてた。
- 少年は疲れていた。黙っている時間が過ぎるほど、小屋を揺るがす騒がしい吹雪の音も、心地よい子守歌に変わっていった。
- 少年は知らぬ間に目蓋を閉じ、眠りの世界に落ちていた。
- その夜、少年は不思議な夢を見た。
- 少年は広大な葦原の真ん中に立っていた。見渡す限りに広がる葦原は、緩やかな風に揺られて優しくなびいている。初めて見る景色だった。不思議にこれが夢であるという区別はついた。『待っているぞ……』誰かがそう言ったような気がした。
- 意識の世界では、心に止まったものから現象として現われる。
- その時になって葦原の向こうに、今まではなかった断崖が現われた。断崖の上部は巨大な波を思わせる形で大きくうねっている。確かにその断崖の方から呼ばれたような感覚があった。 集落だろうか、その下に幾つかの藁葺きの屋根も見える。夢にしては余りにも細部まで理解でき、奇妙なほど現実味を帯びていた。
- 誰かが葦原の向こうに聳える断崖の上で待っていようだった。
- 少年は自分を待つ存在を確かに感じとっていた。
- 吹雪は一晩のうちに嘘のように去り、優しい日差しが炭焼き小屋を照らしたが、朝になって少年が目覚めると、老人は冷たくなっていた。
- 眠る前、こうなるかも知れないとの予感はどこかにあった。
- 心に響く悲しみは深く、もう先程まで見ていた夢のことなど、少年の記憶から、すっかり消し去られていた。少年は泣かなかった。たった一人で丸一日をかけて老人を埋葬した。
- 名も知らぬ土地で屍となった老人は、自分の人生に満足だったのだろうか……。
- 十歳の少年は大人でも考えないようなことを思いながら、唯一の旅の道連れであった老人の顔を土で隠した。
- これからは一人きりだった。昨晩の老人の言葉が、何度も少年の心の中で響いていた。
- <h2>黒の神軍</h2>
- ガロアの国境の村、クアル。
- そこは、赤茶けた大地に暮らす者たちの貧しい村だった。
- 土地のほとんどは作物も育たない赤土で、開墾が可能な土地は、村の北東にある丘陵のわずかな部分だけだ。その土も冬は石飛礫のように硬く、村の生活の多くは山羊の放牧に頼っていた。ようやく鍬が使えるほど土もやわらぎ、待ちに待った春の到来に、村人たちは二日ほど前から丘陵を切り開いて作った段々畑に出ていた。
- 村人の一人が一息つけようと、作業の手を休めて腰を伸ばした。
- 段々畑からクアルの村が一望できる。赤土を塗り込めただけの粗末な家が、点々と五十戸ほどあるだけだ。小川さえなく、水は井戸に頼っていた。貧しくちっぽけな村だが、ここで生まれ、ここで死んでいく村人にとっては、ここが唯一の生き場所であり、ここが世界の全てだった。山裾で少年が山羊の群れを追っていた。見馴れた風景を見ながら、村人は気晴らしに丘陵を昇った。
- 丘陵の頂上から東を臨むと紅の街道がよく見えた。この辺り特有の赤土の土壌が、往来する旅人や商人に踏み固められ、赤い道となっている。紅の街道は遥か東の国ヒナータから続き、クアルの村を貫き、ダビ山の麓まで続いている。
- 東からガロアを訪れる者は、誰であろうとこの街道を通らなければならない。それは何の取り柄もない貧しいクアルの村で、唯一村人たちが誇りに思えることだった。
- 紅の街道の遥か向こうに土煙が上がっていた。土煙は大地を這い、たなびく雲のように舞い上がっている。遠過ぎるためか音は届かない。それでも耳をそばだてると、大地を踏みしめる馬の蹄の音が聞こえるようだった。
- 村人は黙々と作業を続けている仲間たちを呼び、土煙を指差した。
- ふいに大地を春の強風が渡り、視界をさえぎる土煙を拭い去った。村人たちは目を疑った。 黒い巨大な蛇が、紅の街道に添って這っていたのだ。
- 一人がようやく鍬を捨て、叫びながら段々畑を駆け降りる。その叫びはたちまち村の端々に軍隊の訪れを告げた。国境に位置する村の性か、一瞬の動揺はあったものの、村人たちの行動は手慣れたものだった。野鼠のように慌ただしく動き、隠すものは隠し、息を殺して未知の軍隊の通過を待った。
- ややあって、紅の街道から数えきれぬほどの武装兵が進軍してきた。黒い甲冑に身を包んだ兵士たちの行軍は、まるで兵隊蟻の行進を思わせた。村人たちは物陰に隠れて行軍の様子を窺っていた。ひそめた声が洩れた。
- 「あの旗、黒地に交わった二本の紅の鎌。ゲルニアの進軍旗だ」
- 「じゃあ、先頭の髭面がボルタイ将軍か?」
- 情報通の村人がボルタイの名を口にした。この村にも隊商はやってくる。時として商人から得る情報は国の間諜の調べより早く正確だった。
- 「ガロアが侵略される……。まさかゲルニア帝国がガロアにまで手を伸ばすとは……」
- 村人たちは馬上で胸を張る髭面の将軍の姿を見ただけでガロアの運命を悟った。
- 熊のような大男だった。兜の下の顔は黒い髭に埋もれ、その中から鋭い目と大きな鷲鼻がのぞいている。将軍の統制が行き渡っているのか、予想に反し整然とした行軍に、村人たちは少しずつ姿を現した。騎馬隊。槍や弓を担いだ歩兵。遠征に必要な食糧や物資を載せた荷車に牛車。そして、金色の馬車が厳かに通過する。
- 「あれは……。ゲルニアの皇帝、チャロナの馬車じゃないのか……?」
- 「皇帝も遠征に参加しているのか……」
- 「ごらんよ、あれだ」
- 現金なもので、直接自分たちに被害がなさそうだとみると、村人たちは行軍を囲むように両脇に出てきた。
- 六頭の白馬に引かれた馬車は全面金色に塗られていた。扉、窓枠、車輪を問わず、高価な美術品のように細部まで壮麗な彫刻が施され、窓の内側には真紅のカーテンが艶やかに揺れていた。村人たちの目は真紅のカーテンを追った。伝説の暴君フヒド=ワラーの再来と恐れられ、非道の侵略を続けるゲルニアの皇帝、チャロナが目の前を通っている。自国に進軍されているにも関わらず、一目でもチャロナを垣間見ることができれば、それだけで重要な歴史の場面に出くわしたという、希に見ぬ体験が得られるとでも思ったのか、奇妙な興奮が村人たちの心を支配した。
- 行軍はクアルの村を全く無視していた。荒らくれた雰囲気もなく、整然とした行軍を続けている。村人たちには、その静けさが余計に不気味でもあった。
- 日々の暮らしに追われる村人には、国が滅ぼされようとも国王が代わろうとも関係なかった。
- ただ、この場だけ、何事もなく通り過ぎてくれと祈るばかりだった。
- 「どうしてあいつだけ、黒い鎧つけてないんだよ。なんで一人だけ赤い鎧つけてんのさ?」
- 突然、無邪気な少年の声が聞こえた。袖のないボロボロの麻服を着ただけの少年は、周囲の緊張を余所に、一人の傭兵を指差していた。
- 「こらっ、指を差しちゃいかん」歳のいった村人が慌ててたしなめた。
- 別の村人が小声で答えた。
- 「傭兵だからだ。金のためなら関係のない国の人間までも殺す奴らだ……」
- 確かにその兵士だけ異質だった。一人だけ血のように赤い鎧に身を包み、うまそうに林檎の実を齧っている。鼻筋の通った精悍な顔立ちで、兜もつけず、伸ばし放題の髪は乱れ、焦茶色にちぢれていた。傭兵は黒い瞳で少年を見た。
- 「坊主!」
- 弾みのある鋭い声が響き、村人たちはすくみあがった。
- 傭兵は少年に向けてニヤリと笑みを見せると、少年を狙い、齧りかけの林檎を放った。
- 少年は宙を舞う林檎を受け止めた。一瞬、固唾を飲んだ村人たちの緊張も、波が引くようにそこで消えた。
- 振り向くと、傭兵の姿はもう、行軍の流れの中に紛れ込んでいた。
- 少年は林檎の実を握り、遠くなっていく赤い傭兵の背中を目で追った。埃まみれの行軍はまだまだ続いた。後から後から兵士たちが横切って行く。だが少年には、もう、赤い傭兵の背中しか目に入らなかった。
- 少年の名はカーイと言った。少年は自分が何処で生まれたのかも知らない。
- 親の顔さえ知らず、気がついた時には歳老いた伯父のルードと諸国をさすらっていた。自分が十二歳であると知っているのも、以前、伯父に聞かされた年令に毎年加えているだけのことで、それが本当の歳であるかも定かではない。好奇心をあらわす頃になって伯父に自分のことを尋ねることもできたが、ルードとの旅には、その話題に水を向けない暗黙の壁があった。カーイは伯父が好きだった。だから話の成り行きで、その方向に話題に向くたび表情を曇らせる老人を見たくなかった。いつの頃からかカーイは自分のことを訊くのをやめた。
- その伯父も二年前に死に、独りぼっちで辿り着いたのがこの村だった。
- 少年には赤い傭兵が、ずっと昔から知っている知り合いのように思えた。初めての出会いであるにも関わらず、不思議な懐かしさを秘めた感覚だった。
- この地で赤い傭兵に出会ったことが、何か特別な運命のように、カーイの心にくっきりと刷り込まれていた。
- 赤い鎧の傭兵はアレスと言った。
- 全ては成り行きにまかせ、傭兵にもなれば用心棒にもなる、脈絡のない男だった。
- 適当な賞金首がいれば賞金稼ぎで食いつなぎ、今回のように大規模な戦が勃発すれば、道理の善悪に拘らず、儲けが深そうな側に平気で身を預けた。故郷を捨て十年。自らの剣技だけを頼りに放浪を続けるアレスは、すでに二十二の歳にして、老獪な刃を心に隠す剣士となっていた。
- アレスは国境の村で擦れ違った少年のことを思い出していた。
- ---貧村の浮浪児か……。ああいうガキはどこにでもいるもんだ。
- 戦場となった村で泣き叫ぶ子供を何人も見ていた。親を殺された子供の、恨みの篭もった瞳も、放心して何も言えなくなった子供も見た。あの年頃で悲しみを背負った子供には、共通する匂いのようなものがあった。その匂いをあの少年に感じていた。だが、少年の瞳は闇を燈していなかった。そのことが奇妙なほど新鮮で、しばらくの間、忘れかけていた過去の自分を思い起こさせていた。アレスが村を出たのも、丁度あの少年と同じくらいの歳だった。もう十年になる放浪の中で、自分のことなど一度も振り返ったことなどなかったが、名も知らぬ少年を介して蘇る郷愁は無限に湧き出す泉のように止めどがなく、アレスの険しさに馴れた感情を洗い流していった。
- ---戦の前に思い出すことではないか……。
- アレスは強引に意識を閉じ、ガロアとの戦いのことだけに意識を集中させた。
- 気になっていたのか、隣を進む古参の傭兵が少年と同じことを訊ねた。
- 「ゲルニア帝国に雇われた傭兵は、誰も皆、ゲルニアの鎧を身につけることになっているはずだ。なぜ、他の者のようにゲルニアの鎧を身につけない?」
- アレスは答えなかった。
- 「せいぜい味方に討たれんことだな」
- 答えないアレスに古参の傭兵は吐き捨てるように言った。いつもの自分を取り戻したアレスは、報奨金のことで頭が一杯だった。ガロアの国王ダムチには三千ゴールドの報奨金が懸かっている。
- 予定どおりに進めばダビ山で野営があるはずだった。
- ---決戦が始まる前に、戦いの全貌を把握する必要がある。野営で味方陣営の情報を収拾しておくのも悪くない……。
- アレスは一流の傭兵は賞金稼ぎであると信じていた。手柄を立てない限り戦う意味がない。そしてそのために何をすればよいかをよく心得ていた。
- ---名誉を重んじるガロアのことだ。国王自らが指揮を取り、最前線にのこのこと出て来るのは目に見えている。俺にもダムチの首を跳ねるチャンスはある。
- アレスは一人楽しい皮算用に北叟笑んでいた。
- ガロアはヒウケビロス大陸のほぼ中央に位置している。
- 収穫の少ない領土ではあったが、国王ダムチの善政によって国家は平穏に統括されていた。
- カウラン城は森林に囲まれた美しい緑の中にあった。ゲルニアの矛先がガロアに向けられたとの知らせが届いたのは、つい一週間ほど前のことだ。国王ダムチは即座に密偵を放ったが、各地から情報が集まるにつれ、ガロアの官吏たちの顔は土気色に変わっていった。
- 「まさか、これほどまでに早く……」
- 「ゲルニア軍、クアルを通過!!」
- 「そろそろ紅の街道を抜けてダビ山に差しかかる頃であります!!」
- 「敵の総勢は?」
- 「およそ、二万五千の大遠征部隊と思われます!!」
- 「こちらの情報では三万はいるとのことだ!」
- 「馬鹿なっ!!」
- その時、喧騒をたしなめる声が室内に響いた。
- 「それでも誉れ高いガロアの兵か! 動揺に身を任せては冷静な判断はできまいぞ!」
- 声の主は国王ダムチの腹心、フォルト=ギルダンだった。フォルトは先代よりガロアの摂政として仕える、厳格な表情を湛えた老人だった。国王、官吏ばかりでなく民衆からの信頼も厚く、これまでこの国が平穏に営まれてきたのも彼の貢献によるものが大きいと誰もが認めていた。
- 「フォルト殿」
- その老人の背に、影のように存在感のない声が掛けられた。
- 画策士ミアラ=ドドーである。群青のローブを纏ったミアラは、包み込むように背を屈める一礼をした。フォルトより、さらに一回りほど高齢であるにも関わらず、足腰の衰えた様子もなく、魔道を極めたミアラは、初老そこそこで歳をとるのを止めたかのように見える。
- 「ミアラ、報告は出揃ったか?」
- 「こちらへ」
- ミアラはその場での報告をためらった。
- 二人は広間を出て、人気のない回廊を選んで歩いた。足音だけが荘厳な踊り場に響き、やがてフォルトとミアラは宮廷に面したバルコニーの一角に辿り着いた。見下ろせば、眼下の宮廷では豆粒のようなガロアの兵士たちが出陣の準備にかかっている。フォルトは不安げな視線を兵士たちに投げ掛けた。
- 「フォルト殿。ゲルニア軍は、四万を越える兵力」
- 「四万だと……」
- 「黒騎士隊長ボルタイ率いる騎馬部隊、二万騎。さらに弓や槍を携えた一万五千の歩兵。しかも、それら正規軍に合わせ傭兵を引きつれております。ウビロス大陸をほぼ手中にしたチャロナは、このガロアの地を落とし、ヒウケビロスの拠点にする腹積りでしょう」
- 「拠点だと? 舐められたものだな。すでにゲルニアは次の戦いを考えているというわけか」
- 「おそらく、奴らの本当の狙いは世界最大の大陸トーラス。ウビロスからトーラスを狙うには、海路を進むより、ヒウケビロスを経由し、陸路を渡る方のが効果的だと考えたのでしょう」
- フォルトは視線を伸ばしガロアの街を眺めた。ガロアには三万の民がいたが、その民を上回る大侵攻部隊がこの国に踏み入ろうとしているのだ。
- 「すでに二千の兵を配備しておきました」
- 「策があるのか?」
- 「策はございます。ただ、今回ばかりはお覚悟が必要かと」
- 「よかろう。その旨、ダムチ様にご報告し、ご判断いただく」
- 告げなければならない言葉を頭の中で反芻しながら、フォルトはミアラと別れたその足で国王ダムチの元を訪れた。
- ダムチは玉座に静かに腰を下ろしていた。二十五の歳に即位して十二年、若く公正で勇猛な君主は、いささかの動揺も見せずフォルトを迎えた。
- 「申し上げます。現在、クアルの村に四万に及ぶゲルニアの進軍を確認いたしております。おそらく街道を上り、ダビ山の峠で朝を待つものと思われます」
- 「手は打ってあるのか?」
- 「はい。伏兵の配置は終えております。ミアラの読みが正しければ、敵が襲撃をかけてくる前に打撃を与えることができます」
- 「そうか」
- 「しかし。四万の兵に対し、我が軍は正規軍三千名、人民兵、傭兵を合わせても、五千を満たせませぬ……」
- 「ミアラはどう言っておった?」
- 「策は尽くしますが、お覚悟をと……」
- 沈黙が流れた。フォルトは国王の言葉を待った。ダムチは一度目蓋をゆっくりと閉じ、そして開くと、涼やかな表情で告げた。
- 「フォルトよ。戦いの助けにならぬ老人、女、子供をすみやかにブディドへ逃がすがよい。東洋の神秘国ブディドならば、奴らも容易くは手を伸ばせまい。村々の者にもふれを出せ。残るも去るも自由とな。お前には脱出民の指揮を命ずる」
- 「陛下、戦うのであれば、是非とも御供を……」
- 「言うな。万がいちの場合、頼みは、お前が連れ行く民となる」
- フォルトには言葉を返すことができなかった。
- 「道は決まった。ミアラを呼べ。それから……ヘグリスを頼む」
- 「ヘグリス王子は命に代えてもお守り申し上げます」
- 国王にとって気掛かりは、幼い王子の身だった。若くして病で他界した王妃イリスとの子、ただ一人の王位継承者ヘグリス。国王の目は遠くを見つめていた。
- 国王ダムチが決断を下すとガロアの行動は速く、しばらくもするとカウラン城の宮廷には準備を整えた兵士たちが整列した。伏兵についた第一陣と合わせても五千に満たない兵力ではあるが、腹を据えた兵士たちの風貌はどれも凛々しかった。
- 「敵は遠征で疲れておる!! 無法を尽くすゲルニアに、目にもの見せてくれようぞ!!」
- 白銀の鎧に身を包み、兵士たちの前に出た国王ダムチは叫んだ。先頭のミアラに続き、兵士たちは門に向かって流れ出した。
- ダムチは険しい眼差しで歩み出した兵士たちを見ていた。
- 「陛下」
- 脱出民の指揮にあたっていたフォルトが語りかけた。
- 振り返るとフォルトに伴われ、まだ八つになったばかりのヘグリスの姿があった。
- 「父上!」
- ダムチは飛び込んできたヘグリスを体で受け止めた。
- 「ヘグリスよ、爺の言うことをよく聞くのだぞ」
- 八つのヘグリスに、この事態がどこまで理解できているのかダムチにはわからなかった。ダムチは静かにヘグリスの体をフォルトに押しやった。
- 「フォルト、くれぐれもヘグリスを頼んだ」
- 「承りまして御座います。御武運を……」
- ダムチは馬に跨がり、もう一度ヘグリスを見ると、勢いよく隊列の先頭に向けて馬を繰り出した。
- フォルトは幼い王子とともに戦場に出る国王の背を見送った。国王の命令に従うのが、今の自分にできるせめてものことだった。慌ただしい出兵を見送りながら、ガロアの忠臣フォルト=ギルダンはブディドへの長い道のりを思っていた。
- <h2>託宣</h2>
- 紅の街道は果てしなく続いている。ようやく国境の村を通過したものの、ゲルニアの大遠征部隊は代わり映えのしない赤土の道を進んでいた。
- 「夜を迎える前にダビ山に着きたいものだが……」
- 隊の先頭を務めるボルタイが、隙のない目を細めて呟いた。少しでも早く、兵を休ませたかった。予想以上に乏しくなっている食糧も心配だった。
- 背後から伝令の早馬が近づいた。手綱を引き締める声に一瞬馬が二足立ちになり、兜の下から瑠璃色の長髪がはらりと流れ出た。近衛兵団隊長のジュミレスである。
- 今回の遠征は皇帝自らが行軍に参加している。そのために、ほとんど本国から離れることのないジュミレスが、珍しく遠征に同行していた。そのせいか、この遠征で皇帝のチャロナが直接命令を下すことはなく、いつの頃からかジュミレスが代弁者として命令を伝えるようになっていた。本来全権を任されるはずのボルタイにしてみれば面白くないことだった。ジュミレスは馬の速度を緩め、器用にボルタイの馬に歩みを合わせた。 「皇帝の伝令を伝える。ダビ山にて野営せよとのことである」
- 女のように透る声でジュミレスは伝令を伝えた。今更聞かされることでもない。ボルタイには承知済みのことだった。
- 「聞いているのか?」
- 重い表情で反応のないボルタイにジュミレスが訊ねた。
- 「……わかった」
- 明らかに取りつくろった返事だった。ジュミレスは勝ち誇ったように形の良い鼻を空に向けると、満足気な表情で馬を戻した。
- 「いけすかぬ野郎だ。皇帝の代弁者でなければ、とうに始末したものを……」
- ボルタイは視界から消えたジュミレスに心の底から悪態をついた。
- 黄昏が迫り始めた頃、ゲルニアの行軍はダビ山の麓に到達した。眼前のダビ山を越えればガロア東南のコルア地方の圏内になる。ゲルニアの行軍は紅の街道を外れ、岩肌を剥いだような峠に次々と踏み行った。
- 「この峠の上で野営を行なう! もう少し踏張ってくれ!」
- ボルタイが何度目かの檄を飛ばす頃、辺りはすっかり闇の中へと飲み込まれた。
- ダビ山で野営の準備が始まった。野営の本陣は山頂の平地に置かれ、それを中心にとぐろを巻く蛇のように兵が囲んだ。四万の大部隊である。山頂に場所がとれるのはわずかな兵だけで、多くの者たちは山頂から峠にかけての身を隠す場所もない、固く冷たい土の上で夜をしのぐしかなかった。
- アレスは手頃な岩に馬の手綱を結ぶと、飯炊き兵の出す温かな匂いに誘われた。焼いたイノシシの肉を受け取ると、それを片手に、松明を囲む兵士たちの間に加わった。
- 他愛のない自慢話が始まっていた。
- 「明日の俺を見て驚くな。タリウスの戦で二十人は斬ったんだぜ」
- 「ほう、タリウスの戦いか」隣の兵士が調子のいい相槌を打った。
- 「おいおい、俺だってトーラスの内乱では褒章ものの働きだったぜ」
- 「トーラスか。稀代の戦士マトリ=カークランドと一緒に戦ったもんだ」
- 歳のいった傭兵が目を細めて懐かしそうに言った。
- 「あの、マトリとかい?」驚きと憧れが入り混じった表情で若い傭兵が訊ねた。
- アレスもマトリのことなら知っていた。マトリは同郷アシュワの英雄である。トーラス大陸の片田舎の村のことなど知らなくても、英雄マトリの名を知らない者はなかった。アレスがもの心ついた頃から、マトリは伝説の人物だった。傑出した技に操られる剣。厚い人望。的確な判断に裏付けられる大胆な行動は、彼が戦略家としてもいかに有能であるかを物語っていた。マトリとアレスの父シドは、一時期、トーラスのベルトハイム城に宮廷戦士として仕えた仲だった。二人とも、生きていれば五十に手が届きそうな歳だった。
- やがて兵士たちの話は、自然にマトリの消息についての話題に移った。
- 「マトリは何処にいるんだろうな?」
- 「まだ生きてるのか?」
- 「さあな、噂ではトーラスの内乱以降は誰も姿を見ていないそうだ」
- 「英雄も、死んでしまえば、ただの夢物語か」
- マトリの消息は誰も知らなかった。
- 知らない。分からない。そして、いつの間にか兵士たちの中で、マトリは死んだものとなっていた。それがアレスには、妙に可笑しかった。
- ガロアの国王ダムチが人民の逃亡地としたブディドは、広大なトーラス大陸の南端に位置していた。大河を二本に仕切るデルタ地域に発達した自治宗教国家であり、この地に伝わる伝承では、およそ三百年前に水没したと言われるタミアラ大陸より渡来した六人の賢者によって興された国とされている。本来ならトーラスの君主ベルトハイムの統括地に当たる国であるが、彼自身の系譜がタミアラに遡るという理由から、政治的干渉を受けることもなく、自治国家として成立していた。
- 天界の力と意識を直結することにより、自らの魂を昇華させることを基本に置いたブディド教は世界各地に多くの信者を生み、瞬く間に世界中に広まった。
- 国の中には常に世界各国から集う神官や僧侶の姿が見える。ブディド教の者だけではなく、あらゆる宗門宗派の道師が集っていた。彼らは異教徒でありながら、自らが信じる教えを探求するうちに、どうやらその起源がブディド教に伝わる失われた大陸、タミアラから発生したのではないかという考えに至った人々だった。
- もちろん末端の信者においては、自らの信じる神が絶対であり、他は邪教と決めつけるきらいもあったが、巡礼としてだけでなく、哲学、宗教学の探究を目的にブディドを訪れる者は皆、真摯な態度を保っていた。
- 大小幾つものドーム状の屋根を持つ聖堂が建ち並ぶ町並みは、各々の宗門を表わす衣服を付けた人々でごったがえしている。赤や黄の原色を使った派手な衣装を着た僧侶がいると思えば、黒いローブを身に纏い、顔まで布で隠した地味な神官も往来している。さながら宗教の万国史を一堂に会したような情景だ。
- 中央の大聖堂に向かう幅広い参道には、継目がわからないほどきっちりと、薄茶に霞む石畳が敷き詰められていた。
- 参道の両側には等間隔で石柱が並び、石柱同士を繋ぐようにして、人の肩ほどの高さの石塀が組まれてあった。左側の石塀には、通りの入口から大聖堂に至るまでの間、古代文字の碑文が刻まれている。ここが建築された時、タミアラ大陸から伝わったとされる経文を刻みつけたものだ。左から右に流れる横書きの文字は実に不可解なものだった。
- その内容は不明で、それがここを訪れる者たちの第一の研究対象となっている。文字の一つ一つは日乾し煉瓦ほどの升状に区切られ、直線と曲線の組合せでできていた。中にはアヒルの形のような象形文字を思わせるものもあった。
- その聖職者ばかりの国に、一見してそぐわない剣士の姿が見えた。さっぱりと分けた銀髪に屈強な体躯。初老の剣士だった。男は鋭い眼差しで石塀の文字を見つめている。石塀に刻まれた文字を指でなぞり、何かを考えていた。その目は肉体だけに頼る剣士にはない、並み外れた聡明さを湛えていた。
- 男はゆっくりと文字から指を離すと、通りを大聖堂に向けて歩み出した。
- 老剣士は人の溢れる大聖堂の前の広場を折れ、参礼殿に向けて足を進めた。大聖堂の敷地には別棟に参礼殿があった。一見すると円形劇場を思わせる建物である。参礼殿はブディド教の神官が託宣を受けるためにあり、一般の信者や外来者が大聖堂で礼拝するのに対して、高位の信者のみ入場を許される所だった。参礼殿のアーチをくぐると、地味なローブを纏った老人が立っていた。わずかな風に揺れるローブが枯れ枝に掛かった布のようにたなびいている。老人は来訪者を見ると、柔和な顔で迎え入れた。 「マトリ、久しぶりじゃな」
- 「大神官カンベーテ、お久しゅうございます」
- マトリと呼ばれた老剣士は堅苦しいほど丁寧に答えた。
- 「私が来るのがわかっておられたのですか?」
- 「そのくらいは、風が教えてくれる」
- 老人の頭髪はきれいに剃られ、鼻下と顎から植物の根のように白髭が伸びていた。 「確か、前にここに来たのはトーラスの内乱が起る前じゃから、もう十年になるか?」
- 大神官は独り言のようにそう言うと、背を向けて先に歩いた。
- 奥へと続く回廊は、明かり取りの窓から入る淡い光に照らされていた。
- 左回りに建物の外周にそってしばらく歩くと、左側に中心の部屋に入る扉が現われた。二人は無言でその扉をくぐった。中心の部屋には天井がなかった。星の運行を読むために吹き抜けになっているのだ。大理石の床には水を流すための溝が幾筋も走り、真ん中の小高くなった台座を囲むように四方には篝火の用意がされている。
- マトリは初めて見る参礼殿の内部に圧倒されていた。
- 「ここは初めてであったな?」
- 「はい。以前訪れた時には、表で託宣を待っておりました」
- 「己が目で確かめるのもよいじゃろう」
- 「ありがとうございます」
- 「神事を行なう時は火を掲げ水を流す。篝火はサラマンダーを象徴し、水はウンディーネの力を象徴する。力はいつも精霊とともにある。そして天界と対話するのじゃ」
- 「精霊とともに……」
- 「そう。ときに、スクネ殿は健やかにしておいでかな?」
- 「はい、祖父は今もアシュワの地で健やかに」
- 「そうか、なによりじゃ。スクネ殿はもう十分にお働きになられた。残る余生は静かに送っていただきたいものだ……」
- 「祖父の命を受け、お願いがあって参りました」
- 「やはりな……。安住は見つけられぬようじゃな。十年ぶりに訪れて……しかも、新月の日を選んでやって来るとは余程のことと察するが」
- 皺だらけのカンベーテの眉間に、さらに深く皺が刻まれた。
- 「はい。ゲルニアの皇帝、チャロナのことはご存じでございましょう?」
- マトリは幾分表情を曇らせながら神妙に訊ねた。
- 「侵攻を続けるゲルニアのことは聞いておる」
- 「ゲルニア帝国の皇帝、チャロナなる者。フヒドの想念を受けたに相違ないと思われます。十年前、世界に蔓延した流行病も、各地で勃発した内乱も、その悪しき想念の影響であったのでしょう。アシュワも手ひどくやられました」
- 「それで、スクネ殿はどのように?」
- 「まずは戦士を集めよと。魔神の行動を阻止できるのは、かつて天界よりきたる我々の祖先、天界の精霊の血を色濃く残す者たち以外には考えられぬとのことです。つきましては、大神官のお力をお借りしとうございます」
- 「戦士の所在を占えと言われたのじゃな。力に対し、力で迎え撃つか……」
- 聖職者には気の重い話だった。
- 「相手が魔神ならば、それもいたしかたありません」
- 「しかし、すでにそれだけの力を残す者が、この世界に存在しなければどうする?」
- 「我々が、初めてフヒドの想念を察知したのは十年前、あの時、考えられる限りの手を尽くし、フヒドの復活を阻止しようと試みました。確かにあの戦いで、多くの者が帰らぬ者となりました。しかし、フヒドの力をある程度抑えることはできました。十年という時間を稼ぐことに成功したと考えたいものです。新たなる戦士たちが育っていることを、私は期待したい」
- 「人は長い間、星に願い、星に祈り。ある時は星を呪って生きてきた。その思いが届けば良いのじゃがのう。だが、大いなる天界の力は、人の為にだけあるものではない」
- カンベーテは中央の台座に上がると、両膝をつけて跪き、円形に抜けた天井から空を見上げた。咳払いのような気合いを二、三度発っすると、火をくべたわけでもないのに四方の松明に火が燈り、大理石の溝に水が流れ始めた。水はせせらぎのような音をたて溝を渡った。
- 参礼殿内の空気が一瞬にしてひんやりとした神気を帯び、託宣の儀式は始まった。
- 「うう……ああ……おお……」と、喉からしぼり出す気合いが響き、か細い外見からは想像もできないほどの強力な波動が年老いた体から放たれた。
- マトリは信じられない光景に目を見張った。陽の光を投げかけていた天井の青い空が、曇りガラスを透過したように入射光を緩やかに遮り、少しずつ明るさを弱めた。昼間の空は、陽の光を弱めるだけでなく、わずかに歪みながら夜の星空へと変貌していった。空は瞬く間に星々の煌めく夜空となった。
- 「見逃すな」
- 「はい」
- マトリは何も見逃すまいと星空に目を凝らした。
- ふいに、星が一つ流れた。
- 「見えたか?」
- マトリは星空を見据えたまま頷いた。
- 「星はガロアからカーンに流れる」
- 「ガロアからカーンに……?」
- ゲルニア帝国はヒウケビロス大陸のガロアに侵攻を企てる動きがあるとの情報は、マトリも掴んでいた。
- ---狙いがガロアであるならば、すでにその動きの渦中に捜すべき者も組み込まれているというのか……。だが、カーンに流れるとはどういうことだ……?
- 頭上の空が昼間に戻っても、視線はまだ、星の流れた場所を見つめていた。
- <h2>決戦前夜</h2>
- 野営の松明は、ダビ山の尾根にへばりつくサラマンダーのように延々と続いている。
- 圧倒的な兵力の差に、明日の勝利を疑わないゲルニア兵たちは酒に手をつけていた。野営の賑わいの尽きる気配はない。
- アレスは黒い陣幕で覆われた本陣の前まで来ていた。
- 入口には、厳つい顔をした門衛が左右に立っている。陣幕の内側には三つの巨大なテントが設置され、その中心に皇帝の馬車があるようだった。アレスは用事がある風を装い、門衛たちに軽く右手を上げただけで陣幕の関門を素通りした。あれこれ策を弄するより、自然な行動が何よりも有効なこともある。
- 人の気配のあるテントは司令室にあてがわれているはずだった。目星をつけ、密接する隣のテントに潜り込んだ。中は薄暗く、麻の生地を透かし、何があるのか仄かに識別できる程度だった。食糧、酒、旅の必需品など、傭兵たちの前には出せない様々な資材があった。
- アレスはテントの隅々に鋭い視線を投げた。人の気配はない。テントの端に風抜き用の隙間があるのを見つけた。そこからそっと外を窺うと隣のテントが見えた。煌々とランプの明かりが洩れている。内側から放たれる明かりは、中の者たちを影絵のように映し出していた。
- 耳を傾けると、わずかに中の者たちの声が聞こえてくる。近衛兵団のジュミレス隊長やボルタイ将軍らが最終の侵攻作戦を詰めているようだった。
- 司令室にあてた野営のテントでは、ジュミレスが自らが立てた作戦を語り始めようとしていた。
- 「さて、私の立てた作戦だが」
- ジュミレスの白く細い指が、組み立て式のテーブルに拡げられた地図の上を移動した。ガロアの東南コルア地方のものである。指はその地図のほぼ中央にあるカゴヤラという村の上で止まった。カゴヤラならば、現在地から夜でも往復が効く距離である。
- 「カゴヤラの村だ。ガロアのカウラン城からもちょうど直線上にあたる。ここをまず落とす。一気に攻めれば容易に落とせる。先兵隊五千名によりカゴヤラを夜襲し、明朝そこに本陣を移し、カウランに攻め入るといった作戦だ」
- ボルタイは黙って地図を見ていた。地図の北東が現在陣のあるダビ山。そこから尾根づたいに西南に向かうと両側は深い森林となる。ここで二つの道が選択できた。一つは尾根を南に進み、山道を通ってカゴヤラに行く道。もう一つは、そのまま西南に突き進み、キニドバの谷を経由する道である。どちらもカゴヤラに出ることに変わりないが、微妙な選択が要求される。
- 山道は敵に悟られにくいが兵の移動が困難だった。逆に谷を行く道は見通しが効く分だけ敵にも見つかりやすい。行軍による兵の疲労が少なくとも、万がいち待ち伏せにあえば、かなりの被害は免れないだろう。無論、この二本の道がすべてという訳ではない。攻撃の成果だけを考えれば、あえて森林を突き進み、秘密裏に懐に入るという手もある。だが、夜の行軍を前提とする以上、魔物の出没も予想される森を、土地勘もない兵士たちに歩かせるのは避けた方が賢明だった。まして後々の合流を考えると、道のあるところを選んで進むのが良策に思える。ジュミレスが敵の画策士ミアラ=ドドーのことを念頭に入れていないのも、ボルタイは気に入らなかった。
- ---功を焦り、先手を狙うことだけが戦さではない。勝利を急ぐより、今は兵士たちにできるだけ休息をとらせるべきだ。勝利は明朝堂々とつければよい。それでこそ黒の神軍と恐れられるゲルニア軍なのだ。
- 動かないことが良い時もある。むしろ皇帝のいるこの野営地の護りを固めるのが先決だと、ボルタイは腹の中で自分なりの結論を導きだした。
- 「先兵隊には反対だ」ボルタイは低く太い声で言った。
- 「なにっ!?」目をぎらつかせたジュミレスがボルタイを見た。
- 「すでに敵との距離が縮み過ぎている。地の利は敵にある。敵の参謀は手だれの画策士ミアラ=ドドーだ。迂闊に動くより、朝を待つのが得策。むしろ、敵の襲撃に備えて本陣の守備を固めるべきだ」
- 「臆病風に吹かれたか?」
- 「戦いでは、必ずしも先手が必勝ではない」
- ボルタイは譲らない。ジュミレスの表情が不愉快に歪んだ。
- 「手緩いな。本来ならば、先兵隊の夜襲ですべてのけりをつけるのが本道というもの。どうだガイソン、お前はどう思う?」
- ジュミレスは大隊長のガイソンに水を向けた。あくまで先兵隊による襲撃を決行するつもりだった。しばらくの間があり、ガイソンはか細い声で答えた。
- 「皇帝の御意志のままに……」
- ジュミレスにもボルタイにも反対できない苦しい答えだった。
- 「皇帝の意志は私と同じである」ジュミレスは言い切った。
- 皇帝の名を出されては、ボルタイに反論の余地はない。胸中に思いを呑み込み、押し黙るしかなかった。
- 「分かったな、ボルタイ将軍」
- 挑発するようなジュミレスの物言いにも、もうボルタイは異論を唱えなかった。
- ジュミレスは反論がないことをいいことに、さらに言葉をつけ加えた。
- 「先兵隊の指揮は私がとる。ボルタイ将軍はここに残り、皇帝をお守りしていていただこう。では、準備でき次第、すぐに出兵する。以上だ」
- ---はねっ返りの近衛兵が、何処までやれるか見てやろう。
- ボルタイは自らの立場を傍観者として決め込むことにした。
- 盗み聞きのアレスは、暗いテントの中で仕入れた情報を分析していた。
- ---先兵隊を送るつもりか。しかし、ボルタイとジュミレスがこれほど仲が悪いとは……。先兵隊が先に出るとなれば、少々厄介だ……。
- このまま本陣で待っていても、賞金首を逃すだけに思えた。
- アレスは手近な酒樽を肩に担いで表へ出ることにした。こうすれば、もし尋問を受けても酒を取りにきたと言えばいいし、それが嘘だとバレたところで酒泥棒以上の罪にはならない。
- テントを出て数歩歩いた時、物陰で眠っている倉庫番を見つけた。
- 見咎められた時の言い訳まで考えていたアレスにとっては、いささか拍子抜けだった。
- だが、落ち着いて見直すと、気配が違う。
- 「ん……!?」
- 男は呼吸をしていなかった。緊張がアレスの体を貫いた。
- ---どうする。黙って行き過ぎるか?
- 自問しながら男の体に目を走らせた。すぐにわかる外傷はない。首筋を確かめると吹き矢の刺さった跡があった。痕跡に毒のぬめりがある。
- 微かに呪文のような声が聞こえた。誰かが何かを唱えている。アレスは酒樽を静かに地面に下ろし、異質な響きに耳をそばだてた。呪文は低く地を這うように届いていた。気配を頼りに進むと、三つ目のテントの影の最も闇の深い部分に行き着いた。立ち止まり、気配の辺りにじっと目を懲らす。蠢きのような気配は、テントの裏側から発せられていた。そこだけテントの生地を潰す闇の空間が、奇妙に歪んでいるように見えた。
- ---魔道の通信か。
- 以前、魔道師が念による通信をしているのを覗いたことがあった。その時も空間は歪んだように見えた。先程の男を殺したのが呪文の主ならば、間違いなくガロアの密偵に違いない。確かめたいのは山々だが、ここで一悶着起すのは避けたかった。ただの傭兵が本陣の中をうろついていたと知れれば、それはそれでややこしいことにもなりかねない。思案のしどころだ。
- 「何をしている?」
- ふいに背後から、野太い声を掛けられた。
- ふり向いたアレスの顔を、ボルタイが胡散臭そうに見た。
- 初対面にも拘らず、すぐにこの男がボルタイであるとわかった。何もおびえる必要はないと思いながらも、先程まで会議を立ち聞きをしていたバツの悪さが表情に出た。ボルタイはそれを見逃さなかった。引き締めた鋭い表情で腰の剣に手を伸ばす。わずかでも妙な動きを見せれば斬りかかるつもりだ。鋭利な刃物を前にした時の空気に似ていた。
- アレスは対決に向う衝動を意識的に殺し、心の中で「俺は敵じゃない、敵じゃない」と繰り返した。それが伝わったのか、ボルタイの険しさが次第に納まっていった。アレスはすかさず顎で闇を示した。
- 闇に目を懲らしたボルタイもそれを確認した。二人は互いに頷くと、まるで旧知の友のように息を合わせ、静かにテントの入口に回り込んだ。気取られぬよう、細心の注意を払った。テントの中は、暗く不穏な空気が漂っていた。先に行くボルタイが、テントの隅でくぐまっている黒衣の男を見つけた。
- 「何者だ!!」
- 突然の大声に、怒鳴られた黒衣の男が息を飲んだ。ボルタイは仁王立ちになって逃げ道を塞いだ。
- 「ガロアの魔道師だな!?」巨漢の将軍は素早く剣を抜いた。
- 魔道師も素早く懐中から筒を取出し、口にあてがった。テント内の空気が急激に重圧を増した。
- 「毒矢だ……」アレスは小声でボルタイに伝えた。
- 吹き矢が必中なら、アレスかボルタイのどちらかが死ぬ。三人は睨み合った。
- 「殺せるのは一人だ」
- ボルタイの後から、剣を抜きそびれたアレスが太太しく言った。
- 魔道師の目が光った。挑発にのった魔道師は、ボルタイに向けて毒矢を吹いた。巨漢からは想像もできない早さでボルタイは身をひるがえす。同時にアレスの掌から、キラリと光る物が魔道師に向けて飛んだ。
- 魔道師は小さく呻きを上げて崩れた。一瞬のことでボルタイには何が起ったのかわからなかった。黒衣の胸元には小刀が深く突き刺さっていた。
- アレスは魔道師の屍に近寄り、小刀を腕の篭手に戻した。両腕の篭手には一本ずつ小刀を忍ばせてある。それがアレスの隠し玉だった。
- 屍になった魔道師の黒衣をまさぐると、フードの下から老人の顔が現われた。
- 「見覚えはあるかい? こんな爺さんじゃ、飯炊きにでも化けられちゃ分から---ん!?」
- 背中に刺すような殺気を感じたアレスは瞬時に飛び退いた。
- 背後でボルタイの剣が唸りを上げた。
- 「何のまねだ!!」
- 闇の中でもボルタイの瞳孔が開いているのがわかった。
- ボルタイも自分の混乱に戸惑っていた。それは、目の前の傭兵が魔道師に殺気を向けた瞬間に訪れた。この殺気を知っていた。だが、いつ出会ったものなのかわからない。それを知りたい……。そう思った時、ボルタイの剣はアレスに向かって振り降ろされていた。
- アレスも剣を抜いた。体重をのせたボルタイの剣がアレスを襲う。アレスは後退しながら渾身の力でそれを払ったが、あまりの衝撃に手に痺れが走った。
- 「狂ったか、将軍!!」
- ボルタイは構わず剣を揮った。アレスは攻撃を弾き、その勢いで懐に入って足を払った。 巨漢が尻餅をついて倒れた。
- 「お前、ただの傭兵ではないな!?」
- ボルタイはアレスを値踏みするように眺めながら、ゆっくりと立ち上がった。
- 呼吸の探り合いが始まった。
- 二人は同時に呼吸の狭間を捉え、重い剣は闇の中で交錯した。
- ---この傭兵、何者だ……。俺の肝を掻き回すようなこの感覚はなんだ……?
- 暗いテントの中、二人の押し殺した気合いが弾けた。アレスが躱したボルタイの剣が、重い音をたててテントの支柱に深く突き刺さった。恐ろしいほどの破壊力だ。ボルタイは軽く引く仕草を見せただけで、支柱から剣を引き抜いた。
- 「お前は何者だ……?」憑かれたようにボルタイは呟いた。
- 巨漢は大上段に振りかぶり、正面から飛び込む。天から振り降ろされたようなボルタイの重い一撃を、アレスは剣を両手で支え受け止めた。辛うじて堪えたが、腹がガラ空きになった。すかさずボルタイは鳩尾に蹴りを入れる。雷撃のような痛みとともに、アレスの体は軽々と宙に飛ばされた。臓器が痙攣を起こし、目をむいたまま地面に叩きつけられた。
- ボルタイは闇の中で笑みを浮かべ、アレスが立ち上がるのを待っていた。アレスは苦痛に顔を歪めながら、呼吸を整え、唾を吐き、ゆっくりと立ち上がった。不思議な対決だった。戦う二人は、いつしかこれまでに味わったことのない高揚感を覚え始めていた。
- <h2>先兵と伏兵</h2>
- 本陣の一角に、さらに二重の陣幕で厳重に仕切られた場所がある。
- その中に皇帝の金色の馬車は鎮座するごとく止められ、数十名の警護兵に守られていた。
- ジュミレスはそこで皇帝チャロナと謁見していた。先兵隊の出発を報告するために訪れたのである。皇帝チャロナは、金と赤と黄色を織り混ぜた厚手の司祭服に身を包んでいた。露出した手と顔には、干涸びたミイラのように深い皺が走り、細く鋭い目はいつも空間の一点を見つめている。謁見に馴れたジュミレスも、皇帝が一体何を見つめているのか、時折疑問に思うことがある。代弁者の命を受ける彼にとっても、皇帝との対面は緊張と悪寒のつきまとうものだった。赤いカーテンの内側は、移動する王の間そのものだった。本国の城と少しも変わらぬ高価な玉座が組み込まれ、床は金糸の絨毯に埋まっていた。
- 「只今より、精鋭の先兵隊、五千名にてカゴヤラに向かいます」
- 玉座のチャロナは瞬きもせず、冷えた視線で空間を見ていた。チャロナは何も言わない。だが、ジュミレスにはチャロナの声が聞こえていた。
- (ガロアを落とせ……。ダムチを殺せ……)
- 言葉の代わりにチャロナの想念が送られてくる。ジュミレスは催眠術のように繰り返される皇帝の想念を全身で感じていた。
- その時、チャロナの想念がガラリと変わった。敵の訪れを察知した警戒信号だった。
- 「まさか……?」呼応してジュミレスも悟った。
- いつの間にか本陣の傍らまですり寄ったガロア軍を、野営の兵たちはまったく気づいていなかった。画策士ミアラの指示で草木に紛れ時を待っていたガロアの伏兵二千名である。彼らはダビ山の峰に連なる森に隠れ、襲撃の合図を待っていた。
- すでに配陣を済ませ、国王ダムチと別れたミアラは伏兵部隊と合流していた。
- 「本陣だけならば、たかが一万名ほどに過ぎん。本陣のみを叩けばよいのだ。道はそこから開かれる。かかれっ!」
- ミアラの合図で腹ばいになった弓矢隊が一斉に矢を放った。矢は闇を切り裂き、焚火に集まるゲルニアの兵士たちを容赦なく貫いた。
- 「やっ、夜襲だーっ!!」
- 叫びの波紋はすぐにダビ山の野営地に広がった。闇の中で次々と剣を抜く音が聞こえた。ガロア兵はゲルニアの本陣に目掛け、雄叫びを上げながらなだれ込んだ。
- 奇妙な高揚感に支配されたアレスとボルタイの戦いは依然としてテントの中で続いていた。ボルタイが力一杯の大振でアレスに斬り掛かる。アレスはこともなげにそれを受け止めた。この短い戦いの中で、アレスはボルタイの巨体から繰り出される攻撃の緩和方法を身につけていた。ぶつかり合う重い剣の音が炸裂する。その頃になって、二人の耳にも漸くただならぬ喧騒が伝わってきた。
- 二人の動きが一瞬止まった。
- 「夜襲だと?」ボルタイは信じられないとばかりに呟き、驚きを拭いさるかのようにアレスに向けて斬り掛かった。
- 夜襲の混乱の中、ジュミレスは姿の見えないボルタイの所在を兵に訊ねた。
- 「ボルタイ将軍はどうした? 敵が夜襲をかけてきたという、この時に!」
- 臨戦体制を解いていたゲルニアの大遠征部隊は、出兵の準備をしていた一部の先兵隊を除き烏合の衆と化していた。
- 「おのれ、正面からゲルニアに対抗してくるとは……。ガロアどもを返り討ちにしろ!」
- ジュミレスのヒステリックな叫びに、先兵隊であったはずの兵たちが漸く応戦を開始したが、勢いにのるガロア兵と、狼狽えるばかりのゲルニア兵では勝負にならなかった。なだれ込むガロア兵は、瞬く間に野営地に攻め入り、本陣を目指し集結した。ゲルニア兵たちは突然の奇襲に悲鳴を上げながら、次々と倒されていった。ミアラの読みは的中した。兵力の差にあぐらをかくゲルニアの怠慢は致命的だった。不意を突かれた足並みは瞬時には揃わない。松明が投げられ、テントに火が燃え移った。
- 自分たちの戦いに夢中のアレスとボルタイも、さすがに外のただならぬ騒ぎを無視できなくなった。アレスは隙をつき、テントの生地を大きく袈裟掛けに斬って外に飛び出した。ボルタイも続いて飛び出す。二人の戦いの場は、月明かりに照らされる屋外へと変わった。辺りではガロアとゲルニアの戦いが始まっていた。二人が鍔競り合いを繰り返す間、傍らでは絶叫とともに何人ものゲルニア兵が倒された。
- 「小僧! 勝負は預ける!」
- 力一杯にアレスの剣を弾くと、ボルタイは戦う相手をガロア兵へと移した。
- ちょうどその時、戦場と化した野営地に法螺貝の音が鳴り渡った。ガロアの奇襲部隊はその音を聞くと攻撃を止め、潮が引くように撤退を始めた。
- 「敵が引くぞ、逃がすなっ!!」皇帝の馬車の近くで指揮をとっていたジュミレスはいきりたっていた。
- 「追跡する! 馬の用意だ!」
- ガロア兵の影は見る見る闇の中に溶け込んでいった。ボルタイの姿は未だ見えない。無論、ジュミレスにもボルタイが別の場所で戦っているだろうとは想像がついたが、ボルタイの忠告どおりガロアの夜襲があったことが忌々しくてならなかった。側にいれば、逆に罵倒を浴びせたいほどの心境だった。
- 「私に続け! 一人たりとも逃がすなっ!」
- ジュミレスは馬に跨がると付近の兵を率い、逃げる奇襲部隊を追跡した。
- 伏兵たちは散るように逃げたが、一塊の集団はカゴヤラへの道を真正直に突き進んでいる。
- ジュミレスはその一団を獲物と定めた。
- ---逃がしてたまるか……。
- 分け入る道はすぐに地形を変えた。岩地の山頂を過ぎると、両脇に繁る背の高い草木が星明かりを遮り闇の濃度が増した。本当の伏兵は、その闇に紛れて静かに待っていた。奇襲部隊を除くガロア兵すべてが伏兵と化していたのだ。彼らは茂みの中で固唾を飲み、追撃隊の到来を待っていた。
- 獲物が近づいてくる。伏兵たちの心は躍った。弓を持つ手に力が入り、闇の中で何百もの矢が標的に向けられた。指揮は国王ダムチ自らが執っていた。
- 「射て!!」ダムチが叫び、一斉に矢が射られる。途端に雨のような矢がジュミレスの率いるゲルニアの追撃部隊に放たれた。突然、叫びも上げられないまま、何人かが倒れた。
- 「罠か!?」ジュミレスは背中に冷たいものを感じた。
- 「伏兵だ!! 伏兵がいるぞ!!」
- 「松明を消せーっ!!」
- ある者はそのまま馬から落とされ、またある者は針鼠のように全身に矢を受けて倒された。応戦する猶予さえ与えられず、ジュミレスたちは無様にも、地に伏せて矢をかわすのが精一杯だった。
- 「馬鹿な! この有様は何だ!!」あまりの口惜しさに怒りの言葉が出た。
- 「ジュミレス様、ご命令を!!」
- 「応戦だ!! 応戦に決まっている!!」
- 「敵が見えません!」
- 「構わん!! 矢を射返せ!!」
- ジュミレスの脳裏には、戦っている相手よりもボルタイの嘲笑う顔が浮かんでいた。ジュミレスは弓を取ると手本を示すように闇に向け矢を放った。
- 「おのれっ!! こうするのだ!!」
- 他の者たちも震えながら射返したが、盲射ちの矢は効果が得られるはずもなかった。応戦の甲斐も虚しく絶叫が闇に響き、一人また一人とジュミレスの追撃隊はガロアの伏兵の矢に倒された。
- <h2>魔霊</h2>
- ジュミレスはいくつもの矢傷を受け、哀れな姿で本陣に戻ってきた。
- ボルタイは本陣に逃げ戻ったジュミレスたちを見て複雑な心境だった。ジュミレスがドジを踏んだのは痛快だったが、まさか、これほどの損害を受けるとは思ってもいなかった。
- 「見苦しいなジュミレス。忠告したはずだぞ。兵を失った弁解なら、本国に帰ってからゆっくりと聞いてやる」
- 「ボルタイ、貴様こそ何をしていたのだ?」
- 襲撃の際、ボルタイの姿がなかったことを追求しようとしたジュミレスだが、自らの失態を感じたのか、いつもの高飛車な語感は消えていた。
- ---ザマをみろ。近衛兵なら近衛兵らしく、皇帝をお守りしておればよいのだ……。
- この失態で大遠征部隊の指揮権はボルタイに移った。
- ボルタイは全面対決に持ち込む決意をした。恐らく、動かなければ夜襲の第二波がくる。このまま朝を待つよりも、ここまできてしまえば、全軍を率いて一気に兵を挙げる方が士気を保てる。ボルタイは朝を待たずして総攻撃をしかける策を選んだ。
- 皇帝への報告はジュミレスに取らせた。進言に不安はあったが、戦いのための移動との理由で皇帝の承諾も下った。
- 本陣の片付けも早々に全軍は再び歩き始めた。大部隊は追撃隊と同じ轍を踏まぬよう松明を消し、闇の中を進んだ。ボルタイは大部隊をキニドバの谷へ導いた。渓谷を抜ける道ならば木々の少ない分だけ見通しが効くと踏んだのだ。下り坂の続いた闇の道はやがて谷へと通じ、地面は土から小石へと変わる。星明かりが渓谷の岩を照らし、予想どおり先刻からは比べものにならないほどに見通しは効いた。
- ボルタイは険しい眼差しで辺りに気を配った。摺り鉢状になった岩の渓谷に入ると出口まで逸れる道はない。これまでのガロアの戦略は完璧だった。小部隊の仕掛けではあったが、ボルタイに動くことを余儀なくさせた。敵の参謀が噂に名高い画策士ミアラ=ドドーならば、警戒してし過ぎということはありえない。
- ---次に攻撃をかけてくるとすれば、谷の出口か……。
- ボルタイが先を読んで前衛の強化を指示しようとしたとき、星の煌めく天上に、霞のような白いものが覆いかぶさっていった。
- ボルタイの表情が凍った。ボルタイはミアラが画策士であるとともに、一流の魔道師でもあったことを思い出した。ジュミレスも同じものを見て顔を引きつらせた。霞は見る間に広がっていく。白い霞の広がった空は次第にその中心から星明かりを隠して、暗黒の空間を覗かせていった。
- 「魔霊が降りて来るぞ! 捕まるなーっ!!」
- ボルタイの声に行軍の速度が早まる。だが白い霞は行軍よりも早い速度でその勢力範囲を拡大した。
- 魔霊は四象にも属さない魔物の類である。四象とは「地・水・火・風」の世界を形成する四大要素のことを指す。各々には精霊が関与し、時として不思議な力を発揮する源となることもある。だが、魔霊はその枠のさらに外にある存在だった。魔道師か悪魔祓いでもない限り、人間に対抗手段があるわけもない。
- 広がっていた霞が、今度は逆に暗黒の中心に集まり始めた。兵士たちは叫び出したい衝動を抑えて先を急いだ。
- アレスも上空を見上げた。霞はゆっくりとうねりながら、次第に数限りない魔霊の姿へと変貌を始めた。白い塊は何百というおぞましい人面の形に固定されていく。どの顔も泣き叫び悶絶する表情を浮かべ、恨めしそうに地上を急ぐ兵士たちを見下ろしている。魔霊は浮かばれぬ霊たちの魂だった。生ある者に出会えばそれにとり憑き破滅を共有する。
- 「ミアラめ。魔霊を召喚させて同士討をさせるつもりか」
- ボルタイの頭上で魔霊が飛び散った。魔霊の一つ一つが白い尾のような余韻を残しながら暗黒の空間を駆け巡る。魑魅魍魎の魔霊は自在に浮遊して行軍に襲いかかった。
- 「散れ!! 分散しろーっ!! 固まるなーっ!!」
- それが適切な措置であるかボルタイにはわからなかった。しかし、同士討を避けるためにも隊列を解き、魔霊の標的を分散させることが賢明であると判断した。
- 「ジュミレス! 我らは皇帝の馬車の守りを!!」
- 散開する兵の中、ボルタイとジュミレスは、すかさず皇帝の馬車に向け、馬を繰り出した。 無数の魔霊がおぞましい姿で兵士たちにまとわりつく。剣で斬りかかっても手応えはない。霞のような魔霊は分散したかと思えば、また元に戻り、抵抗も虚しく空を切った。剣をたてた兵士に手応えがある。だが、絶叫は仲間の上げたものだった。魔霊の幻影が現われ始めたのだ。 方々で同士討が起こり、兵士たちの悲鳴が上がった。 「剣を使うなーっ!! この場から離れるのだ!!」
- ボルタイの絶叫が虚しく響いた。兵士たちは魔霊の幻影に怯え、逃げ惑うばかりだった。
- 魔霊を召喚させたミアラは、谷の上から笑みを浮かべ、この様子を見ていた。魔霊の渦は完全にゲルニア軍を包囲している。しかも、先刻ゲルニアの野営地襲撃に成功した部隊は、谷の両翼から火矢を携えて合図を待っていた。矢尻に次々と移されていく炎が谷を取り巻いた。
- 「火矢か……?!」
- 今更ボルタイが気づいても手遅れだった。
- 「射てっ!!」
- ミアラの指示で火矢は降り注いだ。
- 「火矢だ?!」
- ゲルニアの兵士たちは矢を避けるため、狂ったように剣を振った。閉ざされた谷で魔霊と火矢の攻撃を受け、さすがに数に慢れる四万の兵も周到な罠にはまったことを自覚した。
- キニドバの谷に絶叫がこだまし、炎は谷間を赤々と染めた。
- 谷を染め上げる炎を、遠く離れた北の山頂から見ている者たちがいた。
- ガロアから旅立った脱出民たちである。一団を連れてようやく北の山頂に辿り着いたフォルト=ギルダンは、悲痛な表情で谷を照らす炎を見ていた。
- 「キニドバの谷が燃えておる……」
- 静まり返った夜の空気は遠方の兵士たちの叫びを風に乗せて運んだ。着の身着のままの脱出だった。戦いに負ければガロアはゲルニアの統治下になる。想像をしたくない展開だった。
- 国王ダムチの命により脱出民を編成したが、人数にしてわずか百余名。再建を期待するには心許ない数だった。
- ---無事にブディドに辿り着いたにせよ、故郷なき民をどこへ導けばよいのか……。
- 弱気な想像はするものでわないとわかっていながらも、現実を知る老人は、冷静な判断を執らねばならなかった。
- 「父上が戦っているのですね」
- 目立たぬよう、粗末な牧童の服を身に纏ったヘグリス王子が、谷の炎を見ながら言った。
- フォルトは優しく王子の肩に手をあてると一団をうながし、ブディドへの逃亡の旅に歩み出した。
- <h2>乱心</h2>
- 長い時間が過ぎた。漆黒の闇が薄みを帯び、闇に変化が訪れた。
- 兵士たちの呻きが地を這っている。余りの恐怖に翻弄され泣いている者や、気狂いのようにわけのわからぬことを口走っている者もいた。
- アレスは魔霊や火矢の攻撃を逃れ、谷の隅にあるわずかな茂みの中で朝を待っていた。
- 東の空が白み始め、やがて眩しい陽の光が谷を照らし始めた。傍若無人に浮遊していた魔霊は陽の光に悶絶し、不快な絶叫を上げながら、次々とかき消えていく。所詮は闇の中でしか存在できない魔霊は、朝まで持ち堪えることさえできれば敵の数には入らない。アレスは匍匐で移動し、注意深く辺りを窺った。火矢や同士討でやられた兵士たちが横たわる無惨な光景だけが目に映った。
- 馬が必要だった。まだ使えそうな馬がいないものかと辺りを見回す。少なくとも目に映る範囲では、ほとんどの馬は横倒れになって唸っているか、あるいは兵士同様に火矢の餌食となり、半身を焦がして死んでいるかのどちらかだった。好運なことに、その間を縫って一頭の暴れ馬が駆けてきた。
- アレスは勢い良く茂みから駆け出すと、弾けるように跳躍して馬の背に飛び移った。突然背に人の気配を感じた馬も驚いたが、アレスが二、三度手綱を軽く引くと、その動きに素直に応じた。目指すはガロアの国王ダムチの首のみだった。
- 掛け声とともに馬は矢のように走り出し、アレスは疾風となって朝焼けの谷を駆け下った。 一方、ボルタイは魔霊たちの出現とともに素早く皇帝の馬車の守りにつき、チャロナの警護にあたっていた。雨のように降り注いだ火矢の攻撃も終わった。金色の馬車には何本もの矢が突き刺さり、炎の焦げ跡がミアラの作戦のあざとさを物語っている。
- 「敵は引いたか……。だが、いつまでもこうしてはおれん」
- 悪夢のような混乱を越えても、豪傑と謳われるボルタイは馬に跨がっていた。視線を滑らせると、馬車からさほど離れていないところで、兜を落として瑠璃色の髪を無様に乱したジュミレスがぼう然として立っていた。
- 「皇帝を守っていろっ!!」狼狽えるばかりのジュミレスにボルタイは強く言い放った。
- 「戦う気のある者はついて来い!! 俺につづけ!!」
- 馬に鞭をたて、いななきとともにボルタイは駆け出した。魔霊や火矢に翻弄されたものの、ボルタイの鍛えた黒騎士隊も厳しい訓練をつんだ強者揃いだった。人数こそ減っていたが、駆け出すボルタイの姿を見ると我先に集結を始めた。
- キニドバの谷を駆るアレスはゲルニア軍の先頭をとった。アレスは水を得た魚の勢いで賞金首を目指し朝焼けの谷を駆った。遅れて続くボルタイ率いる約五千の黒騎士隊も今や手負いの獅子となり、決死の表情で馬を走らせていた。
- 待ち構えるガロア軍もここを最終決戦の場と考えていた。全面戦闘になればガロアに勝ち目はない。ゲルニア軍の足並みが揃う前に決着をつける覚悟だった。野営地の奇襲。伏兵による追撃隊の殲滅。魔霊による撹乱と火矢の攻撃。ミアラの作戦はことごとく成功を収めた。
- ミアラがキニドバの谷でゲルニア軍を足止めしている間、ダムチはカゴヤラの村に本陣を移した。兵力の差を補うためにミアラが導き出した大規模な移動作戦もこれまでだ。もう伏兵などと言う姑息な作戦は通用しない。
- アレスを先頭とするゲルニアの騎馬隊は砂埃を巻き上げながら朝焼けの谷を下ってきた。 「射てっ!!」
- 空を裂く矢が唸り、騎馬隊を目掛けて矢は降り注いだ。矢を受けた兵士の馬が、もんどりをうって倒れた。いななきに砂塵が舞う。アレスは構わず馬で突き進んだ。放たれた矢を巧みに躱し、間に合わないと判断した時は手刀で叩き落とした。
- 猛然と馬を駆るアレスは敵に矢をつがえる余裕を与えなかった。居並ぶ弓矢隊に正面から飛び込む。ガロア兵が大きく弾け飛んだ。おって参入したボルタイたちも構わず体当たりを試みた。防衛線である弓矢隊の陣形が崩れ、たちまち敵と味方が入り乱れる。もう飛び道具は使えない。
- 馬から飛び降りたアレスは、取り囲むガロア兵たちを見回しながら、ゆっくりと剣を構え直した。長剣の重さは心地よい。接近戦はアレスの望むところだ。
- 「いくぜ!」
- 剣が舞うように振り下ろされ、ガロア兵の絶叫があがった。アレスは次々とガロア兵を斬り裂いた。攻守が一体となった動きには無駄がなく、辺りの敵兵は瞬く間にアレスの剣の錆となった。ボルタイもガロアの騎馬隊と戦っていた。巧みに手綱をさばき、アレスに負けず次々とガロア兵を討ち倒している。アレスは横目でボルタイの働きを見て苦笑いを浮かべた。ここで先を越されては身も蓋もない。一層色めき立ってダムチを捜した。
- ---どこだ……? 奴はどこにいる。
- アレスは次々と押し寄せるガロア兵を斬り続けた。傭兵根性むき出しのアレスは、少しも臆することを知らない。兵の壁の向こうにガロアの陣幕が見えた。ガロア兵たちの動揺が国王の所在を告げている。アレスは猛然と陣幕に向けて駆けた。
- 妨害する兵を、剣を合わせることもなく、擦れ違いざまに斬り捨てた。
- 陣幕を一振りで斬り分けると、敵も味方も周囲の者は皆、動きを止めた。
- ガロアの国王ダムチがその中に立っていた。居合わす兵たちは、昨夜から続く戦いが、遂に終末を迎えようとしていることを悟った。
- 「その殺気。お前の気配。何故か覚えがある」
- アレスを見たダムチは不思議そうに呟いた。
- 陣の外ではガロアとゲルニアの戦いが続いている。だが、ダムチの周辺には静寂が立ち篭めていた。ボルタイは鋭い視線でダムチと傭兵のやりとりを見ていた。
- 覚えのある気配---。ダムチの言葉は同時にボルタイの疑問でもあった。
- 「あんたに恨みはないが、その首をいただく」
- アレスは感情を押し殺した声で言った。
- 誰もが固唾を呑み、ことの流れを見守った。
- 国王は静かに剣を抜いた。互いに五感の全てを集中させて相手の動きを読む。二人は間合いを取って移動した。つかず離れずの間合いは双方つけ入る隙を与えない。ダムチが噂以上に腕がたつことをアレスは知った。構えを上段に移すダムチに、アレスは腰をかがめて低い構えを取った。互いに機を捉え、目にも止まらぬ速さで剣が弾き合う。突き上げる剣と振り下ろす剣が弾け合い、二人の掌に痺れが走った。その反動にアレスは左に回転し、ダムチは剣だけを大振りにして構えを立て直す。一瞬詰まった間合いはすぐに元に戻った。
- アレスはゆっくりと剣を回転させる。重い長剣は回転させることにより、さらに破壊力を増す。その様は、あたかも獲物を追い詰めた狩人が、相手を威嚇するために剣を振り回している姿のように見えた。ダムチは腹の前で剣を構え、接近を待った。アレスが少しずつ間合いを詰める。先程の弾き合いでタイミングはわかっていた。
- 「ぬん!!」
- 確実にひと呼吸前に踏み込んだにも拘らず、アレスの剣は重い音をたて、ずしりと受け止められた。二人は渾身の力を込めて押し合った。斬りつけることも引くこともできず、鍔を合わせたまま移動した。押し合いはほとんど互角だった。重なった鍔を中心にして二人は回り込む。ダムチが更に力を込める。アレスの握りが少しづつ返り手になって力が抜け始めた。強い力がそのままアレスの腕を押し上げる。ダムチが気合いとともに押し上げた瞬間、アレスは飛び退いた。続けざまに鋭い剣が唸る。避けたアレスも間髪を入れず間合いに飛び込んでいた。 人体を斬り裂く鈍い音がし、二人は絡み合った剣士の彫像のように動きを止めた。ほとんど同時に踏み込みをかけていた。長剣は深々とダムチの胸を貫いていた。わずかにアレスが早かった。ダムチの胸から真紅の血が溢れ出た。
- 「名を……、聞こう……」
- 「アシュワの傭兵、アレス=トラーノス」アレスは静かに答えた。
- 「…………アシュワの……? そうか……皮肉な時代の……到来か……」
- 国王は苦しげに吐血して、ゆっくりと崩れた。
- 最後に繰り出した止めの剣で、ガロアの王、ダムチの首は高々と荒野に舞い上がった。
- 数刻後---。カゴヤラに施設されていたガロアの陣はゲルニアの陣となっていた。
- 無論、ゲルニアに奪われたのはカゴヤラの陣だけではない。国王を失ったヒウケビロス大陸のガロアはもう存在しないのだ。この地はダムチを失った瞬間より、ウビロス大陸のゲルニア帝国下に落ちたのである。民も領土も全てはゲルニアのものとなった。
- だが、大遠征の果てにようやく戦いを終えた兵たちにしてみれば、勝利を喜ぶより、生き残り、ひと区切りの戦いから開放される喜びの方が遥かに大きかった。キニドバの谷で足留めさせられていた部隊も到着し、兵士たちは疲労を浮かべながらも戦いの終決に安堵した。
- 遠征に同行しながら、一度もその姿を兵士たちの前に見せなかったゲルニアの皇帝チャロナが姿を見せた。
- 皇帝チャロナは陣の正面に配置された木彫りの椅子に深く腰を掛けていた。初めて皇帝の姿を目にした兵士たちの感嘆が、騒めきの波となっていた。
- 「ガロアの国王、ダムチの首をここへ!」
- ガイソン大隊長の声に、アレスはダムチの首を持ち、居並ぶ兵士たちの間を抜けて、チャロナの前に歩み出た。敵の大将を仕留めたアレスには、皇帝に勝利の報告をする大役が与えられた。アレスは皇帝の前に跪き、下を向いたままの姿勢でダムチの首を差し出した。その首に、皇帝の干涸びた手が伸びた。確実にその手に首を預けるため、アレスは少し顔をもたげた。
- ダムチの首の向こうに、ミイラのようなチャロナの顔があった。青白い輝きを放つ不気味な眼がアレスを見た。
- その瞬間、途轍もない悪寒がアレスの全身を貫いた。
- 全身を流れる血液が一度停止し、逆流を始めたかと思われるほどの悪寒だった。
- チャロナの眼の奥に宿った青白い輝きが、今までに感じたこともない邪悪な波動を送りつけていた。冷汗が噴き出し、全身が震え、脳味噌からけたたましい拒絶反応が起こった。
- アレスの目は完全に焦点を失った。
- 首を差し出す手から力が抜け、ことりっ---と、ダムチの首が地に転がった。
- あたかもそれが合図のようだった。
- その刹那、理性が消え、本能が傭兵を動かした。
- 突然アレスは野獣のように叫び、剣を抜いた。
- 剣が弧を描くのを誰もが信じられずに見ていた。
- 血飛沫が舞った---。
- 皇帝チャロナは肩口からアレスの剣を受け、血に塗れてその場に倒れた。
- アレスはただ立ち尽くしていた。全ての者が口をあんぐりと開けるばかりで動けなかった。
- しばらくたち、兵士たちはようやく何が起ったのか理解した。腕に覚えのある者たちが放心状態で立ち尽くすアレスに向かい我先にと飛び出した。
- 「待てーい!! 静まれ!! 静まれーっ!!」
- ボルタイの叫びが制した。そのあまりの声量に、アレスを手にかけようとして飛び出した兵士たちは動きを止めた。ボルタイは叫びながら正面に踊り出た。
- 「聞けーい!! この者を手にかけることは俺が許さん!! そのようなことはこの俺が認めん 戻れ! 戻らんか!! お前たちの見たとおり、皇帝は今、お亡くなりになられた! この者は荒野の掟に従い、流刑地カーン送りとする!! 異論のある者は前に出るがいい!!」
- ボルタイはこのチャンスを逃すまいと息巻いた。
- あきらかに、アレスの処置をダシにした権力宣言だった。ジュミレスは口惜しい表情で金色の馬車の前に立ち、生き残った近衛兵団とともにそれを見ていた。皇帝亡き今となっては口をはさむ余地はなかった。
- 「皇帝の骸を馬車へ!」
- ジュミレスは騒めきの隅で忌々しげに兵に命じると、この場にいるのも堪えられないというように眉間を歪め、隊列から離れ去った。
- 両腕を兵士たちに固められても、アレスは未だ放心状態のままだった。自分のしたことも、措かれた状況もわからない。ただ、うつろな笑みを浮かべ、為されるがままに重い手枷に繋がれるばかりだった。
- ゲルニアは勝利を収めたが、予想以上のガロアの抵抗に思わぬ苦戦をしいられた。気がつけばガロアの猛攻に四万の大遠征部隊も半数近くに減っていた。しかも、一介の傭兵の乱心により、皇帝チャロナは命を落とした。思わぬ展開を好機に主導権を得たボルタイは戦後処理を行い、ガロアはゲルニアの属国となった。しかし、それは皇帝にもっとも近いとされていたジュミレスをかやの外に置くものであり、ゲルニア帝国の権力構造は大きな変化を見せる結果となった。
- そしてこの戦いにより、この地から旅立った者たちがいた。フォルト=ギルダンに連れられてブディドへの逃亡の道を辿る、ガロアの王子ヘグリス。もう一人は皇帝を殺害し、流刑地カーンに送られた乱心の傭兵アレス。
- 一つの戦いは幕を閉じた。だが、戦乱の渦は見えない力に操られ、さらに巨大な渦に変貌しようとしていた。
- <h1>第二章 辺境の流人</h1>
- <h2>流れゆく星</h2>
- ゲルニアの大遠征部隊が村を通過して四日が過ぎていた。
- カーイは小石を拾い、牧場の端にある木を狙い、それを投げた。小石はゆるい軌道を描き、木に当たって小さな音をたてた。
- ---あいつ、どうなったんだろう。
- 少年はゲルニアの兵隊に混じり、ガロアに進軍していった傭兵のことを考えていた。
- ---噂じゃゲルニアがやっぱり勝ったらしいけど、あいつまた、この村を通るのかな。
- 木の根元には、いくつもの小石が転がっている。全部カーイが投げたものだ。
- ---でも変な話だ。この村を通ってゲルニアに戻っていく兵士たちは、勝ったっていうのにまるで元気がない。あれじゃ敗残兵だ。
- 昨日あたりからぼつぼつと現われた帰還兵は、クアルの村を再び通り、紅の街道を戻り始めた。行きの整然とした大遠征部隊とは違い、兵士たちは勝手気ままに村を通過した。
- ---うん。連中は元気がなさすぎる。勝ってガロアの領土を手に入れたんだ。もっと喜んでてもよさそうなもんだ。
- 兵士たちの行動は腑に落ちなかった。それに、何よりも赤い傭兵がどうなったのか気になった。見渡すと、柵の向こうの小道に、肩を落として歩く老兵士の姿が見えた。
- カーイは駆け出すと、老兵士を呼び止めて話を聞いてみた。
- 「勝ったとも。どうもこうもない。こんな戦は初めてだ。勝ち戦のくせに、褒賞もなければ戦利品の分配もない。一文の足しにもならん戦だった。もっとも、皇帝が亡くなられてはいたしかたないが……」
- 「皇帝が死んだって?」
- 「傭兵だ。傭兵が乱心したんだ」老兵士はいくぶん恨みがましく呟いた。
- 「きっと、あいつだ……。ねぇ、その傭兵。赤い鎧の奴じゃないか?」
- 「そうだ。よく知ってるな。名前は、確か……アレスとかいっておったか」
- 「アレス……」カーイは初めて聞く傭兵の名を噛み締めた。
- 「奴は見事にガロアの国王ダムチを仕留めた。だが、その報告をするために皇帝の前に立ったとき、突然乱心を起こしたのだ。こともあろうに皇帝に斬りかかるとは……」
- 「それで……どうなったのさ?」
- 「傭兵は流刑地のカーン送りになったそうだ」
- 「流刑地カーン……」
- 口にしたと同時に、少年は一つの決心をした。老兵士に礼をいい別れると、カーイはすぐに旅支度を整えてクアルを出ることにした。旅支度といっても大した荷物はない。寝倉の洞穴に戻り、思いつくままに小袋に詰め込んだ。もともと一人旅で立ち寄っただけの村だ。村人に洞穴を借りて冬を越えたが、この村に長居する気はなかった。
- カーイが旅支度を整えて洞穴の出口に立った時、丁度段々畑の下をゲルニア兵の一団とともに、あの金色の馬車が通りかかった。
- 「金色の馬車だ……」
- それを見た途端、吐き気に似た感覚が少年を襲い、見たくもないものを見てしまったような嫌悪感が心に広がった。無論、カーイはその中にチャロナの亡骸が納められていることを知らない。恐らく、ガロアの反撃にあったのだろう。金色の馬車は所々に矢の刺さった跡を残し、炎に焦がされた跡があった。
- 少年は金色の馬車が視界から消えるまで動けなかった。
- 「ちぇっ、なんだよ。やな感じだ……。まるで葬式の列じゃないか……」
- 出鼻を挫かれた思いがした。
- 突然襲った不条理な感覚は強烈だったが、今の少年には新しい目的ができていた。
- カーイは気を取り直して、元気よく段々畑を駆け降りた。
- 赤い傭兵に逢うことが、少年の目的になっていた。カーイは馬車の消えた方向と反対側に紅の街道を歩み始めた。少年は一人歩いた。暑すぎず寒くもなく、日和りは申し分ない。袖のないボロボロの麻服でいくつも袋をぶらさげた姿はみすぼらしかったが、少年は鼻歌を歌っていた。忘れていた旅の楽しさを、知らず知らずのうちに思い出していた。足を交互に踏み出すだけで妙に楽しかった。
- 「ガロアのカウラン城に行くにはダビ山を越えなきゃいけないけど、あいつがいないのがわかってて行ってもしょうがない。あいつはカーンにいるんだ。さあ行くぞ、カーンまで。どんなことがあっても、またあいつに逢ってやるんだ。アレスっていったな。顔を見たら言ってやるんだ。あんたはでっかいことをやると思ってたって。でも、間抜けだよな。やすやすとつかまっちゃうなんてさ。せっかく二つの国の王を倒したんだ。そのまま国王におさまっちゃえば良かったんだ。そうだ、そう言ってやるんだ」
- 果てしなく続く紅の街道を前に、カーイは自分の血が騒ぐのを感じた。少年の足取りは軽かった。どうしても赤い傭兵アレスに逢いたい。カーイは自分が何故、これほどまでに赤い傭兵に逢いたいのかわからなかった。逢えばわかると思った。今は旅を再開し、目的を決めて歩き出したことが何よりも心地よかった。
- 荒野は紅の街道を歩むカーイに涼しげな風を投げかけていた。
- 砂塵が地を横切っていた。蹄に散らされた砂が乾いた音を繰り返している。流刑地カーンの巡回隊は定期巡回を行なっていた。
- 十年前のことだ。ゲルニアの遠征部隊がこの地を訪れた際、砂漠の辺境に信じられない文明の痕跡を発見した。砂漠を上を分厚い塀のような長城が分断していたのである。
- 遺跡と呼ぶにはあまりにも大規模で、長城は永年にわたる砂塵の洗礼に曝されていたにも拘らず、朽ちた様子もなかった。
- 報告を受けた皇帝チャロナはこの地を流刑地と定めた。先住人の遺跡として発見された長城は監獄の塀として使われ、各地から流刑者たちが送られることになった。
- 巡回隊の面々は細心の注意を払いながら馬を進めている。馬に乗っているとはいえ、ここでは決して気を許せなかった。砂嵐はいつ巻き起こるかわからない。一度砂嵐が始まれば極寒の吹雪同様に視界は断たれる。迷ったら最後、城壁に辿り着くことは不可能に近い。
- 二十頭の馬で編成された巡回隊はあらゆる事態を想定して装備を固め、神経質過ぎるほどの緊張を漂わせていた。遮眼帯と特大の蹄鉄を付けた馬。一日分の水、干しパン、砂塵避けのマスク、一人一人が長剣の他に長槍まで持参していた。
- 「モイラン隊長、あれをっ!」
- 巡回隊の一人が砂漠に埋もれて折り重なる、流刑者の死体を発見した。誰も馬から降りようとしなかった。砂虫を警戒しているのだ。薄く砂を被り、八体の流刑者の死体が倒れていた。腹に銅剣の刺さっている者もいれば、肩口に深々と傷口を残している者もいる。血はどす黒く変色して、皆一様に干涸び始めていた。巡回隊が今朝砂漠に出てから見た、三度目の死体の山だった。城壁を出て早々に目にした死体の山は陰惨な気分を残したが、今ではもう、そんな感覚にも慣れ、冷静に亡骸を見比べて分析することさえもできるようになっていた。
- 「だいぶ時間が経ってますね」巡回隊の一人が折り重なる死体を馬上から見下ろして言った。「死体ばかりで本当に気味の悪いところだ」もう、いい加減に嫌だといった口調で、副隊長のギバードが口を開いた。
- 「砂虫に食われた痕跡はないな」隊長のモイランが死体の山に入念に目を走らせた。
- 「隊長、折り返しの刻限かと。そろそろ帰途に着かないと日暮れまでに城壁に戻れません」
- 隊員たちの気持ちを代弁するようにギバードが進言した。
- モイランもこの地獄のような砂漠から、一刻も早く抜け出したかった。だが、巡回隊は流刑地の巡回とともに、もう一つの命令を受けていた。
- 「ギバード、悪く思うな。我々にはカーンの地図を作成するという仕事がある。少しでも早くカザル様に地図をお渡しせねばならん」
- 「ですが、無理もできません。もう一ヶ所測量を終えたら、帰途の指示をお出し下さい」
- 「そうしよう」
- 一行は死体の山を離れ、北に向けて馬を走らせた。
- つい一カ月ほど前のことだ。モイランたち巡回隊は流刑地の砂漠を巡回中、新たな遺跡を発見した。メンヒル(石柱)の残骸である。これまで遺跡は城壁だけだと思われていたが、この発見により獄長のカザルは、他にもカーンには未発見の遺跡があるのではないかと考え、今まで測量もせず手もつけなかった砂漠に目を向け、巡回隊に地図の作成と遺跡の探査を命じた。
- この調査は、あわよくば昇進をと願うカザルの目論みから、本国のゲルニアにも告げずにすすめられていた。そして調査の甲斐があり、これまでに砂漠のいくつかの地点で紡錘形のメンヒル(石柱)が発見された。
- 測量は城壁の起点から、最初に見つかったメンヒルまでの距離を1メンヒルとし、これを基本として行なわれた。獄長のカザルから測量の命令を受けたモイランは、ギバードのアイデアにより独自の計測単位を持つことで情報の機密化を図った。
- 巡回隊の一行は、すでに城壁から北に2メンヒルほどの位置まで到達していた。
- 「もう今日は、何も見つかりそうもないな」隊員の一人が城壁を懐かしんだその時、ギバードがなだらかな砂の丘陵の向こうから突き出た岩柱の頭らしきものを見つけた。
- 「あれは……?!」距離と先端の大きさから考えて、あきらかにこれまで見つかったメンヒルとは規模が違った。巡回隊は馬に鞭をたて、砂塵を巻き上げて丘陵を越えた。
- そこで彼らは途轍もなく巨大なメンヒルを発見した。優に人の十倍の高さはある。今まで見つかったメンヒルの残骸とは比べものにならないほど、しっかりと原型を留めていた。
- 巨大な石柱は、砂漠の大地にどっしりとそそり立っていた。
- 「なんて巨大なメンヒルだ。急いで測量だ!」
- モイランは思いがけない発見に上擦った。だが、すでに帰途の刻限は迫っている。重要な発見をしても生きて帰れなければ意味がない。馬から降りた隊員たちはそれぞれの仕事を開始した。遠眼鏡で辺りの丘陵を覗きスケッチをとる者、目測で地図に書き込む者、ある者は最新式の外洋船から取り外した羅針盤で方位の計測を始めた。
- 「ギバード、メンヒルを調べるぞ」
- モイランとギバードは足首まで埋まる砂地を踏みしめてメンヒルに駆け寄った。接近した二人の足に砂地とは違った感覚があった。
- 薄くかかった砂のためにわからなかったが、よく見ると巨大なメンヒルを中心に大小さまざまな敷石が放射状に組まれてあった。
- 「ギバード、このメンヒルをどう思う?」
- モイランは踵を敷石に打ちつけながら意見を求めた。
- 「明らかに他のものとは違うようです。それに、今まで見つかったものの中で一番巨大です。他のメンヒルとは違って、何か特別な意味を持ったものかも知れません」
- 羅針盤で計測をしていた男が慌てた様子で駆けてきた。
- 「羅針盤が狂って、計測ができません」
- 「なんだと……」羅針盤が狂うことなど今まで一度もなかった。モイランは不吉な症状に言葉を失った。
- 「このメンヒルの影響かも知れませんね」
- ギバードはそう言いながらも、敷石を丹念に調べていた。
- 「ん? これは……」砂に隠れた敷石に何かを見つけた。身を屈め、邪魔な砂を手でどけると敷石に組み込まれた砂岩板が現われた。
- 「見てください。砂岩板です。文字が刻んであります」
- モイランも羅針盤の男も、ギバードの示す砂岩板に注目した。
- 「読めるか?」
- モイランの問いにギバードは首を横に振った。見たこともない文字だった。鋭い刃物で削いだのか、表面には文字の溝がきれいに残っている。一文字ずつ角ばり、区分けされ、奇妙な象形文字のレリーフが刻まれていた。
- 「どうだ、これを外して持ち帰れそうか?」
- 「外せないこともないでしょうが……。時間がかかりそうです。これに手を触れるのは、詳しい調査を終えてからの方がよろしいかと思います」
- 「そうか」
- 「とにかく、この文字を書き写しましょう」
- 「そうしてくれ。他にも何かないか捜させよう」
- そうは言ったものの、二人とも本心はすぐにでも城壁に戻りたかった。予定の刻限はとっくに過ぎている。巡回隊の面々は帰りがけのタイミングの悪い発見を、大いに呪っていた。
- 目に映るのは砂地ばかりだ。
- アレスを護送する馬車がカーンに着いたのは、ガロアの荒野を出て二十四日目だった。ガロアからヒウケビロス大陸の北西にあるノスタの港まで下り船に乗せられ、海を渡りカーンの港ベルボボに着いた。そこで一度拘留されたアレスは護送用の馬車を待ち、他の犯罪者とともに世界の北西の果てに運ばれてきた。
- 「あの御者、一言もしゃべらないぜ」
- 「なあに、俺たちが暴れるんじゃないかとびびってんのさ」
- 乗り合わせた流刑者たちが軽口を叩いても、アレスは馬車の隅に黙って座っていた。
- 唯一の財産だった赤い鎧も剥がされ、代わりに麻のボロ服をあてがわれた。馬車はきしみをたてて揺れている。護送用の馬車は、台車の上に木で組んだ檻が載っているだけの粗末なものだった。同行するのは無口な御者一人と、警備兵二人だけ。その気になりさえすればいつでも逃げることはできた。だが、未だ放心状態から脱していないアレスは、チャロナから放たれた悪寒に震え、脱出など思いつく頭もなかった。膝を抱え、黙って檻の隅に座るアレスの焦点は何かに結ばれることもく、ただ馬車の揺れに合わせて揺らいでいる。惚けたように自分の殻に閉じこもったまま、アレスは砂漠の道を運ばれた。
- 夕闇が砂漠の世界を包んだ頃、ようやく馬車はカーンの城壁に辿り着いた。
- 御者の合図で門が開き、馬車はアーチ状の入口から城壁の内部に呑み込まれた。馬車が二台すれ違える幅は優にある。石造りのトンネルは意外なほど幅広く、規則正しく幾重にも組まれた積み石が松明の炎に照らし出されていた。トンネルの壁石はわずかな隙間もなく精巧に積み重ねられている。その完成度は緻密に計算された貴族たちの城以上だった。馬車は薄暗いトンネルを奥へと進んだ。石畳を蹴る馬の蹄の音が響いた。松明の炎に揺れる壁面が単調に流れ、催眠術のように時間の観念を奪った。不意に馬車は止まり、闇に埋もれていた壁面の扉から城壁の兵士たちが現われた。
- 「着いたぜ」御者の声を初めて聞くと、アレスたち流刑者は追い立てられるようにして馬車から降ろされた。 兵に肩を押されて通されたのは、薄暗い、息の詰まりそうな部屋だった。受刑者たちは順番に入獄の手続きを行なった。しばらく待たされるとアレスの番がきた。二人の老人が待っていた。二人とも、かなりの年嵩で、くたびれた黒いフードを纏い、延ばし放題の白髭を生やしている。アレスは老人たちと古めかしい机を挟んで椅子に腰掛けた。老人の一人が兵から受け取った連絡状を拡げた。
- 「名前は---」
- もう一人の老人が、しゃがれた声で読み上げて照合を始めた。
- 「アレス=トラーノス。拘束地、ガロア」
- 「罪状は---」
- 老人たちは連絡状に書かれた罪状を目にして息を止めた。
- そこには「皇帝殺害」と書かれていた。老人たちは興味深げにアレスを見直した。目の前にいる一介の受刑者が、皇帝殺害などという大それた事件を起こした当人であるとは信じ難いことだった。そして何よりも、数日前から駆け巡っていた皇帝の死の噂が事実だと知らされたショックは大きかった。
- 「本当に皇帝はお亡くなりになられたのか?」
- 連絡状を持つ老人が小刻みに手を震わせて念を押した。
- 「そうらしいな……」アレスは無気力な呟きで答えた。しばらくの沈黙が包んだ後、書状をめくる音が、やけに大きく聞こえた。
- 「アレス=トラーノス。明朝より流刑を執行する」
- 冥府の審判のような老人の言葉にも、アレスの心は揺れようともしなかった。
- 窓のない独房には光は届かない。入獄の手続きをした老人は、確かに一晩だけの独房と言った。妙だった。パンと水の食事はあれから四度運ばれた。二日が経過したことになる。アレスの体内時計もそれくらいの時間を告げていた。ここにきて、ようやく悪寒をもたらしたチャロナの邪悪な感覚も、冷静に思い起こせるようになっていた。それでもなぜ自分がチャロナを斬ったのかわからない。首尾よく賞金首を落とした後にこんな事態が待っているとは、アレス自身にも信じられないことだった。
- なぜ、自分はあの時チャロナを斬ったのか? 納得できる答えは何もない。一つだけ考えられる答えは、まったく馬鹿げたものだった。
- ---あいつ自身が……。俺に斬るように仕向けた……。
- アレスは一瞬浮かんだ想像を打ち消した。とにかく、ここから出たかった。止まったような時間に悶々としているのが堪えられなかった。この時間から逃れられるのなら、流刑にされた方がマシだとさえ思った。
- 命令を出すべき獄長のカザルは困惑していた。皇帝を殺した男が送り込まれている。連絡状には当たり前のことしか記されていない。一便遅れてボルタイからの通達状が届いたが、それがまた、カザルを悩ませた。
- 「皇帝殺害者アレス=トラーノスを送る。よろしくされたし」
- 「よろしく」という部分がわからなかった。早く殺せという意味なのか、それともボルタイの姦計に協力した同志として優遇しろという意味なのか、どちらにもとれた。本国に問い合わせても返事が届くまでには二月はかかる。「当人に訊ねるしかないか……」二日がかりで考えあぐねた答えがそれだった。
- 固い足音が独房の前で止まった。扉が開き、監獄の通路を何度も屈折した光が独房の中に差し込んだ。かなり弱い光だが、闇に馴れたアレスの目には強過ぎた。
- アレスは城壁の内部を網の目のように渡る通路を連行され、やがて一つの扉の前で止められた。
- 部屋の中では小綺麗なマントを纏った男が待っていた。看守は事務的な声で、それが流刑地カーンの獄長カザルであると告げた。
- 「お前のおかげでボルタイ様がゲルニアを統治することになったそうだな。通達状が届いている。くれぐれもお前をよろしくとのことだ」
- アレスは反応を見せなかった。たとえ悪意はないにしろ、中央に秘密でメンヒルの調査や地図の作成を進めているカザルにとって、目の前のアレスは密命を帯びた監査員にも思えた。
- カザルは内心困惑しながらアレスの表情をうかがった。
- 「皇帝の殺害はお前とボルタイ様が仕組んだものなのか?」
- 思い切って訊ねても、何の反応も示さない。見れば目の前の男は生気もなく、視線は宙を泳いでいる。
- ---深読みのし過ぎだったか。
- カザルは自分が敏感になり過ぎていたようだと理解した。
- 「わかった。ならば流刑者としてお前を扱うが、それでいいんだな?」
- 言葉が伝わっているのかいないのか、アレスはへらっと笑った。それが唯一の反応だった。
- <h2>星の道連れ</h2>
- ヒウケビロス大陸の北西の突端にあるノスタはにぎやかな港町だった。カーイは町に入るなり、旅をすれば新しい町に着き、そこで生活をしている人々に逢うことができるという、あたりまえのことに喜びを覚えた。
- 港に通じる街角には赤煉瓦が敷きつめられていた。その上にさまざまな露店がたち並んでいる。町全体が市場のようだった。魚、果物、野菜、牛肉、軒を並べる露店には何でも売っていた。そろそろ夕食の買い出しが始まる時刻のようだ。商人の声と品物をもとめる客たちの声が、まるで喧嘩でもしているかのように荒々しく飛び交っている。活気のある町は久しぶりだった。少年は人の溢れる町を嬉しそうに眺めながら港を目指した。漁港であり、外洋船の航路にもなっているノスタの港は大きい。岩を組んだ埠頭は海に向け巨大な弧を描いて突き出、数えきれないほどの漁船が縄で繋がれている。
- その一角に、外洋船の停泊場所も定められてあった。
- 「どれがカーンに行く船なんだろう」
- 小さな漁船を威圧するように、三本マストの外用船が二隻停泊していた。一隻は帆をたたみ人足たちが一生懸命に荷を降ろしている。もう一隻はすでに船乗りたちが乗り込み、船長の出航の合図を待っているだけのようだった。街角のにぎやかさに負けることなく、港も活気に満ちていた。荷物の上げ下ろしに人足たちが慌ただしく船と埠頭を往復している。人足頭が荒々しく怒鳴っていた。
- 港の慌ただしさに混じり、カラカラという馬車の音が後ろから近づいた。振り向くと木の檻を載せた護送馬車だった。檻の中には受刑者が三人乗っている。どの顔も狂暴そうな顔つきで、カーイは思わず唾を飲み込んだ。
- ---流刑地に送られる奴らの馬車だ。連中が乗る船に忍び込めばいいんだな。
- 獰猛そうな受刑者たちを目で追いながら、カーイは彼らが運ばれる船に目星をつけた。
- 弓なりに曲がった港が黄金に染まった頃、港から一隻の船が出航した。ノスタの港から出航した船は星明かりの海を進み、順調な航行を続けた。
- 他の甲板よりも一段高い中央のマストの縁に少年は忍び込んでいた。マストに吊られたカンテラの灯りが縦に横に揺れている。港の喧騒に紛れて船に潜り込むのは、体の小さいカーイには容易いことだった。カーイはマストにもたれて大きく伸びをした。朝には目的地に着いているはずだ。ひと心地つけて星を眺めていると、誰かが甲板に上がってくる足音がした。身を低くして覗き見ると、星明かりが痩せた船乗りの姿を映し出した。船乗りは甲板のあちらこちらにあるカンテラの一つ一つに、油を差して回り始めた。
- ---まずいぞ……。
- いよいよ中央のマストに向かってくる。カーイは身を屈めたがカンテラは真上にある。足音が一歩一歩近づいてきた。船乗りは怪訝そうに一段上の甲板にうずくまる影を覗いた。
- 「誰だ?」
- 「やっ、やあ……」カーイは頭をかきながら観念した。
- 「このガキ、密航か!?」
- 「へへっ」
- いつもなら、これで済む時もあった。だが今日のカーイはついていなかった。痩せた船乗りの眼は爬虫類の眼のように冷たく、心の通いを期待できそうもない。力にはへつらうが、弱い者に対しては容赦のない残忍さを見せる眼だ。
- 船乗りは乱暴にカーイの襟首を掴むと、無理矢理甲板の下に引きずり降ろそうとした。
- 「何すんだよ!」
- カーイはその腕を思いっきり弾いた。船乗りは予期せぬ子供の抵抗に目を丸くした。
- 「船長のところに突き出してやろうと思ったがヤメだ。俺がしばらくお灸をすえてやる」
- 襟首に再び手が伸びた。今度は船乗りも慎重だった。子供に振り払われるようなやわな力でなく、力を込めて襟首を締め上げた。カーイの足は甲板から離れ、体は軽々と持ち上げられた。器官が塞がれて声も出ない。カーイは足をバタつかせてもがいた。船乗りは残忍な笑みを浮かべると、そのままカーイを甲板に投げつけた。甲板に穴が開くかと思うほどの大きな音がした。カーイは苦痛のあまり動けなかった。俯く少年の顎を、船乗りは左手で持ち上げた。
- 「生意気なガキは気にくわねえんだよ」
- 船乗りは少年を虐待すべく右手の拳を振り上げた。ところが、繰り出そうとしたその腕がぴくりと止まった。動かない。誰かが手首を掴んでいた。
- 「そのあたりでやめたらどうだ」
- 低いがとおる声だった。さっぱりと分けた銀髪、青い瞳、鼻の下に蓄えた髭。仕立てのよいマントをつけ、腰からは長剣をさげている。歳の頃は五十くらいの旅の剣士のようだった。
- 「あんた……誰だ?」
- 初老の剣士は答えずに、万力のような力で船乗りの腕をそのまま返し、その上に何枚かの硬貨をのせた。
- 「この坊主の船賃だ」闇から現われた剣士はそう言うと、顎で追いやる仕草を見せた。
- 船乗りは初老の剣士の醸し出す気配に抵抗する勇気もなく、すごすごとその場から姿を消した。
- 「坊主、大丈夫か?」
- 「助かったよ」
- 「それにしても、こんな船に密航とは船を間違えたようだな。この船は流刑の大陸カーンに向かっている。ベルボボの港に着いたら乗り換えるんだな」
- 「なら間違えてないさ。おいら、カーンに行くんだ」
- 剣士は少年の意外な答えに興味を覚えた。カーンに向かうのは受刑者くらいのものだ。このような少年がどんな目的を持って辺境を目指しているのか想像ができなかった。
- 「坊主、名前は?」
- 「カーイさ、カーイ=ジムクント。おじさんは?」
- 「俺はマトリ。マトリ=カークランドだ」
- 救われた礼もそこそこに、少年はその場に寝転がった。安心したためか、それともよほど度胸がいいのか、カーイは横になるとそのまま眠りについてしまった。
- マトリは半ば呆れながら満天の星々に視線を移した。夜空では降るような星が輝きを競っている。
- ---早急にアレスを確保しなくては……。
- ブディドでの託宣の示した星がアレスならば、流刑の地で何が起きても不思議はない。天界の流れが全てを導き、邪悪なるものも動き出す。邪神が次の動きを見せる前に何が何でもアレスを救い出す必要があった。
- 船は夜通し進み続け、朝には予定どおりカーンが見えてきた。
- 「坊主、着いたぞ。ベルボボだ」
- すっかり寝入っていたカーイはマトリの声に目を覚ました。寝呆け眼で立ち上がったカーイは甲板の上から砂漠の大陸を見た。港以外は砂ばかりに見えた。
- 「カーイだったな。お前はここに何をしにきたのだ?」
- 「人捜しさ」
- 「流刑者に身内でもいるのか?」
- 「いいや。おいら、逢いたい奴がいるんだ。おじさんこそ、何しにきたのさ?」
- 今度は逆にカーイが訊ねた。マトリはしばらく砂漠の大地を眺めてから静かに答えた。
- 「同じだ。人捜しだ」
- 港が間近になり、船乗りたちが接岸の準備のために慌ただしく甲板に出てきた。
- 棗椰子の葉に午後の日差しが揺らいでいた。
- エリマはカーンに残された楽園だった。カーンには珍しく、水源になる泉と作物を収穫できる土地を持っていた。流刑地の城壁には一番近く、水のない城壁を支える水源として、エリマは重要な役割を担っていた。もっとも、近いといっても城壁からは馬車でも優に二日はかかる。しかも、その道は噴煙を上げるエクシ山を頂くテベステ山脈を貫くものだ。無理矢理に峠道を通したものの、好まれて旅人が往来する街道とは異なり、殺風景な険しい道だった。それでも城壁からは三日に一度「樽馬車」と呼ばれる便が赴き、水を確保するために定期的にエリマに訪れた。どんなに険しい道でも必要不可欠な水の道だった。
- その峠道を一台の樽馬車が車輪を軋ませていた。
- 「そろそろエリマだ。いつもながら往きは楽なんだがな」
- 御者を務める兵士が、眼下に見え始めたエリマの村を認め、連れの兵士に話しかけた。
- 「まったくだ。帰りの道のりを思うと、うんざりするぞ」
- 樽に水を満たした帰り道は困難を極める。馬も大変だが人間も滅入った。
- 「それに、今回は水運びだけでなく、モイラン隊長の御命令もあるからな」
- 「巡回隊のモイラン隊長か?」
- 「ああ、メンヒルから見つかった砂岩板の文字を読める者を捜せってことだ」
- 兵士は懐から四ッ折りにしてしまいこんでいた紙を取り出した。巡回隊の副隊長ギバードがメンヒルの砂岩板から写し取った古代文字だった。
- 「こんなものを読める奴がいるのかね?」
- 「ギバード様の話じゃ、エリマが一番望みがあるとのことだ」
- 「砂漠の民の伝説のことだな」
- 「ああ、ベルボボまで行ってしまえば、古代からのこの地の住人とはおぼつかんが、エリマの住人の祖は砂漠の民の可能性がもっとも強いそうだ」
- 「砂漠の漂泊民族か。さすがに学者肌のギバード様だ。巡回隊の副隊長をなさるより、研究者としてカーンに駐留される方が性に合っておられるかもな」
- 泉を求めて辺境を移動する砂漠の民---。いくら生活が困難でも決してカーンを離れることなく、生き抜けるだけの水と作物を得て聖地を守り続ける部族。伝説ではそんな砂漠の民が存在すると語り継がれていた。
- 「俺ならもっと肥沃な土地にでも移って、さっさと金回りのいい仕事に変わってしまうんだがな。それにしても、カーンが聖地だってのはどう言うことだ? 地獄の流刑地がその昔は聖地だったってのは、変われば変わるものだ」
- 「まったくだ。一体何の聖地だったのやら……だ」
- 村に下る峠道とベルボボからくる街道が交わっていた。樽馬車はそこで二人の旅人を追い越した。「旅人か。珍しいな」行き過ぎながら御者の兵士が呟いた。地味だが仕立てのよいマントをつけた男と、もう一人は浮浪児のようにみすぼらしい服装をした少年だった。
- 「足は丈夫なようだな?」マトリはカーイに言った。
- 「ああ、旅はなれっこさ。でさあ、そろそろ教えてくれてもいいんじゃないの? おじさんが捜しにきたのってどんな奴さ?」
- 「お前こそ白状したらどうだ」
- 問い返されたカーイは悪戯っぽく笑った。
- ベルボボの港から歩き始めてから、ずっとこの調子だった。二人は船がベルボボに到着するなり、申し合わせたように同じ方向に歩き出した。マトリがエリマを目指して歩き出した時、カーイが後をついてきた。かと言って別にマトリを頼りにしている感じでもなく、カーイはあくまでも自分自身の旅としてエリマを目指しているようだった。
- 「お前、宿は決まっているのか?」
- 少年に宿の用意など、あるはずもないことはわかっていた。
- 「俺はひとまずエリマで宿をとるが、一緒にどうだ?」
- カーイは嬉しそうにニコリと笑って頷いた。
- エリマの宿は酒場を兼ねた小さな旅宿だった。表には木をあぶった看板に「銀の角笛」と店の名がぶらさげられている。入ると窓ぎわにテーブルが三つあり、あとは厨房と食堂を仕切るカウンター席しかなかった。フロアから奥に階段が伸びている。客室はすべて二階のようだった。他の客はいなかった。二人は手近なテーブルに落ち着き、食事の支度が整うのを待った。料理を待つあいだ、マトリは果実酒に口をつけた。カーイはじっとしてマトリが酒を呑む様子を見ていたが、しばらくして料理が運ばれてくると大食らいが始まった。懸命に肉にかぶりつき、スープをすする。運んできた主人が目を丸くするほどの勢いだった。
- 「親爺、客は俺たちだけか?」器を下げにきた主人にマトリが訊ねた。
- 「いや、今日は城壁の兵士が泊まることになってる。大方、女のところにでも、しけこんでいるんだろう」
- 「ああ、馬車の連中だな」
- マトリは村の入口で自分たちを追い越していった馬車を思い出した。
- 「樽馬車じゃよ。いい客じゃないがね。ここの泉に水を汲みにくる兵士は、決まってこの宿に泊まることになってる。旅の客などほとんどありゃあせん。ゲルニアから金をせびってやっているような店だから文句は言えんがね」
- 「そうか、それで町から離れているわりには、いい料理がでるんだな」
- 「そういうわけだ」主人は笑って見せた。
- 「ああ、もう食えねえや。でも、まだ食えるよ」
- 「食い過ぎて腹を壊すぞ」
- 「だいじょうぶだって」
- 膨らんだ腹をさすって、カーイは幸せそうに笑った
- <h2>一番鶏</h2>
- 夜明け前。「銀の角笛」の狭い客室に衣擦れの音がした。
- マトリは眠っているカーイを起こさないように気を配りながら出発の準備をしていた。
- ---坊主、お前のことは昨夜主人に頼んでおいた。きっとお前の捜す者が見つかるように手筈をつけてくれるだろう。
- マトリはカーイの寝顔を見ながら心の中でつぶやいた。腰に剣を差し、マントをつける。音をたてないよう扉に向かった時、背中で声がした。
- 「おじさん、そりゃあないよな。おいてきぼりかい?」
- マトリは悪戯が見つかった子供のように戸惑いながら振り向いた。
- 「監獄の城壁に行くんだろ?」
- 「声が大きい」マトリは小さな声で制した。
- 「隣の部屋の兵士たちに聞こえたらヤバイんだろ?」
- 夜明けを待つ部屋でひそひそ話になった。
- 「おじさんの人捜しも、どうやらまともな仕事じゃなさそうだね。ねぇ、おいらも連れてってくれよ」
- 「ダメだ。お前を連れて行くには俺がやろうとしていることは危険すぎる」
- マトリは答えてから、孫ほども歳が違うカーイの誘導尋問にかかったことに気づいた。
- 「カーイ、俺の言うことを聞け。ここでお別れだ」
- 幾分目を細めたマトリの表情には鋭さがあった。赤い傭兵に逢いたい。どうしようもない衝動にかられてカーイはここまできた。心の底から湧き出すような欲求はまだ続いている。
- 「いやだ、あいつに逢うんだ」
- 強情に食い下がるカーイがマトリには新鮮だった。
- 「それほどまでに言うのならば訊ねるが、お前の捜している"あいつ"とは、どういう者なのだ? お前が命を賭るほど、逢う価値のある奴なのか?」
- 「そんなこと、逢ってみなきゃわかんないよ。でも、おいら赤い傭兵に逢いたいんだ」
- 「赤い傭兵?」
- 「ガロアの国王を倒し、ゲルニアの皇帝チャロナを殺した傭兵さ」
- マトリは息を止めた。少年が捜している人物が同じアレスだったとは……。どのような理由でカーイがアレスを追っているのか興味がわいた。
- 「アレスだ。あいつの名前はアレスってんだ」
- 「なぜ……? なぜその傭兵に逢いたい?」
- 「わかんない。でも、逢わなきゃいけないんだ。クアルの村でゲルニアの行軍の中にあいつを見かけた時から、ずっとそう思ってたんだ。なぁ、連れてってよ」
- 「クアルだと。お前、ガロアからきたのか?」
- マトリはブディドでのカンベーテの託宣を思い出した。
- 星はガロアからカーンに流れる---。まさかとは思うが、星に導かれるのが大人だけとは限らない。
- 「お前は、わからないことに命を賭られるのか?」
- 見つめ合った互いの瞳には、もう答えが映っていた。
- 「よし、連れていこう。ゲルニアの全権大使に化けてのり込む算段だ。お前は俺の剣を持て。旅の途中で拾った従者という筋書きだ。できるな?」
- 「ああ、バッチリさ」
- 「城壁に着いたら一言もしゃべるんじゃないぞ」
- 「そりゃないよ。こう見えてもおいら、しっかりしてんだぜ」
- 「おいらはやめろ」
- 「おいらはおいらだよ。それより、おじさんの捜してる人ってどんな奴なのさ?」
- カーイは横目でマトリの表情を窺った。
- 「逢えばわかる」
- マトリの口元が少し笑っているように見えた。気がつくと一番鶏の叫びが、一日の始まりを告げていた。
- その朝、アレスは砂漠の流刑地に放り出されることになった。開け放たれた内門から延々と遥か彼方まで続く砂漠が見えた。
- 「本当に流刑にしていいのだな」
- カザルが念を押しても相変わらずアレスの反応はなかった。看守がアレスの腕を後ろ手にして、馴れた手つきで荒縄で縛る。そして、その背中に刃の広い銅の長剣を挟み込んだ。
- 「かつて異教徒を葬った時の名残でな。お前だけに渡すわけじゃない。これも掟だ。それと食い物だ」
- 看守が用意した黒パンを二個、カザルはアレスの襟元に入れた。
- 「どうして食い物と銅剣を渡すかわかるか? その食い物を狙って殺し合いをさせるためだ。死刑を執行しなくても流刑者たちが勝手に殺し合う。手間が省けるというわけだ。そうだ、お前には特別に助言を与えてやろう。砂虫とは、闘おうと思わん方がいい」
- アレスは無表情だった。自由にならない両腕を後ろ手に回し、とぼとぼと砂漠の中に足を踏み入れて行った。
- ---アレス=トラーノスか。砂岩板のこともある。あの男が、しらを切りとおし、死ぬつもりならば、それもよかろう。
- その姿が砂漠に出たのを確認すると、カザルは腕を軽く上げて門番に合図を送った。軋みが響き、アレスの背にカーンの内門の閉じる音が聞こえた。
- 果てしない砂漠が目前に広がっていた。砂漠の太陽は容赦なく照りつける。願いが叶って城壁から出たが、今度は灼熱の地獄が待っていた。生暖かい風が体を包み込んだ。
- ---せめて腕を自由にしたい……。
- 荒縄はとても容易に解けるものではなかった。銅剣に擦り付けようとしても腕の動きに合わせ、同じように動く。荒縄を縛った看守の顔が恨めしく思い出された。立ち止まって目を走らせても、まだ他の流刑者の姿は見えなかった。空を見上げると照りつける太陽の反対側にうっすらと月が輪郭を見せていた。うだるような日中に月を見るのは妙なものだ。一歩進むごとに足は深々と砂にめり込んだ。 不意に背後の砂が微かに不自然な音をたてたような気がした。何かが砂の中から自分を窺っている。
- 突然、砂が大きく巻き上がり、奇声とともに銅剣を構えた男が踊り出た。牙をむく銅剣が空を裂く。体は勝手に反応し、飛び退いていた。
- 「死ねーい!!」
- 転がったアレスに流刑者が襲いかかる。見るからに盗賊然とした顔の流刑者だった。両腕が使えない上、砂の足場では思うように動きがとれない。アレスは身を転がして逃げるしかなかった。
- ---くそっ……!
- 攻撃の間をつき、素早く立ち上がる。アレスは相手の動きを見定めると、脇腹へ重い蹴りを入れた。
- 「けっ、逆らうんじゃねぇよ。ここで死んだ方が楽だぜ」
- 待ち伏せ男は激痛に堪えながら言った。
- 流刑者の剣がまた襲いかかる。アレスは繰り出された剣を躱すと、同じように蹴りを一発返した。流刑者が斬りかかり、アレスが蹴り返す。単調な攻守を何度か繰り返しているうちに、流刑者の足がもつれた。呼吸は乱れ、争いが長引くにしたがって確実に流刑者の体力は消耗していく。本能のままに体を動かすことで、霞がかかっていたように不鮮明だったアレスの思考は、次第に明確さを取り戻していった。待っていたヤケの大振がきた。アレスの美しく上がった右足が、男の延髄を見事に捕らえる。流刑者は目を剥いたまま砂地に倒れ込んだ。
- 「取り引きだ。縄を解いてもらおうか。嫌ならこの場で殺す」砂煙を引き摺って倒れた流刑者にアレスは言った。
- 「解いた後で殺す気じゃないだろうな……」
- 「かんぐっても仕方ないだろう。どうせここは口約束が通用する世界じゃなさそうだ」
- 「けっ」
- 「名前は?」
- 「モーガン。人呼んで、待ち伏せモーガン。俺の罠から逃れたのは、あんたが初めてだ。あんたは?」
- 「アレス。ただのアレスだ」
- 力の差を認めたのか、モーガンはアレスの後ろに回った。しばらくするとスルスルと荒縄が抜かれていく感覚が腕につたわり、背負わされていた銅剣がズリ落ちた。
- 「ここにきて何日だ?」
- 「四、五日ってとこだ。ここで四、五日も生きればもう古株だぜ」
- モーガンは自慢げに言った。
- ---四、五日で古株か……。
- ここに放たれた流刑者のほとんどは、二、三日ももたない。モーガンの言葉はもっともだった。
- 「ここには強制労働もないし、しちめんどくせい決めごともない。そのかわり、砂虫や砂漠狼が五万といやがる。とんでもねえとこだぜ」
- 「じゃあな」
- 銅剣を拾うとアレスは歩き出した。モーガンに有益な情報は望めそうもない。これ以上「待ち伏せ野郎」と関わっていても無駄だとアレスは思った。
- 「おい、待ってくれ! これからどうすんだい?」
- 「さあな、当てはない」
- 「ただ当てもなく歩き回るなんて寿命を縮めるだけだぜ」
- モーガンの意見は的を得ていた。当てになるかどうかは別として、アレスには一つ気になっていることがあった。必要以上に城壁のカザルが気を回していたのが気になっていた。
- 探りは秘密の裏返しである場合が多い。カザルが何を隠している匂いがした。
- 「ここにきてから何か見かけなかったか?」
- 「見かけるって? 巡回隊ぐれえだな」
- 「どっちの方角だ?」
- 「向こうの方だ。何度も行ったり来たりしてやがる」
- モーガンは砂漠の一点を指差した。
- 「行ってみるか」
- 方角を定めるなりアレスはすぐに歩き始めた。モーガンも、なぜかそれに続いた。
- 「けど、奴らは馬で移動してるんだぜ。どれだけ遠くに行ってたのか見当もつかねえ」
- 「当てさえあればいいんだろ?」
- 「まあ、そうだが……」
- 「なんでお前、ついてくるんだ?」
- 「いいじゃねえか。俺も歩いてみたくなっただけだ」
- 二人にはどちらが東なのか西なのか、それさえもわからなかった。ただここに止まっているにもいかず、アレスの直感だけを頼りに砂漠を歩き始めた。
- <h2>食人種たち</h2>
- 強烈な血の匂いが漂っている。流刑者同士の殺戮に出くわしたアレスとモーガンは、慌てて砂漠の丘陵に身を隠した。
- ひい、ふう、みい、よう……。モーガンは砂漠の丘陵に隠れ、流刑者たちを数えた。
- 二十人はいる。銅剣を携えた流刑者たちの群れは地獄の亡者のようだった。焼けつく太陽の下で極限に置かれ、生存本能のみが彼らを動かしている。雄叫びを上げ斬り掛かる流刑者。血飛沫を上げ倒れる者。動けなくなった者は、その瞬間から食料へと変わった。覆いかぶさり人肉を食らう者。さらにその者を銅剣で狙う者までもいた。
- 「ひどいもんだ……」
- 待ち伏せ専門のモーガンでさえも、思わず声を洩らした。食うか食われるか。文字どおりの戦いが繰り広げられていた。
- 息を潜めて見守る二人をよそに、人肉をむさぼる流刑者たちの地獄絵は続いた。
- 「食人種か……」アレスの喉の奥から胃液のすっぱさが上ってきた。
- 「とても人肉まで食らう気にはならんぜ」モーガンが吐き出すように呟いた。
- 「ここでの修業が足りないのかも知れないな」
- 「冗談じゃねぇ」
- アレスの冗談は笑えなかった。モーガンはこの現実にあらためて戦慄を覚えた。食事を終えた食人種たちが死体から離れていった。哀れにも食人種たちの餌になり果てた屍が、砂の上に散らばったいる。ほとんどは人間の姿を留めていない。まるで気紛れな殺人台風が過ぎ去った後のようだった。血の匂いを臭ぎ付けて砂虫がくる可能性がある。二人はすぐにその場を立ち去った。
- いつしか太陽は傾き、時間の経過をアレスたちに示していた。朝、砂漠に放たれてから歩きづめのはずなのに風景は一向に変わらず、かろうじて変わったものがあるとすれば、ふり向いた時に見える城壁がいくらか小さくなっているというくらいだ。体の疲労は正直で、足は棒のように感覚を失っている。腿を交互に持ち上げるというだけの作業が、途轍もなく困難な仕事になっていた。
- 「よう、ここらで一休みにしようぜ」
- 「そうしたいところだが、何処か岩場を捜してからにしよう。砂虫には用心するに越したことはないだろうからな」
- 適当な岩場を捜してアレスは砂漠を見渡した。そんな時に限って休めるような場所はない。代わりに、遥か遠方を駆ける砂煙が視界に入った。
- 「巡回隊だ。城壁に戻るところみたいだぜ」
- 「急ごう。うかうかしてると寝床を見つける前に暗くなる」
- 砂塵を目で追っていても仕方がない。太陽の休息を告げるかのように砂漠全体が冷え始めている。いつの間にか猛暑は去っていた。風に払われた雲が黄昏に染まるのも時間の問題だ。二人は疲れを騙しながら先を急いだ。
- いくつかの砂漠の丘陵を越えた時、黄昏が訪れた。二人はその中で、砂漠にそそり立つ異様な物体を目にした。
- それは真っ赤な西日を受けて砂漠の大地に直立していた。
- 「アレス。ありゃ、なんだ?」
- 「わからん。……石のようだ。巨大な石の柱だ」
- 石柱は砂漠に残された墓標のように立っていた。人間の三倍の高さはある石柱だった。人が造ったものなのか、それとも自然の造り出したものなのか、アレスには判断できなかった。先端こそ風化して丸くなっているが、紡錘形の巨大な石は間近で見れば人工的なもののようにも見えた。周囲には砕けた大岩が散乱している。
- 「ここが巡回隊の奴らが調べ回っている所なのか。とにかく、今日はここで休もう。砂虫を避けることだけはできそうだ」
- 二人は小舟ほどの広さのある平らな岩の上に陣取ることができた。いくら砂虫でも岩を破って襲ってはこない。しばらくすると夜のとばりが静かに下り、昼間から白い輪郭を見せていた月が、太陽の代わりに砂漠の世界を照らし始めた。
- 長く尾を引く狼の啼き声がこだました。
- 月の世界が始まった途端、今度は狼の遠吠えだった。
- 「しめた。砂漠狼か……」アレスは腰を上げると遠吠えのする方角に走り出した。
- 「おい、何だよ? 何をするつもりだ」
- 「そこで待ってろ!」モーガンを岩場に残し、アレスは構わず丘陵に駆けた。
- 月光の照らす砂漠の丘陵に出ると銅剣を砂に突き刺し、両手で筒を作るようにして口にあてがった。岩場から見るモーガンは、その行動に首を傾げた。アレスは山岳地帯の羊飼いがするように、独特の呼び声をあげて砂漠狼を誘った。
- 「ろーろろろっ……! ろーろろろっ……!」
- すぐに四匹の砂漠狼が現われた。砂漠狼たちは警戒をとかず、低い唸りを上げながら遠巻きに接近した。砂漠狼の眼が月光を反射して光った。軽やかに砂を蹴り、砂漠狼の一匹がアレスに向けて飛びかかる。砂地に刺しておいた銅剣を素早く抜き、アレスはすくい上げるように斬り上げた。間髪を置かず、次の砂漠狼が襲いかかる。正確な剣さばきが次々に砂漠狼を仕留めた。狼たちは剣に吸い寄せられるように空中を舞い、落下した時には息絶えていた。残るは一匹。アレスは身を屈めたままの低い姿勢で相手の出方を見た。
- まるで、一流の剣士を相手にしているような緊張感を味わっていた。狼が砂地を蹴った。剣を振り下ろす。砂漠狼は瞬発力の塊のように飛び退いて躱した。敏捷だった。至近距離からの跳躍で、突然目の前に跳び出、アレスの腕のリーチよりも内側に飛び込まれた。首を守るため、アレスは咄嗟に自分から左腕を牙に押し込んだ。腕に激痛が走った。腕に狼をくっつけたまま、アレスは後ろに転倒した。砂漠狼は獲物を離さない。牙は深く刺さっている。砂漠狼の唾液が腕を濡らした。苦悶の銅剣が砂漠狼のあばらをゆっくりと貫き、狼の痙攣が伝わった。剣を引き剥がすと、あばらから溢れ出した血が、飛沫のように降りかかった。
- 「くそっ。モーガン、運ぶのを手伝え!」アレスは岩場に向けて叫んだ。
- 呼ばれたモーガンが慌てて駆けてきた。
- 「砂虫に取られたら骨折り損だ。運んでくれ」
- 「ああ、わかった」
- アレスは一匹を引きずって岩場まで運んだ。モーガンは二度往復して残りを運んだ。
- 「けっこう旨そうだ」腕の痛みも忘れ、肉をさばきながらアレスが言った。
- 「こいつら人間を喰ったのかな、間接的な共食いかもな」
- そう呟くモーガンだったが、食べ始めればそんな迷いなど、すぐに消し飛んだ。水分が不足している体には、わずかな肉汁でも心地よく喉にしみわたった。肉は腹がハチ切れるほどある。二人はものも言わず肉に食らいついた。腹が膨れると、二人の興味は石柱に移った。
- 「しかし、こんなもんがあるとはねえ」疲れた足を伸ばしながらモーガンが言った。
- 月の光に照らされた石柱は、デコボコとした表面を青白く映し出している。
- 「何かの遺跡か……」石柱を見上げ、アレスは漠然とした感想を口にした。
- モーガンが不意に立ち上がった。
- 「そうだ、間違いねえ。あんた、カーンに伝わる古い話を聞いたことあるかい?」
- 「俺はトーラスの生まれだ。そんなもんは知らん」
- 「そうかい、この辺りにはおかしないい伝えがあるんだ。ガキの頃、婆さんから聞いたんだがこの辺りも大昔は人の住めるところだったんだそうだ」
- モーガンは夜の砂漠を眺めて言った。
- 「その昔、ここで神々の戦いがあってな。その戦いのせいだっていうんだ。何か悪さをやって天界を追放された神がいて、そいつがヤケになって地上をめちゃくちゃにしようとしたらしい。慌てた神々は精霊たちを使い、その神を取り押さえようとここへ送ったって話だ」
- 「じゃあ、ここの砂漠は、神々の喧嘩のとばっちりと言う訳か?」
- 「まあ、そう言うこったな。この柱がその時の戦いで壊されたものの残骸だとすりゃあ、説明もつくぜ。お伽話だとばかり思っていたが、そうでもなかったみてえだな」
- 「それで、その我侭な神はどうなったんだ?」
- モーガンは首を横に振った。言い伝えの類はいつも大事なところが抜け落ちているものだ。「その話、ここの看守たちは知ってるのか?」
- 「どうだか。奴らはもともとここの人間じゃねえからな。知らないんじゃねえか」
- 話し終えたモーガンはさっさと横になり、高鼾をかき始めた。
- ---神々の喧嘩の跡か……。我侭で迷惑な神もいたもんだ。
- 伝説の神々の戦いと遺跡。そして獄長カザルの隠し事は、関連のあるものに思えた。
- 今はまだ結び目の見えない糸口を探りながら、いつしかアレスも眠りについていた。
- 朝焼けが砂漠を照らし始めた頃、まだ、まどろみの中にあるアレスの耳に、砂を摺る沢山の足音が聞こえた。音は殺気に変り、すぐさま警戒信号を送った。
- 「起きろっ、モーガン!!」
- 岩場の上に陣取ったことで安心したのが迂闊だった。四十人、いや、五十人はいた。
- 食人種たちは岩場を取り囲むようにして近づいている。ようやく目を覚ましたモーガンが自分の置かれている立場を理解した。砂漠狼の血の匂いを臭ぎつけられたのだ。
- 食人種たちの目は野獣のようにらんらんと輝いている。相手が人間であるだけに、その輝きは昨晩の砂漠狼より、一層不気味に見えた。食人種と化した流刑者たちは、四方からゆっくりと岩場に這い上がってきた。
- 「こいつらの朝飯になるのだけは、ごめんだな」
- 「ああ、ごめんだ……」
- ものは試しだった。アレスは昨日の残りの砂漠狼の肉塊を、食人種の一団目掛けて投げつけた。途端に肉食魚のように群がり、砂漠狼の五体は跡形もなくなった。
- 「残りの肉を全部奴らに投げつけるんだ! 道が開いたところを突っ切るぞ!」
- 「よし来たっ!」
- モーガンが勢いよく砂漠狼の肉を投げつけると、すぐに十名ほどの食人種が肉片に群がった。「これでも食ってろ!!」
- アレスも続けて投げた。その間にも食人種たちは岩場に這い上がってきた。昇ってくる食人種たちをアレスは蹴落とした。
- 「いくぞ、モーガン!」
- 掛け声とともにアレスとモーガンは岩場から飛び下りた。肉にあぶれた食人種たちが二人に襲いかかる。アレスは進路を妨害する者だけ斬った。まとわりつく食人種を払うのに、モーガンは手間取った。
- 「どけ! どきやがれ!」二人の間隔が広がる。
- 「モーガン、早く来いっ!!」アレスが通過した砂地の下で、わさわさと蠢く気配があった。
- 突然、砂の中から何かが跳ね上がった。イノシシほどもある巨大な砂虫だ。砂虫は芋虫のような体をくねらせ、ちょうど駆けて来たモーガンの前に跳躍した。
- 「モーガン!! 離れろっ!!」
- 食人種を斬りながらアレスが叫んだ。跳ね上がった砂虫を、転びそうになりながらモーガンが避ける。食人種が砂虫を狙った。
- 「やめろっ!! 斬るなーっ!!」
- 流刑者は構わず銅剣を砂虫に振り下ろし、砂虫の体内から強酸性の体液がほとばしった。
- 体液をあびた食人種が絶叫を上げながら倒れた。体液は衣服を焦がすだけにとどまらず、食人種の皮膚まで焼き焦がした。
- 「モーガン!! 砂虫から離れるんだ!!」
- アレスの叫びが悶える食人種の絶叫と重なった。
- 砂虫の体液は水袋が弾けるように飛散する。かろうじて躱したモーガンは必死の形相で駆けた。砂虫は何匹も砂の中から跳ね上がる。跳ね上がった場所には煙玉を割ったように砂塵が四散した。砂虫は獲物を目掛けて胃液を吐く。受けた食人種の銅剣がぐつぐつと溶けた。
- アレスは流刑者たちが銅剣を持たされる理由を理解した。銅剣は殺し合いには使えても、砂虫相手には何の役にも立たない、皮肉のたっぷりと込められた無用の長物だった。
- <h2>メンヒルの謎</h2>
- アレスが砂漠に放たれて三日が過ぎた日の朝、カーンの城壁に訪問客があった。二人の訪問客はエリマの宿から樽馬車の通る峠道を使い、テベステ山脈を三日かけて越えてきた。
- 用立てた馬に跨がったマトリは、すっかりゲルニアの全権大使に化けていた。カーイといえば、相変わらず埃にまみれた浮浪児だったが、馬の手綱を引くその姿は正真正銘の従者にしか見えないから不思議だった。
- 「勅命だ!! 開門しろーっ!!」
- マトリは堂々と大声で叫んだ。毅然とした態度に門兵が慌てて応対した。
- 「ゲルニアの全権大使カーク=マクラレンだ」
- マトリはでたらめの名前を言った。門兵は狼狽えながらマトリを迎え、すぐにカザルの執務室に通された。カーイはあらかじめの打ち合せどおり、扉の外でマトリの剣を持ち、立ちんぼうで待つことになった。
- 「お初にお目にかかります。カーンの監獄責任者カザルでございます」
- ---やはり来たか。
- そんな目をしながらカザルは慇懃に言った。その目を見て、マトリは頭から本題に入った。「アレス=トラーノスと言う男が送られているはずだが」
- 「はい。流刑者として扱いましたが」
- 「流刑にしただと?」
- マトリは意識して鋭い表情でカザルを睨んだ。カザルの肝は縮みあがった。
- 「なぜ、流刑が方便だとわからなかった? ことの流れを見れば、あいつがボルタイ様の手の者であると、わかるであろう」
- ---そう言われても……。だから俺は奴に確かめたのだ。だが奴は何の反応も示さなかった。
- 心でそう思いながらもカザルに弁解の余地はなかった。
- 「もうよい! 即刻回収の準備をさせろ。これは型どおりの赦免状だ。目を通しておけ」
- もちろん赦免状は勝手にでっちあげた偽の書類だった。宮廷戦士として経験を積んでいるマトリは書類の体裁も一とおり心得ていた。怒鳴られたカザルはマトリが本物の全権大使と疑いもしない。
- 「ほかに変わったことはないだろうな?」
- 赦免状に目を通し始めたカザルに追い打ちをかけた。カザルは動揺を隠せなかった。この上、本国に連絡もなく遺跡の調査をすすめていたのが知られれば、不穏分子ともとられかねない。すべてを話しておいた方がよさそうだと、カザルは思った。
- 「実は……。この機会にお話がございます」赦免状を巻き整えながらカザルは言った。
- 「まだ、ご報告をいたしておりませんでしたが、流刑地の砂漠の中より、遺跡とも思われる巨石群を発見しました」
- 「ほう、なぜそのような重要なことを、今まで黙っていた?」
- マトリはカザルの心情を見通したように言った。目に見えてカザルの額に冷汗が浮かんだ。「すぐに詳しいご説明を」
- 暫らくして、呼び寄せられた巡回隊のモイランとギバードが、カーイの前を通り過ぎ執務室に入ってきた。カザルの急かす仕草に、モイランはマトリに一礼しただけで、さっそく説明を始めた。
- 「まだ未完成ですが、地図をご覧下さい。巨石は七つの地点で発見されております。これらの印がそれを示すものです」
- モイランは地図上に×印を示している部分を指差した。×印は砂漠の一角を意味ありげに丸く取り囲んでいる。
- 「六つの巨石が砂漠を取り囲み、その中心に、もっとも巨大で原型を留めているメンヒルが発見されました」
- 「メンヒル?」マトリは聞き馴れない言葉に問い返した。
- 「紡錘形の立石です。高さは人の三、四倍といったところです。中でも一番中心のものは特別巨大で人の十倍はあります」
- 「そんな巨大なものが、どうして今まで発見されずにいたのだ?」
- 「砂漠は常に形を変えるものです。これまでは丘陵の中に隠れており、発見できなかったものだと思われます。目に触れていたものも風化が激しく、自然のものだと思われておりました。今回地図を作成し、関連づけて考えて、始めて人工のものであったという確証が得られたわけです」
- モイランに代わり、ギバードが説明を続けた。
- 「かつて皇帝がここを流刑地と定めて以来、我々はこの城壁を使ってきましたが、今もってここの城壁を誰が建てたのかも謎のままです。今回の発見は初めてその謎に近づく手がかりになると思われます」
- ギバードは机の隅に用意しておいた砂岩板の写しを広げた。あの巨大なメンヒルの敷石から自らが写し取ったものだ。
- ---これは……。
- マトリはその文字を一目見て、それがブディドに伝わる古代文字に酷似していることに気づいた。
- 「中心に位置するメンヒルに、砂岩板として据え付けられておりました。今のところ解読はできておりません。しかし、これが読めれば有力な手がかりになるはずです。現在、隣境の長老、語り部、学者などに打診して解読を急いでいるところです」
- 「この写しは、まだあるのか?」
- マトリは古代文字の書かれた紙を取り上げて訊ねた。
- 「どうぞ、それをお持ち下さい」媚びるようにカザルが答えた。
- 「そうか。では貰っておく。本国に説明の必要があるからな。すぐにアレスを回収に出るぞ。案内しろ」
- 懐に古代文字の紙切れを仕舞ながら、有無を言わせない口調でマトリは命令した。
- カザルはモイランとギバードに砂漠に出る準備するようにと目で促しながら、アレスが生存していてくれることを心から祈った。回収といってもこの広大な砂漠だった。この地獄の流刑地で、まだアレスが生きているという確証はなかった。
- 準備のできる間、マトリはカザルから、こと細かにアレスが砂漠に放たれた時の情況を聞き出した。やがて準備が整うと、モイランの率いる巡回隊の案内で、マトリは砂漠へと出ることになった。
- 「どこに行くのさ?」兵士たちに悟られないようにカーイはマトリに訊ねた。
- 「いいから黙ってついてこい」マトリは短く答えた。
- いくら従者という役柄でもカーイに砂虫の出没する砂漠を走らせるわけにもいかず、マトリは特別な計らいということでカーイを自分の馬の前に乗せた。
- 「ご案内すると言っても、正直に申しまして見当もつきません」
- モイランは困惑した表情でマトリに言った。
- どんなに難しい問題でも糸口はあるもの。マトリは自分の経験からアレスの行動を推察し、思いを巡らせた。たとえば、流刑に出された時の様子から、生きることへの執着が失せていることがわかった。それとは逆に、傭兵として染みついた本能から、逆境にはしぶといという予測もたつ。少なくとも、生きていれば城壁を離れ、移動を続けているのではないかと思った。
- ---冷静になれば自分の行動に対して目標を捜し始めるはずだ。それが傭兵というものだ。
- 目標とは……?
- マトリは最後の判断を直感に任せた。
- 「……メンヒルだ。城壁から一番近いメンヒルはどこだ? 徒歩ならどのくらいかかる?」
- 「ほぼ真北です。徒歩なら丸一日はかかるでしょう」ギバードが答えた。
- 「丸一日か。奴が放たれてから三日か。次のメンヒルは?」
- 「直線に進めば砂岩板のあった中心のメンヒルです」
- 「それだ」マトリには確信めいたものがあった。
- アレスがもう死んでいるかも知れない、などとは考えもしなかった。戦場でも砂漠でも同じことだ。弱音を吐いたら望みも運も逃げる。砂漠を走り出した馬に揺られながら、アレスは絶対に生きていると心に念じた。
- <h2>魔神の息吹</h2>
- 鉄を含んだ土壌は焦げた灰色だった。岩石が鋭利な石面を剥出しにしている。ゲルニア帝国の城のある高台は、そんな岩石でできていた。
- ウビロス大陸の中ほどにある世界最強の軍事国家ゲルニア。その首都は城を中心にして八角形のプレート状に広がっていた。街は見るからに要塞としての機能だけを考慮された造りで、冷たく人の温もりを感じさせない区画都市だった。城壁の中から巨大な円錐形の塔が曇り空に向けてそびえている。それは天界の秩序に反発する軍事国家ゲルニアを象徴する光景そのものに見えた。
- ガロア遠征から戻ったボルタイは、命を落としたチャロナに代わって新しいゲルニアの君主に立った。新しい統治者の登場はすぐに諸国に広まった。ボルタイの指揮権は揺るぎない。ジュミレスの存在も、皇帝亡き今では気に止める必要はなかった。
- ジュミレスは最後の望みとして皇帝の埋葬を自分の手順で取り行ないたいと申し出た。ボルタイはその申し入れを受けた。皇帝に近かったジュミレスの願いを許すことにより、新君主の寛大さを誇示しようとの思いからである。
- ジュミレスはいっさいの者たちを本殿のチャロナの間から排除した。厚いカーテンを閉ざし、部屋を暗闇で覆い、何百という蝋燭を部屋一杯に燈した。ジュミレスはたった一人で失われたタミアラ大陸の秘儀を試みていた。生前チャロナ自身から教えられた秘儀だった。
- 『死して脱け殻となった肉体に魔神の魂を吹き込み、現世に蘇る法がある。我は魔神の魂を封じたヒーロルを持っている。それを使った時、より強大な力と永遠の生を得るのだ』
- 今にして思えば、チャロナはすでに出兵前、圧倒的優位の状況にも関わらず、まるでこの法を必要とする事態が起こることを予期していたかのように、ジュミレスに説いていたのだ。
- 一日が過ぎ、二日が過ぎた。初めは本殿の中で行なわれている儀式に興味を覚えていた人々も、日が経つにつれて関心を薄れさせていった。四日も過ぎるとジュミレスのことさえも忘れた。
- 本殿の正面に安置された皇帝の亡骸を、ジュミレスは狂気の表情で見ている。
- もともとがミイラのようだったチャロナの亡骸は、腐ることもなく苦悶に満ちた表情のまま横たわっていた。
- ---今こそ、魔神の息吹を吹き込む時……。
- ジュミレスは傍らに置いた小箱に手を伸ばした。小箱には黄金の光を放つ半透明の物体が入っていた。水没したタミアラ大陸の遺産、伝説の金属ヒーロルだ。この中に魔神の魂が封じ込まれているとチャロナは告げていた。ジュミレスは皇帝の棺の前でゆっくりとそれを掲げた。「さあ、皇帝を目覚めさせたまえ!」
- 途端にヒーロルの内部から黄金の輝きが放たれた。輝きはみるみる増し、闇にぬり込められていた本殿の隅々まで照らし出す。内包する魔力が爆発したように感じられた。
- 放出される輝きが絶頂に達し、迸る光の渦の中、目には見えない何かがチャロナの亡骸に飛び込んだ。光がかき消えたその時、横たわっているチャロナの目蓋が静かに開いた。チャロナの復活はあまりにも凶悪な邪悪さに満ちていた。自らが仕組んだこととはいえ、ジュミレスは儀式を成就した喜びより重く、後戻りのできない怯えを感じた。
- チャロナは瞬きもせずジュミレスを見た。
- ゲルニアの最高権力者となったボルタイは忙しい日々を送っていた。
- 新体制での官吏の人事、属国の情勢の把握、実行中の作戦の変更、やらなければならないことはいくらでもあった。
- その日も朝から議事室で属国の新しい管理方針について官僚たちと会議を続けていた。
- ようやく会議が一段落つき始めた頃、近衛兵団隊長に任命されたばかりのガイソンが血相を変えて入ってきた。
- 「申し上げます。謁見の間に兵が集まっております」
- そんな命令を出した覚えはボルタイにはなかった。会議を放り出し駆け出すと、二万名は収容できる広大な謁見の間に兵士たちが整列していた。
- 灰色の焼き煉瓦で作られた演台に一人の男が歩み出ている。瑠璃色の長い髪で、女のように華奢な体つきだった。
- 「ジュミレス……」
- ジュミレスは白銀の鎧に銀糸の刺繍を施したマントをつけ、近衛兵団の正装をしている。
- ---本殿に篭もって皇帝の魂を慰めていると聞いていたが……。
- ボルタイは久しぶりに見るジュミレスに鋭い眼差しを向けた。ジュミレスはゆっくりと兵士たちを眺め回してから口を開いた。
- 「諸君。本日は素晴らしい知らせがある。我々の皇帝が復活なされた」
- 信じ難い言葉に、兵士たちの間に疑いの波が起った。ボルタイは兵士たちの騒つきを見て、苦笑いを浮かべた。
- ---気でもふれたかジュミレス。死んだ者が蘇るわけがない。醜態をさらしてどうする。
- ボルタイは心でそう呟いてから、真っすぐと姿勢を正して演台に向った。兵士たちがそのボルタイに気づき、ほとんどがその場で首を跳ねられるジュミレスの姿を頭に描いた。ボルタイは十分にジュミレスの顔を見られる距離まで近づいた。すると、ボルタイに気づいたジュミレスが小さく笑った。
- ---何だ、その笑みは……?
- 凍るような衝撃を受けた。それでもボルタイは兵士たちを意識して、毅然とした態度をつくりジュミレスに言った。
- 「何事だ。血迷ったか!」
- ジュミレスは涼しげな顔でもう一度ボルタイに冷笑を浴びせると、反対にボルタイを真っ向から指差し怒鳴りつけた。
- 「無礼だぞボルタイ! 皇帝の御前だ、跪けっ! 皆も跪くのだ!!」
- 「なんだと!?」
- 怒鳴り返そうとした時、ジュミレスの立つ演台の後ろから神輿がせり上がってきた。二十四名で支える皇帝の神輿だ。かついでいるのはジュミレスの配下の、以前の近衛兵団の面々だった。ジュミレスと同じく彼らは皆正装していた。そして神輿の上にはミイラのようなチャロナの姿があった。兵士たちはさざなみが打ち寄せるように、前から順々に跪いた。
- 「馬鹿な……」
- ボルタイは浜に取り残された小石のように立っていた。
- 「皇帝は一度お亡くなりになられた。だが皇帝は死を克服された。死をもって命を得たのだ。そして、もはや永遠に死ぬことはない」
- ジュミレスは狼狽えるボルタイに、勝ち誇ったように告げた。
- 静かに降ろされた神輿の玉座から、チャロナの冷たい眼が見ている。ボルタイは震えていた。ようやくゆっくりと跪くと、自分の命の終末をいさぎよく感じた。
- 「ボルタイ将軍。皇帝の御意志を代弁する。皇帝不在における貴殿の働き、称賛に値する。よって属国バジザンの統治を命じ、その国名をボルテアと改め、貴殿の管轄下とすることを許すとのことである」
- 理解できない不条理な戸惑いがボルタイの心に込み上げた。
- ---なぜ……。なぜ俺を殺さん。称賛に値するだと……。馬鹿な。一体何を目論んでおるのだ!?
- たとえ皇帝が死んでいたとは言え、不在中に玉座についた家臣など、殺されて当然だった。心中で疑問をぶつけるボルタイに、ジュミレスはただ冷笑を浴びせるばかりだった。
- 砂漠を行く二人は憔悴しきっていた。アレスもモーガンも、ふらつきながら歩くのが精一杯だった。重い足を引き摺り、小さな砂の丘でさえ、越えるためには数時間を要した。
- 登りは蟻地獄に落ちた蟻のように手足でもがき、下りは重力に身を任せ、降りるというよりも転がり落ちた。
- 「もしも……神がいるのなら、今すぐこの俺に水とパンをくれ……」
- モーガンが砂のこびりついた唇を震わせて言った。
- 「無理だ……。俺たちは神に貸しがない。それに、ここの神はとんでもない奴らしい……。神頼みするだけ無駄だ」アレスは半分独り言のように答えた。
- 口にできるものは何もない。もう食人種になってもいいとさえ思った。
- 実際にはアレスが砂漠に放たれてから、まだ三日しか経っていなかったが、ここに来てからの様々な出来事が、遥か遠い昔のことのように思えた。
- 『お前たちの運は尽きたのだ---』
- 砂漠の風に混じり、誰かが囁いたような気がした。
- 目は霞み、砂漠の景色が陽炎に揺れている。朦朧とする頭と視界。陽炎の中、目の前に巨大な何かが聳えていた。
- 「墓標だ。俺たちの墓標に違いない」二人は同じことを思った。
- その時、砂漠の風があたかも意志を持ったように吹き荒れた。露出した肌を砂の一粒一粒が針のように突き刺した。視界はすっかり閉ざされ、先程まで隣で喘いでいたモーガンの姿さえ見えない。すべてが砂嵐の轟音にかき消され、風圧が口を封じた。目も鼻も口も、いくら砂の侵入を防ごうとしても無駄だった。
- 「モーガン! どこだ!」
- 返事がない。叫んだ口に砂が吹き込み、吐き捨てても口にごわごわとした感覚が残った。
- アレスはうつ伏せになって砂漠にへばりついた。隠れる場所のない今、砂虫を気にする余裕もなかった。
- 砂嵐は吹き荒れ、叫び、時間が経つにしたがって強くなる一方だった。アレスは乾燥して膨れ上がった唇を意味もなく震わせた。
- 何者かが放つ、深く強大で邪悪な想念を感じた。その感覚はチャロナを斬る前に感じたものと同じものだった。笑みを浮かべるチャロナが脳裏に見えた。
- ---お前のせいか? 答えろ!
- 砂嵐の渦の中で幻想と現実が入り混じり、アレスの意識をかき乱した。間違いなくチャロナが笑っている。
- 不意にアレスは意識の中で一段落下したような感覚を覚えた。
- 「星だ。星が見える……」次に口走ったのはそんな言葉だった。
- その時には、心は別の世界に旅していた。もう、砂漠の行軍も砂嵐も、別の次元のものだった。アレスは意識の中のもう一つ深いところで、自分に近づく二つの影を感じた。子供と、もう一人は剣士のようだった。
- 「星だ、星が二つ近づいてくる……」
- 吹き荒ぶ砂嵐をものともせず、二つの影はしっかりとした足取りで歩んでいた。アレスは二人が砂を踏みしめて歩く音を、意識の底で聞いていた。
- <h1>第三章 呼び覚ます運命</h1>
- <h2>漂白の民</h2>
- 懐かしい風景が見えた。芦原が広がっている。故郷の村、アシュワだ。春には野花が咲き乱れ、秋には収穫を祝う宴の声が村中に響くような村だった。
- 優しい人々は、穏やかな日差しの中で慈しみ合うように暮らしていた。
- 村の北側には険しい岩山がある。断崖はデッパと呼ばれていた。迫り出した断崖は、嵐の海の巨大な大波のようだった。
- 父の姿が見える。それはアレスが十歳になった年の、ある日の光景だった。風のそよぐ芦原にアレスと父は立っていた。父は逞しい腕を伸ばし、芦原の先にそびえる断崖を指差した。
- 「見ろ、アレス。デッパは神の領域だ。お前が十三になったら、あの崖を登れ」
- 父の言葉が耳鳴りのように脳裏を過ぎ去ると、今度は母の姿が見えた。見慣れた家の中で、病身の母が床についている。土壁に藁葺きの屋根。質素な部屋に、暖炉の炎だけが赤々と燃えている。母は病に蝕まれていた。その年の秋口から流行り出した疫病は、瞬く間に村中に広がったのだ……。
- 男たちが旅の支度をしている。手に手に武器を持ち、旅の理由も告げず、男たちは旅立った。それからも、毎日のように疫病の犠牲者たちの葬式は続いた。男たちは誰一人として戻らなかった。もちろん、父も。
- 二年目の冬。母も死んだ。珍しく深く雪の積もった明け方だった。アレスはその時の自分を見ていた。まだ幼さの残る横顔が震えている。
- 母の葬式を済ませると、アレスは一人、村を出た。
- アレスはデッパに登らなかった。
- テベステ山脈を貫く険しい峠道を一台の馬車が進んでいた。麻の幌を付けた四頭立ての馬車だ。幌の下には大木のように二人の男が転がっている。
- カーイは二人の邪魔にならないよう、馬車の隅に張り付いていた。
- 「うまく行ったろ? きっと、おいらがいたから怪しまれなかったのさ」
- 手綱を操るマトリにカーイは自慢げに言った。
- 「こいつ、何なんだろうね。見るからに悪党の顔つきだけどさ」
- 眠るモーガンの顔を見て、胡散臭そうにカーイは続けた。
- マトリとカーイがメンヒルに着いた時、アレスは半分砂に埋もれていた。そのすぐ側にこの男も埋もれていた。
- 「とりあえず一緒に助けたけど。どうも、インチキ臭い奴だよな」
- 「気がつけば、わかることだ」しゃべりすぎるカーイに、マトリはそっけなく答えた。
- 「でも、あいつら間抜けだよね。帰りの馬車まで用意してくれてさ」御者の背凭れを掴み、激しく揺れる馬車の上に立ち、カーイは言った。
- 「おい、馬車から落ちるなよ」
- 「平気さ。ねぇ、おじさんは、何でアレスを捜していたのさ?」
- マトリは少年に話すべきか迷っていた。カーンに向かう船上で知り合い、この短い間で二人はそれなりに打ち解けた。だが、アレスのことを説明するには、理解や信頼より重い、星の繋がりを必要とした。つきつめた話は避けたかった。
- 「わかったよ、今はいいや」マトリの表情を読み取ったのか、少年は拍子抜けするほど物分かりのよい答えを返した。
- 「いいさ。どっちみちアレスが教えてくれる。アレスには話すんだろ? だったらおいらはアレスから聞けばいい。おいらとアレスは、きっとすごい縁があるんだ。おじさんもね。ひょっとすると、こいつもさ」
- カーイはアレスの横に倒れている悪党面を顎で示した。気がつくと、たなびく雲の向こうから日暮が迫っている。
- 暮れかけたせいか、昼間は噴煙しか見せなかったテベステ山の火口に、仄かな火柱が上がっているのが見えた。
- マトリの操る馬車は夜を徹して走り、二日でエリマの村に到着した。
- 村の人影が消えた頃、「銀の角笛」の停車場に、幌馬車は静かに着けられた。
- 「カーイ、宿の主人に俺たちが戻ったことを伝えろ。部屋の用意に、それから医者だ」
- 「うん、わかった」
- 答えるとカーイは宿の中に駆けて行った。マトリは馬車の手綱をしっかりと結びつけ、まずアレスを馬車から担ぎ出した。肩からアレスの鼓動が伝わってくる。カーイに聞いたのか、主人がすぐに出てきた。
- 「二階の奥の部屋だ。医者を呼んでくる」
- 主人はそれだけ言うと、アレスを担いだマトリとすれ違いに、外へと出て行った。
- 二人を部屋に運び入れてしばらくすると、扉の外で足音が聞こえた。
- 「主人に頼まれてきた」
- しゃがれているが、優しげな老人の声だった。
- 「医者か?」
- 「医者のタイナーじゃ」
- マトリは扉を開け、医者を招き入れた。中に入ってきた医者は、声から想像したとおり、温厚そうな白髪の老人だった。袖口の広い麻服で、薬草を詰めた粗末な大袋を肩から袈裟掛けにぶらさげていた。
- 「だいぶ水気を抜かれている。肌も弱っておるようじゃな」挨拶も抜きに、ベッドに横たわる二人の男を見て、老人は言った。
- 「ねぇ、なんとかしてくれよ。全然気がつかないんだ」
- タイナーは軽く頷くと、さっそくアレスの額に手を当て、そしてモーガンの額にも手を当てて体調をうかがった。
- 「熱はないようじゃが、二人とも皮膚がひどく弱っておる。風土病の心配はないと思うが、薬を塗っておいた方がいいじゃろう。坊主、これを塗ってやれ」
- タイナーは大袋の中から塗り薬の容器を出してカーイに渡した。
- 「へんな匂いだ」
- 蓋を開けるなり、カーイは顔をしかめた。薬草を混ぜ合わせた青臭い匂いが鼻をついた。
- 「この薬には気付けの効能のある成分も含まれておる。嫌でも目を覚ます。全身に塗ってやるといい」
- 「どうして自分で塗らないのさ?」
- 鼻で息をしないようにして、カーイはタイナーに訊ねた。
- 「臭うからのう」タイナーはそう言うと、病人に構わず小さく笑った。
- カーイは鼻を曲げながら、丹念にアレスとモーガンの体に薬を塗り付けた。
- 「それでいい。二人ともかなり無理をしたようじゃが、しぶといらしいな。後は体力が回復すれば自然に治る」
- そう言いながら、老人は袋の中からいくつか薬草を取り出した。香草にはさまざまな神秘の力が隠されている。病気、ケガの治療はもちろん、魔除けや疲労回復、体力増強、能力開発と、あらゆる方面に役立つ。鎮静作用のあるカモミール。体力増強のカルダモン。殺菌の薬効があるセージは筋肉疲労にも抜群の効力を発揮する。タイナーはそれらの香草を目算で計り、適当な分量だけをテーブルの上に置いた。
- 「坊主、二人が気がついたら、このハーブを宿の主人に頼んでスープにしてもらえ。すぐに元気になる」
- 「うん」
- 「あんたたちも飲めばいい。凄い味じゃよ」
- タイナーは笑みを含んでそう言ったが、カーイは味を想像するだけで恐かった。
- 「おいらはいいや、普通のスープにするから……」
- 「さて、わしは行くとするか」
- 「金はいくらになる?」マトリが医者に尋ねた。
- 「わしはこの宿のお抱えの医者じゃ。料金は宿代を払う時に一緒でいい」
- 「そうか、世話をかけたな」
- 「たいしたことではない。しかし、カーンの監獄から流刑者を助け出すとは、穏やかではないのう」
- タイナーの口振りはマトリたちを責めているようには聞こえなかった。マトリは穏やかに胸中を告げた。
- 「できれば、ここに泊まる樽馬車の連中には、口をつぐんでいてもらいたい。万がいち、ベルボボから船に乗るまでに追われることになると、厄介なのでな」
- 「いや、そのことなら心配はない。わしもこの宿の主人も、城壁の奴らとは、所詮、打ち解けぬあいだがらじゃ」 「打ち解けぬあいだがら?」
- 「ウビロス辺りから来た者などに、何も勝手にさせておるわけではない。元よりこの地にいる者は、誰もいい顔はしておらん」
- それを聞いた時、マトリに閃くものがあった。
- 「もしや? 漂泊の民と呼ばれる人々がこの大陸にいると聞いたことがあるが……」
- タイナーは静かに頷いた。
- 「いかにも。わしもその一人じゃ」
- 城壁の連中は血眼になってカーンの賢者や砂漠の漂泊の民を捜していた。それが、こんなに近くにいたとはマトリもいささか驚いた。
- マトリは黙って懐から、城壁で手に入れた古代文字の書かれた紙を取り出した。
- 「我が祖先の残したもの」タイナーは軽く文字を見ただけで、あっさりと言った。
- 「城壁の中でこの文字を目にした時、ブディドにある文字と似ていると思ったのだが」
- 「言われるとおりじゃ。これは東洋の神秘国、ブディドに残るものと同じ文字で書かれておる。もちろん、今ではとうに忘れ去られた文字じゃが」
- 「なぜそのような文字が、このカーンに?」
- 「すべてはカーンから始まったからじゃ。ブディドの文字も、このカーンから伝わったものなのだろう。だが、その文字は決して歴史の表舞台に出ることはなかった。なぜだか、わかるかな?」
- 答えられないマトリに、タイナーは自ら答えを語った。
- 「神の文字だからじゃよ」
- 「神の文字? 詳しく聞きたい」
- 「いいとも、別に特別な話じゃない。ここの者なら誰でも知っていることじゃ。もっとも、城壁にいるゲルニアの連中には、誰も教えんがね」
- タイナーは笑みを見せてから続けた。
- 「遡ること三百年ほど前のことじゃ。この地は、今のような砂漠の大地からは想像もできぬほど、緑に恵まれた豊かな土地だった。ある日、この地を治める王の元に、奴は突然現われた。その姿は人間とたがわず、白き衣を纏った姿はどこにでもいる年寄と変わりなかったそうじゃ。奴は王にこう言った。
- 『自分は天界の神の一人で、闇を支配する神である。これより人間は闇に属すべきものと決まったのだ。いたずらに生きるのみの人間がこのまま蔓延れば、この世界のみならず大宇宙の秩序さえも乱すことになりかねない。人間は闇に従い生きるのだ。三日後、地上に送り込んだ私の息子が兵を率いてお前の城を訪れる。申し出に従い、城をあけ渡すのだ』
- それだけ言い残すと、奴は霞のようにその場から消え失せた。
- 城をあけ渡すべきか、断固として闇の神と名乗る者の申し出を拒むべきか。王はすぐに長老たちを集め意見を聞いた。闇の神が人の神であるわけがない。たとえ神と名乗る者の申し出であっても、やすやすと承諾できるものではなかった。協議の末、王は勇気をもって闇の神の申し出を退けることに決めたのじゃ。三日後、闇の神が言ったとおり、何千もの死者の兵を引きいて闇の神の息子が現われた。その男こそ、フヒド=ワラー。今でも伝説の暴君として名をとどめる、あのフヒドじゃ。奴はこう言った。
- 『愚かなる者たちよ。お前たちがいかに拒絶しようとも、もはや闇の呪縛から逃れることはかなわん。闇に支配されてこそ、真実の安らぎを永遠のものとできるのだ。我が申し出を受けることが最良の道と知れ』
- カーンの軍隊は闇の妖しい力に守られたフヒドの兵の前に、あまりにも無力だった。なす術もなく倒されて、王宮も民たちも混乱の中で散々となり、抵抗する力さえも封じられた。
- 王は離宮に幽閉され、世界は太陽の光を失った。昼でもぶ厚い曇が垂れ篭め、陽の光は地上に届くことはなくなった。闇だけが世界を覆ったのじゃ。人々は見えなくなった太陽を想い、祈り続けた。すると、光を失って七日目の朝、太陽の神から離宮の王の元に啓示があった。
- 啓示は言葉ではなく、直接王の頭の中に文字として流れたそうじゃ。なぜ、王がそれを理解できたかは知るところではない。だが、王はその啓示に従い、わずかに残った仲間とともに再び立ち上がったのじゃ。離宮を抜け出した王はメンヒルを立て結界を張り、闇の力を弱めた。そして長くつらい戦いの末、砂漠と化した大地と交換にカーンは太陽の光を取り戻した。その戦いが歴史に残るフヒド=ワラーの最期とされておる。我々の祖先は闇の神に勝ち、フヒドを倒したのだ。王はその戦いを記し、太陽の神から啓示として受けた文字をメンヒルに刻んだとされておる。その文字には、そういう謂れがあるのじゃ」
- 「ブディドの文字は水没したタミアラ大陸から伝わったと聞いたことがあるが?」
- 「タミアラは地上の神の国。同じで当然じゃ」
- タイナーは寝ている二人の呼吸を確かめた。
- 「いい呼吸じゃ。この呼吸ならひと寝入りすれば目を覚ますじゃろう」
- 「ご老人。この文字を読める者はいないのか?」
- 「残念じゃがな。漂泊の民と呼ばれるわしらでさえ、読める者はおらん。だが、あるいはブディドの高僧などの中には、この文字を読み取れる者がおるかも知れんが……」
- ---ブディドの高僧。
- カンベーテが思い浮かんだ。あるいは祖父のスクネもこの文字を解することが出来るのではないかと思えた。ブディドに残る文字も同じく、もしかしたら、カンベーテやスクネは、謎とされている文字をすでに読み、理解しているのではないか?
- ---だとすれば、なぜ、謎としたままにしているのだ……。公表をはばかるようなことが書かれているのか?
- メンヒルの文字は偶然に手にしたものだった。しかし、その内容が闇の神の暴虐から逃れるための方法が印されたものだとすれば、今、世界が迎えようとしている邪悪神との戦いにも、何らかの手掛かりを指し示してくれるのではないかと、マトリは思った。
- タイナーが帰り、真夜中、盗賊顔の流刑者が目を覚ました。
- 椅子に腰を掛け、寝ずの見張りをしていたマトリはその瞬間を見逃さなかった。床ではカーイが大きな寝息をたてている。目を覚ました流刑者は、自分の置かれている事態を掴めず、呆然として辺りを見渡した。
- 「どうなってんだ……。砂嵐で死んだと思ったら、ベッドの上だ……。俺は、いったいどうなっちまってんだ?」
- すぐに疑問に答えるマトリの声がした。
- 「安心しろ。ここはまだカーンだが、流刑地じゃない。エリマの宿だ」
- カーイを起こさないように小さな声だった。
- 「今はまだ夜更けだ。あれこれ考えるのは明日にしろ」
- 「あ、ああ」
- モーガンは素直に従って目を閉じると、十も数えないうちに、再び寝息をたて始めた。
- しばらくして、今度はアレスが目を覚ました。
- 「気がついたな、アレス」
- 「誰だ? 俺を知ってるのか」
- アレスは闇の中で椅子に座る人影に訊ねた。闇の人影には敵意はなかった。
- 「挨拶は明日の朝にしよう。まだ眠った方がいい」
- 「そうさせてもらう」
- 一度寝返りをうって、アレスも再び眠りについた。朝まではまだ時間がある。マトリは椅子に凭れたまま、静かに目を閉じた。
- <h2>邪神の血脈</h2>
- 窓からは眩しい太陽の輝きが差し込めている。
- マトリが目を覚ますと、部屋の中には誰もいなかった。肩が張っている。顔をしかめながら肩を回し、自覚以上に自分も疲れていたことを痛切に感じた。
- 「どこに行ったんだ?」
- 部屋を見回すと、荷物はそのままだった。取り残されたわけではないようだ。マトリは年甲斐もなく動揺した自分に失笑した。
- 「あの二人、もう動き回れるほど良くなったのか。カーイも、どこに行ったんだ」
- 軽やかな足音とともに、カーイが部屋に入ってきた。
- 「おじさん、起きたね。アレスたちなら、下で馬みたいに食ってるよ。今からハーブのスープを作ってやるんだ。昨日の爺さんもきてるよ」
- カーイはテーブルの上にある薬草を摘みながら楽しげに言った。見るからにアレスが意識を取り戻したのが嬉しくて仕方がないといった様子だった。
- 「もうアレスと話したのか?」
- 「ちょっとだけね。早く、行こうよ」
- まるで子供にせかされる父親のようだった。カーイのペースに巻き込まれると、マトリは殆ど無抵抗になっている。それがカーイの不思議なところだった。
- マトリは寝起きの頭を押さえながら、元気一杯のカーイの後から部屋を出た。
- 主人は厨房で肉を焼いていた。カーイとマトリが階段から降りてくるのを見ると、マトリに向かって軽く右手を挙げて見せた。
- マトリも軽く視線で挨拶を返した。カウンターにはハーブ茶を飲む老人がいる。昨晩の医者のタイナーだ。
- 「急げよ。夕方には次の樽馬車が到着する」
- マトリが後ろを通った時、タイナーは小声でそう告げた。
- 窓側のテーブルでモーガンが懸命に食事をとっている。
- 「あんたの連れてくる客は大食らいばかりだな」焼き上がった肉を運びながら主人は言った。「もう一人の男はどうした?」
- 「外で水をかぶってる」
- 窓越しに外を見ると、主人の言うとおり、アレスが停車場の横にある井戸で、水をかぶっているのが見えた。
- カーイは薬草を抱えてカウンターの中に入ると、ハーブ茶を楽しむタイナーと何やら話しながら、まるで自分の家の厨房を使うように、遠慮なく薬草のスープを作り始めた。
- 食事に熱中していた大食らいが、ようやくマトリに気づいた。モーガンは新しい腿肉を持ったまま立ち上がった。
- 「旦那。助かった、恩にきるぜ。俺はモーガンってんだ」
- 「かまわん。つづけてくれ」
- マトリはモーガンの肩に手をあてて再び座らせた。
- テーブルの上には食い散らかしたパンや肉の切れ端、それに空になったバスケット。舐めまわしたように綺麗になった木の皿が幾枚も折り重なっている。二人でたいらげたとしても、本当に馬並みの大食らいだった。
- マトリは光の溢れる外に出た。アレスはボロボロになった麻の囚人服を腰に巻いただけの姿で、何度も水をかぶっていた。弾ける水滴が日差しに輝き、真珠のように飛び散った。
- 「すっかりいいみたいだな?」
- マトリの声に、アレスは桶を持ったまま、幽霊でも見るように近づく英雄を見た。
- 「こんな所で英雄の幽霊に逢えるとは、思わなかったぜ」
- アレスにはマトリの出現が、どんな経緯によるものなのか、まったく見当もつかなかった。はっきりとしているのは、伝説の英雄が目の前に現われて、自分を死の淵から救ってくれたという事実だけだった。
- 「お前を迎えにきた」マトリは正面からアレスを見て言った。
- 「俺を迎えにきた?」
- マトリはこれまでの経緯を手短にアレスに語って聞かせた。
- 小さな内乱の終結とともにトーラスの宮廷戦士マトリは姿を消した。君主ベルトハイムの要請だった。信頼に足り、穏密行動を託するにあたいする人材は、希代の戦士マトリ=カークランドをおいてほかにない。知将ベルトハイムは内乱のさなか、トーラスに振り注ぐ数々の災いが、偶然のものではないと察知したのだった。同じ頃、世界の各地で疫病が蔓延していた。その被害はトーラスにある小さな村々まで襲い、比較的に統治状態の良かったトーラスにも大打撃を与えた。当時よりアシュワの長老であり、トーラス最高の賢者とされていたマトリの祖父スクネは、疫病と内乱の原因が、魔の復活の予兆であるとの答えを導き出していた。
- 内乱の首謀者たちは、皆一様に正気を失ったように計算もなく、突然反旗をひるがえした。何の意味もない内乱ばかりだった。まるで、治安の破壊だけを目的にしたような内乱が続いた。初めは一つ一つの内乱を鎮圧していたベルトハイムも、事態を把握するにつれ、スクネの言葉を重く受け止めた。
- 王の間に呼ばれたマトリは、ベルトハイムから直接に命令を下された。
- 「邪悪なる波動を振りまく魔の根源を探れ。その力に打ち勝つ法があらば、すべての事柄より優先し、全霊を傾けよ」 その日より、マトリは表舞台から消えた。それから数年余り、マトリは人知れず諸国を渡り歩いた。トーラスのみならず、ヨモック、ヒナータ、ヒウケビロス、大海を隔てたオネスト、ウビロスに至るまで、世界の動向を探るべく旅は続いた。世界中でトーラスと同様の混乱が見られた。疫病で全滅した村。内乱で破滅した国家。ただ一つ、その混乱の中で隆盛を誇っていた国があった。それがウビロス大陸の軍事国家ゲルニア帝国だった。ゲルニアは魔皇帝と恐れられるチャロナのもと、侵攻を続け勢力の拡大に明け暮れていた。マトリはスクネが睨んだとおりであったことを確信した。チャロナの邪悪な波動の奥に、三百年の昔、地上での君臨を図り世界を荒れ狂った邪悪神グルの存在をまざまざと感じたのだ。
- マトリは確信を得ると、あらかじめスクネと示し合わせていたとおり、邪悪神グルに立ち向かうだけの力を持つ仲間の所在を占うためにブディドへと赴いた。スクネが占うことも可能だったが、呪術的結界の薄いアシュワで卜占を行なえば、グルにこちらの動向をさらす行為になりかねない。スクネはそれを考慮して、結界の厚いブディドでの卜占を指示したのだった。
- そして、ガロアからカーンへ、星は流れた。
- マトリの話を聞き終えたアレスは、しばらくテベステ山の噴煙に目をやっていた。
- 「それで、俺に白羽の矢がたったってわけか。だが、生憎だが、俺はアシュワに戻るつもりはない」
- 「お前は自分の運命に逆らうのか?」
- 「よしてくれ。俺はアシュワを捨てたんだ」
- 「捨てられないものもある」
- 「そんなものはない---」
- 「だったらなぜ、お前はチャロナを斬った?」
- その問いに、アレスは胸板を殴られたような衝撃を受けた。言われるまでもなく、アレスがこのカーンの地にいるのは、自分自身がチャロナを斬った為なのだ。だが、当のアレスには、自分がなぜあのような行動をとったのか、それさえもわかっていなかった。
- 「その答えが……。アシュワにあるのか?」
- 「アシュワに着いてから、直接スクネに聞くがいい」
- アレスは夢の中で見たアシュワを思い出した。もう何年も故郷の夢など見なかった。それが、夢を見た途端、マトリが現われアシュワに戻れと言う。
- ---夢と言えば。あの砂嵐の中で見た夢はなんだったんだ。
- 二つの星の気配は、今にして思えばマトリとあの少年だったような気がした。そして、あのチャロナの気配。自分の意志に関係なく、天界の動きは確実に自分を何かに引き寄せている。窓越しに宿屋の中の少年を見ながら、漠然とそう思った。
- 「スクネが話してくれるんだな?」
- アレスは風が二つ吹く間考えて、答えを出した。
- マトリが簡単な食事をとる間、アレスとモーガンはカーイから逃げ回っていた。予告どおり物凄い匂いを振りまくハーブのスープを出されたからだ。結局のところ、二人とも命の恩人には逆らえなかった。二人は鼻を摘んでスープを胃袋へと流し込んだ。
- 「全部飲めよ。せっかく作ってやったんだからな」
- マトリは普通のスープを飲みながら、微笑ましい光景を眺めた。まずはアシュワに戻ることが先決だ。タイナーの忠告どおり、次の樽馬車がくる前に、ここを出発した方がよさそうだと、マトリは思った。
- <h2>アシュワへ</h2>
- アルテアは二十代半ばの美しい女だった。黒真珠のように輝く瞳に、真っすぐと、とおった鼻筋。瞳の色と同じ長い黒髪を、後ろで一つに束ねていた。平穏な地で生まれていれば、決して血なまぐさい戦いの中で指揮をとるような女にはならなかっただろう。事実、彼女からゲルニア海軍の鎧と、時折見せる冷血な表情さえ取り除けば、いい寄る男の十人や二十人は軽くいたに違いない美貌を持っていた。しかし、幼い頃からのゲルニアの軍事教育は良くも悪くも彼女の才能を開かせ、二十歳前にして近衛兵団の分隊長を任せられるまでにした。以前より、その才能に目をつけていたジュミレスは、彼女を将軍付けで大陸の北東に位置する軍港ゲドラに居留させ、新しい侵攻作戦を進めようとしていた。
- 皇帝チャロナの死亡が誤報であり、ボルタイがボルテアの統治を任されたという伝令が属国中に走った直後、アルテアはゲルニアの軍港から本国に呼び出された。待ちに待った呼び出しだった。身をただし、武者震いを隠してアルテアはジュミレスの前に出頭した。薄暗い本殿の一室で、命令は下された。
- 「今回の任務は遠征戦ではない。トーラスに宣戦するものでもない。そのことを決して忘れるな。アシュワの住民のみを根絶やしにするのだ。成果はそれで十分」
- ジュミレスの下した命令は、アルテアにとって余りにも消極的な作戦だった。
- ---奇妙な命令だ。地図にもないような、ただの村を殲滅しろだと……。
- 回廊を歩みながら、アルテアは馴れた男言葉で思考した。軍艦は二隻ある。兵力にして軍艦一隻に三百名。計六百名の兵である。村一つ消すのなど、赤子の手をひねるよりも容易なことだった。アルテアには、この兵力でベルトハイムを落とせと言われれば、それを成し遂げる自信さえあった。
- 「かまわんか。ジュミレス様が村を落とせと言うのだ。大規模な侵略だけが戦さではない。海路による奇襲の訓練になれば、それでいいか」アルテアは自分を納得させるように一人呟いた。 何よりもジュミレスに作戦を任されたことが嬉しかった。
- ---アシュワの民の血で期待に答えようぞ。
- アルテアの美しい顔には、冷たい微笑が浮かんでいた。
- マトリたち一行はカーンの港町ベルボボで馬車を売り払うと、トーラス行きの船に乗り込んだ。船は三日をかけてトーラス大陸の西の港、ミューマに着いた。マトリはそこでアレスとモーガンに、一通りの衣服と武器を揃えさせた。陸路は徒歩で行くことも考えたが、新しい幌つきの馬車を買うことにした。元気そうに見えてもアレスたちの体調は完全ではない。せめてアシュワに着くまでは無理をさせたくないというマトリの配慮だった。
- 馬車はトーラスを縦断するように西から東南に下った。四人は二ヵ月あまりの旅を続け、ようやく大陸を突っ切り、バロル海が見えるところまで辿り着いた。
- 流れる風は潮の香りを運んでいる。もう、アシュワが近い。アレスにとっては十年ぶりの帰郷だった。遠くの方に芦原が見えてきた。
- 「アシュワか……。まさか、お尋ね者になって舞い戻ってくるとはな」
- 「だからさ、どうせならガロアとゲルニアをもらっちゃえば良かったんだ。中途半端だから、お尋ね者になっちまうんだ。なっ、そうだろモーガン?」
- 「そりゃ、そうだけどよ」
- モーガンには、アレスがチャロナを斬った傭兵であったと旅の途中で知らされた驚きが、まだ尾を引いていた。腕のたつ奴だとは思っていたが、それほどまでの者とは思ってもいなかった。だからどうだということもないが、とうとう別れそびれてここまでついてきてしまった。
- 馬車は曲がりくねった海岸線の道をひた走る。やがて、右手に海に面した断崖が見えてきた。しばらくして道は芦原に隠れ、馬車は背丈より高い葦を分け入った。視界は葦で閉ざされ、馬車はまるで葦の海を進む小舟のようだった。
- 「道がすっかり消えてやがる」アレスが寂しげに呟いた。
- 「人の往来が絶えたせいだ。今では商人も訪ねてはこない」マトリが呟きに答えた。
- 景観が急速に変わっていく。馬車が進むにつれ、芦原の向こうに見える北壁が右から左へと眼前にそそり始める。
- 「あの断崖はデッパと呼ばれている。あの下に見えてきたのがアシュワだ」景色に見とれているカーイにマトリが言った。カーイは息を止めて断崖を見ていた。少年の胸の奥で、記憶の襞が振動を始めていた。
- デッパの下に村が見えてきた。断崖は村を呑み込むように巨大な波の形を見せている。
- 「この景色……。いつか見た気がする……」不意にカーイが呟いた。
- 「なんだと?」アレスは自分の耳を確かめるように聞いた。
- ---この景色を見たことがある。いつだっけ……。伯父さんと旅をしていた時かな。いや、ちがうよ。トーラスのこんなところにきたのは初めてだ。でも、あの崖を見たことがあるような気がする……。
- カーイは身じろぎもしないでデッパの断崖を見つめている。アレスには、今、カーイの心に湧きあがったものが、単なる思い込みには思えなかった。
- ---そうだ。こいつはなぜ俺と旅をしているんだ。ガロアから俺を追ってきたと言ったが……。妙なガキだぜ。
- カーイが何かの含みを持って自分に近づいたとも思えない。
- 村の入口が、もう、すぐそこに見えてきた。
- <h2>呼び覚ます運命</h2>
- 粗末な藁葺きの家の軒先で、村人が葦の茎ですだれを編んでいる。どの家も似たような造りだった。軒先には葦や蒲の茎が山積みになって乾燥させてある。村人たちは農業のひまを見つけてはそれらを編み、駕篭やすだれやむしろを作って生活の足しにしていた。湿地の多いアシュワは葦や蒲の宝庫だった。蒲は夏、ろうそくの形に似た花を咲かせる。葦は秋、しなやかな穂をたなびかせた。季節は夏へと向かう今、一年中でもっとも茎の揃う時期だ。
- 不思議なことに、マトリたちの馬車が通りかかっても、村人たちは一向に関心を示さなかった。マトリやアレスの顔を忘れるはずはない。だが、言葉をかける者もなく、村人たちは黙って茎を編んでいる。別に歓迎を期待していた訳ではないが、何か重たい空気が流れているのを感じた。「妙だね」カーイも気まずさを感じていた。
- 村人は明らかにアレスやマトリたちを避けていた。物影に隠れ、上目遣いにじっと見ている者までもいる。
- 「あの人たち、みんなアレスの知ってる人なんだろ?」
- カーイの言葉にアレスは静かに頷いた。
- 「まるで我々を、死神か何かのように避けているようだ」マトリが手綱を操りながら呟いた。「とにかくスクネの家に行こう。まさかスクネまで逃げ出さないだろう」
- アレスにはそれ以外の案は浮かばなかった。マトリは慎重に手綱を操り、村の高台にある祖父の家に馬車を進めた。馬車の上から、アレスは自分の家を見つけた。十年ぶりに見る我が家は変わらぬ外景を留め、にわかに懐かしさを呼び起こした。
- 「寄らなくていいか?」マトリが気を効かせて言った。
- 「いや、いい。どうせ誰もいない」
- アレスは郷愁に溺れそうになった自分を、心の隅で戒めた。
- スクネの家は寺院を兼ねた土壁の家だった。この村で唯一、人々が集うだけの広さを備えた家屋である。屋根こそ藁葺きだが、壁の塗り方は他の家よりも丁寧で、ゴツゴツとした質感が地味ながら寺院の尊い雰囲気を醸し出していた。
- 老人は表に立っていた。白く長い顎髭を生やし、右手には固そうな杖を持っていた。長年着込んだと思われる薄茶色のローブを身につけ、もう百歳に近いスクネは力なく微笑んだ。
- 「この者たちは?」老人はカーイとモーガンを見て、落着いた声で訊ねた。
- 「カーイとモーガンと言います。この二人はカーンへの旅で道連れになった者たちです」
- 「そうか。入りなさい」
- 広い間口を抜け、土間の祈祷場に入ったマトリたちは、スクネにならって葦のむしろに腰を下ろした。
- 「村の者たちの様子がおかしいようでしたが?」マトリが訪ねた。
- 「無理もない。村の者たちも気づいておるのじゃ。お前が戦士を連れて村に帰ってきた時、災いが訪れるということをな」
- 「やはり俺たちは、死神扱いか……」アレスは苦笑いともつかない声で呟いた。
- マトリはそんなアレスの乾いた表情を見てから、スクネに告げた。
- 「託宣の結果、このアレスが我々の捜していた戦士だということがわかりました」
- 「ほう……」と、老人はアレスの顔を眺めて続けた。
- 「お前は母を失った疫病を覚えておるじゃろう。あの疫病は始めから、我らアシュワの民を狙って振りまかれたものだったのじゃ。邪悪神グルによってな」
- 「邪悪神?」
- 「我らアシュワの民は、この世界の中で特別な役割を背負う民なのじゃ。ペンタウァという名は知っているな?」
- 「名前は聞いたことはあるが、あれはお伽話の中だけに出てくる町じゃないのか?」
- 「ペンタウァは実在する町じゃ。このアシュワは、そのペンタウァの流れをくむ隠れ部落なのじゃ。まずはグルと我々の関わりから語っておいた方がよかろう」
- スクネはそう言ってから、自分の記憶を探るように、遠い伝説を語り始めた。言葉は伝承特有の古語が入り混じり、理解することを少し困難にさせた。
- 話は天界の神々の会議の場から始まった。神々はこの世界の地上に生まれた人間を、どのように導くべきか語り合っていた。さまざまな意見が出た後、神々の一人、闇を司るグルは、闇の中でこそ、純粋に人間の魂を育めると主張した。そのためには人間を恐怖により縛り、統制を保たせるべきだと。他の神々はその意見を退けた。だが、自分の考えを唯一のものとするグルは、他の神々の目を盗み、地上に悪の種を撒いた。その行動を知った神々はグルを天界から追放した。ところが、追放されたグルはそれをよいことに、ウビロスの時の皇帝フヒド=ワラーに憑依して、地上での君臨を図った---と、いうものだった。
- ---似たような話があるものだ。マトリはカーンの医者タイナーに聞かされた伝説を、アレスはモーガンに聞かされたお伽話を思った。
- 「天界の神々は、グルの悪業を阻止するがために、精霊の下僕たちを地上に遣わした。それがペンタウァの民の祖先であり、アシュワの民の祖先なのじゃ。壮絶な戦いの末、我らの祖先はフヒドに憑依したグルを封じることに成功した。だが、グルは悪しくとも神じゃ。精霊の下僕に完全なる封印は果たせるものではない。我らの祖先はそのことを案じて、この地上に残ったのじゃ。そしてその日より、邪悪神グルの眠りを見守る役割を課された民となったのじゃ」
- スクネの話を聞き、カーンではその名がわからなかった神の名が「邪悪神グル」であることがわかった。託宣の話も信じ難いものだったが、アレスにとって自分たちの村が精霊の血を引く村であるとは思いもよらないことだった。
- 「その邪悪神が、再び目覚めたと言うのか」
- 「グル復活の兆候が見え始めたのが、あの疫病だった。各地で起った内乱もそうじゃ。復活を始めたグルは、末裔である我らをいぶりだすために無差別に疫病と混乱を振りまいたのじゃ。アレスよ。お前は、お前の父たちが村から出て行ったのを覚えておるじゃろう? あの時、邪悪な波動を感じたが、何一つ確証はなかった。かと言って、こちらが表立って動き出せばグルの思惑どおりにもなりかねん。そこでやむなく、仮封印に向かわせたのじゃ。お前の父たちが出て、しばらくの間、グルの波動は確かに衰えておった。お前が成長するまで時間が稼げただけでも、無駄ではなかった」
- ---あの時から始まっていたのか。
- アレスはスクネに明かされていく真実を、ゆるやかな驚きで受け止めた。
- 「カーイとか、言ったのう?」不意に老人はカーイを見て言った。
- 「歳はいくつになる?」
- 「えっと。十二だけど?」
- スクネは軽く目を細めた。
- 「十二か。デッパに登っても、よい歳じゃ」
- 「え?」
- カーイは村の入口で見た、断崖の景観を思い出した。
- 「カーイには、アレスの代わりにデッパに登ってもらう」スクネは少し強引な感じがするほど、きっぱりと言い切った。
- 「俺の代わりに?」
- 「そうじゃ、今すぐにじゃ。村の者が成人の儀式として、デッパに登ることは知っておるな。儀式は単なる慣習ではない。本来の目的はグノームの力を頒け与えられた友と、邂逅することにある。土の力を糧に、デッパに生きる住人とな」
- アレスにはスクネの言っていることが、容易には飲み込めなかった。デッパの上に暮らす者がいるなどとは初耳だった。片田舎の村の、さらに奥に、人が隠れ住んでいるとは信じ難いことだ。だが、それが人間でないとすれば、想像もつく。
- 「ドワーフのことか?」
- スクネはゆっくりと頷いた。
- 「デッパの上で待っているドワーフは、我らの兄弟。かつて我々の祖先たちが邪悪神グルの復活を危惧してこの地上に残った時、さまざまな形で地上の者たちと同化した。その中に、ドワーフと魂を共有した者たちもおったのじゃ。しかし、その肉体に宿ってしばらくすると、異なる種と種は互いに避け合うようになった。それも地上の者と同化したことによる精神的な退化のなせる技じゃろう。ドワーフは岩戸を閉じてしまった。そこで我々は儀式という形をかりてデッパに近づき、ドワーフの岩戸が開いておらんか調べていたのじゃ。数十年前、最後に登った者の報告では、岩戸は開いていなかった。だが今、グルは完全に動き出しておる。ドワーフとて、それを理解しておるじゃろう。岩戸は開いておるはずじゃ。今こそ我々は再び手を結ばねばならん」
- カーイが瞳を輝かせていた。
- 「ドワーフの友か……。行くよ。おいら、登ってみるよ」
- カーイの心は決まっていた。スクネに言われるまでもなく、カーイはデッパを見たときに受けた不思議な感覚の正体を知りたかった。その断崖に登れとスクネは言った。カーイには願ってもないことだ。
- 「ただ、心して欲しいことが一つある」
- スクネはわずかに眉間を曇らせた。
- 「関門があるのじゃ。岩戸が開いていたとして、中に踏み入れば、カーイは関門の門番に試されることとなる。我らの祖先は、岩戸の内側に門番を置いた。関門を通過するためには門番の許可がいる。だがそれは形あるものではなく、意識の底にある心の鍵のようなものだ。その鍵を心に持っている者はそう多くはない」
- 「関門を通れないかも知れないと言うことか?」カーイの代わりにアレスが訊ねた。
- 「どうかのう」スクネは関門の重さを計りかねているようだった。
- 「もし、カーイがその鍵を持っていなかったら?」今度はマトリが訊ねた。
- 「門番に殺されるじゃろう」
- スクネの答えに沈黙が包んだ。
- 「こんなガキにそれを託せと言うのか」アレスは頼りげのない少年を気遣っていた。
- 「その昔に立てたデッパの住人との盟約により、関門を通るには汚れなき心、未来への希望、大人になると薄れてしまう、さまざまな要求を充たさねばならん。子供が絶えたこの村では、もう登れる者はない。希望を託せる者はこの坊主しかおらんのだ。もっとも、これが十年も前ならば、お前が行けばよかったのだろうが、今のお前は血塗られておる。門番はそれを見逃さんじゃろう」
- アレスは芦原に立ち、父がデッパを指差した時のことを思い出した。アレスはデッパに登らなかった。その因果が巡り、今、旅の途中で知り合っただけの子供に、自分の使命とも言える仕事を託さねばならないのは、運命の皮肉としか思えなかった。
- しばらくの後、カーイは皆に伴われ、デッパの下に立っていた。荷物は最低限のものを小袋に一つと、スクネから受け取った荒縄が一巻きだけだった。
- 「まかしといてよ、きっとドワーフを連れてくるからさ」
- 心配そうに見守る面々をよそに、カーイは小石の積もる斜面を元気よく駆け登った。
- クアルを旅立ったときに感じた心のうずきと、似たような興奮が少年を包んでいた。
- ---登るんだ。
- それはアシュワの入口でデッパを見た瞬間から課せられた使命にも、それ以前から決まっていたことのようにも思えた。命を落とすかも知れない仕事だったが、カーイは少しも気にならかった。
- スクネがデッパに登る者を求めていること。カーイにその資格があること。そして悲しいことに、以前この村を襲った疫病のために本来登るべき村の子供が絶えたこと。
- ドワーフの友が待っている。カーイにはそれで十分だった。
- <h2>アカーシャ</h2>
- カーイを送り出し家に戻ると、マトリはスクネにアレスが流刑地に送られた顛末を語った。
- スクネは一言一言頷きながら聞き終えると、思考をまとめるように眉を寄らせた。
- 「チャロナを、斬ったのじゃな」
- 「はい。アレスが乱心し、チャロナを倒したのは間違いないようです」
- マトリは固い表情で答えた。
- アレスはチャロナの不気味な目を思い出していた。
- 「残念じゃが、奴は死んではおらん」スクネはきっぱりと言い放った。
- 「死んでないだと?」薄暗い祈祷場でアレスの眼が光った。
- 「邪悪神グルは自分の持つ邪悪な波動に感応する者を待っていたのじゃ。ちょうどその昔、ウビロスの皇帝フヒド=ワラーに憑依したようにな。時代が再び戦乱の世を迎えた時、力と権力に溺れる人間が現われる。人の道を離れ、魔道に堕ちても野望を達成しようとする輩。それがチャロナじゃ。グルに直接感応できるほど権力に溺れる者は少ない。そう簡単にグルはチャロナの肉体を手放さんじゃろう。今もチャロナを媒介にして、闇の帝国を築こうとしておる。わしはその波動を強く感じる」
- 「もしや、アレスがチャロナの前で乱心したのは……」マトリは自分の閃きに震えた。続きを口にするまでもなく、スクネはマトリの思ったことを理解していた。
- 「グルはアレスの血脈に気づいたのじゃ。皮肉な舞台をあつらえたものじゃ。因縁で結ばれたアレスを踏み台にして、チャロナを完全に乗っ取りおった。もはやゲルニアの皇帝はチャロナではなく、グルそのものと考えてよかろう」
- その言葉にアレスたちは震撼した。アレスは自分でも気づかぬうちに渦の中心にいたのだ。しかも、邪悪神復活の片棒まで担いでいた。いくら傭兵に身をやつすアレスでも、心の痛みを感じずにはいられなかった。
- 「我らの祖先が成し遂げられなかった邪悪神の最終封印を行なうのじゃ。そのためには、いくつかのものを揃えなければならん。一つは、我らの祖先がグルを封印した時にもちいた封印石ヒーロル。これは、今もペンタウァにあるはずじゃ。そして今一つは魔霊の類さえ斬るエスカリオン。グルの憑依した体には、もはや、ただの剣では無力」
- 「エスカリオン?」
- 「お前の父が持っていたものだ」マトリが口を挟んだ。
- 言われてみれば覚えがあった。父は代々トラーノスの家に伝わるものだと、古めかしい剣をアレスに見せたことがある。銀色に輝く片刃の剣だった。刃の元に、何やら読めない文字が書かれていたのを思い出した。
- 「あの剣は、親父が持って出て行ったままだ」
- 「そうじゃ。仮封印を施すためにな」
- 「それを捜すなんて、まるで雲を掴むような話だ」
- 「捜すしかなかろう。だが、それ以上に困難なのが最後の条件じゃ。誰でもいい、アカーシャを得るのじゃ」
- 「アカーシャ……?」
- 耳にしたこともない言葉だった。
- 「ブディドでは、天地を創造する四つの元素、地・水・火・風の他に、五番目の元素があると伝えられておる。それがアカーシャじゃ。アカーシャには宇宙のあらゆる欲望、想念、感情、意志が時を超越して蓄積されておるという。いわゆる空の力じゃ。もし、それに触れることができれば、その者は無限の力と叡知を得るのじゃ。それ無くしてはグルの封印は望めん。かつて我が祖先は地・水・火・風の四象を操ることにより、グルに封印を挑んだ。だが、アカーシャを得る者がいなかったため、完全なる封印を施すことができなかった---」 「どうすればそれを得られる?」
- 「それはわからん。恐らく、定まった得る方法などない。自分で見つけるしかあるまい」
- 所在のわからない剣と、謎の力。スクネの言ったもので唯一手の届きそうなものは、ペンタウァにあるという封印石だけだった。
- 「ペンタウァへ行け。謎の大半はそこでわかるはずじゃ」
- 「どこにあるんだ?」
- 「ペンタウァは、元来、グルの封印を見守るために作られた町じゃ。フヒドの眠る魔宮のすぐ近くにある」
- 「ウビロス大陸か? まさか、ゲルニアにあるのか!?」
- 「ペンタウァは、ブディドより強い結界に守られておる。並みの者にはそこに町があることさえわかるまい。ペンタウァを目指せ。この世界には我々と同じように精霊から同化した兄弟たちがおる。その力は薄れ、使命さえ忘れかけておるのがほとんどじゃが、星は必ず引き寄せ合う。出会いに気を配れ。まだ見ぬ仲間たちを集め、邪悪神の最終封印を成し遂げるのじゃ。お前にすべてを理解させる時間は残されていない。しかし、今ここでお前が立たなければ、グルによって世界は闇に包まれる。これは我が祖先、天界の下僕と、邪悪神グルの宿命の戦いなのじゃ。そしてもう、その戦いは始まっておる……」
- マトリはカーンの城壁で手に入れた古代文字の写しを拡げた。
- 「アレスを救出したカーンの城壁で手に入れました。流刑地の中で見つかった巨大な石柱に書かれてあったそうです。あちらで世話になった医者が神の文字だといっていました。カーンを聖地と崇め、自らを砂漠の民と名乗る者たちの一人です」
- スクネは遠い昔を懐古する眼差しを見せた。
- 「カーンこそ、我らの祖先が邪悪神グルと戦ったところなのじゃ」
- 「砂漠の民も、我らと同根と言うことでしょうか?」
- スクネはマトリの問いに静かに頷いた。
- 「やはり、この文字がブディドのものと同じというのは……」
- 「ブディドに残るようにしたのも我らの祖先じゃ」
- 「タミアラから伝わったものと聞いていましたが?」
- 「タミアラは神が最初に生んだ大地。だから、フヒドはタミアラを沈めたのじゃ」
- スクネはゆっくりとした動作で紙を取り上げ、声を出してそれを読み上げた。
- 「完全なる封印かなわぬがため、我らその力を持って三体に封印するものなり。ここに封印せしはフヒドの意識なり。残る生命を封印石ヒーロルに。そして邪悪なる神はフヒドの肉体に閉じ込めしまま、魔宮に封ずるものなり……」
- スクネの言葉は重い響きを持っていた。
- 「つまり、三つに分けて封印したと言ってるのか」モーガンが言った。あまりの話の展開に口を挟む余地のなかったモーガンだが、砂漠の民も兄弟であるとスクネの口から出たことで、にわかに他人事でない思いが沸いていた。
- 「あの石柱はフヒドの意識を封じた墓標だったわけだ」
- マトリは砂漠で見たメンヒルを思い浮かべ、納得した。
- 「墓標か。あれは確かに墓標に見えたさ」
- しみじみと言うアレスにモーガンが頷いた。共通の地獄の体験が懐かしくも思えた。
- 「封印は憑依されたフヒドを母体としてなされたとされている。恐らく、肉体の檻に閉じ込めることにより、グルの超越した力を弱めさせたのだろう」
- スクネは遠い祖先からの伝言を考察した。
- 「それにしても、三体に分けて封印を施しても完全なる封印が望めなかったとは……」
- マトリは今更ながらに、グルの強大な力に恐怖を覚えた。
- 「悪しきとも、神。そのことを肝に銘じておくことじゃ。そうじゃ、ペンタウァに行く前に、フィベリアへ寄って行くがいい」
- 「小国フィベリアですか?」マトリが聞き返した。
- 「フィベリアのタントールと言う町の外れに、ヴァルカンと言う魔道師が住んでおる。ヴァルカンはタミアラの時代より、惑星神官の流れをくむ者だ。封印とアカーシャについての知識を借りるがよい」
- 今度こそ最終封印を施さねばならないのだ。強大なグルの力を前に、祖先ほどの力もない子孫たちが、どう戦えばいいのか?
- 事態を認識すればするほど、困難な道を指し示すばかりだった。
- 少年は断崖を登っていた。岩に貼りついて仰ぎ見れば、巨大な波形の断崖は、遥か頭上でうねり、ゴツゴツとした岩の喉を見せている。思うような速度では、なかなか登れなかった。
- 一つ一つの岩を確かめながら腕を伸ばす。髪が強風にあおられた。登れば登るほど風は強くなる。足をずって横に移動させると、小石が軽い音をたてて崖下に転がった。地上から見る以上に険しい断崖だ。カーイは気を配りながら、少しでも足場が良く、早く上に行ける道を選んだ。ちっとも進まないと思っていたが、空を飛ぶ海猫の声に、自分がかなり高い所まで登ったのを知った。翼を拡げた海猫が、自分より低い所を飛んでいる。勇気をふるい起して下を見ると、箱庭のようなアシュワの村が小さく見えた。あまりの高さに震えがきた。もう、下を見るのはよそうとカーイは思った。慎重に道を選んだはずなのに、しばらく登り続けると、進める足場がなくなった。掴める岩もない。
- 「どうやって登ればいいんだ」
- もう一つ、困ったことがある。日暮れが近づいていた。岩肌を照らす陽が赤みを帯びてきている。少しでも早く登り切りたいという気持ちには変わりなかったが、足を滑らせれば終わりだ。ヘタに動けば中途半端なカッコウで夜を迎えることになる。足場もない所で一晩耐えるのはゴメンだった。カーイは逸る気を抑えて決断した。スクネに渡された荒縄を手頃な岩にぐるりと回すと、自分の胴に何重にもくくりつけ、岩肌で夜をやり過ごす準備に入った。
- 陽が落ちると、スクネは祭壇に火を焚いた。
- アレスは食事を終えてから、ぶらりと外に出た。十年振りの村だ。星明かりに浮かぶ藁葺きの屋根、畦道、子供の頃、水をくんだ井戸……。気がつけば誰もいない自分の家の前に立っていた。鍵はかかっていない。中に入り意味もなく部屋を一回りする。荒らされた様子はない。たまった綿埃と蜘蛛の巣を除けば、すべてがそのままだった。自分がここを飛び出した歳とカーイの歳が、偶然にも同じということが、今更ながら、皮肉に思えた。
- ---奴は俺の代わりか。
- 今はカーイが無事に戻るのを待つことしかできない。アレスは何もせず部屋から出ると、夜景にそびえるデッパの断崖にカーイの姿を捜した。おぼろな月に青白く浮かぶ壁面に、少年の姿が見えるはずもなかった。
- 「出会いに気を配れか……」
- カーイも、そしてモーガンも、もう偶然の旅の道連れには思えなかった。
- 一人一人が役目を持った星なのだ。今でははっきりと、流刑地で見た二つの星が、マトリとカーイの二人だったのだとアレスは確信していた。
- <h2>龍の鱗</h2>
- 翌朝、陽が昇ると同時に、カーイは再び行動を開始した。休んだおかげで体の疲れもとれて頭もすっきりした。カーイは荒縄を利用して崖上に登る試みに挑戦していた。細長い石を荒縄の先に結びつけて、すぐ上の岩と岩との隙間を狙って投げつける。隙間にうまく石がひっかかれば荒縄を頼りに登れそうだった。一度目は狙いが外れ、二度目は狙いは良かったが、うまくひっかからなかった。三度目で荒縄を巻いた石は見事に岩の隙間に収まり、うまくひっかかった。途中でそれが外れないように祈りながら荒縄に体重をのせる。石ころと荒縄に命を委ねるのは度胸がいったが、カーイは腹を決めて荒縄を引っ張った。もう一段登れば道が開けるのだ。 少年は顔に皺をよせて、唸りながら少しずつ体を引き上げた。
- やっとの思いで上の岩に出た。どうやらここからは岩を掴んで登れそうだとみると、休みもせず登り続けた。しばらくすると断崖のせり出した喉の部分にまできた。
- 苦しみながら登ったその上に、ヘの字型に切れ込んだ洞窟の入口が口を開けていた。子供が背を屈め、やっと入れるほどの隙間だった。辺りには岩が砕け散った後のように小石が散乱している。 「きっと、ここが爺さんの言っていた岩戸だったんだ」
- 迷うことはなかった。少年は背を屈めて洞窟の中に入った。入口の形のまま差し込んだ陽の光は、真っすぐに前方を指し示している。カーイは光を背負うように洞窟を進んだ。強風が洞窟の口に当り、奇妙な音をたてている。
- 「おかしいな。こんな音が出るのは洞窟の奥がふさがっているからなのか? この洞窟は抜けられないのかなぁ……」
- 先に進むほど光は弱くなり、見透しが効かなくなってきた。だが、カーイの目が闇に慣れるにしたがい、発光苔や水晶、細かく反射する鉱物の放つ淡い光が視界を助け、かろうじて洞窟の中を進むことができた。
- 不意に洞窟の奥から、ゴロゴロと喉を鳴らすような低い音が聞こえた。
- ---何かがいる。ドワーフ?
- カーイは洞窟の闇の隠れた部分に何者かの気配を感じた。目を懲らすと、闇はほんの少しだけ輪郭を見せてくれた。洞窟の天井がいつのまにか高くなっている。闇の中に、柱のようなものが立っていた。
- ---なんだ?
- そう思った瞬間、柱の上に二つの明かりが燈った。それは、まるで巨大な鞭がしなるように勢いをつけ、二つの明かりを載せたまま、いきなりカーイを目掛けて倒れ込んできた。
- 「わっ!?」
- しなった柱はわずかにカーイをそれ、轟音を上げて洞窟の壁面に激突した。壁面が砕け、破片が細かく飛び散った。柱から、喉を鳴らすような低い音が聞こえる。それはすぐに唸って持ち上がり、ようやくカーイは柱の正体を見極めた。長い首を伸ばした巨大な生物だ。
- 「龍だ!」
- 巨大な龍は頭の上だけ青味がかっていた。翼をたたみ、体を前屈みにうずくまった姿が窮屈そうだった。龍を見るのは初めてだ。カーイは巨大な生物を前に、狼狽えながらも、懸命に頭を働かせようと努力した。
- 銀の短剣を持っていることを思い出した。青頭の龍と視線を外さず、腕だけを動かし、腰紐にくくりつけた小袋を確かめる。小袋に手を入れると、冷たい柄の感触が伝わった。カーイは素早くそれを取り出し、胸の前で構えた。短剣の刃は洞窟の壁を幾度も屈折した頼りない明かりに照らされて鈍く光った。
- 「よーし、相手になってやるぞ!!」
- 声は洞窟に反響し、よけいに静けさを残して消えた。
- 龍が長い喉を伸ばし息を吸い込む。空気が巨大な生物の体内に音をたてて集まっていった。
- 一瞬、閃光が口元で広がり、龍は赤々とした炎を放った。
- カーイは闇に転がり、それを避けた。
- 「うわっ。くそっ!?」
- 続けざまに炎が広がる。炎が闇を照らす。カーイは青頭の龍の死角を求めて別の闇に転がった。 ---よーし。
- カーイは勢いよく闇から飛び出した。
- 「やい、炎を吐いて見ろ!」
- 龍が誘いにのって炎を吐いた。少年はこま鼠のようにすばしっこく、闇から闇へと駆けた。 二度目の炎も避けた。だが、三度目は予想以上に早く、危うく丸焦げになりそこねた。
- 青頭の龍の炎が止まった。
- 「いくぞ!」その隙をつき、カーイは正面から銀の短剣を振りかぶって青頭の龍に突っ込んだ。 その時、声が聞こえた。
- 『待て---』
- ---えっ?
- 声はカーイの頭の奥に直接聞こえた。
- 『私は、かつてこの地の祖先、天界の精霊に召喚させられし龍なり。境界の門番としてこの地に留まりぬ---』
- カーイは青頭の龍を見上げた。龍は少年を見下ろしている。青頭の龍には、もう炎を噴きかける気配はなかった。やがて青頭の龍は何かを納得したように少しだけ首を動かせると、鋭い牙のはみ出る顎をゆっくりと移動させ、鱗の浮きでた自分の二の腕を噛み切ると、長い首をひねり、その肉片をカーイの足元に投げた。
- 肉片は淡い黄金色に発光し、カーイの足元で凝縮した。
- 『受け取れ---。これはお前がここを通過した証しだ---』
- 足元に転がる肉片は、小石ほどの大きさの、一枚の龍の鱗と化していた。カーイは言われるままにそれを拾った。
- 『別たれた絆を結ぶ魂を、お前の中に見つけた。かつて天界の精霊が定めし盟約を復活に導く力……。私の務めは、今、ようやく終わった。天界に帰れと言ってくれ。そうすれば、私は自分の世界に戻り、デッパへの道は開ける。今、地上の閉ざされた境界を越える者よ。お前が異形の友と友を結ぶ使徒となれ---』
- カーイは龍の目を見て頷くと、静かに言った。
- 「龍よ。天界に帰れ」
- 青頭の龍の目は、長い間の使命を終えた安堵感を讃えていた。龍はたたんでいた翼を洞窟一杯に広げると、その身を大きく反らせて一度咆哮をした。洞窟の中をつんざく、雄々しい一声だった。咆哮が消えていくにつれて、龍の姿は次第に透明になり、木漏れ日の光のように分散して洞窟の闇に溶け込んだ。
- 「消えた……」
- 先ほどまで、青頭の龍と向き合っていたのが嘘のようだった。
- 気がつくと、龍のいた岩盤の後ろに、人が通れるほどの穴が開いていた。青頭の龍がデッパへの道を塞いでいたのだ。風の流れが変わり、洞窟に充満していた空気が穴から突き抜けて流れ出た。
- 洞窟を抜けると、驚いたことに森に出た。蔦が茂り、鬱蒼とした巨木が密集してそびえる。下からは見えなかったが、断崖の上は緑濃い木々の根づく森だった。時折、地中から浮き出した根が足を掬いそうになる。カーイは足を引っ掛けないように気をつけながら進んだ。しだいに梢の重なりが薄くなり、揺れる木漏れ日が足元を照らした。木々の間を抜けて風が吹き込んでくる。断崖では煩わしかった風も、ここでは、この上なく気持ちの良い穏やかな風に感じられた。
- ---ドワーフを捜さなきゃ。
- ようやく断崖の上に出たものの、どちらに向えばよいのか、まったくあてがない。カーイは森の中を闇雲に進んだ。しばらく行くと、茂みの向こうに平坦な広場が見えた。そこだけ土が剥き出しになっている。広場を覗き見ると、貴族の庭園のように、石の彫刻がいくつも置かれていた。
- それは人を象って造られた石の彫刻のように見えた。しかし、よく見るとその姿は人間とは少し違っている。人間よりは少し小柄で、ずんぐりとした感じがあった。カーイは広場に入って彫刻の一つに触れてみた。
- ---ドワーフだ。
- まるで、つい先ほどまで息をしていたかのようだ。
- ---これは……石像なんかじゃない。
- 「みんな、石になってる……」
- 途端に広場は静寂の庭園から、死者たちの眠る墓場に見え始めた。
- ドワーフは太陽の光に触れると石になる。カーイはいつか伯父のルードから教えられた話を思い出した。カーイにとっては心地よい太陽の光も、ドワーフには命取りなのだ。だが、ドワーフが陽の光の下で生きられないのなら、スクネはドワーフとの邂逅に、何を託しているのだろうか……。カーイはここにきて、ようやくデッパを訪れた意味を、自分なりに導き出そうとしていた。
- その時、反対側の森の茂みをみしみしとかき分ける音がした。息を詰めて振り向くと、巨漢の男が広場に出てくるところだった。筋肉質の体つき。大きな鼻。眉も太く、顔全体を真っ黒な髭が覆っている。身につけているのは獣の皮で作った服だった。
- ---ドワーフ!
- 彼には他のドワーフと決定的に違うところが二つあった。彼は大人の人間以上に背が高く、巨漢だった。ドワーフは小柄だと聞かされていたカーイには信じられないことだった。そして何よりも、彼は陽の光の下でも平気だった。巨漢のドワーフはカーイ見つめ、そのままおし黙って立っている。カーイも黙ってドワーフの目を見つめた。ドワーフは、優しく、もの悲しい目で少年を見ていた。
- 二人は申し合わせたように動かなかった。
- 風を感じ、木漏れ日を感じ。どのくらいそうしていただろう。やがて、カーイの心の奥にある、いつか失ったキタラの弦が、懐かしく、どこかもの悲しい調べを奏で始めた。
- 「そうだったのか……。あの日見た夢だ。伯父さんの死んだ日の……。待っていたのはキミだったんだ」
- いきなり、カーイの二つの眼から、とめどなく涙が溢れ出た。巨漢のドワーフは一言もしゃべらなかった。だが、カーイは、ドワーフの心をすべて理解した。
- 「キミが……、最後の一人なんだね……」
- カーイは懐から龍の鱗を取り出し、ドワーフに見せた。
- 最後のドワーフは、優しい目で少年を見つめたまま、静かに頷いた。
- <h2>アシュワ殲滅</h2>
- カーイの帰りを待つアレスたちの耳に、突然、村人たちの絶叫が聞こえた。
- アレスは本能的に剣を引き寄せ、マトリも険しい顔で剣に手を置いた。
- 続いて炎を含んだ火矢の飛ぶ音が聞こえ、雄叫びと新しい絶叫が耳に届いた。
- 「まさか!? ゲルニアか?」アレスは唇を噛み絞めた。
- 「行くな、行ってはならん!!」
- 「そうはいくかっ!」スクネの制止を振り切って、アレスは表に飛び出した。マトリもモーガンも武器を持ち、後に続いた。
- 表に飛び出したアレスたちは愕然とした。
- 奇襲の兵たちは村の外周の家から火矢を投げかけて退路を断ち、しかも風向きを計算して、炎が無駄にならないように風上の家から狙っている。これほど手際の良い奇襲はなかった。その様子から、相手が綿密な作戦に従い行動していることがわかった。藁葺きの屋根はすぐに燃えさかる。手をこまねいている暇はない。
- 軒先に積まれていた葦の小駕篭が、兵士たちの足に払われ、崩れ散った。村人の悲鳴が響き渡っている。アレスは自分が『アシュワの傭兵』と名乗ったためにここが狙われたのだと思った。兵士たちの火矢は村人にも狙いをつける。放たれた火矢に老婆が貫かれた。
- アレスは目についた兵士から斬った。
- 兵士たちは村人を一人残らず殺すつもりだ。マトリは群がる兵士たちを斬りながら、命令者の非情さを感じた。モーガンも叫びながら兵士に立ち向い、剣を大振りにして威嚇した。
- 突然現われた三人に兵士たちはたじろぎを見せた。だが、それも一瞬のことで、すぐに三人に合わせて陣形を整えた。
- 途端にアレスたちはバラバラに離され、各々が円形の陣に囲まれた。
- 「手強いな……」マトリが関心するほどの手際だった。囲まれている間にも火の手は拡がる。
- 上段に構え、アレスは叫びながら兵士の輪から飛び出した。マトリもモーガンもこの機を逃さず斬り込む。アレスは独楽のように身を回転させ、一瞬のうちに数名の兵士を蹴散らした。
- 矢が狙っていた。モーガンを狙っている。弓の弦が弾けた。
- 「モーガン!?」アレスの視界の隅に、矢を受けたモーガンがゆっくりと倒れていくのが見えた。 兵士たちが陣形を縮小させる。モーガンの体は、その中に見えなくなった。
- 村は着実に破壊されている。マトリの心に焦りが過った。いくら斬っても形勢の逆転は考えられない。
- 「アレス!!」
- その叫びは撤退を意味していた。
- 「カーイがまだだ! あいつを置いては行けん!」
- 殲滅部隊を指揮する女将アルテアの耳にも、その叫びは聞こえていた。
- 「アレスだと?」
- その名に聞き覚えがあった。
- ---まさか・・・乱心の傭兵アレスか?
- アルテアには理解できなかった。この村とアレスとの関係は知らされていない。それに、皇帝に傷を負わした乱心の傭兵は、流刑地にいるはずだった。
- ---相手が誰であろうと、任務の邪魔立ては許せない。奴がそのアレスならば、それもよかろう。その首とってジュミレス様への土産にしてくれる。
- 「何を手間取っている! 討ちとれーい!!」アルテアは女豹のように叫んだ。
- その叫びに、アレスとマトリを取り囲む兵士の輪が、みるみる幾重にも厚くなった。
- スクネは祈祷場で瞑想をしていた。
- この家にも炎が広がっていたが、意識を外界から断っている老人には、炎の熱さも、人々の叫びも、側で何が起ころうとも一切眼中になかった。
- 老人は何かを察知した。こめかみがぴくりと動き、目蓋を見開いた。
- 「間に合ったか……」老いた瞳に、希望の光が燈った。
- 同じ時、突然、デッパの断崖の中腹が内側から弾け飛んだ。固い岩面が砕け散り、土煙りが舞い上がる。崖の腹にポッカリと穴が開いた。
- 土煙りの中に、二人の人影が立っていた。巨漢のドワーフとカーイだった。二人は黒煙を上げるアシュワを見下ろすと、勢いをつけて断崖の斜面を滑り降りた。
- 兵士たちは的をアレスとマトリに絞っていた。村は放っていても焼け落ちる。目障りな二人を片付けることが先決だった。
- 天に昇る黒煙に混じり、火の粉が螢の大群のように舞っていた。
- 「殺せ!」
- 「この二人から片付けるんだ!」兵士たちは自らの気迫を上げるために、口々に叫んだ。
- 包囲する兵士たちが迫る。
- その時、兵士たちは何か別のものの出現に気を奪われた。黒煙と火の粉に霞む、焼けただれた村の向こうから、大男の黒い影が突進してきた。
- 「何事だ!?」動揺が兵士たちの間で駆け抜けた。
- 「今だ!」マトリの合図に、アレスとマトリは同時に左右に斬り込んで陣形を崩した。
- さらに、飛び込んできた大男の太い腕が、一度に数名もの兵士を薙ぎ倒した。
- 「ドワーフ……!?」
- すべての者が口を開け、その存在に驚愕した。
- 「カーイが連れてきたのか?」アレスは横目でカーイの姿を探した。カーイの姿はない。巨漢のドワーフは兵士の襟元を軽々と掴み、兵たちの固まりに向け投げつける。飛んできた仲間にぶつかり、兵士たちはまとめて倒された。
- 「援軍にしては上出来だ---」
- ドワーフは武器を使わなかった。逞しい体そのものが武器だった。俊敏に動き、兵士たちに攻撃をさせる隙を与えずに、次々と薙ぎ倒した。
- その頃、カーイは燃えさかるスクネの家に飛び込んでいた。
- 燃えた屋根の梁が斜めに崩れ、屋根に開いた穴から煙りが逃げている。
- 「スクネ! 爺さんいるんだろ!!」
- スクネが奥の部屋で自分を待っているのをカーイは知っていた。
- カーイが炎を避けながら踏み入ると、燃えさかる祈祷場の中に老人の姿があった。炎が二人の間で燃えている。
- 「爺さん!」
- 「カーイ、よく戻った」
- 火の粉が渦を巻いた。
- 「逃げるんだよ、爺さん!」
- 「ここから出たところで、わしはもう寿命じゃ。カーイ、お前はアレスともどもフィベリアへ行け。ヴァルカンに逢うのじゃ。やるべきことは星々が指し示してくれるじゃろう」
- 老人の言葉は静かだったが、あらがえない強さがあった。
- 「う、うん」
- 「龍から鱗を預かったようじゃな?」
- 「うん」
- スクネは安心したように炎の向こうで頷いた。
- 「これより、わしは最期の力を振り絞り、お前たちをここより逃す。だが、それにはお前の力が必要じゃ。よいの?」
- 「ああ、どんなことだってやって見せるさ」
- 「よい返事じゃ」
- スクネは炎の向こうから、眩しげにカーイの顔を見つめた。
- 「兵士たちに見つからぬよう、お前は芦原へ逃れろ」
- 「アレスたちも一緒じゃないのか?」
- 「お前が逃れられれば、アレスたちも助かる。安心しろ。お前のいる所まで転移させる術がある。だが、お前が途中で見つかれば、それも使えん」
- 「わかった!」カーイは力強く答えた。
- 「芦原の安全な所まで辿り着いたら、龍の鱗を天に掲げろ」
- 「うん、わかったよ」
- 「よし。行けっ、カーイ!」
- 少年は炎の向こうに死を覚悟した老人を見た。
- 「急げっ!」
- カーイは燃えさかる祈祷場から飛び出して懸命に走った。
- ぬかるみを越え、土を蹴り上げ、ひたすら芦原に向けて駆け抜けた。少年は、その小さな体以上に大きな役目を背負っていた。
- 「よい頃じゃ」しばらくの時間をよみ、スクネは静かに呟いた。
- 杖を持ち、二度ほどその先で地面を軽く叩く。
- 「天界の神々よ、その大いなる力をもって、我らの希望の使者に逃れの道を開け。我が命をここに捧げ、託したる望みをかなえん!!」
- その瞬間、言葉は力となった。脈々とした力が杖に蓄積されていく。
- スクネは力強く念を開放する。杖から閃光が迸り、輝きは光球となってゆっくり天井の穴から上昇した。
- 「なんだ!? あの輝きは?」光球に気づいた兵士たちが驚きのあまり立ち尽くした。
- 輝きは弾かれたように上空で三つに分かれ、それぞれがアレス、マトリ、ドワーフに向けて、尾を引きながら落下し、三人の体はつぎつぎと輝きに包まれた。
- 不思議な光はさらに輝きを増し、中の者の輪郭もわからないほど、まばゆく輝いた。
- 「どういうことだ……?」アルテアは驚きのあまり、その場に凍てついた。
- アレスたちを呑み込んだ三つの光球は不意に消滅した。
- 「消えた……。この村はいったい……。このような術を目にするとは……」
- アルテアはジュミレスの命令の奥に隠された何かを、見た思いがした。
- 龍の鱗は天に向けて掲げられていた。
- 芦原の中に立ち、カーイはスクネに言われたとおりにした。
- 少年の前で突然閃光が迸り、身を屈めたままの姿勢で三人の男が転がり出た。
- アレス、マトリ、ドワーフの三人は空間から湧き出したかのように、忽然と芦原に現われた。三人には、自分の身に何が起こったのか、わからなかった。
- 「俺たちは……どうしたってんだ?」アレスは身に起こったことを理解しようと辺りを見渡した。芦原の中だ。カーイが立っている。船酔いに似た吐き気がする。頭が少し、重かった。
- 同じく、頭を押さえながら気づいたマトリがカーイを見つけた。
- 「カーイ……。お前どうして?」
- 「スクネの言ったとおりにしただけさ」
- 「お前の力なのか?」アレスが訊ねた。
- 「違うさ。スクネがやったのさ」
- ドワーフは優しい目でカーイを見ている。モーガンがいないのにカーイは気づいた。
- 「モーガンは?」
- 「やられた」アレスが短く答えた。
- それ以上は、誰も何も口にしなかった。芦原の遥か向こうに、黒煙を上げているアシュワの村が見えた。
- 芦原は静かに揺れている。ドワーフは別れを告げるように断崖のデッパを見上げた。
- 「行こう。フィベリアへ」
- カーイはそう言うと、芦原を歩み出した。
- 断片的に残る異なった伝承は、一つの大きな戦いの歴史を、アレスたちの前に明らかにさせた。天界の神々の裁決から始まった闇の神の干渉は、今再び、この世界を暗黒の闇で覆い尽くそうとしている。邪悪神グルと、神々から遣わされた天界の下僕との戦いは、たとえ三百年という時間を隔てても、終決を迎えることなく続いていたのだ。
- 精霊の血を継ぐ者たちの使命は余りにも重く、それは否応もなく、アレスの避けられない運命を呼び覚ますこととなった。
- 闇を司る神、邪悪神グルの伝承は、タミアラ、ブディド、カーン、そしてアシュワと、時を越え、語り部を変えても一層の凶悪さを増し、底知れぬ邪悪さを伝えている。
- かつて、三体に分けられた邪悪神グルの鼓動は、再び大地を闇で蹂躙するために、今、一つに戻ろうとしていた。
- ウビロスの暴君、フヒド=ワラーに憑依し、そして今、封印を破り、ゲルニアの皇帝チャロナに憑依したグルの魂は、さらなる力を取り戻すがため、残る二つの魂を求め、邪悪なる脈動を拡げていた。
- 『ブランディッシュ・アレス 呼び覚ます運命』 完
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement