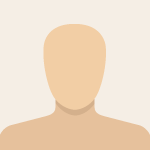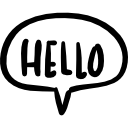Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 第9章 真夜中の決闘
- The Midnight Duel
- ダドリーより嫌なヤツがこの世の中にいるなんて、ハリーは思ってもみなかった。でもそれはドラコ・マルフォイと出会うまでの話だ。一年生ではグリフィンドールとスリザリンが一緒のクラスになるのは魔法薬学の授業だけだったので、グリフィンドール寮生もマルフォイのことでそれほど嫌な思いをせずにすんだ。少なくとも、グリフィンドールの談話室に「お知らせ」が出るまではそうだった。掲示を読んでみんながっくりした。
- ――飛行訓練は木曜日に始まります。グリフィンドールとスリザリンとの合同授業です――
- 「そらきた。お望みどおりだ。マルフォイの目の前で箒に乗って、物笑いの種になるのさ」
- 何よりも空を飛ぶ授業を楽しみにしていたハリーは、失望した。
- 「そうなるとはかぎらないよ。あいつ、クィディッチがうまいっていつも自慢してるけど、口先だけだよ」
- ロンの言うことはもっともだった。
- マルフォイは確かによく飛行の話をしたし、一年生がクィディッチ・チームの寮代表選手になれないなんて残念だとみんなの前で聞こえよがしに不満を言った。マルフォイの長ったらしい自慢話は、なぜかいつも、マグルの乗ったヘリコプターを危うくかわしたところで話が終わる。自慢するのはマルフォイばかりではない。シェーマス・フィネガンは、子供の頃いつも箒に乗って、田舎の上空を飛び回っていたという。ロンでさえ、聞いてくれる人がいれば、チャーリーのお古の箒に乗って、ハンググライダーにぶつかりそうになった時の話をしただろう。
- 魔法使いの家の子はみんなひっきりなしにクィディッチの話をした。ロンも同室のディーン・トーマスとサッカーについて、大論争をやらかしていた。ロンにしてみれば、ボールがたった一つしかなくて、しかも選手が飛べないゲームなんてどこがおもしろいのかわからない、というわけだ。ディーンの好きなウエストハム・サッカーチームのポスターの前で、ロンが選手を指でつついて動かそうとしているのをハリーは見たことがある。
- ネビルは今まで一度も箒に乗ったことがなかった。おばあさんが決して近づかせなかったからで、ハリーも密かにおばあさんが正しいと思った。だいたいネビルは両足が地面に着いていたって、ひっきりなしに事故を起こすのだから。
- ハーマイオニー・グレンジャーも飛ぶことに関してはネビルと同じぐらいピリピリしていた。こればっかりは、本を読んで暗記すればすむものではない――だからといって彼女が飛行の本を読まなかったわけではない。木曜日の朝食の時ハーマイオニーは図書館で借りた「クィディッチ今昔」で仕入れた飛行のコツをウンザリするほど話しまくった。ネビルだけは、ハーマイオニーの話に今しがみついていれば、あとで箒にもしがみついていられると思ったのか、必死で一言も聞き漏らすまいとした。その時ふくろう便が届き、ハーマイオニーの講義がさえぎられたのでみんなホッとした。
- ハグリッドの手紙の後、ハリーにはただの一通も手紙が来ていない。もちろんマルフォイはすぐにそれに気がついた。マルフォイのワシミミズクは、いつも家から菓子の包みを運んできたし、マルフォイはスリザリンのテーブルでいつも得意げにそれを広げてみせた。
- めんふくろうがネビルにおばあさんからの小さな包みを持ってきた。ネビルはウキウキとそれを開けて、白い煙のようなものが詰まっているように見える大きなビー玉ぐらいのガラス玉をみんなに見せた。
- 「『思いだし玉』だ!ばあちゃんは僕が忘れっぽいこと知ってるから――何か忘れてると、この玉が教えてくれるんだ。見ててごらん。こういうふうにギュッと握るんだよ。もし赤くなったら――あれれ……」
- 思いだし玉が突然真っ赤に光りだしたので、ネビルは愕然とした。
- 「……何かを忘れてるってことなんだけど……」
- ネビルが何を忘れたのか思い出そうとしている時、マルフォイがグリフィンドールのテーブルのそばを通りかかり、玉をひったくった。
- ハリーとロンははじけるように立ち上がった。二人ともマルフォイと喧嘩する口実を心のどこかで待っていた。ところがマクゴナガル先生がサッと現れた。いざこざを目ざとく見つけるのはいつもマクゴナガル先生だった。
- 「どうしたんですか?」
- 「先生、マルフォイが僕の『思いだし玉』を取ったんです」
- マルフォイはしかめっ面で、すばやく玉をテーブルに戻した。
- 「見てただけですよ」
- そう言うと、マルフォイはクラップとゴイルを従えてスルリと逃げた。
- その日の午後三時半、ハリーもロンも、グリフィンドール寮生と一緒に、始めての飛行訓練を受けるため、正面階段から校庭へと急いだ。よく晴れた少し風のある日で、足下の草がサワサワと波立っていた。傾斜のある芝生を下り、校庭を横切って平坦な芝生まで歩いて行くと、校庭の反対側には「禁じられた森」が見え、遠くの方に暗い森の木々が揺れていた。
- スリザリン寮生はすでに到着していて、二十本の箒が地面に整然と並べられていた。ハリーは双子のフレッドとジョージが、学校の箒のことをこぼしていたのを思い出した。高い所に行くと震えだす箒とか、どうしても少し左に行ってしまうくせがあるものとか。
- マダム・フーチが来た。白髪を短く切り、鷹のような黄色い目をしている。
- 「なにをボヤボヤしてるんですか」開口一番ガミガミだ。「みんな箒のそばに立って。さあ、早く」
- ハリーは自分の箒をチラリと見下ろした。古ぼけて、小枝が何本かとんでもない方向に飛び出している。
- 「右手を箒の上に突き出して」マダム・フーチが掛け声をかけた。
- 「そして、『上がれ!』と言う」
- みんなが「上がれ!」と叫んだ。
- ハリーの箒はすぐさま飛び上がってハリーの手に収まったが、飛び上った箒は少なかった。
- ハーマイオニーの箒は地面をコロリと転がっただけで、ネビルの箒ときたらピクリともしない。
- たぶん箒も馬と同じで、乗り手が恐がっているのがわかるんだ、とハリーは思った。ネビルの震え声じゃ、地面に両足を着けていたい、と言っているのが見えみえだ。ハーマイオニーなんか箒を叱り飛ばしそうだ。
- 次にマダム・フーチは、箒の端から滑り落ちないように箒にまたがる方法をやって見せ、生徒たちの列の間を回って、箒の握り方を直した。マルフォイがずっと間違った握り方をしていたと先生に指摘されたので、ハリーとロンは大喜びだった。
- 「さあ、私が笛を吹いたら、地面を強く蹴ってください。箒はぐらつかないように押さえ、二メートルぐらい浮上して、それから少し前屈みになってすぐに降りてきてください。笛を吹いたらですよ――一、二の――」
- ところが、ネビルは、緊張するやら怖気づくやら、一人だけ地上に置いてきぼりを食いたくないのやらで、先生の唇が笛に触れる前に思いきり地面を蹴ってしまった。
- 「こら、戻ってきなさい!」先生の大声をよそに、ネビルはシャンペンのコルク栓が抜けたようにヒューッと飛んでいった――四メートル――六メートル――ハリーはネビルが真っ青な顔でグングン離れていく地面を見下ろしているのを見た。声にならない悲鳴を上げ、ネビルは箒から真っ逆さまに落ちた。そして……
- ガーン――ドサッ、ポキッといういやな昔をたてて、ネビルは草の上にうつぶせに墜落し、草地にこぶができたように突っ伏した。箒だけはさらに高く高く昇り続け、「禁じられた森」の方へユラユラ漂いはじめ、やがて見えなくなってしまった。
- マダム・フーチは、ネビルと同じくらい真っ青になって、ネビルの上に屈み込んだ。
- 「手首が折れてるわ」
- ハリーは先生がそうつぶやくのを開いた。
- 「さあさあ、ネビル、大丈夫。立って」
- 先生は他の生徒のほうに向き直った。
- 「私がこの子を医務室に連れていきますから、その間誰も動いてはいけません。箒もそのままにして置いておくように。さもないと、クィディッチの『ク』を言う前にホグワーツから出ていってもらいますよ」
- 「さあ、行きましょう」
- 涙でグチャグチャの顔をしたネビルは、手首を押さえ、先生に抱きかかえられるようにして、ヨレヨレになって歩いていった。
- 二人がもう声の届かないところまで行ったとたん、マルフォイは大声で笑い出した。
- 「あいつの顔を見たか?あの大まぬけの」
- 他のスリザリン寮生たちもはやし立てた。
- 「やめてよ、マルフォイ」パーバティ・パチルがとがめた。
- 「ヘー、ロングボトムの肩を持つの?」
- 「パーバティったら、まさかあなたが、チビデブの泣き虫小僧に気があるなんて知らなかったわ」
- 気の強そうなスリザリンの女の子、パンジィ・パーキンソンが冷やかした。
- 「ごらんよ!」
- マルフォイが飛び出して草むらの中から何かを拾い出した。
- 「ロングボトムのばあさんが送ってきたバカ玉だ」
- マルフォイが高々とさし上げると、『思い出し玉』はキラキラと陽に輝いた。
- 「マルフォイ、こっちへ渡してもらおう」
- ハリーの静かな声に、みんなはおしゃべりを止め、二人に注目した。
- マルフォイはニヤリと笑った。
- 「それじゃ、ロングボトムが後で取りにこられる所に置いておくよ。そうだな――木の上なんてどうだい?」
- 「こっちに渡せったら!」
- ハリーは強い口調で言った。マルフォイはヒラリと箒に乗り、飛び上がった。上手に飛べると言っていたのは確かにうそではなかった――マルフォイは樫の木の梢と同じ高さまで舞い上がり、そこに浮いたまま呼びかけた。
- 「ここまで取りにこいよ、ポッター」
- ハリーは箒をつかんだ。
- 「ダメ!フーチ先生がおっしゃったでしょう、動いちゃいけないって。私たちみんなが迷惑するのよ」
- ハーマイオニーがハリーの袖を掴んで叫んだ。
- ハリーは無視した。ドクン、ドクンと血が騒ぐのを感じた。箒にまたがり地面を強く蹴ると、ハリーは急上昇した。高く高く、風を切り、髪がなびく。マントがはためく。強く激しい喜びが押し寄せてくる。
- ――僕には教えてもらわなくてもできることがあったんだ――簡単だよ。飛ぶってなんて素晴らしいんだ!もっと高いところに行こう。
- ハリーは箒を上向きに引っ張った。下で女の子たちが息をのみ、キャーキャ一言う声や、ロンが感心して歓声を上げているのが聞こえた。
- ハリーはクルリと箒の向きを変え、空中でマルフォイと向き合った。マルフォイは呆然としている。
- 「こっちへ渡せよ。でないと箒から突き落としてやる」
- 「へえ、そうかい?」
- マルフォイはせせら笑おうとしたが、顔がこわばっていた。
- 不思議なことに、どうすればいいかハリーにはわかっていた。前屈みになる。そして箒を両手でしっかりとつかむ。すると箒は槍のようにマルフォイめがけて飛び出した。マルフォイは危くかわした。ハリーは鋭く一回転して、箒をしっかりつかみなおした。下では何人か拍手をしている。
- 「クラップもゴイルもここまでは助けにこないぞ。ピンチだな、マルフォイ」
- マルフォイもちょうど同じことを考えたらしい。
- 「取れるものなら取るがいい、ほら!」
- と叫んで、マルフォイはガラス玉を空中高く放り投げ、稲妻のように地面に戻っていった。
- ハリーには高く上がった玉が次に落下しはじめるのが、まるでスローモーションで見ているようによく見えた。ハリーは前屈みになって箒の柄を下に向けた。次の瞬間、ハリーは一直線に急降下し、見るみるスピードを上げて玉と競走していた。下で見ている人の悲鳴と交じり合って、風が耳元でヒューヒュー鳴った――ハリーは手を伸ばす――地面スレスレのところで玉をつかんだ。間一髪でハリーは箒を引き上げ、水平に立てなおし、草の上に転がるように軟着陸した。「思いだし玉」をしっかりと手のひらに握りしめたまま。
- 「ハリー・ポッター…!」
- マクゴナガル先生が走ってきた。ハリーの気持は、今しがたのダイビングよりなお速いスピードでしぼんでいった。ハリーはブルブル震えながら立ち上った。
- 「まさか――こんなことはホグワーツで一度も……」マクゴナガル先生はショックで言葉も出なかった。メガネが激しく光っている。
- 「……よくもまあ、そんな大それたことを……首の骨を折ったかもしれないのに――」
- 「先生、ハリーが悪いんじゃないんです……」
- 「おだまりなさい。ミス・パチル――」
- 「でも、マルフォイが……」
- 「くどいですよ。ミスター・ウィーズリー。ポッター、さあ、一緒にいらっしゃい」
- マクゴナガル先生は大股に城に向かって歩き出し、ハリーは麻痺したようにトボトボとついていった。マルフォイ、クラップ、ゴイルの勝ち誇った顔がチラリと目に入った。ハーマイオニーが両手で口を押さえ悲痛な瞳を向けるのも見えた。
- 僕は退学になるんだ。わかってる。弁解したかったが、どういうわけか声が出ない。マクゴナガル先生は、ハリーには目もくれず飛ぶように歩いた。ハリーはほとんどかけ足にならないとついていけなかった。
- ――とうとうやってしまった。二週間ももたなかった。きっと十分後には荷物をまとめるハメになっている。僕が玄関に姿を現したら、ダーズリー一家はなんて言うだろう?
- 正面階段を上がり、大理石の階段を上がり、それでもマクゴナガル先生はハリーに一言も口をきかない。先生はドアをグイッとひねるように開け、廊下を突き進む。ハリーは惨めな姿で早足でついていく……たぶん、ダンブルドアのところに連れていくんだろうな。ハリーはハグリッドのことを考えた。彼も退学にはなったけど、森の番人としてここにいる。もしかしたらハグリッドの助手になれるかもしれない。ロンや他の子が魔法使いになっていくのをそばで見ながら、僕はハグリッドの荷物をかついで、校庭をはいずり回っているんだ……想像するだけで胃がよじれる思いだった。
- マクゴナガル先生は教室の前で立ち止まり、ドアを開けて中に首を乗っ込んだ。
- 「フリットウィック先生。申し訳ありませんが、ちょっとウッドをお借りできませんか」
- ウッド?ウッドって、木のこと?僕を叩くための棒のことかな。ハリーはわけがわからなかった。
- ウッドは人間だった。フリットウィック先生のクラスから出てきたのはたくましい五年生で、何ごとだろうという顔をしていた。
- 「二人とも私についていらっしゃい」
- そう言うなりマクゴナガル先生はどんどん廊下を歩き出した。ウッドは珍しいものでも見るようにハリーを見ている。
- 「お入りなさい」
- マクゴナガル先生は人気のない教室を指し示した。中でピーブズが黒板に下品な言葉を書きなぐっていた。
- 「出ていきなさい、ピーブズ!」
- 先生に一喝されてピーブズの投げたチョークがゴミ箱に当たり、大きな音をたてた。ピーブズは捨てぜりふを吐きながらスイーッと出ていった。マクゴナガル先生はその後ろからドアをピシャリと閉めて、二人の方に向きなおった。
- 「ポッター、こちら、オリバー・ウッドです。ウッド、シーカーを見つけましたよ」
- 狐につままれたようだったウッドの表情がほころんだ。
- 「本当ですか?」
- 「間違いありません」先生はきっぱりと言った。
- 「この子は生まれつきそうなんです。あんなものを私は初めて見ました。ポッター、初めてなんでしょう?箒に乗ったのは」
- ハリーは黙ってうなずいた。事態がどうなっているのか、さっぱりわからなかったが、退学処分だけは免れそうだ。ようやく足にも感覚が戻ってきた。マクゴナガル先生がウッドに説明している。
- 「この子は、今手に持っている玉を、十六メートルもダイビングしてつかみました。かすり傷ひとつ負わずに。チャーリー・ウィーズリーだってそんなことできませんでしたよ」
- ウッドは夢が一挙に実現したという顔をした。
- 「ポッター、クィディッチの試合を見たことあるかい?」ウッドの声が興奮している。
- 「ウッドはグリフィンドール・チームのキャプテンです」先生が説明してくれた。
- 「体格もシーカーにぴったりだ」
- ウッドはハリーの回りを歩きながらしげしげ観察している。
- 「身軽だし……すばしこいし……ふさわしい箒を持たせないといけませんね、先生――ニンバス2000とか、クリーンスイープの7番なんかがいいですね」
- 「私からダンブルドア先生に話してみましょう。一年生の規則を曲げられるかどうか。是が非でも去年よりは強いチームにしなければ。あの最終試合でスリザリンにペシャンコにされて、私はそれから何週間もセブルス・スネイプの顔をまともに見られませんでしたよ……」
- マクゴナガル先生はメガネごしに厳格な目つきでハリーを見た。
- 「ポッター、あなたが厳しい練習を積んでいるという報告を聞きたいものです。さもないと処罰について考え直すかもしれませんよ」
- それから突然先生はにっこりした。
- 「あなたのお父さまがどんなにお喜びになったことか。お父さまも素晴らしい選手でした」
- 「まさか」
- 夕食時だった。マクゴナガル先生に連れられてグラウンドを離れてから何があったか、ハリーはロンに話して聞かせた。ロンはステーキ・キドニーパイを口に入れようとしたところだったが、そんなことはすっかり忘れて叫んだ。
- 「シーカーだって?だけど一年生は絶対ダメだと……なら、君は最年少の寮代表選手だよ。ここ何年来かな……」
- 「……百年ぶりだって。ウッドがそう言ってたよ」
- ハリーはパイを掻き込むように食べていた。大興奮の午後だったので、ひどくお腹が空いていた。
- あまりに驚いて、感動して、ロンはただボーッとハリーを見つめるばかりだった。
- 「来週から練習が始まるんだ。でも誰にも言うなよ。ウッドは秘密にしておきたいんだって」
- その時、双子のウィーズリーがホールに入ってきて、ハリーを見つけると足早にやってきた。
- 「すごいな」ジョージが低い声で言った。「ウッドから聞いたよ。僕たちも選手だ――ビーターだ」
- 「今年のクィディッチ・カップはいただきだぜ」とフレッドが言った。「チャーリーがいなくなってから、一度も取ってないんだよ。だけど今年は抜群のチームになりそうだ。ハリー、君はよっぽどすごいんだね。ウッドときたら小躍りしてたぜ」
- 「じゃあな、僕たち行かなくちゃ。リー・ジョーダンが学校を出る秘密の抜け道を見つけたって言うんだ」
- 「それって僕たちが最初の週に見つけちまったやつだと思うけどね。きっと『おべんちゃらのグレゴリー』の銅像の裏にあるヤツさ。じゃ、またな」
- フレッドとジョージが消えるやいなや、会いたくもない顔が現れた。クラップとゴイルを従えたマルフォイだ。
- 「ポッター、最後の食事かい?マグルのところに帰る汽車にいつ乗るんだい?」
- 「地上ではやけに元気だね。小さなお友達もいるしね」
- ハリーは冷ややかに言った。クラップもゴイルもどう見たって小さくはないが、上座のテーブルには先生がズラリと座っているので、二人とも握り拳をボキボキ鳴らし、にらみつけることしかできなかった。
- 「僕一人でいつだって相手になろうじゃないか。ご所望なら今夜だっていい。魔法使いの決闘だ。杖だけだ――相手には触れない。どうしたんだい?魔法使いの決闘なんて開いたこともないんじゃないの?」マルフォイが言った。
- 「もちろんあるさ。僕が介添人をする。お前のは誰だい?」ロンが口をはさんだ。
- マルフォイはクラップとゴイルの大きさを比べるように二人を見た。
- 「クラップだ。真夜中でいいね?トロフィー室にしよう。いつも鍵が開いてるんでね」
- マルフォイがいなくなると、二人は顔を見合わせた。
- 「魔法使いの決闘って何だい?君が僕の介添人ってどういうこと?」
- 「介添人っていうのは、君が死んだらかわりに僕が戦うという意味さ」
- すっかり冷めてしまった食べかけのパイをようやく口に入れながら、ロンは気軽に言った。
- ハリーの顔色が変わったのを見て、ロンはあわててつけ加えた。
- 「死ぬのは、本当の魔法使い同士の本格的な決闘の場合だけだよ。君とマルフォイだったらせいぜい火花をぶつけ合う程度だよ。二人とも、まだ相手に本当のダメージを与えるような魔法なんて使えない。マルフォイはきっと君が断ると思っていたんだよ」
- 「もし僕が杖を振っても何も起こらなかったら?」
- 「杖なんか捨てちゃえ。鼻にパンチを食らわせろ」ロンの意見だ。
- 「ちょっと、失礼」
- 二人が見上げると、今度はハーマイオニー・グレンジャーだった。
- 「まったく、ここじゃ落ち着いて食べることもできないんですかね?」とロンが言う。
- ハーマイオニーはロンを無視して、ハリーに話しかけた。
- 「聞くつもりはなかったんだけど、あなたとマルフォイの話が聞こえちゃったの……」
- 「聞くつもりがあったんじゃないの」ロンがつぶやいた。ハーマイオニーは目を逸らしながら真っ赤になった。
- 「……夜、校内をウロウロするのは絶対ダメ。もし捕まったらグリフィンドールが何点減点されるか考えてよ。それに捕まるに決まってるわ。まったくなんて自分勝手なの」
- 「まったく大きなお世話だよ」ハリーが言い返した。
- 「バイバイ」ロンがとどめを刺した。
- いずれにしても、「終わりよければすべてよし」の一日にはならなかったなと考えながら、ハリーはその夜遅く、ベッドに横になり、ディーンとシェーマスの寝息を聞いていた(ネビルはまだ医務室から帰ってきていない)。ロンは夕食後つききりでハリーに知恵をつけてくれた。
- 「呪いを防ぐ方法は忘れちゃったから、もし呪いをかけられたら身をかわせ」などなど。フィルチやミセス・ノリスに見つかる恐れも大いにあった。同じ日に二度も校則を破るなんて、あぶない運試しだという気がした。しかし、せせら笑うようなマルフォイの顔が暗闇の中に浮かび上がってくる――今こそマルフォイを一対一でやっつけるまたとないチャンスだ。逃してなるものか。
- 「十一時半だ。そろそろ行くか」ロンがささやいた。
- 二人はパジャマの上にガウンを引っ掛け、杖を手に、寝室をはって横切り、塔のらせん階段を下り、グリフィンドールの談話室に下りてきた。暖炉にはまだわずかに残り火が燃え、ひじかけ椅子が弓なりの黒い影に見えた。出口の肖像画の穴に入ろうとした時、一番近くの椅子から声がした。
- 「ハリー、まさかあなたがこんなことするとは思わなかったわ」
- ランプがポッと現れた。ハーマイオニーだ。ピンクのガウンを着てしかめ面をしている。ピンクが良く似合うなとハリーはぼんやり思った。
- 「また君か!ベッドに戻れよ!」ロンがカンカンになって言った。
- 「本当はあなたのお兄さんに言おうかと思ったのよ。パーシーに。監督生だから、絶対に止めさせるわ」ハーマイオニーは容赦なく言った。
- ハリーはここまでお節介なのが世の中にいるなんて信じられなかった。
- 「行くぞ」とロンに声をかけると、ハリーは「太った婦人の肖像画」を押し開け、その穴を乗り越えた。
- そんなことであきらめるハーマイオニーではない。ロンに続いて肖像画の穴を乗り越え、二人に向かって怒ったアヒルのように、ガーガー言い続けた。
- 「グリフィンドールがどうなるか気にならないの?自分のことばっかり気にして。スリザリンが寮杯を取るなんて私はいやよ。私が変身呪文を知ってたおかげでマクゴナガル先生がくださった点数を、あなたたちがご破算にするんだわ」
- 「あっちへ行けよ」
- 「いいわ。ちゃんと忠告しましたからね。明日家に帰る汽車の中で私の言ったことを思い出すでしょうよ。あなたたちは本当に……」
- 本当に何なのか、そのあとは聞けずじまいだった。ハーマイオニーが中に戻ろうと後ろを向くと、肖像画がなかった。太った婦人は夜のお出かけで、ハーマイオニーはグリフィンドール塔から締め出されてしまったのだ。
- 「さあ、どうしてくれるの?」ハーマイオニーはけたたましい声で問い詰めた。
- 「知ったことか」とロンが言った。「僕たちはもう行かなきや。遅れちゃうよ」
- 廊下の入口にさえたどり着かないうちに、ハーマイオニーが追いついた。
- 「一緒に行くわ」
- 「ダメ。来るなよ」
- 「ここに突っ立ってフィルチに捕まるのを待ってろっていうの?二人とも見つかったら、私、フィルチに本当のことを言うわ。私はあなたたちを止めようとしたって。あなたたち、わたしの証人になるのよ」
- 「君、相当の神経してるぜ……」ロンが大声を出した。
- 「シッ。二人とも静かに。なんか聞こえるぞ」
- ハリーが短く言った。喚ぎ回っているような音だ。
- 「ミセス・ノリスか?」
- 暗がりを透かし見ながら、ロンがヒソヒソ声で言った。
- ミセス・ノリスではない。ネビルだった。床に丸まってグッスリと眠っていたが、三人が忍び寄るとビクッと目を覚ました。
- 「ああよかった!見つけてくれて。もう何時間もここにいるんだよ。ベッドに行こうとしたら新しい合言葉を忘れちゃったんだ」
- 「小さい声で話せよ、ネビル。合言葉は『豚の鼻』だけど、今は役に立ちゃしない。太った婦人はどっかへ行っちまった」
- 「腕の具合はどう?」とハリーが聞いた。
- 「大丈夫。マダム・ポンフリーがあっという間に治してくれたよ」
- 「よかったね――悪いけど、ネビル、僕たちはこれから行くところがあるんだ。また後でね」
- 「そんな、置いていかないで!」ネビルはあわてて立ちあがった。
- 「ここに一人でいるのはいやだよ。『血みどろ男爵』がもう二度もここを通ったんだよ」
- 口ンは腕時計に目をやり、それからものすごい顔でネビルとハーマイオニーをにらんだ。
- 「もし君たちのせいで、僕たちが捕まるようなことになったら、クィレルが言ってた『悪霊の呪い』を覚えて君たちにかけるまでは、僕、絶対に許さない」
- ハーマイオニーは口を開きかけた。「悪霊の呪い」の使い方をきっちりロンに教えようとしたのかもしれない。でもハリーはシーッと黙らせ、目配せでみんなに進めと言った。
- 高窓からの月の光が廊下に縞模様を作っていた。その中を四人はすばやく移動した。曲がり角に来るたび、ハリーはフィルチかミセス・ノリスに出くわすような気がしたが、出会わずにすんだのはラッキーだった。大急ぎで四階への階段を上がり、抜き足差し足でトロフィー室に向かった。
- マルフォイもクラップもまだ来ていなかった。トロフィー棚のガラスがところどころ月の光を受けてキラキラと輝き、カップ、盾、賞杯、像などが、暗がりの中で時々瞬くように金銀にきらめいた。
- 四人は部屋の両端にあるドアから目を離さないようにしながら、壁を伝って歩いた。マルフォイが飛びこんできて不意打ちを食らわすかもしれないと、ハリーは杖を取りだした。数分の時間なのに長く感じられる。
- 「遅いな、たぶん怖気づいたんだよ」とロンがささやいた。
- その時、隣の部屋で物音がして、四人は飛び上がった。ハリーが杖を振り上げようとした時、誰かの声が聞こえた――マルフォイではない。
- 「いい子だ。しっかり嗅ぐんだぞ。隅の方に潜んでいるかもしれないからな」
- フィルチがミセス・ノリスに話しかけている。心臓が凍る思いで、ハリーはメチャメチャに三人を手招きし、急いで自分についてくるよう合図した。四人は昔を立てずに、フィルチの声とは反対側のドアへと急いだ。ネビルの服が曲り角からヒョイと消えたとたん、間一髪、フィルチがトロフィー室に入ってくるのが聞こえた。
- 「どこかこのへんにいるぞ。隠れているに違いない」フィルチがブツブツ言う声がする。
- 「こっちだよ!」
- ハリーが他の三人に耳打ちした。鎧がたくさん飾ってある長い回廊を、四人は石のようにこわばってはい進んだ。フィルチがどんどん近づいて来るのがわかる。ネビルが恐怖のあまり突然悲鳴を上げ、やみくもに走り出した――つまずいてロンの腰に抱きつき、二人揃ってまともに鎧にぶつかって倒れ込んだ。
- ガラガラガッシャーン、城中の人を起こしてしまいそうなすさまじい音がした。
- 「逃げろ!」
- ハリーが声を張り上げ、四人は回廊を疾走した。フィルチが追いかけてくるかどうか振り向きもせず――全速力でドアを通り、次から次へと廊下をかけ抜け、今どこなのか、どこへ向かっているか、先頭を走っているハリーにも全然わからない――夕ペストリーの裂け目から隠れた抜け道を見つけ、矢のようにそこを抜け、出てきたところが「呪文学」の教室の近くだった。そこはトロフィー室からだいぶ離れていることがわかっていた。
- 「フィルチを巻いたと思うよ」
- 冷たい壁に寄りかかり、額の汗を拭いながらハリーは息をはずませていた。ネビルは体を二つ折りにしてゼイゼイ咳き込んでいた。
- 「だから――そう――言ったじゃない」
- ハーマイオニーは胸を押さえて、あえぎあえぎ言った。
- 「グリフィンドール塔に戻らなくちゃ、できるだけ早く」とロン。
- 「マルフォイにはめられたのよ。ハリー、あなたもわかってるんでしょう?はじめから来る気なんかなかったんだわ――マルフォイが告げ口したのよね。だからフィルチは誰かがトロフィー室に来るって知ってたのよ」
- ハリーもたぶんそうだと思ったが、ハーマイオニーの前ではそうだと言いたくなかった。
- 「行こう」
- そうは問屋がおろさなかった。ほんの十歩と進まないうちに、ドアの取っ手がガチャガチャ鳴り、教室から何かが飛びだしてきた。
- ピーブズだ。四人を見ると歓声を上げた。
- 「黙れ、ピーブズ……お願いだから――じゃないと僕たち退学になっちゃう」
- ピーブズはケラケラ笑っている。
- 「真夜中にフラフラしてるのかい?一年生ちゃん。チッ、チッ、チッ、悪い子、悪い子、捕まるぞ」
- 「黙っててくれたら捕まらずにすむよ。お願いだ。ピーブズ」
- 「フィルチに言おう。言わなくちゃ。君たちのためになることだものね」
- ピーブズは聖人君子のような声を出したが、目は意地悪く光っていた。
- 「どいてくれよ」
- とロンが怒鳴ってピーブズを払いのけようとした――これが大間違いだった。
- 「生徒がベッドから抜け出した!――「呪文学」教室の廊下にいるぞ!」
- ピーブズは大声で叫んだ。
- ピーブズの下をすり抜け、四人は命からがら逃げ出した。廊下の突き当たりでドアにぶち当たった――鍵が掛かっている。
- 「もうダメだ!」とロンがうめいた。みんなでドアを押したがどうにもならない。
- 「おしまいだ!一巻の終わりだ!」足音が聞こえた。ピーブズの声を聞きつけ、フィルチが全速力で走ってくる。
- 「ちょっとどいて」
- ハーマイオニーは押し殺したような声でそう言うと、ハリーの杖をひったくり、鍵を杖で軽く叩き、つぶやいた。
- 「アロホモラ!」
- カチッと鍵が開き、ドアがパッと開いた――四人は折り重なってなだれ込み、いそいでドアを閉めた。みんなドアに耳をピッタリつけて、耳を澄ました。
- 「どっちに行った?早く言え、ピーブズ」フィルチの声だ。
- 「『どうぞ』と言いな」
- 「ゴチャゴチャ言うな。さあ連中はどっちに行った?」
- 「どうぞと言わないなーら、なーんにも言わないよ」
- ピーブズはいつもの変な抑揚のあるカンにさわる声で言った。
- 「しかたがない――――どうぞ」
- 「なーんにも!ははは。言っただろう。『どうぞ』と言わなけりゃ『なーんにも』言わないって。はっはのはーだ!」
- ピーブズがヒューッと消える音と、フィルチが怒り狂って悪態をつく声が聞こえた。
- 「フィルチはこのドアに鍵が掛かってると思ってる。もうオーケーだ――ネビル、離してくれよ!」
- ハリーがヒソヒソ声で言った。ネビルはさっきからハリーのガウンの袖を引っ張っていたのだ。
- 「え?なに?」
- ハリーは振り返った――そしてはっきりと見た。「なに」を。しばらくの間、悪夢を見ているに違いないと思った――あんまりだ。今日はもう、嫌というほどいろいろあったのに。
- そこはハリーが思っていたような部屋ではなく、廊下だった。しかも四階の『禁じられた廊下』だ。今こそ、なぜ立ち入り禁止なのか納得した。
- 四人が真正面に見たのは、怪獣のような犬の目だった――床から天井までの空間全部がその犬で埋まっている。頭が三つ。血走った三組のギョロ目。三つの鼻がそれぞれの方向にヒクヒク、ピクピクしている。三つの口から黄色い牙をむきだし、その間からヌメヌメとした縄のように、ダラリとよだれが垂れ下がっていた。
- 怪物犬はじっと立ったまま、その六つの目全部でハリーたちをじっと見ている。まだ四人の命があったのは、ハリーたちが急に現れたので怪物犬がフイを突かれて戸惑ったからだ。もうその戸惑いも消えたらしい。雷のようなうなり声が間違いなくそう言っている。
- ハリーはドアの取っ手をまさぐった――フィルチか死か――フィルチの方がましだ。
- 四人はさっきとは反対方向に倒れこんだ。ハリーはドアを後ろでバタンと閉め、みんな飛ぶようにさっき来た廊下を走った。フィルチの姿はない。急いで別の場所を探しにいっているらしい。そんなことはもうどうでもよかった――とにかくあの怪獣犬から少しでも遠くに離れたい一心だ。かけにかけ続けて、やっと七階の太った婦人の肖像画までたどり着いた。
- 「まあいったいどこに行ってたの?」
- ガウンは肩からズレ落ちそうだし、顔は紅潮して汗だくだし、婦人はその様子を見て驚いた。
- 「何でもないよ――豚の鼻、豚の鼻」
- 息も絶え絶えにハリーがそう言うと、肖像画がパッと前に開いた。四人はやっとの思いで談話室に入り、ワナワナ震えながらひじかけ椅子にへたりこんだ。口がきけるようになるまでにしばらくかかった。ネビルときたら二度と口がきけないんじゃないかとさえ思えた。
- 「あんな怪物を学校の中に閉じ込めておくなんて、連中はいったい何を考えているんだろう」
- やっとロンが口を開いた。「世の中に運動不足の犬がいるとしたら、まさにあの犬だね」
- ハーマイオニーは息も不機嫌さも同時に戻ってきた。
- 「あなたたち、どこに目をつけてるの?」ハーマイオニーがつっかかるように言った。
- 「あの犬が何の上に立ってたか、見なかったの?」
- 「床の上じゃない?」ハリーが一応意見を述べた。「僕、足なんか見てなかった。頭を三つ見るだけで精一杯だったよ」
- ハーマイオニーは立ち上がってみんなをにらみつけた。
- 「ちがう。床じゃない。仕掛け扉の上に立ってたのよ。何かを守ってるのに違いないわ。あなたたち、さぞかしご満足でしょうよ。もしかしたらみんな殺されてたかもしれないのに――もっと悪いことに、退学になったかもしれないのよ。では、みなさん、おさしつかえなければ、休ませていただくわ」
- ロンはポカンと口をあけてハーマイオニーを見送った。
- 「おさしつかえなんかあるわけないよな。あれじゃ、まるで僕たちがあいつを引っ張り込んだみたいに聞こえるじゃないか、ねえ?」
- ハーマイオニーの言ったことがハリーには別の意味でひっかかった。ベッドに入ってからそれを考えていた。犬が何かを守っている……ハグリッドが何て言ったっけ?
- 「グリンゴッツは何かを隠すには世界で一番安全な場所だ――たぶんホグワーツ以外では……」
- 七一三番金庫から持ってきたあの汚い小さな包みが、今どこにあるのか、ハリーはそれがわかったような気がした。
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement