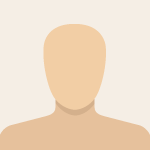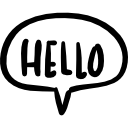Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 書き下ろし・僕の可愛い婚約者
- ──可愛い。
- 初めての口づけに真っ赤になったリリを見つめる。この可愛らしい人が、ようやく自分のものになったという実感がじわりじわりと湧いてきた。
- 「リリ、好きだよ」
- 「わ、私もです……」
- 甘く囁けば、愛らしい答えが返ってくる。それがこの上なく嬉しかった。
- 二人きりの夜のバルコニー。
- 夜会の喧噪は遠く、邪魔する者は誰もいない。
- 愛しい人は僕だけを見つめ、微笑んでくれている。これ以上の幸せがこの世にあるだろうかと本気で考えてしまった。
- ──ようやく、手に入れた。
- 出会った時から、欲しくて仕方のなかった人。その人が、今、自分のものとしてあることに深い満足感を覚える。
- 正直、不安で仕方なかった。
- デビュタントのために誂あつらえたドレスを着た彼女は、もう僕を見てくれないのではないかと本気で思ってしまうくらい美しかったからだ。
- 実際、夜会会場では、思った通り、皆が彼女に見惚れていた。
- ただただ、ぼうっと彼女を見つめる者。手に持ったワイングラスを取り落とす者。様々だったが、皆が彼女に注目していたのは間違いない。
- それを見て、僕が思ったのは「嫌だな」ということ。
- 可愛い、可愛い僕のリリ。
- 美しく、だけども傲慢で、皆から嫌われていたという彼女は、自らの努力で、過去の自分と決別した。
- 何が悪かったのか、これからどうすればいいのか一生懸命考え、行動し、結果を出したのだ。
- ──僕と一緒に。
- そう、僕と一緒に、だ。
- ただ、綺麗になった彼女に見惚れている者たちと同列にされたくない。
- 彼女の歩みを見てきたのは僕で、彼女が必要としているのも僕なのだ。
- ──ああ、駄目だな。苛々する。
- 僕が抱いたのは、そんなドロドロとした黒い穏やかならぬ感情。
- リリが僕のことを想っていると分かっていても生まれてしまう、醜い嫉妬だ。
- だけどそれをリリには悟られたくない。
- 彼女には、いつだって余裕のある男だと思われたいではないか。
- 年上の、男としてのちっぽけな矜持。
- 嫉妬を綺麗に押し隠し、彼女にダンスを申し込む。手を差し出すと、リリは笑顔で受けてくれた。
- 彼女のファーストダンスの相手を務めること。これは婚約者である僕の権利だ。
- 他の誰にも渡すものか。
- 周りの男共が羨ましげに僕を見ているのが分かる。
- それに気づき、彼らに見せつけるように彼女と踊った。
- さぞ羨ましいことだろう。僕のリリだ。お前たちには指一本触れさせるものか。
- 自分でも馬鹿なことをしていると思ったが、苛ついた気持ちが少しだけ収まった気がした。
- ダンスが終わる。その後、少しばかりゴタゴタがあったが、なんとか彼女と二人きりになることができた。
- バルコニーに連れ出し、彼女の気持ちを尋ねる。
- 答えなど分かってはいたが、彼女自身の口から告げられた『好き』の言葉は格別だった。
- 婚約者として側にいてくれた彼女が、真実、恋人になった瞬間。
- 誰に憚はばかることなく、彼女を『自分のもの』だと主張できる権利を手に入れたあの瞬間は、今までの僕の人生の中で一番幸せだったと言って間違いない。
- 「アル?」
- 「……あ、ごめん」
- 長かったこれまでの道のりに思いを馳はせていると、リリが僕の名前を呼んだ。
- 我に返る。
- 何食わぬ顔で彼女に返事をし、笑みを浮かべた。
- 「えっと、どうしたの?」
- 「いえ……なんだかぼうっとしていらっしゃるように見えたので」
- 気落ちしたような声。それを疑問に思った僕は、冗談めかして聞いてみた。
- 「君にようやく好きだって言ってもらえたなって考えていただけだよ。うん? もしかして不安にでもなっていたのかな?」
- 「っ……」
- まるで図星を突かれたとでも言わんばかりに、リリは気まずそうに俯いてしまう。
- それを見て、僕は愕然としていた。
- ──不安って……噓だろう?
- 僕はこんなに彼女のことを愛しているのに、一体何が不安だというのだろう。
- 「リリ?」
- できるだけ優しい声音を心がけ、彼女に呼びかける。
- だけどリリは顔を上げない。そんな彼女に、僕は根気よく声をかけた。
- 「リリ。顔を上げてよ。俯いていたら、可愛い君の顔が見られないじゃないか」
- 「きゃっ……ア、アル……」
- 埒らちがあかないので、指で彼女の顎を掬う。
- 強引に顔を上げさせると、顔を真っ赤にしたリリがいた。
- ……うん。そういう顔はずるいと思うのだけど。問い詰めようと思っていた気持ちが挫くじけてしまうじゃないか。
- 「どうしたの。凶悪なほど可愛い顔になってるよ。何? 僕を誘ってるつもり? もう一度キスしたいって言うのなら、僕は大歓迎だけど」
- 「ち、違います!」
- 「なんだ。違うのか、残念」
- 彼女の顎から大人しく指を離す。リリは顔を赤くしたまま目を瞬かせた。
- 「ざ、残念って……」
- 「ん? 何も噓は言っていないよ。君が「はい」って答えてくれたらキスするつもりだったんだから」
- 「キ……キス……」
- 狼狽える彼女に一歩近づく。リリは慌てたように後ろに下がった。
- 「どうして逃げるの。さっきもしたじゃないか。君の唇はとても柔らかくて甘かったよ。もう一度と言わず、何度でもしたいと思ったけど」
- 「そ、そういうことを言うのは止めて下さい」
- 「どうして?」
- 心底不思議だったので首を傾げると、彼女はプルプルと震えながら言った。
- 「は、恥ずかしいじゃないですか!」
- 「恥ずかしい? 僕は別に恥ずかしくなんてないけど」
- 僕としては、ようやく愛しい人の唇に触れられて嬉しいばかりだったのだけど。
- 「君は、嬉しいって思ってくれなかったの?」
- だとしたら悲しい。僕一人だけが喜んでいても仕方ないからだ。
- がっかりした顔をすると、リリは慌てて否定した。
- がっかりした顔をすると、リリは慌てて否定した。
- 「も、もちろん嬉しかったです! あ、当たり前じゃないですか」
- 「そう、それは良かった。君の口からそう言ってもらえて嬉しいよ」
- 「~~!」
- やられたという顔で、リリが僕を見つめてくる。そんな彼女に僕はにっこりと笑いながら言った。
- 「で? 話を戻すよ。リリは何を不安がっていたのか、理由を教えてくれるかな?」
- 「えっ! そ、その話は終わったんじゃ……」
- 「いつ終わりだなんて言った? もちろん聞かせてもらうに決まってる」
- 「噓……」
- 「ほら、答えて」
- 答えを促すと、リリはあからさまにたじろいだ。
- 「わ、私……」
- 「正直に言ってご覧。怒らないから」
- 優しい声で諭す。しばらく黙っていたが、誤魔化せないと分かったのだろう。リリはおずおずと口を開いた。
- 「そ、その……アルは素敵な方ですから……やっぱり私では釣り合わないのではないかって思って……だって、私は『悪役令嬢』だった女だから……」
- 「馬鹿だな」
- 「きゃっ!」
- 彼女の腕を引っ張り、少々強引にではあるが、自分の腕の中へと引き込む。そのまま抱き締めると、リリは「ひゃあ……」と可愛い声を上げた。その耳元で囁く。
- 「僕こそ、君を誰かに取られないかっていつも気が気でないっていうのに。リリ、君は本当に綺麗になったよ。油断していたら、あっという間に誰かにかっ攫さらわれてしまいそうだって心配するくらいには」
- 「そ、そんなこと……。心配なのは私の方です」
- ばっと顔を上げ、リリが言い返してくる。それに僕も真顔で返した。
- 「僕の方だって」
- 「私です」
- 「僕だよ」
- 「私ですってば」
- 「僕」
- 僕も彼女も一歩も退かない。そのうち、なんだか楽しくなってきてしまった。
- 無意味なやりとりなのに、何故だろう。妙に心がぽかぽかと温かくなるのだ。
- 彼女も同じ気持ちなのか、表情がどんどん可愛らしくなっていく。それを見て、僕は言った。
- 「じゃ、二人とも心配だってことにしとこうか」
- 「そ、そうですね……このままだと決着もつきませんし」
- 「僕としては、どっちの方が心配というより、どっちの方が好きって言い合いたいんだけど。その方が楽しそうだよね」
- 「っ!」
- 僕の腕の中で固まってしまった彼女に甘く告げる。
- 「ねえ? 僕は君のことが本当に大好きなんだよ? だから、他の誰かを見る予定なんてどこにもないんだ。それを信じてもらいたいし、君にもそうしてもらいたいって思ってる」
- 「わ、私……アルしか見てません。初めてお会いした時からずっとあなただけが好きだったんですから」
- そう言ってくれる彼女の顔は真剣だ。
- 「本当に? 嬉しいな。じゃ、これからもよそ見なんてしないでよ?」
- 「し、しません。そ、そんな余裕ありませんから」
- そう言ってくれる彼女の顔は真剣だ。
- 「本当に? 嬉しいな。じゃ、これからもよそ見なんてしないでよ?」
- 「し、しません。そ、そんな余裕ありませんから」
- 真摯な表情で訴えてくる彼女が酷く愛おしく思える。
- そんな彼女の額に軽く口づけ、小声で告げた。
- 「──約束、だよ。でなければ、僕は何をしてしまうか分からないからね」
- 「っ!」
- 冗談なんかではない。これは、僕の偽らざる本音だ。
- だって僕はもう、僕の唯一を彼女だと決めている。リリが、たとえ僕以外がいいと言ったところで、今更手放せるはずがないのだ。
- どんな手を使ったとしても、僕は彼女を捕らえ続ける。
- 僕が、僕であるために。
- 「ア、アル……」
- リリの声が震えていた。それに気づき、僕は笑顔を作る。
- 「怖がらせちゃったかな? だけどこれが僕の本心。君には受け入れがたいかもしれないけど」
- 「──いいえ」
- どんな答えが返ってきても構わない。そんなつもりで正直に告げたのだが、リリは臆せず僕の目を見つめてきた。その真っ直すぐな瞳がとても美しいと思う。
- 「リリ──」
- 「いいえ。私は、どんなあなたでも愛しています。だって、私を助けてくれたのは他ならぬあなたなのですから。それに──」
- 言葉を句切り、リリは恥ずかしそうに俯いた。
- 「その……大好きなあなたにそこまで想っていただけるのはとても嬉しいことだと思います。私も──今更、あなたを誰かに取られたくはありませんから」
- 「っ!」
- 一緒ですね、と恥ずかしげに笑うリリが愛おしすぎてたまらない。
- 思わず、抱き締めた腕に力を込めた。
- 「リリ……愛してる。君は僕だけのものだ。絶対に、他の誰にも渡さないから。だから、覚悟しておいて」
- 「──はい」
- 「本当に、いいんだね?」
- 念を押すと、彼女は花が咲いたような美しい笑みを僕に向けてくれた。そして、もう一度、答えてくれる。
- 「はい、もちろんです」
- 承諾と共に、僕の背中に彼女の細い両手が回された。それをとても嬉しいと思う。
- ──姿を消した僕らを探しに来た兵士たちに見つかるまで、多分、あと少し。
- そうしたら、きっと恥ずかしがりやの彼女は僕から離れてしまうから。
- だから、せめて彼らに見つかってしまうまでの間だけでも、こうして彼女を抱き締め続けていたいと、僕はそう願うのだ。
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement