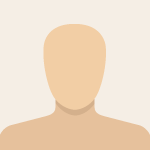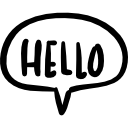Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- D: The Novel by Kenji Eno
- Ripped from D: Director's Cut (3DO)
- [CHAPTER 00]
- 胎児は、夢を見ていた。
- 太古の海にも似た、濃く暖かい液体の中で分裂を始めた細胞が、やがてはひとつの生物としての機能を持つ。
- まさにその瞬間から、夢は始まったのだ。
- 手や足はおろか、脳や神経すら未だ形をとっていなかった胎児は、宿ったばかりの魂の眼をもってそれを見た。
- 夢は、血とうめきに満ちた凄惨な悪夢だった。
- 人体が、さながら遊びの様なたやすさで引き裂かれた。
- 鋭い杭が繰り返し温かい肉に突き刺さった。
- 苦悶の叫びと呪詛の声が空間にあふれ、膨大な血しぶきとともにしたたった。
- 自身何の経験も持たない胎児は、その情景の意味するところを知らず、最初はただ心の眼をみはってそれを眺めていた。
- しかし、殺戮の光景は絶えることなく続き、胎児の脳と体が形造られるにつれ鮮明になっていった。
- やがて、胎児の意識の中に、始めての感情が生まれた。
- それは、後に不安と呼ばれる感情の芽であった。
- 胎児は、常に殺戮の中心に立ちはだかっている巨大な影に気づいていた。
- 影は、男だった。
- 身にまとっているのは漆黒のマントであったが、時として血のりを浴びた白衣にも見えた。
- 無残に虐殺されていく人々の呪詛はその男に向けられていたが、男はそれに残忍な笑みをもって応えた。
- 蒼白な面に亀裂の如く走る唇には、それらの犠牲者の鮮血が滲んでいた。
- 胎児は、男に強い恐れを感じた。
- 限りない惨劇の演出者がまさにこの男である事を、胎児は知っていた。
- すべてが、この男の手によるものだったのだ。
- 胎児がこの夢を見ていることですら、男は承知しているようだった。
- 否、
- この夢自身が、男の意思によるものかも知れなかった。
- 胎児はもがいた。
- ようやく得た自分の力の限りに、胎児は手足を動かして悪夢から逃れようとしたが、それは不可能だった。
- 男はそんな胎児の反応を嘲笑うかのように、ますます冷たい笑いを深めていった。
- 人々の絶叫はさらに大きくなり、血はあたかも川のように流れた。
- 目を閉じることも、耳を塞ぐこともできない胎児は、ただ空しい動きを続けていた。
- 積み重なっていく死体の山の前に、胎児の意識をひく何者かの幻影が浮かび上がってきた。
- それは、ひとりの女性の姿だった。
- 黄金の髪を持ち、澄んだ青い目をみはって男を見つめている。
- 美しい顔には驚愕の表情が浮かび、女性はほっそりとした足を踏み出して、男に歩み寄ろうとしていた。
- 胎児の意識に、新たな恐怖がわき上がった。
- 女性が男に見つかったら、胎児自身にとって何か取り返しのつかないことが起こるような気がした。
- 叫べるものなら、叫んでいただろう。
- しかし、胎児には何もできなかった。
- 男の目がゆっくりと回され、黄金の髪の女性にすえられた。
- 血塗られた唇が喜悦に歪み、白く尖った歯と真紅に染まった舌がちらりとのぞいた。
- 男は、底響く声で言った。
- 「こっちへ来い」
- 胎児は、
- 必死にもがいた。
- 胎児は絶対に見たくなかった。
- 女性が、宙を踏む足取りで男に向かって行く所を……
- 男がマントだか白衣だかを広げて、愛情とは対極の仕種で女性を抱き締めるところを……
- そして……
- ふいに、胎児は全身を締め付ける力を感じた。
- 夢の情景がみるみる色あせていき、胎児の脳裏から初めて消えうせた。
- 胎児を浮かべていた温かい海はあふれだし、胎児をどこかへ押し流そうとしていた。
- 胎児は無意識のうちに身を縮め、激流に従って狭い門をくぐり抜けた。
- 誕生の時であった。
- [CHAPTER 01]
- その地は、ヨーロッパの東の縁に位置していた。
- 西洋と東洋が出会い、こすれあい、牙をむいて相手ののどを食い破ろうと狙う長い時間が、この地の歴史だった。
- 文化も宗教もまったく異なるが故に、その戦いは凄惨を極めた。
- 敵はどういう意味であれ人間ではないという認識が、残虐行為を限りなくエスカレートさせていた。
- どのようなむごい行いも、敵に対する限り『神』と『正義』の名において祝福されたのだった。
- その中でも、伝説となるほどの残酷さで、敵味方すべてに恐れられた男がいた。
- 彼の領地は、険しい山と深い森に囲まれた小国だった。
- 強大なオスマン・トルコと国境を接して、常にその圧力を受けていたその国は、武力と外交の戦いに揉まれ続けていた。
- その国の継承者として生まれた彼は、幼い日々を敵国の人質として、屈辱と抑圧の中に育った。
- さらに、領主の座に着くためには、味方陣営の陰謀の渦をも生き抜かなければならなかった。
- 彼が地位について後は、敵国兵士はもちろん、政敵に対してもひとかけらの容赦もしなかった。
- 従来大きな力を持っていた領内の貴族や豪族を次々と粛正し、わずかな時間でその権力を確固たるものに変えていった。
- 彼は、小高い丘と森に守られた古い城を選んで住んだ。
- 城の再建にあたっては、多くの奴隷や貧しい領民が狩りだされ、過酷な鞭の元に働かされた。
- 領民たちは、血とうめきの上にそそりたった城を畏怖の念をもって見上げた。
- 彼の権力の基は、恐怖であった。
- 彼の名は、その本名よりあだなをもって知られた。
- 父の大公が『ドラクル』、つまり悪魔、龍と呼ばれたのに因み、彼はその子という意味の『ドラキュラ』と呼ばれたのである。
- そして、彼の別名を、『串刺公』という。
- 彼は、石畳みに膝をついている男を見た。
- かすかな灯がゆれる、広さも定かならぬ部屋の中である。
- 窓の外の闇から、時々鋭い閃光が走って、大きな椅子に座した彼の青白い面を照らし出す。
- 広い額に豊かな黒髪がかかり、その下の瞳には、限りない英知と、見る者をおののかせずにはいない氷のごとき冷酷さが宿っている。
- 東洋風に宝石をちりばめた上着と、豪奢な毛皮に縁取られたマントをまとった彼は、血の気のない、そいだような頬に指を軽く当てた。
- つややかな口髭をなでながら言う。
- 「予の治世もようやく定まったというのに、今だ予の方針に疑問を挟む者がおるとは残念だ。
- あの勇猛だった父を位から追い、恥辱の最後を与えたこの国の貴族たちは、もうとうに片付けたと思っていたのに。
- そなたも、かつて予をトルコに売り、その手先となった者どもの仲間というわけか」
- 男は、ようやく顔を上げた。
- まだ若い端正な顔立ちだが、所々に散ったアザと、額から垂れた血の汚れが、青年の年齢を倍に見せている。
- 彼ほどではないにしろ、それなりに上等な服装がずたずたに裂けて、むごい扱いを受けたことを物語っていた。
- 大地の底から響いてくるような遠雷が、灯をか細く震わせた。
- 青年は、絞り出すように言った。
- 「……私がトルコのスパイなどと……
- とんでもない誤解です。
- 私は、ご領主様の真意をうかがいたいと思っただけなのです。
- それが、ご領主様のお耳にその様な形で入ろうとは……。
- この地方で、ご領主様に逆らう者はもう、誰ひとりとしておりません。
- 私も……」
- 「……もう、誰ひとりとして、か」
- 「その、とおりです」
- 答えてから、青年ははっとしたように口をつぐんだ。
- 彼は、唇の色さえ失っている青年を、いっそ楽しげな笑みをもって眺めた。
- 「そのとおりだな。
- 予に逆らう者はほとんどすべてが、その愚かしさを知ったのだ。
- そなたもまた、それを知る番だ」
- 「どうか、お許し下さい!」
- 青年は、石畳みに頭を打ちつけるようにして請うた。
- 彼は、ゆっくりと窓に顔を振り向ける。
- 稲妻が、再びその細面に刻まれた冷たい微笑を浮き出させる。
- と同時に、窓から望まれる黒々とした丘と、その頂きに数多く立てられた杭の林をも照らしだした。
- 杭の一本一本の天辺に、さながら繰り人形を立てたように、人体がつき刺されていた。
- すでにぼろぼろの布切れがまつわりついているようになったもの、
- 白い骨だけになった体が引っかかっているもの、
- そして、例外なくぽっかりと口を開けて、永遠の呪詛を叫んでいるまだ新しい死体たち。
- その大部分はトルコ兵や敵として戦った周辺国の兵士であったが、なかには彼の政策に非を唱えた、青年と同じ『ご領主』領内に財産を持つ小貴族たちが含まれていた。
- 青年も、ずっと恐れていた『自分の番』がやってきたのを悟っていた。
- 彼は、悲鳴に近く叫んだ。
- 「お許しいただけるのでしたら、すべてを捧げます。
- 財産も、奴隷も、すべて、ご領主様の、ご意思のままに……」
- 「すべて、な」
- 彼は軽くつぶやいた。
- 改めて、必死の面持ちで彼を見つめる青年に視線を戻す。
- 彼は、豊かな毛皮のひだに手を差し込んだ。
- 華奢な黄金の鍵をひとつ、白いほっそりとした指でつまみ出す。
- 「いい心掛けだ。
- そなたのすべて、受け取ろうではないか」
- 「で……
- では」
- 彼は指先で鍵を弾いた。
- チィーン、と澄んだ音を立てて、金のきらめきが青年のひざ元に落ちた。
- 「この鍵はな、予がそなたのすべてを収めた証しだ。
- 替わりに受け取るがよい」
- 青年はわななく指で、その金の鍵を握り締めた。
- さらに、もの問いたげに唇を震わせる。
- 「さあ、ゆくがよい」
- 彼はそれだけ言って、ドアの方向に手を振った。
- 「ゆけ」
- 青年は、なんとか立ち上がった。
- 連行された時に負った傷のためにおぼつかない足取りで、それでも彼の気が変わるのを恐れるように、ドアから去った。
- 見送った彼は、とうとうくすくすと声をたてて笑い出した。
- 椅子に背を預け、全身を震わせて笑い続けた彼は、やがてかすれた声でつぶやいた。
- 「愚かなものだ……
- 人間とは……
- 本当に愚かなものだ……」
- そして、振り向くことなく、部屋の隅に向けて「来い」と命じた。
- 闇がゆらりと揺れて、巨大な鉄の甲冑が一体、灯の中に現れた。
- 面金の奥には、人の目のかわりにまがまがしい暗黒のみがのぞいている。
- 「追って、見届けよ」
- カッと閃光が走る。
- 銀色に輝く甲冑が、きしむ音を立ててドアをくぐり抜ける時も、彼はまだ笑っていた。
- 耳を聾する雷鳴が大地にとどろく。
- 稲妻は、研ぎすまされた刃になって、天を縦横に切り裂く。
- やがて音と光がほとんど同時となって、彼に襲いかかるかのように部屋に満ちた。
- 彼は、きっと窓に視線を向けた。
- 丘が燃えている。
- どの柱が落雷を受けたのか、強風にあおられた柱の群れは、鮮やかな朱金の炎に包まれていた。
- 火と風が死骸たちに再び命を吹き込んだとでもいうように、彼等は柱の上で腰を揺らし、手足を動かしていた。
- それは、文字通り『死の舞踏』であった。
- 人々を死へと誘うそのダンスは、今はただ一人、彼に向けられたものだった。
- 『お前は俺を串刺しにした』
- 『生きたまま、許しを請う涙には目もくれずに』
- 『とどめを刺す情けすら持たず』
- 『苦痛を長引かせるために、杭をわざと浅く刺して』
- 『幾日も、幾日も』
- 『鳥についばまれ、虫に吸い付かれて』
- 『慈悲ぶかい死が、ようやく苦しみを終わらせてくれるまで』
- 真っ赤な砂子を撒き散らして柱が焼け落ちる瞬間、死骸たちはそれぞれに、雷鳴を圧するほどの大声で叫んだ。
- 『お前も来い!』
- 『お前の死をもって償え!』
- 『俺たちの恨みを忘れるな!』
- 『きっと……!』
- 彼は、眉ひとつ動かさずにそれを見詰めていた。
- その凄まじい情景が彼の表情に刻んだものは、恐怖ではなく、嘲りであった。
- 彼は、城の一郭の大きな扉を開けた。
- 広い一室だった。
- 羽目板と、幾重にも重なった薄絹が石壁を隠し、数え切れない灯が、そこここに置かれた優美な装飾品を照らしている。
- この城で唯一、似つかわしくない美しさを持った部屋だった。
- 天葢の下に、一人の女性が座っている。
- 部屋と同じく、この城にふさわしからぬ花のような女性であった。
- 抜けるように白い肌、くっきりと弧を描く眉の下に、サファイアの輝きが宿っていた。
- 金色の髪が広がって、背後からそのほっそりとした体を包み、聖光に守られた天使か女神を思わせた。
- 彼を見るこわばった表情も、彼女の美しさを少しも損なっていなかった。
- 彼を認めてあわてて顔を伏せる侍女に下がるように手を振ると、彼女は堅い声音で言った。
- 「何か、ご用でございますか」
- 「ずいぶんな挨拶だな」
- 彼は大股に部屋に入ると、彼女の正面の暖炉に無造作に寄りかかった。
- 見返す彼女の瞳には、他の誰もが彼を見る時に浮かべる恐れの色は無く、ただひややかな強い光があった。
- 「そなたは予の妃だ。
- 用が無ければ、そなたの部屋を訪ねてはいけないと言うのか」
- 彼女はゆるやかに首を振った。
- なめらかな陶器を思わせる肩に散りかかる、黄金の髪が微かに揺れる。
- 「……何か、申されたいことがございますのでしょう。
- おうかがいいたします」
- 「よい勘だ」
- 彼は、先刻若い貴族に向けたのと同質の笑みを、唇に刻んだ。
- 「つい先ほど、そなたの従兄弟、バルテニのゼトラツェークが、領地を予に差し出してくれたぞ」
- それを聞いた彼女の頬から、みるみるうちに血の気が失せた。
- 「誠に殊勝な男だ。
- 予はそれを嘉納し、かわりにと申して金の鍵をくれてやったわ。
- と言っても、鍵はそれ、その机の鍵だ。
- どの扉も開きはしないがな」
- 脇机をあごで示して、彼はおかしそうに続ける。
- 「さあて、あやつは城を抜け出せるかな。
- なまじ鍵を持っているがために、いろいろと迷うであろうな」
- 「あ……
- あなた様は……」
- 震える声でつぶやいた彼女は、白い手をのど元に当てる。
- 手の下で、首から細い金鎖で吊った玉虫のペンダントが、彼女のおののきを伝えてきらきらと輝いた。
- 「あやつが無事に城を抜け出せれば、あやつの命は助けてやろうと思っている。
- なにしろあやつは、予にとってもそなたを通じて遠縁にあたる者だ。
- 最もそれ故に、今日まで柱に登るのを免れていたのだからなあ」
- 「同じ……
- 同じことでございましょう。
- この城から無事に逃げるなど、とてもできますまい」
- 「そうだ。
- よほどの幸運に巡り合わぬ限り、予の城からは出られぬだろう。
- しかし、そなたの従兄弟であるからこそ、助かる術のある道を選ばせてやったのだ」
- 彼女は、色あせた花びらのような唇を噛んだ。
- 彼の冷たい笑みは、ますます深くなる。
- ふいに、地獄の底から響くようなノックがとどろいた。
- 金属の軋みを聞きつけた彼は、「かまわぬ」と答える。
- 扉が開き、青年を追っていった甲冑が姿を現した。
- 禍々しいギシギシという音と共に、彼の前にひざまづく。
- ただひたすら体を堅くして座っている彼女には何も聞こえなかったが、彼は報告を受けるように幾度か頷き、
- くくく…
- と声をたてて笑った。
- 「ご苦労だったな。
- 下がってよいぞ」
- 甲冑は再びぎこちなく立ち上がると、ゆっくりと部屋を出てゆく。
- 「そなたの従兄弟は、なかなかいい所まで行ったそうだぞ。
- 鎧の回廊では、あいつも少々遊んでやったそうだ。
- あいつが穴に落ちたので、倒せたとでも思ったのだろうな、胸像の部屋へ逃げ込んだ」
- 「……」
- 「そして、奥のドアに入ってしまったのだな。
- さぞ驚いただろう、あそこは隣国の貴族たちを閉じ込めておいた部屋だ。
- 中からは、決して開かない。
- 今頃は、ミイラに囲まれて震えているであろうな。
- 明日の我が身をながめながら」
- 「あなた様は!」
- 彼女はうめいた。
- 「ご満足でございますか!
- もうこの国には、あなた様に反する貴族はもう……
- いえ、逆らおうと逆らうまいと、力を持った者はほとんどおりません」
- 「……あやつも、そう申しておったな」
- 「誰でも知っております。
- あなた様は、邪魔者をすべて片付けてしまわれた……
- 私の家も……
- 一族も」
- 彼は相変わらず薄く笑ったまま、静かな声音で言う。
- 「そなたの一族は、予の一族と代々婚姻を重ねてきた家だ。
- 予の母もそうであった。
- こうなるとそなたは、予の血筋に連なる唯一の者という事になる。
- そなたの家は、父を裏切る陰謀に荷担しておった。
- 本来なら根絶やしにすべき所だったが、予が国に戻ったとたんに、予におもねるためにそなたを寄越しおった。
- まあ、うまい手であったと言えような。
- ゼトラツェークの血は、そなたを通じて残るわけだ。
- そなたと予の子が、この国を継ぐのであるからな」
- 彼女は反射的に、両手を自分の腹部に当てる。
- 柔らかな布に包まれたその部分はふっくらと盛り上がって、新たな生命が息づいているのがうかがわれた。
- 彼女は、苦しげに目を閉じた。
- 震える細い声は、あたかも呪詛に似ていた。
- 「あなた様は、あまりにたくさんの血を流されました。
- 戦場で流す血でしたら、騎士として当然でございましょう。
- ……しかし、あなた様が浴びるほど流された血は、この城一杯にあふれております。
- 怨みの声は、この城と国の空中に響き渡っております。
- ……神は、けして私たちをお許しにはなりますまい。
- 私たちの子供に……
- あるいは、その子供たちに……
- 神の怒りが……」
- 「神、か……」
- 彼は、その顔から始めて笑みを消した。
- 「神など、何の意味もない!
- 神聖ローマ帝国が神に守られていたのなら、コンスタンティノープルは何故落ちた?
- ローマの神もトルコの神も、現実には何の力も持ってはいないのだ。
- 力は……」
- 彼は叩きつけるように叫んだ。
- 「予が持っておるのだ!
- 予が、この手で作りだすのだ!
- そしてその力を、すべての者に思い知らせてやるのだ!」
- 彼女は聞くまいと耳をふさいで、身を伏せた。
- 髪が金色の霞に広がり、きらきらと光を跳ね返す。
- 微かなすすり泣きが始まると、玉虫のペンダントが生あるもののように踊った。
- 彼は冷然と、それをみつめていた。
- [CHAPTER 02]
- 「第9宮、射手の座は、破壊を現しまする」
- 「破壊か。
- まさに、予にこそふさわしいと申せそうだな」
- 強い酒を口に含みながら、彼はつぶやいた。
- 小さな影が3つ、椅子に座った彼の前にうずくまっていた。
- 暗い灰色のローブを被り、どれも同じように見える。
- さながら闇が凝固したような、どこか不吉な影たちであった。
- 中央の影がゆらゆら揺れながら、奇妙に響く声でしゃべる。
- 「御意にございます。
- これはあなた様の運命を司る座でございます。
- 星の守護を得るために、像をお造り下さい」
- 右側の影が、低く歌うように言う。
- 「炎の矢が駆ける。
- 天を焼き、地を焼き、敵を焼き尽くす炎が……」
- 左の影は無言のまま、ローブをかきわけて骨のような両手を上げた。
- 空中に何かの形を描きだす。
- とたんに、部屋の中に熱気が爆発した。
- 巨大な炎の龍が現れたのだ。
- 魔の世界から呼び出された幻の龍は、高い天井まで駆け上がり、部屋中を荒れ狂った。
- 恐ろしい熱の波が石壁にぶつかり、かけられていたタペストリイをぶすぶすとくすぶらせた。
- が、3つの影は動かなかった。
- 彼も、面白いものでも見物するように、ただ見上げている。
- 龍はもう一度上へ伸び上がると、真っ逆様に彼に向かってなだれ落ちてきた。
- 彼は、わずかに目を細めただけで、龍を全身で受け止めた。
- 龍は彼の体に吸い込まれるように消えた。
- 「……あの龍は」
- 闇が戻ってきて、熱気が薄れた。
- 中の影がささやく。
- 「あなた様ご自身にございます。
- あなた様は、龍の御子でいらっしゃいますから」
- 「……」
- 彼は何事もなかったかのように、軽く肩をすくめた。
- 「それから、もうひとつ像をお造りになられますように」
- 「何の像だ」
- 「第11宮、水瓶の座。
- 奥方様の宮でございます」
- 「ふうむ」
- 「水は守り也。
- すべての子は、水に生まれまする故」
- ふいに、彼は皮肉な笑いを唇に刻んだ。
- 「水は、火を消すのではないのか?
- 予の力を消してしまうのではないだろうな」
- 「それは……」
- 右の影が、呪文を唱えるようにつぶやいた。
- 「水……
- ただの水ではない。
- 赤い……
- 真っ赤な水……
- 血だ。
- 血が流れる。
- 瓶に血を満たすのだ。
- 満ちれば満ちるほど……
- あふれればあふれるほど……
- 力が加わる。
- さらに、力を欲する者は……」
- 影は黙った。
- 彼は左の影を見たが、ただゆらゆらと揺れているだけで、何の仕種もしない。
- やがて、用の無くなった右と左の影はにじむように崩れだし、闇に溶けていった。
- 残った影は、ほとんど聞き取れないくらい低い声で言った。
- 「あなた様は、暗黒の力を手にされた。
- お使いになるがよい。
- その代償として流された血は、この城の石組を伝わって、黄泉の国へと滴り落ちます」
- 声の余韻が、石の床に吸い込まれる。
- しばらくの後、彼は杯をあおると立ち上がった。
- 一段高くなった床を歩き回りながら、独語のように語りだした。
- 「予は、虜となった父の身代わりとなってオスマン・トルコの人質となり、スルタンの館で育った。
- 奴等は予に、屈辱の限りを与えたものだった。
- 予の心に、奴等に逆らうことの恐ろしさを植えつけようとしたのだ。
- 幼なかった予は、始めせいいっぱい抵抗したが、ただ奴等の楽しみを増しただけだった。
- 奴等は予を脅かすために、予の目の前で捕虜を何人も杭に刺してみせたものだ。
- 予を、杭の足元に立たせて、血を頭から浴びるようにして……。
- 予ははっきりと覚えている。
- 温かい血が、苦悶の呻きとともに上から降ってきて、予の目と口に入り込む……
- 全身を濡らし、予の内部まで……
- 真っ赤に濡らしたのだ。
- すぐに死なぬように、心臓を避けて刺すのが上手い兵がいてな、奴等は捕虜の命がいつまで持つかを賭けるのだ。
- 終いには、予もその賭けに加わるようになっておったよ。
- 無駄に逆らっても、何の益もない。
- おとなしく……
- 誇りの最後の一片をも捨てて……
- 予は奴等の言いなりになった」
- 黒い影は、彼の独白を聞いているのかいないのか、ただもやもやとわだかまっているだけである。
- 彼はかまわずに続ける。
- 「ずいぶんと恨んだものだ。
- 奴等を、そして子供を犠牲にして長らえている父を。
- いつの日にかトルコを逃げ出し、父に代わってこの国を手にいれてやる。
- そして、奴等から受けた仕打ちを、全て奴等に返してやる。
- そう思う事で、毎日をどうにか耐えていたのだ。
- そこへ、父が裏切りにあって殺されたという知らせが舞い込んだ。
- 奴等は、予に兵を与えて国に返した。
- 傀儡とするつもりで……。
- それから、真の領主としてこの国を治めるようになるまで、長い月日と激しい戦いが必要だったのだ。
- その戦いはまだ、終わってはいない。
- 力がいるのだ、強い力が。
- たとえ、邪悪なものであっても」
- 「……お使い下さいと、申しております」
- 影が答える。
- 「あなた様は我らを呼びだし、我らに血の供物を与えた。
- 供物の絶えぬ限り、我らの力はあなた様のものでございます」
- 「予がトルコで過ごした年月、無駄ではなかったな。
- そなたたちを呼び出す術は、スルタンの秘本で知ったのだから。
- あ奴等は、自ら伝えた秘儀の生け贄になるのだ。
- しかも、奴等お得意の杭でな」
- 彼は、陰鬱な笑い声をもらした。
- 「そなたの言うとおり、2つの像を造ろう。
- 噴水とでも組み合わせれば、いい装飾になるだろう。
- それで、予の目的を達成するだけの力が手に入るのだな」
- 影は即答せず、ゆらゆらと揺れた。
- 次第に輪郭が崩れだし、先のふたつの影と同様に、ゆっくりと床に吸い込まれていく。
- 彼は、眉をしかめてそれを見送った。
- 影が消えた後には、四方を金具で固めた、一冊の本がころがっていた。
- 密かな噂が、広まっていた。
- 「……ドラクルの子、龍の子が……」
- 「龍というより、あれは悪魔じゃ。
- あれは、わし等貴族の権利を、すべて剥ぎ取ろうとしておるのじゃ」
- 「権利だけではない」
- 「そうだ、権利だけではない。
- 命もじゃ。
- あれににらまれた者は、どんなに警護を固めても、いつの間にか連れ去られてしまう」
- 「あの城に、だ」
- 「そして、2度と戻っては来ない」
- 「悪魔じゃ。
- 悪魔の仕業じゃ。
- 悪魔に逆らえる者など、どこにもいない」
- 「……こんな話をしていると、我々も危ないぞ」
- 「まさか……」
- 「いや、わからん。
- あれは、どこに耳を持っておるか……」
- 「うらやましい気もするがな。
- わが国とて地主貴族の力が強く、国王とは名ばかりじゃ。
- いっそ貴族どもを全員、杭に登らせてしまいたいと思うのは、私もD公と同様じゃ」
- 「とんでもないことを……」
- 「ああ、それはできぬな。
- 私がこんなことを言ったとわかったら、我が国の貴族たちは、私自身を杭に突き刺してしまうだろうよ。
- そこへいくと、D公は誠にお強い。
- 公でなくては、トルコとの戦いの中で国など保てまいからな。
- 敵兵どもは、公を悪魔のように恐れているそうな」
- 「もっともでございますな。
- 公が陣頭に立たれた時は、兵の勢いが違いまする」
- 「いつ、あのような力を蓄えられたのか……
- トルコから戻られてすぐ、また裏切りにあってハンガリーに亡命……
- 再び戻って大公の座に着かれてから、まだいくらも経ってはいないのに」
- 「敵には、回されないことですな。
- 友軍としては、これほど頼りになる方もございますまい。
- とは申しましても、いつ状況が変わるかはわかりませぬが……」
- 「……見た
- ……俺は見たんだ。
- 黒い甲冑が音もなくやってきて、カレルの奴を連れていったんだ」
- 「……」
- 「あいつは、いつものように畑で草を取っていた。
- 甲冑が現れた時、気丈なあいつは、脇にあった鍬で撃ちかかっていったんだ。
- それなのに……」
- 「……」
- 「あいつは、剛力で知られていたんだ。
- そうだろう?
- それなのに、あいつの鍬は、当たらなかったんだ。
- まるで、幽霊に撃ちかかっていったみたいだった。
- 鍬は甲冑を通り抜けちまったんだ」
- 「……おい」
- 「信じられねえ……
- 見た俺だって、信じられねえけど……」
- 「おい、よせ!」
- 「甲冑はカレルの腕を取ると、引きずってっちまったよ……
- カレルはもう、声も出ねえみたいだった……
- 透き通った幽霊が、どうしてやつを掴まえられるのか、わかんねえけどよお……」
- 「もう、よせ!
- そんな事は、言わない方がいい!」
- 「カレルの連れていかれた先は、わかってるんだ……
- お城だよ……
- あのお城に……」
- 「ばか!
- そんな事を言っていると、お前も連れていかれちまう……
- 俺だって……」
- 「オ城ニハ、タクサンノ杭ガアルンダ。
- オ城ニ連レテイカレタ奴ハ、ミンナ杭ニ刺サレテ死ヌンダ。
- イッパイ、イッパイ、血ヲ流シテ。
- イッパイ、イッパイ……。
- ゴ領主様ハ、笑ッテイラッシャル」
- ステンドグラスから淡い光が入って、辺りをほのかに染め上げている。
- 金の髪の乙女が杖を抱いて立つ。
- 夜の支配者である月が、もう一人の支配者である彼の像を見守っている。
- ステンドグラスのさらに上には、晴れた日であってもそこだけは常に灰色の雲を集めているように見える、大きなドームがそそり立っている。
- ドームの最上階へは、階段が無いと信じられていた。
- 領主である彼だけが、何か神秘的な方法でその上に登ることが出来るのだ。
- 領民たちは城を、心の底からの恐怖をもって眺めた。
- そしてこのドームは、恐怖の中心たる彼の座であった。
- その彼は、今日も闇の世から呼び出した影の前で杯を傾けていた。
- 「……人間とは、もろい生き物だと思っていた。
- 杭一本で、やすやすと殺せる」
- 「……」
- 「しかし、時々、妙にしぶとい奴がおる。
- この間捕らえた坊主なぞ、壁に繋いでおいたら、指にはめていた指輪で石壁に穴を開けおった。
- その心意気に免じて、杭に刺さずにそのままにしておいてやった。
- あ奴の偉業は、この城のある限り残ることだろう」
- 影はただ、ゆらゆらと揺れているだけであった。
- 彼はふと眉をしかめる。
- 「無駄口を叩く気は無いという訳だな。
- 射手の像、水瓶の像とも出来上がった。
- 血も、あちこちの罠を通じて、城の地下に絶えず流れ込むようにしてある。
- そなたたちが必要だといった、あの奇妙な仕掛けの類いも、細工師に命じて作らせた。
- これ以上、何が必要だというのだ?」
- 少々いらだたしげな響きを持った彼の言葉を聞くと、闇の使いはそれまでのゆるやかな動きを止めた。
- 灰色のローブの影にのぞく暗黒が、いっそう濃くなって渦を巻く。
- と、ふいにその渦が部屋中にあふれ出した。
- 彼は、初めて顔をこわばらせた。
- 闇が空間を満たし、部屋をまったく別の次元に変えようとしている。
- 灰色のローブはいつの間にか消え、彼は底知れぬ深淵の上に、たったひとり浮かんでいるのに気付いた。
- 「汝、ドラキュラ。
- 悪魔の息子よ……」
- 深淵から吹き付けてくる瘴気を含んだ風が、低くひび割れた声を送ってきた。
- 「な……
- 何者だ!」
- 「我は、お前に選ばれ、お前を選びし者」
- 「なんだって!?」
- 生臭い風が彼の回りを舞い、手足にまとわりつく。
- 風の中には確かに、彼が串刺しにした人々の怨念がこもっていた。
- 風は、彼の体を絡めとり、深淵の奥深くにひきずりこもうとしていた。
- しかし、彼は臆する様子もなく、それらの気配を振り払った。
- この期に及んでも、彼に毛ほどの傷も負わせられないことを悟った怨霊たちは、さらに悔しげに泣き叫ぶ。
- 深淵の奥からの声は、邪悪な笑い声を響かせた。
- 「さすがにドラキュラ。
- それでこそ、我らの選んだ者だ」
- 「選んだだと!」
- 「そうだ。
- お前は、自分で我らを呼び出し、使っている積もりだったかも知れない。
- しかし、我らの方も、お前を選んだのだ。
- まだ幼かったお前は、杭に貫かれた体からの血を浴び、滴った血潮を唇で受け止めた。
- 恐れやおののきではなく、怒りと憎しみに満ちていたあの時のお前の舌には、血潮は甘かったであろう。
- あの時から、お前は生きる糧として人の血を選んだのだ。
- 憎悪と、復讐と、破壊に生きる、糧として。
- 血を選んだ時、お前は我らに選ばれた。
- 我らとお前は、同じものとなったのだ」
- 彼は、きっと唇を噛んで闇の奥底を凝視していた。
- 声の言うとおりだった。
- あの時から、彼の心は血を求め続けていた。
- 数限りない虐殺と流血は、秘術の闇に捧げるためばかりではなかった。
- 彼自身の体を浸し、心を満たすためにこそ、必要だったのだ。
- 「お前はまだ、満足していない。
- 従って、我らもまだ、満足してはいない。
- お前は永遠に、血を求め続ける。
- お前の餓えが、完全に満たされるまで」
- 彼ののどを、強烈な疼きが襲った。
- 血が飲みたい、と彼は思った。
- まだ動きを止めない温かい肉に歯を立て、のどを滑り落ちる甘い液体を存分に貪りたかった。
- 彼の髪はざわざわと逆立ち、瞳には凶暴な炎が点じられる。
- 長く伸びた爪が何者かを求めるように宙をかきむしり、朱に染まった唇からのぞく歯が、見るみるうちに鋭く尖った。
- 回りでざわめいていた怨霊たちは、生前そうであったように、恐怖のおののきとともに身を引こうとした。
- 彼は、漆黒のマントを一閃した。
- 荒れ狂う暗黒の龍が、闇の底から姿を現した。
- 龍は真っ赤に染まった顎を開き、逃げ惑う怨霊たちを瞬く間に飲み込んでいく。
- 魂の悲鳴が交錯する中で、彼は大声で笑った。
- 深淵は、闇は、彼の心の中に口開いたものだったのだ。
- 声がとどろく。
- 「もっと、もっと血を啜るのだ。
- お前には、我らには、それが必要だ。
- 龍の子よ。
- 悪魔の子、ドラキュラよ。
- 最後の力が欲しければ、お前に最も近い血を啜るのだ。
- お前の血筋に連なる者、
- お前の血肉を分けた者、
- その者の血こそが、お前に永遠の生命と、絶大無比の力を与えるであろう」
- 彼は笑っていた。
- 最後の力への扉の鍵が、今、与えられたのだ。
- とどろき渡った声は、彼がよく知っているものだった。
- その声は、彼の父の声に似ていた。
- 否、
- 彼自身の声だった。
- [CHAPTER 03]
- 少年は、汗ばんだ広い額にかかってくる淡い色の髪を神経質にかきあげながら、しゃがんだ足元を見つめていた。
- 庭の隅、噴水の裏側の息がつまるような草いきれの中に、微かに異臭がある。
- 彼の足元にあるのは、ウサギの屍だった。
- 腹部がざっくりと噛み裂かれ、強い陽射しに濡れた内臓を露にしている。
- あまり、時間は経っていない。
- 食われた形跡がないところを見ると、おそらくは遊び半分の犬の仕業であろう。
- 少年の目は、ウサギの傷に注がれていた。
- ウサギはまだ自分の死に気付かないとでもいうように、曇りのないガラスの瞳を見開いていた。
- 金茶色の柔らかな毛が血潮に染まって、傷の間際であいまいに消え、かわりに暗い色彩が形も定かでなく重なっている。
- 小さな虫たちが、匂いを嗅ぎつけて集まり始めている。
- 流れている血は、意外に少なかった。
- どこか別の所で殺されて、運ばれてきたらしい。
- 少年は、乾いた唇を細い舌でなめた。
- 汗に含まれたわずかな塩味が、彼の口中をくすぐった。
- もの足りない、と少年は思った。
- ウサギは、もっと大量の鮮血の中に倒れているべきだった。
- ウサギの内部からあふれた液体は、ウサギ自身を溺れさせる、海ができるほどあるはずなのだ。
- 血は、どこかにいってしまった。
- どこにあるのだろう。
- 少年の脳裏に、夜の正餐の食卓に置かれた、フィンガーボウルが浮かんだ。
- 食後の果物をむく時、冷たい水に指をひたすその瞬間、灯を跳ね返している小さな水面が真紅に染まったら。
- きらめく銀の器にたたえられた鮮血は、彼の指に温かく懐かしい感触を伝えるに違いない。
- そして、その血はやがて、謎の数字を写し出すのだ。
- この世の裏側にある、暗い恐ろしい闇の世界へ続く、扉を開けるキイ・ナンバーを……。
- ふいに、少年は身震いをした。
- たった今まで、魅せられたように見つめていた物体が何か、ようやく気付いたのだ。
- 嫌悪感と吐き気がのどの奥から沸きあがり、彼は弾かれたように立ち上がった。
- 自分が、何故そんな物にみとれていたのか、まったくわからなかった。
- 同時に、銀のきらめきと重い赤の印象も、彼の脳裏を去っていた。
- しかし少年は、何者かに追われるようにその場を走り去る前に、ちらりと後ろを振り返らずにはいられなかった。
- 夏草に隠れて、死骸ははっきりとは見えなかったが、目の隅をかすめた鮮紅色のものは、少年の胸の中にえたいの知れないうごめきを残した。
- 噴水と2つの石像を後ろに、館の正面に回り、開け放してある重い巨大な扉を駆けぬける。
- 西海岸の明るく強い陽光が遮られると、洞窟の冷たさが瞬時に少年を包む。
- 彼は玄関ホールの中央に立ち止まり、まぶしい表を見返した。
- この扉を通る時、彼はいつも違う世界への入り口をくぐるようだと思っていた。
- 「リクター」
- 呼ばれて、彼はダイニングのドアを振り向いた。
- 古めかしい服装の老女が立っていた。
- 老女は、彼の顔を見ると一瞬身を引くような動きをした。
- 老女の表情に、微かな怯えが走るのを、彼ははっきりと見た。
- 「なんですか、おばあさん」
- 「あ……
- お前は……」
- 老女は目をしばたたくと、少しあわてたようにハンカチを取りだし、額を押さえながら早口に言った。
- 「外は、陽射しが強すぎる。
- 家の中においで。
- さもないと、体に悪いよ」
- 「はい」
- 彼は素直にうなづいた。
- 何かのきっかけで、彼女が彼にそんな反応を示すのは、ほんの時折ではあったが初めてではなかった。
- 『彼女は、僕を怖がっている。
- 何故なら……
- 僕に、殺されると思っているんだ』
- その時彼の脳裏に、そんな言葉が唐突に浮かんだ。
- 立ちすくんだ彼に気付かずに、老女はそそくさと背を返してドアを閉めた。
- リクターの父親は、彼が生まれた年にヨーロッパで戦死していた。
- 母親も彼を生む時に亡くなっていたので、リクターは両親の顔をまったく知らなかった。
- 彼は広大な館に、彼を育てた老女とふたりきりで住んでいた。
- おばあさん、と呼んではいたが、老女はリクターの祖母ではなく、父の遠縁にあたる女性であると彼は聞いていた。
- 老女は、リクターに厳しかった。
- 甘えさせるどころか、彼を長い時間身近に置くことすら好んでいなかった。
- リクターは、老女からも、老女のかたくなさから短い期間で変わるわずかな人数の使用人からも、愛情と名付けられるものは一切与えられないで育った。
- 知人も、一族の最後の一人である彼には親類もいなかったので、彼はその幼年時代を、館の中でたった一人で過ごした。
- ロサンゼルス郊外に建てられた古い館は、回りの陽気な風物にまったくそぐわない建物だった。
- リクターの一族が、東ヨーロッパで代々暮らしていた城を小規模に模したという館で、一切の明るさを傲然と拒んでそびえていた。
- この館は、古い時間をそのまま満たしている容器だった。
- 館の一部は、妙な造りになっている。
- 使い道のない地下室やからっぽの塔が、一見でたらめに配置されていた。
- 開けてみると石壁が立ち塞がっている大きなドアや、どこにもつながっていない通路などもあった。
- なかでも一番不思議なのは、館の中央に突き出ている丸屋根の塔だった。
- そのドーム状の部分には相当のスペースがあると思われるのに、館のどこからも登れないのだ。
- 下から見上げると、凝ったステンドグラスがドームを取り巻き、その上には鎧戸がついている。
- しかし、その内側がどうなっているのかは、誰も知らない。
- リクターは一度だけ老女にこのことを聞いてみたのだが、めずらしく機嫌の良かった彼女は、笑いながら首を振った。
- 「お城にあったのだよ」
- 「……」
- 「お城に。
- 素晴らしいお城だったそうだよ。
- 大きく、すべての者の上にそびえていた。
- その天辺にあの塔があった。
- あの塔は、ご領主様の座だ」
- 「ご領主様の座?」
- 「そうだ。
- ご領主様だけしか、登ることのできない塔だ。
- お城にも、塔に通じる階段や通路はひとつもなかったのだそうだ」
- 「それじゃ、領主は、どうやって塔に登ったの?」
- 老女はまた首を振った。
- 「ご領主様は、そんなものを必要ではなかった」
- 「どうして?
- 領主は空が飛べたの?」
- 「ご領主様は……」
- 老女はリクターの顔をまじまじと見て、ふと眉をひそめた。
- リクターは、老女のしわだらけの顔に埋めこまれた暗い瞳に、いつものおののきが浮かぶのを見て、続きを聞くのをあきらめた。
- しかし老女は彼の予想に反して、小声ではあったが言葉を続けた。
- 「何でも、おできになったのだ。
- ご領主様はとても強い力をお持ちだった。
- だからリクター、お前も……」
- 言葉を切った老女を、リクターは目を丸くして見つめた。
- 「僕も?
- 僕も強い力が持てるの?」
- 老女は、今度は本当に身を引いた。
- 「昔の話さ!!」
- 彼は夢を見た。
- 館の中を、必死に逃げている夢である。
- 追ってくるのは、姿の見えない『ご領主様』だった。
- もし掴まったら、恐ろしい目に会わされる。
- よく知っている廊下を、足をもつれさせながら走り、階段を駆け登り、ドアを引き開ける……
- と、何もないはずの石壁の部屋に、先回りした『ご領主様』が待ち構えているのだ!
- 彼は、悲鳴を上げて目を覚ました。
- が、その悲鳴を聞きつけて来てくれる人は誰もいない。
- 老女も、使用人も、離れた部屋を使っているのだ。
- 彼はぐっしょりと汗をかきながら、一晩中ベッドの中で震えている。
- この悪夢は、その後も繰り返し現れた。
- 時には、追いかけているのは彼の方だった。
- その夢では、逃げているのが誰だか、彼にはわからなかった。
- 夢を見ている彼は、自分がその誰かを掴まえてしまうのが怖かった。
- 掴まえて、何をするのかが恐ろしいのだ。
- しかし夢の中の自分は、冷酷な足取りで追いかけ続ける。
- 追いかけて、追いつめて……
- 夢を見ている彼が、耐えきれずに悲鳴をあげて飛び起きるまで
- ・・・。
- 学校に通うようになっても、リクターは孤独だった。
- 『化け物屋敷の優等生』というのが、彼に与えられた最初のアダ名だった。
- リクター自身、同年輩の子供とどうやって付き合っていいか、よくわからなかった。
- 彼は周囲には、生真面目でおとなしい子供として成長していった。
- しかし、彼の中にはいつも闇があった。
- リクターが意識していたのは、奇妙な疼きだった。
- のどの乾きにも似たその感覚は、いつも唐突に彼を襲った。
- 暗い、押しつぶされるような不安の中で、彼は何かを求めて喘ぐのだが、何を求めているのかはまるでわからなかった。
- 彼はそれを老女にはもちろん、誰に話すこともできなかった。
- 成長するにつれ彼は、その感覚に否応なしに慣れていった。
- そしていつの日か、その原因を突きとめ、消し去ってやろうと思い始めた。
- 帰宅すると彼はよく、父と母の部屋で過ごした。
- といっても、すっかりと片付けられて、人が住んだ気配のまるでないその部屋には、父や母の香りなど残ってはいなかった。
- 彼はただなんとなく、その部屋にひかれていたのだ。
- 薄いほこりの積もった家具の中で、彼は本を読んだり置物をいじったりして、何時間でも過ごすのだった。
- 部屋は広い続き部屋で、寝室と本棚の置かれた書斎に別れている。
- 手前の寝室には天葢のかかったベッドと大きな暖炉がある。
- ここにも、館の奇妙さと呼応するようなわけのわからない物があった。
- ベッドの脇に背の高い戸棚があって、その前に4つの円盤をのせた丸い盆のようなものが置かれているのだ。
- 円盤には、
- ウマ、
- トリ、
- ウサギ、
- シカが描かれている。
- 彼は盆を回してみようとしたが、ぴくりとも動かなかった。
- 円盤に手を当てたり、物を乗せたりもしてみたが、何も起きない。
- 結局彼は、ただの飾りだとあきらめた。
- 暖炉の上には、赤い服を着た少女の絵がかかっている。
- まだ幼かった時、リクターはこの少女の絵が怖かった。
- 部屋のどこにいても、いつも彼を見つめているようで、しかも目を離していると、背後でにやっと微笑んでいるような気がするのである。
- 大きくなってからもこの部屋にいる彼は、時折背中越しにこの絵を確かめる癖がついていた。
- 書斎の突き当たりにも扉があったが、中は円筒型の石壁があるだけで何も入ってはいない。
- 壁に、何かをつないでおくような錆びた金属片が埋め込まれている。
- 書斎の隅のチェストの中には、いろいろながらくたがあった。
- 古い書類やねじ式の樽の栓、クラシックな短銃まで入っている。
- リクターはその中から、いくつかのアクセサリーを見つけた。
- 血の滴のきらめきを宿した、ルビーの指輪がある。
- 青緑の光を妖しく放つ、玉虫のペンダントがある。
- リクターはそれらをもてあそびながら、父母のことを考える。
- わずかな枚数のうち1枚だけ、着色された写真が残っていた。
- 軍服を着て、口髭を蓄えた口元を厳しく結んだ父。
- その隣で、黄色い髪に包まれた白い面に、神経質そうな表情を浮かべている母。
- その瞳は、古い着色写真独特の、人工的な青に染められている。
- 豊かな胴着の胸元に飾られているのは、あの玉虫のペンダントだ。
- 写真家はどういうわけか、このペンダントを赤紫に色付けている。
- リクターは、父や母の話をあまり聞かされてはいなかった。
- 両親がいてくれたらと思わないではなかったが、一家が揃った生活は、彼の想像の外にあった。
- 父母の写真に見入っていると、あの疼きに似たものが起きる時があった。
- しかしこれは、失った家族への当然の想いだと、彼は考えていた。
- リクターが、老女に大学進学の希望を話したのは、もうそれが決定した後だった。
- 「……医学部はいいのだけれど、どうしてお前は……」
- 「そうですね、ちょっと遠い」
- 彼はゆったりと引き取った。
- 遠いどころか、彼が選んだ学校は、ニューハンプシャー州の片田舎にあった。
- 「ロスにも学校はたくさんありますが、僕はずっとこの家で過ごしてきましたから、この際ひとり立ちしてみたいんです。
- いつまでも、おばあ様に面倒をかけるわけにもいきません」
- この館から出たいのだ、と彼は心の中で付け加えた。
- できるだけ遠くに、離れたいのだ。
- 僕の心の闇を、僕自身が治療するために。
- ここにいたのでは、闇は深くなるばかりなのだ。
- 老女は、リクターを思い止まらせようとはしなかった。
- そればかりか、まるで気が変わるのを恐れるように口早に言った。
- 「そうね、それがいいわ。
- お前は財産もあるし、これから何でもできるだろう。
- 好きなようにおし」
- リクターは、アメリカを横断してカレッジに入学した。
- 片田舎にあるとはいえ、ごく最近作られたその医学校は、新しい設備と理論を積極的に取り入れ、アメリカ中から優秀な学生を集めていた。
- リクターは見慣れないニューイングランド風の町で、初めての解放感を楽しんでいた。
- 幾人かの友人もでき、勉強も面白かった。
- 精神科とともに、外科にも興味が出てきた。
- 心の闇を意識することは、ごくまれになっていた。
- [CHAPTER 04]
- 「リクター・ハリス、我ら同期の誇りよ!」
- 大きな手に肩を叩かれて、リクターはあわててコーヒーの紙コップをテーブルに下ろした。
- ラルフはかまわずに大声で続ける。
- 「ホブソン親父のセリフは、我がライト記念大学の歴史に永遠に残るであろう」
- リクターは、微かな笑いを浮かべてつぶやいた。
- 「教授は、何も言わなかったよ。
- 終わった時、よし、と言われただけだ」
- 「おお、それこそ名セリフ!」
- ラルフ・クレインの背後から、やはりクラスメイトでラルフのステディ、ジャネット・マックブライトが日に焼けた顔をのぞかせた。
- 「全グループのテストが終わった時点でね、ホブソン教授に何の文句もつけられなかったのは、あなただけだったのよ」
- リクターはジャネットを見て、軽く腰を上げた。
- 二人はくすくす笑いながら、彼のテーブルに座る。
- 女性に対するリクターの礼儀正しさは、仲間内では好意あるからかいの種なのだ。
- 「文句?
- ありゃ、そんなものじゃないよ。
- 俺に与えられた教授のセリフの、ほんのダイジェストをお聞かせしよう。
- 何という不器用さだ。
- これはもう、技術以前の問題だ。
- 気の毒に、君はまだホモ・サピエンスにまで進化していないに違いない。
- ちゃんと進化したら、もう一度テストをしてやろう……。
- あの犬が全身麻酔されていてよかったよ。
- 局部麻酔だったら、途中で逃げるか、俺に噛みついていたな」
- 「あたしのも、教えてあげるわよ」
- ジャネットは、真っ赤な髪をかきあげながらコークのカップを置いた。
- 「ミシンを持ってきてやろうか?
- ですって。
- こっちが必死に縫合糸を結んでる最中によ」
- 「ああ、持ってきてもらえばよかったな。
- ジャンの縫合はなかなか芸術的だから」
- 「なによ!」
- ジャネットは口を尖らせて、ラルフに小さな拳を振り上げた。
- ラルフはきゃあ、と黄色い声をあげ、リクターは心おきなく笑った。
- カレッジのティールームはすいていた。
- 授業に遅れた下級生が、今まで開いていた本を閉じてあわてて出て行く。
- 彼等は学部最上級生の余裕で、それを見送った。
- 「やれやれ、外科は再試験だ。
- ミシンは合格線だよ、ジャン。
- 術式はうまくいったんだろう?」
- 「3度の舌打ちを招いたことを除いて、ね」
- 「ホブソンの外科実技は、歴代半分の合格率だそうだからな。
- リクター、君はやっぱり外科に行くんだろ」
- 彼は小さく首をかしげ、黙ったままコーヒーを啜る。
- ラルフとジャネットは、顔を見合わせた。
- ジャネットが叫ぶ。
- 「いやだ、迷わないでよ、リクター。
- あたしだって、外科に行きたいのよ。
- クラス最高のメスを持ったあなたが外科に行かなかったら、あたしを始め他の外科医志望のぶきっちょたちは、立つ瀬がないわ」
- 「そうだよな」
- ラルフは、ジャネットのコークを遠慮なしに飲んだ。
- 「リクター、俺も君のメスは抜群だと思うよ。
- どんなに複雑な術式も、いとも簡単にやってのけるんだものな。
- 教授連だってわかってるさ。
- 脳外科だろうが心臓だろうが、どこの教室でもウェルカムだよ。
- 最も、病理って手もあるかな。
- 君のメスも、宝の持ち腐れにならずに済む」
- たしかに、小さい鋭い刃物は、最初からリクタの手にしっくりと納まった。
- 彼はそれを、自由に操ることができた。
- 誰でも初めは尻込みし、そのために手を誤る者の多い解剖実習も、リクターはすらすらとやってのけた。
- 教授たちも、彼を高く評価していた。
- リクターは曖昧に笑ったまま、二人の顔を見た。
- 「僕も臨床志望だから、病理はないだろうね。
- ただ、僕は元々、精神科志望なんだよ」
- 「あーらら……」
- ジャネットは肩をすくめてみせた。
- 「そりゃ、アメリカで最も儲かる医者は、精神科医よ。
- 道具もなにもいらない、ベッドひとつで即開業。
- 急患もなく、医療過誤の裁判にも縁がない。
- でもねえ……」
- カフェテラスの天井にすえられたスピーカーが、雑音混じりのチャイムを響かせた。
- 漂っていた話し声が、一瞬とぎれる。
- 『第6学年のリクター・ハリス。
- 至急学生事務室に連絡をとること。
- 第6学年のリクター・ハリス……』
- 自分たちに関係がないと知って再開されたざわめきの中で、リクターと友人ふたりは驚きの表情を見合わせた。
- 学生に対してこういう形の呼び出しがあるのは、ごくまれだった。
- 「……何かしら」
- 不安そうにつぶやいたジャネットにつられるように、ラルフもリクターを見た。
- リクターは軽く首をふって、立ち上がった。
- 「外科の落第が決まったのかも知れないな。
- それじゃ、失礼」
- 事務室を訪ねたリクターに、年配の秘書が妙に暗い声で言った。
- 「リクター・ハリス?
- 学生部長がお会いになるそうよ」
- リクターは、いぶかしげに秘書の顔を見た。
- 学生部長のラッセン教授は、消化器学の授業でよく知っている。
- しかし授業や試験のことなら、教授室に呼び出すはずだ。
- 学生部長としての教授が、直接彼に何の用があるのか、リクターにはさっぱり見当がつかなかった。
- 何か、悪いことでも言い渡されるのだろうか。
- 彼は秘書にうながされるままに、部長室のドアを開けた。
- 「やあ、リクター」
- 教授はデスクに座っていたが、彼を見て立ち上がった。
- 彼はそれにも驚いた。
- 普段の教授は、一学生に対してわざわざ席を立つタイプではないのだ。
- 教授は、やわらかな口調でソファを示した。
- 「まあ、座りたまえ」
- リクターはますます戸惑いながら、ソファに腰を下ろす。
- 教授はデスクの上から紙片を取ると、彼の正面に座った。
- 指を組み、低い声で話し始める。
- 「君に、こんなことを知らせる役目は本意ではないのだがね。
- 実は、さっきロスから電話が入ったんだ。
- 君のおばあ様が昨夜、病気で亡くなられたそうだ」
- リクターは教授の態度を、一度に了解した。
- 「心から、お悔やみ申し上げる。
- 君には、ご両親もいらっしゃらなかったね。
- お身内の最後の一人だったとか……。
- 何か、飲み物でもあげようか。
- コーヒーか何か……」
- あの老女が死んだのか、とリクターは考えていた。
- 自分を育ててくれたには違いないが、心の交流らしきものは、一切なかった。
- カレッジに進むために館を出る彼に対して、老女は明らかな安堵の色を浮かべていた。
- やっかいばらいなどというものではない、もっと切実な……
- まるで、ひどく危険な任務からやっと解放されたとでもいいたげだった彼女の表情を、リクターは思い出していた。
- 彼はそれきり、館には帰っていなかった。
- 学校の休暇は、アパートか小さな旅で過ごしていたのだ。
- 彼には、老女とは別の信託が用意されていたので経済的な必要もなかったし、何より老女が、彼の帰省を望んでいるとは思えなかったからである。
- 館と老女は、彼にとってあまりに遠いものになってしまっていた。
- 懐かしいとすら、思ったことがなかったのだ。
- 今の彼にとって老女の訃報は、赤の他人の死を聞くのとほとんど同じだった。
- 教授はドアの所へ行き、秘書にコーヒーを言いつけている。
- 返した視線に同情があふれているのに気付き、リクターは密かにおかしくなった。
- 黙って座っている彼が、愛する祖母を失って落胆していると勘違いしているのだ。
- しかし、彼はその誤解を解こうとはしなかった。
- 祖母ではないのだとも言わなかった。
- そんな必要はなかったし、説明の仕様もまた、なかったのである。
- リクターはただ、教授に軽く頭を下げた。
- 「ありがとうございます、先生。
- いろいろお気遣いいただきまして……」
- 「なに、当然だよ」
- 教授はソファに戻ると、紙片を彼の方に滑らせた。
- 「君はすぐ、帰らなければならないね。
- 電話をしてきたのは、おばあ様の銀
- 行の人だった。
- いろいろと君に……
- その、用があるようだった。
- 電話番号を聞いておいたよ」
- 「彼女の縁者は、僕だけですから」
- 「うん、そうらしいね。
- 君もこれから、大変だろう」
- 「ええ、まあ……」
- 教授は、温かい笑みを浮かべてリクターを見た。
- 「リクター、君は優秀な学生だ。
- 我々も、君にはおおいに期待しているのだ。
- 言うまでもないが、今学期は君たちの学年にとってとても重要な時期だ。
- 一日も早く、元気になって学校に戻ってきてほしい。
- 何か相談したいことがあったら、遠慮なく言ってくるんだよ」
- リクターは、まだ内心のおかしみを感じながら、それでも教授に感謝していた。
- 老女は、館の近くの墓地に埋葬された。
- 会葬者は彼と、彼が顔も知らない数人の使用人、そして電話をかけてきた銀行員だけという淋しさだった。
- 最初の土を落とすのは、彼の役目だった。
- 彼は歩み出て、穴の真上に手を伸ばした。
- 『おばあさん、何故あなたは、僕を愛してはくれなかったのですか?』
- ふいに、彼の意識の底から浮き上がってきたものがあった。
- 彼が、すっかりと忘れていたことだった。
- 『あなたは本当に、僕に殺されると思っていたのですか?』
- 彼は呆然とした。
- 無意識に掌を開き、さらさらと音をたてて、土が棺の上に落ちる。
- 思考は、彼におかまいなしに続いた。
- 『……それは、一体、どうしてだったんですか?』
- 心の中の問いが終わった時、それに答える底深い声が、リクターの頭の中に響き渡った。
- 『同じ血の流れている者の肉を食えば、力が得られるからだ』
- 立ちすくんでいるリクターを、会葬者は教授と同じ誤解をして見守った。
- 館は、相変わらず傲然とリクターを迎えた。
- 彼は、雑草の生い茂った前庭からドームを見上げて、溜め息をついた。
- 「ミスター・ハリス……
- もうすぐ、ドクターになるんだったね」
- 「リクターでけっこうですよ」
- 彼は銀行員を振り返った。
- 初老の銀行員は、自分の子供ほどの年齢のリクターを、どのように扱っていいかまだ迷っているようだった。
- 二人は扉を開けて、玄関ホールからダイニングに入った。
- シャンデリア、白布のかかったテーブル、置かれた銀の燭台も、リクターの記憶通りだった。
- ただ、すべてにうっすらとほこりが降りていた。
- 老女が入院して2週間、掃除を怠っていたものと思われる。
- ふたりは苦笑いで、椅子を払った。
- 「……さて、リクター。
- 私は君に会ったのは初めてだが、君の信託を管理していたのは、ずっと我が銀行だった。
- 知っているね」
- 「はい、もちろん」
- 「故ローズ・ハリスさんの信託も同様だ」
- リクターは、他人が老女の名を発音するのを、不思議な気持ちで聞いた。
- 「この信託も、君が相続する。
- 館は元々君のものなのだが、ローズさんが管理者に指定されていた。
- これも君の管理に入る。
- 君は、かなりの財産家だと言えるだろう。
- 税金や詳しい数字は、書類で渡そう」
- リクターはうなずいた。
- それは最初から、わかっていた。
- 「君は学業が途中だ。
- 君がこの館に帰ってくるまで、館の管理をする者が必要だろう。
- 我々が手配してあげるよ。
- 普段の掃除までは手が回らないかも知れないが、必要な修理や防犯はまかせておけるよ。
- ずいぶんと年代ものなのだね、この館は。
- まったく、大したものだよ」
- リクターは、ひとつ大きく息をついた。
- この時のことは、前々から考えていたのだ。
- 「この館は、処分しようと思っています」
- 「なんだって!?」
- 銀行員は驚きのあまり、腰まで浮かせる。
- リクターは、館中が聞き耳をたてているようだと思いながらも、断固として言葉を続けた。
- 「土地はこのままでもいいのですけれども、建物は全部、壊してしまうつもりなのです」
- 「き……
- 君は、何を言っているんだ。
- こんなに美しい館を……
- 君は、ここで育ったんだろう?
- お父上、お母上、お祖母様のローズさん……
- 君の思い出は、すべてここにあるはずだ……」
- リクターは眉を寄せ、また溜め息をついた。
- この銀行員が、細かい事情や館の内部についてよく知らないのは明らかな上、彼の思いを完全に説明するのは、難しかった。
- かわりに、彼は相手に聞いてみた。
- 「美しいって、本当にそう思われますか?」
- 銀行員は、ちょっと口ごもってから答えた。
- 「そう……
- 美しいじゃないか。
- 古くて……
- えもいわれない味があると、私は思うが……」
- 「僕は、この古い家が嫌いなんです。
- 思い出と言っても、僕は父も母も知りませんし、祖母は……」
- リクターは言葉を切って、肩をすくめて見せた。
- 銀行員は、しばらく黙って彼を見ていたが、やがて溜め息混じりにつぶやいた。
- 「まあ、君はまだ若いのだから……
- ゆっくり、考えてみたまえ。
- 古いものを壊すのは簡単だがね、これだけのものを作るのは、もう不可能だ」
- その古いものが嫌なのだ、とリクターは思った。
- 僕の心の中に、奇妙な闇がある。
- 幼い時から感じている胸の疼き、さっきも聞いた変な声……
- これらは、どこかでこの館とつながっているのだ。
- 精神分析を受ける気はなかったが、自分で熱心に勉強した結果、彼はそういう診断を下していた。
- 何の意味もない、妄想なのだ、と彼は考えていた。
- 僕は父母もなく、育ての親の老女には愛されなかった。
- 老女のふるまいは、彼を愛さなかった彼女の罪悪感によるものだろう。
- 僕はといえば、そういった細かい出来事がコンプレックスを生み、トラウマ(精神の傷)となっている。
- さっきのばかげた頭の中の受け答えなど、まったくいい症例じゃないか。
- そして、その象徴がこの館なのだ。
- 老女が亡くなった今、この館を消し去ってしまえば、僕の心の闇も消えるだろう。
- この銀行員にはわかるまい、とリクターは思った。
- いや、学校の教授、クラスメイト、誰にもわからないだろう。
- 彼がこの館を、どれほど夢に見ていたか。
- 悪夢として。
- しかしリクターは、この場はただ、笑ってうなずいておいた。
- 学部を卒業し医師の資格を得るのと同時に、彼は銀行に、館の取り壊しを決めたと伝えた。
- 例の銀行員は、もう何も言わなかった。
- リクターは再び長い旅をして館に戻ると、父母の写真を始めわずかな物品だけを持ち出し、わけのわからないものは、すべてそのままにしておいた。
- 父母の寝室を出る時、リクターはあの赤い服の少女ににやっと笑って見せた。
- 「ずいぶん脅かしてくれたけど、もうこれでお別れだ」
- きびすを返した彼は、後ろを振り向かなかった。
- ドームの下がどうなっていたのか、取り壊しをした業者に聞こうと思えば聞けたのだが、彼はもう、それすらどうでもよかった。
- 「……そう、家具も処分してください。
- ええ、価値のあるアンティークであることは承知しています。
- しかるべき業者が引き取るでしょう。
- 絵画も、食器も……
- ええ、僕は全部、いりません」
- そして、すべてのものが取り払われ、土地が更地になったと連絡を受けた夜、リクターは手足のかせが外されたように感じた。
- 館はもう、この世には存在していない。
- 遠くヨーロッパにあったという、館のモデルとなった城も、きっととうに歴史の彼方に消え去っていることだろう。
- 僕の闇も、消え去ったはずだ。
- 彼は、生まれて初めて、安心して眠りについた。
- 質素なアパートの小さな机の片隅に、リクターが館から持ち出したものが収められていた。
- 写真の上に置かれた玉虫のペンダントが、どこからともない光を受けて、鈍く輝いていた。
- リクター・ハリスは、レジデントとしても極めて優秀な成績を示し、大学病院の心臓外科に医局員として採用された。
- 精神科の研究は続けるにしても、彼は自分の問題がもう解決したと信じていた。
- 彼はもう、メスの開く世界の方に興味を引かれていた。
- 彼の心の声は、すっかりと消えていた。
- 胸の疼きの方は、どういうわけか彼が患者に執刀する折に、時々蘇った。
- メスが皮膚にくいこみ、鮮血に染まった内臓が現れる時、彼ののどに小さな固まりが上がってくる。
- 彼はそれを、飲み込んで無視した。
- 僕は、実は血に弱いのかも知れないな、とリクターは苦笑いで考えた。
- 教授やスタッフには、とても信じられないかもしれないけれど。
- あの疼きは、館とは関係のないコンプレックスによるものらしい。
- やれやれ、これは誤診だったな。
- と言ってもこの現象は、外科医として障害になるほどではなかった。
- 奇妙なことに、この疼きが現れた場合の方が、メスが滑らかに進むのである。
- 彼は、診断と治療がうまくいった時の医師が感じる満足感を、自分という患者に対して感じていた。
- [CHAPTER 05]
- リクター・ハリスの名は、新進外科医としてアメリカ医学界で知られ始めていた。
- 手術室の彼は極めて大胆なメスさばきで、スタッフと患者の驚嘆と信頼を得た。
- 学会でも精力的に発表を行い、毎回高い評価を受けた。
- 気がつくと、彼は『成功者』の階段を順調に登っていたのだ。
- カリフォルニア大学からの招きを受けた時、リクターは少し迷った。
- しかし、彼のキャリアにとってはこれは大きなチャンスだった。
- 何より、ロサンゼルスにはもう、あの館はない。
- 彼は、十数年ぶりに故郷に居を構えることにした。
- 彼は、大学の近くにアパートメントを借りた。
- スペイン風の白いテラコッタと、色とりどりのタイルに飾られたバルコニー。
- プールの脇には、アボガドとシュロが涼しげな影を落としている。
- 開け放した窓から、微かにピアノの音が聞こえてくる。
- クール・ジャズ。
- これがロサンゼルスだ、とリクターは思った。
- 私は、初めてこの町を知ったのだ。
- リクターは、産婦人科主任のレイ・ロビンソンの家へ向かって、車を走らせていた。
- ブリッジ・パーティーに招かれたのだ。
- 途中で、臨床検査技師のマリアン・セレスをひろうことになっている。
- 彼は窓を開けて、やや冷たい風に腕をさらしていた。
- どこの花壇にも満開のゴールデンポピーが、黄金の花冠を揺らせている。
- らしくないとは思いながらも、リクターは小さく口笛を吹いていた。
- ロビンソンは病院の若手スタッフのボス的な男で、最初からリクターの世話を買って出てくれていた。
- 育ちのせいでどちらかといえば堅苦しい雰囲気を持っていたリクターが、西海岸風のラフな付き合いにすんなり溶け込めたのは、彼のおかげだと言ってもよかった。
- 今日、マリアンを迎えに行けと言ったのも、彼である。
- リクターは、昨日それを彼女に告げた時のことを思い出して、苦笑した。
- 「要するに、レイは私たちをくっつけようとしているの」
- マリアン・セレスは秘密を打ち明ける口調で、リクターにささやいた。
- 「もう、おせっかいなんだから。
- 大体、レイが、というより、奥方の方針よ。
- 彼女、病院の社交界を牛耳るつもりなのよ。
- 有能そうな若手と見ると、病院内の手駒の中から選んでくっつけるの。
- そうすれば、夫婦そろって彼女の思いどおりになるってわけ」
- リクターは、眉をあげた。
- 「そりゃ、君には気の毒だったね。
- そんな陰謀に巻き込まれて、しかも、相手が私では…」
- 「あらあ、そういう意味じゃあないのよ!」
- マリアンは、褐色の瞳をおおげさに開いてみせた。
- 「陰謀なんて、そんな大仰なものではないのよ。
- 多少の野心はあるんでしょうけど、彼女は基本的には、単なるおせっかいなのよ。
- それに、リクター、あなたが迷惑なんじゃないの。
- 私には、ステディがいるのよ。
- 今はビジネスで、ニューヨークの方に行っていますけどね。
- 公にしていないだけ。
- デートぐらいなら、いつでも付き合うわよ」
- 笑ってうなずいた彼に、マリアンはふいに身を乗り出すように聞いた。
- 「ねえ、リクター。
- あなた、東に誰か、いい娘でも置いてきているの?」
- 「えっ!?」
- 「あなた、けっこう人気があるのに、誰かとデートしたって噂も聞かないし。
- そろそろ白状しないと、又ロビンソン夫人が陰謀を巡らすわよ」
- 「残念ながら、そういうことはないね」
- 「本当に?
- だったら、立候補する娘を何人か知ってるわよ。
- 看護婦にも、患者にも…」
- 「まあ、お手やわらかに頼むよ。
- 女性にはかなり臆病なんでね」
- マリアンは、明るい笑い声をたて
- た。
- 女性の笑い声というのはいいものだ、とリクターは考えていた。
- 私の少年時代には、一度も耳にしなかった。
- マリアン・セレスに特別な感情はなかったので、別に残念ではなかったのだが、彼はその声を好もしいとは思っていた。
- 彼はハンドルを操りながら、一人肩をすくめた。
- おやおや、これまた、トラウマか。
- ロビンソン夫人に申し込み書でも出して、早いところ結婚した方がいいのかも。
- と言っても、何だかぴんとこない。
- 家庭というものと自分とは、一度も結びついていないのだから。
- 突然、フロントグラスに閃光が爆発した。
- リクターは、あわててブレーキを踏んだ。
- それほどスピードが出ていなかったが幸だった。
- 車はさほどコントロールを失わずに、右側に寄って停止した。
- リクターはハンドルを握り締めたまま、太い息をついた。
- こわばった指をようやくはずし、アドレナリンの刺激でまだ微かに震えている手で、ドアを開ける。
- 歩道に降り立ち、回りを見回した。
- 「なんだったんだ、いったい……」
- そこは、人通りのない住宅地の道だった。
- 小綺麗な家が並び、街路樹がそよいでいる。
- 閃光の原因になるようなものは、どこにもなかった。
- 州花のゴールデンポピーが、ここにも季節の香りを撒き散らしているだけである。
- 錯覚?
- あの光が?
- リクターは車に寄りかかったまま、もう一度深呼吸をした。
- 何がなんだか、さっぱりわからない。
- しかし、事故を起こさないでよかった。
- とにかく
- ・・・。
- 首をかしげながらも、再び車に乗り込もうとした彼の目に、きらりと光るものが飛び込んできた。
- ポピーの植え込みの中に、何かがある。
- その花の金色と、まごうばかりの輝きを放つものが……。
- 彼は、植え込みに歩み寄った。
- それは、一人の女性だった。
- 白いガウンのようなものを纏い、黄金の髪を伏せて、彼女は倒れている。
- リクターは、走り寄って叫んだ。
- 「君!
- だ…
- だいじょうぶか!」
- 一呼吸の後、彼女はゆるやかに身を起こした。
- ほの白い面に、ぼんやりとした表情を浮かべて、彼女はリクターを見た。
- 彼は、息を飲んだ。
- まるで、光に縁取られた宝石のようだった。
- 季節が異なる花の、あえかな色をとどめた唇。
- 陶器の肌にくっきりとした眉が弧を描き、その下に見開かれた瞳は、サファイアの深い輝きをたたえている。
- 花の、妖精?
- まさか!
- そんなバカなことが、現実に起こるわけがない!
- 立ちすくんだリクターの前で、彼女は小さな吐息をつくと、再び崩れるようにその身を花の上に横たえた。
- 彼はようやく我に帰ると、彼女に駆け寄った。
- 肩にかけた手に、温かい確かな手触りがする。
- 彼は我知らず安堵した。
- これは、人間だ。
- 「おい!
- どうしたんだ、しっかりしろ!」
- 抱き起こした彼女は、意識を失っていた。
- リクターは、まだ夢の中にでもいるような気分で、腕の中の女性を見つめていた。
- 「リクター。
- おい、ドクター・ハリス!」
- 医局でぼんやりしていた彼は、レイ・ロビンソンの声に振り向いた。
- 「
- ……
- ああ、レイ」
- 「聞いたぞ。
- 君の運び込んだレディのこと」
- レイは、ベンダーの紙コップを持ったまま座りこむ。
- 「行き倒れを拾ったなんて聞いたから、またどうしたのかと思ったら」
- 「すまなかった、パーティーを失礼してしまって」
- 「それはいいって。
- それより、彼女、記憶喪失だって?
- また、とんでもないものを拾ったな」
- リクターは、肩をすくめて見せた。
- 「ああ。
- 衰弱してはいるようだったが、外傷も何もなかったから、意識が戻れば帰る所があるだろうと思ったんだけれど。
- 精神科のバークが調べてくれているけれど、今までの記憶がまったくないんだそうだ」
- 「警察には、届けたんだろう」
- 「近所の聞き込みでも解らなかったし、行方不明者にも該当しなかったらしい。
- 事件に巻き込まれた形跡もないから、困っていたようだった。
- 一応続けて調べるらしいけれども、それほど熱心な様子じゃなかった」
- レイは彼に、探るようなまなざしを当てる。
- 「じゃ、どうするんだろうな」
- 「普通はYWCAかなんかが、身元引き受けをするらしいけれど……」
- 言いよどんだ彼に、レイはやっぱりというように少し眉をひそめた。
- 「さっき聞いてきたんだが、彼女の請求書を自分に回すように、経理に言ったそうだな。
- 君はまさか……」
- 黙って視線を返した彼に、レイは人が変わったような厳しい声音で言った。
- 「おい、忠告しとくぞ。
- 君はこの病院のホープなんだぜ。
- 妙なことで経歴に傷をつけるような真似は、止めておくんだな。
- いくら彼女がとんでもない美人だと言っても、どこの誰かも解らない女と関係を持ったら、後で何が起こるかわからないんだぞ。
- 彼女が、犯罪と関わっている可能性だってあり得るんだ」
- リクターは、堅い表情で聞いていた。
- レイの心配も、もっともだった。
- いくらなんでも、それぐらいは彼にもわかっているのだ。
- しかし
- ・・・。
- 意識を取り戻した彼女が、再びその瞳を開いた時、リクターは悟ったのだった。
- この女性は、彼のために生まれてきた女性なのだ。
- レイは、口を閉ざしたままの彼を眺めて、ぶつぶつとつぶやいた。
- 「
- ……
- 今は、何を言っても駄目か。
- 堅い奴ってのは、これだから困る」
- 彼の肩を軽く叩くと、レイは元通り気楽に立ち上がった。
- 「まあ、とにかく少し様子を見るんだな。
- ああ見えても、バークの腕はいいぜ。
- その内、記憶が戻るかも知れない。
- その時になって、泣くなよ。
- 3児の母だったってことも、あるんだぜ」
- リクターは、眩しげに彼女を見つめた。
- 「先生が、私のためにいろいろとお心を砕いてくださったとうかがいました」
- 枕に寄りかかった彼女は、いきいきとした美しさに輝いている。
- もう、妖精には見えない。
- そのかわりに、女王のように華麗な威厳すら漂わせている。
- 金の光にくるまれた顔が、彼を見つめて微笑んだ。
- 「本当に、ありがとうございます。
- 先生がいらっしゃらなかったら、どうなっていたかわかりません」
- 「気にしなくてもいいんですよ。
- 安心して、ゆっくり休んでください」
- 「それにしても、私は……」
- 彼女の瞳が、霞みがかかったように曇る。
- ふっさりとした睫を伏せた彼女を見て、リクターは小さな胸の痛みすら覚えた。
- 「どうして、こんなことになってしまったのかしら。
- 自分の名前も覚えていないなんて、情けなくって……」
- 彼はあわてて言った。
- 「心配しなくてもいいのです。
- 思いつめても、仕方がありません。
- 気を楽に持つようにした方が、いいはずです」
- 「バーク先生も、そうおっしゃっていましたが……」
- 「警察も、調べてくれています」
- 「何の手掛かりも、ないと言っていました。
- 先生もご存じのとおり、何も持っていなかったんです」
- 彼女は、力なく笑った。
- 「着ていた服も、何だか寝間着みたいなものだったって」
- 「
- ……
- そうでしたね」
- 「私、不安なんです。
- 私はこれから、どうなるんでしょう。
- いつまでもこんな状態が続いたら、私はいったい……」
- 彼女の表情に、またはかなげな影が落ちた。
- リクターは、思わず叫ぶように言った。
- 「心配することはありません。
- 仮にあなたが何も思い出さなくても、私があなたを守ります!」
- 彼女は、驚いて目をみはった。
- 真っ青な瞳に、潤んだ光が浮かぶ。
- リクターは、その中に吸い込まれるように感じていた。
- 回り中に沸き起こった善意と悪意の大声に、リクターは辛抱強い沈黙と強い意思で応えた。
- 彼女の身元引き受け人となり、退院後はアパートを借り、軽い事務仕事を見付けてやった。
- 時が経つにつれ、声はだんだんに小さくなっていった。
- 彼女の記憶は戻らず、警察の調査でも何もわからなかったのだが、彼女自身に接した人たちは皆、その人柄が信頼すべきものであるのに気付いた。
- 「彼女は、本当に素敵な人よ」
- 彼女とすっかり親しくなったマリアン・セレスは、病院中に言い回る役を自分から引き受けた。
- 「育ちもいいみたいだし、相当な教育を受けていることも確かよ。
- なくしているのは記憶だけで、性格はしっかりしてて明るいし、思いやりも深いし、女の私が見ても、ほれぼれしちゃう」
- マリアンは微笑し、少し声を低めて付け加える。
- 「それにね、彼女、本当にリクターを愛しているわ。
- リクターもよ。
- もう、お互いがいなければ生きていけないって感じ」
- レイ・ロビンソンは、呆れ返ったような溜め息で応じた。
- 「こうなると、仕方がないねえ。
- これはもう、記憶が戻らない方がいいのかも知れないな。
- ……ところで、彼女の名前を付けたんだってね」
- 「リクターが付けたのよ。
- ジェーン・ドウ(身元不明の女性につける仮名)じゃ、あんまりだもの。
- でもねえ……」
- マリアンは、首をかしげる。
- 「あれ、そんな変な名前なのか?」
- 「そういうわけじゃないけど……。
- レノーア・リーっていうのよ」
- 「なかなか綺麗な名前じゃないか」
- 「もう、医者なんて皆、文学には無知なのね。
- レノーアっていうのは、ポーの詩にあるのよ。
- 偶然彼女と同じ金髪だけれども、死んだ女性の名前なのよ。
- 不吉だわ」
- 「ふうん。
- それ、リクターに教えてやったのか?」
- 「ええ、リクターはびっくりしてたわ。
- ところが、彼女の方が気にいっちゃったから、いいんだって」
- 「へえ。
- 本人がいいって言っているんなら、いいんじゃないか?」
- 「まあ、ね。
- 今度、奥様に紹介するって。
- よろしくお引き回しのほど、お願いするわね」
- レイは笑い出した。
- 「まかせとけよ。
- うちの、リクターがお気に入りでさ。
- 今度の話には、なんてロマンチックなんでしょうって、叫んでいたからな。
- リクターの、粘り勝ちだな」
- マリアンも笑顔でうなずいた。
- レノーアが過去を失っていることを、リクターは密かに喜んでさえいた。
- 彼女は、純白な布だった。
- そのすべてが、彼への愛で染まっていったのだった。
- 時間が経つとともに、レノーアの過去が失われていることは、人々の脳裏から忘れ去られていった。
- 彼女はリクターを中心とした世界にしっかりと根を下ろし、その人柄で人々を魅了していった。
- レイ・ロビンソンは、マリアンに言った。
- 「考えてみれば、理想的な結婚相手かもなあ」
- 「あーら、ずいぶん方向が変わったのね」
- 「あんまり豊富な過去を持った女より、ずっとましさ。
- それに第一、親戚がいないじゃないか。
- 女房の親戚なんて、面倒の極みだぜ」
- リクターがプロポーズした時、レノーアはあの時と同じように目をみはった。
- その顔が歓喜に輝いた一瞬の後、彼女はふいに彼に背を向けた。
- 「レノーア……。
- 嫌なのかい?」
- おそるおそるつぶやいた彼に、啜り泣くような声が聞こえた。
- 「だって……
- 私は、記憶もない、何者なんだかもわからない、そんな女に、あなたのような立派なお医者様の奥様なんか、つとまるのかどうか……」
- 「そんなことは関係ない!」
- リクターは叫んだ。
- 「私は、最初に君を見た時から、確信したんだ。
- 君は、私の妻になる人だ。
- 記憶があろうと、なかろうと」
- 「本当に?」
- 彼女は、ゆっくりと振り返った。
- 涙に濡れた彼女の頬を、リクターはそっと両手に包んだ。
- リクターとレノーアは結婚した。
- リクターは館の跡地に、新しい家を建てた。
- 同じ場所とはいえ、前の館を思い出させる景観は、まったくなかった。
- 二人の希望を写したような、明るく落ち着いた家だった。
- 寝室の壁には、リクターが密かに描かせた、彼女の肖像画がかけられていた。
- 濃いローズピンクのセーターを着て小さな白い手を穏やかに重ね、正面を向いた顔には、小さく優しい笑みを浮かべている。
- 「まあ、リクター。
- なんて素敵なの!」
- 彼女は歓声を上げ、彼を振り返った。
- 「でもなんだか、恥ずかしいわ。
- 私、こんなに堂々とした女性じゃないのだもの。
- この絵はまるで、女王様みたいに見えるわ」
- 「君はこの家の女王様さ」
- リクターは笑って、ポケットから金の鎖を取り出した。
- あの、玉虫のペンダントだった。
- 「まあ、それは……」
- 「どうやら私の家に、代々伝わったものらしいのだがね。
- 古いものでまことに申しわけないのだけれど、ぜひ、君に着けて欲しいんだ」
- 「……うれしいわ」
- 彼は、差し延べた彼女の首に、ペンダントをかけてやった。
- 頭を振って髪を払った彼女の金髪の中で、玉虫が虹の色を放った。
- その時、彼の胸に強い疼きが沸き上がった。
- それは、新たに知った愛情の衝動ではなかった。
- 昔からリクターが、よく知っている感覚だった。
- 「リクター、どうしたの?」
- 抱擁するかわりに一瞬身を引いた彼を、レノーアは不審そうな顔を上げた。
- その表情に、彼は再び強い衝撃を受けた。
- ペンダントを下げたレノーアは、あの写真の母にそっくりに見えた。
- [CHAPTER 06]
- 自分の心にあの闇が帰って来たことを、リクターは認めなかった。
- あり得ない、と彼は考えていたのだ。
- 館は、もうない。
- 新しい家では、愛する妻との幸せな生活がいつまでも続くだろう。
- どうして、そんなことがある?
- しかし、彼の悪夢は蘇ってきた。
- あの館の悪夢だ。
- 彼はもう、追われる立場ではなかった。
- 噴水と、二つの石像のある庭を通り、玄関からシャンデリアの輝くダイニングルームへ。
- 鏡のかけられた廊下から、石の階段を上って暖炉のある部屋へ。
- 赤い服の少女が笑っている父母の部屋、どこまでも続く石組みの長い廊下、そしてどこからも登れないあのドーム……。
- もうとうに、この世から消え去ったあの館が、再び彼の前に現れる。
- 彼は、何者かを追いかけている。
- 曲がり角のたびに、追いかけられている者の姿が、わずかに目に入ってくる。
- 掴まえたら……
- 彼は、その者を、引き裂くのだ。
- 以前の夢には欠けていたそんな意識が、稲妻のように脳裏を走る。
- ただ殺すのではない、手足を引き裂いて、苦悶にうごめいているまだ生温かい肉に、存分に歯をたてるのだ。
- ……血だ。
- いつもはメスの下からほとばしり、薄いゴム手袋をもどかしく濡らす血。
- 今度は違う。
- 鋭いメスではなく、鈍く太い杭が、生きている人間におもうさま突き刺さるのだ。
- 血は流れ、あふれ、いっぱいに満たす。
- 彼を。
- 追われる者の姿は、まだはっきりとは見えない。
- ただ、後ろになびいている、金の髪が……。
- 悲鳴を上げるのだけは何とかまぬがれて、彼は目覚める。
- 汗に濡れた頭を回すと、枕に半ば埋めた、レノーアの寝顔が見える。
- 彼は、心からの恐怖に震えた。
- リクターには、忙しい日々が待っていた。
- 手術室と、学会と、高名な人々が集まった華やかなパーティーとが、彼のスケジュールを満たした。
- 彼の名声は、確固としたものになっていった。
- 回りの人々は、仕事の成功と幸せな家庭を共に手にした彼に、賞賛と羨望の声を浴びせた。
- レノーアは優しく、従順な妻だった。
- 彼女の記憶が失われていることは、何の問題にもならなかった。
- 広い新しい家の中で、彼女が彼のためにこまごまと動いているのを見ていると、愛しさが津波のように寄せてくる。
- 手を伸ばせば、彼女は喜びの笑みとともに、彼の腕に飛び込んでくる。
- それなのに時として、思わず抱きしめようとする腕を、彼は自ら止めなければならないと感じるのだ。
- レノーアの柔らかい体を抱き、絹の滑らかさで絡み付いてくる金の髪に唇を埋める時、愛しさとはかけ離れた欲望が、彼ののどを締め付けてくる。
- リクターは、愕然とする。
- 私は一体、何がしたいのだ。
- あの、悪夢……?
- なんてバカなことを!
- 抱擁の途中で体を強張らせる彼に、レノーアは驚いて尋ねる。
- 「……どうなさったの、あなた」
- リクターは口ごもる。
- 答えようがないのだ。
- 黙って目をそらす彼を見て、レノーアは悲しげに身を引く。
- 彼も悲しかった。
- 彼女を愛しているからだ、と答えたかった。
- しかし彼はあの悪夢のことを、彼女には話せないでいた。
- その示唆するところが、あまりにもバカげていたからだ。
- そうは思っても、リクターはもう、心のままにレノーアを抱きしめることができなくなっていた。
- いつあの悪夢の中の欲望が、彼を絡め取るかわからなかった。
- その欲望には、彼を苦しめるほどの邪悪さが潜んでいたのだ。
- レノーアには、彼のためらいを理解できなかった。
- 彼女の過去がいまさら二人の溝にならない以上、彼女には夫の愛が薄れてきた証しだとしか思えない。
- しかし、だからと言って、自分に何ができるだろう。
- 彼女には、帰る所はなかった。
- 彼女の持っている短い歴史の中には、彼の腕の温もりだけが存在している。
- 彼女には、それに掴まっている他に術がない。
- それに何より、彼女は変わらずに彼を愛しているのだ。
- 側にいられるだけで、幸せなのだ。
- そう、考えることにしよう。
- 夫には、なるべく負担をかけないように……。
- レノーアは、次第に彼から距離を置くようになっていった。
- リクターの忙しさが、それに拍車をかけた。
- レノーアが離れていけばいくほど、リクターは仕事に打ち込む結果となった。
- 彼の胸の疼きは頻繁となり、彼のメスはますます冴え渡っていった。
- その夜、ドアを開けた彼女を見て、リクターは驚いた。
- いつものようにただ身を引いて彼を迎えるかわりに、レノーアは飛び立つように彼に抱きついたのだ。
- 戸惑っている彼を見上げて、彼女はくすくすと笑った。
- 「……いったい、どうしたんだい」
- レノーアはまた、笑い声をあげる。
- 頬が花びらの色に染まり、この頃は憂いばかりが漂っていた青い瞳に、明るいきらめきが踊っている。
- まるで、絢爛と花開いたゴールデンポピーの妖精のようだ。
- リクターの脳裏を、そんな意識が掠める。
- 彼女は爪先立って、彼の耳に囁いた。
- 「私、今日、病院に行ったの」
- 「えっ?」
- 「それでね、わかったの。
- リクター、来年には、あなたはパパになるのよ!」
- 彼は、時間が止まったように感じた。
- 歓喜に全身を輝かせた妻を腕の中に見ながら、彼は呆然と立っていた。
- 子供……?
- 私の子供。
- それは……
- レノーアの顔に、ふとおののきが走った。
- 「リクター、あなた……
- うれしく、ないの?」
- 「……うれしいに
- ……決まっているじゃないか!」
- 彼は叫んだ。
- レノーアを抱き上げ、安堵と喜びに顔をくちゃくちゃにしている彼女にキスを浴びせた。
- 彼の胸に沸き上がり、あふれだしているのは、レノーアに対する愛情だけだった。
- そこには、あの暗い衝動のかけらもなかった。
- リクターは、自分が彼女を傷つけることなど、金輪際ないと思った。
- レノーアは、彼の子供を生むのだ。
- この運命の女性は、まさに彼のために生まれてきてくれたのだ。
- 悪夢など、どこかに消えてしまえ!
- その通りだった。
- 悪夢も、疼きも、まるで最初から何もなかったように消えた。
- 終いには、ただの妄想だったのかもしれない、とリクターは考えた。
- 環境の変化、仕事の疲れ、理由なんて、いくつでも付けられる。
- レノーアには気の毒なことをしてしまった、とリクターは心底思った。
- 彼女が彼の愛を信じられず、苦しんでいたのを彼は察していた。
- すべての原因は彼にあったのだ。
- もう、そんな想いをさせることはない。
- リクターは、今度こそ遠慮なく、彼女に愛を注いだ。
- 彼女は、ずっと光り輝いていた。
- レイ・ロビンソンは、リクターに立ち会いを勧めたが、彼はきっぱりと断った。
- 「まあ、産科の医者でも、半々だな。
- 絶対自分でやる奴と、絶対自分じゃやらない奴とだ。
- 心臓外科には、出番はないからね。
- へその緒ぐらい、切らせてやろうと思ったんだが」
- 結局、彼は病院中のスタッフに冷やかされながら、外来の人々と一緒に廊下で待っていた。
- 産声がここまで響くことなどあり得ないと知りながら、リクターは耳をそばだてている自分がおかしかった。
- やがてドアが開き、ロビンソン医師が首をのぞかせて手招きした。
- 「おめでとう、パパ。
- 美人だよ」
- 手術着に飛んだ血の跡を見た時、リクターののどがひくっと鳴った。
- 看護婦に導かれ術後室に入って、やつれた、しかし誇らしげな笑顔を見せているレノーアの脇に寝かされた新生児を見つめる。
- まだ泣き声になっていない泣き声をあげている赤ん坊は、濡れた頭にわずかな髪をへばりつかせていた。
- その髪は、明らかに母譲りの金髪だった。
- [CHAPTER 07]
- 「……マリアン、私、あの人がよくわからないの。
- あの人の気持ちがどこにあるのか……
- 忙しいのはよくわかっているのだけれど、急に口をきかなくなったり、突然部屋を出て行ってしまったり……
- もう、私を愛していないのかと思うと、とても思いやりのある様子を見せてくれたり……
- ローラに対しても、同じなの。
- 目の中に入れても痛くないってほど溺愛してるのかと思えば、顔も見たくないような態度を取る時もあるの。
- ……私、もう、あの人とどういうふうに暮らしていけばいいのかが、わからない」
- マリアン・セレスは手を伸ばして、レノーアの手を握った。
- 「ねえ、そんなに考え込まない方がいいわ。
- あなたの考えているようなことでは、ないのかも知れないもの」
- レノーアはそれを振り払って、激しく首を振る。
- 「考えていることって、いったい何なの?
- あんな態度を取る理由なんて、私にはさっぱりわからないわ!」
- 「……リクターが浮気でもしているなんて考えているのだったら、多分間違っていると思うわ」
- レノーアは愕然として友人を見つめた。
- マリアンは椅子に寄りかかると、煙草を取り出して火をつける。
- 「確かに、ドクター・ハリスは忙しいわ。
- 多分、ロスで一番忙しい医者じゃないかしら。
- あの先生の腕のおかげで、助かった患者は数知れない。
- 新しい理論や方法なんかも積極的に取り入れるし、学会でも毎回ものすごい注目度よ。
- 彼のメスを頼って、アメリカ中の病院から患者が回されてくるわ」
- レノーアは微かな声で言う。
- 「おかげで、ほとんど家にいないわ」
- 「それが、普通じゃないの?」
- マリアンはあっさり言って、煙りを吹き上げた。
- 「流行っている医者なんて、そんなものよ。
- 開業医だったら自分でスケジュールが組めるけれど、彼は勤務医ですもの。
- もっとも心臓外科じゃ、開業は無理ね。
- ただの外科に替わるならまだしも、彼の腕がもったいないわ。
- そんなことは、彼、考えてもいないでしょう」
- 「今の仕事には、満足していると思うわ」
- 「あれは、天職よ。
- ……でも、レノーア、言っておくけど、彼は病院でも有名な愛妻家で通っているのよ。
- 浮気なんか、絶対していないと思うわ」
- レノーアは、悲しげにつぶやいた。
- 「浮気をしているなんて、言った覚えはないわ」
- マリアンは、ふと眉をしかめた。
- 「まさか、あなたの過去のことを、彼が何か言うとか……」
- 「違うわ!」
- レノーアは叫んだ。
- 「そんなこと、一度もないわ。
- 私も彼も、そんなこと忘れてしまっているくらいですもの。
- それは何の関係もないわ!」
- 「それじゃあ……」
- マリアンは身を乗り出して、厳しい声を出す。
- 「一体何が不満なの?
- アメリカ中から尊敬されている夫を持って、かわいい子供がいて、こんな素敵な家に住んでいて……。
- あなたは愛されていないなんて言うけれど、はたから見ればあなたほど幸せな人なんて、どこにもいないわ。
- 私たち、彼と仕事をしていて、ちょっとしたきっかけであなたやローラちゃんの話が出たりするでしょ。
- その時の彼の顔ったら、まるで溶けてしまいそうなのよ。
- こっちが、バカバカしくなってくるくらいよ。
- 仕事が終わった後に誘われても、3度に2度は断って、飛んで帰ってしまう。
- あなただって、知っているでしょう?」
- レノーアはただ、うなずいた。
- 「それでも、あまり家にいられないほど忙しいのよ。
- 少しくらい彼が冷たくったって、疲れているせいだって考えてあげられないの?」
- レノーアは深い吐息をついた。
- 彼女もせめて、そう考えようとしているのだった。
- 夫は仕事で、疲れているのだ。
- 人の命を預かり、神経を磨り減らす毎日。
- だから、妻や娘がうるさく感じる時があるのだ。
- それは、彼のせいではない。
- しかし、彼女の中で、それだけではないという思いが日に日に強くなっていた。
- 彼女の抱擁を避ける時、彼の目に走るのは、ある種の恐怖に思えた。
- ただうるさい、煩わしいというだけで、あんな表情をするだろうか。
- ローラを抱いてあやしていると、娘を見つめてとろけそうだった彼の目が、一瞬驚いたように見開かれる。
- すると彼は、突然ローラの体を放り出すようにベッドに置く。
- 激しく泣き出すローラにあわてて走り寄ると、彼はまるで憎んでいるような目で彼女をにらむ。
- まるで、背筋が寒くなるような憎悪の目で。
- 彼女の過去がこれに関わっているかもしれないと、考えないでもなかった。
- しかし、レノーアには不思議な確信があった。
- それとこれとは、無関係なのだ。
- 彼が憎んでいるようにみえるのは彼女自身であって、彼女の過去ではない。
- だから、つらいのだ。
- ただ、こう言ったところで解ってもらえまい。
- 彼女の気のせいだと言われれば、それまでなのである。
- 黙ってしまったレノーアに、マリアンはふと、すまなそうな笑みを浮かべた。
- 「……ごめんなさいね、ずいぶんきついことを言ったわ。
- でも、病院のスタッフの中には、ずいぶん遊んでいる人もいるのよ。
- 時々ひどい話も聞くしね。
- そんな連中に比べれば、我がリクター・ハリス先生なんか真面目一方。
- つまりね……」
- 彼女は、茶目っけのある笑いで続けた。
- 「彼氏は、理想の旦那様ナンバーワンだって思われているのよ。
- その妻たるあなたがそんな様子じゃ、私たち独身女性はどこに目標を置いていいかわからなくなるじゃないの」
- レノーアも、弱々しい笑みで答えた。
- と、微かな泣き声が聞こえた。
- 「あら……」
- レノーアは立上がり、足早に部屋を出た。
- マリアンは、あわてて煙草を揉み消す。
- レノーアは、ローラを抱いて戻ってきた。
- まだ眠そうな目に涙の跡を残したローラは、それでも顔見知りのマリアンに気がついた。
- 「ハーイ」
- 「ハーイ、ローラ。
- まあ、美人がだいなしよ。
- 涙はまだしも、鼻水はいただけないわ」
- 席について、ローラの顔をふいてやっているレノーアに、マリアンはふと真顔になって聞いた。
- 「お手伝いの人、やめてしまったの?」
- 「ええ、あの人は臨時だったのよ。
- ローラももう、あまり手がかからなくなったし」
- 「こんな広い家で、手伝ってくれる人がいないんじゃ、大変じゃないの」
- 「家の中に他人がいるのって、私が慣れられないの。
- 外回りはその時々に頼んでいるし、私は一日中家にいるのだから、何とかなっているわ」
- ローラはようやくきれいになって、2本の歯が生えた口でマリアンに笑いかけた。
- 「……まったく、あなたたちはそっくりね。
- 金髪に青い目の母子なんて、絵みたいだわ」
- 「でも、顔の輪郭なんかはリクター似だと思うわ」
- 「あら、そうかしら。
- やっぱりあなたに似ているんじゃない?」
- 「性格も多分、彼に似ているわね。
- 普段は静かなんだけれども、実は気が強いというか、頑固なところがあるのよ」
- 「けっこうじゃないの。
- これからの女は、そうでなくっちゃ。
- ね、ローラ?」
- ローラは、美しい子供だった。
- 彼女はまだほんの赤ん坊の内から、強い意思を主張を持っているようだった。
- 欲しいものがあると力強い声で泣き、満足すればごくおとなしく笑っている。
- 気紛れが当たり前の他の子供に比べ、きっぱりとした彼女の性格は、その顔付きや仕種にも現れていた。
- それがローラに、際立った特徴を与えており、彼女は会った大人たちをことごとく魅了した。
- レノーアは、ローラを育てることだけに自分の生活を注いだ。
- 病院での地位が上ったリクターはますます忙しくなり、家族と過ごす時間は前にも増して少なくなった。
- レノーアはそれを淋しく思うより、気が楽だと考えるようになっていた。
- 一緒にいる時間が少なくなればなるほど、夫の奇妙な態度に会うのもまれになる。
- 私にはローラがいる、とレノーアは思った。
- ローラはすくすくと育っていった。
- ほとんどすべての時間一緒にいる母にも、一日にほんの数十分しか顔を会わせない父にも、同じように甘え、なついた。
- 学校に上ると、その利発さで教師の賞賛を浴びた。
- 子供たちの中に入っても、いつの間にかその中心になるような子だった。
- 「本当に、素晴らしいお子さんです」
- 担任の教師は、目を細めてレノーアに笑いかけた。
- 「ああいうお子さんは、まっすぐに育っていただきたいですわ。
- 彼女の素質を損なわずに、どんどん伸ばして差し上げたいと思っています」
- レノーアは、うれしかった。
- リクターの態度は変わらないが、彼がローラを愛しているのは確かだった。
- そして、私もローラを愛している。
- この子は、二人の子供なのだ。
- この子を育てることは、二人の愛を育てているのと同じなのだ。
- 母に気付いて、腕に飛び込んで来たローラの柔らかい体を抱き締めて、レノーアは思った。
- やっぱり、私は彼を愛しているのだ。
- [CHAPTER 08]
- 「今日は、家で夕食が食べられると思う」
- ネクタイをしめながら、リクターは妻に言った。
- 「学会の連中は、今日の午前中の飛行機で帰る。
- 10日間、パーティー続きだったから、午後は回診だけにしてある」
- レノーアは、彼の上着にブラシをかけている。
- 今朝の彼は、機嫌がいいようだと思っていた。
- 「それはうれしいわ。
- あなたに、ローラが何か話したがっていたから。
- 昨晩も、あなたの帰りを待っていたのよ」
- 「すまなかった。
- まったく、ニューヨークの奴等ときたら、つぶれるまで飲まないと気がすまないんだ。
- つきあわされる身にも、なって欲しいよ」
- 彼女は爪先立って、笑っている彼の肩に上着をかけてやる。
- 「お嬢様はもう、お出かけかい?」
- 「ええ、なんだか、バンドの練習があるってずいぶん早く行ったわ」
- 「バンドって?」
- 「マーチングバンドの、笛の練習よ。
- 彼女の話は、多分それだと思うわ」
- 「ああ、直接聞くよ。
- 私が知っていると、ローラががっかりするからね」
- 玄関で、リクターはごく当たり前に、レノーアにキスした。
- 「……レノーア、この頃、あのペンダントをしないね」
- 胸元に目を落として、彼女は少し小さな声になって答えた。
- 「……そうね」
- 「まあ、いいよ。
- じゃ、行ってくる」
- 車を見送って、レノーアはゆっくり自室に戻った。
- ドレッサーの、高価なアクセサリー類に混じって、あの玉虫のペンダントが光っている。
- 彼の愛の証しだった、そのアクセサリー。
- これを着けなくなってから、どれだけの月日が経ってしまったのだろう。
- もしかして、彼との絆が切れたのは、それが原因だったのかもしれない。
- 私はどういうわけか、このペンダントがあまり好きではなかった。
- もらった時はうれしかったのだが、いつの間にかこれを身に着けることをためらうようになっていた。
- ローラが生まれてからは、一回も着けていないような気がする。
- いったい、何故なんだろう。
- 彼女は、そっとペンダントを取り上げた。
- ローズピンクのセーターの上から、首にかける。
- リクターがプレゼントしてくれたコンパクトを取り上げ、軽く頬を押さえてから、体を伸ばす。
- 鏡に写る、金髪の女性。
- 今日の私は、あの絵と同じ格好をしている。
- レノーアは、絡み付いてくる理由のない不安を払い除けるように、足早に部屋を出た。
- リクターは車のドアを閉め、家の灯を見上げて溜め息をついた。
- 遅くなってしまった。
- 午後の回診の最中に、急患が入った。
- 手術が終わったのは、夕食の時間を大幅に過ぎてからだった。
- この数十年。
- リクターも、苦しんでいた。
- 彼の中の邪悪なうごめきは、大きくなり、小さくなりながらもけっして消えなかった。
- 悪夢も繰り返され、今でははっきりと、妻を目的としていることがわかっていた。
- そして、最初に感じたように、その衝動はローラにも向いているのだった。
- 子供特有の甘酸っぱい匂いを嗅ぎ、ふっくらとした腕を首に回されると、沸き上がってくる飢餓感に、ほとんど息ができなくなってくる。
- リクターは、レノーアを、ローラを愛していた。
- 二人を守るためなら、どんなことでもしようと思っていた。
- それなのに、彼自身が二人を傷付けたいと願っているのだ。
- 私は、狂っているのかもしれない。
- その恐れから、精神分析学や心理学をずっと学び続けてきたが、彼にはもう判断がつかなかった。
- 今となってはもう、専門家に相談する気持ちにもなれない。
- とにかく、私は、二人の側を離れられない。
- 彼はレノーアと同じように、仕事のため家庭で過ごす時間が短いことを、安堵の材料にしていた。
- 今日は、大丈夫だといい。
- 心のままに、二人を腕に抱きたい。
- 遅くはなったが、まだローラは起きているだろう。
- 彼女の高い、澄んだ声を聞きながら、レノーアの優しい姿に見入っていたい。
- ドアを開けた時、レノーアもローラも迎えに出てこないのに、リクターはがっかりした。
- いつもなら、どんなに遅くなっても出て来てくれるのに。
- 夕食に遅れたのを、怒っているのかもしれない。
- 彼は、ダイニングルームのドアを開けた。
- リクターの目に飛び込んできたのは、
- 血溜まりに横たわっている妻の姿、
- そして、その傍らに立って、肘から切断した腕を両手に持ち、小さな口を真っ赤に染めてそれに歯を立てている、
- 娘の姿だった。
- リクターの脳裏に、しゃがれた笑い声がこだまする。
- 『D
- 』
- 闇。
- 『D。
- ドラキュラ。
- お前にも、お前の娘にも、Dの血が流れている』
- 闇の声。
- 子供の頃から、幾度となく彼の心に鳴り響いてきた、邪悪そのものの声。
- 『お前の娘が、殺したのだ』
- レノーア。
- ダイニングルームの床に、うつぶせに倒れている彼の妻。
- 死せる、金の髪の女性。
- 『血が、必要なのだ。
- お前にも、お前の娘にも』
- 胸元と、切り取られた腕から流れた血が、赤黒いプールになって広がっている。
- 彼女が好きな、濃いローズピンクのセーター。
- 銀のナイフが、重い赤に染まった刃を光らせる。
- 『だから、食うのだ』
- ローラ。
- 立ち尽くす父にも気付かず、一心に母の腕を食い続ける彼の娘。
- 『本当の力を得るために』
- 鎖が切れた、玉虫のペンダントが赤紫に光っている。
- 『D
- 』
- 闇。
- それから数時間、リクターはほとんど自動的に動いた。
- レノーアを抱き上げ、息がないのを確かめ、繰り返し突き刺されたその傷が、脇にころがっている肉切りナイフによるものであることを確かめる。
- ローラを背後からそっと抱き締め、レノーアの腕を取り上げる。
- そのまま、魂を失ったように口を動かし続けるローラを、バスルームに抱いていく。
- ローラは、ガラスのような瞳をただ見開いている。
- 口をゆすがせ、服を脱がせ、シャワーで血を洗い流す。
- ぐったりと弛緩した体をベッドに運び、鎮静剤を注射する。
- ナイフを洗い、外科用手袋をした上で、もう一度血に浸す。
- そして、ローラの歯形がついたレノーアの腕を、厳重にくるんで車のシャシーの下に隠す。
- 部屋を見回し、念入りに確かめた後、警察に電話する。
- 刑事は、ソファに腰を落とし、両手に顔を埋めているリクターに、鋭い目を向けた。
- 「……では、お宅にお帰りになって、初めて気がつかれたんですな」
- 「……ええ」
- 「奥様は、お一人だった?」
- 「いえ、娘がおりました」
- 「こんなに広い家に、奥様とお嬢さん二人だけで?
- 手伝いの人とかは、誰もいないのですか?」
- 「妻が、他人と暮らすのを嫌がっていたもので」
- 「お嬢さんは、どうなさっていたのですか?」
- リクターは顔を上げた。
- 「倒れていました」
- 「どこに?」
- 「妻の脇に」
- 「今は、どこに……」
- 「気を失っていたので、部屋へ連れていきました。
- 鎮静剤を射って、今眠っています」
- 刑事は、目をきらっと光らせた。
- 「薬から覚めたら、お話をうかがえますね」
- リクターは立ち上がって叫んだ。
- 「駄目です!
- 絶対に駄目です。
- 娘は、強いショックを受けている。
- たった12才でこんな目にあって、娘の心には深い傷がついているんだ。
- こんな状態で、尋問なんて、とても……」
- 「先生……
- 先生!」
- 刑事は、彼の両肩に手をかけて、ソファに座らせた。
- 「どうか、落ち着いてください。
- 尋問ではなく、何があったのか、質問させていただきたいだけなのです。
- 私どもも、12才のお嬢さんに、あまりおつらいことを聞きたくはないのです。
- しかし、この憎むべき犯人を捕らえるためには……」
- 「それでも、駄目です。
- どうか、わかってください……」
- リクターは又、両手で頭を抱えた。
- 「私には、もうあの子しかいないんだ……」
- 刑事は肩をすくめて、とりあえずその場は退いた。
- 後ろで、毛布にすっぽりとくるまれた担架が、警官たちの手によって運び去られようとしている。
- 「ローラ」
- 「……」
- リクターは、娘の目をのぞきこんだ。
- 瞳の中に、見え隠れしている、闇。
- 凶暴な閃き。
- ローラの唇に、邪悪な笑みが浮かんでくる。
- 天使のようだった彼女の微笑の、醜悪極まりないパロディ。
- リクターは思わず、目をそむけた。
- 手早く、用意してあったアンプルをカットする。
- D。
- 彼は点滴の中に、さらに薬物を加えた。
- たちまち、ローラの顔から邪悪な表情が消え、ぼんやりと霞がかかったようになる。
- 「ローラ、聞きなさい。
- すべて、忘れるのだ。
- 今夜のことはすべて……。
- 目が覚めても、何も覚えていない。
- 何も。
- 忘れるのだ……」
- 繰り返し、
- 繰り返し。
- 彼が今まで学んできた、あらゆる方法を使って、リクターはローラの記憶を消去しようとしていた。
- これは、大事件だった。
- リクター・ハリスは高名な医師であり、その夫人が惨殺されたのだ。
- しかも、マスコミには伏せられていたが、腕が持ち去られているというショッキングな事実があった。
- 警察は、威信をかけた捜査に乗り出した。
- リクターのアリバイは、成立していた。
- 解剖によって判明した死亡時刻には、彼はまだ手術室にいたのだ。
- 最初は厳しかった刑事たちの口調も、アリバイが判明するとたちまち和らいだ。
- しかし、質問は厳しかった。
- 「一つだけ、うかがっておきたいことがあるのです。
- 先生は、奥様がお亡くなりになった時間には手術中でいらした。
- しかし、お帰りになったと推定される時間から、警察の連絡された時間まで、ずいぶんあいているんです。
- この時間、先生は何をなさっていらしたのですか?」
- リクターは、考え抜いておいた言葉を口にした。
- 「一目見て、妻が死んでいるのはわかりました。
- 初め、娘も死んでいるのかと思った。
- ……血に、まみれていたので。
- 抱き上げると、生きていた」
- 「それで?」
- 「外傷がなかったので、服を脱がせて、シャワーで洗ってやりました」
- 「どうしてその前に、警察に電話しなかったのですか」
- 「……
- 警察のことなど、浮かばなかった。
- とにかく、娘が心配で……。
- 目を覚ました時、自分が母親の血に染まっているのに気付いたら、と思うと、とにかくきれいにしてやりたかった」
- 「まあ、そんなものかも知れませんな」
- 刑事は、しぶしぶといった口調で言った。
- 「あ、それにもう一つ。
- 奥様は、何か思い出されていましたでしょうか」
- 「……え?」
- 「記憶を失くしていらっしゃいましたよね。
- そう聞いています。
- 奥様の過去に何があったか、それが鍵かもしれません」
- リクターは、内心驚いていた。
- レノーアの記憶がないことなど、彼はとっくに忘れていた。
- レノーアだってこの長い年月の間、特別それを気にしている様子はなかった。
- 彼等夫婦にとっては、そのことは問題ではなかったのだ。
- しかし、真相を知っている彼にはともかく、刑事がそれを問題にするのは当然かも知れなかった。
- 「いいえ、何も。
- 最初のうちはずっと精神科にかかっていましたが、もうあきらめていました。
- 何せもう、15年も経っていますし……」
- 「そうでしたよね、15年も」
- 口ではそう言ったが、刑事は鋭い目付きを崩さなかった。
- 一週間後に、リクターはようやくローラへの質問を刑事に許した。
- 中年の刑事は、やつれ果ててひどく幼く見えるローラに、せいいっぱいの心使いをみせながら、質問を始めた。
- あの日は、いつ学校から帰って来た?
- 午後、遅く。
- お友達の家に寄ったから。
- ママはどうしていた?
- いつものとおり、お夕食の支度をしていた。
- 何を話した?
- 学校の話。
- ママから、今日ははパパが早く帰ってくると聞いた。
- バンドのことを話せるので、うれしかった。
- それから?
- ママのお手伝いをして、お皿を並べて、パパを待っていた。
- でも、なかなか帰って来なかった。
- ママはだんだん悲しそうな顔になって、また、大変な患者さんが来たのかもね、と言った。
- 先に食べていましょうか、と言ってお肉を焼いた。
- パパと一緒でないのは淋しかったが、いつものことだったし、お腹が空いていた。
- ふたりは、食べ始めた。
- 刑事は、身を乗り出した。
- ローラは、頬に黒い影を落とした目をみはったまま、小さい声でではあるがすらすらと続けた。
- 「御飯を食べている途中で、気持ちが悪くなって、気がついたら、パパがベッドに寝かせてくれたの」
- 「な……」
- 刑事は驚きに体を起こして、ローラの椅子の後ろに立っていたリクターの顔を見る。
- リクターは、ゆっくり首を振ってみせた。
- 「……何も、覚えていなんだよ」
- ベテランの刑事は、タイプライターに挟んだ報告書をにらんでつぶやいた。
- 「事件前後の記憶が、きれいに消えているんだ。
- 食事をした時から、父親が帰ってきてベッドに運んでもらった時まで、間が抜けてしまっている」
- 「そんなことって、あるんですか!」
- まだ若い刑事が、すっとんきょうな声を上げる。
- 「あるんだろうよ。
- 殺された母親だって、記憶喪失だったんだ。
- 後で父親に聞いてみたんだが、あの日からずっと高い熱を出していたらしい。
- 熱が下がって、父親が何があったか聞いた時から……
- ああだったんだそうだ。
- おそらく、ショックのせいだろうと言っていた。
- 状況から見て、あの子の目の前で母親が殺された可能性は高いからな。
- 精神科の医者も、同じ意見だそうだ。
- 記憶喪失になりやすい体質が遺伝するものかどうかは、知らないがねえ。
- というわけで、あの子はあの晩のことを、何にも覚えていない。
- 父親も、話していない、いや話せないのだと言っていた。
- ……質問してる途中で、急に振り向いて父親の顔を見て……
- ママはどこって、聞いたんだぜ。
- 俺はもう、どうしたらいいのかって思った」
- 若い刑事は、その場にいたのが自分じゃなくてよかった、とあからさまに書いてある顔で聞いている。
- 「父親がな、ママは、ちょっと遠くに行っているとかなんとか……
- あれじゃ、仕方がないよ。
- その後もまた、熱を出してしまったらしい。
- あの子は、病人だ。
- 俺には12才どころか、8才くらいに見えたよ。
- 無理やり聞き出すなんて、とてもできやしない」
- 「でも、他に、手掛かりはないんですよ。
- 隣は遠くて、悲鳴を聞いてもいないし、不審人物を目撃した者もいない」
- 「俺は、さ……」
- ベテラン刑事は、声を低めて言った。
- 「最初、あの父親が怪しいと思っていたんだ」
- 「ハリス先生が!?
- まさか!
- すごい名医だって、アメリカ中で有名な人だそうですよ!」
- 「関係ないだろ。
- 妻が殺されたら、一番先に疑うべきなのは、夫だぞ」
- 「だって、アリバイが……」
- 「あの先生が手を下したんじゃないことだけは確かだが、誰かに依頼した可能性はある」
- 「でも、動機がありませんよ。
- 財産は全部先生のものだし、高額の保険なんてかけてなかったし、夫婦仲は良かったらしいし」
- 「ああ、愛人でもいるかと思って調べたが、とんでもない、きれいなものだった。
- もしかして、奥さんの過去でもどこかで知って……
- と考えたんだが、殺すほどの理由というのも、考えにくいしなあ。
- それに、そういう場合だったら、自分で手を下すと思う。
- 殺しを他人に依頼はしないだろう」
- 「じゃあ、奥さんを殺す理由なんて、かけらもないじゃないですか。
- 一体、何がそんなに気になるんですか?」
- 「はっきりとは言えないんだが……
- 何となく変なんだよ、あの先生。
- 娘、娘で、犯人のことなんか、どうでもいいみたいなんだ」
- 「変にもなるでしょう。
- 奥さんが殺された上に、娘さんはおかしくなる……
- 普通でいろって方が、無理ってもんです。
- 犯人を掴まえたって、奥さんが戻って来るわけじゃなし、今は娘さんのことの方が重大なんですよ」
- 「結局、奥さんの過去が問題かなあ」
- 中年の刑事は溜め息をついた。
- 「当時の調書も調べたんだけれど、何の手掛かりもなかったんだ。
- 言葉の訛りはロスのものなのに、行方不明の届けはないし。
- あれほど育ちの良さそうな女性だったら、誰かが探していてもよさそうなものなんだがな」
- 「でも、15年も前のことですよ」
- 「あの奥さんを殺す動機を持った人なんか、回りでは誰も見付からなかったじゃないか。
- 奥さんが忘れた過去に、動機を持った人間がいたのかもしれない。
- 今まで会っていなくて、今回ようやく目的を遂げたか、あるいは現在の境遇に動機を持ったか……。
- 俺はその可能性もあると思う」
- 若い刑事は、賛成できないとでもいうように首を振った。
- ベテラン刑事は、じろっと彼をにらんだ。
- 「それより、僕は気になるんですよ」
- 若い刑事は、苦虫を噛み潰したような相手にかまわず、言葉を続ける。
- 「腕は、どうしたんでしょうねえ」
- 「……」
- 「僕、考えたんですけどね。
- 高価な指輪か、腕輪でもしていて、取れなかったんじゃないんですか?
- それで、腕ごと持って行った」
- 「バカかお前。
- 指輪なら指を切るだろうが。
- 腕輪だって、手首を切れば外れるだろう。
- 切る手間は同じなんだから、腕ごと持っていく理由にはならないだろ。
- それに、現金を始め、盗まれたものなんか、何もないんだぞ」
- 「あーあ……」
- 若い刑事は、首を縮めた。
- 「それじゃ、変質者ですよ。
- 通り魔の犯行。
- 15年前の怨念より、僕はそっちに賭けますけどね」
- ベテラン刑事は、ますます苦い顔でタイプライターをにらみつけた。
- ベテランの刑事はレノーアの過去を探し回ったが、何も見付けることができなかった。
- そして結局、警察の出した結論は、若い刑事の言うとおりになったのだった。
- 彼は、病院のオフィスにリクター・ハリスを訪ねた。
- 「……というわけです。
- 奥様を殺した犯人は、必ず掴まえると申し上げました。
- 私たちはまだ、あきらめてはいません」
- リクターは、瞑目して座っている。
- 刑事は、彼の苦悩に満ちた表情を、しばらくながめていた。
- 「……わかりました」
- リクターは、暗い影の揺れる目を開いた。
- 「お願いします」
- 刑事はしばらく待ったが、リクターの言葉はそれだけであった。
- 刑事は、首をふりながら立ち上がった。
- 握手をして、ドアを出る時、彼は振り向いて尋ねた。
- 「お嬢さんの具合は、いかがですか」
- 「あまり、よくはありません」
- 暗いまなざしをぼんやりと投げたまま、リクターは答えた。
- 「レノーアは病気で死んだのだ、と話しました。
- 改めて、ショックを受けています」
- 「それはそれは……。
- で、治療は……」
- 「この病院の精神科にかかっていますが……
- 治るということは、あの記憶が戻るということです。
- 私は、できればもう、二度と思い出さない方がいいのではないかと思っています」
- 刑事は、呆然として彼を見つめた。
- 彼は、弱々しい微笑を浮かべた。
- 「私には、もう、あの子しかいないのです」
- 刑事はドアを閉め、まだ首を横にふりながら歩み去った。
- リクターは再び座ると、デスクの上に指を組んだ。
- 美しきレノーアは死んだ。
- ポーの詩にうたわれたように。
- その体は地中に横たわり、その腕は
- ・・・
- 彼はあの腕を、病院の焼却炉で処分した。
- 誰も、気がつかなかった。
- ローラは、何も覚えていない。
- 精神科の医師がどんな方法を使っても、彼女のブロックを破ることはできないだろう。
- D。
- 私の体を伝わって、ローラへと受け継がれた、Dの血。
- ローラは、その血の求めるままに、レノーアの肉を食ったのだ。
- 同じ血のものの肉を。
- 今になって、ようやく彼は、自分を育ててくれた老女の恐怖を理解した。
- 彼女は、彼がDの血に目覚め、彼女を食ってしまうのではないかと恐れていたのだ。
- 彼女は、彼の家系の呪いを、知っていたのだ。
- リクターは、デスクの上で、両手の拳を握り締めた。
- 私は、大丈夫だ。
- この長い年月、ずっと耐えてきたではないか。
- 暗い、闇からの呼び声に応えず、妻と娘をずっと守ってきた。
- これからも、守ってやる。
- やれるのだ。
- ローラを。
- レノーア。
- 君を愛していた。
- わかってもらえなかったかも知れないが、私は君を心から愛していた。
- これからの私は、君の残したローラを守ることに一生を捧げよう。
- レノーア、どうか、許してくれ。
- [CHAPTER 09]
- リクターは、ローラを連れ、アメリカ中を転地して回った。
- 幸い、アメリカ中の病院が彼の腕を求めていた。
- 「いい考えかも知れないな……」
- 精神科の医師、バークはそう言った。
- 「君の言うとおり、今の彼女に事実を認識させるのは、あまりにも過酷だ」
- 「ローラには、レノーアが病死したと言い聞かせた。
- ここにいると、誰かが本当のことを話してしまうのではないかと心配なんだ」
- バークは、濃いあごひげを撫でながら、暗い目でカルテをながめた。
- 「ただ、リクター、解っているとは思うが、これは問題を後回しにするということなんだよ。
- 彼女が受けた傷は、たいへんに大きい。
- 真実を知らなければ、傷は隠されたままで、けっして癒えない。
- この傷をそのままにして大人になったとして、後々彼女にどんな影響が出るかは、誰にもわからないんだぞ」
- 「わかっているさ。
- でも、記憶をなくすというのは、頭脳と精神の防衛だろう。
- 防衛しなければならないと、彼女の精神が感じたんだ。
- 事実を全部認識することが、必ずしもベストではないんじゃないか?」
- バークは、憂欝な溜め息をついた。
- 明らかに賛成できないという顔でリクターを見やったが、彼はかたくなな表情を崩さなかった。
- 「……まあ、とりあえず今は、それでいいだろう。
- それで、そのうちには、帰ってくるつもりなんだろう?」
- 「今は、わからない」
- 「まあ、数年も経てば、皆忘れるさ。
- どんな大事件だって、そんなに長い間話題にはならない……
- あ、いや、そういう意味ではないんだ。
- 奥さんのことは……」
- 「いいんだ。
- そっちは、警察に任せてある。
- 私は、ローラのことだけを考えている」
- 「……君も、君自身にも、注意したまえよ」
- リクターは、いきなり殴られたような顔をした。
- 「気が付いているかね。
- 君もひどい顔をしている。
- 君だって、傷付いているんだ」
- リクターは吐息をついて、ただうなずいた。
- 細心の注意を払って、リクターはローラを育てた。
- あの晩に起きたことだけではなく、目覚めたDの血をも封印しなければならなかったので、彼は強力な薬物と方法を使って、彼女の心を制御した。
- そのためローラは、それ以前の記憶と現在の経験を、つなげる回路を失った。
- 副作用のせいか、半年ほどは発熱が繰り返され、さらに記憶を混乱させた。
- しかし、ローラの素質は損なわれてはいなかった。
- 快活さに欠けるとはいうものの、明敏で利発であることに変わりはなかった。
- 彼女が最初から持っていた、芯の強さも健在だった。
- 体が回復した後は、彼女はもの静かでしっかりした、美しい少女に成長していった。
- リクターは、自らの闇と戦いながらローラを見守った。
- Dの血は、今や唯一の家族となったローラに強い衝動を起こしていたが、彼は必死の努力で、それに耐えていた。
- 彼の生活も愛情も、すべてローラを中心に過ぎていった。
- ローラは、文字通りの『お父さん子』だった。
- 数年後に、二人はロサンゼルスの家に戻ってきた。
- 家はそのままにしてあったので、ダイニングを始め、大幅な改装を行った。
- リクターは大学には戻らず、ダウンタウンの病院に職を得た。
- かつての同僚の指摘のように、事件の記憶は人々から失われているようだった。
- 微かな噂が囁かれたとしても、ローラの耳に入った様子はなかったので、リクターは心から安心した。
- ローラは普通に学校に通い、以前と同じように素直で優秀な生徒として、教師や他の生徒に受け入れられた。
- ブロックが破れる気配はなく、彼の行った強引なコントロールが残した、悪影響も見られなかった。
- 彼は、こればかりはかわらずに寝室にかけてあるレノーアの肖像を見上げ、彼女がローラを守ってくれているのかもしれないと考えた。
- ローラは、ちゃんと美しく育っているよ。
- 出会った頃の君に、とても似てきた。
- 時々、君が生き返ってきたのかと驚くほどだ。
- そう、この絵はローラの絵だと言っても、誰もがうなずくだろう。
- 彼女が、この服を着て、ペンダントをかければ……。
- ペンダント。
- 玉虫のペンダント。
- リクターは、愕然とした。
- この長い月日、どうして思い出さなかったのか。
- 惨劇の晩、横たわったレノーアのかたわらに、鎖の切れた玉虫のペンダントがころがっていた。
- あれは、どこに行ったのだろう。
- 彼は、あの晩のすべてを順に考えてみた。
- ペンダントがあったのは、間違いない。
- 朝、リクターが久し振りに口にしたので、レノーアは首から下げていたのだろう。
- 床にころがったペンダントが、いつもの青緑とちがって、赤紫色に見えたのも覚えている。
- だが、ローラを運んでからは、見た記憶がない。
- 警察が証拠品として持って行ったのは、銀のナイフだけである。
- いや、彼が死体を動かしたと言ったので、あの夜のうちに警察は、彼に何度も現場を見せた。
- その時にはもう、ペンダントは落ちていなかった。
- 今から考えると、あの時に気付いてもよかったのだ。
- 念のため、家中を調べてまわって、どこにもないのを確認してから、リクターは考えこんだ。
- いったい、何故……?
- 何か、意味があるのだろうか。
- しかし、しばらくして彼は、それを忘れることにした。
- 仮にあのペンダントが見付かっても、他の宝石類と同じようにローラに渡す気にはなれなかった。
- あれをレノーラに与えたことさえ、間違っていたのだ。
- ローラはもう、過去からは切り離されているのだ。
- 私のメスで。
- 彼女はこれからは、何者にも囚われない、自由な人生を歩んで行くだろう。
- 私は、そう、願っているのだ。
- 『……本当に、そうかな?』
- リクターは、沸き上がってきた闇の声を黙殺した。
- リクターは、一度だけ、夢を見た。
- 昔の館の中を、生き返った玉虫が這い回っている。
- 玉虫の体は、次々と色を変えていた。
- どこからともなく、しゃがれた含み笑いがずっと続いていた。
- 朝食の席で、医学部に行きたいと言い出したローラを、リクターは眩しげに見た。
- 広い窓から、植木の葉に揺れる朝日が射しこんで、娘の金髪を明るく輝かせている。
- すらっと伸びた長い手足を流行りの飾り気のない衣類に包んでも、彼女はどこか品を失わない娘だ。
- 「……それは、なかなか大変だよ」
- 「わかっているわ。
- でも、がんばるから。
- 私、パパと同じ仕事がしたいの。
- ずっとパパを見ていて、人の命を助けるのって、本当にやりがいがある仕事だと思ったの」
- リクターは、ますます目を細めた。
- 「まあ、そうだね。
- やりがいは、ある」
- 「先生方も、どこの大学の医学部でも、入れるって言ってくれているの。
- ロスには、いい大学がたくさんあるし、だから……」
- 「ちょっと、待ちなさい」
- 彼は、体を起こした。
- 前から考えていた言葉を口にしようとすると、胸の奥から例の疼きがこみあげてくる。
- 厳しい顔つきになった彼を見て、ローラはあっけに取られた表情をした。
- 「パパ……反対なの?」
- 闇が、阻止しようとするだろうということも、彼にはわかっていた。
- しかし、彼は無理やりに捩じ伏せた。
- 「……そうじゃない。
- ローラ、お前はこの家を出、ロスから離れて、違う場所の学校に行きなさい」
- 「どうして!」
- 彼女は叫んだ。
- 「どうしてロスじゃいけないの?
- どうして、この家に、パパと一緒にいてはいけないの!」
- また、闇がのどを押しあげてくる。
- これが、理由なのだ、ローラ。
- 父さんは、今までずっと、我慢してきた。
- 一生、我慢するつもりでいる。
- けれど、もし万が一、と思うと、父さんはいても立ってもいられないのだ。
- 父さんは、お前を愛しているから、お前にとって少しでも危険な場所からは、お前を離しておきたいのだ。
- つまり、父さんの側から、だ。
- 「そうだよ、ローラ。
- 私は、お前が一人前になったら、そうするべきだと考えていた」
- 「まって、パパ……」
- 「しかも、お前は、父さんと同じ医者になりたいと言った。
- だったら、なおさらだ。
- このロスにいたのでは、父さんの娘であることが、お前にとって悪い影響になる」
- 「そんなこと、絶対にないわ!」
- 「いや、あるんだ。
- 父さんは、一応名の知られた医者だ。
- お前がどんなにがんばって、いい結果を残しても、それは父さんの力だと思われてしまう。
- もちろん、どこの学校に行っても、言われるかもしれない。
- しかし、ロスで勉強するよりはずっとましだ」
- ローラは、悲しげに黙った。
- リクターは、手の震えを押さえながら、続けた。
- 「お前が医者になることには、父さんは大賛成だ。
- どこの大学でもいい。
- もしそうしたければ、外国に留学してもいい。
- ただし、ロスは駄目だ」
- ローラは唇をかみながら、うつむいていた。
- 葉もれ日に光る髪を見ながら、リクターは苦痛と安堵を両方感じていた。
- ローラが選んだのは、サンフランシスコの学校だった。
- 休暇には、簡単に帰ってこられるでしょ、とローラは笑った。
- 「それとも、パパ。
- もっと、遠くの方がよかった?」
- 挑戦するように言うローラに、リクターは苦笑いで応えた。
- 突然ローラは、飛び立つように彼に抱きついてきた。
- 「パパ……
- パパが言ったの、本当だと思う。
- でも、パパが一人になっちゃう。
- 淋しいでしょう?
- それとも、淋しくないの?
- パパは私が、邪魔なの?」
- リクターは、歯をくいしばって疼きを押さえた。
- いけにえを逃すな!
- と闇の声がわめいていた。
- かろうじて口にできたのは、震える言葉だった。
- 「邪魔だなんて……
- そんなこと、あるわけがないじゃないか。
- 父さんは、お前を……」
- ローラが顔を上げた。
- 青く澄んだ瞳に、涙が浮かんでいた。
- あふれ出てきた愛しさが、闇を圧し、駆逐した。
- リクターは優しい腕で、彼女を力いっぱい抱きしめた。
- 「……この世の中で、お前だけを、愛しているんだ」
- ローラは透明な声を上げて、笑った。
- その笑い声は彼の胸に、ずっと残った。
- [CHAPTER 10]
- 私は、母をよく覚えていない。
- 母が病死したのは、私が12才の時である。
- 母の死は、急だったらしい。
- 私はショックで、病気になり、その前後の記憶を失ってしまったのだ。
- とともにそれ以前の記憶も、何だかぼんやりとした夢のようになってしまっていた。
- 母のことを考える時、脳裏に浮かぶのはほんのわずかな断片である。
- 白い、何やらふわふわとした物を着て、庭で花を切っている母。
- 小さな小花模様のスラックスと、共布のスカーフで髪をくるみ、台所でくるくると働いている母。
- 食卓で、父のカップにお茶を注ぐために、すんなりとした腕を伸ばしている母。
- しかし、そのどれもが薄い紗をかけたように霞み、古い映画で見たシーンのように感じられる。
- 私自身の体に触れたはずの、母の手のぬくもりが残っていないのである。
- 抱き締められたり、キスを受けたり、私の記憶にはそういった体の触れ合いだけではなく、母との会話すら含まれていない。
- ただ映像が、ぼんやりとしたスクリーンに動くだけなのである。
- 私にとっての母のイメージは、物語の中の天使である。
- お母様は天使になったのよ、という決まり文句を、誰かが私にささやいたのかもしれない。
- 彼女は私を守ってくれている反面、私に直接話しかけてはくれないのである。
- お母様がいなくて淋しいでしょうと、何回となく聞かれた。
- 私も、母がいてくれたらどんな生活だっただろうと、考えないではなかった。
- けれど、淋しくはなかった。
- 父がいてくれたからである。
- 私の秩序だった記憶は、父とともにアメリカ中を旅した数年間に始まっている。
- しかも病のせいか、初めの半年ほどの記憶は、とぎれとぎれである。
- 長くても一年、短い時は数か月で、私たちは次の土地に移った。
- 小さなアパートを借り、父は週にほんの2~3日、近くの大学か病院に通う。
- 私のためにその時だけ、臨時のお手伝いさんか家庭教師が来る。
- 私は体が弱いという理由で、学校へは行かない。
- あんな生活ができたのも、父がずばぬけた腕を持つ外科医だったからだろう。
- 私は後に医学部に行ってから、父の手術の腕が、およそ芸術的と言ってもいいほどの域に達していると聞いた。
- また、この頃次々と現れてくる新しい技術や機械に対しても、父の判断は実に正確であるということも。
- 私はそれを聞きながら、誇らしさを胸いっぱいに感じていた。
- そう、父は私の誇りだった。
- いや、私のすべてだったと言ってもいい。
- 病が治ってきた頃だったと思う。
- どこの都市だったのか、そこは建物の2階か3階の部屋だった。
- 私はベッドで目覚め、カーテンが風で揺れるのをずっと見ていた。
- 隣室で声がした。
- 昼間私の世話をしていた看護婦が、低い声でしゃべっている。
- 父の、静かな声も聞こえる。
- やがて、看護婦が帰っていく気配がする。
- ドアが開き、父が顔をのぞかせる。
- 「……ローラ。
- 起きていたのかい?」
- 私はうなずく。
- 父は部屋に入り、私のベッドサイドに立つ。
- 「気分は、どうだ?」
- 父は手を伸ばし、私の額に触れる。
- 父の身辺に、いつも漂っている消毒薬の匂いが、私の鼻孔をくすぐる。
- 私は、その匂いが大好きだ。
- 父の手は、ほっそりとして白い。
- いかにも外科医の手らしい、長い指を持っている。
- 「熱は、ないな。
- あまり食欲がないのだって?
- 何でも、食べたいものを言うんだよ。
- 買ってきてあげるから……」
- 私はかぶりを振る。
- 父は困ったような表情をして、体を起こす。
- 父は、長身である。
- まだ幼い私には、父の頭が天井に届くように見える。
- 「パパ……」
- 私がささやくと、父は屈んで、顔を近付けてくる。
- 私の目には、父の顔が視界いっぱいに落ちてくるように見える。
- また消毒薬の匂いがして、私はうれしくなる。
- 「ここにいてね」
- 父は、相変わらず困ったような笑いのまま、うなずく。
- そして、ベッドサイドに大きな椅子をひきずってきて、私が再び眠りにつくまで本を読んでくれるのだ。
- これが私の、最初の確かな思い出なのである。
- 同じような夜が何度となく重なって、私の歴史を記していった。
- どのページにも父がいて、いつも私を見守ってくれていた。
- 各地を転々としていたので、私には友人がいなかった。
- しかし私は、父がいてくれればそれでよかった。
- 仕事のない日には、父はいつも私と一緒にいてくれた。
- 体の具合がよくなってからは、父は私をいろいろな所に連れて行ってくれた。
- 私は、充分に幸せだった。
- ロサンゼルスに帰って来た時、私が生まれた家はずいぶん様子が変わっていたらしい。
- 私は、広い美しい部屋をもらってうれしかった。
- 今までは、自分の部屋といっても名ばかりで、ずっと住めるわけではなかったからだ。
- 部屋は、今の私に合わせて飾られていた。
- 私は、お礼を言うために、父の部屋に飛び込んだ。
- 帰ってきてこの部屋に入るのは、初めてだった。
- 私は、思わず立ち止まった。
- 正面の壁に、大きな肖像画がかけられている。
- 母の肖像だ。
- 濃いピンクのセーターを着て、手を組み、優しい微笑みをたたえた母。
- 私の記憶の中の彼女より、ずっと大きな存在感を持っている。
- 私は、ふと振り返った。
- 部屋の片隅で、父が棒立ちになっている。
- その顔には、見たことのないほどの不安が影を落としている。
- 「パパ?」
- 私が呼びかけると、父は何かをためらうように、一歩足を進めた。
- 「パパ、どうしたの?」
- 私の声を聞くと、父はたちまちほっとしたような表情で、歩み寄ってきた。
- 私は父の様子が不思議だったが、肩を抱かれて同じようにまた、肖像画を見上げた。
- 「きれいだろう?」
- その声には、染み入るような響きがあった。
- 私は、強くうなずいた。
- ロサンゼルスの生活は、序々に落ち着いた。
- 私は、学校に通うようになった。
- 昔の私を知っている人は誰もいなかったので、私はただの転入生だった。
- 同年輩の少女たちとの付き合いは、私にとっては生まれて初めてと同じだったので、私は少々心配だった。
- しかし、私はすぐに慣れた。
- 有名な医師の娘であること、母がいないことなどが多少は影響したのかもしれないが、友人たちは私を受け入れてくれた。
- 成績も、いい方だった。
- これも、父のおかげだった。
- ロスに帰っていくらも経たない頃、父の昔の同僚たちが、家にやってきたことがある。
- 私が挨拶に出ると、彼等は一様に会話をやめ、こちらを見て目をみはった。
- 「……ローラ?
- ローラね!」
- 中年にさしかかった女性が、声をあげた。
- 彼女は駆け寄ってくると、両手を広げて私を抱こうとした。
- 知らない人だったので、私は驚いて身を引いた。
- 女性ははっとして立ち止まり、こわばった表情をしている父を見た。
- 父は、ゆっくりと歩いてきて、私と女性の間に立ってこう言った。
- 「こちらは、マリアン・セレスさん。
- 母さんのお友達だった。
- お前も、ずいぶんお守りをしてもらったんだよ」
- 私はうなずき、彼女は安心したように微笑んで、改めて私を抱きしめた。
- 「そうよ、ローラ。
- 本当に大きくなったわね。
- 驚いたわ、あなたはレノーアそっくりよ」
- 彼女は私の肩を抱いて、隅のソファの方に誘った。
- 私は、父がまだ奇妙に堅い顔をしているのが気になったが、そのまま彼女に連れていかれた。
- マリアンは、ひっきりなしにしゃべっている。
- 「あなたのお母様は、とっても素敵な人だったわ。
- 私たちは皆、彼女に夢中だったのよ。
- 私も、ずいぶんこの家で楽しい時間を過ごさせてもらったわ。
- まるで、女学生みたいにおしゃべりをしてね。
- 赤ちゃんだったあなたも、一緒だったのよ……」
- 父は、背の高いあごひげのある男の人に話しかけられていたが、何だかしきりにこちらを見ている。
- マリアンの話に、私はただうなずいていた。
- 母のことにはもちろん、興味があった。
- マリアンはひとしきり、思い出話を続けた。
- 母がどんなに美しく、幸せそうだったか、
- どんなに父を愛していたか、
- 父が仕事で忙しい中、どんなに私に愛情を注いでくれたか……
- 初めて聞く母のいきいきとした姿は、私の胸に甘酸っぱい感動を呼び起こした。
- 私は思わず、涙ぐんでしまった。
- それを見たマリアンも、目を赤くして微笑んだ。
- 私はふと、以前から気になっていたことを、彼女に聞いてみようと思った。
- 「あの……
- 私の母は、何の病気だったのですか?」
- マリアンは、ふいに息を引いた。
- 目を大きくみはって私を見つめる。
- それは、さっき私を抱こうとした時と同じ目だった。
- 「ローラ、あなた……
- リクターに、聞いていないの?」
- 私は、あいまいに首を振った。
- 実は何度か聞いてみたのだが、「難しい病気だったんだよ」としか、父は言わなかったのである。
- その時の父の苦渋に満ちた表情が、私にそれ以上の質問を断念させた。
- おそらく医者として、母を救えなかったことへの慙愧の念が、父を苦しめているのだろうと私は考えていた。
- マリアンの返事は、なんだか口の中でもぐもぐ言うような、頼りないものだった。
- 「……私も、よくは覚えていないの。
- 何だかとっても珍しくって、難しい名前で。
- 英語じゃないみたいな……」
- 私は、首をかしげた。
- 彼女は、医者ではないのだろうか。
- そんなに親しかった母の病名を、忘れてしまうなんて。
- マリアンはすぐ、まるで私の心を読んだように言った。
- 「私は、お医者さんではないのよ。
- ただの臨床検査技師。
- ごめんなさいね、ローラ」
- マリアンは、するっと立ち上がった。
- まるで見計らっていたように、父がこちらに来た。
- 「さて、ローラ。
- 皆さんにお休みなさいをしなければね」
- 確かに時計は、私のいつもの就寝時刻を過ぎていた。
- 私は、また全員の注視を浴びながら、挨拶をして部屋を出た。
- 客たちの何人か、特に先ほど父に話しかけていたあごひげの男が、まるで刺すような目で私を見ていた。
- 部屋に引き取っても、私はぐずぐずしていた。
- 客たちの様子は、どこか変だった。
- 私が客間の居る間、彼等はどこかぎこちなく、わざとらしい会話と笑いが流れていたように思えてきた。
- 今思い返してみると、マリアンという母の友人の思い出話も、私がほんの赤ん坊の時期に限られていた。
- 彼女は、私の母の最後に近付くことを、故意に避けていたようだった。
- そして、父の態度は……。
- 私は、そっと自室を出て、客間の方
- に引き返した。
- ドアに近付いただけで、声高な議論が聞こえてきた。
- 「……あの子にカウンセリングも受けさせないで、ずっとあのままにしておくつもりか!」
- 私は、撃たれたように立ち止まった。
- その声は、あのあごひげの医者のものだった。
- あの子とは、私を指しているに違いない。
- 「言っただろう。
- あの時はそれでもいいがって。
- 君は精神科にも詳しいはずじゃないか。
- 問題の重大性は、君にも解っていたはずだ!」
- 「わかっているさ」
- 父の声は、今までに聞いたことがないほど冷ややかだった。
- 「いや、わかっていない!
- わかっていれば、あの子の体が回復した時点で、しかるべき治療を受けさせているはずだ。
- それを……
- 今までカウンセリングひとつ受けさせたことがないだと!
- ……とんでもない!」
- 小さく、なだめる声が聞こえる。
- マリアンの声だ。
- 「バーク、ねえ、そんなに大声で怒鳴らないでよ。
- ローラに聞こえてしまうわよ」
- 私は体を堅くして、廊下の隅に寄った。
- しかし、部屋に帰るつもりはなかった。
- 部屋の中の声は、少し小さくなった。
- 誰か、知らない声が聞いている。
- 「なあリクター、ローラに何か問題があるのかい?」
- 「あるものか」
- 父の自信に満ちた声がして、私は心から安堵した。
- 「確かにあの子の記憶は、一時とぎれている。
- しかしそれ自体を除けば、あの子はすべて正常なんだ。
- どこにも問題はなく、普通の子供として発達している。
- 学校にもなじみ、友達もできた。
- あの子は今、楽しく暮らしているんだ。
- 無理をして昔の記憶を蘇らせる必要が、いったいどこにあるんだ」
- ざわめき……
- よくは聞き取れないが、わずかに、父に同意するような断片が聞こえる。
- と、押し殺してはいるが、きっぱりとした言葉が響く。
- 「不自然だからだ。
- 人間は、一貫した記憶を持って生きている。
- ローラには、それがない」
- 「あるさ」
- 「12才からのか?
- じゃ、母親の記憶は」
- 「……」
- 「つながっていないだろう。
- 今は、問題はないかもしれない。
- 明日も、明後日も、彼女は正常かもしれない。
- しかし、10年後、20年後はどうだ。
- 誰にも、わからない。
- いつ爆発するかわからない、時限爆弾を抱えているようなものなんだぞ。
- 早いうちに、解決しておくべきだということくらい、君だってわかっているはずなんだ。
- いいか、悪いことは言わない。
- 私のところでなくてもいい。
- 誰か、信頼できる医者を探して、治療を受けさせるんだ!」
- 途中から、私はひざを抱えてうずくまってしまった。
- 私の記憶がとぎれていることが、そんなにも重大なことだとは思っていなかった。
- 私は、怯えた。
- まるで、不治の病を宣告されたような気分だった。
- 震えがとまらなかった。
- その時、父の声が流れてきた。
- 「私は、確信しているんだ。
- ローラは、大丈夫なんだ」
- 静かな声だった。
- それは私の耳から、胸の中に染み込んだ。
- 凍りついていた心臓が、再び温かい血を全身に流してくれる。
- 「ローラは、今のままでいいんだ」
- 「リクター!」
- 「静かに!」
- 叫び声が重なり、誰かの靴音がドアに近付いた。
- 私は、弾かれたように立上がり、廊下を素早く曲がった。
- ドアが開く音はしなかったが、私はもう、廊下で聞き耳をたてる気が失せていた。
- その夜も、またその後も、私は考え続けていた。
- 私には、覚えていない時期があるというのに気付いたのは、いつだっただろう。
- はっきりとはしないが、父に聞いてみたことはある。
- 父は……
- そう、ひどく苦しげな顔をしたような気がする。
- 言った言葉は、気にするな、だった。
- ずいぶん大きくなってから、父はきちんと話してくれた。
- 母の病気、私の病気。
- 「お前は、ママが大好きだったから、ママが死んだのを忘れてしまおうとしたんだ。
- そして、忘れてしまった。
- 人間には、そういうことがあるんだ。
- 別に、珍しいことじゃないんだよ。
- パパだって、ママが大好きだったから、忘れてしまいたいんだ」
- 私は、父の言葉に納得した。
- 後から読んだ本の中にも、そういう話はいくつかあった。
- そしてそれ以来、私は父にそのことを話さなくなった。
- 父も忘れたいのだ、という言葉が重かったのだ。
- 私は父の苦しげな顔を、見たくはなかった。
- しかし、私は考え続けた。
- いつかきっと、私は私自身の記憶を、ちゃんと蘇らせよう。
- たとえそれがつらいものでも、私は受け入れられるだろう。
- 私はもう、12才の子供ではないのである。
- 父には聞くまい。
- 私が、私自身で思い出すのだ。
- 父に、よけいな心配をかける必要はないのだ。
- ただ私の心は、どこか父の言葉に甘えていた。
- 私は正常で、どこにも問題はない。
- 父への信頼が、私を支えてくれていた。
- その夜の客たちはどういうわけか、二度と家に来なかった。
- 他の人はともかく、私はマリアン・セレスにはもう一度会いたかったのだが、その機会はとうとうなかった。
- ロサンゼルスに帰ってきたとたんに、父はたいへんに忙しくなってしまった。
- それまでの生活とあまりにも違っていたので、私は戸惑っていた。
- なにせ父と話す時間も、ほとんどないのだ。
- 父ほどの地位になれば、普通当直などはないはずだったが、気になる患者がいると、父は病院に泊まりこむ。
- そうでない時も、父の帰りは遅かったので、私はひとりで夕食のテーブルに着く日が多かった。
- 食事が済むと、お手伝いの人は帰ってしまう。
- 私は父を待ちながら、長い夜をひとりきりで過ごすのだ。
- おしゃべりの時、夜私がひとりだと聞いた学校の友人たちは、様々な反応を示した。
- 「やだ、淋しくないの?!」
- 「なんか、怖くない?」
- 髪の長い、おとなしい目をした友人が、自分が怯えたような顔で言う。
- 「ローラ、本当に怖くないの?
- 私なんか、夜外で変な音がしただけで怖くなっちゃうわ。
- 弟に見てきてって言っても、笑いとばされちゃうし」
- 「セキュリティ会社がいろいろやってくれてるから、別に」
- 「そういうんじゃなくて、ほら、何か超自然のものが……」
- 回りの友達は、皆笑い出した。
- 「もう、オカルトものばっかり、読んだり見たりしてるから!
- そのくせ怖がりなんだから!」
- 「あたし、ローラがうらやましーい!」
- 活発で知られる友達は、派手な声を上げる。
- 「家なんて、親がうるさくって!
- テレビ見ていても、今日何があったとかつまんないこと聞くし、部屋にいても、なんだかんだと口実をつけて入ってこようとしてさ。
- もう、一晩でいいから、家でひとりになりたいわ!」
- 「そうよねえ」
- うなずいた友人は、多かった。
- 「時々、うるさーいとかわめきたくならない?
- 特に、父親よ」
- 「そうそう。
- 娘のことなんか、普段何も知らないくせにしてさ。
- 時々みょうに偉そうな顔して、的外れなこと言いだすのよ」
- 「男の子の友達とか、いるのか?
- なんてさ。
- ばっかみたい」
- 彼女は一年上の相手と、既にステディの関係にあると、皆知っていた。
- 「ローラのところなんて、パパだけじゃない。
- うるさいでしょ」
- 彼女のそんな無遠慮な言葉に、おとなしい友達は私よりショックを受けたようだった。
- しかし、私はかまわずに答えた。
- 「うるさくなんて、ないわ。
- 聞かれなくても、パパには何でも言うもの」
- 「えー?!」
- 「ローラは、真面目だから……」
- 「でも、信じられない!
- 何でもって、本当に何でも?」
- 「ええ。
- あったことも、考えたことも、みんな言うわよ」
- 友人たちは、一様に目を丸くした。
- 「……ねえ、ローラ、あなたって……」
- 派手な彼女が、なんだか変に意地の悪い口調でささやいた。
- 「ファザコンなんじゃなあい?」
- 座にいた友人たちは、半分の非難と半分の同意を表情に浮かべ、そっと私の顔を盗み見る。
- 私は、きっぱりと言った。
- 「そうよ。
- どこがいけないの?
- 私のパパ、とっても素敵なのよ」
- 彼女は、わざとらしい、呆れ返った声で叫んだ。
- 「それってとっても、あぶないわよお。
- それに、そんな素敵なパパなら、きっともてるわよ。
- そのうち、新しいママが来たりして、泣くことになるんだから」
- 私は、彼女をにらんだ。
- 気弱な友達は、泣きそうな顔で私たち二人を見ている。
- その時になって、私は彼女の両親が再婚同志であり、彼女の今の母親が、義理の母であることを思い出した。
- 私は、茶目っけのある笑いとともに言ってやった。
- 「……そうかもね。
- でも、私、負けないもの!」
- 一瞬の後、彼女は肩をすくめて笑い、他の人達も安心したようにそれに加わった。
- 彼女たちは、私が冗談でその場を納めたと受け取ったのだ。
- でも私は、一緒に笑いながら、冗談であるものかと思っていた。
- 父はけっして再婚などしない。
- 父は、母と私を愛している。
- 今は、私だけを。
- 私のこの考えは、誰が聞いても思春期特有の強情に思われたかもしれない。
- しかしこれは、確信だった。
- 私の生活は友人たちのそれとは、ずいぶんと違っていた。
- 母がいないのが最大の理由だったが、私が成長するにつれ、どうもそれだけではないことに気付いた。
- わずかなお手伝い以外に、人を雇おうとはしないこと。
- 親類がまったくいないこと。
- 父の社会的地位にもかかわらず、来客をはじめ、社交生活がほとんどないこと。
- つまり私と父は、最低限の社会生活の他には、この世でたったふたりで暮らしているのだった。
- これは、ロサンゼルスに戻ってくる前と同じだった。
- そして、私はロスに帰る前と同じように、この生活に満足していた。
- ハイスクールの間中、とうとう私は一度もデートをしなかった。
- 何度も誘われたのだが、私には同年輩の男の子たちが、どうしても子供にしか見えなかったのだ。
- 父の言うとおりロスをあきらめ、シスコの大学に進んでからも、私はデートの誘いをかたっぱしから断った。
- 休みのたびに車を飛ばして帰る私に、友達はロスに恋人がいるのだろうと噂していた。
- 私は、否定しなかった。
- 私のつもりとしては、その通りだったのである。
- 父は、そんな私の態度に、時々困った様子をしていた。
- 故意に避けるとまではいかないが、帰るたびに「お前はお前で暮らせばいいんだ」と弱い口調でつぶやいた。
- でも、私は平気だった。
- 父は私が邪魔なのではなく、心配して言っているのがわかっていたからだ。
- 私が去って以来少しやつれた父の顔を見ながら、私ははっきりと言ってあげる。
- 「パパ、私を追い払おうとしても、駄目よ。
- パパはもてるから、私がママのかわりにみはっているの」
- 父は、以前より明らかに影が濃くなった頬に、ますます弱々しい苦笑いを浮かべる。
- 私だって、父が心配なのだ。
- 今の父には、仕事しかない。
- 私がいなければ、父は働き過ぎて、体を壊してしまうだろう。
- やはり、父にも私が必要なのだ。
- それははっきりと、わかっている。
- 私は、たったひとつだけ母の形見を持っていた。
- 昔、父が母にプレゼントしたというブルーのコンパクトである。
- 私はその小さな鏡に写る、母とそっくりだという顔に向かって話しかける。
- 「ねえ、ママ。
- 私、パパが大好きなの。
- 医学部に行ったのもね、パパと同じ医者になって、パパのお仕事を手伝ってあげたいからなの。
- 私ずっと、パパと一緒にいるつもりよ。
- ママも、私だったら許してくれるわよね」
- 金の髪と青い目をしたその顔は、優しくうなずいてくれるのだ。
- [CHAPTER 11]
- リクター・ハリスは、ロサンゼルス総合病院の院長の椅子に着いた。
- 病院のスタッフや患者も、この高名で温厚な医師が頂点に座ることを喜んだ。
- リクターは、院長になってもメスを握り続けた。
- 心臓外科医としての彼の腕を頼んで、各地から患者が集まって来た。
- 彼のメスは、多くの人の命を救った。
- リクターは、脇目もふらずに働いた。
- 仕事に打ち込めば、忘れられるかもしれないと思っていた。
- しかし、それは不可能だった。
- 彼の内部の闇は、ローラがいなくなった時から沈黙していた。
- 不気味な沈黙だった。
- 何も語らないかわりに、わずかずつ膨らんで行く。
- 常に息づき、微かなうごめきを続けながら、リクターを序々に犯していくのだ。
- 今までもずっとそうだったように、メスを握る時にはのど元に、暗い固まりが這い上がってくる。
- リクターのメスは、その固まりに急かされるように患部を走り、切り裂いた。
- 熟練した指が、血溜まりの中で滑らかに動き、針を操った。
- しかし、手術が終わっても、その固まりは消えない。
- 服を着替えたリクターは、院長室の椅子に崩れこむ。
- まるで、溺れているようだ。
- 内心の闇があふれ、腐った海のように自我を飲み込もうとしている。
- 息が、できない……。
- 長い年月、レノーアとローラのためだけに闇と戦ってきたのだ。
- 今、一人になった私は、闇に抵抗する手段を持たない。
- 溺れる……
- 飲み込まれてしまう。
- 開け放しのドアを通じて、秘書が心配そうに彼を見ている。
- 「先生……。
- お疲れでいらっしゃるのでしたら、執刀は他の先生にお任せしたらいかがでしょうか」
- 「いや……」
- リクターはハンカチで汗をふきながら、ようやく答えた。
- 「私が執刀した方がいい時は、できるだけやりたいんだ。
- ……別に、スタッフを信頼していないわけじゃない。
- ただ……」
- 「ええ、先生がなさった方が時間も短いですし、余後もいいのは先生方もわかっていらっしゃるのですが。
- ハリス先生は、院長先生としてのスケジュールでもお忙しいのですから、あまりご無理をなさらないでいただきたいのです」
- 「ありがとう」
- リクターはふいに顔を上げ、にやっと笑った。
- 秘書は院長の笑顔に、いつもの温かさではなく、どす黒い冷たさを見て驚いた。
- ローラは休暇ごとに、元気な姿を見せた。
- 少女から大人の女性に移り変わる時にある彼女は、そのたびごとに、輝きを増していた。
- 「……パパ、少し痩せたんじゃない?」
- 「そんなことはないよ。
- 独身生活を、堪能しているからね」
- おどけた口調は、かえってローラの眉をひそめさせた。
- 「あまり無理をしないでね」
- 「ああ、わかっているさ」
- リクターは、ウインクをして見せた。
- ほっとしたように微笑んだローラが席を立った後、リクターは目を堅く閉じた。
- 1997年、某日。
- 院長秘書は、院長室の中で、奇妙な物音を聞いた。
- それは、笑い声だった。
- 先刻、手術を終わったハリス医師が、白衣のまま入って行ってから、秘書は心配のあまり何度か声をかけていた。
- 院長の顔が、まるで別人のように歪んで、しとどな汗に濡れていたからである。
- 秘書の、大丈夫ですか、という声に対して、院長は大丈夫だと答えるだけで、他に何の物音もしなかったのだ。
- 秘書は、笑い声を聞いて棒立ちになった。
- 院長の声では、なかった。
- 他の誰もいないはずのオフィスから聞こえてきたその声は、地の底から響くように低く、また、人間の声とも思えないほどひび割れていた。
- 秘書はドアに駆け寄って、力いっぱいノックした。
- 「先生!
- ハリス先生!
- どうなさったんですか、先生!」
- ドアには、鍵がかかっていた。
- が、すぐに開けられた。
- 秘書は、息を飲んだ。
- ドアの向こうには、奇怪な仮面のような笑みを浮かべ、ピストルを構えたハリス院長が立っていたのである。
- 銃弾が秘書の胸に炸裂し、血潮を撒き散らした。
- リクターは、「ノー!!」と叫んだつもりだった。
- しかし、彼の指は、ためらいもなく引き金を引いていた。
- 有能で、いつも彼に忠実だった秘書は、あっけにとられた表情のまま床に倒れた。
- 見開いた目が、みるみるうちに光を失う。
- リクターは再び、ノー、とうめいた。
- 同じ口から、「イエス!!」という満足そうな声がもれた。
- 唇が引きつり、邪悪な含み笑いが続く。
- 彼は、広がっていく秘書の血を大股に踏んで、廊下に出た。
- 敷きつめられた暗い臙脂色の絨毯が、そのまま血の川に見えた。
- 彼はいったん、エレベーターで階下に降りた。
- 正面玄関を入ってすぐに、待ち合いのホールがある。
- 診察をすませ、薬を待つ人々がちらほらと椅子に座っている。
- 車椅子の患者をいたわる看護婦。
- カルテを胸元に抱えた事務員が、すれ違いざまに、彼に会釈する。
- 彼は、ホールの中央に立ち止まると、白衣のポケットからピストルを取り出した。
- 椅子に座っている患者たちに、ひとりひとり無造作に弾を撃ちこむ。
- すでに、闇の声に体を奪い取られたリクターは、悲鳴をあげる。
- 重なるように、人々の悲鳴が響く。
- 驚愕の声をあげて、逃げようとする患者。
- 驚きのあまり、床に崩れ込み、動けなくなる事務員。
- 車椅子を押して、柱の後ろに駆け込む看護婦。
- 目の前が、真っ赤に染まる。
- 彼は冷静にマガジンを取換え、虐殺を続ける。
- 涙を流し、まだカルテを抱えたまま口もきけない事務員に、笑いかけながら引き金を引く。
- 身軽く柱をまわり、背中で車椅子を庇って震えている看護婦に、まっすぐピストルを構える。
- 「……せ
- ……先生
- ……どうして
- ・・・」
- まだ若い看護婦は、ロウのような色の顔でささやく。
- 「どうして……
- だろうねえ……」
- 彼は、また引きつった笑いをもらす。
- 引き金を引く。
- 倒れる看護婦を押し退け、頭を抱えて震えている車椅子の患者も、簡単に射殺する。
- 「先生!」
- 叫びが、ホールに響く。
- 振り向くと、警備員が銃を構えて立っている。
- 警備員はまだ、いつも穏やかな院長が、この惨劇を引き起こしたことが信じられない。
- 撃つのをためらっている。
- 彼は、にやにやと笑う。
- リクターは病院の壁が、ぐらっと揺れたように感じる。
- 銃を腰だめにした警備員の、背後に影が揺らめく。
- 「う……
- わわ……わ……」
- 闇から生まれた銀の甲冑が、警備員の両腕を押さえつける。
- 彼は、怯え切った警備員の顔に満足しながら、その胸に銃弾を撃ちこむ。
- 病院が、二重写しになってくる。
- リノリウムの廊下が石畳みになり、蛍光灯がシャンデリアと重なる。
- 彼は、悠々とした足取りで、廊下を進んでゆく。
- ここは、あの館だ。
- いや、違う。
- ここは、城だ。
- 館がモデルにしたという、東ヨーロッパにあった城。
- Dの、
- 城だ。
- 銃声に驚いた人々が、廊下に飛び出してくる。
- 彼の銃が、ためらいもなく火を吐く。
- リクターの目には、倒れ付す人々の背に、体を貫き通した鋭い杭と棘が見える。
- 抵抗しようとする者は、甲冑や影が押さえつける。
- 彼は無敵だ。
- Dの城の中では、すべての人間がDの前にひれ伏すのだ。
- ベッドの患者。
- 数時間前にリクターが執刀して、ようやく命を取り止めたばかりの患者にも、彼は容赦しない。
- リクターが縫合した、まさにその場所を、彼の弾が引き裂く。
- やめてくれ、と、リクターは叫ぶ。
- 跳ね返った血が、リクターの白衣を染め上げてゆく。
- 『これが、お前の求めていたものだ』
- 「違う!
- 私は、医者だ!
- 人の命を救うために……」
- 『お前のメスを動かしていたのは、Dの血なのだ。
- 生きている人間の血は、お前の指に、心地好かっただろう』
- 「違う!!」
- 『そうなのだ。
- お前のメスは、杭の替わりだったのだ』
- 「やめてくれ、どうか、もう……」
- リクターが信頼していた医師たち。
- 看護婦。
- リクターを信頼していた、多くの患者たち。
- 許しを求めて泣き伏す者たちを、薄い笑いを浮かべたままの彼は、撃ち殺していく。
- 『やめてくれだと?
- お前は、何を言っている。
- これを行っているのは、お前自身だ。
- お前の中のDの血が、本当に目覚めたのだ。
- これは、お前の望んだことなのだ。
- しかも
- ・・・』
- 彼は再び、自分のオフィスに戻っていた。
- 秘書の死体を回り、デスクに歩み寄って、電話を取り上げる。
- 『まだ、終わってはいない。
- ここからが、真の目的なのだ』
- ロサンゼルス警察は、蜂の巣をつついたような騒ぎになった。
- ダウンタウンからの通報は、最初、いたずらだと受けとられるほど悲惨なものだった。
- しかし、とどろいた銃声が終わるか終わらないうちに、犯人自身からの電話が入ったのだ。
- 「……私の娘、ローラ・ハリスをサンフランシスコから呼び寄せろ」
- 「な……
- なんだと!?」
- 「ローラを呼べと言ったのだ。
- 病院内には、まだ大勢の患者がいる。
- 患者を殺したくなかったら、娘を一人でこちらによこせ」
- 「バカな真似はよせ!
- 何が目的だか知らないが、こんなことをして……
- おい!
- おい!」
- 刑事は、蒼白な顔を上げた。
- 「切れてしまった。
- 電話線を切ったらしい。
- もう、何も聞こえない」
- 「いったいぜんたい、何でこんなことが起きたんだろう。
- とても信じられん」
- 「狂ったんだ。
- そうとしか考えられない」
- 口々にわめく刑事たちの中で、腕を組んで黙っていた初老の刑事が、重い口を開く。
- 「娘に、連絡しよう」
- 他の刑事は、いっせいに彼を見る。
- 「まさか、奴の言う通りに、一人でやるって言うのか?」
- 初老の刑事は、溜め息をつく。
- 「病院は、広い。
- 勝手知ったる奴が、病院のどこにいるのか、我々には見当もつかん。
- だとしたら、簡単に踏み込むわけにもいかないだろう」
- 「それにしても……」
- 「どちらにしても、娘を呼んで、説得させよう。
- サンフランシスコと言ったな。
- おそらく、大学だろう。
- もう、そのくらいの年齢になっているはずだ」
- 「……知っているのか!?」
- 刑事は再び、暗い溜め息をもらした。
- 「ああ。
- 少し、な」
- 私は、ただ前を見ながら、アクセルを踏んでいた。
- 頭の中は、真っ白だった。
- 私は、大学のカフェテリアでそのニュースを聞いた。
- テレビの番組の途中で、突然挿入された緊急ニュース。
- ロザンゼルス総合病院で、惨事発生。
- 病院長、患者と職員を次々と虐殺。
- 病院は、血の海。
- 犯人のリクター・ハリスは、人質を取って立てこもっている様子。
- 私は、その場に凍りついた。
- 回りにいた友人たちが、私を避けるように立上がり、後ずさるのが目の隅に入ってくる。
- テレビは、見慣れた病院の門と、玄関を映し出す。
- 父の写真を映し出す。
- 眩暈が、私を襲う。
- ざわめきが遠くなり、かわりに甲高い金属音が頭に鳴り響く。
- 犯人は、
- 病院長の、
- リクター・ハリス。
- ばかな!!
- 私は、立ち上がっていた。
- 気が狂いそうだった。
- 現実とは思えなかった。
- 悪い夢だと思った。
- ふいに、名を呼ばれた。
- あわてふためいた様子の大学職員が、カフェテリアの入り口で私の名を叫んでいた。
- 私はよろめく足で、そちらの方に歩いていった。
- 人々はまるで、化け物を見るように私を見、私を避ける。
- 職員は、ひったてるように私の腕を掴んだ。
- 事務室には、大勢の人がいたように思う。
- ひきずりこまれるように、私が事務室に入っていくと、皆が一瞬に黙った。
- 「……ローラ・ハリス」
- 誰だかが、うめくように言った。
- 「電話が、入っている」
- 私の手に、受話器が押し付けられる。
- 私はそれを耳にあてる。
- 『ローラ・ハリスさん?』
- 「……はい」
- 『ロサンゼルス警察です』
- 赤いテールランプ。
- 私は、前の車を追い、追いつき、追い越す。
- パパ。
- パパが、私を呼んでいる。
- 1マイル、
- 1マイル。
- 私は、ロサンゼルスに近付いている。
- パパに近付いている。
- 私は、
- 一人で、
- 病院に入っていった。
- [END]
Add Comment
Please, Sign In to add comment