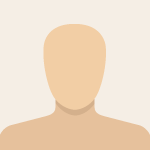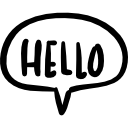Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 始まりが ない。 それは そこに あるだけだ。 空港から モーターウェイ沿いに 西側の 幹線ルートを 通って 行くと、 すでに そこは 郊外。 チュ-ドル様式を 真似た 家の 梁の リボン。 あらゆる 種類の ファックや いざこざを 隠す 窓際の カーテン。 この場所の 狭さは あらゆる面に はっきりと 表れている。 それは 多分、 まだ 髪の 油分に、 毛穴に、 僕が <東京>を 引き摺って いるからだろう。 でも エセ都会の ハマ-スミスに 着く頃には、 去った 場所に 対する ホームシックに 駆られる 自分に 気付き、 出来るだけ 早く そこに 戻りたいと 思う。 早い ペースを 保ち、 事を 済ませたい。 雨が 降る中、 <タクシー>が ガタガタと 音を 鳴らして 止まり、 僕は 生まれ育った 家の 外で 降りる。 家は 正面が 平らな、 3階建ての よくある 四角い レンガ建てで、 テムズ川の 南にある、 ランべスの 奥まった 場所に 位置する。 18世紀に よく見られた ロンドン ストックレンガと 真っ白な 窓が <2>つずつ 交互に 建物の 前部に 積み上がる。 フロントドアに 続く 階段は 地下の キッチンの 格子窓と 小路を つなぐ。 全て、 <真っ黒>な 鉄の 柵の 向こうに 位置している。 門が <クジラ捕りの歌>の ように 鳴る。 ベルを 鳴らすと 母親が 玄関に 出る。 軽く 抱き合い 彼女の 頬に キスを する。 <60>歳だが 年より 若く 見える。 彼女の 肩に 手を 置き、 見つめて 表情を 伺った。 「親父は?」 と聞くと 彼女は (少し恥ずかしそうに) 「うーんと、 仕事場にいるわ」 と言う。 これには 驚いた。 僕は 着替えが 入った 鞄を 正面玄関に 放り置く。 母は 家の 中を キッチンに 向かって 歩きながら 肩ごしに、 2日前には 父親が <人>と話も 出来ない 状態で 床に伏し、 死を 真近に していたのだと 話す。 医者が 来て 血圧と 心脈を 計り、 父親が 死の 瀬戸際に 立っていると 宣告を したのだと。 父親の 特異な <痴呆>は 会話、 説明、 人と 通じあうことを 不可能に した。 彼は 単に 眠りに 入っただけ だったのだ。 彼女は 医者が 去った後、 僕の ホテルに 電話を して、 メッセージを 残した。 そして 今、 この 頑固な 老人は 起きて 動き回り、 仕事場に 座っている。 キッチンを 通り抜け、 階段を 下り 庭へと 歩いていく。 雫を 落とす 冬木の 下を 20ヤード程 行くと そこに 仕事場が ある。 小さな コンクリート 作りの 一階建ての 建物で、 ドアの 両側に 四角い 窓が ある。 平らな 黒い 屋根が ついている。 家から その 小さな 建物の 角に 電話線が 引かれている。 雨がふり、 <水>が ねじれた 黒い 線から 粒と なって 落ち、 2月の ロンドンの 灰色の 光りを 受けている。 ミニチュアの 木の 世界を 逆さに 写す 小さな レンズ。 僕は 小雨の 中を、 芝生に 埋もれ、 草に 囲まれた 丸い 石畳の 上を 歩いて行く。 その いくつかは 深緑色を している。 ペンキで 塗られた ドアを 押して 馴染み深い 仕事場に 入って行く。 父親は ブナ木の 大きな ワークベンチの 一つの 端に 腰掛け、 窓から 雨を 見ていた。 ノミは きっちりと 大きいものから 小さいものへと 順番に、 壁に 取り付けた 木製ラックに 並べられている。 淡い 緑の のこぎりが 部屋の 一隅に あり、 天井の 長さに 沿って 3つの フッドが 置かれ、 旋盤が あり、 そして 2つの キャビネットには 他の 道具が しまってある。 様々な サイズの かんな、 かなづち、 のみ、 定規、 曲尺の セットの 箱。 大きく 柔らかな ほうき、 火の 付いていない 鉄ストーブの 上に ある 接着剤の 容器。 壁の 上の 方には <赤>く 光る 電気ヒーターの バーが 2本。 淡い 色の おがくずが、 鈍く 暗い 色の 寄せ木細工の 床の ブロックの 間に 挟まっている。 接着剤や 樹液、 木製棚や 雨、 そして その場所の <匂い>が 僕を 瞬時に 少年期に 引き戻す。 僕は 同じ 戸口に 立ち 彼が 仕事を するのを 眺める。 かんなを 引く 長い ストローク、 リズミカルに 生木を 操る 様子。 奇跡的な 程 簡単に 直角な 形が 彼の 手を 通して 表れ、 金具で 留められ、 接着され、 解き放ったれ、 磨かれる。 テーブル ひとつに しろ、 きめ細かに 完璧に ヤスリが かけられ、 自然な 良質感が あり、 角の 継ぎ目は ぴったりと していて、 接続部分、 仕上げ、 そして 堅固さは まるで 柔らかくて 素晴らしい 機械に よって 仕上げ されたかの ようである。 僕は 中に 入って 行くが、 父親は 挨拶を しようと 振り向きは しない。 僕が そこに いることを 知らないかの ようだ。 いや、 彼は 気づかない。 気が付いて いないのだ。 仕事場を さらに 中に 入り、 棚の 端に 置かれた 木ずちを 手に 取る。 手に その 重みを 感じる。 空から 地上へと 落ちる 大量の 雨粒を 眺め続ける 彼の 後頭部を 僕は 見る。 彼の 細くなった グレイの 髪、 ピンク色の 肌、 ツイードの 服の 中で 小さくなり、 年老いた 彼。 「親父?」 10度程、 振り向く。 「庭に 激しく 雨が 降っている。 地上は 水浸しに なる」 と 彼は 言う。 これは 事実の 陳述。 卒中を 煩ってから このように なり、 特異な 状態に なった 彼の 会話は、 このような 事実の 陳述と、 奇妙な 質問で 成り立つ。 彼の 家具を 作る時の 鋭さ、 単刀直入さが 彼の 物の 感じ方へと 形を 変えたかの ようだ。 父親の 言葉が 発せられるとき、 そこには 彼の 手によって 組み立てられた 家具の 要素に 見られる ように、 互いの 距離の 取り方に おいて、 同様の 正確さ、 正しさが ある。 そして 彼は もう 何も 言わない。 そして 僕達は 庭を 通り 家へと 戻る。
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement