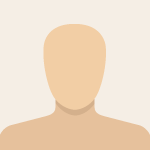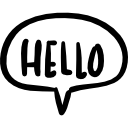Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 小学館eBooks
- 妖姫のおとむらい
- 希
- イラスト こずみっく
- 目次
- プロローグ
- 第一話「風鈴ライチの音色」
- 第二話「焼き立て琥珀パンの匂い」
- 第三話「ツグミ貝の杯の触り心地」
- 第四話「ホロホロ肉の歯ごたえ」
- プロローグ
- 古本が、でたらめな高低差で部屋の畳たたみに直接積まれている。
- 時代がかった六畳一間の貸し間で、よく見ればその大量の古本以外は家具調度に乏とぼしい。
- 間借り人は万年金欠気味の男子学生、比ひ良ら坂さか半なかば。
- 彼がその懐ふところ事情の厳しさを押しきって卓袱ちやぶ台だいに並べたのが、バラエティに富んだ、というより統一性に欠ける山盛りの料理だ。
- ニスの剥はげかかった卓上には、鱧はもと里芋の汁物の椀わんがある。
- アンディーブと貝のサラダの皿も置かれた。
- ピラフと豚カツとスパゲッティを一緒くたに盛ったプレートも並んだ。
- それらが所狭しとひしめいた。
- 「ほお。京料理に、フランス料理風のがあり、そちらのは確かどこかで、見聞きした。確か『トルコライス』とか」
- 積み上がった古本に雅びやかな物腰で腰掛けた笠かさ縫ぬいが、小首を傾かしげる。
- 姿形は華きや奢しやな少女としか思われない彼女。
- なのに、身にまとう気配は、優ゆう艶えんで、練れて、不思議に人間離れしていた。
- 「どれも美お味いしそうだこと。ずいぶんおごったものだわえ。こんなにもたくさん」
- 「もちろん俺ひとりの分じゃない。君の分もあるからだ」
- 普段は呑のん気きで眠たげな面つらつきをしている半なのだが、今は何やら思い詰めた顔色だ。
- 「またぞろ、俺はここにいられなくなってきたっぽい。それを今から確かめる。まあ君も付き合ってくれ。そして俺に教えてほしい。この食い物が、どんな味してるのかってことを」
- 奇妙な言い草だが、半は真剣そのものといった顔で、いただきますと手を合わせた。
- 卓上の料理を、挑んでいくといった方が良さげな勢いで食べ始める。
- 「……ああ、またそういう頃合いに差しかかるのかや」
- 笠縫も何事か察した様子で半に頷うなずき返す。
- さっそくお相伴にあずかる彼女の箸はし遣づかいと礼儀は、場違いなほど水際立って優雅だった。
- まず始めに鱧と里芋の汁物。
- 入念に骨引きした鱧を注意深く湯がいて葛くず湯ゆに浸して、里芋の練り物とししとうと薬味を添えた温かなもの。
- 笠縫の口の中で、淡白でいて奥深い味の鱧の身と柔らかな芋が、丹念にとった出だ汁しの春の陽射しのような温ぬくみに溶けていくかのよう。
- 「とっても美味しい。鱧は夏が旬なり、薄造りにその妙がある、とはいえ、こういう温かな品もわたくしは好きさ。お口の中に春が来たようだもの」
- 口中の幸せに、自身が春の女神のように目元を和らげる笠かさ縫ぬいに、一方半なかばはといえば───哀し気な面つらだった。
- 「そうか。それはよかった。ちなみに俺は……なんにも味がしないんだ」
- 「あら」
- 笠縫にはほのぼのと味わい深い汁物が、半には何も味が感じられなかったのである。
- 一声発しただけで、笠縫はさして同情も示さず、今度はサラダを取り皿に分けた。
- バルサミコ酢のドレッシングを利かせたアンディーブの切片が、笠縫の口内で丁てい寧ねいに噛かみ砕かれる。
- 酸っぱく青い匂い、淡い苦み、貝柱の旨味も加わり、胸ときめかせるほどの美味だ。
- 「これも素す敵てきじゃ。香りがさっと強くなびいて、けれどすぐに薄れて舌を洗ってくれました」
- 「そうか。それはよかった。なお俺は……いっさい匂いも感じられない」
- 笠縫には風味爽やかなサラダだったのに。
- しかし半の嗅覚は全く反応しなかったのである。
- 次に控えたのはトルコライス、大人の男でもたじろぎそうなボリューム満点の飯と麺と肉の集合体だ。
- 笠縫はその華きや奢しやな見た目からは信じられないくらいの健けん啖たんぶりを発揮した。
- あくまで悠然と、けれど着実に肉と炭水化物を平らげていく。
- そんな彼女と裏腹に半は。
- 「こっちも、味も匂いも食感も感じられないときた……」
- 一口二口で、諦めたようにナイフとフォークを置いてしまって。
- 「せっかく用意したのにやっぱり無駄になった。どれもこれも好物だったのに。俺、またどっかに行かないといけなくなったよ、笠縫」
- ───この半という青年、その茫ぼう洋ようとした外見に似合わず奇怪な病に取り憑つかれている。
- それは同じ場所に長く留まり続けると、徐々に味覚が失われていくという宿しゆく痾あだ。
- 食べ物に関してだけ、味も匂いも食感も減少し、しまいにゼロとなる。
- そうなってしまう間隔はその時々でばらばら。
- ただこれがひとたび彼に訪れてしまうと、非常なるストレスと虚むなしさをもたらすのだ。
- 精神的苦痛と焦燥感に苛まれ、いてもたってもいられなくなる。
- こうなってしまうと、半はどこか他所、ここではないどこかに行ってしまうほかにない。
- 旅先ならば、味覚も回復して、食べ物の味を味わうことができたから。
- ただ、そんな奇病に衝つき動かされての道行きが、半と笠縫の出会いをもたらした、ともいえて───
- 半はその時のことを追想しつつ、そっと彼女を見やれば。
- むらむらと催もよおした感情が半にある。
- それは、自分には味の感じられない食べ物を満喫している、彼女へのやっかみだったろうか。
- いや、そんなものだったのなら、まだいい。
- それは、妖姫への、抑えがたい───食欲。文字通りの飢え。飢き餓が感。
- こっそりと膝ひざでにじって卓袱ちやぶ台だいを回りこみ、笠かさ縫ぬいとの間を詰めながら囁ささやきかける。
- 「なあ笠縫、覚えているか。いつか君と食った、あの風鈴ライチ。あれは美う味まかったなあ」
- 「覚えていますとも。まったく、あの時のお前さまときたら……会うなりわたくしをかき口く説どいてきて」
- 「ツグミ貝の酒も、銀河キノコのグラタンも何もかも。君と会ってから、いろいろ変なところに迷いこんだ。あれこれ不思議で美味いものも食った。それでだ、笠縫」
- 言葉を切って半なかばが持ちかけた願いは、異常としか言いようがなく───
- 「……そろそろ一口くらい、君を食べてもいいだろう……?」
- 出会ってからというもの、半が笠縫に対して抱いだいているのは、この食欲。
- 彼自身おぞましい欲望だと理解しつつも抑えられない。それくらい激烈だった。
- 卑いやしく伸ばされた半の手は、妖姫の玲れい瓏ろうかつ冷酷な声で、宙を虚むなしく掻かくに留まる。
- 「わたくしはまだ食べている最中。それを邪魔いたすおつもりとでも───?」
- 妖姫から吹き寄せる、凄せい艶えんなほどの迫力に、半はすごすごと引き下がるしかなかった。
- ───満たされない食事の後片づけを終えて、青年は旅たび支じ度たくを始める。
- この町から暫しばらく離れないといけない。
- どこか他所、遠いところで過ごして、舌に味が戻ってくるまでは。
- そんな半に問いかけた笠縫は、彼の身を案じているとも、また他人事のように無関心とも、どちらとも言えない態度を見せて。
- 「お前さま、どちらかなりと行くあては?」
- 「あるかそんなもん。いつものように気分任せの風任せだ。それで笠縫、君はどうする? 一緒に行くか? 来てくれるのか?」
- 「───さて」
- 一
- 光が、高窓のステンドグラスを透過し、教会建築の天井じみた弓形の連つらなりや装飾的な鉄細工のベンチの列に投げかけられ、童画のような色合いを醸かもし出していた。
- ───丸天井の大きな広間である。忘れられた古い駅舎のような。
- 郷愁を誘うような静せい謐ひつに満たされていたが、それをかき乱して怪音が湧き上がった。
- その聞き苦しく、地鳴りにも似て凄すさまじい音は、広間に立ち尽くすたった一人の青年の腹の中からなのだが。
- 誰よりもこの浅ましい腹の虫に辟へき易えきしているのは、この青年、比ひ良ら坂さか半なかば、彼自身だった。
- (ああもう……腹の虫め。また聞きそびれただろうが)
- 広間のあちこちに頭こうべを巡らせ何事か探っている風だけれど、別にこんなところで食い物の匂いなどを嗅かぎ取ろうというのではない。
- たっぷり一日とそれ以上は食事もとらず過ごした半が、ひもじさに苛さいなまれつつも待ち焦がれているのは───
- きり……ぃぃぃん───
- ───今、たった今。腹の音が偶然収まり、耳に沁しみるほどの静寂が戻ってきた瞬間に。
- あまりにも澄んで、涼しい、甘やかな音ね色いろだった。薄はつ荷かのリキュールを色ガラスに仕立て、薄く硬いベルを作り、白金のマドラーで弾いたならこうも鳴ろうかというくらい。
- ───ちりぃ……ぃぃぃん───
- また鳴り来る音色の美しさ、思わず聞き惚ほれ、つい棒立ちになってしまいそう。
- けれど半はほとんど耳から引っ張られるように飛び出した。
- 「こっちか!」
- 大広間の向こうの観音開きの大扉へと駆け出す。
- 妙なる音色は扉の外から、と聴きつけ走る半の、眼は物に憑つかれたように血走った。
- 腹の音も復活し、むしろ深刻さはいよいよ増した。
- あんなにも清さやかな音色なのに、半には感かん銘めいや陶とう酔すいよりも飢き餓が感をもたらすのである。
- ……なるほど彼が、あの清涼な音色に引き寄せられるようにして、貧乏旅行の所期の道筋ルートを外れ、この奇妙な空間に入りこんだのは事実だ。けれど───
- (だいたい俺は、どうやってあそこを通り抜けられたんだ?)
- そもそもからして、と駆けながら振り返れば、広間の壁の床近くに開いた一つの穴。
- そのサイズは鼠ねずみの巣穴大。だが半なかばはそこを潜くぐってこの大広間に入りこんだのである。
- それまでの記憶は確かにある。意識に断絶もない。
- 山越えしようと歩いていた峠とうげ道みち、途中であの音ね色いろを耳にした途端、強烈な飢えに襲われふらふら引き寄せられて道を外れ、廃トンネルに出くわし、潜り抜けて今に至る。
- で、戻れなくなった。理不尽としか言いようがないが、彼の潜った入り口は奇ッ怪な一方通行だったと考えるほかになさそうなのだ。
- (引き返そうにも、あれじゃあな……)
- まあいずれにしても、あの涼やかな音色に飢えを刺激され続ける限りは、半が引き返すなど有り得なかったろう。
- 不思議な広間を猛進して一直線、扉口を跳んで跨またいで、半は次の瞬間に、白光に呑のみこまれて目が眩くらんだ。が、頬ほおを乾いた薫くん風ぷうが撫なで、すぐに視界も慣れてくる。
- 半が目にしていたのは、草原と木こ立だちの、ガラス絵のように明めい瞭りような景色と。
- そして、青草の上、空中に浮かび、流体じみた滑らかさで身をくねらせ遊泳している、半透明の大きな魚たちと。
- 二
- 大広間を外から顧かえりみればそれは、淡黄色クリームと橙だいだい色の丸屋根の、古びた天文台じみた建物で、周りの草々と木立の明るい緑の中で、外国の焼き菓子にも見えて美お味いしそうな様子。
- 明めい媚びな風光であるが、半としては眉まゆに唾つばして眺ながめたい気分だったのだ。宙を泳ぐ魚はもちろんのこと、菓子細工めいた天文台まがいの建物も。
- さてこの半だが───陽射しの下に置いてみると、身なりは長旅にくたびれ、飢えた目を晒さらしていても、どこか眠たげな面つらして暢のん気きな、妙に落ち着いた風を漂わせる。
- ……などと言えば、旅慣れして物の道理にも通じたひとかどの人物にも聞こえるけれど、なにそんな大した青年ではない。
- この青年、もはや病の域にまで達した「放浪癖」の持ち主であり、一つ処どころに長く留まっていられない。そんな奇癖の故ゆえに、全国をしょっちゅう旅行して回っている、というだけの話。
- それも大して金もコネもない一介の学生であるため、路銀を絞った貧乏旅行というのになるのが必然で、ために昨日から食事を抜いていた───
- 丸屋根の建物の前に佇たたずんだ半の視界に広がるのは、高原の草花映はえる草地と、その果ては木立茂った山肌という牧歌的な眺め。空気は涼しく草木の放つ芳香で味わい深い。
- どこか隠いん棲せい的な景色であり、こんな状況でなければ、逸はやる足も自然と緩ゆるまり、芳かんばしい空気の中に憩いこう気分にもなったろう。
- ───こんな状況でなかったならば。
- 胃の腑ふはまだ飢えにちりちり焙あぶられている上に、宙を泳ぐ魚という奇き天て烈れつな生き物が、わらわらと半なかばに集たかりつつある、という状況でなかったならば。
- 宙に浮かび、水の中にいるのと同じに泳ぐというだけでも、人に自身の正気を疑わせる代しろ物ものなのに加えて、まだある、常の魚と異なる点がまだ。
- この魚たちの体は薄灰色に透き通っているばかりか、その鱗うろこの上に様々な画像を写していたのだった。いずれもモノクロームの、古い写真と見えた。
- しかし半の中に、瞬時によぎって去ったのは、したたかとさえいえる感想だった。
- (こいつら、食えないか……?)
- 実はこの半、その乏とぼしい財布事情により、貧乏旅行の間に野山河川、浜辺磯辺であれこれと、普通人だったら尻込みするような物をあれこれし、飢えを凌しのいだことが何度もある。
- 世間一般からすれば相当な悪あく食じきと言えるものさえ腹に収めてきており、なんにしてもこの青年の直感は、食えるもの食えないものを見分けることに不思議に長たけていた。
- そんな食い気が今まさに発動して、半は写真の魚たちの、ガラス玉のような感情の窺うかがえない瞳ひとみを覗のぞきこみ、そして下した判断は。
- 「……だめだ。食えないなこいつらは」
- 魚たちが帯びていたのは、魚類の生なま臭ぐささなどではなく。有機溶剤が乾燥したようなにおいで、嗅かぎ分けた途と端たんに半の中に、喰えたものじゃないという直感が降りる。
- と言うより、彼らは半が知るどんな生き物とも異なっているのだと、戦せん慄りつとともに意識する。
- 「というか、こいつらそもそも生き物か? ……魚……違う……ガラスの……乾かん板ぱん!?」
- ガラス質の魚体に、その表面に焼きつけられた画像、そこに古い溶剤のにおいと揃そろって、半の脳裏に浮かんだ単語は───乾板。写真乾板。
- 魚たちの無表情な面つらつきも手伝ってか、取り巻く輪が不穏な圧力を帯びる……。
- 「……囲むなよお前ら……」
- 思わず呟つぶやいた、半の言葉が引き金になってしまったのか。
- 一尾の魚が宙を奔はしった、半の鼻先めがけ、魂たま消げげるくらいの勢いで。
- 幸い、わっと手を前に翳かざすのが間に合って、魚は半の掌てのひらを突くに留まった。思ったよりは衝撃は軽い。それでも突かれた掌が傷でも負っていないかとあらためて半は、そこにモノクローム、セピアの色合いがべったり伸びているのに仰天する。
- 「う、わ、なんだこれ、毒でも吐かれた……え、あ、写真んん!?」
- 手には、いつともどことも知れぬ街角の画像が転写されてあり、今の魚の一突つきがそんな置き土産みやげを残していったとしか───
- 魚たちが乾かん板ぱんだと思えば、これは正しい機能なのではないかと思えなくもない。
- が、自分はこんなスナップなど注文していない、と掌てのひらを眺ながめてしばし愕がく然ぜんと固まった、そんな半なかばに次々と乾板の魚たちが殺到した。
- 「あ。よせ。やめろ、俺は印画紙なんかじゃない」
- どれだけ半が手を振り回して追いやろうと、魚の敏びん捷しよう性というのは人間の及ぶところではなく、たちまちにつんと突かれてはまた突かれ、青年は露出した肌と問わず服と問わず、体一面にモノクロームの写真を転写されて無惨なザマに。
- 「お前ら、よくも好き放題に……これ、洗って落ちるのか? いい加減にしろよな……」
- 毒づきながら包囲から逃れようとしても、魚たちは巧たくみに半を取り囲んで離れず、逃がさず、にっちもさっちもいかない膠こう着ちやく状態に、半はついに堪たえきれなくなった。
- 背のリュックからごつく頑丈なマグライトを手荒に引っ張り出して棍こん棒ぼう代わりに構える。
- 半がもう一度魚たちの包囲に隙すきを求めて走らせた目には、追い詰められた光が揺らいだ。
- (いきなり不意打ちかければ……それで退ひかなけりゃお前らが悪い。)
- 暴力沙ざ汰たは避さける性分の青年なのだが、我が身の脅おびやかされそうな際には沙汰の限りではない。半の内でぎりぎり敵意が高まって、限界までたわめた発バ条ネの勢いで弾け───
- 「滅多にないこと。今時この辺りに迷いこまれるお方がいらっしゃるとは、の」
- と、声の美しさ。頭上から注がれた。瑞みず々みずしいのに練れて成熟した艶つやが匂うよう。
- 叙情的センテイメントを通り越し、禁忌タブーのようでさえあり、その甘やかさ、もはや妖あやしいまでだった。
- 「ふへえ」
- 一方半は、聞くだに間抜けた調子で息が鼻から抜けて、身の内に溜めていた力を宙に吹き散らしてしまっていた。
- 頭上からその声が降った機タイミングというのが余りにも絶妙で、半の拍子リズムを完全に崩したのだ。
- 今にも乾板の魚に撃ちかけようとして踏みこんだ力は、踵かかとの辺りで暴発して半の膝ひざを崩して生まれたての子馬のようにしてがくがくがく。
- 「何な、誰だ、ど!?」
- 声も言いきれず聞き苦しい単音節に抜けるが関の山、それでも必死に見上げれば。
- ───銀の粉を撒まきながら風に流される、妖精郷の蝶ちようの到来か、とさえ見えた。
- 天文台まがいの丸屋根から、柔らかに宙をよぎり、半の頭上へと飛んで。
- ふわりと飛び、とんと降りた。半の頭のてっぺんに。
- 「きひん!?」
- 刹せつ那な、半は震しん撼かんした。
- そっと拳を落とした程度の軽やかな衝撃なのに、瞬間、半の身内を名状しがたい戦せん慄りつが貫いて四肢の先端にまで浸しん透とうして衝つき抜けていった。
- この衝撃が大気中を伝でん播ぱしたのか、あれほどしつこかったのが嘘うそのように、乾かん板ぱんの魚たちが一斉にさっと散っていって、もうあんなに遠くに。
- ついでに言えばその一踏みで、半なかばに転写されていた画像も一瞬でざっと消滅していた。
- そして半の頭上の何かは、彼の頭を踏み石にまた蹴って、もう一度宙をしなやかに舞う。
- 白しろ銀がねの軌跡を麗うるわしい円えん弧こに曳ひいて、膝ひざを淑しとやかに抱えこんで一回転し、スカートの裾にふわりと空気を含ませ、降り立っていたのは───
- 姿も、背丈も、少女と見えたのに、昼ひる日ひ中なかの夢のように、妖あやしく、不思議な。
- 髪は白銀、艶つややかな光の輪をまとう。眸ひとみは、黄こ金がねのような光沢を溜めた。
- 髪も眸の色もこの国の人々の黒髪黒い目とは大いに隔へだたっているのに、全体としての佇たたずまいは不思議と和の情緒を深く湛たたえてある。
- 「その魚たちは、誰かと見ると、つい写真を写したくなるのが性分でして、の。あまり怒らずにいてたまわれ」
- 白く、艶を帯びて肌にまとわりつくような衣装は、月の光を生き地じにして拵こしらえたものであるかのよう。踏み出した黒艶の沓くつは足元に、細かな光の粒を散らさなかったか、今。
- さっき頭を踏みつけにしていったのがあの足なのだと思うと、半の心中に何とも表しようのない内圧がこみ上げてくる。悔しさ? 不ぶ躾しつけを詰つめるべきなのか? 多分そうではない。嬉うれしさ? そこまでの被ひ虐ぎやく嗜し好こうは彼にはない。
- (───女の子? 外国人? でも言葉や顔立ちは日本の? それになんて綺き麗れいな───)
- 旅先で出会ったどんな絶景よりも半を魅了して、心が麻ま痺ひしたようにまともに働かなくなる。
- 「このものたちは、いつかの日、いつかの場所で。いろいろの景色や人々を写し撮りましたガラスの板、それが魚になったもので御座いますよ、お前さま」
- 悪びれることなど知らぬげに、滔とう々とうと銀ぎん糸しを繰るような麗しさはいつまでも聞き惚ほれていたくなるほど。もっと続きが聞きたいと、半にほとんど無意識に返事をさせたほど。
- 「あ、ああ知ってる。乾板だろう? フィルム式カメラの前の。もっとも今じゃそのフィルム式だってデジカメにとって代わら……れ……その───君は?」
- ただ喋り出したはいいが、語尾はやがて尻すぼまりに、無為な会話を続けるにはこの少女はあまりに麗しく整い過ぎている。
- 背丈は半より頭一つ低く、ずっと年下と思おぼしいのに、既に完成された女性としての優美を具そなえていたし、物言いもひどく時代がかっている彼女。
- その上極めつけの美少女というに留まらず、放つ気配がどうにも特異で人間離れしていた。
- これは少女の形にして少女に非あらざるものなのだと、どちらかといえば人を見る目がない半にして、相対したその一目で悟る、というより悟らざるを得ない。
- 血肉を具えた人間の女の子、というよりも、人界に時折降りて一時遊び、また還かえる精霊か妖あやかしなのだと、いっそ認めてしまおう、そう受け容れるべきだと半なかばは腹を括くくった。
- 半が自分が名乗る礼も忘れてまず相手の名を問うたのは、きっと、もうこの数瞬で彼女に魅了されていたからなのだろう。
- そうに違いない、それ以外の何がある。
- それは、きっと恋の始まり───
- ───本当に?
- 「問われて名乗るは烏お滸こがましゅうありますが、わたくしのことは笠かさ縫ぬいと、そう思おぼし召めしませ」
- 自分の背丈よりも長い、先端が半円の鉤かぎの形に丸められた、これも白い、石とも金属ともつかぬ材質の細身の杖を小脇にかいこんで(ああ半は、この時まで彼女がそんな杖を携たずさえていたことにさえ気づかずにいたほど、その美び貌ぼうばかりを見つめてあったのだ)。
- スカートの腰の辺りを軽く摘つまみ、淑しとやかに軽くおじぎした笠縫の、そのほんの短い仕草の中に、彼女の美質が凝集され零こぼれるよう。
- この名乗りには、かなう限り最高の礼を尽くして返礼するべきだったのだろうが───
- だが半には礼儀などお構いなしの肉体的精神的な最高潮クライマツクスが早くも到来してあった。
- すなわち急激な動どう悸きと発熱発汗唾だ液えきの不足、咽いん喉こう部の息苦しさに、思考の尖せん鋭えい化と硬直化、その他もろもろ突発的かつ抑制不可能な心身の変調だ。
- まあ要は、
- ───この笠縫が、欲しい───
- ───ただただ、彼女が、欲しい───
- ───もう、他のなにも、考えられない───
- という情動の暴発と、それに伴う炎のごとき発熱だ。
- だからきっとそれは、もう彼がこの妖あやしき笠縫に、一目で恋に落ちていたことの、紛まぎれもない証あかしで───
- ───本当に、そう?
- (笠縫……かさぬい……古く、ゆかしい響きだ……そんな神社が奈良にあったな……)
- 舌の上で、まず慎重に味わうようにその名前を繰り返し、しかる後にゆっくりと呑のみ下して胸の裡うちに深く沈めた、ら、もう駄目だった。
- つぅんと甘美に過ぎる痺しびれが鼻に抜けて脳を葛くず湯ゆのように煮に蕩とろかした。
- 名に籠こもった言こと霊だまの力だけで半は、自分が数瞬後に想いの丈全てをぶちまけるだろうと自覚して、それが避さけがたい事態なのだということも理解する。
- それは生まれて生きて二〇年余、かつてなく、初めての、暴風のような凄すさまじい衝動。
- 自分が自分自身に何もかも吹き散らかされる前に、必死で辛うじて、言葉を絞り出す。
- 「あ……俺は……比ひ良ら坂さかだ。比良坂、半なかばという───」
- せめて名乗り返してだけはおきたかった。自分が何もかもかなぐり捨てて、笠かさ縫ぬいに全てをぶちまける前に。じきにその瞬間がやってくる。そうなったらこの美しいものはどんな顔をするのだろう。
- 「ひらさか。なかば。───意味のあるような、ないような」
- 間もなく決定的な展開を迎えるだろうに、それをわざわざ次の瞬間に早めたのは笠縫だった。
- 「でもなかなかに、面白い、趣おもむきの深いお名前じゃ。これでわたくしたちは、名乗り合いましたな。誰かと名を告げ合うなど、幾久しいことか。ああ、これは悪くない。よい───」
- 微笑ほほえんだ、笠縫の。
- 鏡面のように光を弾く眸ひとみの、自分へ、柔和に、悪戯いたずらに細められていることが、どれだけ嬉うれしかったか、とか。
- 最上の細筆で引いたような唇が綻ほころんで、色いろ艶つやの華やぐとともにかすかに届いてきた匂びやかな息遣いに、蕩けそうになったり、とか。
- とにかく笠縫の微笑みそれだけで、半はもう、あの、ああ、その、どうなったかというと、こういう場合は言葉を長く連つらねるよりもただ一言がいい。
- 人として駄目になりました、と。
- 「どうしよう───!!」
- 輪郭がぶれたかと見るや、半の体が撃ち出される、笠縫へ。
- その瞬発力は目覚ましくはあったが、恋の相手に想いを告げるならば粗そ忽こつに過ぎる。
- というより決してやってはいけない見せてはいけない。
- 獣けものじみた構えに飛びかかっていくような真ま似ねなど、やってはいけない。
- 半開きの口の端はからよだれを垂らし、雫しずくを宙に振りまく様ザマなど、見せてはいけない。
- これは恋を寄せる相手にするやり方としては、完全に間違っていたけれど。
- 「どうしよう。君から凄すごく良い匂いがしている。嗅かいでるだけで下っ腹が痛いほど空っぽになって舌の根が引き攣つってくる。たまらない。頼む。先っぽだけ。先っぽだけでいいから。食いたい。それが駄目ならちょっとだけでも君のどこかをしゃぶらせちゃくれないか───!!」
- 半の、食えるものを見極める直観が、唸うなりをあげて全開に起動していた。
- 食うにはどう捌さばくかなど判りきっていた。この笠縫は、どう料理しても絶頂級に美味うまい食い物なのだと、半の直感が祝福の鐘を乱打していた。
- 笠縫はといえば青年の切迫した声が、まあ始めは恋の熱に分別失った若い騎士の求愛のようにも聞こえたのだろう、優ゆう艶えんに見守る貴婦人の如き眼まな差ざしだった、のに。
- 「先だけ、だの舐ねぶりたい、だの……強ね請だるにも、もうちと品というのを示せませなんだか」
- 半なかばの要求がえげつなく加速していくにつれ、眉み間けんの辺りに呆あきれ模様の薄靄かかり、片足の踵半歩引いて青年の駄目さ加減を承諾しかねる意を示した。
- まあつまり、半の訴えは、恋心を告げるやり方としては最低最悪だが、食い気を伝えるにはこれほど判りが良いアクションもなかったろう。
- ───はて、一体どこのどいつがど阿あ呆ほうが、半が笠かさ縫ぬいに抱いだいたものが恋心だと、さて無責任にも仄ほのめかしたものやら───
- いずれにしても笠縫という存在は、半にとって絶後だった。唯一にして無二だった。
- なにも半が潜在的喰しよく人じん嗜し好こう者しやだったというわけではない。
- 食人の禁きん忌きなど説かれなくても理性の基盤に刻みこまれている。正体はどうであれ少女としか見えない笠縫を食らおうとするなど、どれだけおぞましい行為なのかは承知している。
- ───承知、していたけれど笠縫という存在の前において、半の人としての倫理や禁忌など白熱した鉄に垂らした水滴のようにあっさりと揮き発はつしていた。それくらい圧倒的だった。
- 「そんな綺き麗れいに、物は言えない! 君が欲しい、どうしようもなく! 会ったばかりだけど!」
- 彼女に対して抱いた飢えは、あの涼すず音ねに感じた食い気などとは比較にもならない。
- 今となってはあんな食欲などは、まだ髄ずいが残った牛骨に覚える程度のそれに過ぎない。引き替え笠縫が半に及ぼしたのは、ブラックホールの超質量が及ぼす引力に等しく、どうして逆らえたものだろう。
- 「その台詞せりふを、食い気だけで申されて、ハイどうぞと差し許す、おなごがいるとお思いかや、お前さま」
- 「ちょっとだけでいい! なるべく優しくするから!」
- どうにも信しん憑ぴよう性せいに乏とぼしい形相で、最低な口く説どき文句を垂れ流しながら半は、はて一体なぜ俺は彼女に手が届かないのだろうと訝いぶかしんだ。
- 「よほどせっかちなお方じゃ。厭いや、とはっきり口で告げるまでもないことでしょうに」
- 見れば、笠縫が脇にかいこんだ白の杖が斜めに伸びて、半の額ひたいに先端がつがえられ、ために青年は進むもならず、足は虚むなしく空回りしているという塩あん梅ばい。
- やっと無駄を悟って駆け足を停める前に、笠縫がさっとつっかえ杖を外したものだからひとたまりもない。たたらを踏んで前にのめってしまい───
- 「げう!」
- 笠縫にすいと造ぞう作さもなく躱かわされ、半は顔面で溝を掘らんばかりの勢いでぶっ倒れる始末。
- 立ち上がろうともがく半、下が柔らかい草地であったからまだいいようなものの、それでも草の切れっ端や汁にまみれて随分見苦しい形なりとなり果てた。
- 「おお汚むさや汚や。風はこんなにも涼しゅう吹いておりますのに」
- 見苦しい半と麗うるわしい少女の対比への嘆息のように、草原に涼しい風がさらりと吹き流れる。
- 「風だけでは物足りぬとの仰おおせなら、ほら、鈴りんの音も足しましょう」
- 離れた木こ立だちに向けて杖を一振るい。するとなんと、まだ若い白しら樺かばが二列、生えたまま地を滑り、ざざざとこちらに近づいてきたのが、これは笠かさ縫ぬいの顕あらわす奇き特どくか、なんとも妖あやしげな。
- ───きりぃぃぃぃぃん───
- ───りぃぃぃぃん───
- ───きぃぃぃぃん───
- ついで涼やかに響いたのは風鈴の音ね色いろか、それを聞けば乾かん板ぱんの魚たちは半なかばに興味を失ったと見え、そちらの方へすらすら寄っていく。
- そこには、蔓つるにまさに鈴なりに吊つるされて、透き通った風鈴の幾つも連つらなって。
- 招き寄せられた白樺の木立から小立へと、結界のように張り巡らされていた。
- 一見透明なガラスの鈴のように見える。ただその音は金属質で、長く尾を引く。不思議な風鈴だった。
- ───そしてこれだった。半をこの地に招き寄せたのが、この音色だった。
- 魚たちはその風鈴の音色を楽しむ風に身を寄せ、最前までとうって変わって大人しい。
- 見れば一尾一尾好みが異なっているのか、身を寄せる風鈴が異なっていた。
- 「あー……これの音色だったわけか。不思議で、いい音色だな……やっぱり美味うまそうだ」
- 「また食い気ですか、お前さま。なれど随分お聡さといこと。それは確かに、元々は果物みずかしだったのだもの。とはいえこの鈴りんはその種なれど。実の方は、不思議で、夢のように美お味いしくて」
- 美味の追憶に耽ふける風ふ情ぜいの笠縫を、隙すきと見て、半、また跳びかかった。
- 懲こりるということを知らないというより、彼の笠縫への飢えの深刻さを物語る。
- 「殿方にそうまで猛烈に焦がれられるのは女として冥みよう加がなのでしょうが、御免こうむりますよ」
- 風に舞う蝶ちようのようにするりと躱かわし、半の視界から消え去る笠縫だったが、その匂いは消し難く青年の鼻の奥に刻み込まれていて、それを頼りにすれば追いかけられよう。
- こうして半と笠縫の、二人の追いかけっこは始まったのである。
- ───いや、もう一尾。群れから抜け出して、半の後を追い浮遊していった乾板の魚がある。その魚は、他と異なって、その身に画像が定着させられていない、灰色の無地。恐らくはまだ画像未感光の一尾だった。
- 三
- 眠気を誘うような優しい暗がりと涼しさを宿した木立が続く、その奥へ、白い裾すそが翻ひるがえる。
- 笠縫の、銀を融かして絹糸より細く伸ばした髪が、ついさっきは指先をかすめるくらいに、半は彼女のすぐ後ろまで迫ったのに。シャボンの泡か鷺さぎの羽毛か、ふわりとすり抜け遠ざかる。
- 追って追いかけ冷涼とした木こ立だちの中へ、道などあろうがなかろうが半なかばにはお構いなし。
- なにしろ笠かさ縫ぬいの汚れなき白さは、枝葉の下にうっすらと光を灯したようで、追うだけならこれほど見やすい色合いはない。追うだけならば、だが。
- 「ああもう! どうしてこんなにこう、つかみどころがなくって焦じれったいったら!」
- 「お前さま……そんな、瓢ひよう箪たんで鯰なまずを摘つまむような、とわたくしに言いたいのかえ?」
- 「違う! ふわふわひらひらして、夢の中の桜の花びらみたいに綺き麗れいなのに! 掴つかめない、んんん───捕まえた!」
- 今度こそと確信して、熊くま罠わなのように抱きしめたはずが、また間合いから逃れられる。
- 繰り返すうちに白い少女の姿したモノは、森の奥で半に水際を踏ませていた。
- 泉が密やかに、澄んだ水を湛たたえてあったのである。その静けさに敬意を払いたくなるほどの。泉の、底まで透かした澄明な水面に、そこかしこに浮かんでいたのは蓮はすの葉と思おぼしいが、花の代わりにつけていたのが、水晶だの瑠る璃りだの月げつ長ちよう石せきだのいう準宝石だ。
- 無機質の珠たまというより缶の中のドロップでも無む造ぞう作さに撒まいた風ふうがある。
- 「なんだ、今度はここの池でばちゃばちゃか? 騒がすのが悪いくらいの泉じゃないか」
- 「なんの。ざわめかしいのはお前さまだけさ」
- 泉の準宝石の上から上へと、たんと跳ねてはふわりと舞って、楽しげな遊びのように水面を渡っていくのが白い姿、靡なびける夏着の笠縫の。
- 石は踏まれても軽く揺れるばかりで、ただ沓くつは踏むたびに光ってはすぐに消える銀の粉を撒いた。
- が、笠縫が気軽に跳んでるからと、同じ様にできると思いこむのは身の程知らず。
- 笠縫のように花が舞う、とまではいかずとも、水面に浮かぶ石を飛び石伝いに追っていくことくらいはと真ま似ねをした半は───現在腰まで水に浸かって、泉をじゃぶじゃぶやっていた。
- 石など足を置いた途と端たんにずぼんと沈んで、諸もろ共ともに泉に呑のまれたことである。
- 笠縫にこれ以上引き離されまいと、浄きよい水に咽むせ、水底を泥でかき乱し、額ひたいに雫しずくをまぶして、喘あえぎ喘ぎに白い姿を呼びとめようとする半の見苦しさ。
- 「わかった。もうかじらせてくれとか舐なめさせてくれとか言わない。ちょっとの間傍そばにいてくれるだけでいい。それでどうか考えちゃくれないか」
- 「いきなり殊勝らしゅうなりましたこと。してわたくしをお傍に置いて、いかがなさるおつもりか。お歌でも歌えと? それともヤスデの葉を団扇うちわにして扇あおげとでも」
- いったん停まり、わざわざ振り向いた辺り、この少女の形したモノは本気で逃げるつもりがないのか、あるいは半ごときはいつでも振り切れるとの覚え故ゆえか。
- 半、笠縫の存外素直に応じて立ち止まったのに、しめたとのほくそ笑み、内心に押し隠しつつ、冷たい水の中、気取られぬようにとゆっくり間合いを詰めながら。
- 「ええと、君の姿をおかずに米を食う。間近に見るだけでも唾つばが湧いてくるから。ついでに匂いも嗅かぎたい。それだけでもどんぶりに二杯はいけそうだ」
- 「落語のようなお方じゃな。したが、お会いするなり山犬の面つらで、むしゃぶりつこうとなされたお前さまだもの。今そうと訴えられましても、信じてようございますやら」
- 間合いに入った、と見れば笠かさ縫ぬいの、振り返りもせずに後ろに、とんと跳んでふわりと降りるが半なかばがぎりぎり届かない先の準宝石の上。
- そっと近寄ったつもりが、半が間を詰めようとするたびに右に左に自在に、足元を見た様子もないのに、誤らずに石の上に跳んでは降りる。風に吹かれ舞う薄布の如く。
- 「信じてほしい、大丈夫だとももちろん」
- 「おなごを誑たぶらかして暗がりに引きこもうという、いけない殿でん御ごと同じ眼に見ゆるがの。お前さま、ほんにわたくしの姿と匂いだけで満足なされると?」
- 「満足できるかどうかはわからないが我慢はしよう、約束しよう」
- そんな下らぬ下半身遊ゆう戯ぎの話などしている余裕など蚊の目玉ほどもないのだと、怒ど鳴なりつけたくなった半の方がこの場合はよほど理不尽なのだとも。
- それでも衝動を胸の底に押しこめて、顔をいかにも無害に作れば、元が眠たげで暢のん気きな造ぞう作さをしているだけに、若隠居じみた、女子供に安全そうな面つきになるはなる。
- そして、清水は緑に凪ないで、草は匂いも芳かんばしく、笠縫と半の間に粥かゆを緩ゆるめたような、なんともぬるく気の抜けた間が降りて、しばしふんわかふわりとたれこめた。
- これだけ『待て』をすれば味見くらいは許されたはずと、本人は躾しつけのできた犬のつもりで静々と、他人からすれば獲物に寄る鮫さめまがいの無表情さで、笠縫へと近づく半だったが───
- 「さて本当かしらん」
- とさらり、スカートの片側をちょいと軽く、摘つまんでたくし上げれば覗のぞくふくらはぎの、白さ、滑らかさ、描いた曲線の形のよさ。結構な芸術品にも勝り、目にするだけで寿命が延びようという眺ながめは、これが半にも著いちじるしい感動をもたらした。
- 「いかがじゃ」
- あの白くてすべすべして、雫しずくをシロップのように二、三粒光らせるふくらはぎ。
- 「いかがもなにも!」
- 一体どうなのか、そんなのは実際にかじりついてみるほか確かめようなどないのだからしてまた半は笠縫の素足めがけて掴つかみかかった。アシカの仔を捕食するシャチまがいに何の躊躇ためらいもなく、先ほど取り付けたばかりの約束などあっさり脳から蒸発させて。
- 「その白くて美味うまそうなところを一口でいいからあああ! 食わせてくれえええ!」
- ───半の腹の内などとうに見透かしていたのだろう。
- 「やめなんし」
- 笠縫は小脇にしていた白の杖の石づきを、軽く水面を落としたと見るや。二人の間に浮いていた、蓮はすに似た葉が幾つもさっと起き上がって半の眼前に。
- 掴つかみかかった勢い止まらず青年は、鼻先から緑の壁に突っ込んだ。さして強きよう靭じんな壁とは見えなかったけれども、半なかばは葉に弾かれ泉の中に叩たたき落とされ、跳ねかした飛沫しぶきの派手さである。
- ……腰から下ばかりか、遂には全身水み漬づくとなって、起き上がって濡れ頭を掻かき上げる半の憮ぶ然ぜんな面つらといったらない。
- 「水も滴したたるよき男、とかいう言葉も聞きますが。今のお前さまは、金づちの地じ鼠ねずみが洗顔でもしたような」
- 「……人が必死に堪こらえているところに、あんな美食の誘惑はないだろうが。あれはひどい」
- 「何を訳の判らぬことを。だいたい今のにしたところで、わたくしの裾すその奥を覗のぞこうとかいう馬っ気でもあれば、まだ艶あで事ごとめかした戯れ合いだったと笑えもしましょうが。それがお前さまときたら、頭からお尻まで食い気食い気、食い気」
- 確かに半には、笠かさ縫ぬいのスカートの奥を見たかったとかそちら方面の欲は決してなかったと、それだけは言い切れる、としてもそれはこの際彼の名誉の回復などにならない。一切ならない。
- やれやれと頭を振って、綺き麗れいな溜ため息いきひとつ漏らしてから笠縫が半に据すえた眼まな差ざしが尖とがる。
- 鏡面光沢の眸ひとみがすぼまったのが、銃器の照準器が絞りこまれたかのよう。
- 「して今のが、約束だとのたまった、舌の根の乾かぬうちにあっさり破った言い訳にするなら、いささか芸がなさ過ぎじゃ、のう半」
- 注いだ眼差しは、なんとも白けていて、なのに綺麗で、あるいは身の内にぞくぞくとした悦よろこびを催もよおしてしまう輩やからもあろう。けれどもやはり半にとっては針で突かれたように痛い視線だった。
- 「お前さま、拳げん骨こつのひとつでも降らせて然しかりさ。ですが、わたくしは厭いやですそんな、手が痛い」
- 笠縫はまたスカートの裾すそを手た繰ぐったけれど、今度のそれは脚の捌さばきを易くするためで、笠縫は傍かたわらにちょうど浮かんでいた薄緑に透き通った石へ、爪先を引いて狙ねらいを定める。
- 「代わりに、こう」
- とその薄緑の石をごく軽く蹴った、ら、石は、笠縫の足元が撒まく銀の粉粒と軽やかな仕草と裏腹に、相当な勢いで飛んで、半の額ひたいへまっすぐに、彼が避よける間もなく強打すれば。
- きぃぃぃぃぃぃん───と。
- 「痛いつてえええ!?」
- 冴さえたいい音が鳴って、跳ねかえって水面に落ちて浮かんだ時でも、細かな漣さざなみを立てて震えていた。まるで音おん叉さのように。いや実際小さな音叉のような形をしているではないか。
- そしてその余よ韻いんがまだ止やまぬうちにも、泉周りの木こ立だちの間から伝わってきたのが、
- きりぃぃんんん───
- の、半がこれまでさんざん聞いてきたのと同じ風鈴の音ね色いろ。
- 木立のどこかにあの風鈴が吊つるされているのだろうか、まるでその音叉の形した石に共鳴したかのタイミングだった。
- 澄んだ音の輪唱に、痛みも忘れて半なかばはつい石を拾い上げ、まじまじ左と見み右こう見み、すれば薄緑に澄んだ石は、可愛かわいらしい小ぶりの二又の音おん叉さの形、まるで妖精の細工物のように姿よい。
- 「音叉……か、これ? 鉱石でできた? それに今の、どこかであの風鈴が共鳴した……?」
- 「……妙な運をお持ちのお方だこと。わたくし、細かく見ずに蹴りやったつもりでしたが」
- と半の手の中の石の音叉を覗のぞきこみ、
- 「なかなかに珍かな石で薄はつ荷か水すい晶しようと名づくもの。しゃぶれば最上等の薄荷糖の味がいたします」
- 「こんな形で天然もので味までするとか、聞いたこともないな、そんな石……それに、ハッカ飴あめくらいじゃ喉のどのイガイガには効くだろうが、空腹の口抑えにもならない。」
- それでも少しくらいは気が紛まぎれるだろうかと、半は手の中の水晶音叉を見やる。
- 綺き麗れいで、滑らかで、泉に浮かぶ他の準宝石と同じく、飴ドロップの類たぐいと見えなくもない。
- なるほど確かに新鮮な薄荷の葉を磨すり潰つぶした時のあの、清すが々すがしく涼しい甘さが薫かおった。
- 「……ただ、石は味がするだけ。身の養いにはならぬし、終しまいには中毒になって死にまする」
- 「おいこら」
- 薄荷の芳香に、舌の根に軽く唾つばが湧いて、そそられた端からそんなオチをつけてくるなどわざとやっているのかいないのか。睨にらみつけたところで、彼女に響く気配もない。
- 「それとな、この泉は鉱泉でして」
- 「鉱泉がなんだって? いきなりだな。この冷たさだと冷泉くらいか? 何か効能でも?」
- つらつら平然と続けた笠縫だったが、話の脈絡をいくらか外していて、半は少し戸惑った。
- 「効能と、言えば言えるのやもしれませぬな。ここの水は歳月の間に凝こごって石を産みまする。澄んだの、光るの、いろいろの。だから鉱石の泉、鉱泉と言う。ほら、そちらこちらに浮かんだり沈んだりしているのは皆それじゃ」
- と辺りの色とりどりの準宝石を指さし示してから、
- 「そういう水であるだけに、生き物もこの泉にそのまま浸かったままだと石になります。その蓮はすだけはここの水によく馴な染じんで、花の代わりに石を生ならせますが。で、お前さまは暢のん気きに水遊びなどなさっていてよろしいのかや?」
- そう言えばこの泉は、これほど美しい水なのに、中に泳ぐ魚も底に這はう井い守もり、山さん椒しよう魚うおの類いも一匹だに見えないのであった───水の温度がひやりと背せ筋すじに冷たく伝う。戦せん慄りつ恐きよう懼くして泉から這い上がった半の慌て焦あせった様さま、笠縫の言葉通り水嫌いな地じ鼠ねずみとさして変わらなかった。
- ただそれでも薄荷水晶を放り捨てもせず懐ふところにねじこんだのは、彼自身なにか感ずるところがあったのだろう───
- 「そんなおっかない池の中に人のことを誘いこんだのか。涼しい顔して怖いやつだな君は!」
- 「むしろわたくしの方が不思議で。そもわたくしを追いかけると言って、なにも水に入らずともようございましたのに、ね。なんでわざわざじゃぶじゃぶばしゃばしゃと」
- 「なんでだって? そんなのは物の勢いに決まってる。言わせるなよいちいち! それに怖いこた怖いが、ちょっとだけ気持ちいいぞ、服着たまま水に入るのは!」
- 確かに笠かさ縫ぬいが水の上を突っ切っていこうと、回りこめないほどの広さの泉ではなく。半なかばの声こわ音ねが跳ね上がったのは、己が間抜けさ加減への負け惜しみであること言うまでもない。
- 「おお、怖や怖や」
- 口ではなんと怖がろうとも、声には笑みを含んで、口元を覆おおった手もきっと綻ほころんだ唇を隠すため。とん、とん、たぁんとまた浮き石を跳んで泉の縁に降りる。
- 回りこんで駆け寄ってくる半に一度だけ、鼓こ笛てき隊たいに先立つバトン操者よろしく白の杖をくるりと回して見せたのが、誘うように蠱こ惑わく的でもあり、からかうように底意地悪くもある。
- またすぐ踵きびすを返して木こ立だちの中に紛まぎれていったけれど、それを見逃してやるには笠縫は半にとって魅惑の食材でありすぎた服の水を絞るのももどかしく、後を追う追う性懲こりもなく。
- 笠縫を追う、そんな半の後ろに。高原からずっと追いかけてきたのであろう、彼にしつこく寄りついていた、無地の、未感光の乾かん板ぱんの魚だった。鉱泉の上を渡って、ふわふわと半の後を追っていった。
- 四
- ───木立の、緑でしめやかな暗がりから抜け出て、また明るく照らされていたかと思えば、いつしか空は雲もないのに陽が見えない、高たか曇ぐもりという空模様へと移っていた。
- そのどっちつかずの光加減は、半が入りこんでいた峡きよう谷こくの底の、土色、岩色の景色にはあるいはふさわしい。
- 泉を抱いた森を抜けて、続いて拓けた草原は、やがて左右が丘きゆう陵りようにと隆りゆう起きしていって、峡谷となって半の視界の左右を塞ふさいだ。
- 今さら引き返して丘の上によじ登るのも億おつ劫くうであったし、何より半は峡谷の奥へと走り去っていく笠縫の背を見た、ならばそのまま追うしか彼にはあるまい。
- 先ほど濡れ鼠ねずみとなった服は、着たまま適当に裾を絞ったくらいだけれど、青年の笠縫への熱を示してなのか、もうほとんど乾いてあった。
- 「この時季だ、風邪なんてひかないだろうが、ちょっとさっきのアレはないだろう、あんな風にからかうなんて。あの杖をくるり、だけでも芸だ。おひねりを投げたくなったじゃないか」
- 妙な憤慨の仕方というのの見本であり、半としては心のまま呟つぶやいただけ、返事なぞもとから期待していない、のに───
- ───銅貨銀貨、当たると痛い硬いお金も、透かしの入った紙のお金もいりませぬ。あんなものが芸だというのなら、風車の方がよほど御達者でしょうに───
- ……姿も見せず、峡谷の奥から木こ魂だまに乗せて届けた声なのに、半なかばは額ひたいを小突かれたように鼻白んだ、という。何の気なしの独り言のつもりだったから。
- 彼女の声を響かせた、左右の岸壁は、高さは四・五メートルほどだったがほぼ垂直に切り立って、幾重もの地層をなして堆たい積せきして白茶けた。
- 谷底は元は渓流れだったと思おぼしき小石と砂じや利りの地面の、こちらも白く褪あせた色合いで、ここに陽射しが降り注いだなら、反射がぎらぎらと目を刺したろう。半には今の高曇りの空は有り難い。
- 谷間、というよりどこか切り通しじみた岩と岩の隙すき間まを、ただ笠かさ縫ぬいだけを一心に追っていた半であったが、さすがにその彼にも無視しがたい奇妙な眺ながめが左右に展開されてあった。
- 両岸に迫る地層の壁に、化石が露出して延々と連つらなっていって、しかもそれが古代の恐竜やら虫やらの生き物が石となったものでない。
- 「なんで、こんなのがこんな風に……?」
- 『ご存じないと? お前さまたちが写真機、カメラと呼ばれる器械でしょう』
- 「いやそれくらいは判るんだが……」
- 半の困惑を見抜いた風なタイミングでまた響いてきたこだまの通り、どう見てもカメラ、それもクラシックなスタイルのものばかりが化石となって岩壁の面に露出していた。
- そればかりか、それぞれにご丁てい寧ねいに、似合いの古めかしい額縁と展示ラベルまでつけられて上に下に、前に奥に連なっている───「カメラの化石の谷間」という言葉が半の頭に浮かんだ。
- ただ、奇妙ではあっても、ここの眺めもどこか懐かい旧きゆうの感を心に呼び起こす。
- 額縁と展示ラベルとが相まって、まるで古い美術館か博物館の、人ひと気けのない一画にでも入りこんだかのような心ここ地ちにさせるからだろうと、半はその文字を見るともなしにふと足を止める。
- (イカ・ファブリット・トロピカル……って読むのかこれは。聞いた事もないぞ。でもここにあるのって、多分……全部、乾かん板ぱん式の奴なんじゃないか?)
- 蛇じや腹ばら式の機構を備えたカメラの化石に、半はぼんやりそんな事を当て推量する。
- 蛇腹式だからと言って、フィルム使用のカメラもある。
- クラシックカメラという深沼のような世界には門外漢の漠然としたイメージもあったけれど、半がそれを連想したのは、きっと先の草原であの奇妙な魚たちに遭遇していたせいなのだろう。
- 石になっているとはいえ往時のディティールをそのまま残したカメラは、いかなる設計思想によってか相当に奇抜な形状なものも多く、一時笠縫の事を脇に置かせて半の目を奪うほど。
- そんな青年の耳に、ぱさり、と音とも言えない幽かそけき音が届いて、なにかと頭を巡らせれば、やや離れた化石の額縁の下に落ちている、一葉の、写真大の剥はく片へんが。
- 「これは……?」
- 先ほどまではなかったはずと、寄って屈かがみこみ、拾い上げようとした、彼の背後から耳元に、囁ささやかれた声は、夕暮れ時の白おし粉ろい花ばなの匂いを伴って薫かおった。
- 「そぉっとですよ……。そう、と優しく、好いたおなごの睫まつ毛げから塵ちりを取ってやるほどに、丁てい寧ねいに拾ってあげるとよい」
- 笠かさ縫ぬい!? と戦慄わななきそうになる肩に、彼女の淑しとやかな手が被されば、強く抑えこまれたわけでもないのに、半なかばは琥こ珀はくの中の虫のように動きを封じられた。
- ただ剥はく片へんにと差し伸べた半の手だけが、笠縫に操られたものか、青年の意思を離れ、ゆるゆると動く。金きん箔ぱく細工師まがいの慎重な手つきで拾い上げれば剥片は、ぼけた金緑色の、樹脂とも厚紙ともつかぬ質感である。
- 「雲うん母も……?」
- 「そうじゃ。とくとご覧あれ。息を潜めて、優しく、の」
- いつの間にか背後に現れていた笠縫に、むしゃぶりつきたいのは当たり前のことながら、雲母の剥片の子し細さいも気になって、半、じっと凝視すれば。
- 金緑色の表面に、どこかの景勝地なのだろう。
- 入り江と灯台を背景として、恋人同士なのか、寄り添う男女の姿が写って、まるで写真のように。
- 「え……? なんだ、俺と……この女ひとは誰だ……?」
- そう、写っていたのは半自身とそして、女性の方は───けれどくすんだ雲母片の上の画像はどうにも細部が曇ってはっきりしない。
- もっとよく確かめようと、半が目の前へ翳かざそうとした途と端たんに、いや脆もろいのなんの。
- 雲母片はもろもろと砕けて散って、指にかけらばかりを残す。
- 「今の雲母に写っていたのは、俺と、一体誰なんだ……? いやそれ以前に俺は誰かと、あんな二人きりで写真なんて撮った覚えはない……はず……なんだけど」
- 笠縫が、白の杖の石づきを、雲母片が崩れて落ちた辺りへとんと突くと、かけらは小さな光を発しながら皆消えていってそれっきり。
- 「今の雲母の薄紙はな、写真が化石となったものさな」
- 「なんでそんなモノに俺が写ってるんだ。それにあの女性は?」
- 「───この谷間に入りこんだ者が今のような写真の化石を拾うとな、そこには自身の顔と、そして前世からの定まった縁の人が写っているというお話さ、お前さま」
- 「え。じゃあ俺はいつの日か誰かと一緒になるってか。いや有り得ないから。そんな絵空事」
- 「……なんとも慎ましやかに我が身を述べたものだこと」
- ない、ないと手を振って否いなむ半の、これは彼自身は正当的な自己評価だと思いこんでいるのだけれど、笠縫はまた、泉の時と似たような白けた横目をくれて、谷間の奥へと歩き出す。
- 「ただ、どなたが、どのような相手が写っているのか見定められることは少なく、雲母片の脆さ、ほとんどは確かめる前に崩れて散っていってしまう、というのがあの写真の化石にまつわるお話なのですが。お前さまが分けてそうなのか、近頃の殿方が皆そう言う風潮なのか、縁えにしの相手に興味がない、などとは若いにも似ず膏あぶら気けの抜けたことを」
- 元が川床なのに、小石に足も取られず踏み乱す音も立てず、速足なのは、超俗の彼女らしくはあったが、恐らくは半なかばが話に乗ってこないことへの不満も手伝っていたのではないか。
- 「放っておいてくれ。諸事情あって、異性とまともに付き合えるとは思っちゃいないんだよ」
- それは半の度を外した放浪癖の哀しき弊へい害がいの一つであって、ふい、と衝動任せにいなくなっていつ帰るか不明、といった彼氏を許せるほどできた娘というのは確かにそうそうないだろう。
- 後を追いかけ、歩み去る笠かさ縫ぬいの肩へ伸ばした手は、言い訳を重ねようとしたつもりもあったのかもしれないが、まあ途中からは柿を鷲わしづかみせんとする猿の意地汚さが漲みなぎる。
- 「それに今の俺には、誰と付き合うかなんてよりもっと大切なことが───!」
- さて笠縫ならばきっと後ろにも目がある、よくて躱かわされるか、さもなくばその杖でこっ酷ぴどくどやしつけられるか、くらいに半は身構えていたというのに。
- 手は彼女の肩を捕えていた。水面に映る月を捕まえたようなもので、誰より半自身が驚いて、一瞬手をかけたまま固まって、ただ、手の中の笠縫の肩が細い、薄い、それでいて触り心ごこ地ちの得も言われず素す敵てきなことと言ったら。
- 何か思う、言うよりも早く体が作動して、青年が華きや奢しやな体を引きずり寄せがっぷり抱きすくめた様さまは、子供を河に引きこむ河童かつぱ顔負けの早はや業わざだった。
- 「笠縫、やっと捕まえた、ああ、手荒にしてしまって済まない、けど俺は、俺は、俺は……っ」
- 後はもう言葉にならず声が詰まったのは、口中が湧きあがった涎よだれで一杯になって、という。
- なんとも目を覆おおいたくなる浅ましさで、さてこの妙なる獲物のどこからどうかぶりつこうかと、嬉うれしくも悩ましくそして身勝手に迷う半の腕の中で、
- 「のうお前さま。本当はわたくしも、このあたり一帯の写真機と同じで、もう、とうに石になっていて、そこの額縁の中に飾られているのです───と、もしそう言ったなら、お前さまはどうお思いになるのかしらん」
- 半の腕の中からすぐ傍そばの額縁を振り仰ぎ、そんな問いだけ残して、笠縫の体重と体の芯が不意に失うせてくしゃり、と崩れた。
- 不注意にも半に捕えられてしまい、引き続いて待ち受ける事態に気が遠くなって膝ひざが藁と化してしまい、崩れ落ちたとでもいうのか?
- 「……笠縫?」
- 余りの脆さ呆あつ気けなさに、半もあらためて腕の中、いぶかしく確かめれば、笠縫など形もなく失せていた。ただ白い衣装ばかりが残っていた。
- 彼女の輪郭を留めていたのも暫しばしのこと、すぐにくたくた崩れて、半を少女の衣装だけを相手にダンスの振りに打ち興じる道化にも見せたけれど。
- ただ半は、笠縫が失うせる前に見上げていた額縁に視線が引き寄せられていた。
- 他と違って、その額がくの中にはカメラの化石はなく、岩肌が凹おう凸とつを為しているだけ。
- けれど。腕の中の衣装の、頼りない手応えに呆ぼう然ぜんとなりながら岩肌を見つめるうちに───
- 半なかばの視界の中で、何もないはずの額縁の中の岩肌の色合い、凹凸に焦点が合った。
- すると岩肌の上に、騙だまし絵の中に隠されていた輪郭が浮かび上がるように、判然となる。
- 一見はただ岩肌のなす凹凸、けれどそうと一度認めてしまえば、胎たい児じのように身を丸め、地層の中に憩いこう、少女の姿がはっきりと目に映る、浮き彫りとなる。
- これは、これが笠かさ縫ぬいなのだ。
- それも彼女の姿を写したレリーフや彫像などではなく、彼女そのものなのだ。最早そうとしか半には考えられず、それが彼を悲しく著いちじるしく落胆させた。
- 今まで自分が追いかけていた彼女は、肉体などすでにこうして石化していて───
- (彼女の魂とか、記憶の名な残ごりとか。そんなものがこの岩の中の化石から抜け出して、俺の前に現れていた……そんなところなんだろう、笠縫……結局俺は、もう身も肉も喪うしなわれていた君にのぼせ上がって、喰うだの一口だけだのと大騒ぎしてたのか……)
- そう悄然とうなだれた半の背後から、今まで気配もなかったのに笠縫がひょこと出て、青年の悲哀を造ぞう作さもなくひっくり返した。
- 一緒に並んで額縁を見上げた小柄な姿に、こいつ誰だろうと横目に見て、誰だもへったくれもあったものかの、今岩の中に消えたばかりの笠縫である。
- 腕の中に残されていた彼女の衣装をどうしたものかと持て余すうちに、それは彼の手からするすると、自おのずから地に零こぼれて笠縫の影に吸いこまれて消えた……始末の良いことなので。
- 「どうなされたのかや、そんなにしょげ返って。わたくしはただちょっと岩の中に入ってみただけなのですが」
- いかにも無邪気で毒のない物腰でつるりと流すのが、半のついさっきまでの落胆へ可哀かわい想そうにも砂をかけるようなもの。青年が憤ふん然ぜんとなったのも当然だったろう。
- 「……岩の中に入ってみただけ、ときた。君は自分の本体はもう化石になってるみたいなことを、いかにももっともらしい口ぶりで話したじゃないかっ」
- 「はて。わたくしは『もしそう言ったなら』と申したはずですが」
- 「ああ判ったとも。そんな綺き麗れいな顔となりだが君の性根はどうにもひねくれているってのが!」
- 「あれ怒りましたか。まあ、わたくしからの、些さ細さいな意い趣しゆ返がえしと思おぼし召しませ」
- そうころころ笑いながら、また身を翻ひるがえして谷間の奥へ、走り出した彼女の姿を見たなら半のすることはただ一つ。目を血走らせて追いかけるだけ。
- しかし一瞬だけ彼の足を止めたものがある。
- きぃぃぃぃぃん、と胸をくすぐるような細かな振動、が内ポケットから。
- あの鉱泉で拾った水晶音おん叉さから。
- 「なんだ……?」
- 引っ張り出してみれば、薄はつ荷か水すい晶しようの音おん叉さはひときわ高く震えて、それに呼応したかのように、峡きよう谷こくのどこかから、
- ジ、カシャッ!
- と、くぐもってはいたが、それは紛まぎれもない、機械式カメラ特有のシャッター音。
- けれどここの峪間のカメラは皆一様に化石となっているのに、そんな生きたシャッター音を響かせるものなど、一体どこにあるというのだろう。
- いずれにしてもその音も、今の半なかばの足を引き留めることはできなかった。
- 五
- カメラの化石の峡谷を、また笠かさ縫ぬいを追って進みゆけば、次第次第に両岸は狭くなって、果てにはぽっかりと何やら象徴的に空いた穴、洞どう窟くつの入り口を半は見た。
- 笠縫がそこに入りこんでいったのは、空気にかすかに残った芳香からも明らか、とあれば、半にはなに躊躇ためらうところはない。
- 踏み込みゆけば、洞どう内ないは光ひかり苔ごけに薄ぼんやりと照らし出されてあり、さらに進めば───
- 半は、また陽光を浴びて、目を慣らすまでにしばしの間を置いた。地中にあるうちに空は高曇りからまた晴れ間へと移ろったと見える。
- 光苔の冷光から陽射しへの劇的な転換は、青年が洞窟の行き止まりに垂らされていた一本の綱をよじ登って地上に出たことによる。
- 這はい上がってみればそこは井戸口、緑に彩られた摺すり鉢状の窪くぼ地ちの底の。
- 窪地の法のり面めんには螺ら旋せん状に通路が切られて、そこの井戸口から地表までぐるぐる巻きながら続いていて、恐らくは水を汲くむ際につらい傾斜を、和らげるための工夫と見える。
- こういう様式の井戸は「まいまいず井戸」といって、関東地方の一部に今もその姿を残す。
- ただこの井戸はすでに枯れていたけれど。
- 「どこだ、笠縫……?」
- 緩ゆるく傾斜しながらの螺旋状の小こ径みちには上から下まで、藤棚めいた棚がさしかけられてあり、そこに密にこんもりと這はわされているのは藤ならぬ蔓つる状の植物。
- 大きさは梨くらい、ライチとよく似た実を一杯にぶら下げているけれど、そのどれもが石の塊かたまりのような堅果。
- 実み生なりの蔓の賑にぎやかさというよりは、切れた電飾のコードを思わせてどこやら侘わびしい。
- それでも緑濃く茂った樹棚を目でぐるぐる追っていくと、視覚的になかなか面白くはある。
- 「わたくしは、ここに───」
- この眺ながめを楽しんでいるのは今一人。半が下から見上げて、もう一人は窪地の縁近くの棚の上から底を見下ろして。
- 慎ましやかに膝ひざを揃そろえて樹棚の上に座った姿は、緑の中に目覚ましい白を点てん睛せいと配した。
- 一帯の草木の精だと言い張っても通用するだろう。
- 銀の髪を指先で軽く梳くしけずりながら、半なかばに置いた眼まな差ざしには、幼子に諭す姉のような色合いが揺よう曳えいしている。そろそろ遊ゆう戯ぎもお終しまいと告げようとする姉の。
- 「さてもお前さま、そろそろ思い直されてはいかが。わたくしがお前さまにこの身を食らわせてやろうと差し許すなど、本気でお思いか。そもそも、この辺りのお山には、食べるモノなどいくらでもありましょう。現にここに生なっているのは、魚たちが聞き入る風鈴の、元の実じゃ」
- 樹棚の縁を軽く叩たたいて示せば、蔓から伝わり、僅わずかに揺れる実が、重たげに、みっしりと果肉が詰まっていそうではあるけれど、半が見る限りでは石がぶら下がっているようで、喰えそうな愛想というのがない。事実青年の食い物に関する直観にも何ら響くものがなく、手近なものを手を伸ばしてつつく限りでは、爪どころか歯も立ちそうにないほど堅い。
- 「名づくるにいわく『風鈴ライチ』───と。汁気の多い、薄はつ荷かの良い香りのする、夢のように美お味いしい果物みずかしでしての。その種の殻が、ほら、あの風鈴になる」
- それであの涼すず音ねに食い気を感じていたのだろうかと半は独りごちる。
- 「……随分と風流な名だし、聞くだに美味うまそうだが……食えるような感じじゃないぞこれ」
- 「さようですとも。皆まだ熟してはおらなんだ様子。食べ頃になるまで、このままではあと……四よん年とせ五ご年とせはかかりましょうや」
- 「ダメダメじゃないか、熟すまで待ってたらどっちにしろ飢えて死ぬ」
- 「このままでは、と申しましたよ。お前さまは不思議の巡り合せがある殿でん御ごのよう。鉱泉で薄荷水晶の音おん叉さをお手になられた。ここまでこの笠かさ縫ぬいがお前さまを案あ内ないいたしたは、その故ゆえによって。その石がこの風鈴ライチの眠りを覚まし───」
- 何事か笠縫は、さらに言い募ろうとしたのに、半ときたらそれを遮さえぎり、
- 「いいや───君ではなくては、駄目だ」
- 「はて?」
- 「どんなものであろうとも、君を知ったら君以外では決して俺のこの飢えは満たされない。君がいいんだ。君しかいないんだ。だから───」
- きっぱりと言い切ったものの、駆けだそうとはせず、今まではどうにも粗そ忽こつに迫りすぎたと反省したのかしらん。
- 樹棚の下、緑の木こ漏もれ陽の裡うちにと入り、小こ径みちを辿たどり笠縫へと上りゆく半の足取りはゆっくりとして、その顔つきも切ないまでの真しん摯しを湛たたえてあって、これは何の巡礼者か幻視者か。
- 「どうか一口でもいいから食わせてくれないか」
- まあ結局はどういう顔でどんな声こわ音ねで告げようが、半は徹てつ頭とう徹てつ尾びこれなので、そのぶれも小揺るぎもない欲望にはさすがの笠縫も、感嘆の息をつくほかなく。
- 「はぁ───なんとまあ。あっぱれとしか言いようのない、真正直一本やりの口く説どき文句だったこと。おなごとしての冥みよう利りに尽きましょう……が、どうなのです、全て食い気とは」
- 「吐く言葉が全部下半身事情に直結しているよりは、なんぼか公こう序じよ良りよう俗ぞくのうちだと思うが?」
- ……半なかばとしては気の利いた切り返しのつもりだろうが、彼の飢えはそんな風紀がどうこうを越え、はるかに根源的な問題を孕はらんでいる。
- 「お前さま。そうあけすけに、食わせろ食わせろと口やかましいことですが、その意味を本当にお判りかえ? それは───」
- 鏡面光沢の眼まな差ざしが、すっと伏せられ、髪と同色の睫まつ毛げに翳かげりが宿る。
- 「……てもまあ実のところ、ちとかじられたくらいでは、応えもせぬのがこのわたくしさ」
- 瞼まぶたの陰影などすっと晴れたし、かつ造ぞう作さもなく言ってのけたもの。
- 「お前さまとて、うすうすお気づきなのでしょう? なにしろわたくしは、御覧の通りの娘の身ではない。そも、お前さまと違って『ひと』にあらず。そうさの───妖あやかしとでも魔とでも。お好きにお呼びなさいませ」
- これまであれだけ人間離れしたことを言って、やってのけて、半としては何を今さらな告白ではあったけれど、本人の口から述べられると、ようやく据すわりよく納まったという感がある。
- この少女の形したモノは、妖怪、妖物、そう書物口伝で様々に伝えられるモノなのだろう。
- 細かな定義を問えば、妖怪というのはちゃんと『名前』を与えられ、広く膾かい炙しやされてこそ、それ足りえるものだ。
- それを引き合いに出すなら、笠かさ縫ぬいという名は、数あま多たある有名無名の化け物図録、書物でも語られたことはなかったものだけれど───
- 確かに半もこれまで『笠縫』という名の妖など聞いたこともなかったが、それはただ自分が知らなかっただけ、やはり妖という語以外に彼女を表す言葉は、青年には見当たらない。
- それも妖の中でもこの笠縫は尋常ただごとではない、と感じていた。
- 彼らの中でもとりわけ貴たつとく、いと高きもの、言うなれば妖の姫御前、妖怪の姫───妖よう姫き。
- 幾つかの言葉が浮上しては、最後にその言葉が最も半の舌の上にしっくりと馴な染じんだ。
- そうだ、妖姫笠縫というのがこれになんともふさわしい。だが。だとしても。
- 俺のこの飢え、ひもじさ、食いたさは全くたじろぎもせず、ただひどくなっていく、と半はきりきり痛むくらいのはらわたを手で押さえつつ、必死に歩を継ぐ。
- 「まあそりゃ今までやってのけたことからしても常人とは思えない。だがまあ、人かどうかなぞ俺にゃもう関係ないし、少しくらいならかじられても問題ないんだったら───っ!!」
- 「落ち着きなんし」
- 「落ち着いてなぞいられるかっ」
- 血走った眼を引ン剥むき、餓鬼道一直線のご面相で、逃げるがいい、どこまでも追い詰めるとの迷惑な覚悟の気き炎えん、背中にゆらめかせてさらに迫る半に、笠縫がすっと指さすは、彼の背後へと。
- 「そのままでは影を取られますがよろしいか」
- 「……あ?」
- きょとんと振り返れば、あの未感光の乾かん板ぱんの魚がそこにいた。笠かさ縫ぬいと青年の追いかけっこを延々とついてきて、今追いついて。
- 棚の蔓つるからの木洩れ陽が落とす、半なかばの影を口先でしきりにつついてはつつきを繰り返しているのが何のつもりなのやら。
- それだけなら影踏み遊びの類たぐいと見過ごしにできたのだろうが、半はふっと気づいて凝然ぎよつと我が影を凝視した。
- この乾板の魚が突く端から、僅わずかずつではあるが自分の影が減っていて、かじり取られているような……。このままだと下へ手たをすれば、自分の影は全部この魚に吸い尽くされる───?
- 「うわあああ!?」
- ───妖姫と対たい峙じし、その肉を食おうというものが、たかだか影を取られるというだけで度胸がない。
- 上うわ擦ずった悲鳴を迸ほとばしらせ、泡を食って魚に蹴りを叩たたきこめばしゅっと躱かわされる。
- なにか武器になるものとリュックの中を探ったところで笠縫からの涼しい声。
- 「お前さま。まだ何も写しておらぬその魚うおを壊こわいてしまわるおつもりかや。ほ、これは情のないこと。それはおのこおなごが初うぶなまま、ちぎりも知らず死んでしまうも同じですよ」
- 「だけどこのままじゃ俺の影が……」
- 「そんなもの、少しくらいかじられたところで、じきに元に戻るというもの」
- 笠縫がそう請け合ったし、童貞処女のままくたばらせるのも同じことだと、説き聞かされれば憐れん憫びんを覚えぬものでもない。
- とは言え。自分の影がチーズを端からかじるように欠けだらけにされていくのはどうにも落ち着かず、半、最前まで食わせろと迫っていた相手に今度は助け船を求めたというのだから、その節操のなさといったらない。
- 「じゃあどうすれば」
- 「その魚たちはの、お前さま、先の野原でご覧になったように、殊ことのほか風鈴ライチの音ね色いろを好むのさ。その音に聞き入っている間は大人しゅうして、まるで眠るややこのよう……ただし」
- まだ半の足元の影にまとわりつく乾板の魚を見やる。
- 「魚たちにはそれぞれに好みの音色というのがありまして。合わない風鈴にはあまり寄り付かないのも、お前さまの見た通り。このまだ写し絵を持たぬ魚もそう」
- 「そんな都合よく、この魚の好みに合う音色の果実が見つかるものなのか? それに大体君だって言ったばかりだろう。風鈴ライチが実るには四、五年かかると」
- 「だからわたくしはそのお話をしようとしていたのに、中途で嘴くちばし挟んだはお前さまであろ」
- 軽く半を睨にらんで言葉を継いだ。
- 「目覚ましがあれば、お話は別。いつか熟すまでの時の中に憩いこうてある、果実たちにも届く音ね色いろがあれば、お話は別。お前さまはその音をご存じのはず」
- 笠かさ縫ぬい、半なかばに手を差し伸べて、その指先で音高く指弾きをやったのは、妖姫がするにしては品の良い仕草とは思われなかったけれど、宙を裂くかに小気味よく、鳴った音の高く、青年は顔を軽く打たれたほどにも響いた。
- 知っている、と半の脳裏で何事か閃ひらめいた。この鼻の奥に突き抜けるような衝撃は、鉱泉で笠縫に薄はつ荷か水すい晶しようを蹴り当てられた時とそっくりだ、と。笠縫も言いかけていたではないか。
- 懐ふところにねじこんでいた薄荷水晶を取り出せば、緑に透ける天啓として、彼に確信をもたらす。
- 確信に導かれるままに、人差し指と親指で輪を作って、溜めて、弾いた水晶音おん叉さは───
- きぃぃぃぃぃん───と。
- 透明で清涼な音色でもって一瞬間にまいまいず井戸に満ち、長く長く余よ韻いんを引いた。
- 「それでよいのですよ、お前さま」
- やがて───まいまいず井戸のすり鉢の中に、初めはごくかすかに、やがてはっきりと耳に聞こえるくらいに、鳴り出した風鈴の音がある。
- 風鈴の音とともに、巻き蔓つるやその葉もするすると伸びて増えて、未熟の木の実がいくらか膨ふくらんだ、とともに堅牢な表皮が柔みを帯びて、得も言われぬ芳香を放ち出し───風鈴の音はその実の中からややくぐもって、けれど確かに聞こえているのだった。
- 「ほら、もう食べ頃じゃ。よい音色を鳴らしている」
- 鳴音と芳香を放つ樹棚の上から、笠縫は先生が問題を上じよう手ずに解きおおせた生徒へ送るように半へ笑みかけて、手近のライチ似の実に手を伸ばせば、造ぞう作さもなく蔓から離れる。
- 白い珊瑚のような手の中で、まだりぃんりぃんと鳴っていた。
- 薄荷水晶の音叉に目覚ましされて、共鳴して、熟した証拠ではあれ、これから食べようというには少々風流が勝る。笠縫が両の掌てのひらで実を包むと、音色はじきに止やんだ。
- 石ころのようだった皮は今では色づいて、透明味さえ帯びて、そこへ笠縫は指先を伸ばして、爪の先でなぞる、と、ぷつりとその線なりに割れ目が素直に入る。で、つるりと、湯通ししたトマトよりも、あの硬そうな皮が容易たやすく剥はがれて、緑を帯びた白い果肉が、まるで宝珠のように妖姫の手の中で、ぷるん、と。
- 薄荷の清せい冽れつとライチの甘みの混交した芳香の、実に薄はく朱しゆ色の唇が吸いついていったのか、それとも実の方が妖姫の麗うるわしの唇に恋して身を寄せたのか、いずれにしても笠縫は白い果肉を唇に噛かんでいて、汁が顎あご先さきに滴したたる、指を濡らす……。
- 水気の多い肉から汁が零こぼれるのも気にせずに、噛み分けて、舌で吸って、白磁の喉のどを小さく鳴らして飲み下して、口中に満ちる悦えつ楽らくに銀細工の睫まつ毛げが柔和に下ろされる。
- 無心に食べる笠縫のその情緒、少女の貌かおでありながら艶めかしく、官能的ですらあった。
- 「ああ、美お味いし───」
- 典雅で、なのにある種の秘め事さえ連想させる笠かさ縫ぬいの食べる仕草。半なかばが目を奪われているうちに、少女の姿した妖姫は、実をいくつかもいで半の傍そばへ、とんと軽やかに飛び、降りる。
- 彼の目の前でまた上じよう手ずに爪を立てて剥むいて、
- 「ほら、お前さまも召し上がれ」
- 馬鹿のように見入っていた青年の口の中につぷりと押しこんでやったから半も、笠縫と口中の幸福を共有したのである。
- 押しこまれて反射的に一ひと噛かみすれば、口の中に広がったのは高原の朝に満ちた薄い薄はつ荷かの爽さわやかさ。口から体の中一杯に満ちていく涼やかな香り、その後に品の良い、異国の荘園を思わせるような程よい甘さと酸味が追いかける。
- 果肉は一時歯と舌に艶めかしく絡んではすぐに解ほぐれ、喉のどにどこまでも清せい冽れつに滑り降りていく。
- 果物にままあるべたついたしつこさはまるでなく、仄ほのかな苦味があったがそれさえ爽そう快かい感を引き立てる。軽い苦味はむしろうま味を引き立てるものとは半も知ってはいたけれど、ここまでの相乗効果はそうはない。
- 果肉自体がひんやり冷えて、そしてこの清涼感、なんとも夏向きの食べ物だ。
- この食べ物はなんだ───?
- 風鈴ライチという暢のん気きな名前に似ずに天上の食べ物ではないか。一つだけでは全然足りない、もっと、と半はもう一粒で夢中となって、笠縫の手から次から次へとおかわりの、彼女の様さまには爪で上手に向けなかったから、自分のナイフで表皮を剥き、かじりつく。
- ただ、果肉はその見た目ほどの量はなく、丸い大き目の種が実の中の多くを占めていて、ガラスのように透き通って宙空だった。
- これがきっとあの風鈴になるのであろうが、半の勘はどうやらその気になればその部分も食えないことはなさそうだと告げている。
- こうして不思議な場所の不思議な実を貪むさぼり食う喜き悦えつの時間、ひとしきり───
- その味わいたるや、一時だとしても、半の笠縫への食い気さえも忘れさせるほどだったというからその美味なること推して知るべしで、何粒食べたことやら、樹棚の隅には殻が山盛り。
- 満足の吐息をついた半へ、笠縫がまた薄荷水晶を鳴らすよう促したのだった。
- 「まだですよ、お前さま。もう一度、井戸の底に降りて、薄荷水晶を鳴らしやれ。鳴らしながらぐるりと回るのです。すれば、どこかでひときわ響く実があるはず」
- 「なんでそんなことを?」
- 「お前さまが満足しても、そちらの魚うおはまだ不満のご様子だから」
- 見ればすっかり忘れていたけれど、未感光の乾かん板ぱんの魚は、まだ半の影をかじり取ろうと、尾を揺らしてゆらゆらと。
- だから笠縫に言われるままに井戸まで降りて、水晶音おん叉さをまた鳴らしてぐるりと回る……確かに、樹棚のある一か所に、より強く共鳴するのがあったのである。
- その共鳴を追うかのように、未感光の乾かん板ぱんの魚が、そちらの方に泳ぎ寄っていって、陶とう然ぜんとした様子で一つの実の音に聞き入った。まさしくその実が魚の好みに合っていたと見える。
- 腹が満たされ疑念を抱いだく余裕ができたのか、半なかばはそんな魚にふと思うところがあった。
- 「なんで俺の影を狙ねらうのが、この音おん叉さにより強く共鳴する実の音ね色いろを、対のように好むんだ?」
- 「それはその薄はつ荷か水すい晶しようが、お前さまのおでこにぶつかった時に、お前さまに合わせて音が整ったからであるかと」
- 「音叉ってのはそういうもんだっけか……? でもまあそれはいいよ」
- 「なあ君、笠かさ縫ぬい。君はあの魚について、まだ何も写していないのに捌さばくのは不ふ憫びんだ、とか何とか言ったな。だったら、何かを写し撮ってやるのは、あいつに取って良いことなんだろうか」
- 「そういうことになりましょう」
- 「あいつが乾板だというのなら、そこに映像を焼きつけるには、カメラがいりようになる」
- 「道理かと」
- 何を言いたいのかと、物問いたげな風ふ情ぜいを見せてから、笠縫はしばしお待ちあれと井戸まで降りていって、釣つる瓶べで水を汲くんで汁に塗まみれた手を流してから戻ってきた。
- (……あの井戸はやはり枯れ井戸で水など一滴も汲めないはずだから、笠縫がまた何かやらかしていたのだろう)
- 「お待たせ。お話の続きを」
- 手の汁は流しても、風鈴ライチの名な残ごりを息に優しく香らせる笠縫に、
- 「俺たち、カメラの化石の谷を通ってきた……あそこでも、一瞬だけこの水晶音叉が鳴ったんだ。もしかしたら、あそこにも何かあるのかもしれない」
- 「ふぅむ……お前さまの心の動きは、なかなかに面白うありますな」
- 笠縫は、蔓つるがらみ、未感光の乾板の魚が好みの実を取り外して、猫をじゃらすように左右に揺らし、魚を右う往おう左さ往おうさせてからかいながら、興を催もよおしたように半を見上げた。
- 六
- ───で半は、カメラの化石の峡きよう谷こくまで引き返していた。今までは追いかければ逃げていたのに、今度は笠縫、とことこついてきたのが小こ癪しやくなこと。彼女だけでなく、未感光の乾板の魚もまた風鈴ライチの音を追ってついてきていた。
- 水晶音叉を鳴らしながらカメラの化石の前を巡っていくうちに、やはりひときわ強い反応を示すものがある。
- 半がそれに手を伸ばすと、化石化していたはずのカメラが、石の中からことりと抜け落ちてきて、青年の手の中にすとんと収まった。
- すると、もう石ではない。ちゃんとした、動作していた往時の姿に戻っていたのは、共鳴する水晶音おん叉さのもたらした作用だったのだろう。
- 蛇じや腹ばら式のカメラで、よく整備され、丹精されていたのに違いない。手て擦ずれはしていたけれど、破損や歪ゆがみはどこにも見えない。門外漢の半なかばには知る由よしもなかったけれど、それはパテント・エツィというハンドカメラで、蛇腹部分を折り畳むと、同形式のカメラとしては破格にコンパクトにまとまることで好評を博したカメラだった。
- 手には妙に馴な染じむけれど、こんな古いカメラの操作法など見当もつかぬと、半が困惑していると、魚はするりとレンズの中に吸いこまれていった。当然カメラにはあんな魚を入れられる嵩かさなどないが、半もこの辺りになってくると、多少の不条理には慣れてきてはいた。
- 「しかしこんな古いカメラの操作なんてどうすりゃいいのか……」
- 「そう惑わずとも、中の魚うおに任せるがよかし」
- 戸惑っていた半の手から、カメラはあの魚のようにふわりと浮き上がる。撮影の準備が整った、ということを示すかのように。レンズが向けられた先は、半と、連れ立つ笠かさ縫ぬいへと。
- 笠縫に心の準備があったかは定かならず、半にはほとんど不意打ちで、合図もなく。
- ストロボの閃せん光こうが視界を白く灼やいて、機械式カメラ一流の小気味よいシャッター音が響いて、もう二人は乾かん板ぱんに焼きつけられていたのだった。
- カメラは役目を終えたと言わんばかりに元の額縁の中に吸いこまれていってまた化石に戻り、その中から抜け出してきた乾板の魚には、二人の姿がはっきりと写し撮られていた。
- ただその画像は───半は本人が思っている自画像よりもずっと滑こつ稽けいで、そして笠縫については、成熟して、優美で威厳に満ち満ち、どこか恐ろしくもある女性として映っていた。
- きっと乾板の魚の目には二人がそのように映っていたのだろう。
- 「あ。そう言えば、ここで見つかる写真の化石には、将来一緒になる異性が写っているとかそんな話がなかったか? ……じゃあ今こいつに写った画えの場合、その話……どうなるんだ?」
- 「さて、どうなりますことやら。あるいはお前さま、今あの魚に焼きつけられたわたくしたちたちの写し絵。いずれふたり添い遂げることになる証となると、そうご判じかえ?」
- 「また『もしも』の話だよな……?」
- 笠縫は薄い笑みを唇に含んだばかりで、それ以上は答えなかった。
- 七
- あの天文台のような建物の傍そばの、始まりの草原───
- カメラの化石の谷間からさらに来し方を辿たどり、戻ってきている二人の姿がある。魚はもう半への執着も失うせたのか、青年から離れて高原を泳ぐ同類の中に戻り、迎えられていた。
- 古い駅舎のような広間を皮切りに、この不思議の高原に入りこんでから、あれこれしてあちらこちら走り回って、ずいぶん過ごしたように思えるのに太陽は午後の位置にかかったまま。おそらくここでは時間の流れようからして異なるのだろう。
- 半なかばはあらためて自分の状況を考える。とにかく腹は満たされた。けれどもここはどこだ? どうすれば自分が知っている世界へ戻れるのだろう? それらは依然として不明だ。
- つまりは、状況は半にとり必ずしも喜ばしいものではないというままで。
- そういう段になって、妖姫のすげない一言だった。
- 「それではわたくしはこの辺でお暇いとまをば。お前さまの食い気がまたぞろ頭をもたげる前に」
- 笠かさ縫ぬいはここまでついてはきたけれど、もうあとは大した用もないと見え、あからさまに留まる気が失せているのが半にも判る。まこと由ゆ々ゆしき事態といえよう。
- 「いやそのちょっと、待ってくれ。結局ここはどこで、俺は元来た道へ、どうすれば戻れるのかわからないままだ。きっと君なら知っていそうな気がする。そうなら教えてほしい。あと腹は満たされたが、けど君への食い気が完全に消えたわけじゃない。これもどうしよう」
- 臆おく面めんもなくまくしたてる半に、笠縫は聞いているのかいないのか、呆あきれているとも聞き流しているともとれる顔で、まだ一つ持ってきていた風鈴ライチを剥むいて、種を丁てい寧ねいにのけてから、つるりとまた一口に。
- そして、汁のついたままの指先を半の唇の中に押し込んだ。口の中に軽く押しこまれて、舌の上を軽くなぞって、押しつけられたのは、指、あれほど食いたいと希こいねがった妖姫、笠縫の、ほんのわずかだけれども確かに彼女の、一部分。
- 風鈴ライチの味はすぐに薄れ、残ったのは、笠縫の指の形をした、純粋な歓喜そのもの。
- その指先が口中にあるだけで、半は自分がそこから溶けていくかの感動と多幸感に包まれたという。溶け合うとか、融合するとか、あるべきところに収まった、という感覚すらあった。
- 風鈴ライチの味を天与の美味とすれば、こちらは半の根幹をなす部分に決定的な変化を与えてしまう味というべきか。
- 「───ああ。そうじゃ。やはり、この舌。感じた通り。ここへ招いたのは正しゅうありました……。お前さまでしたか、半とやら───」
- だから笠縫がこのような言葉を、鏡面のような眸ひとみにどこか憂愁を湛たたえて呟つぶやいた言葉も、恍こう惚こつの余り意識が溶けだしていた半には届かず。
- だから、妖姫の指が口内から失せていった時、周囲で世界が立ち戻ってくると同時に、半は途方もない喪失感に押し包まれて、ほとんど虚脱状態に陥ったくらいだった。
- 「……お味見じゃ。まあ、これくらいは。わたくしもたまには、気まぐれというのをします」
- 気まぐれ? 今の、自分を大きく変えてしまうくらいの感覚が、単に気まぐれから出いでたのかと、半が愕がく然ぜんと見つめれば笠縫と視線が交錯する。
- ───判らない。妖姫だから? 人とは違うものだから?
- 半にはその心は何も読み取れない。少なくとも、今はまだ、何も───
- 「それとな、戻る道がどうこうとお困りのようですが、そんなのは簡単。あの岩屋の、通ってきた穴に、また入ろうとするのではなく、お尻を、背なを向けたままであとじさって行かれればよい。そのまま、ずっと。すればそのうちに、お前さまの元来た道に立っていましょうよ」
- 虚脱したままに、反射的にありがとうとか何とか云いかけた半なかばに、笠かさ縫ぬいが唇の端を吊り上げたのがどこやら酷薄だった。
- 「して、なんとも親切に隠れ里からの帰り道まで教えて差し上げたわたくしは、お前さまから何をいただけるのかしらん? よもやわたくしのような妖あやかしから、ただで何かをせしめられるとお思いか? ちとそれは虫がよすぎるというもの」
- ……何やら、半の知らぬうちに、勝手に一つの売り買いというか契約というかが、なされてしまっていた、ような……。
- 笠縫は、先ほど半の口の中に押し込んで、まだ彼の唾つばに濡れた指先舐なめながら───
- 「そうですねえ。お前さまの舌を代価として、いずれ取りましょう。もっといろいろの美お味いしいものを食べて、味が染みこんだその頃合いを見て」
- ───そして笠縫は。今度こそ瞬間に半の視界から消え去って。本当に見えなくなった。気配も匂いも残さず。
- あとには、取り残された半ただ一人。
- こうして半は元来た道にどうにか引き返してきたのだけれど。
- 妖姫に教えられたままに、トンネルを危なっかしく後ろ歩き、背後から外界の光が指してきたのに出口が近いとほっとして、やがて潜くぐり抜けざまに。闇やみの奥から伝わってきた声がある。
- なんとも言い知れぬ、不穏な託たく宣せんじみた言葉だった。
- ───さてもお前さま。一度でもこのような場所に踏み込んだ足は、これより先も似通う場所に迷い出す癖くせがつく。それをば心に置かれるがよかし───
- 第一話・了
- 一
- 眼下に街並み、まだ瓦かわら屋根が多く残るその上に突き出す、物もの見み櫓やぐらのような風ふ情ぜいの時計台を眺ながめながら、坂道を上がって半なかばは手荷物を持ち直した。まだ晩夏とて空気に籠こもった熱に、滲にじんだ額ひたいの汗を拭ぬぐう。
- 比ひ良ら坂さか半はあの不思議な高原に入りこんだ旅から、間借り先のある町に戻ってきたばかり。町は地方の学生街といった趣おもむきのところ。
- 彼の両の手の買い物袋には一杯の食材。まだ味が『判る』うちに、鱈たら腹ふく食ってやろうという心づもりで。
- 間借り先の民家は坂の上のどん詰まり、ここからでもやはり時計台は見える。ただ今はその時計台、惜しいことには稼働していない。そして少々奇妙なことには、町の小高い場所からだとどこからでも認められるそこに、どうすれば行き着くことができるのか、半も、半の少ない仲間内にも知る者はいないということだった。
- 大家の老ろう爺やに、旅行から戻った旨の挨あい拶さつをして、土産みやげ物を渡してから、二階の自分の部屋へと上がっていく。
- 現在、半の住まうのは、前時代の遺物のような、木造の日本家屋の二階の貸し部屋、六畳一間。
- 風呂、台所は共用で食事の提供はなしという、言ってしまえば今時珍しいくらいのつましい住まいで、ただしそのおかげで家賃は抜群に安い。その上門限もないという緩ゆるさが彼は気に入っていた。
- 半の他にもうひとり間借り人がいるという話ではあるが、この人物はどういう生活様態をしているのか、青年はほとんど遭遇した例しはない。大家もまた超然として干渉してこない人物なので、この借り部屋は酷い放浪癖持ちの半にとってはなんとも都合がよい。
- 軋きしむ廊下を踏んで部屋に入れば。
- 部屋は戦前の書生部屋のような佇たたずまいで、普段は至る所に半の旅行の記念品と、そして文庫本などの安価な書物が山と積まれているという、男子学生らしいと言えばらしい、むさくるしい有様なのだが、戻ってきた今日はなにやら様相が異なっていた。
- なんとなれば部屋の中一杯にかまくら? イヌイットたちが雪で作る住居イグルー? とにかく小ドームが築かれていた。雪ならぬ、全て本で。
- 見ればどうやら、もともと部屋にあった文庫本やら全て用い、互い違いにレンガのように積み上げて作ったものらしい。おかげで半は自室の畳たたみを久方ぶりに目にしたものである。
- そして書物のドームの中では、半が所有している衣服のあらかたが引き出されて、清潔に洗濯されて干され綺き麗れいに畳まれた上で、ずらりと円形に並べ置かれてあった。もちろん下着の類たぐいも分け隔へだてなく。
- その衣類の円の中心に正座している女性が一人。長い黒髪をお下げにして、端正だがどこか陰気な翳かげりを宿した女で、年の頃はどうやら半なかばの一つ二つ上なのだろうが、白割かつ烹ぽう着ぎなどをつけているせいかどうにもその……『お母さんおかん』くさい。
- そんな女性が、お膳の上の、山盛りにした白米の碗に箸を突き立て、お祈りの形に両手を合わせていた、という───
- 彼女は部屋の襖ふすま戸どを開けた半に、動じもせず目元を和らげ、仄ほのかながら優しい笑みではあるのだけれどいかんせん状況が状況、ちと常軌を逸しすぎた。
- 「まつ璃り姉……これは。この本のかまくら? は一体何事……」
- だが半の方の驚きは、部屋に女がいたことよりも、本のかまくらの方に寄っている。
- 女性も女性で、青年と交わす言葉、物腰がごく自然で馴な染じんであって。
- 「半くんのお部屋はいつもご本に埋もれて、お布ふ団とんの敷き場も足の踏み場もないくらい。だからといって勝手に処分するわけにもいかないし、ちょっと工夫してみた」
- 「それに俺の服。いつものように後先考えず飛び出したものだから、汚れ物だって交ざってたろうに」
- 「ええ、全部綺き麗れいにお洗濯して、乾かして、穴のあいた靴下とかシャツのほつれとかも全部繕つくろって、アイロンかけて。今は粗熱を冷ましているところ」
- 「それから、その飯の茶碗の前でなんでお祈りなんかを。食うんだったらさっさと食えばいいじゃないか」
- 「あら。食べるなんて。だってこれは陰かげ膳ぜんだもの。半くんの。きみが道中、ご飯に困らないように。ひもじい思いをしないようにって」
- ……仏様に供えるご飯をそう唱えることがあるけれど、耳慣れない者もあろう。
- ましてや旅の家族の無事を祈って、こんな風に飯を用意するなど、既に死したる習俗なのを、まつ璃と呼ばれたこの女性、ごく当たり前のように。
- 「大家の爺さんにはなにも言われなかったのか」
- 「だってあの人はわたしをきみの従姉だって信じこんでいるのだし」
- ……実は彼女のこういった、奇行の域にまで至った半への『世話焼き』はこれが初めてではない。それでも青年は言いようのない脱力感に囚とらわれて、買いこんだ食材を床にとり零こぼしたものである。
- 「食材、たくさん買いこんできたのね。それならお姉ちゃんがあれこれ作ってあげる。待ってて、なかちゃん」
- 食材を拾い上げて台所へと下りていく彼女は、年上の通い妻、というにはどうにも慣れきっていて、まだ若いのに所帯じみてさえあった。
- 彼女は大おお櫛ぐしまつ璃。
- 半なかばの通う大学の同学部同学年の女性なのだが、二浪しており年は二つ上。半と同郷の幼おさな馴な染じみである。幼少の頃から何くれと半のお姉さんぶって世話を焼くという、そんな関係だった。
- 一時期は学校が分かれたに従い交流も絶え、その後、半は大学進学のために故郷を出てしまったのだけれど、その入学先で再会を果たしたのが奇妙な縁、半としては懐かしくも嬉うれしくもあったのだけれど、彼女の接する態度距離感が昔と全く変わらないのにはやや面食らった。
- なにかというと半の世話を焼きたがり、気がつくとするりと下宿先の部屋にまで入りこんであれこれする。
- 半にしてみれば有り難くあるはある。それは彼の仲間内でも知れ渡っていて、部屋にまで押しかけて世話をする年上の女とあっては、通常色恋が取りざたされそうなもの。
- けれど、その行動傾向が先ほどのような奇行の相を呈ていすということもいつしか知れ渡り、ために半とまつ璃りについては恋人というより、ブラコンをこじらせた姉とその弟という周知がやがてなされた。それは当人たちにとってもおおよそ正しくて、半がまつ璃に対して抱いているのは恋愛感情というより、家族めいた感慨だった。有り難くもあるが、いささか厄やつ介かいな。
- そんなこんなを追想しつつ半はまつ璃の後を追って台所に入る。
- 彼女を手伝ったり、彼は彼で別の一品を料理したり、その情景は長年連れ添った夫婦のように極めて自然で、息が合ったものではあると言えた───が、どうにも若い男女の初々しさやときめきからは、ちと遠かった。
- 半も料理は手て馴なれた方だが、まつ璃は彼よりずっと上じよう手ずで、二人で作れば仕事も早い。程なく部屋に元からある、時代物の卓袱ちやぶ台だいで晩おそい昼ひる餉げをとる半とまつ璃。
- 卓上だけを見れば、古い邦画の一場面のような情緒だが、そこは例の本のかまくらの中。
- 周囲を囲む本の壁と、まつ璃が行あん灯どん代わりに引きこんでいた卓上ライトが投げかける明かりと醸かもし出す雰囲気の、どうにも奇き矯きようなるところ。
- ともあれ半、食べ物の味があることにしみじみ安あん堵どして、大根と豆腐と油揚げと茗みよう荷がを実にし、しっかり出汁だしを取った味噌汁を有り難く啜すすれば、なんとも滋じ味み深い。またここにいられる、まだしばらくは、と心の底から安心感がこみ上げてきて深い溜ため息いきをつく。
- 「お味噌の加減はどう? 今日は少し赤味噌も混ぜてみたのだけれど」
- 「それでか。いつもよりコクがある感じなのは。美う味まいよ。俺の揚げ浸しはどう? めんつゆに紅葉おろしを入れてみた」
- 「おつゆが少しぴりってして、さっぱりと締まってとっても美お味いしい」
- まつ璃と半が作った食事はさして奇異なるところはない、小松菜のおひたしに根菜の筑前煮、鰆さわらの西京漬け焼きに、茄な子すの揚げ浸しといった和食だけれど、いずれもひと手間をかけて、心がほっと和む家庭の味を滲にじませる。
- 確かに忙しい現代人にはなかなか食べることの難しい料理ではあれ、それでも先ほどの半の吐息は切実に過ぎた。
- だがそれだけの理由というのが半なかばにはあって。
- 彼の放浪癖にまつわる、というかその病原である。
- 有あり体ていに言って半の精神の病根である、と言えば大おお仰ぎようだがこれが過言ではない。
- というのもこの青年、同じ場所に留まり続けると、食べる物の味がしなくなってくる、という奇怪で厄やつ介かいな性向というか病に取り憑つかれている。そして味がしない食べ物をとり続けるというのは半にとっては非常な虚むなしさと苦痛をもたらすのだ。
- 絶食には慣れているが、そんなのには限界がある。その状態が到来する間隔はばらばらで、数か月は落ち着いていられる時もあるし、時によっては二週間も持たない場合すらある。
- 故ゆえに半は発作的に、大学の講義も日常生活もかなぐり捨てて、ふらりと目的もない旅に出かける。いつからこうなったのか正確な記憶がないが、少なくとも中学時分からはそうだった。
- 親しい仲間内にもこの奇病は詳つまびらかにしておらず、半は放浪癖をこじらせた奇人として扱われている。
- が、まつ璃りには幼おさな馴な染じみという気易さもあり、かつ学校での便宜をいろいろと図ってもらっているという事情もあり(可能な限りの代返、講義のノートのコピーなどなど)、正直に打ち明けていた。
- 「あらためて、お帰りなさい、半くん。今度はこっちに長くいられるといいわね」
- 「そればかりは俺にもなんともわからない……」
- 「いい旅行だった? 旅先で逢った女の子をつまみ食いとかしちゃった?」
- ……ぎくり、と半の身が強こわ張ばる。これはまつ璃が旅から帰った半を迎えるたびに言う、もちろん冗談なのだけれど、どこかその芯には怖い情念が潜ひそんでいる。
- ともかく半の旅は精神の損耗から逃れるための道行きなので、旅先のアバンチュールなど考えたこともなく、実際そういう機会も余裕もあるはずもなく。
- ただし今回に関しては───笠かさ縫ぬいのことがあった。
- 色気のつまみ食いどころではなく、食い気で本気でかぶりつきにかかった。
- 「………………別に、何にも」
- 答えるまでの間の、明らかなる不自然な長さは、いっそ沈黙を保ったままでいた方がよほどましだったほど。
- まさか半の内心を見透かしたでもあるまいが、底光りのする目でじり、とまつ璃は半に膝ひざでにじり寄る、げに恐ろしきは女の勘働きよ。
- 「まさかして、本当に……何か、誰かあったの? ねえ、なかちゃん……?」
- 思春期を迎えてからは半を「くん」づけにする、まつ璃が「なかちゃん」と、昔の呼び方に戻るのは、彼女が子供時代の追憶に浸っている時か、あるいは感情が大きく振れた際である。
- だから半はそう呼ばれるたびに、すこし面おも映はゆくもあり、素直な気持ちにもなるのだが、ここで全てぶちまけてしまうのは話をもっとややこしくさせてしまいそう、歯止めがかかる。
- 「いや……ガラス乾かん板ぱんの魚に影を食われかかったくらいで」
- 全ては言わず、苦しくもごまかして、残りの料理をかきこむ。
- 「影を。お魚に。ガラスの。お姉ちゃんには判らない言葉なのだけれど」
- 「実は俺にもよく判らない。いつか話すさ」
- 苦しくもごまかして、残りの料理をかきこむ。
- まつ璃りの疑念の目に晒さらされても食事は美味で、半なかばは再三味がする食い物の有り難さを噛かみ締めたものだった。
- 二
- 翌日のこと。昨日で醤油を使い切っていたことを思い出した半が、他にもいろいろ必需品をついでに買い足しておくかと下宿先を出た時のこと。
- 今日も世話焼きかはたまた昨日有う耶や無む耶やになった話を明らかにさせようとしてか、玄関先でまつ璃と鉢合わせした。これから買い物に出ることを伝えたところ、これがまつ璃もついてくるとのこと。
- 「まつ璃姉、別に俺の買い物に付き合わなくってもいいんだが」
- 「ううん、わたしもお風呂用のぬか袋とへちまを切らしていて。買い足しておきたいのね」
- ……まつ璃は美形は美形で、スタイルなどもすらりとよく整い、通常なら異性に受けないはずがない女性なのだが、どうにもそのセンスが『母親』じみていて、今まで彼氏がいたという話を聞かない。今の一言からもそのあたり、窺うかがえよう。
- さて、半が常用している醤油その他日用品はいつも坂の下の商店街で買っている、ので、昨日とは逆にだらだら二人で下る。
- その坂の下の商店街というのは戦前から続いている古い屋並みで、昭和初期の風合いを色濃く残して今に至る。
- よく見られる、一本の通りの両側に店舗が連なっているスタイルではなく、かなり入り組んだ小こう路じにあれやこれやの店がより集つどい、懐かしみのあるとともに『濃い』空間を構成している。
- 扱う品もスーパーなどの流通より細やかで、徳用品もあれば量り売りもやり、琺ほう瑯ろう看板が残った小路から小路を眺ながめて回るだけでも、小さな発見と喜びとで半を飽きさせなかった。
- そんな商店街を、年上の綺き麗れいな女性との共歩きの半なわけだが───
- これがまつ璃がなにくれとなく姉か母親のように世話焼きをしようとするとなると、はっきりと羨うらやましいと言えるかどうか。
- 若者なら見向きもしないような洋品店などに半を連れこんで、下着の棚など指しながら、
- 「そういえば、パンツが結構くたびれたものばかりになってた。新しいの買い足しておいた方がよくなくって、半なかばくん? こちらのブリーフが上等だそうよ。職人さんの手て縫ぬいなんだって聞いたわ」
- とか引っ張り出したのが、確かに縫製も布地も上等そうだが、いやに股また上がみが長くもっさりとした、なんとも『おっさんくさい』代しろ物もので、あまり服にこだわりのない半もこれには少々勘弁願いたい。
- まつ璃りの買い物とやらが済んでいないことを口実に辞退し、彼女の目当ての小間物屋へと足を向ければ、そこでも。
- 「あ、茄な子すの黒焼きの歯磨き粉なんておいてあったんだ。これ、お口の健康にとってもいいらしいの。半くん、どう?」
- 「……どう? と言われても、口の中真っ黒にして歯磨きとかどうにもな……普通の歯磨き粉でいいよ俺は」
- とどうにも年寄りくさいお世話に余念がない。ともかくまつ璃はいろいろと小物を買いこみ、勘定を済ませようとして、帳場の四十がらみの女性に話しかける。
- 「あの、いつものお婆さんは?」
- 「あー、あたし小さ百ゆ合りさんの姪めいなんだけど、小百合さん、腰を痛めて入院しちゃったのよ。その間の店番を頼まれて、ね」
- 「それは……早く良くなるといいんですが」
- 顔馴な染じみのお婆さんの具合を真顔で案じるまつ璃に、婦人は何事かレジに手間取っている様子。
- 半もいつかにまつ璃に付き合ってこの店でそれを見た際にもえらく感心したのだが、この小間物屋のレジカウンターは戦前から生き残っているのではないかと思われる、彫物細工の施された木製の、宝箱とタイプライターの合いの子じみた姿をした骨こつ董とう品ひんだ。
- 作動していること自体が驚嘆ものだし、店番代理の婦人には容易には扱いかねる代物だろう。実際お釣りのやり取りにもいくらか手間取っているのが窺うかがえる。
- と、婦人がふと首を傾かしげた。
- 「あれ。今福引キャンペーン中なんだけど、福引券が見当たらないわ。お客さん千円以上お買い上げだから、一回分の券あげないといけないんだけど……えーと、どこに入っているんだろう。小百合さん、入れ忘れたのかねえ……?」
- と小銭入れの中をあれこれと手探りするうちに、かちり、と音がして何事か嵌はまりこんだような気配があった。婦人の指先が何らかの仕掛けに偶然触れてしまったらしいのだが。
- 「やだ、今あたし何か変なの押しちゃった?」
- ───と。チロリン! と妙に小気味のいい音が響いて、一拍の間。
- するとレジ脇のハンドルが勝手に回転して、さらに。小銭入れの脇板の、よもやそんなところにそんな仕掛けがあろうとは思いもかけぬ箇所から、また一つ小引き出しが迫せり出したのであった。
- 中に入っていたのは、藤色の、古い福引券。
- 三人とも不思議なものでも見るようにそれを眺ながめたが、婦人は一つ頷うなずいてそれを取り、手近のメモ帳になにやら一筆記して店印を押したものと一緒にして、まつ璃りに手渡した。
- 「福引所の人にその添え書き見せてやって。そうすりゃ福引させてくれるはずだから」
- なんとも鷹おう揚ようなことだが、まつ璃も深くは考えた様子もなく受け取って、財布にしまいこんだ。そこまで福引に執着がないのだろう。
- で、二人の買い物が済んで、店を出た半なかばがふと何気なしに上を仰げば、ここでも商店街の軒並みの向こうにあの時計台が望見される。半の間借り先よりは随分と近い。
- 位置的には商店街の中心近くにあるようだが、考えてみればここで買い物をしていて、あの建物を間近に見た覚えがない。なんとなく気にかかって、しばし眺めるうちに、なんとも妙なる涼しい鈴の音が───
- (この音ね色いろ───!! あの高原で!)
- あの日あの時。忘れもしない、忘れられるわけがない。
- 迷いこんだ不思議の高原。あの妖姫と出会うきっかけともなった、美しい音色。
- 風鈴ライチの音色だと半は聞き分けた。時計台の方からだ、と目が釘付けになると、その建物の窓からこちらを覗のぞいた顔がある。
- それは銀色の髪の少女の形なりをして、この上なく美しい───笠かさ縫ぬいだ、と知覚するより先に、足が勝手に走り出していた。
- 「どうしたの半くん、いきなりそんなにして───!?」
- 「後で話す! あの時計台まで行きたい!」
- 人波を掻かき分けるようにして走り出した半を、まつ璃は怪け訝げんそうに、それでも追いかける。こうして二人は商店街の小こう路じの中をぐるぐる走り回ったのだけれど、なのにどうしても時計台があると思おぼしき区画に行き着けない。
- 奇妙なことに、商店街の細い小路はどれもこれもが折れ、曲がり、しながら中心部を迂う回かいするような道筋となっているのらしい。
- どこかの建物の裏口からなら入りこめるのだろうかと焦じれつつ、半がまた目測で入りこんだ小路は、残念ながら、どん詰まりのしもた屋で行き止まっていた。ただそのしもた屋は、今日は福引の抽選場として店先を開けているようだった。
- 「ここ、福引所? そういえば場所はどこかって知らなかったけれど。んん……どうしよっか、半くん」
- 半としても気持ちは急せいていたが、このまま闇やみ雲くもに駆けずり回ったところで時計台には行き着けそうにない。いったん商店街の位置関係を整理してみた方が良いのかもしれない。
- 福引に付き合うなどして、頭を冷やそうと、まつ璃りにいいよと頷うなずいた。
- しもた屋の中は、今は抽選客が途切れているようで、いろいろ実用的な景品を背後に、番の者が暇そうな顔だったのに───まつ璃が遠慮がちに差し出した例の抽選券と添え書きを差し出すと、にわかに唖あ然ぜんとした顔で眉まゆをひそめて券を凝視することしばし。
- 使えない券だったかと居い心ごこ地ちの悪さを覚えたまつ璃が、不安げに尋ねる。
- 「やっぱりその券じゃだめでしょうか。だったらわたし、別に引けなくっても構わない……」
- まつ璃が頼りなさげに問うたところ、
- 「いや違うんだ。そうじゃない。ただなんというか、ちょっと面食らっただけで。『美みしろ』の婆さんは……ああ入院中か。姪っ子が店番しているのだったか。ってことはわかってねえんだろうなそいつ。まあいいや、これも縁だ。回していきなよ」
- とか何とか、半なかばとまつ璃にはどうにもあやふやなことを独りごちて、番の者は抽選のガラガラ車のハンドルをまつ璃に握らせる。
- で、回すことになったわけだが───ガラガラ車が回った途と端たんにまつ璃は当然のこと半も飛びあがりそうになった。
- どういう仕掛けになっているのか、ガラガラ車が半回転するとともに、何事か絡から繰くり仕掛けが作動するような音が響いて、しもた屋それ自体が回転したのである。正確には床はそのままで、前後左右の壁だけが、まるで古い遊園地にある「不思議の家」のように。
- 仰天して手を止めたまつ璃を、店番の者はさらに促した。
- 「いいんだよそれで。ちとびっくりはするだろうが、まあ回し切ってごらん」
- おずおずと回し切った時、さらにしもた屋は回転して、建物の入り口と壁の位置が百八十度反対に入れ替わっていて。
- 戸のガラス越しには、商店街の一角と思おぼしき景色が垣かい間ま見みえていたけれど、どことなく奇妙な雰囲気が漂っているような。
- 「さあこれが景品だよ。『藤券』は、『商店街薄うす闇やみ通り』への案内と引き換えなんだ」
- 訳が判らぬ面持ちのまつ璃と、一方はっと気づいた半だ。行き止まりと思っていた小こう路じは、実はその先がまだ『薄闇通り』とやらに続いているのだという。それはもしや、あの時計台にも繋つながっていないだろうか、と。
- まだ戸惑い顔のまつ璃の手を引いて、半は元は入り口の、今は裏口となった戸を潜くぐれば。木製の階段が下っていっていて───下りていくとそこは奇妙な空間だった。
- 三
- 半地下の広間、というか空間だった。頭上はほとんどが梁はりも屋根板も剥むき出しな屋根で覆おおわれている。広間の内壁は、坂の下の商店街の店の裏口、お勝手口が立ち並んでぐるりと構成されていた。内部も小屋や数軒続きの長屋が建ち並び、商店街の路地とよく似ている。
- 灯りはあちこちにあって昼夜を問わずに照らしているが、全体的に薄暗がりが垂れこめていて、まるで夜に開かれた猥わい雑ざつな市場のよう。
- 内部の建て屋は坂の下の商店街と同じくらい、あるいはもっと年代物の造りをしており、ぼろいと言えばおんぼろの、けれど古い写真を眺ながめるような味わいと、許された者だけに開かれる、秘密の通つう廊ろうを覗のぞいたような興奮を覚えさせる。
- 「……どこかの博物館とかアミューズメント施設でこういうの、なかった?」
- 「俺はこの見た目で『闇市』って言葉が浮かんできた。いや実際には違うんだけど。てか商店街にこんなところあったのか……」
- 二人ともに唖あ然ぜんとしたとしか言いようがなく、半なかばは下りてきた階段を振り向けば、入り口の上には『坂の下商店街薄うす闇やみ通り』という看板が掲げられていた。
- 「こんなところ、知らない人には全然判らないんじゃないのかしら。入り方だってそうでしょう」
- 「一体どこに向けて商売するつもりなんだ、これ」
- 探検気分で歩き出せば、「薄闇通り」の店番や行き来する人々は商店街で知った顔がほとんどで、彼らの会話から察するに、この半地下の空間は商店街の人々の内輪の場所であるらしい。
- 並んでいる店は表側に輪をかけて渋い、というか、通り越して妙なのがあり、いかにもいわくありげな本ばかり扱っていそうな『古こ書しよ肆し黒くろ弥み撒さ館かん』だの、調味料のような化粧品のような綺き麗れいなガラス瓶を並べた『舶来品取り扱い・マアベル商会』だの、半が聞いたことも見たこともないような喫煙具や銘柄の煙草たばこを取りそろえた『喫きつ煙えん具ぐ彗すい星せい堂どう』だの他にも細かく見ればいろいろありそうな。
- 半もついついそちらに気を取られて覗きこんだりしていると。
- 「半くん、そういえばきみ、時計台に行きたいって言ってなかった? 位置的にはたぶんこの中のどこかじゃないの?」
- 「あ……」
- 初めの目的を思い出して周囲に目を巡らせれば、しばし見当がつきかねたけれど、奥に奇妙な一角がある。
- 他が板張りの床になっているのに、そこだけ他より盛り上がり、生け垣に囲まれた小高い丘のようになっている。丘の斜面には一面、灌かん木ぼく、低い草木が茂る。
- 白々と明るく照らされているのは、薄闇通りのほとんどを覆おおう屋根がその一角だけ開いていて、傾きかけた陽が差し込んでくるからだ。
- その灌木の丘のてっぺん辺りから、屋根を越えて伸びあがっている建築物がある。どうやらそれが時計台らしかったが。
- まるでスポットライトのような光の中に、彼女はいた───笠かさ縫ぬいだった。
- 白く細く長い杖を膝ひざの上に横に抱きこみ、その先端には件くだんの風鈴ライチの鈴が下げられていた。屈かがみこんでなにか小さな、見慣れぬ動物に話しかけている。
- ともあれ見た瞬間に半なかばの理性は、やはりと言おうかあっさり消し飛んだ。
- 「やっぱりか、いたあぁぁぁぁ───!!」
- 「半くんいきなりどうしたの!?」
- パチンコの礫つぶてよろしく飛び出していく半には、まつ璃りの声もなにもあったものか。
- 笠かさ縫ぬいが話しかけているのが、純白の細長い動物で、それが後ろ脚で人間めかして立ち上がり、なにか黄色のレンズめいた物を手渡そうとしているところだったとか、そんな状況など湧きあがった食い気に支配された半にとっては些さ末まつ事じである。
- とにかく笠縫を捕まえなくては、その一心で突進していく半の前で立ち上がる妖姫は、彼を認めて軽い溜ため息いき顔だった。呆あきれた、と言わんばかりに。
- 笠縫にあと数歩で手が届く、というところで半の鼻先をくすぐったのはなんとも言えぬいい香り。花、香水の類たぐいではなく、もっと実のある食欲に訴える、なんともいい匂いがくすぐった。
- 笠縫の匂いではない。近いとすればパンの匂いだと思う、が半はこんな薫かおり高いパンなど知らない。いずれにせよ今さら芳香程度で止まる半でない。
- 後先も考えずに掴つかみかかろうとした時、笠縫は長杖の石づきを軽く地に突き下ろせば。
- 大した力を入れた風もなかったのに、打ち込んだ杖は笠縫と白い動物を中心として数メートル、板張りの床を下から巨大な拳で突き上げたように震しん撼かんさせ、その圏内にあったものを衝撃で宙に弾き飛ばしたほど。
- 半も数十センチは浮かび上がって、疾走の勢い余って宙を舞う。
- ただ結果的には笠縫への間を詰めることにもなって、捕まえんと手を振り回したけれど、少女の姿したものはすいと軽やかに躱かわした。
- もちろん笠縫は造ぞう作さもなく躱したのだけれど───彼女のすぐ傍そばにいた、白い動物が。
- 半が振り回した腕に脅おどかされて後ろに跳ねた弾みに、掲げていた琥こ珀はく色の、カップソーサー程度の大きさのレンズのようなものを宙に投げ上げてしまうことになって。
- 途と端たんに頭上から、薄うす闇やみ通りを覆おおっていた屋根の開いているところから、飛んできたのは烏からすだ。
- 一羽の烏が飛びこんできて、宙にあったそのレンズ様のなにかを嘴くちばしにかけて奪い去ったのが、半が板床に叩たたきつけられたのとほぼ同時。
- 「これは、したり───」
- 笠縫、銀の髪を一本引き抜いて、指先で摘つまめばそれはたちまち銀の細針と硬く尖とがった。
- 銀針を烏へ、正確にはくわえていたレンズ様のものへ投げ放てば見事に的中。
- 驚いた烏はだみ声一声で離してしまい、落ちてきたそれをば笠縫、受け止める。
- 烏はなおも頭上を飛び回っていて、なんとも未練がましげだ。笠縫はまた溜息一つ。
- 「そう、じゃの。お前には未練でしょうよ、せっかくの美お味いしいものを。それにわたくしも、誰かが一度口をつけたものを食べようというのは、いささか憚はばかられる」
- 「……ほら、持っておいき。朋ほう輩ばいと仲良く分けるのですよ」
- とて、琥こ珀はく色のそれを結局は烏からすへ投げ与えてしまうのだった。
- 烏は慌てて飛び去る一方、半なかばは。
- 半は背中へ笠かさ縫ぬいに杖の石づきを突き下ろされて動きを封じられていた。ばかりか横顔を彼女の靴のつま先でぐりぐりと踏みにじられていた。
- そのつま先からはやはり銀の粉が散っては消えて、半はそれが消える前にと舌先で舐なめ取ろうと、なんとも浅ましいことだが彼は真剣だった。
- なにしろ笠縫が散らす粉である。その味わいたるや、いかばかりのものか。半は昔菓子の材料として店頭に並んでいたアラザンという銀の粒に、どんなにか素す晴ばらしい味なのだろうと勝手な幻想を抱いて、その単なる砂糖味というのに裏切られたことがあるけれど、笠縫の銀粒はきっとその幻想のままの味がするに違いない。
- そんなことを思いながら舌を伸ばしている半の目と、合った、笠縫の目のなんと蔑さげすみきったことか。顔に食い込むつま先の圧もいや増した。
- 「痛い、痛いぞ笠縫」
- 「お黙りあそべ、お前さま。あのパンはな、他は皆奉納されてしまいましたというに。あれはわたくしへのお裾分けだった。それをお前さまときましたら」
- 「パンだって? 今のが? 奉納?」
- 「左様。琥珀パンというめずらかな食べ物です。こちらの白びやく蓮れん宮ぐう司じが奉納のために捏こねて、焼かれます」
- 笠縫の言を受けて、頷うなずいた白い動物を、ようやく半はカワウソなのだと気がついた。純白の毛皮の。
- 遅れて駆けつけてきたまつ璃りは、笠縫と半と白いカワウソをそれぞれ見回すものの、状況がさっぱり呑のみこめない。
- 「この生き物、カワウソ? そしてこの子は……?」
- 「半、こちらはお前さまのお連れとお見受けしますが、はあ、そも共連れのご婦人がおらるるというのに、他のおなごの首筋にかぶりつこうとするのはいかがものか───まあそれはそれとして」
- 「貴姉あなた、しばしお待ちあれ。わたくし、この半をどう活き締めにするか今思案の最中じゃ。さて生きたままに肝を抜こうか、それとも生き血を吸い出そうか」
- 半を杖の先にかけて容易たやすく引きずり起こし、吊つるし上げ、青年の腹へと翳かざす手の先で、しゃりんと、たちまち凶器のように尖とがる、笠縫の爪。
- 鏡面光沢の眸ひとみが、冷たく無機質な光を放って、これはあながち冗談ばかりとも思われぬ。
- 「待ってくれ、琥珀パンか、そのパンのことは謝る。弁償しよう。だからその爪を下げてくれ、そんなに睨にらまないでくれ」
- 「償うと。ハ。わたくしの話を聞いておられなんだか。他は奉納されたと申しました。そして白びやく蓮れん殿は滅多なことではそのお手を振るわれませぬ」
- ぐいと爪を突き出す笠かさ縫ぬいに、いつしか周囲に寄ってきていた『薄うす闇やみ通り』の人々が頷うなずいた、同じコミュニティ内特有の訳知り顔で。
- 「なんだって、琥こ珀はくパン、烏からすにとられたって? あーあ、もったいない」
- 「白蓮さんもしばらくぶりに顔を見たよ。でもあの子は誰だろう。見ない顔だけど、鞍くら印いん明みよう神じんのゆかりの子かねえ」
- 薄闇通りの人々には琥珀パンの事は周知で、白いカワウソについても、薄闇通りのどこだかに祀まつられる『鞍印明神』とやらの神職として受け容いれられているようだった。
- 衆しゆう人じん環かん視しの中で美しい少女の形なりしたものに吊つるし上げられ責め立てられて、半なかばは慙ざん愧きの思いしていたけれど、同時に笠縫に対しての食い気はまだ止められなくて、二重の意味で煩はん悶もんしていた。そんな笠縫の傍そばにすっと膝ひざをついて願い出たのがまつ璃りである。
- 「やめてあげて、あなた。半くんにはそんなひどいこと、しないであげて。わたしからも謝ります。ごめんなさい。その、パンの弁償が難しいのなら、なにか他のことで……」
- 笠縫はまつ璃に横目をくれて、それでも半を床に降ろして、また溜ため息いき一つ。
- 「はぁ、苦しかった……」
- 「───はぁ。などて。あまり角立てて叱りつけるのも、顧かえりみればはしたない。ひとさまの目を集めた中でお腹を割さくの割かないだのも、汚むさなお話。おまけに綺き麗れいなひとからの口添えもあった。いつもまでも未練がましく言うのはやめましょう。お前さま、どうにも命冥みよう加がなお人よの」
- 白蓮宮ぐう司じが笠縫の裾を引いてなにやら言ってきているのに褄つまを捌さばく挙措も淑しとやかにしゃがみこむ。白いカワウソがなにやら告げているのに聴きいった。
- ……半は既にあの高原で乾かん板ぱんの魚という変奇なものに遭遇したこともある。その上に笠縫との出会いだ。
- なら世の中には二足で立って人並みに振る舞うカワウソというのもあろう、となし崩しに認めてしまっているけれど、冷静に眺めればこれは相当に奇妙な情景ではある。
- 「はあ。もう一度パンを焼くくらいの気力は満ちているから、また作って下さる……と。それはなんとも滅多な……ありがたや。なれど、捏こねる時の酵母……ああ、パン種のことですか。そちらが足らない、と。また時計台まで行かないと、ないと……ふむ」
- そこまで聞いて笠縫は、すらすら立ち上がり、半の耳たぶを引っ張って悲鳴を上げさせ、彼女の口元の高さまで引き下ろす手の、容赦のなさ。まあ今回はあまり半に同情はできないが。
- 「半、もったいなくも白蓮殿は、今一度琥珀パンを焼いて下さるとのこと」
- 「ただそれにはパン種を切らしてしまっている、取りに行かねばなりませぬ。お前さま、罪滅ぼしというものじゃ、それくらいは付き合ってもらいましょう」
- あそこに、と真珠母のような滑らかな顎あご先さきを、軽く逸そらして示した先は。背の低い木の生い茂った丘の、てっぺんで佇たたずむ時計台だった。
- 四
- 薄うす闇やみ通りの一角、丘には道らしいものはついておらず、上の時計台までは斜面に茂った灌かん木ぼくを跨またぎ越していく他なさそうな。
- 多少面倒でもさっさとお使いごとを済ませてしまおうと、踏みこんでみたところが、これが見た目通りの茂みではない、容易ならないと半なかばはすぐさま思い知ることになった。
- 「な、うわ、歩きづらい……何だこりゃ?」
- いちいち踏み折って歩くのも忍びないと、なるべく隙すき間まを選んで下ろしたつもりの足に、いや細枝がさながら粘着性の蔓つるのように巻きつくわ絡みつくわ。
- 足を取られ堪たえきれず前にのめって、灌木の中についた手にも同様に細枝がぞろぞろ絡んで、まるで半を意地悪に捕まえるために伸ばしてやったと言わんばかりの塩あん梅ばいだった。
- 進むも退ひくもままならず、身を起こして踏みこんだ足を引き抜くのもやっとの有様で、茂みから身をもぎ離して困惑しきりの半に、笠かさ縫ぬいが呆あきれたように説いたものである。
- 「そこな茂みは、お前さまには造ぞう作さもなく見えておられようが、それでも歴れつきとした鞍くら印いん明みよう神じんの杜もりじゃ。跨ぎ越していくなど畏おそれ多いと思おぼし召せ」
- 「ならどうやって時計台まで行けばいいんだ」
- 「跨いでいくのが畏れ多いなら、身を慎んで、頭を下げてお進みあれ。パンのことはわたくしにも落ち度がないとは言えませぬ。同道いたします」
- 一緒に行くと、笠縫は半を嬉うれしがらせることを言ったものだが、その鏡面光沢の双そう眸ぼうはまたうっすら冷気を放って、青年が台無しにしたパンの件、まだ陰気に根に持っている様子。
- 「だからさっきのことは謝るってば……で、頭を下げて行けってのは? こうお辞儀しながら進めとか?」
- ひょこりと、身を折るように頭を下げてみせた仕草が、近頃あまり見なくなった水飲み鳥の玩がん具ぐめいたが、笠縫はつまらなさそうな一いち瞥べつをくれたくらいで、
- 「それは、こちらへ」
- と半を伴い、丘を回りこめば、生け垣の一角に僅わずかな切れ間があって、そこに小振りの鳥居が差し掛けられていた。丹にを塗られてから長い様子なのに、手入れも良く艶つや々つやとしているのが、小こ体ていで細工の良いもの特有のゆかしさを醸かもし出す。
- 中を覗のぞきこめば、手首から肘ひじ程度の幅の隙間が、灌木の奥へと延びているのが窺うかがえた。
- 小柄な彼女よりもまだ背の低いこの鳥居に、すっと頭を下げて潜くぐったのが先ほどの言葉通り。
- 茂みの中に入る笠かさ縫ぬいが、どこやら秘密の舞台裏にでも入っていくような。
- 「なにをしておられる。お前さまも来るのですよ。わたくしと同じう、ほら、身を屈かがめてお入りあれ」
- ぼんやり見送っていれば急せかし口の、面倒ではあれ拒めた流れではなく、やれやれと半なかばは笠縫に倣ならって腰を屈める。
- ほとんどしゃがみ歩きするような形で鳥居を潜くぐる半は、背中に落ち枝を踏む気配を聞いた。肩越しに見やればまつ璃りが後に続いて、やはり同じような姿勢で、身を低くしてにじりにじり。
- ……正体は物もの凄すさまじき妖姫とはいえ、見かけは少女の形なりした笠縫を、先遣りにしていい年をした男女がぞろぞろと、鳥居を抜けて藪やぶに吸いこまれていくというのはどこか諷ふう刺し画がめかした烏お滸この沙さ汰たではあるまいか。そんなことを考えるともなし、半はまつ璃に呼びかければ。
- 「あれ……まつ璃姉までわざわざ付き合うことはないって思うんだけど」
- 「あのね半くん、なんだかよく事情も判らないうち、わたしの知らないところでお話が進んでいて、しかもそれでわたし一人でほっぽっておかれるなんて、お姉ちゃん、ちょっとそれはないって思うのよ? そんなの……ちょっと寂しいじゃない」
- まだ穏やかな声こわ音ねながらも、わずかにむくれた気色があって、なるほど無理もないと、さすがに自省の半である。
- まつ璃にとっては自分が笠縫に突進していった辺りから、とんと前後の事情の見えない成り行きであったろうし、ここで薄うす闇やみ通りへ置いていかれても、その後どうしたものかと手をこまねいたことだろう。
- これは日頃の親しさをいいことに、人扱いがぞんざいであったと半は内心でまつ璃に詫びた……が、笠縫のことは一体どう説明したものかとなると、それはいささか青年の手には余った。
- さて初めは這はいずりこむようにしないと入れないくらい狭苦しかったのに、いざ潜ってみればおかしなことに、中は外から見たよりもどう考えても広く深い。
- 背の低い樹々の生け垣どころか藪だった。
- 外から見ればせいぜいが半の膝ひざの上くらいの丈だったはずなのに、中に入ってみればぞろぞろ伸びた木々が密生し、伸び生はえ絡み合う枝葉が濃く、梢こずえもろくに覗のぞけず、高さが窺うかがえないくらい。
- 目と鼻の先に見えていたはずの時計台など、枝と葉群に阻はばまれ影も見えない。
- 「さっきまで、普通の、背の低いツツジとか山吹とか笹が植わってただけだったのに……」
- 辺りを見回したまつ璃が、その濡れて黒い目を見張りながら呆ぼう然ぜんと呟つぶやいたのも無理のない話といえよう。
- 「笠縫、君が何か妖あやしい目くらましでもかけたんじゃないだろうな」
- 「異なことを。ここは、鞍くら印いんの社やしろの杜もり、鎮守の森であるわけですが、一名『惑わしの藪知らず』とも呼ばれておりましてな。つまりは、誘惑が多い、ということ」
- 「誘惑って、こんな森だか藪やぶだかの中でか?」
- 狐こ狸りの類たぐいが現役であった時代でもあるまいし、こんな藪の中で人を惑わすようなものとはなにか、と半なかばが疑問を抱いたのは事実である。
- そもそも誘惑といえば、見やすいのが人の欲に訴えて釣るやつで、金に食い気に後は色気と……確かに半は連想的に美食やら詐さ欺ぎ師やら肌も露あらわな女やらを考えたものだけれど。
- そんな青年に注がれる咎とがめ立ての目線が二つ。
- 「半くん、なんだかいやらしいこと、考えてなぁい?」
- 「やれやれ。お前さまもまあ殿方だということなのでしょうが、もそっと気分を引き締めなさいませ」
- 「……なんでそうなるんだよ」
- いささかこれは濡ぬれ衣ぎぬめいて、納得いたしかねると半は鼻び梁りように皺しわよせた。
- 笠かさ縫ぬいなどはきっとわかっていてあげつらっているのに違いない……青年が抗議の言葉、選ぶより先に笠縫はさらに踏み入ってしまって、銀の髪を軽やかに曳ひきつつ藪の奥へ足元迷わずすらすらすら。
- とにかくここを抜けていかないことには時計台まで行き着かない、琥こ珀はくパンとやらの種が得られないというなら、半も少々の不満は脇にやって笠縫に従うしかないのだった。
- 「しかしあの生け垣の中が、こんなになっていたとはな……」
- こうして笠縫を先立ちに歩んでいけば、奇妙な感慨を抱かせる藪の中だった。
- 半が貧乏旅行の道々で歩いた、林道、山道、森の抜け道のどことも異なる。
- 新鮮な草木の香りに満ちて爽そう快かい、というのではない。
- 歳月を経てねじくれ、お化けじみた輪郭の木こ立だちが並んで不気味、というのとも違う。
- 言ってみればその感覚は、普段はすっかり見慣れてさして気にも留めなかったご近所の空き地の木立の中に、気まぐれで踏みこんでみれば、思いもかけないほどの奥の深さを見た時の驚きに近い。
- 半にとっては追い立てられるような成り行きで潜りこんだ藪ではあったが、ある種風雅な興を抱いだいた。
- けれどそれ以上にぞくぞくとした戦せん慄りつが背せ筋すじを撫なで上げてくる───なにしろあれ以来青年の心に大きな錨いかりとなって沈んでいる、小さな笠縫の姿が手を伸ばせば届く位置にあるのだからして。
- 「半くん、あの、ちょっといい?」
- まつ璃りが何か問いかけているけれど、先立ち歩く笠縫の、見れば肩と背にさらさら銀髪が揺れている。催眠的ですらあり、理性など曖あい昧まいにしそうなくらい滑らかに、銀の髪が歩度に軽く靡なびける。
- 肩から二の腕にかけての華きや奢しやな丸みなどは、両の手で掴つかんでかぶりつくためにあんなに優しく形作られているのに違いない。口内に急速に唾つばが溜まっていくのが判る。
- 「……ええと、半なかばくん?」
- まつ璃りが半の肩を軽く叩たたこうとした手は、青年が足を速めたので不発に終わる。
- (笠かさ縫ぬい、笠縫、笠縫───まさかこの町で、君と───笠縫、ああ笠縫───)
- 知らず足が速まって、我慢というものを知らぬ手が伸びて笠縫に触れる、掴つかむ。
- 多分その瞬間に半がこれまでの人生で積み上げてきたいろいろのものが土台から台無しになる。
- 「半くんてば、お姉ちゃんのお話、聞いて」
- ───寸前でまつ璃が半の袖そでを引いた。
- ……がくんと、半の体は立ったままではあったが、意識の方は高いところから叩き落とされたかの衝撃を伴い彼の輪郭なりに戻って、青年に大量の冷や汗を滲にじませた。
- そう、ここにいるのは半と笠縫だけではない。まつ璃という半を幼い頃より知る年上の女性もちゃんといて、見ている、青年をちゃんと見つめている。
- といって、まつ璃は別段、青年の中に瞬時に噴き上がった食欲の暴走に気づいた風ふうはない。
- 最前から何度も呼んでいたのに、つれなくされていたのにむくれる風はあったけれど。
- 「半くん、今さらになってなんだけれど、この子は?」
- 先ほどの衝撃に半は、しばし認識が怪しくなっていて、舌が言葉を取り戻すまでちょっとかかったけれど、物を言えるようになったところでどう答えたものやら。
- 半はとりあえず、嘘うそはないが全てを語らずに済ませようと───
- 「ああ、彼女は笠縫。ええとな……いいや、話すよ」
- 「こないだの出先で会ったんだ、彼女に。いろいろと助けられた。その時は特にまた会う約束もしないで別れたから、さっきあんな風に再会して、ついうっかり動転した」
- 半としては穏当で無難な言葉を選んだつもりなのだろう。
- しかしそれでもそもそもが間違っていて、なにしろまだ学生とはいえ曲がりなりにも成人男性の半と、見た目はあくまで少女の笠縫と。
- それが、旅先で会ったのいろいろ助けられたのまた会う約束だの、成人女性にする文脈で語ろうとすれば、どうにも誤差が生ずる、無理がある。
- まつ璃は半を見た。ついで笠縫の、いかにも少女然としたひ弱く薄い背中を眺ながめた。
- ───ついでまつ璃の貌かおに浮かんだものは───
- 人としての倫理が。でも長年の幼おさな馴な染じみとしての理解を示すならば。けれど法と情との線引きは必要で。そもそもわたしの気持ちは。
- ほんの数呼吸のうちに、なにやらいろいろな気持ちが透けて見えそうな葛かつ藤とうの終しまいに、まつ璃は、万感を呑のみこんだ笑顔であったそうな。
- 「……半くんが誰かとお付き合いしたお話とか聞いたこともなかったけれど。そっかー……小さい女の子の方が、好きだったっていう───でも大人として弁わきまえてあげてね、半なかばくん。お天道様に顔向けできないことだけは、絶対にだめなんだから」
- ……妙な理解を示されるより、いっそ表立って非難してくれた方がまだましだった、という。
- 「なんでそうなるんだよまつ璃り姉。彼女を見てどうにも思わないのか。確かになりはああなんだけれど……その、見た目のままじゃないっていうか」
- 「え。確かにとっても、すごく綺き麗れいな子だけれど、まだ小さな女の子……でも……? んん」
- 言われてやっとまつ璃も、笠かさ縫ぬいの、並みの成人女性よりはるかに超然として超俗の気配を認めたようで、瞬まばたきしきり。
- 銀と白の背を見て、また見つめて、首を傾かしげる。
- 「小さな子……?」
- 疑う呟つぶやきは口の中に潜ひそめていたけれど、笠縫は聴き取って、振り向いた顔こそが、幼女をあやす乳母じみていた。
- 「貴姉あなた。わたくしの名前はそこな半から聞きましたな。わたくしも貴姉をまつ璃と伺った。半の言う通り、彼とは一度会うてあります。その際わたくし、半に何度なく『食べさせてくれ』とせがまれ往おう生じよういたしたもの」
- 半が言わずに済ませようとしたところを、あっさりとぶちまけてくれたばかりか。
- 「わたくしは見た通りの妖あやかしづれで、人を脅おどかすがならいのもの。そんなのに、半ときたら怖がるどころか食わせろ食わせろと迫ってきて。こんな人の子はそうはおらず、呆あきれていたのですよ」
- 「妖……お化け? あなたが。けどそう言われるとそうとしか……うん。違うのよね、あなたはただの女の子じゃない……でも、なのに半くんが『食べたい』っていうのは一体。それっていやらしい意味じゃ……」
- 笠縫が妖であること、半はあの不思議の高原の一件で身に染みているけれど。
- いかに彼女が人間離れして見えたとて、言葉だけなら夢見がちな少女の妄もう想そう、戯ざれ言ごと、と取られても仕方のない話を、まつ璃が平然と受け容れていたのには半も恐れ入りや。
- ただあの瞬時に猛たけっては身を焦がす、笠縫食いたしの衝動まではさしものまつ璃にも理解不能だったよう。無理もあるまい、半もそれを説明できないし、晒さらされても言い訳もできない、事実なのだから。
- 「うん、ほんと、なにかごめん、まつ璃姉。そういう小児性愛者ペドフアイル的な話かというとそうじゃないんだが、ちょっと自分でも説明しかねる。とにかくいろいろ自制しないとな……」
- など口にはしてみたものの、笠縫がすぐそこにいるのは、阿あ片へん耽たん溺でき者が鼻の下に最上等の練り阿片を押しつけられているようなもの。
- 言葉通りに抑えられるなどと半自身端はなから我を信じていない。
- けれどそこで半はふと気づいた。まだ困惑しきりに考えこんだ風ふ情ぜいのまつ璃には少々憚はばかられることではある。というのは。
- まつ璃りが傍そばにあり、彼女の目を気にするならば、独りでいる時よりは笠かさ縫ぬいへの飢え、いくらかは抑えられそう、ということであり───
- (こりゃ身内が見てるって感覚は、あんがい侮あなどれないもんだな……)
- 実際先ほども、暴発して自分からはみ出るまでに膨ふくれ上がった笠縫への食い気が、まつ璃に袖そでを引かれたので、一緒にすとんと我を取り戻して、抑えられるくらいには鎮まったではないか。
- 藪やぶ歩あるきを始めて幾いく許ばくか。
- 外から見たように、藪の中も上り道ではあったが見たほどの角度はないだらだら坂、息が上がるほどではなかったけれど、先に飽きが来たというか、違和感が兆きざした。先にそれを口にしたのはまつ璃である。また半なかばの袖を引きながら囁ささやく。
- 「半くん、ちょっと変じゃない? さっきまですぐそこに見えていたのに、わたしたちもう随分歩いてない? いつになったら時計台に着くのかしら……」
- 藪の奥へ踏み入っていくうち、枯れた静けさに軽く陶とう然ぜんと彷徨さまよいかかっていた心が我に返れば、なるほど、どう考えても外から見た時よりも長い距離を藪の中で歩いている。
- 笠縫に問いただしてみたところ、
- 「羊よう腸ちようの小こ径みちは、と歌にも歌います通り。たとい小さく狭く映っても、中の小径は、羊の腹の管と同じに曲がりくねって長く伸びるもの」
- 笠縫からはぐらかされるように返されて、
- 「それは箱根の山の話じゃないか。それともそんな天下の険を越えるほどの難所ってことか、ここが?」
- 「とにかく、まだ歩くっていうことね」
- なんにしてもまだ歩き続けなくてはならないことはわかった。
- 五
- この藪歩き、静寂の中に、どこかからキジバトの籠こもったような声が聞こえてくるのは心を鎮めてくれるようで、かつまた、足元柔らかな落ち葉の中に交ざった枯れ枝をぱきんと踏みしだくのは、着想に活の閃ひらめきを入れるようで、半にはむしろ好ましいくらい。
- けれど、旅行に歩き慣れた自分はともかくと、半にはまつ璃の、女の足腰の弱さが気遣われた。あまり長いこと歩くのはできれば勘弁願いたいとも願う。
- 一体どれくらい広いのだ。それに笠縫の言っていた誘惑というのも気にかかる。
- 妖姫が言うならそれは虚こ仮け脅おどしではすまず、確実に何かがあるはずなのだ、と半が周囲を見回した時、枝間を透かして向こうに明かりの連なりがちらほらと覗のぞいた。
- 妖姫の脅おどし文句に、森に迷い死んだ者の無念の火、などいう百物語的連想が働いたけれど、明かりは不気味さよりも、懐かしさをかきたてる可愛かわいらしさで、何事か、確かめずにおられず、半なかばの足はふらふら向かった。
- 「半くん、どこに行くの? そっちでいいの?」
- 「いやまつ璃り姉、何かがある。何かの明かりが点いてる……電気とも違うような……」
- 「ふぅ……また早速に誑たぶらかされて」
- まつ璃の声や笠かさ縫ぬいの溜ため息いきを背中に、近寄らずにいられないのが半という青年の性さがである。
- 下した生ばえを分けて近寄れば、そこは、駄菓子屋なのであった。
- 屋根も壁もないけれど、密生した薮やぶ木立ちや頭上に差し掛かった枝群れがその代わりとなって充分用は足りる。
- 枝から枝へ、蔓つる生なりの烏からす瓜うりとその実をくりぬいて、小さな小さな蝋ろう燭そくを灯した明かりが幾つもぶら下げられている。先ほど半が見た光はこれなのだろう。
- そんな懐かしい、草深い田舎明かりの下に古めかしいガラス戸の平台を並べ、戸棚にはずらりとガラス瓶を置いて、じゃらじゃらと籠かごやらおもちゃやらを吊り下げ、片隅には遊ゆう戯ぎ台を据すえ。今時は田舎でも滅多に見ない、絵に描いたような駄菓子屋。そうとしか思えない空間が、藪の中の空洞じみた隙すき間まに収まっていた。
- 「駄菓子屋……? こんなところで?」
- 「なんだかとっても懐かしい。田舎で半くんとよく通ったのが、こんなお店だったっけね。覚えてる? ほら『十じつ銭せん店』ってあだ名の」
- まつ璃も結局ついてきていて、中の様子に懐かしそうに目元を和ませた。
- 「ああ、あったあった! 百円、二百円くらいの小銭で、下へ手たすりゃ半日遊んでられた。なにか、一体どこで作ってるんだっていう安そうな、煙が出る紙とか、全然爆発しないかんしゃく玉とかな。お菓子なんかはいまだとコンビニとかでも売ってるけどさ、くじとかのはないよな」
- 「三角の飴あめ玉だまのやつとかね。あれ、当たりはおっきいサイズの飴なんだけど、大きすぎて口に入らなくって、引き当てても持て余したっけ」
- 多少配置や造ぞう作さは変わっても、特有の空気は似通って、二人に故郷での共通の追憶のよりどころとなる。
- きょろきょろと見回せば、きっと子供たちには手ごろな広さなのだろうが、大人二人が並ぶとやや手狭なくらいに、びっしりと並べられた駄菓子やおもちゃ、くじ物などいろいろの。
- 是非に食べたい、欲しいというのではないが、懐かしさに惹ひかれあれこれ手に取っているうちに、半もまつ璃も首を捻ひねった。
- 「半くん、こんなの知ってる? さっき言った、指で擦こすって煙を出す紙だって思うんだけど、ここのは『煙とともに体も消えてしまいますのでご注意ください』とかって、変なことが書いてあるの」
- 「まつ璃り姉、こっちのくじ飴あめは『舐なめて小さくなるのと一緒に、体も溶けます』だそうだ」
- 他にも、発泡スチロールと竹ひごとゴムのプロペラ飛行機には『自分も飛んでいってしまいますので注意』、編み紐手芸セットには『自分も編みこまれてなくなってしまうので注意』だの、水と粉を練り合わせて作るお菓子には『自分も練りこんでなくしてしまわないよう注意』とかなんとか。
- とにかく迂う闊かつに食べたり遊んでいると諸もろ共ともに自分がいなくなってしまう系列の注意書きばかりが並んで、読んだ後では試してみる気にもなれず、二人、なんとも塩気をまぶされた顔で元の棚に戻した。
- こんなにも、子供はもちろん大人の気も惹きそうな駄菓子屋なのに、誰もいないのはもしかしてここのお菓子やおもちゃを手に取って消えてしまったのでは、とか怪談めいた疑いさえ湧いてくる始末。烏からす瓜うりの提灯も、やっぱりなんだか人魂めいてふらふら揺れて見える。
- まあ手を出さない限りは懐かしくもあり珍奇でもあり、なによりひときわ目を惹いたのは、片隅に置かれたガラスと真しん鍮ちゆう細工の遊ゆう戯ぎ台だった。
- ドーム状のガラスが嵌はめこまれた八角の台。中には真鍮のレールが複雑に張り巡らされ、それは小さな都市であり遊園地だった。
- なんともハイカラな気配を漂わせる台の中の、ストックではシルバークロームの鋼玉が曇りない艶つやを放って、弾かれるのを今か今かと待っているような。
- 「でもこんなのは田舎のお店にはなかった。わたし、こんなのは初めて見るわ。これ……当てもの? 遊戯台?」
- 「なんだろう。お金入れると球が出てきて、この中のレールをくるくる回って、最後にこのスマートボールの釘盤みたいなとこに落ちて、入った桝ますで当たり外れ、って感じか?」
- これまでどんなアミューズメント施設でも見たことはなく、流は行やりの電子制御装置も演出モニターとも一切無縁であるけれど、それらのどれよりも半なかばを惹ひきつけた。
- その魅力は、子供の頃に贅沢すぎると買ってもらえなかった高級玩がん具ぐが放つそれ。代替品というものはない。半をどうしても試してみなくては気が済まない心ここ地ちにさせて、つい手持ちの小銭を確かめる青年に、妖姫の声は無情だった。
- 「はて半。お前さまは一体何をしに、こんな藪やぶを漕いでいるのかお忘れか。銀玉相手に遊んでいるゆとりなぞ、さておありとでも?」
- 冷たい眼まな差ざしを注いで諫いさめる笠かさ縫ぬいの、しかしなんとも未練気な半の様子に、諦めたように肩を下げた。
- 「一回。お一人さま一回だけですよ。当たりも外れもなく一回だけ。遊んだら、それで終しまいということ、お忘れなく」
- 「えと、わたしは別に遊ばなくってもいいのだけど……」
- 許しも出て、早速遊戯台に小銭を投入してみる半だったが、初めての遊戯台故ゆえにどうにも勝手が掴つかめない。
- ピンボール台のプランジャーに似て、もう少し優美な取っ手を弾けば銀玉は、ガラスの中で小さな都市周遊行を展開していく。
- やがてレールの終端から釘盤にと落ちていって、釘に弾かれ、入った桝ますの結果は、残念、外れで、景品は笛ガム一袋だけが景品口から落ちてきた。こんなものでは子供だって喜ばない。
- けれど半なかばが笠かさ縫ぬいの言いつけにも関わらず、どうしてももう一回、一回だけでいいからまた繰り返したくなったのは、当たり外れがどうこうよりも。
- 真しん鍮ちゆうのレールの細工と配置と、そこを巡っていく銀玉の動きが余りにも滑らかで、魅惑的であったから。
- 走り転がり、エレベータに運ばれ上っては下り、ループに錐きり揉もみ回転し、時には飛び、レールから落ちそうなほどに速く、時には停まる寸前まで鈍く、そしてまた動き出す銀玉の動きが。
- 「あの、笠縫、できればその、もう一回だけ……」
- 「わたくしは一度まで、と申し置いたはず。聞かぬならば、置いていくまで。あとはあい知りません」
- すげなく今にもその場を後にしそうな笠縫に、おずおずと呼びかけたのはまつ璃りである。
- 「でも、まだ一回あるよね、わたしの分。それを半くんに譲ってもかまわないでしょう? わたしはしなくってもいいから。ね?」
- 「まあ、それで勘定は合うのだけれど───貴姉あなた、随分とあまやかしじゃ、の」
- 先ほどと同じく銀玉が滑り転がる今度は半も最初に弾く力加減の見当がついていたし、それ以上にまつ璃の思い遣りが銀玉の動き補正をかけたのであろうが。
- 銀玉は見事大当たりの桝へ入賞、落ちてきた景品は白い無地の小箱の、いやが上にも期待を高めて、もどかしく開ければ、それは確かに一等賞足りえた。肥後守ひごのかみの小刀だった。どきどきするほど研とがれて、小さな鎌かまと鋸のこぎりまでついている。
- 半は山岳民族が元服に与えられるという山刀をいただく想いで懐ふところに収めたし、まつ璃はころころとわがことのように喜んだ。笠縫までもどこかほのぼのと見守ったほどだが、すぐにまた素に戻る。
- 「……ようございましたな。それで満足でしょう、お前さま」
- 「ああ、うん。でもこれは、なにかもらっておくのが悪いような。まつ璃姉、やっぱりこれはあなたが取っておくのが筋じゃないかな」
- 「小刀なんて、特に欲しくないものわたし。半くんが持っておきなさいよ。それじゃ気が済まない、おねえちゃんにくれるっていうなら、わたしはそっちのお菓子でいいのよ」
- まつ璃は笛ガムだけ受け取って、
- 「ここで吹くと蛇が来そうだし、かといってくちゃくちゃ噛かむのも、神様の杜もりの中では失礼でしょう」
- としまいこんだきり。
- こうしてちゃんと戦利品まで得たのだもの、もう心残しは半なかばにもなく、三人は駄菓子屋を出て、また藪やぶの中へ。
- 六
- 藪の中にぽっかり隙すき間まのように開いたその平地で一行は、今度は枝葉を車庫の屋根のように差し掛けられた路面電車の車体を目まの当たりにしていた。
- 半などはそのあまりにも秘ひ匿とく的な眺ながめに、パルチザンが当局の目を逃れて隠した車輌というのはきっとこんな風かと、刹せつ那なそんな妄もう想そうに囚とらわれたくらい。
- 藪の中でただ一輌きり、枯れ葉落ち枝などを静かに被かぶって佇たたずむ廃車輌には、確かにどこか史実の裏側からはみ出てきたかの感が付きまとう。
- まつ璃りはしばし怪け訝げんそうに眺めてふっと得心がいったように頷うなずいた。
- 「学校の資料館に飾ってある写真で見たわ。市内の路面電車の古いのじゃないかしら、これ。たしか昭和の二〇~三〇年代くらいまではこの車輌だったっていう」
- 二人の通う大学がある市内には、現在も路面電車が営業中なのであるが、使用車輌はいくつか代替わりして、この藪の中に鎮座しているのは過去のそれらの中の一つなのだろう。
- 「そういやそんな写真、俺も見たことあるな。街並みとかも今とは全然違う……でもそれはそれとしてまつ璃姉さん、この廃車輌、何か妙な……?」
- 廃車輌に近寄れば、旧時代の車輌にふさわしく、全体的にごつごつとした無骨な車体をしていながらも、控え目ではあるけれど端々に華やかな彫金細工などが施され、なんとなく劇場を想起させる。車窓の内に下ろされたカーテンも細やかな刺し繍しゆう地の、ただどれもこれもどうにも意匠が古くさく見えた。
- この廃車輌の正体は、車体の前面や胴に、本来なら行き先標などがある位置に嵌はめこまれた、真しん鍮ちゆう浮かし彫りのプレートが告げていた。
- 〝Chinemahouseシネマハウス・ neueノイエ Paraiso・パライソ〟
- 「シネマハウス……ってこれ映画館ってことか? こんな、旧車輌一輌きりで? 廃車されてからこんな風に改造されたのか? それとも昔こんな風な映画車輛? が路面電車で走ってたのか? まつ璃姉、聞いたことある?」
- 「わたしだって半くんと同じで、ここの地元民じゃないし、昔のことはそんなに詳しくないもの、判らないわ」
- 藪の中で野ざらしになっていたにもかかわらず、車体は奇妙に状態が良く、昇降口から地面にと据すえられた鋳ちゆう鉄てつ細工の階段にもさして錆さびがない。
- 半がとんとんと、上がって出入り口に手をかければ、扉はずしりと持ち応えはしたが思いのほか滑らかに開いた。そこから中に滑りこんだのがごく当たり前な風なら、まつ璃りが青年に続いて入っていったのも当然の流れとしか見えず───
- 鍵がかかっていなかったことへの違和感を訴える者はいなかった。
- 「誘いが多いからご注意召されと言うたに。先ほどなどはまんまとひっかけられたのに。本当にもう、二人とも子供っぽくて困りものじゃ、そんなでは」
- 笠かさ縫ぬいだけが呆あきれた様子に双そう眸ぼうを冷たく半眼に、白の杖の先に下げられたあの風鈴を一度だけ、二人への警告のように鳴らしたけれど、その余よ韻いんが藪の静せい謐ひつに吸い取られていっても二人が出てくる気配がないと見定め、映画車輛に背を向けた。
- そのまま平地から独り出ていくかに見えたが。
- 足を止め、溜ため息いき一つに肩を落として、引き返してきた様子というのはそうあれだ、玩がん具ぐや人形に気を取られてついてこない幼児を連れ戻す、母親のそれ。
- 車内の客席は、間に合わせ程度に高低つけて、劇場の階段式に改造してあった、
- 客車内には半とまつ璃の他に映写師も誰もおらずしんとして、舞台には機械が三基ほど。
- 舞台に上がって、半はそこに押しこめられた奇妙な機械たちを興きよう味み津しん々しんに見入る。
- 機械のことを説明してくれるような口もなかったけれど、並べられてある三つの機械を半は、それぞれ『幻灯機』『覗のぞき絡から繰くり』、そして『自動紙芝居機』なのではないかと見立てた。
- ───いずれも、電子装置エレクトロニクスなどという得体の知れぬブラックボックスが仕組みの中心を占めるようになる以前の、工芸品じみた造ぞう作さをしていて、先の駄菓子屋の遊ゆう戯ぎ台と一脈通ずる気配がある。
- 「昔の機械時計とか、カメラみたい……これで一体どんなお話や絵を映していたんだろう。きっと昔はみんな、夢中になったんでしょうね……半くん?」
- 「どうにかして動かせないか、これ……」
- 往時の人のみならず、今の半も機械、というかいっそ絡繰り仕掛けというのがふさわしいそれらに引きつけられて、あちこち触れたり覗きこんだりいじったり。
- とはいえ珍奇を好む心だけでは、初見の機械の仕組みまで見透かすことができるわけもない。
- あるいはもともと壊れているためこんな藪の中に置き去りにされているのか、いっこうに作動する気配がない。
- 「駄目か。迂う闊かつに強く押したり引いたりすると、壊しちまいそうで怖いよ。というかそもそもこれ、動力源はなんだろう。電源コードも見えないし……まさかゼンマイ式とか…?」
- 酸っぱい葡ぶ萄どう、の喩たとえの見本のような未練顔で、なおもあれこれまさぐり続ける半の後ろで、とん、と軽い音なのに、青年とまつ璃の足の裏から伝わり、咎とがめるような感触が舞台に伝った。
- 笠縫が双眸を細め妖気漂わせ、白い杖を突いて鳴らしたところだった。
- 「ほんにお前さまときたら……まつ璃、貴姉あなたももっと連れの手綱を絞るがよかし。ここはパンの種とはこれっぱしもかかわりのないところですよ───」
- と笠かさ縫ぬいが、それ以上何か言い募ろうとしたのかどうか。
- 脇から響いた、チキチキ、うぃーん、カシャッ、といった一連の、明めい晰せきな作動音の横よこ入はいりに笠縫の言葉は遮さえぎられ、三人の視線がそちらに集まる。
- 先ほど半なかばが『自動紙芝居機』と見立てた一基の機械。
- 脚付きの、紙芝居を収める函はこを中核として、数本もの機械式の細腕と計算尺とオルゴールのお化けのような機械とで構成されているそれが、半があれほどあれこれしたにもかかわらず無反応だったのに、今にわかに生気を取り戻していたのだった。
- 「ああもう……わたくし、お前たちを起こすつもりなど、ありませなんだのに」
- 笠縫が焦じれったげに呟つぶやいて───きっとこの突然の作動復帰は、笠縫が傍そばに寄ったことでその妖気に反応した、皮肉めいた結果だったのだろうと半は後から推測した。
- 自動機械の、小さな舞台を思わせる函の蓋ふたがからりと開き、機械の腕ががしゃがしゃ動作して、函の裏のストッカーから一組の紙芝居を取り出してきて中に据すえ付けるとともに、オルゴールの無数にピンが植わったシリンダーと、計算尺が連動する。
- 函の中にクロノメーターめいた表示盤が切り替わって、配置された板には、
- 『盗賊紅くれないひばりと少年探偵青せい娥がと怪異馬ば霊れい教きよう』
- とかいう前時代の文脈で綴つづられた表題が現れ、前口上の代わりにぽろんぽろんと音も鳴り出し───
- 「これ半。まつ璃りも。紙芝居語りなどにうつつを抜かさずに。お前さまたち、わたくしの話を全く聞いてござらぬ。わたくしは故ゆえなくして警告したのではないというのに」
- やがて紙芝居の一枚目がめくられ、まるで世界の秘事を開陳する儀式が展開されているかのように、半のみならずまつ璃まで惹ひきつけられて、見入った。
- 時折車体に枝葉が触れて撫なでる、雨だれにも似たさらさらいう幽かそけき音と、紙芝居機の規則正しい作動音とが相まって、催眠的な効果までもたらしていたせいもあったろう。
- 紙芝居は、序盤こそは子供向けと思われたのに、やがてこれは年齢制限を設けた方がよろしいのではと危ぶまれるくらいに、いかがわしくきわどい絵面と話運びになっていき───
- ───けれど二人は、背後から吹き寄せ首筋をひりひりさせるくらいの、熱風とも凍気ともつかぬ気圧に我を取り戻すことになる。
- 笠縫が、その白い杖を大きく振りかぶっていた。
- あまりにも毅然きつぱりとして、刃のごとき鋭い眼まな差ざしだった。
- 「この杖で、その絡から繰くりを叩たたいて黙らせるか、それともお二方のおつむをぶって背せ筋すじをしゃっきりさせるか、どちらがお好みかお選びあそべ」
- 笠縫の威力というのは、物理的な方程式を超えたところにあると気づいている半は当然震えあがったし、まつ璃などは青年の腕を痛いほど掴つかんで縋すがった、膝ひざが崩れていきそうなところを健けな気げに堪こらえているのがわかる。
- 「わかった、もうやめる、もう見ない!」
- 「半なかばくん、早く出よう、ここから早くっ。でないとわたしたちきっと、紙芝居から出られなくなっちゃう───」
- え? と半が訊きき返すより先に、手をしかと握って引っ張って、引きずり出したまつ璃りの力の強さと泡を食った様子はただごとならず、笠かさ縫ぬいに脅おどされたからといっても薬が効きすぎているような。
- 入る時は軽やかに、出る時は転がるように、鋳ちゆう鉄てつ製の階段から飛び出して、まつ璃はどうしたつもりか、半の顔をえらいこと真しん摯しに覗のぞきこんでは、指先で彼の目鼻立ちをまさぐって、そのいささか湿度が高い触れ合いが気恥ずかしく、青年はつい手で払ってしまったけれど。
- 「なんだよまつ姉、俺の顔、そんなにべたべた触ってさ……」
- 「よかったぁ……なかちゃんのお顔だ、いつものあなたの」
- 「な……?」
- 深く安あん堵どの息をついた様子は、むしろ呆あつ気けに取られて言葉を失うほど。
- 「さようですよ、お前さま。まつ璃の言うたことはほとんどが正しい……まったくお二方、いい若い人が、そう物覚えが悪いことには困りもの。わたくしは申しあげましたろう、この藪やぶの中には誘惑が多い、と」
- 呆あきれながら笠縫が、後から出てきて扉を閉めてぱたん、半の未練を断ち切るように。
- 「あの紙芝居の絡繰りはな、見いっているうちに、お話の中の者達と顔を入れ替えられてしまうのです。あのままではお前さまもまつ璃も、別のお顔になり替わっていたでしょうよ」
- 笠縫がその美しい顔に浮かべたうんざり色は、半はもちろんのこと、まつ璃も恥じ入らせた様子だったけれど、それでも彼の前に進み出て、妖姫の呆れる視線から庇かばおうとしたのは、もう青年に甘いというにもほどがあって、砂糖と糖蜜を山がけに被かぶせたくらい。
- 「でもほら、わたしだって気づいたくらいだから、半くんだってすぐにわかったはず。それに、笠縫さんだって、もっと早くに止めてほしかったなあって。だって私、半くんと一緒にあんないかがわしい絵とお話を見るだなんて、恥ずかしい───」
- 笠縫に言い返す気丈、と見えて、俯うつむき加減で足元は藪の落ち葉をつま先で乱して「の」の字の恥じらい草、なんとも今時の娘にしては初心うぶい、と妖姫の目には映って微苦笑させる。
- このまつ璃は、半の前ではいかにも年上然として、わいせつ物関連にも寛大に振る舞ってみせるが内実はこんなもの。かえって半も今になってそわそわ居たたまれなくなって、映画車輛にと振り返り、呟つぶやいたのは照れ隠しのつもりだったのだろう。
- 「あの紙芝居のアングラさ加減……あんなの演やるんだったら、ちゃんと入り口に年齢制限書いておいてくれないと困るよな」
- 「また埒らちもない言い訳を。そんな但し書きなどあってもなくても、きっとお前さまはのこのこ入っていったに違いないわえ」
- 半なかばの言い訳など笠かさ縫ぬいに言下に切り捨てられてしまった。
- 七
- さらに藪やぶ漕こぎを続ける三人の隣に、小流れが添うようになった。井い守もりも泳げばタイコウチやヤゴも棲すまって、子供なら歓声を上げて水遊びを始めたろう。半も多少は興味はあったけれど、ここは抑えて笠縫の後に大人しく従う。
- せせらぎ沿いに伝っていくと、ごとんごとん長閑のどかな音が伝わってきて、やがて出くわしたのは水車小屋。藪の中になかば溶け込むかの、くすんで枯れ葉色の板壁、障子窓、木造の小屋だった。
- こんな藪の中で回り続けている水車、水をまき上げては零こぼし、流れを均ならしつづけているのはなんとも侘びた風ふ情ぜいのあって、立ち止まってしげしげ眺ながめていたい気分になるけれど、これだってきっと誘惑なのだ、とこの頃には半もいい加減に分別している。そのつもりだったのに。
- 「ちょっと寄っていただいていきましょう……この水車では、白びやく蓮れん殿がパンのお粉を引いておられる。まだ足りているとは言うてはいたが、少しばかり運んであげたって罰ばちは当たらない」
- 今度足を止めたは、笠縫なので。
- 彼女が言いだしたことなら、これは大丈夫だろうと半も当然のように妖姫の後に続こうとした、その鼻先に白の杖が突き出され、風鈴が小さく人差し指を突きつけるように鳴る。
- 「したが。半、お前さまは外で大人に待っているように。中に入ればきっとろくでもないことになりましょう、それが今から見えるよう」
- 「えー……そんな風に言われたら余計に気になるだろうが。なにがあるかだけでも教えてほしいぞ」
- 「パンのお粉をもらうだけ、ですよ。種の方は時計台まで行かねばなりませんが。まつ璃り、貴姉あなたはちゃんとこの者について、ふらふらしないよう番をしているように」
- 「わかったけれど……ちょっとそういう気の持たせ方は可哀かわい想そうよ、笠縫さん」
- まつ璃が言いたいことを言ってくれたけれど、といって生殺しには変わらない。
- 水車小屋の中に入っていく笠縫を、つまらなそうに見つめる半だが、小屋の障子窓に大きな破れ目があるのに気づく、いかにも中を覗のぞけと言わんばかりの。
- 入るな、とは言われたが、覗くだけならいいだろう、と半はこっそり障子に近づき、その破れた隙すき間まに目を宛あてがう。万華鏡や望遠鏡を覗きこむよりも、ずっとスリリングな期待とともに。
- 「いけない、半くん、笠縫さんは大人しくしてなさいって」
- 「ちょっと様子を見るだけだよ。それに覗いたところで、何が見えるかもわからないし。な、まつ璃姉。ちょっとだけ」
- 「ちょっとだけ、って言って満足できないのが男のひとなんだけど……でも半なかばくんがそこまで言うのなら……」
- ……まつ璃りのこの半への甘さは、実は青年が気づかぬうちに相当彼をダメ人間にしているのではあるまいか。これでまつ璃がちゃんと半の女であれば、まだ二人を諫いさめようもあるのに、そうではない、幼おさな馴な染じみにして姉めいた、という立ち位置が事態をややこしくしている。
- ともあれ、覗のぞきこむ半にしてみれば魔法のカメラ・オブスキュラを覗くような興奮があったろうが、そのぎょろついた眼はもし内側から見れば障子に湧いた妖怪じみただろう。
- 一つの目で青年は何を見たのかというと───
- 水車の軸が歯車で石いし臼うすに繋つながっているのはまだ当然として、その動力を利用してさらに別の歯車が歯車と連なり噛かみ合い、なんとも複雑な機構に繋がっていた。
- それは、小屋の半分ほどを占めるくらいの大きな台、というより小舞台だ。無数の人形と、背景道具を並べ連ねた。比類ない、美事な絡から繰くり細工、人形劇の小世界だった。
- 彼ら人形たちは全て絡繰り仕掛けで、水車に連動して果てしのない芝居を繰り広げている。 舞台は幾つもの区画に分かたれ、ちょっと見にはむさくるしい街並みと見えたが、全体を俯ふ瞰かんすれば、それは一つの大きな工こう廠しようかと思われる。
- 「半くん、半くん、見すぎ、覗きすぎ───」
- この大工廠の中で人形たちは、一か所だけ見れば、意味のない単純労働であったり、無意味な行ったり来たりを繰り返しているだけのようで、半は次第に気づいて驚嘆した。
- 人形たちは、まず小さな部品から自分たちの同胞を作り出している。
- そしてその同胞を、工廠の生産ラインに乗せると、今度は彼らを使って様々なものを造り出している。それは建物であったり木々であったり山であったり、生き物であったり。
- それらを工廠内に再配分していくと、彼らはそこからいわば『世界の創造』を始めていく。配られた、同朋の体や組み立てられた様々な事物を用いて。
- やがてこのようにして、工廠は端々から自然景にと作り替えられて、小舞台は原始の大地上と化すのだが、そこで人形たちは、今度はその自然の中から道具を作り出し、それをもっと小さな集落を築き、町へと広げて、それを巨大な一つの工廠にと作り上げていって───
- 延々と繰り返される世界の創造とその転変、一体どこの天才がこんな仕掛けを創造しえたのか、半はそこにほとんど魔的な深しん淵えんさえ感じ取ったくらいの。
- さて笠かさ縫ぬいだが、障子窓に背を向け、水車の機構の粉受けから袋にパン粉を詰めている最中で、半が夢中になって覗いていることには気づいていない様子。
- それをいいことに半は、人形舞台にまた没入していく。
- 「半くん、なかちゃん……! もうそれはちょっと覗くってレベルじゃないわ。ほら、もうやめよう? それにきっと……さっきの紙芝居と同じで、ずっと見てるとなにか怖い事が起こるってお姉ちゃん思うのよ」
- どれだけ見ても飽きることを知らず、まつ璃りが何か止めているようだが、目を離せるような舞台ではない、きっとそこには絡から繰くり細工の神が顕けん現げんしているのだから。
- ───と。ひやりと。首筋に。
- 「ようもまあ、見るな、聴くな、の禁じを平気の平へい左ざで破られること。この眼まなこがいけませんか、それともこのお耳が駄目なのかや……?」
- ひやりと、背後から肩越しに、首を伝い横よこ頬ほほに押し当てられる感触の、冷たく冴さえて鋭い刃物のよう。
- 慄りつ然ぜんと目線だけ肩越しに向ければ、半なかばの背後に笠かさ縫ぬいが立って、爪を伸ばし尖とがらせ、銀の刃として脅おどしつけていた。小屋の中には彼女がいるにもかかわらず、である。
- 「だ、だって中には君がまだいるじゃないか!?」
- 「そんな些さ末まつ事ごとより、お前さまはもっと別のことを気にかけたがいい。そうさの、例えば片目だけ、あるいは片耳だけで済むのか、とか。さもなくば、この爪が誤って喉のど笛ぶえまで裂いたりせぬか、とか」
- 優しく囁ささやくような声がかえって怖い。小屋の中と外に同時にいる笠縫の不思議など気にしていられた場合ではない。そういえばあの高原でも似たような妖異な業わざを見せられたか? ……とにかく震えあがる半だったが、ここで助け舟を出さなければまつ璃はまつ璃でない。
- 「あの……半くんはこういう不思議な仕掛けが大好きで。パンの種を取りに行くのは、わたしが代わりに行くから。叱らないであげて。ねえ?」
- 「貴姉あなたはいけないおなごじゃな……そんなでは、殿方を腑ふ抜ぬけにしてしまうでしょうに。とは申せ……実のところ、ここまで来たなら、藪やぶを抜けるのはもう、じきに。そんなところでわたくしも血を見とうはありません」
- 半から爪を離し、笠縫が漏らしたのは小さな溜ため息いきだったのに、これが半にふう、と吹きかけられた途と端たんに轟とどろく烈れつ風ぷうと変じた。
- 「うわああああ!?」
- 勢いも凄すさまじく、青年を吹き飛ばし水車小屋の壁へ磔はりつけにしたくらいで、妖姫の心中の呆あきれ加減の程を示す。
- ずるずる地に崩れる半には一いち瞥べつもくれず、障子の破れ目を撫なでれば破れ目などなかったかのように塞ふさがった。
- それから半にぽんと預けたのが粉袋、笠縫の軽い手つきに反してずしりと持ち余りするそれは、先ほどまで小屋内で袋詰めにしていたものだ。
- 「え、あれ、これってさっきまで君が詰めていた粉袋……でもだってその君はまだ中から出てきてなくて」
- 「半くん、そういうことより、許してもらったことを喜んだ方がよくない?」
- 「この半には、きっと言うだけ無駄なこと。さ、行きましょう。先にも言ったが、もうじきなのだから」
- 粉袋を肩に担いで半なかばは、しみじみ自分の意志の弱さを噛かみ締める、それもあったがそれ以上に、一体こんな藪やぶの中にどこのどいつがどんなつもりでこんな誘惑を仕掛けていやがるのかと憤ふん懣まんの、そこにまだ興味が半分以上混じっていたから始末に負えない。
- まだ『誘惑』はあるのだろうか。それはどんな形をとるのだろうか。
- 共連れの、妖姫と年上の人の心中も知らず、そんなことをどこかしら期待しているあたり、この青年にはそろそろきつい仕置きがあって然しかりのところ、藪が切れて、入った時と同様の小振りの鳥居があって、その向こうに時計台を望むのが先だった。
- 八
- 顧かえりみればあの胡う乱ろんな藪はやはり灌かん木ぼくの茂みでしかなく、数歩も跨またいで降りれば薄うす闇やみ通りまで戻れそうなくらいに幅は狭い。が、藪を顧みるより、半は上を仰いだ。
- 日に晒さらされ、雨雪に濡れてという、長年にわたる野稽古じみた過程の果てに、懐かしく黒ずんだ格子壁と、同様に色あせた後で歳月に色味を深めた日ひ吉え造づくりの軒屋根を三重に重ねた塔だ。
- 下から仰げば大層な由緒の伽が藍らんと見えたが、回りこんでてっぺん近くに嵌はめこまれた時計を見れば、ようやく日頃目にしていた時計台なのだと腑ふに落ちる。
- 小江戸川かわ越ごえ薬師神社の鐘撞堂と似通った風ふ情ぜいの建物だが、あちらが堂門であるのに対して、こちらは鞍くら印いん明みよう神じんの本殿なのであった。
- 「この国が異国に開かれた頃よりやや経たって後、時計台に建て替えられたのです」
- 笠かさ縫ぬいはそう語ったものだが、それ以上の由緒由来の講釈は打ち切って、半とまつ璃りをその本堂の中に押しこんで、この妖姫としては気き忙ぜわな素そ振ぶりをした。
- 彼女も時計台を振り仰いだ時、薄闇通りの屋根の切れ間から覗のぞく空の、染まりつつある茜色を見て、気が急せいたようだった。
- 「あまりおおらかには構えていられぬ。じきです、お二人とも」
- 御み扉とびらを潜くぐる際の、淑しとやかながら軽い会釈は、妖姫が神域に礼を尽くすというより、身内に対する気易さが漂ったのは妙な塩あん梅ばい、ただまつ璃は笠縫が急かし口なのにもかかわらず、二礼二拍手一礼の作法を守って半にもそうさせた。
- 別に分けて信心深いのではないが、まつ璃はどこそこの寺社に詣でた時はもちろん、道端の地蔵や庚こう申しん堂どうを見かけたくらいでも、軽く拝むしその暇がなければ頭を下げて行き過ぎる。
- こんな悠長な心映ばえをしているから、今風の男どもには相手にされないのかもしれないがそれはさておき───
- 本殿の中は、外陣と内陣の区別なく、飴あめ色いろになるまで磨きこまれた板張りの床が一面に広がっているばかりの、これで壁に竹刀でもかかっていれば剣道場だろうし、文机と座ざ布ぶ団とんでも並んでいれば時代外れの寺子屋とも見えたろう。
- が、本殿の大半を占めているのは、銅色、クロームシルバー、赤い金に青い銀色、様々な色合いの金属の輪と支柱を立体的に交差させた、大きな大きな天球儀、そうとしか呼びようのない代しろ物ものだった。
- 「お星さま、お月様とお天道様の、模型……? これ……こんなの、なんていうの? 美術館でも博物館でも、こんなの見たことない……」
- 「天球儀ってやつなんだと思うけど、俺だってこんな立派ででかいのなんて知らないよ……」
- そんな金属細工のミクロコスモスが明みよう神じん様の本殿の中にあって、時計塔の屋根に切られていると思おぼしい明かり採りの窓から降りた、黄昏たそがれの蜂蜜色の陽に染まっている様さまはなんとも夢幻めいている。
- 半なかばとまつ璃りはしばし言葉もなく立ち尽くした。
- 時計台の中でパンの酵母を取ってくると言って、時計台の機構と似たような、歯車とクランクカムで構成された全自動製粉機から粉が出てくるのを待つ、といった情景くらいは予想していたけれど。この錬金術師の工房めいた景色は予想外であったので。
- 「お二方、それなるが、この社やしろの神かむ坐くらです。ご神体はその中におわす」
- そして二人は、蜂蜜の夕映ばえに塗られていく天球儀の中の、ひときわ不思議なオブジェクトを笠かさ縫ぬいに示されて、その正体を確かめるべく歩み寄った。
- 材質は……ガラスなのだと思うけれど、蛍石の澄んだ部分を溶かしてのばし固めた、と言われても頷うなずかれる、色合いはほんのわずかに緑を帯びた透明だった。
- 形は……ここに次元の裏表の秘儀がある、と説かれれば、理解が及ばぬまでもそう信ずるしかない、微妙至極の曲線でもって、口をのばして捻ひねり内部と貫通させて、裏表の別をなくした奇妙不可思議のあの壺つぼ、クラインの壺の形。
- そんなのが、天球儀の中央で金属の支柱で支えられ、まるで永遠に朽ちぬ心臓かとも浮かぶ。
- 笠縫が傍かたわらに寄って二人に頷きかけた。
- 「あれが、こちらの明神のご神体なのですよ」
- 「ご神体って、君、アレは『クラインの壺』じゃないか」
- 「だから鞍くら印いん明神のご神体じゃ」
- 説明がつくのかつかないのか、それが妖あやかしというものの論理なのか首を傾かしげた半に、
- 「見て半くん、西陽が上から……」
- まつ璃が指さしたのは上、見れば天井は吹き抜けで、時計台のてっぺんまでが覗のぞく。大時計のものと思おぼしき機構とそして、塔の内壁に上から下まで仕掛けられた、煌きらめく、幾つもの鏡の細工がある。
- 先ほどから塔てっぺんの採光窓から夕映えは差し込んで、その鏡細工に反射して天球儀に注いでいたのだけれど、その光がいよいよ濃く豊かになりつつある───ちょうど時刻は、日没寸前の、夕映ばえがもっとも色合い豊かに深まる頃合いに差し掛かろう。
- 「夕日が、真上から落ちてくるわ……凄すごい、綺き麗れい……」
- 日没とともに、塔内部ではまさに宇宙の運行を思わせる壮そう麗れいさで夕映えの角度が変移して、天球儀の中のクラインの壷つぼ……鞍くら印いん明みよう神じんのご神体に真上から降り注ぎ───すると、それまでは光を透過させるだけだったオブジェクトが、この時、光を内に溜めていったのである。
- やがて差し込む黄昏たそがれの光は、透き通る壺の中に液体のように満たされていき───
- それとともに透明だった壺は、とろりとした蜂蜜のような、黄こ金がねを溶かしたような色合いに満たされて───
- 「なんて、不思議で……綺麗ねえ……」
- まつ璃りが恍こう惚こつと重ねて呟つぶやいた時に、壺から。
- 口がない、裏と表の区別がないはずの壺から、とろりとろり───と。
- 溢あふれだしたのは、黄昏の陽射しをさらに濃縮させたような金色の光、液体、その両方の性質を兼ね備えていずれとも異なる何かの雫しずく。
- その雫は壺の下に据すえられていた皿へと滴したたり落ち、見る間に琥こ珀はく色の塊かたまりにと結晶化したかと思うと、静かな終しゆう焉えんと密やかな誕生を思わせる鳴音を立てて、割れて、崩れてたちまちに細かな粉にと変じていき───
- ───それが琥珀パンの種、酵母なのだった。
- 皿にさらさら満ちていく細粉の様子を眺ながめて笠かさ縫ぬいが、軽く見開いた眼が、夕映えを映して同じ色。感嘆の吐息とともに半なかばとまつ璃に告げる。
- 「あれが琥珀パンの種です。ともあれ今日はよほどお天道様のご機嫌がいいらしい。こんなにたくさん結晶するなど、滅多にないことですよ、お前さま。それでももうすぐ析せき出しゆつも終わりましょう。そうしたら、取ってくるのですよ、お二人で。半は一人だとどんな粗そ忽こつをやらかすか知らん。まつ璃、貴姉あなたがしかとお手伝いなさいまし、最後まで」
- ……半とまつ璃が、笠縫に促されるまま琥珀パンの種酵母を取りに天球儀の中に踏み入った時には、もう夕映えは採光窓から逸それて、後は残照がさながら光の霞のように揺蕩たゆたっているばかりだった。
- 九
- ───この夜、時計台を眺ながめた者は、もう暗くなっているというのに、そしてその辺りはそんなに烏からすを騒がせるような電飾もないというのに、やけに群れて騒がしいのを見て不審にかられた、という。
- 鞍印明神の社務所にて。
- 宮ぐう司じは白びやく蓮れん、白いカワウソではあるのだけれど、社務所の規格自体は人間大のそれで、半なかばとまつ璃り、そして笠かさ縫ぬいが並んで座っても息苦しさはない。裸電球のもとで畳たたみに座ざ布ぶ団とん敷きの、宮司はお盆に盛った三人分の湯飲みを、器用にそれぞれの前に差し出してから、一礼してパン焼きの工房に戻っていった。まだ窯の余熱の具合を見ないとならないらしい。
- 半とまつ璃としても、あのひどく人間じみた白いカワウソに見られながらよりは、其その方が落ち着いて食えるというものだった。
- 笠縫には言うまでもなく、琥こ珀はくパンは半とまつ璃にまで振る舞われていた。
- 「有り難いことです。このパン、焼くのはとても微妙な加減と、それを見る集中力が必要とかで、とかく作るのが面倒だというお話で。それを、お二人の分まで」
- 「ああ、有り難いよ本当に。もうこれから先、朝晩にこの時計塔に向かって拝もう。だから笠縫、早く、もう……食べてもいいよな? せっかくのほかほかが冷めちまったらもったいない」
- 懇願する声こわ音ねに合わせて、低く、高く鳴っているのは半の腹の虫の、あの高原の時ほどではないにしてもこの今だって相当にやかましく、切実さに満ちている。
- 「そのように焦あせらずとも。このパンの温みは長いこと、他のパンよりずっと長いこともつのだから。きっと黄昏たそがれの陽の温みが宿っているからでしょう」
- 「本当に夕焼けの、琥珀色しているパンなのね……宝石みたい」
- それぞれの膝ひざの前に置かれたお皿は、深い黒曜の中に飴あめ色いろの釉うわぐすりが炎のごとく静かに躍っている土物でパンの琥珀色によく似合い、より美お味いしそうに引き立てる組み合わせ。
- (これきっと高価なものじゃないかしら)
- まつ璃はややたじろいだものの───彼女も舌の根がきゅうきゅうと疼うずいている。空腹は舌の根ばかりではなく、彼女のお腹も鳴かせていて……。
- 「あの……ね、笠縫さん。このお腹の音、半くんばかりじゃないの。実はわたしも、さっきから……。だからそろそろ、いただきます、しましょ……ね?」
- 半ほどではない、彼の腹の音からすれば鈴虫の空鳴きのようなものではあったけれど、まつ璃としてはうっすら赤面するくらいに腹の虫は恥ずかしい、そんな彼女に笠縫はようやく。
- 「ではいただきましょうか。お二方───召し上がれ」
- なぜこいつが仕切るのかと、口にするより先に手がパンに伸びて鷲わし掴づかむ、よりも早いのがなんとまつ璃の手で、半の手を引っ叩ぱたいて、にこやかに、言い聞かせるが有無を言わせぬ調子だ。
- 「半くん、『いただきます』と仏様の手は?」
- 「わ、判った。こりゃ俺が悪かった」
- 慌てていただきますと合掌の、けれどそれさえしてしまえばかじりつくだけ、そして待っていたのはあの懐かしく幸せに満ちた子供時代の、喜びと輝きだった。半とまつ璃はその時代に引きさらわれていた。
- 故郷の河原の土手。辺りには黄昏の光。
- 多分季節は晩秋の、じきに寒さが厳しくなる頃合い。
- 一日をたっぷり遊んだ。といって気の利いた遊びではなく、二人で原や丘を駆け回って、集落の神社の湧水を呑のんで、それぞれ気に入りの秘密の場所に案内し合って、前になって後になって駆けて、そんな風にして二人だけでずっと。
- 集落には二人の他に同年代の子なんていなかったから。
- たっぷりと遊びほうけて、お腹も減って、もうじき晩御飯だけれど二人で買い食いをした。あの『十じつ銭せん店』で焼いて売っていた串団子。お小遣いも乏とぼしかったから、二人で一本、半分こ。
- そこの団子は少し変わっていて、丸い玉ではなく、きりたんぽのように筒の形をしていた。
- まつ璃りは半なかばに先に食べせてくれた。その香ばしさ、甘さ、焦げた醤油のほろ苦さがまた最高だった。あっという間になくなってしまって、もっと食べたくて───
- その黄こ金がね色の瞬間が押し寄せて、押し包まれて、半とまつ璃は知らずに手を握り合って、二人でにっこり笑ったつもりだけれど、その顔は他人からすれば泣き笑いにも見えたのではないか。過去の幸せの思い出は、喜ばしさだけではなく時に切なさまで呼び起こすから。もちろん今が別に不幸せというのではないとしても。
- いずれにしても子供の頃に得た幸福な瞬間のフラッシュバックは、ある意味呪いのように強烈すぎる。
- 最初の一口で追憶の洪水に呑みこまれて、二人は、琥こ珀はくのパンを食べる手を、もう少し慎重に緩ゆるめたのだった。
- 焼き上がったそれは、透き通った艶つやと色を帯びて、まさに大きな琥珀のよう。
- このような見た目は硬質な印象があるのだけれど、パンの手触りと柔らかさはしっかりあり、ちぎって食べられるし、匂い、味わいは仄ほのかに甘く、なのに絶妙な塩味も感じられる。濃密なクリームのようでありながら、口の中で軽やかに溶けていくという、矛盾した味、食感を有している。
- そして香りがなんとも素す晴ばらしい。焼きたてのパンの芳香が、いつまでたっても薄まらず、鼻もそれに慣れることなく、時間が過ぎても鮮やかに華やかに薫かおるのだった。なにやら時計台のあたりで匂いを嗅かぎつけたらしい烏からすが騒いでいるのが聞こえるけれど、それも頷うなずかれる話である。
- 半などは、ゆっくり味わっているつもりがあっという間に食べ尽くしてしまって、少しずつちぎっては静かに幸福そうに食べているまつ璃と笠かさ縫ぬいの口元を、見やる目の、本人は気づいているのかいないのか、そのもの欲しげな顔つきと言ったら。
- 「このパンはな、先ほども言いました通り、温さが長続きするのです。数えていえば二週間は。その間冷めないし、堅くも悪くもならず美お味いしいまま」
- 「戦前の短い間、この町で作られていたのですが、焼き方が伝わらずに途絶えたそうな……白びやく蓮れん殿がそれをどうやって蘇よみがえらせたのかは、わたくしは知らないし深くは問わない」
- 「まあ、数年に一度、彼から報しらせをいただいてこの町に参じてみるのだけれど、此こ度たびは半なかば、お前さまと会うとは、の」
- それでは笠かさ縫ぬいは、半がこの町に部屋を借りるようになる以前から、折に触れてやってきたということか。なにやら灯台下暗しの喩たとえで殴られたような気もするけれど、今の半の関心事はそんなことよりも───まつ璃りが食べ残して、ハンカチに包んでしまいこもうとしているパンの残りだった。
- 「まつ璃姉、こんなに美味うまいパンなのに、食べきれないのか?」
- 「ううん、違うの。あんまりにも美お味いしいから、ごめんなさいね、一人で食べてみたくって。お部屋に持って帰って食べるつもりよ」
- とまつ璃は恥じ入ったように俯うつむいて、は、とすぐさま顔を上げて、何事か振り切るように半を見たという。
- 「もしかして半くん、これ、食べたい? だったらお姉ちゃん、なかちゃんにだったらあげてもいい───」
- 「いやいやいや、さすがにもらうわけにはいかない、ごめん、じろじろ見て!」
- 半にしても、まつ璃から残りを横取りするなど───逸そらした目線が、笠縫と合う。
- 妖姫は、なぜか微笑ほほえんで頷うなずいた。お預けをできた駄犬をねぎらうようだった。
- 十
- 半が大学で講座のレポート提出やらなんやらで帰りが日暮れより遅くなったある晩のこと。
- 琥こ珀はくパンを食した日から既に数日が経たっていて、それでもあの不思議なパンの味は舌に濃密に残っていたけれど、今やそれを押しのけて半を胸苦しくさせるのは、言うまでもない、笠縫への渇かつ望ぼうである。
- あの日は半がパンの味にうっとりするうちに笠縫は消えていた。また出会えるかどうかの保証もないままに。次に白びやく蓮れん宮ぐう司じが琥珀パンを焼けば、狗ぐ賓ひん餅もちに寄り来る天狗のごとくまた誘われてくるのかもしれないけれど、さてそんなのはいつの日になるやらで。
- それではこちらの方から訪ねて歩いてみるか、とは思えど笠縫のいそうな場所などあてもなく、現実的な問題を言えばまだ旅費が貯まらない。
- これはしばらくは飢えに苛さいなまれ、夜の夢にも白昼夢にも見そうなと、苦々しく思っていたら早速にそれを見た。
- 半の部屋で、窓ガラスを開け放ち、桟さんに腰かけ、月の光を浴びていた。
- いかにも悠々と、くつろぎきって、部屋の主あるじはもうずっと先から彼女なのだと言わんばかりに。
- 幻覚を見るかもしれないと心構えしていてもこれはさすがに早すぎる。
- それでも一応頬ほおでも抓つねるか、作法として、と顔に上げた手はさらりとたしなめられた。
- 「夢幻などではなく、わたくしはここに在ある。それはあの日、琥こ珀はくのパンが美お味いしかったのと同じくらい確かなことさな、半なかば」
- 呆あつ気けに取られ、立ち尽くした半に笠かさ縫ぬいは、す、と腕というか肘ひじの内側を差し出し、示。
- その関節のわずかな窪くぼみに、ほんの少し、けれど希少な宝石のように、煌きらめいていた。
- 月の光が雫しずくのように凝ったとしか思えない、薄青の、冴さえた粒。なのに優しい粒が、光の溜まりをわずかに作って、揺れている。
- 「あのように美味しいのは、夕暮れの光ばかりにあらず。こうして、月の影、月の光もまた」
- 半を、もう片方の指で、月の女が男を惑わす仕草はかくもあろうかという美しさで差し招いて───
- 「召し上がれ、お前さま。わたくしの肌と混じって、いい塩あん梅ばいでしょう」
- 半でなくとも堪たえ切れたものか。ふらふらと妖姫の前に跪ひざまずき、唇をそこへ寄せる。
- 笠縫の肌の芳香と、光の混ざった貴とうといもの。味と香りだけが儚はかなく溶ける。
- 肘の内側の窪みなどほんのわずか。けれどもその中に笠縫の精せい髄ずいがある。
- ほんのわずかなのに、啜すすって、啜って、何度も呑のみ干して、まだ香る、味がある。
- 半は夢中になって啜り続けたが、やがてなぜこんな大盤振る舞いを、彼女が? とぼんやり心づくくらいの意識の隙すき間まは取り戻した。そこを見透かしたように笠縫が囁ささやく。
- 「少しは口抑え、宛あてがっておかないと。わたくしを食おう食おうとまた始まります前に。これだけお味見致したなら、しばらくはもちましょう、我慢できましょうお前さま」
- それは。なんとも保証は致しかねるし、だいたいなぜそんな先まで見越したようなことを言う。
- 啜りながらの思いはまた掌てのひら覗のぞかれるように笠縫に読まれる。
- 「後はまあ、このお部屋の店たな代だいですよ、お前さま。わたくしが代銭も払わず居座るような不調法な女とお思いか」
- それはつまり───?
- 今後も笠縫はちょくちょく半の間借り部屋に、押しかけてくるということ、なのか───?
- とそこへ、すらりと襖ふすま戸を開けて入ってきたのがまつ璃りだった。
- あの日、琥珀パンを懐ふところに入れて帰ったせいで、その道すがら犬猫烏からすに追いかけられて大変だった、といったことを話の種に訪れてみれば。
- 日頃から何くれとなく、血の通った弟よりも気にかけて世話を焼いている青年が、少なくとも姿形は少女としか思えない相手の二の腕に吸いついて夢中になって啜っているという情景ときた。
- 「まぁ、仲の良いこと」
- まつ璃は穏やかに笑ったという。
- ただしその口元からは牙が尖とがって覗のぞいているし、手の甲は青筋立てて、出刃包丁の柄えでも構えているのが似合いなくらいに、渾こん身しんの力で握られていたとかなんだとか。
- 第二話・了
- 一
- 本日のお話の始まりは海岸から───
- 空は晴れ渡り秋の特有の透明な陽射しを注いで、海は凪ないで、海鳥などが鳴き交わし、人ひと気けも絶えて、閑静な防波堤の情景である。
- その防波堤に乗りつけてくる空色の旧型車がある。ぱたぱたいう、軽く暢のん気きなエンジン音はスクーターじみていた。軽自動車よりもっと小型の、優美な丸みを帯びた台形で、微笑ほほえみを誘うようにユーモラスなデザインの車体だ。
- 細い防波堤の幅も楽々と進んでいくが、さすがに突とつ端たんまで進んでいくとなると、そのまま転落するのではないかと危なっかしい。
- 縁まで走らせて、あわやのところですれすれでぴたりと停まる。それからドアは、サイドではなくって、フロント全面がぱかりと開いた。
- 意想外なこのドア機構を持つのは、イセッタというもう半世紀以上も前の旧型車である。
- 運転席についていた半なかばは、その姿勢のまま座席の背後の荷物置きに押しこんであった繰り出しの投げ竿ざおを引っ張り出して、するする伸ばして仕掛けをちょいちょい調ととのえると、おもむろに波間へと投ずる。
- 糸は、しゅるるると胸のすく音でリールから繰り出され、放物線も滑らかに針を沈めていって、句く心ごころさえ催もよおさせるくらいの風ふう趣しゆに満ちた余よ韻いんを景色に置いた。
- 「この車に乗った時に思いついて、やってみたかったんだよな」
- 「お前さまにしては風雅な思いつきであること」
- 助手席に、ちょうどよくすっぽり収まった形の笠かさ縫ぬいが、眩まぶしそうに手て庇びさしの、鏡面の光沢の双そう眸ぼうが、眺ながめる波間と同じ拍子で輝いた。
- 「が、それはそれとして笠縫、君にお願いしたいことがある」
- いつもどこか眠たげな眼まな差ざしをした青年としてはそれなりに溌はつ溂らつした顔で、久方ぶりに長く車を運転した緊張感がまだ神経を昂こう揚ようさせているのか、それとも潮の香が心を活気づけたのか、いずれにせよ妖姫へ頼み込んだ声こわ音ねが、随分と歯切れよい。
- で笠縫も、切れよく一言下に切り捨てた。
- 「いやじゃ」
- この辺りの打てば響くような拍子の良さといったらないが、なんともすげなくって、溌溂の貌かおは青菜に塩とたちまち引っこんで、唇尖とがらせ、それでも言いすがる。
- 「まだなにも言う先から『否』はないだろう」
- 「なにも言わずとも知れるというもの。道中、あれだけわたくしの胸元やら腕やらをちらちら覗のぞいておいて。脇見で事故を起こすのではないかと呆あきれましたわえ」
- 「ばれてたか。なら余計に頼む。狭い車内に二人きりで、いやたまらなかった」
- 小柄の体格の笠かさ縫ぬいであれば、イセッタの小型のシートもちょうどよいサイズに見えているのであって、半なかばとしてはやはり、身を縮め、小型飛行機のコクピットに押しこまれる気分で長いことハンドルを操ってきた。
- 肘ひじが彼女の、愛かなしいくらいに薄い、小さな肩口に触れてしまったりする時もあれば、停車した際など、同じ車内に立ちこめる、妖姫の得も言われぬ芳香がどうしても鼻をまさぐり、たまらなく意識されてしまう時もある。
- これなどは世間様から見れば、まだ年とし端はもいかぬ少女を助手席に乗せ、随分長いこと引きずり回してきただけに留まらず、その年に似合わぬ端たん麗れい典てん雅がな美び貌ぼうに、怪しからぬ劣情催してかき口く説どく外道であること確実。
- 何はさておき官憲に突き出しておくのが市民としての義務、ということにもなろう。
- ただそれが半と笠縫となると、物事はちとややこしくなってくる。
- ……出会って以来、この笠縫を食べてしまいたいという衝動にひどく浮かされている半にとって、幸せどころか拷問じみた時間なのだった。運転中にはさすがに、奥歯を軋きしらせるように堪たえたけれど。
- 「なあ笠縫。もう何度も言うけれど。一口だ。そう一口でいいから。君を食べたい。せめてまた『味見』させてくれ。お願いだ」
- 既に半は笠縫の『味見』を一度、二度。指先を舐ねぶり、肘の内側を(正確にはそこに溜まった月光を)啜すすり、彼女の血肉を直に味わったわけでもないのに、それだけで身も心も至上の幸福に包まれた。
- 笠縫を食べることの至福の極み、その一端に一時なりとも触れ得たように半は思う。
- けれどその陶とう酔すいは長くは続かず、一日二日は落ち着いていても、やがてまたぞろ頭をもたげる笠縫への飢え。なまじ彼女を味見してしまっただけに、飢えはより切実になり勝り、多分笠縫はこれをわかっていて、自分に『味見』させているのではないか、と疑わしくなる。
- そんな半の疑念もおねだりもすげなく一いつ蹴しゆうするのが、笠縫なのであった。
- 「……波間に叩たたき落としてしまおうかしらん……いえ、そんな面倒よりも、もっと眺ながめの良いところから海を眺めてこよう。わたくし一人で、な」
- と笠縫は座席から立ち上がりざま、車をかすかに揺らしただけで大きく跳躍し、湾の向こうに佇ちよ立りつしている灯台まで跳んでいくのが、澄んだ蒼そう穹きゆうに昼間の白しろ銀がねの流星。
- 半には目もくれず、銀の粒を車内に散らし残したくらいで、そのつれなさといったら。
- 「……まあ、お願いしたって聞いてくれるとは思っちゃいなかったけどさ……。もうちょっとくらい話に付き合ってくれたっていいだろうに」
- 半はしょうがなく、釣り糸を海に垂れる。一人になっても狭いシートの小型車の上から、なにも今太たい公こう望ぼうを気取るつもりはなく、首尾よく釣れてくれろと念じながら竿さおを繰る。
- そもそもなぜ半なかばと笠かさ縫ぬいが仲良く(?)海になど来ているのかと言うと───
- 二
- 終日そして夜もすがら風雨絶え間なくここ三日ばかり。週の半ばから降り始めてもう週末に至った。夏の終わりを告げる長雨は半を間借りの部屋に押しこめて、余人から見れば無為なる時間を過ごさせたけれど、青年本人としてはさして苦痛でも何でもない。
- 坂の下の商店街は薄うす闇やみ通りの古書店、黒くろ弥み撒さ館かんより三冊百円也で求めてきた得体の知れない文庫本を、腹ばい肘ひじつき、時には煎せん餅べいなどかじりながらのだらしな読みという奴にのんびり耽ふけっていた。
- 長雨を名目にして、いい若い者が何を怠たい惰だなと謗そしられそうだけれども、半としてはこの上ない安息と平穏の時間だ。
- なにしろあの奇病がまたぞろ再発したなら、こんな風に安あん閑かんと部屋に籠こもってなどいられなくなるからして。
- (煎餅もまだ味がちゃんとしてるな……これならまだここにいられる……)
- ───半は決して旅を厭いとうものではないけれど、一方でこの、自分の巣に籠って過ごす、孤独の密やかな一時もこよなく愛している。
- ……そろそろおそってきた眠気に身を委ゆだねることにする。頃合いはもうそろそろ明け方で、常ならそろそろ空が白しらむ頃。それがまだこんなに暗いのは、きっと今日も雨なのだろう、と半はどこか安心した心ここ地ちで寝床に潜りこむ。
- まつ璃りが築いていったあの『本のかまくら』は崩すには惜しいし面倒だ、でそのまま残されていて、その中に布ふ団とんを敷きっぱなしを決めこんでいた。
- 布団にもそもそ這はいずりこんでいき、自分の汗がしみた枕に頬ほおを押し当て目を閉じる。
- (まつ璃姉、ここ何日か見てないな……まあ、雨の中わざわざ来るのも大変だろうし)
- (笠縫の奴もだ。こっちが構えていれば、全然来ない……あいつの気まぐれにはほんと、困るぜ……)
- (ああそうか、俺がなんとなく明日も雨だといいって思ったのは、晴れたらどっかに出かけなくちゃいけないような、そんな気がしてるからか)
- (でも確かに、そろそろ料理の材料が……なくなって……)
- 翌朝半は、小鳥たちのかまびすしく鳴き交わす声に耳を、燦さん々さん降り注ぐ明るい陽射しに目を、それぞれ突かれながら、しょぼしょぼした目で部屋の窓の内から空を見上げていた。
- 晴れ空を嫌うほどひねくれているつもりはないが、雨があれだけ続くとそれなりに名な残ごりが惜しくなって、空を仰ぐ半の胸中がちと微妙な心地なのは、判る者には判る心理だろう。
- 「にしても、お~……見事に晴れたなぁ……朝方まであんなに降ってたのに」
- 今時スクリュー式の鍵を回し、解錠して窓を開けて首を出せば、陽射しは視界に痛いほど。
- 朝の光は、まるでクリスタルの装飾皿でも置いたかに躍り跳ねていて、青年は面食らった。
- そばに鏡でも置いただろうかと、視線を空から横に降ろせば。
- 「まことに。良い日和ひよりです。胸の内までさっと陽射しに洗われるよう」
- 半なかばと肩寄せ合って、窓から身を乗り出し打ち仰いだ、妖姫の銀の髪に、金属光沢の鏡のような双そう眸ぼうに陽射しは弾かれ燦さん々ざめいた。
- そのこめかみや鼻び梁りようなども磨かれたばかりの珠たまのように冴さえる。
- 「うわ!? 笠かさ縫ぬい、君はまたどうしていつも唐突に」
- 笠縫の神しん出しゆつ鬼き没ぼつは身に染みたつもりだったけれど、やはりこうして全くもってなんの先触れもなく、さも当然のように並んでものを言われると、青年にしてもなんとも心臓に悪い。
- あの鞍くら印いんの藪やぶの一件以来、特に用事もなくちょくちょく半の下宿部屋に顔を出すようになっていた(その都度半の食欲を刺激して食わせろ食わせぬの悶もん着ちやくを起こしていた)笠縫だが、この雨の間は姿を見せず、一体どこで雨あめ露つゆを凌しのいでいたのやらと、余計な老ろう婆ば心しんが頭をもたげかかる。
- 「何日ぶりだ。雨の間どこで何をしていた……いや、いい。気にしないでくれ」
- 自由気ままなる妖あやかし相手に人間がそんな配慮などあるいは滑こつ稽けいかと、差し出口は控えた半だったが、笠縫は青年の予想を超えて奔ほん放ぽうだった。
- 「お前さまこそ雨の間、学校以外は閉じこもって、なんのむじなやらもぐらやら。とは申せ、退屈を悪く持て余し暴れるでもなし、大人しい良い子だったと言えば、そう。お前さま、わたくしの前ではいつもあんなにざわめかしいくせに」
- 「……見てたのか!? てか一体どこから!?」
- 「こちらのお庭、そこにな、百日紅さるすべりがありましょう。その木の幹の中ほどに洞うろがある。その木はこちらの家主殿、存じているのか知らぬが、随分古い木です。精が宿るくらいに」
- 「わたくし雨の間、その百日紅の精殿のお招きあって、洞の中に寄せていただいておりました。そこから、お前さまの部屋が見える───見ればいつも眠るかうつらうつらしているか、ご本を読むか」
- 唖あ然ぜんと中庭を見つめれば、猫の額ひたいのようなものだが、家主の老ろう爺やのまめやかな世話があって、木こ立だちもあれば水盤と水みず苔ごけもあり、ちょっとした坪庭めいて名庭といえる。
- その奥には笠縫の言う通り、幹の中ほどに洞の空いた百日紅の老木が一振り。その洞に百日紅の精だかが棲み着いていて、かつ笠縫が雨宿りしていた、と言われると眉まゆ唾つばなのだが、こういうことについては妖姫は冗談は口にしない。というより彼女の口からあまり冗談事を聞いたためしがない。
- とにかく、膝ひざ元でそんな妖精郷へ通じる隙すき間まがあると聞かされ、どうにも気持ちは落ち着かず、すぐさま立って確かめたくなる……ところを、堪こらえた。
- 知らずならとにかく、そうと聞かされて洞うろを覗のぞくのは、人さまの軒下を覗くような、ちと品のないふるまいと思われたので。
- だがそれはそれとしても、同じ屋の庭先にあって一言もなしとは、笠かさ縫ぬいもちとつれなかろうと、半なかばには少しく不満だった。
- 「そんなすぐ傍そばにいたのなら、一言くらい声をかけてくれても……」
- 「それでまたお部屋に寄せてもらったなら寄せてもらったで、お前さま、わたくしの顔やら肩やらにかじりつこうとなさるくせに」
- 「……そうやって言うから、今だってど忘れしていたのを思い出して笠縫を食べたい」
- 「そろそろそれも芸がなくなってまいりましたな。そんなことよりお前さま、この晴れ間を見上げるうちに、わたくし海を眺ながめとうなった。連れて行ってたまわれ」
- 「そんなことって君な、俺にとって君を食いたいってのは凄すごい切実で───なに? 海? なんでいきなり」
- 「この隈くまなく晴れ渡ったお空を映した海は、いかばかり素す敵てきなのかと思いました。眺めとうなった。お前さま、今日は学校もない日だった。故ゆえに、連れて行ってたまわれ」
- なんとも脈絡のあるようなないような、海が見たいとの仰おおせに、半は即応いたしかねた。
- 「たまわれって笠縫……君ならどうせ空飛んだりとか瞬間移動とかでひと飛びだろうに、なんで俺がわざわざ」
- 「いやじゃ。風乗りや遠駆けで一ひと跨またぎに飛んでは風ふ情ぜいというものがありません。さりとて鉄道という気分でもなし。汽車の混みあったりはわたくしの好むところではなし」
- 「となると単車か車か。いや残念だったな笠縫。そんなの俺はどっちも持ってないんだ」
- ……実のところ半は、笠縫にそうして鼻先を取られた犬のように振り回されることを、必ずしも厭いとうものではなく、むしろ受け身の愉たのしさを覚える時さえあるのだけれど、それに慣らされていては、そのうちこの妖姫の言うことに逆らえなくなるだろうと危あやぶんだ。
- 内心では笠縫の誘いを袖そでにすることに後ろめたさを覚えつつ、それでも事実として車などは持たず、無い袖は振れない、そう告げて断れば笠縫は平然と答えた。
- 「お車ならば出しましょう」
- 「へ……?」
- また拍子を外されて、きょとんとなった半をよそに笠縫は、本のかまくらを回って彼の部屋を出る、その前に一度振り向いたのが、外へついてくるようにと促している顔だった。
- 下宿を出て、半の見守る前で、寄宿先のブロック塀にスカートの前を軽く摘つまんで腰屈かがめ、なにやら白はく墨ぼくでかりかり描きこんでいる笠縫である。塀に落書き、と言えば難だけれど、白墨なら洗えば落ちるだろうと、半は内心で家主の老ろう爺やに頭を下げる。
- そんなことを考えている時に、坂道上ってやってきたのが割かつ烹ぽう着ぎ姿のまつ璃りで、彼女も笠かさ縫ぬいも、雨が上がるのを待っていたと言わんばかりの到来だった。
- 両手に提げた、食材入りと思おぼしき買い物袋、半なかばに向けて親しく掲げてみせたのは、青年の冷蔵庫事情を見抜いていて、補充しに来たと問わず語りにしていて、相変わらずの世話焼きぶりというか。その上お下げ髪で真白き割烹着で外歩きというのは、今時どこのお手伝いさんかという姿なので。
- 坂を上りきる辺りで、屈かがんで塀に向かっている笠縫に気がついた風に覗のぞきこむ。
- まつ璃は半の部屋をこの少女の姿したものがたびたび訪れていることに関しても、黙認の立場をとっていた。あるいは気まぐれな犬猫鳥が訪れる程度に見み做なしているのかもしれない。
- 「なぁに? なにしてるのあなたたち?」
- 「彼女が『車出すから海に連れていけ』という強ごう情じようを言いだして。で、車なら出すからって言うんで、外に出てみたんだけど……笠縫、そんなこと言っといて、なにを落書きなんか」
- 「そう急せかすなかれ。ほらできた」
- と、笠縫がブロック塀に描き終えたのは下辺を地面の線とした四角形、まるで何かの窓か門のようなと半が見たのは、だいたいのところ合っていた。
- 笠縫は下辺の縁に指先をかけて、引き上げる仕草をしたかと思うと、なんと彼女が描いた線なりに、塀がまき上げられて、からからといい音まで伴いつつ。まるでガレージのシャッターを引き上げるようだった。
- 塀に出現した矩く形けいの黒い空間を唖あ然ぜんと見守る半とまつ璃の前に、するすると進み出たのが物語冒頭の空色のイセッタである。その不思議をどうこうするよりも、現在の車にはないデザインの妙が気に入ったとみえ、まつ璃が相そう好ごうを崩す。
- 「あら、小さくって丸くって可愛かわいい車」
- 半は半で、度ど肝ぎもを抜かれたことは確かだが、笠縫のやることにいちいち肝を潰つぶしていては始まらず、それよりも、この小さな車の佇たたずまいが記憶の網に引っ掛かった。あれこれ記憶を浚さらえば。
- 「んんん……? なんかで見た、読んだことあるな、この手の軽より小さい車。確かバブルカーとかいう……。うん、この車も画像だけなら見たことあるぞ……イセット? いや、イセッタだったか?」
- 「バブル……? バブル景気の頃の車っていうこと?」
- まつ璃が車体をしげしげ見やれば、BMWのエムブレムが打たれていて、ならば外車、きっとお高い高級品、と彼女は短絡的にそう思ったようだが。
- 「確かにそれっぽく聞こえるけどちょっと違う」
- 詳細は省くが、第二次大戦から程なくして、物資が乏とぼしい中で車としての体裁をぎりぎり整えた、現在からすれば簡易自動車とでもいうような小型車が量産された時期がある。なかでも筆頭がこのイセッタで、その丸っこい、泡のような形状から『バブルカー』のあだ名がついて、一時代を築いたけれど、長くは続かずもっとちゃんとした車にとって代わられた。
- 半なかばの寄宿先があるこの一帯は、だらだら坂に続いて細く古びた路地が入り組んでいるのだけれど、そんな小狭い路地の鄙ひなびた風景にもこの小さなイセッタはよく似合う。
- 車を出してから、笠かさ縫ぬいがまたからからと引き下ろせば、ブロック塀は元通りとなって、白はく墨ぼくの線も消えていた。
- 「これで足もできましたな、お前さま。車の運転くらいおできでしょう?」
- 「まあ、普免は持っちゃいるが。一応MTの奴。この車、きっとマニュアルだろ?」
- と車内を覗のぞきこめば、レイアウトが普通乗用車と違って、ギアレバーがどこにあるのかすぐには判りかねたが、これが運転席側の壁に設しつらえられていた。
- 「その辺りはご自分で確かめなさいまし。いずれにしてもこれで万事差し支えなし。では改めて半、わたくしを海に連れて行ってたまわれ」
- 「え、半くん、ほんとにこれから海に? なにか、いいなあ……」
- せっかく持ち寄った食材、けれどそれは冷蔵庫に入れておけばとりあえずは問題ない。どちらが先約で優先なのかというと、この場合は笠縫なのである。
- ただ笠縫は、妖姫は、この半べったりの娘のことを不思議に甘めに見ている節があって、今日も無下にせずの誘い水。この辺り、半に対するより随分扱いが柔らかい。
- 「さて。まつ璃りもせっかくに居合わせたのだからご一緒に。生あい憎にくこの車は二人乗りなれど、まあわたくしが縮こまればどうにか皆で乗れましょう。随分と窮屈になるけれど、それでもよろしいのであれば、いかがか」
- 「あら、わたしも誘ってくれるの……んー……みんなで、海……んー……」
- まつ璃は随分悩む風だったが、結局辞した。何でも週明けに学科のレポートの再提出があるらしく、この土日はかかりきりになるだろうとの由。
- まつ璃はその慎み深く考え深そうな物腰から、勉強もそつなくこなす才女と見られがちなのだが、実際はさにあらず。
- 意外にも彼女はこと勉強に関してはからきしで、普段から大学の学業単位方面ではひいひい言っているのだった。実際二浪までしていることからも推して知れる。
- とにかく半と笠縫は、その後は思い立ったがなんとやら。
- あれこれ半の荷物と地図を積みこんで準備は完了、さてと半が乗りこんで笠縫が続く。
- 半世紀以上も前の車のはずなのに、車内はどう考えても卸したてで、エンジンだって現行車とは勝手が違うはずなのに一発でかかって、半を驚かせ、呆あきれさせた。
- 初めはご近所をゆっくり一周二周してこの車の感覚に慣れてから、いざ、ということで大通りへの路地へ向かっていくイセッタを、まつ璃が手を振って見送っていた───
- ここからは、半なかばの与あずかり知らぬこと。
- 二人を見送って、半の部屋に上がって、食材を冷蔵庫に詰めるだけ詰めるとまつ璃りは、レポートという厄やつ介かい事があるはずなのに、帰ろうとはせず。割かつ烹ぽう着ぎを脱いで、三つ編みにしていた髪を解ほどいて垂らせば、墨を磨すったような黒髪長く、それは黒曜に艶つやめいているはずなのに、どこか煤すすのようなマットに光を吸いこむ。その目もまた同じ。瞳ひとみは、虚きよ無むの孔あな。
- 自らが築いた本のかまくらの中、敷きっぱなしの半の布ふ団とんの上に座し、さらりとその枕を撫なでる。撫でる、撫でる、撫でては、感極まったようにかき抱いて、立ち上がる青年の匂いを胸いっぱいに吸いこんで、陶とう然ぜんと吐いた溜ため息いき、その顔は。
- 笠かさ縫ぬいに魅せられて跳びかかっていった際の、あるいは妖姫を味見して忘我に浸っている半とさして異ならず、と言えば程度が知れようか。
- 「半くん───やっぱり、その子なの。ええ、そうでしょうね、あなたは。でもね、なかちゃん。お姉ちゃんはそれでもいいもの。だって最後はなかちゃんはおねえちゃんのだもの。なかちゃん、ねえなかちゃん。いつかいつか。思い出してねえ。約束したわよねえ。家のことなんか関係ない。なかちゃん、ああ、大好き。ああ、良い匂い───」
- かき抱いているのは枕ではあるけれど、安あん珍ちんが入った鐘に巻きつく清きよ姫ひめとも見ゆる……枕というのは古来、使う人の形かた代しろともなると考えられていた時代もあり、だとすればまつ璃の邪妄は、半本人が気づいていようがいまいが、その魂に絡みついている、ということはありそうだった。
- 三
- そんなこんなで笠縫に押し流されるように海辺に出ていた半なのだったが、いざ防波堤に面して釣り糸を垂れれば、波の音も海鳥の声も、潮の香りも心ここ地ちよい。景色は、前には海原、後には丘きゆう陵りよう地帯が山にと連なって、地図上の位置的には三浦半島の一角である。
- 思わぬ小旅行となったわけだが、あの無味無臭、灰を噛かむようになった食事に絶望して追い立てられるような道行きよりはよっぽど穏やか。
- まあたまにはこういうのも悪くはないと半は、しばし心を天の青、海の青の狭はざ間まに遊ばせる……までもなく、釣り竿ざおに応えた感触にふと現実に引き戻された。
- アタリだ、魚が引いていると、釣り上げてみれば手応えはずしりと重く、よい型のクロダイで、一竿目を入れたなりこれは幸さい先さきがいい。
- 幸先いいスタートに乗って釣りを続けようとしたところで、半の腹が鳴った。こういう場合は食欲を優先することにしている青年は、早速魚を捌さばきにかかる。
- 小さくはあったが車は車ということで、普段の貧乏旅行では持たないような品もあれこれ積んでいる。折り畳みの小卓などもそうだ。それを調理台代わりにして、これも用意の蛸たこ引ひき包丁で、さくさくと三枚に下ろして冊に作っていくのが魚屋はだしの手際の良さ。
- 包丁も進んであっという間に刺身に引く。活いけ〆じめにしたばかりで、白い身は透き通りそうなほどの新鮮さ、そこに薄皮の銀色と血合いの朱色が交ざって、色合いの艶めかしさ。
- 盛りつけたのがプラ皿なのが少々安いがそこは心ばえで許してほしい、と笠かさ縫ぬいが飛んでいった先、向かいに張り出した堤防の灯台を見上げた。
- 自分が釣り上げたからとて、独り占めにするつもりはない。笠縫に美お味いしいと言ってもらえたなら、きっと嬉うれしい。
- 海鳥が集つどう灯台へ、大きく呼びかけ───
- 「笠かああさあぬ───」
- 「そのような大声いたさずとも、聞こえます」
- 「わあ!」
- すぐ傍そばからの銀泉が注がれるような声、返事に、半なかば、空気を変に吐き出しかかって痰たんが絡まる。
- 灯台にいたはずの笠縫がまた先触れもなく傍かたわらに戻ってきていた。
- しばらく喉のどをゴロゴロやってからようやく具合を整えて文句口。
- 「どうしてそう、凄すごい『だるまさんが転んだ』みたいな挙動をだな。毎回毎回びっくりするんだよ。なんぼ妖怪って言ったって、もう少しこう人に配慮を……」
- まあ笠縫は、やはり大して聞いた風もなく、ただ少々奇妙なことを口にした。
- 「この堤防から、人払いいたしました。なんぞ、妙な気配が聞こえての。お前さまはお気づきかや?」
- 「妙な気配? 俺はなにも。ただ君に釣りたてのクロダイの刺身はどうだろうって……え?」
- 気配がどうのと、そんな武芸者みたいなことを言われても、自分には請け合いかねると、半はクロダイの皿に振り返って怪け訝げん、というか唖あ然ぜんとなった。
- 先ほど皿に盛ったばかりの刺身が、器ごとなくなっていた。醤油を垂らした小皿も一緒に。ほんのちょっと目を離したすきに。
- 車の中や周り、先ほどまで立っていた防波堤の下まで覗のぞきこんだけれどないものはない。
- 「……なんだこれ。今の今まで持ってたものを。なくすとか海に落とすとかは有り得ないだろ」
- 信じられぬといった顔つきであちこち探り、包丁まで確かめて、
- 「……俺、確かに捌いたばっかりで。うん、包丁には脂まで残ってる」
- 「ならば誰たれかが盗っていったのでしょう」
- それが誰か、ということになると、笠縫にも判じかねる様子ではあった。
- 自分が食べたかったのももちろんある。同じくらいに笠縫に食べさせたくて、それがふいになって、ただただ納得いかぬ半ではあったけれど。
- 「なら、また釣って下さいませ、わたくしのために。きっと今日はたくさんたくさん釣れましょうな。この笠かさ縫ぬいが請け合いじゃ」
- そう言われても、先ほどのクロダイに未練が残る、半信半疑でまた竿さおを振れば、よい潮具合だったらしく続けざまに何尾もかかった。それもいずれもアタリが重い。
- よい型のカサゴ、メバル、アジ等、タコまでかかったのに半なかばはなぜかついつい笑ってしまった。笠縫が請け合った通り釣ちよう果かは上々である。
- 今度はまとめて捌さばいた。またなくなったりなどの奇妙なことはもう起こらず、無事二人で新鮮な海の幸にありつく。ただ半は、この良好すぎる釣果に少し疑問を抱いだいた。
- 「……君、なにかしたか? えらい入れ食いだったんだが。こんなのはなかなかないぜ」
- さて? と笠縫は小首を傾かしげるだけで笠縫は答えず、次の刺身へ箸を伸ばす。なかには小振りの、いくらも身が取れないような魚もあったけれど、それでも数匹ともなれば嵩かさは溜まる。また半が調子に乗って次々に下ろしたせいもあって、プラ皿の、数枚がいずれも山盛りに。
- 捌いた後で二人で食いきれるかと危あやぶんだけれど、これがまた小気味いいくらい減って消えていく。
- 当初は、笠縫の、ただ海が見たいだけのはずが、いつしか主旨が海鮮食べ放題に移っているような気がしなくもないが、半もそれに異を唱えるほどの野や暮ぼ天てんではなかった。
- 「ああ、美味うまし。旨や旨や。近頃では街中でも鮮魚を購あがなえる世の中なれど、やはり水際海際で揚げたてに勝る魚ととはなし」
- 「全く同感だ」
- 捌いたばかりよりも、魚によっては少しは熟成させた方が旨味も増すものもあるけれど、二人にはそんな板前じみた蘊うん蓄ちくよりも、海を前にして、釣ったばかりの、という野趣の方が喜ばしい。
- 研とぎたての蛸たこ引ひきで上じよう手ずに下ろされた身は、歯に確かな噛かみ応えを残しつつも溶けるように舌を滑って喉のどに流れ、甘く、旨く、日本酒の冷を欲しくさせる。
- 「お前さまの包丁捌きもなかなかに筋がいい。こんなにも慣れておらるるとはちと予想外」
- 笠縫は割り箸ながら箸先を五分も汚さぬ使い方で、異国めいた銀に移ろう髪と黄こ金がねの鏡面光沢の眸でそこまで綺き麗れいにされるとどうにも妙な気分にさせられる。
- 「……旅先であれこれやっているうちに、な」
- 「しかし怖や怖や。これではわたくしなど、油断していればいつその包丁遣いにかけられて、捌かれてしまうことやら」
- 刺身を美お味いしくいただいていればいいものを、そんな煽あおる言葉など重ねるのだから、半がつい箸先で行儀悪く妖姫を差しながら、言い立ててしまうのも仕方なし。
- 「君なあ、そうやって人を変に煽るような物言いされるとなあ。俺だって君を食いたいってのは洒しや落れじゃないし、結構必死で我慢してるんだぜ、これでも。そこをあんまりそうやって、妙なことを想像させるようなことを言うとだな……」
- 「そこを辛抱いたすのが、男なん女によの礼儀というものさ、な」
- 「そんな特殊な男女間があってたまるか。俺だって君がどんな綺き麗れいな妖あやかしであれ、いきなり食いたいとか暴走するなんて、いくら何でもおかしいって思ってるんだよ───なんでそんなことになるのか、君は何か心当たりとか、ないのか? 君に責せき任にん転てん嫁かしようってんじゃないんだが」
- 刺身を貪むさぼり食いながらするような会話ではないとは思いつつも、ついつい半なかばは内心に溜まっていたものを妖姫にぶつけてしまう形になって。
- 言うだけ言ってしまえば、空には浮かぶMの字海鳥の、こんな折に波の調子が高いのが連続して来て、防波堤の縁からなんとも劇的に飛沫しぶきが飛んで、快晴だったはずなのに、ふっと一片の雲が陽にかかって、辺り一帯が色あせたかに見えたほど。
- 笠かさ縫ぬいはただ、刺身を口に静かに運びながら───
- 「美お味いしい魚ととじゃの、半」
- 「あの、笠縫」
- 「先ほどから、わたくしとお前さま以外、誰もおらぬでしょう?」
- また脈絡のない話の接ぎ穂だが、そういえば確かに、と周囲を見回せば、防波堤に他の釣り人の姿一切なく、散歩や浜辺仕事の人々の姿もない。
- 「先ほど人払いをした、といったはず。まあだから、つまり、今ここはわたくしたちが二人で占領しているようなもの。少々他の方々には迷惑やも知れん。だから半」
- と伏し目にして、姉が幼い弟に噛かんで含めるように言い聞かせる物言いで。
- 「せっかくの美味しい魚ととですが、さくりと食べて、今日はもう帰るといたしましょう」
- 「──────」
- 半は沈黙する他は、箸を動かすくらいしかなかった。
- (知らない、判らない、とは言わなかった。……言いたくないってか。はあ……一体何があるんやら、だ……)
- お終しまいには少しばつの悪い想いはしたけれど、それでもひとしきり食べ終える、と、もう陽も傾く頃合い。そろそろ帰ろうかという段になって後片付けしている半へ、笠縫がまた吹っかけてきた難題がある。
- 「お前さま、わたくしは湯を浴びたい。温泉がよい。ゆっくり浸かって潮の香りを落としていきたく思うのです」
- 「おい今度は温泉とかって。そんなこと急に言われてもな……」
- 笠縫ほどの妖姫なら、潮の香なぞ身を軽く一振るいするだけで造ぞう作さもなく落ちて、後は微香を帯びるばかりであろう。
- そもそもそんな潮臭いか? と鼻面寄せて嗅かごうとしたら、
- 「おなごの匂いをそのように鼻突きつけて嗅ぐものではなし」
- 白の杖でもって額ひたいをこつりとやられて、それ自体は軽い当たりだったのに、刹せつ那な脳天から踵かかとまで垂直に劈つんざいた衝撃に半なかばは、立ったまま失神しそうになった。
- 「す、すまない、今のは俺が無神経だった……でも温泉とか言われたってこの前の旅行が長引いたんで今は懐ふところ具合が……」
- 渋ったけれど、すぐに思い直して、
- 「いや、泊まりとかしないで入浴料だけならそんなにかからないか……この辺りって、どんな温泉があるんだ?」
- 結局は笠かさ縫ぬいに押し切られて、地図を広げて調べ出す半だったが、途中でふと思い出したことがある。
- 「そうか、どうせ温泉行くなら行ってみたい湯がある。付き合ってほしい、笠縫」
- 子し細さいはあえて語らず、持ちかけるだけ持ちかけてみたところ、胸中に期する悪戯いたずら心がやはり顔に漏れてしまっていたようで、笠縫は何事か察しつつも是と頷うなずいた。
- 「どうにも含むところがおありのお顔じゃ。よろしゅうありますよ、お前さま。なにやらいささか面白そう」
- ───二人が乗りこみ、防波堤から走り去っていく車を、見つめる視線があった───
- 四
- 山中の、途中までは細いながらも舗装路だったけれど、最後の数百メートルは民家横の私道だか林道だか判然としない未舗装の砂利道ダートで辺りも宵よい闇やみに泥なずんでいたから、運転も安全優先かつシャーシを擦こすらないように慎重に徐行、イセッタでとっこりとっこり、車というより茶ちや箪だん笥すでも運ばせていくかの加減で砂じや利り道みちに分け入っていった先に。
- バラックの一群が現れたのである。時刻はもうとっぷり陽も暮れた後で夜闇に沈んでいるのは、どれもこれも風雪になかば倒壊して、廃屋に見まがうような小屋ばかり。廃材も辺りにごちゃごちゃと散らばって、山中であるのに難破船が漂着してさらに嵐を受けて倒壊したか、の観を呈ていしている。倒木に押しつぶされたままのトタン板の小屋あり、雪に崩れたと思おぼしきベニヤ板の小屋ありの中で、まともな状態の小屋が二軒程度残って、うち一軒から明かりが漏れており、こんな有様でも人の生活があるのを物語っていた。
- 車を停めて半自身が感に堪たえぬといった有様で呟つぶやく。
- 「どうにかこうにか辿たどり着いたなあ。記憶だよりでどうなるかと思ったが」
- 「これはなかなかに───風ふ情ぜいのある」
- 「……まあ言いたいことはいろいろあるだろうが、でもいいお湯だそうだ。聞いた限りだけど。星ほし八や馬ま温泉という」
- 「たれか人づてに伺った、と?」
- 「旅先でさ、知り合った人に聞いたんだよ」
- 「わたくしはむしろお前さまが、旅の空でお近づきをちゃんと作れるようなお人だった、ということの方がよほど驚いた」
- 「ちょっとひどくないか、それ」
- 言い合いながら車から降りていくと、小屋からこの温泉の主人らしい、六〇がらみの男性が、膝ひざでも悪いのか片脚引き引き出てきて二人を迎えたけれど、大学生と少女の二人連れという組み合わせに、向けた目がまた、胡う散さん臭くさそうな、値踏みをするような……。
- 「わざわざ来てもらって申し訳ないが、もう営業時間は終わっていまして……あとうちは休憩だけで、宿泊はなしなんで」
- 「そう、ですか……」
- 夜陰の山中の小屋に現れた奇異の客なら、山ヤマ和ワ郎ロとか覚サトリ扱いでもしてくれれば、まだ山暮らしの素朴な逸話で済むものを、終しまいには主人が浮かべたのが、半なかばを犯罪者扱いする眼まな差ざしで、これはややこしいことになるより先にと、諦めて引き下がろうとした。
- そんな彼の脇をするり、進み出いでた笠かさ縫ぬいの。山の闇やみに白い花を置いたがごとくだが、花は月下美人ではなく白桔き梗きようの、普段の彼女の妖気は漂わず、ただ清せい楚そなる可か憐れんが香った。
- 「小お父じ様。わたくしは今日は浜風をたんと浴びてきまして。早くお風呂でさっぱりしたいのです。お湯を貸して下さいませ、小父様?」
- 懇願の礼儀も綺き麗れいに、いとも無邪気に、そしてこの少女の姿したモノに『小父様』などと呼ばわれれば、貴家の令嬢が頼る爺やとも森番ともなった心ここ地ちであろう。
- 「え? お嬢さん、あんた……?」
- 「お湯屋はどちらに? こちらのお湯はとてもとてもよいのだと聞かされました。わたくし、楽しみにしてきたの」
- 「え、風呂は……あっちの小屋で……うん。その、なんだ。まあゆっくり浸かっていくといいよ……」
- 「ありがとう存じます、小父様。とっても嬉うれしい。兄様、大丈夫だそうよ、お借りしましょうね」
- 主人の躊躇ためらいと懐かい疑ぎはいつの間にやら溶け流れ、後からはいかにも物分かりよろしい好こう々こう爺や然とした顔で許しを出して、半壊の小屋群の中にもう一つまともに残った、丸太組みのバンガローを示した。
- ただ半にはそれが目の前で指をくるくる回された蜻蛉トンボの様子とどうにも重なってしまうのであった。
- 妖姫の心の法、妖術、という言葉も半の胸中をよぎったけれど、そんな小難しい説明よりも今の『兄様』という声の、甘やかさ、ゆかしさ、親しさのほうがよほど雄弁というもの。つい青年までも茫ぼうと心が溶けそうになるくらいの呼びかけで、同様の『小父様』を真正面から何度も浴びては主人もまともではいられまい。
- (笠かさ縫ぬい、君それずるいだろう。なに可愛かわいい子ぶってご主人を誑たぶらかして……)
- 小声で呼びかけた半なかばに、笠縫はなんとも無心な顔で二度ほど瞬きするばかりで白々しい。
- それで結局なんとも胡う乱ろんな流れで今夜の風呂が決まった。
- 湯は冷泉のようで薪まきで沸かす式、今日はもう湯を落としていたようだけれど汲くみ直して釜に薪をくべるところまでは主人がやってくれたが、以降彼は半と笠縫には関心を寄せず、小屋に籠こもって放置のつもり。
- というより二人の存在が認識から脱落しているらしく、やはり笠縫の妖気にあてられていたのだろう。
- 「それではわたくしがお先に───」
- 笠縫は当然のごとく一番風呂を主張したし半も言い返す愚を犯さず、彼女が湯に浸かっている間に、待つだけなのも暇なので、青年は湯小屋の隣の炊事場を借りた。
- トタン屋根が差し掛けてあるだけの吹きさらしの流しと竈かまどだけだったけれど、温泉とは別に水道も通っていたし、火の気は薪を少々拝借すれば事足りる。
- 日中に釣った魚がまだ刺身にしたり焼いたりするくらいはあって、日が暮れる前に道端で、ムカゴ、ミズ、ノビルといったちょっとした山菜野草も見かけて摘つんだ。
- 四し囲いの山林から盛んに響いてくる夜の虫の音ね色いろを背景楽に、ムカゴは軽く塩しお茹ゆで、ミズはお浸し、ノビルは洗って味噌をつけたりと、片手間程度の料理ながらも刺身と焼き魚に添えれば、立派に海と山の幸が揃そろった飯となろう。
- 「随分と豪勢な飯になりそうだな……となると。どうしても呑のみたくなるよなあ」
- イセッタの方を物欲しげに見やる……車内には、この山中の温泉に向かう途中の酒屋で買ってきた、地酒の瓶が積んであり。
- 乏とぼしい懐ふところ事情の中でやりくりしたもので、もったいないと言えば言えるが、いい肴が揃っているとなれば話は別。ふらふらと車から引っ張り出してきて、そこで気がつく。
- ここで呑んでしまえばもう今夜は運転できず、もう泊まっていくしかないが、まともな部屋はなさそうだしイセッタは車中泊にはどう考えても向いてない。テントの用意は一応あったが、笠縫は野宿に応じるだろうか。
- それを確かめようと、湯小屋───丸木小屋へと回って、風雪に磨すり減って滑らかな、丸太の壁をノックしながら、壁越しに笠縫に呼びかける。
- 笠縫は湯を満喫しているところ。外見は粗末な丸木小屋、中も特に趣向など凝らしてはおらずに単純な板張りの脱衣所と続きの湯屋で、湯船ばかりは一応檜ひのきではあった大人が三人も浸かれば肩がへし合う程度のもの。さすがに槇まきの大風呂までは望めまい。
- それでも笠縫がいかにも寛かん闊かつに手足を伸ばしてくつろいでいる様さまを見るのなら、吊つるされた裸電球の明かりは自ら光る黄水晶の珠たま、湯気に濡れた板張りの四方は、海神の隠れ宮の雫しずく滴したたる岩屋とも映ろう。
- 湯船の縁に結い上げた頭の後ろをもたせかけ、湯の中に憩いこわせた肢体は、熟れて実った女としての柔らかな丸みは確かに欠いていたけれど、けして男のように無骨に平板なのでもなく、かといって未来を予感させるようなふくらみかけというのでもなく、現在で既に完成した、精せい緻ち精せい妙みような均きん衡こうの上に成り立った絶妙の起伏と曲線を描いていた。
- 肌の張りと肌き理めの密なことは言うに及ばず、まさに凝ぎよう脂しという形容があてはまる、湯水を被かぶればころころと小さな珠にして弾こうという肌だった。けれどこめかみに浮いた汗を拭ぬぐおうと、湯面からもたげた腕に、湯は粘りを帯びて滴る。この星八馬の泉質の特徴はこの濃密な泉質にあり、とにかくとろとろとして、さながら何かの潤滑剤の趣おもむきすらある。
- 彼女はこのとろりと稠ちゆう密みつな薬液のような湯の中で、珍かな霊魚のように、ゆったりと四肢を時には揺らめかせ、あるいは浮かせたりなどして愉たのしんだ。
- 「はあ───とぅても、よい、素す敵てきだこと───」
- 風呂の湯気の中で、ほんのりと色づいていそうな、いかにも心ここ地ちよさげな吐息を漏らしたところに、外から丸太壁をこつこつ叩たたく音と、呼びかけてくる声と。
- 『なあ笠かさ縫ぬい。君───』
- 「もうお湯はいい塩あん梅ばい。薪まきは足さずとも結構ですよ……それともお前さま、わたくし食べたさにこのままどんどん火をくべて、煮殺そうというおつもりか」
- 女の風呂に何を口出すつもりの野や暮ぼ天てんと、わざと辛い言葉で応じたのに半なかばは憤った風もなく、壁の向こうから、また。
- 『薪と湯加減じゃなくってだな。飯がいい感じにできたし、俺、せっかくだから酒飲んじゃいたいんだよ。そうなると、ここに野宿ってことになるが、君それで構わないか』
- そういえば美お味いしそうなお酒を買いこんでいた、美酒の前には一晩の仮宿りもまた悪くはないと、笠縫はどこまでも鷹おう揚ように応じ、
- 「ああ、なるほど。わたくしは眠る場所など別にいかようにでも───む!?」
- ───中途で気だるげに伏せていた瞼まぶたをきっ、と。瞠みはられた双そう眸ぼうの金属光沢が強く光って、笠縫はこの時奇妙な気配を聴き取っていたのである。防波堤でも半に仄ほのめかしたあの、妙な。
- 湯小屋の外で、一瞬だけ驟しゆう雨うに見舞われたかの風音が鳴って木こ立だちをざわめかせ、炊事場の中にも風が駆け抜けていったけれど、一吹きで消えて、半は特には気に留めず。
- ただ笠縫は湯船から身を起こしざま、片手で軽く宙をしゃくれば、たん、と湯屋の戸が開き、同時に脱衣場では畳まれていた衣装がふわりと舞う───そして結われていた髪が解けて湯の雫しずくとともに宙を舞って、妖姫の裸身が湯屋から失うせて脱衣場の中に移る。
- 舞い上がった衣装と重なったと思えば、もう次には炊事場に立っていたのが、まるでコマを飛ばしたようだった。
- どんな早回しか、肌の水気は飛んで、衣装は既にちゃんと着けていて、湯に浸かっていたことを示すのはわずかに上気した肌といくらか湿った髪ばかり。驚きよう愕がくしたのは半なかばである。
- ざっ、たん、たん、と湯の音を中と外の扉の音の三つが一つに重なったのを聞いた瞬間には、妖姫が髪を湿らせているくらいですぐ傍そばに立っていたのだから。
- 「び、びっくりした! なんでそんな急に飛び出してきて……」
- 「お前さま。ご飯も酒も台なしということになりそうじゃ」
- 笠かさ縫ぬいの、静かながらもどこか剣けん呑のんに細められた視線を追えば炊事場の、木の卓に並べたはずの料理も酒の瓶も、まとめて姿を消しており───防波堤での一幕と全く同じだった。
- 何がなにやら知れず、訳も判らず───ただ半はそれでも激怒した。飯に加えて酒の恨みは大きすぎた。
- 頭を掻かきむしらんばかり、ほとんど錯乱して、意味もなく番小屋の主人に怒ど鳴なりこもうとした半の襟えり首くびを、笠縫が手を差し伸ばして引き留める。
- 「お待ちなんし、お前さま。こちらのご主人はこのことなぞなにも存ぜぬでしょうよ。これはきっと、多分───お前さま、こちらに」
- 笠縫、辺りをしばし窺うかがうような仕草をすると、おもむろに歩き出したのが廃屋の群れでも砂じや利り道みちの方でもなければ、山中の、木こ立だちの暗くら闇やみへと向かって。
- 五
- バラック群を取り巻く山中の森の中に向かう笠縫のあとを半、訳も判らず追いかける、けれど。ただ足を進めているだけとしか見えないのに、笠縫の足は颯さつ々さつと速い、たちまち引き離されそうになる。
- 慌てて走って追いかける半だったが、笠縫の足取りがまるで舗装された道を行くのとあまりにも変わりないので、ここが民家の明かりと隔へだたった山中の闇の中ということを失念していて、妖姫ならぬ通常人の彼のこと、木の根に足を取られてたちまち転びそうになる。
- とその寸前で、暗くら闇やみの中から白い絹の帯のように伸びて半の手に添えられていたのが笠縫の手の、先に行っていたはずがまたいつの間にか隣に。
- ただ軽く添えただけと見えたのに、半を難なく引き起こし、手と手を繋つないで半を引いてまた歩き出す。
- 「わたくしの手だけに心を向けているように」
- 「わ、わかった……っ」
- 真綿よりも柔らかく、なのに蓮はすの糸を束ねたようにしなやかで、そして小さくて、なにより手の中から胸の底にまで疼うずくような戦せん慄りつが響いて、笠縫の手、半には山林の夜暗さも飯と酒を奪われた怒りも一時忘れさせるほど。
- 繋つないだ手と手ばかりへ自然と、どうしても意識が向かったら、妖姫の不思議の力が伝ったか、彼女と同じように歩くことができていて、もうつまずきもしなかった。
- そうやって森を抜けていけばせせらぎの音が暗中にも軽やかに鳴って、暗がりが開けたと見れば河原に、それはいた。
- 半なかばは田舎町やこういった山中で、月光、月影というのが思いのほか明るく照らすことを知っている。それは陽光とは異なるけれど、銀灰色に四し囲いを濡れ濡れと染めて、時には物の影さえ落とすほど。
- それまで気づいていなかったけれど、この夜もそんな月影の明らかな夜で、木々の切れ間の河原は物凄すごいような銀の小世界と変じていて、その中でひときわ目立つ大岩の上で、それは、そいつは、貪むさぼり食う、食らい、かつ恐ろしい勢いでまた食らい呑のみ干す。
- 半の用意した二人分の食事など、来た時点で三分の二が失うせており、片手で酒の瓶をぐびぐび豪つよい勢いでラッパ飲みしているそいつ───月影の下でも体つきから娘と見えた。
- 「……なんだあいつは。こんな山ン中で独りで、女とか……でもこれって、海の時もあいつがもしかして……?」
- 「まず間違いなく。しかし……残っておったとはの。───一体、どこの一かけらやら」
- 「笠かさ縫ぬい───?」
- 木こ立だちに身を隠し、その様子を窺うかがう半と笠縫だったが───妖姫の囁ささやいた声に滲にじんだのは、深い憂愁と翳かげり、かつまた懐かい旧きゆうと親しみ。
- なによりその言葉が、凝縮された天空、大海、山塊そのもの、そして古い古い時代の残り香のように謎めいていたから、半はどうしても聞き流すことができず、その意味を問おうとして。
- げぇ──ふ、と。深く沈もうとする感慨をいっぺんにぶち壊しにするおくびげつぷの、酒をまたひと煽あおりしたそいつから、ここまで聞こえるくらいに鳴り響いた。
- そいつは満足そうに手の甲で唇を拭ぬぐったが、ふっと鼻先を木立に向けた。隠れているはずの半たちの向きへと、あっさりと。
- 「いるなァ、そこに! 若僧、わかってるんだぜぇ! 妙な匂いさせてよ!」
- 跳躍は、大岩の上から一跳びに数間の距離を軽々詰めた。二人の前に降り立ち、威い嚇かくするように、嘲あざけるようにせせら笑うそいつの姿。袖そでなしの、大きく肩口を出した胴衣に膝ひざ丈の軽かる杉さん袴ばかまともなんともつかぬ衣装、ふくらはぎを剥むき出しにて、上背があるように見えるのは、木履ぽつくりとも沓くつともつかない、踵かかとの高い履物だからで。
- 腰に手を当て背を屈かがめ、覗のぞきこんでくるそいつ。半は相手の居い丈たけ高だかなのに愕がく然ぜんと、笠縫はこちらは堪こたえているのかいないか不明な半眼で、そいつと対たい峙じした。
- 「せっかくオレが気持ちよく昼寝してるところ、その変な匂いで叩たたき起こしやがってさ。魚一匹で許してやろうって思ったが……。まだこの辺りでぐずぐずしやがって。さっさと帰りゃあいいものを、野宿なんかしようとするからこうなる。あの海ら辺からこっちの山ン辺りはこのオレの」
- びっと親指立てて胸を指し、そいつは傲ごう慢まんに己を誇示して、
- 「このオレ、かつての大妖、その名を言うことせぇ畏おそれ多い、玉たま藻もの前も滝たき夜や叉しやも茨いばら木きも目じゃねえくれえの恐ろしの、大妖怪の右腕のこのオレの───」
- 気き炎えん轟ごう々ごう吐き出して、叩たたきつけてくるのがとにかく大音声、ただ耳に痛いだけでなく物理的な圧さえもって半なかばの鼻面を叩くほど。
- つい後ずさったのは当然で、なにしろ今持ち出されたるは玉藻の前をはじめとして皆名だたる女妖、鬼女。それより凄すさまじき大妖怪の眷けん属ぞく一いつ統とうともあれば、こいつの威容は推して知るべし。
- ────────────本当、に?
- 半はもう笠かさ縫ぬいという存在を受け容れてしまっていて慣れもあったろう、妖あやかしを名乗り語るそいつの言葉自体はまだ納得できるとしても、こいつはなにかこう、どこかがこう、傍かたわらの妖姫と比すと地金が透けるというかなんというか───だいたい笠縫も何事か呟つぶやいているでないか。
- 「はてそのような。右腕、と申しましたかお前。右腕───? そんな、大きなかけらが?」
- そいつの胴どう間ま声こえの前では低い呟きなのに、たちまちにさらに機嫌を猛たけらせて、ざわりと頭髪を膨ふくらませたのは怒気か。
- 「うるせえ! なに言ってんだかな女め郎ろが! とにかくここら一帯はオレの、この玉たま串ぐし様の縄張りだぁ! 判ったらとっとと出てけえ……? さもなきゃ今度は痛い目見るぜぇ……ぎゃはははっ」
- 爪が、じゃきりと尖とがりたった。唇まくり上げて覗のぞかせた歯は針のような牙に変じていた。
- 猫科の獣けものの威い嚇かくするように背をたわませ、手は鉤かぎ爪づめにして牙を剥むき、酷薄そうな目つきで睨にらみつけて、しゃあああ、と喉のど鳴なりを一つ、そいつ、玉串は半の前髪を爪の先で弾けば、切れ味鋭く、二筋三筋がはらりと落ちる。
- 次の瞬間、ざん! と砂じや利りが跳ね飛び玉串の姿がぶれた、と見えた時にはまた大きく高く跳んで、宙で身を翻ひるがえすやせせらぎの対岸の山林の中へ。
- 暗くら闇やみへ溶けて、後にはただ耳みみ障ざわりな哄こう笑しようを残すのみ。それもすぐさま遠ざかる。
- かくしていなくなった玉串に、半はしばし呆ぼう然ぜんとしていたものの、すぐさま怒ど髪はつ天を衝ついた。湯気さえ噴きそうだった。山中の夜の暗さも忘れて猛り立った。
- 「……ゆ、ゆ、許さん……っっ!」
- 「はて。玉串。聞いたことがあるような、ないような。なんにせよわざわざ名乗るとは律りち義ぎなこと」
- また何か笠縫が知ったようなことを吐いていたが、そんな細かいことに拘こう泥でいしていられたものかと、半は傍かたわらの立木の幹を腕で叩いて吐き捨てる。
- 「アレがなんで、どこが縄張りだか知ったことか。人の食い物に人の酒……好き放題しておいてそれかぁ!?」
- 「とはいえあれの跳び脚は御覧の通り、なかなかのもの。許そうが許すまいが、お前さま、追いつけるとでも?」
- 「構うか、とにかく追いかけて、とッ捕まえて折せつ檻かんしてくれるっ」
- 「返り討ちに遭うやもしれませぬが。それは鋭そうな歯と爪でしたが」
- 「知るか、食い物の怨うらみだ、晴らさずにおけないだろっ。ああそうだ、笠かさ縫ぬい、君ならきっと追いつけるんじゃないか。追いかけて捕まえてくれ……っ」
- 肝心なところで他人頼み、とは半なかばは理解しておらず、むしろ適材適所、餅もちは餅屋、妖あやかしは妖に任せた方が話が早い程度の分析である。
- 「自分の食い怨みを他人任せにはすまい、お前さま」
- まこともって全く至し当とうな指摘だが、半はなおも食い下がる。
- 「でもあいつは匂いがどうのと言っていただろう。あれって君のことじゃないのかきっと。だとしたら君があいつをいらつかせたようなもので……」
- 「ほ。わたくしの、女の匂いを臭くさしと、厭いやな臭においと」
- そこまで言うつもりはと半はつい口ごもる。だいたい笠縫は随分長風呂をしていたけれど、湯の花の匂いもわずかもないのだからして。ただここでは笠縫の方が鉾を下げた。
- 「とは申せ、わたくしのご飯でもあった。どれ、少すこうし手……というか足を貸しましょうね……」
- 笠縫の手の中に、いつ出現していたのか、あの不思議の実の風鈴を下げた白の杖があった。
- ───きりぃぃぃぃん───
- 一つ鳴らせば山中に澄明で耳に甘い音ね色いろが何かの先触れのように響いて、辺りに満ちていた虫の音が静まり返る。
- 杖の石づきでもって今度は地面に線を描いて、出発の前に塀にしたように。描き終えてから石づきでその端を突けば、山中の地面はからからと軽やかに滑って黒い矩く形けいを覗のぞかせて、その奥からぱっと差した光は、温泉の廃屋軍の前に停めていたはずのイセッタからだ。
- ぷろろん、と軽いエンジン音で、大おお蛙がえるが足回り軽く身を乗り出すように、車は二人の前に現れていた。
- 「お前さま、油ガソリンは……ああ、帰りに一度入れておったっけ。なら保もつわの。ではこれがあの者を追う脚となりましょう、さ、乗りませい」
- さすがにこの小型車では道なき山中を行くのは不可能に思えるが、意味なく呼び出す笠縫ではないだろう。言われるまま乗りこんだ半に妖姫も続く。
- で、エンジンをかけたものの、さてどうしたものかとフロントガラスの向こうに広がる山闇に思案の半の脇で、笠縫は窓を開けて腕を差し出し、白の杖で今度は先端を軽く地面に触れさせればまた甘く涼しい音色の、途と端たんに車体がふっと浮いたような感覚に包まれた。
- 「これでよろしい。さてお前さま、存分に追いかけるがよい」
- 「なんだか判らんが……」
- そろそろと、アクセルを踏んだつもりが加速が半なかばの予想していたよりとんでもない勢いでかかって、たちまち迫る木こ立だちの、
- 「う、わぁ、あ───っっっ!?」
- 「平気です。大事ない」
- もう激突は免れまいと、とっさにブレーキを踏むより先に、なんと、寸前で木がふいっと脇に避よけた。半としては冷や汗もので寿命が縮まる思いだが、実際の情景としてはどこやら滑こつ稽けい味みを帯びる。
- 笠かさ縫ぬいの妖力に包まれたイセッタの進む先では、障害物が道を開けるということらしい。なにやらエンジンの馬力も足回りの発条も、半がこれまで運転していた時より得体の知れぬ地力を見せており───かくして半と笠縫とで、妖怪玉たま串ぐしの追跡劇が始まったことである。
- 六
- その頃玉串は、もうずっと遠く離れた森の中の空き地の倒木の上で、月の光を瓶に映して残りの酒を啜すすっていたのだけれど。木立越しに響いてきた、この林中ではあまり聞かぬ物音に首を傾かしげる。それは車の唸うなり、エンジン音、初めは遠く、たちまちに近づいてくるそれは、明らかに自分を目指しているようだった。
- 「……なんだァ……? 車? こんな山ン中を? マジか!?」
- 酒の残りを呑のみ干すかどうか考える間もなく、木立の奥に点ともった明かりが二つ、獣けもののならば赤く鈍く光るけれどあれは白く眩まばゆい。
- ぐんぐん見る間に近づいてきて、玉串の妖あやかしの目は、逆光に眩くらむ前に、丸い小型車の前で木々が道を開けるのと、その運転席で喚わめいている青年の姿を捉える、もう顔の半ばを口にして、人間なのに恐ろしい。
- 「そこかああああっっ貴様あああっっ」
- 「うええ!? なんだそれなんの手品だよっ」
- ついに木立を割って飛び出してきたイセッタに、玉串は泡食って立ち上がり、また大きく跳んだが今度は横にではなく高く。
- 木の上、梢こずえの上にと一跳びで舞い上がり、さらに他の木々の梢伝いに跳躍し逃れ去る。先ほどよりずっと距離を開けて、ここまでは追いつけまい、登ってこられないだろうと玉串は安あん堵どに酒臭い息を吐いたが、酔いはいつしか飛んでいた。
- 「なんなんだあいつら……車ってあんなもんじゃないだろうが……なんかの術か? でもあんなぼうっとした男が術者……ねえだろうそんなの。じゃああっちの小さい方が? でも余計にそんなのなさそうだろ……」
- ぶつぶつとひっきりなしの疑問符の、軽く玩がん弄ろうできる相手、ただの人間だったはずなのに、今や玉たま串ぐしの、明らかに動揺しきり。
- 木々の梢こずえの上に上がればそこは月影遮さえぎるものない、銀に染まった緑の海で、山の稜線なりに清明な起伏を表わして、玉串はその上を波紋ならぬ葉揺れを置きながら跳んで、どこまで逃れたものかと考えあぐねるうちに。
- エンジン音が高らかに間近に噴き上がったかと見ると、ぼぅんと梢の上に飛び上がってきたのがあのイセッタであった。
- 笠かさ縫ぬいの妖力は単に障害物を退どけるにとどまらず、立木の幹を垂直に駆け上がる機動性まで旧車に与えてと、はっきり言えば玉串の跳躍よりよほど節操がないといえる。
- 「ちょっと待て。待ってくれっ、そんなのいくらなんでも……っ」
- 「いたかぁ! お前そこでじっとしてろ。逃げたって一晩中追っかけるぞ!」
- 梢のてっぺんからてっぺんを、ぼぅんぼぅん跳躍して追い迫ってくるイセッタはまるで猿ましらか山猫か。
- 玉串は前に倍する勢いと必死さ加減で逃げ出すのだけれどもう引き離せない、樹上の利すら奪われた。先ほどの余裕めかした獰どう猛もうな嘲ちよう笑しようとはうって変わって必死な形相で、玉串は逃げる、ひたすら逃げる。
- けれどもイセッタは依然追い続けてくるのが妖あやかしにとってついぞ無縁の悪夢のごとく。
- 「ぜはあ、ぜはあっっ……も、もうこうなったら、オレの隠れ山に逃げこむしか……っ」
- 玉串は樹上からまた地上に降りて、駆けるが駆ける、ここを先せん途どと逃げ馬の脚で、すれば山中の懐ふところ深くの空き地に、まるでスポットライトのように月影が落ちた一本の欅けやきの、少し奇妙な姿で、幹が中ほどから二ふた股またに分かれて伸びている。
- こういうのは股また木ぎといって、山の神とか山の霊だのの結界を示す標識として古伝では注意を促して、その近辺から疾とく立ち去るように戒めたものだ。
- しかし人ならぬ玉串のこと、空き地に飛びこみざま大きく跳ねて、二股の幹の間を跳び越える。
- その瞬間に玉串の姿がかき消えた。まるで別の空間に吸いこまれたように。いや、まるで、ではなく玉串はとうとう彼女の結界の中にまでの退散を強いられたのだった。
- 「ほ。あの玉串とやら、己の根城にまで逃げこむとは、の。よほどお前さまに捕まりたくない様子。まあそれも当然でしょう、そのように目を血走らせていては」
- 「根城だかなんだか知らんが構ったことかい。妖ってのはさすがだな、よくこんな息が続く……でも逃がしてなんかやらん!」
- ───けれど。イセッタの中の半なかばの視界には変わらずに玉串の後ろ姿が映り続けていた。さすがのイセッタでも通り抜けられそうにない方の幹の間に、車を強引に滑りこませた瞬間に、するりと潜くぐり抜けて、半たちもまた山中から姿を消していた。
- 七
- 「なんでぇ……? なんでなんだよう、そんなのずるいじゃんかようっ。なんであいつらこっちまで入ってこられるんだようっ」
- もう半泣きで逃げ続ける玉たま串ぐしの周囲は、先ほどまでの山中とは全く別質の異界であった。
- 月影が異様に明るく、狭霧がたちこめる原生林で、まるで神代の頃の原初の森ならかくもあろうといった霊気さえたちこめて、樹々も巨大で葉も密で、一本一本が神樹として祀まつられそうな古木が密に立ち並び茫ぼう漠ばくとした樹海をなしている。
- 加え、森林中には巨木のみならず、奇妙なものもあれこれ点在していた。飛鳥奈良の奇石群と似てさらに巨大で奇き矯きような形の岩の数々や、樹海の中にそびえ立つあの巨船のごとき代しろ物ものは、あれはもしや砦とりでなのではあるまいか。それもまた神代の、人の手にならぬ代物の。
- そんなあれこれが、樹海の上にイセッタを跳ねさせる半なかばの視界の広がる限りに散らばって、甚はなはだしい奇観であった。大いなる奇景であった。
- 「どうにもまた変なところに入りこんだぞ……見てくれと雰囲気は全然違うが、君と初めて会った時のあの草原を思い出すのはどうしてなんだ」
- 「それはさもありなん。じゃって、ここはもう現世の外、幽かくり世よですもの。あの時言いましたよ。お前さまは、もうそういう場所に迷いこみやすくなっているのだと。あの鞍くら印いんの杜だってそう、同じ。ここもまた然しかり、さ」
- 「……まあ、今はそんなことよりあいつをとッ捕まえるのが先だ。なかなか粘るな……」
- 車は時に巨亀のような奇岩の上を鞠まりのごとく舞った。
- 時に古代の砦の城壁をエンジンを咆ほう哮こうさせて登とう攀はんした。
- 時には不思議な、鶫つぐみに似てもっと尾羽が長く、かつ夜影に一声も鳴かず飛び交う鳥たちの谷間の上を跳び越した際には、さすがの半もいささか肝を冷やすくらいに長く宙にあった。
- 時には滝つぼの裏に隠されていた洞どう窟くつを踏破し、跳ぶ玉串に跳ねるイセッタ、妖あやかしと車の追跡劇は続く続く。
- 半はどうにもこの今の自分になにやら見まがう情景を知っていると思ってステアリングを繰りつつ記憶を浚さらえば───
- 古いアーケードゲームを集めた博物館で、跳んで跳ねて弾を撃つフォルクスワーゲンが、摩天楼やら火山地帯やら洞窟内やら果ては宇宙空間まで旅していくシューティングアクションが置いてあったことを思い出して苦笑した。
- こんな時に妙な記憶が蘇よみがえるものと横目で笠かさ縫ぬいを窺うかがえば、
- 「……さしずめ今のわたくしたちは、『ジャンプバブル~イセッタの不思議な冒険への旅~』と言ったところかや」
- 「君知ってるとか!?」
- 「なんのことやら。なんとなくそう思われただけ」
- ……と、まあ追いかけっこは延々と続くかのように見え、それでもついに、ようやく、やっと、終わりを迎える───
- イセッタは樹海の一画、密教の天部の神将たちに似たところがないでもない石像に取り囲まれた空き地でようやく停車した。
- フロントドアを開けて、降り立った半なかばの前に玉たま串ぐしがいた、もう精も根も尽き果て、土下座して泣きじゃくる彼女が。
- 「ううう、ごごめべんんなあさざいい、悪かった……ほんの出来心、オマエたちの魚とか酒とか美お味いしそうで、だから……ひぐ、ううう……っ」
- 「ああん? 美味うまそうだったから物を盗むんなら、街中は窃せつ盗とう犯はんばかりってことになるが。物のせいにするんじゃない物のせいに」
- ひたすらに謝り続ける玉串の、でもここで許すくらいなら、ここまで追いかけてはきていない、という。
- 「あら、まあ。そのように顔をどろどろにして泣くくらいなら、もうちと早う降参すればよろしうありました」
- 「え……オマエ、誰、なに……!?」
- この時の玉串の仰天ぶりは、笠かさ縫ぬいを今初めて同類と認識したかのような、それでいて全く納得がいかないかのような。
- 「なんだ……なんだオマエ……いや、あんたは……? あんたも物ものの怪けだ。でも全然気配を感じない……なのに、なんでそんなに……おっかない……?」
- 「あ? お前が嗅かぎつけた匂いってのは、彼女のじゃなかったのか?」
- 「違うよう、オマエのことだったんだ。うう、御免なさい、もう許しておくれよう……」
- 「微妙に腑ふに落ちないが、まあそんなことはどうでもいい。御免だ? 許してだ? そんなのは、盗ったものを返してもらってからの話だなあ……?」
- 踵かかとを浮かせて伸びあがり、のしかかるような半の、ひょろひょろとした痩そう身しんなのにこの時は変に悪ずれがして、人というのは心持ち次第で随分とまあ変わるもの。
- なにしろ先に玉串に威圧された時には、それは少しくらいは気け圧おされたかもしれないけれど、今の彼女ほど低くはなっていなかった。
- そう、まだ土下座のままで、ばかりか水みず苔ごけの地面に額ひたい擦こすりつけて顔を上げようともせず、だから声は涙交じりの上にも余計にくぐもった玉串ほどは、あの時の半は全然惨みじめではなかった。
- 「わかった、魚とか山菜だったら採ってくるから」
- こうまで低く出た妖あやかしに、半はもうその土下座の後ろ頭を踏みにじらんばかりであった。
- 「酒もだぞ?」
- 「え……酒なんて、オレ持ってない……」
- ようやく恐こわ々ごわと上げた玉たま串ぐしの顔の、先の兇悪な威い嚇かくの険も、逃走中の見苦しさも抜けて、あらためて見ると、これがなかなかによい顔立ちの、可愛かわいい、と言っていい。妖あやかしの年は判らないが、見た目は半なかばよりやや若いくらい。
- 笠かさ縫ぬいの美を精せい緻ち精せい妙みような芸術品とするならば、こちらは野の薊あざみの花である。けれどその可愛げも、たちまち萎え失うせて引き攣つって、さらなる恐怖に歪ゆがんでしまって哀れやな。なにしろ───
- 「それじゃあ許せんなァァ……?」
- 「わたくしとしてもあのお酒は楽しみにしていた故ゆえ、とりなしなぞいたしませんよ、お前」
- 初めて見た時は間抜けな青年とちっぽけな少女と見えた組み合わせが、今や玉串の前では魔人と妖神のごとく異形の輪郭に拡大変容してどろどろと迫り来るかのよう、魔人の魁かい偉いな手が、いや半の手が、妖神の鉤かぎ爪づめが、いやさ笠縫の繊せん手しゆが、にゅういと哀れな妖に伸びる───
- で。玉串は、茹ゆで串になっていた。
- 先ほどと同じ神将像の空き地のど真ん中で、ドラム缶風呂に浸けられ、どんどんと薪まきをくべられていた。笠縫の髪を縒よりこんだロープで後ろ手に縛られているため、もう逃れられないのであった。
- 「熱いよ、やだよ出してよ許してよお……てか、オレの隠れ山でこんなドラム缶なんか見たことなかったのにどっから出したのこれ」
- 「まあ細かいことは気にするな。足らない酒の分は、お前の出汁だしということで勘弁してやろう。妖怪からはどんな出汁がとれるんだろうな」
- 「熱いぃぃ……茹だるぅ……ニンゲンがオレなんか食ったって、当たって死んじゃうだけだってば……あぢゅいいい、死ぬ、死んじゃう」
- 「そうは言いますがお前、この半は、わたくしを食おうとそれはもう恐ろしく迫ってくるほどの殿でん御ごよ。お前なぞは酒の突き出し程度に食べてしまうのではと危あやぶまれる、の」
- 「マジでか……うう、せめて片腕とかで許してよぉ……」
- 「いやさすがにほんとに食うとかは……ないと思うんだが、笠縫、どうだろう」
- 「わたくしにそのようなことなど訊たずねられましても知らぬこと」
- ───この時、半は。冗談めかしたつもりであったけれど。
- その内実は、この玉串にも軽い『食い気』を催もよおしていたのであった。
- 青年はそれを、立場が逆転した嗜し虐ぎやく的な喜びと思いこもうとしたのだけれど、そうではなく、やはりそれは『食い気』、この哀れな妖を食いたしと思う心。
- それは半が笠縫に対して催すあの衝動と似通い、ただずっと弱い。
- 抑えつけることもできて、半はあくまで冗談に紛まぎらわせて、玉串に意地悪く口角をへの字に吊り下げ、仕置きを続行する───
- 「ま、とにかくもうちょっとそこで反省してもらおうか?」
- 「ダメ、もうダメ、熱あつ死ぬ、もう死んじゃうから……これ……あ!?」
- ぐったりと失神しかかり湯の中に沈みこみそうになって、玉たま串ぐしの目に生気がかすかに蘇よみがえった。どうやら記憶の底を探っているように目を彷徨さまよわせ、それからぴぃんと、なに心中に鐘が鳴ったようなしたり顔、こんな極限状況なのに浮かべて吐いた言葉というのが。
- 「あっ、あっ、そそ、そうだ! 『養老の泉』、とかそんな風にオマエら言うんだろ、水の代わりに酒が湧く泉のこと! あるんだここに、オレの隠れ山に! それで酒を汲くめば代わりになるだろ、だからもう、出して……ホントに……熱い……」
- ……玉串としては起死回生の妙案のつもりだったのだろうが。
- 熱に朦もう朧ろうとした彼女の目にも、半なかばと笠かさ縫ぬいが見交わした視線のほろ苦さといったら。半が焚たき火びの火掻かき棒代わりの落ち枝で、ドラム缶の胴をこんこん叩たたきながら問いただしたのは、じつにもっともな問いだった。
- 「……なんでそんなものがあるなら俺たちの酒を盗ってった」
- 「今まで忘れてたし、アレはオマエたちに嫌がらせするためで」
- 「よーし玉串君、あと百数える間浸かってようか?」
- 「やだあああああっっっ」
- 八
- ……そのまま今度こそ失神して湯の中に溶けかねない玉串に、半もいい加減仕置きを中断し、水分の補給と湯冷ましを許したけれど、それも半時間程度だったから現在の彼がどれだけ容赦がなくなっているのか知れよう。
- 先の火掻き枝で、臀しりを突いて追い立てかねない勢いに、玉串がふらふらと、記憶を辿たどり辿り案内していった先は、先ほどイセッタで飛び越した谷間の、その底にある泉だった。
- 上空にはあの不思議な、どこか鶇つぐみに似通う鳥がまだ月影を浴びながら飛び交っている。振り仰いで半はこの時ようやく、この樹海には月影は差すけれど、月そのものは見えないことに気がついて、あらためてここがしみじみ異界なのだと想いを刻む。
- なんだって妙なところに入りこみ、養老の滝だか泉だかの伝説にまで触れることになった、と我ながら呆あきれる半の、その時まで妖あやかしの言葉を疑いもせなんだことからして、彼はもう充分以上に『こちら側の世界』に馴な染じんでいたのだろう。
- 玉串が、いつかの『鉱泉』よりはぐっと狭く、猫の額ひたい程度の泉の水を手で掬すくって舐なめて、首を傾かしげてはまた舐めて、次第に青ざめていった顔色から、彼女の目当てが外れたらしいと覚さとる。
- その時に、幻想を裏切られたような想いを味わう程度には、異界に不可思議を期待する気持ちさえ、抱いだいていたのだろう。
- 「さて玉たま串ぐし君どうしたのかなァァ? なんだか顔色がおかしい様子だぜぇ……?」
- 「え。待って。こんなはずって。だってオレいつかの夜、酒なんか持たないのにここ来て酔っぱらったのが、確かに……なんで、どうしてぇぇ!?」
- 「知るか! お前約束と言ってただろう、さてこの始末、どうつけてくれるつもりか……」
- 泉はあるにはあっても、酒など湧きだしておらず、清らかで甘そうではあったが、それはただの水の。
- 玉串が進しん退たい窮きわまり、半なかばの態度がまた危険な色合いを帯びるのだが、先ほどから鳴き声もなく飛び交っていた上空の鳥たちが、にわかに、しきりに鳴き始めた。
- 半は夜の鳥といって漠然と梟ふくろうだの不如帰ほととぎすだの、陰に籠こもるような声を想像していたのに、この鳥たちは美しく可か憐れんな、細い金属の笛のような音ね色いろで鳴き交わすのであった。
- ふとその鳥たちを見上げ、何事か得心したように頷うなずいたのが、先ほどから玉串の醜態をつまらなさげに見守っていた笠かさ縫ぬいである。
- 「なるほど。玉串、お前のいうことは、あながち間違いではなかったご様子」
- ぱしゃりと水を跳ねかして、鳥が舞い上がった───のは、半だけでなく玉串も、上空のものたちが水に飛びこんでからまた出たのだと、思いこんだのだがそうではない。
- 上空からの鳴き声に応じたかのように、泉の中から浮かび上がっては飛び立っていく鶫つぐみに似た鳥たちの姿、次々に。
- 泉を覗のぞきこめばマグライトを使うまでもなく月光が底まで照らす。見れば、泉の底に二枚貝が何枚も沈んでいた。小皿、いや平たい杯を二枚合わせにしたような、緑がかって深い色の奇妙な貝だ。ぱかりと開いたその中の身。薄クリーム色、というより鳥の子色というのが適当か。
- その身が、色づき、肉質が見る間に羽毛と翼、嘴くちばしと鉤かぎ脚あしにと変じていって、やがて開いた小さな目、黒々としてただ天ばかりを仰ぎ、水底からまっすぐに浮かび上がって水面を破り、雫しずくを振るい落とすや、上空の同胞たちの元へと飛び立っていく───
- 肉の身のある鳥たちなのに、火の玉が昇るよりも奇くしき妖あやしき、そして心奪われるその眺ながめといったら。
- やがて笠縫が軽く頷きながら、
- 「唐渡りの言い伝えには、海の底で年経た貝の身は、やがて燕つばめに化身して飛び立つ、というのがあります。ここのもその類たぐいなのでしょうが、ここのはもう一つ特徴があったはず。わたくしも今思い出した」
- 飛び立つ鳥が振り零こぼしていった飛沫しぶきが、先ほどから半たちにかかっていて、とはいえ春雨よりも優しい雫で、避けるほども拭ぬぐうまでもないと、そのまま受けていたのだけれど。
- その雫が軽やかな羽ばたきとともに、また、今度は笠縫の華きや奢しやな首筋に落ちて、滴したたり、鎖骨の辺りに垂れる。
- 「そう、この雫しずく」
- と笠かさ縫ぬいは、雫が溜まった鎖骨のくぼみを半なかばに示せば、妖姫の体、肌ということでもう反射的に鼻面を寄せるようになっている青年の、鼻先にふわりと立ったのが、笠縫の肌の匂いとは異なる、なんとも言われぬ芳香で、どうやら溜まった雫が放っているのらしい。
- 「それ、一ひと掬すくいだけ差し許しますよ、お前さま。このたびのお味見として───いかが」
- 妖姫のお味見と、言われればやはりもう勝手に体が動いて、その胸騒ぐほどに滑らかな鎖骨の窪くぼみに指先をそっと、差し入れれば雪せつ花か石せつ膏こうの器のように冷ややかで、笠縫はかすかに、一度だけ、肩を縮こめた。
- そのまま指を置いていたいと望む心、味見したいと願う気持ちで葛かつ藤とうの狭はざ間まで随分長く身を苛さいなまれたように思われるけれど、実際には半はすぐに指先を唇に持っていき───舌が蕩とろけた。そのまま意識が体の外に遊離するかと思われるくらいに。
- 「──────これは。酒、だ───それも滅多にない、旨い───」
- 「酒って、さっき掬った時は水だったぞ、ほんとに!?」
- ───玉たま串ぐしが狼狽うろたえたが、それは確かに酒、それも至上の美酒であり───
- 「ここの泉の貝はの、歳月を経ると鳥に変ずると申しましてな、お前さま。中の身が殻を捨てて鳥になって飛び去るのです」
- 「貝の名はツグミ貝。鳥となって飛び去った後の貝殻からは珠玉の美酒が生ずるそうな」
- 笠縫がしゃがみこんで泉に手を差し込んで、招けば空からの貝殻の方から浮かび上がってその掌てのひらの中にふわりと収まる。
- ツグミ貝の、貝殻。透き通った、緑がかって深い、不思議な色合いの貝殻。
- 「身が鳥に化身して去っていった後の貝殻には、月光と自然の精せい髄ずいが残されていて、それが得も言われぬ妙酒となって湧きだすのだとか」
- ちょうど杯のような形のそれを、笠縫はあと二枚掬って、半と玉串にも手渡して、すっと自分の手の中のを二人に向けたのは、言うまでもない、乾杯の合図だ。
- かといって騒々しく打ち合わせるのではなく、繊細な貝殻を慈いつくしむようにそれぞれそっと触れ合わせて、あとはもう唇に運ぶだけ───
- ───素す晴ばらしい、としか言いようがなかった。透明で軽やかな口当たりなのに、舌の上ではとろりとして、精妙な甘みがあり、呑のんでも呑んでも飽きることがなさそうな。
- 香りもまた、花とも果実とも香木ともつかぬ、清涼な、なんともいえぬ、言うならば月の香りというのが体の中に広がりほどけていくかのよう。
- 「ああ、そうだこれだ、この美味うまいのだ……オレはこれで、酒ってなんて美味いんだろうって知ったんだ。それまでは酒とかあんまり飲まなかったのに……」
- 「日本酒のような甘さ……濃い果実酒のような舌触り……ちょっとだけ蒸留酒のようなキックもあって……なんて言うんだこれは……」
- 「月の酒、というのが一番よくおさまりましょう」
- 「確かに……」
- この妙なる味わいに加え、杯となる貝は、手に持っても程よく冷えたままで、酒を素す晴ばらしい適温に保ち続けるのだった。持ち心ごこ地ちもなんとも具合よく手に収まる。この杯から美酒は、呑のみ干すたびに湧きだした。飲んでも飲んでも尽きることはないが、それは一晩だけなのだと笠かさ縫ぬいは告げた。
- 「次の朝日を見たなら、普通の、いいえ、綺き麗れいなものなれど、ただの貝殻に戻ります。この隠れ山の夜も、やがては明ける夜。それでも夜はまだ長い。それまで召し上がりましょう、お前さま。お前も、命冥みよう加がなことですよ」
- 「なんであんた、ここのこと、こんなにいろいろ知って……」
- 「それには俺も興味がある。笠縫、君は今夜いろいろと意味ありげなことを言ったな。どういうことなのか、全部とは言わない、話せるところだけ話してほしい」
- ふう、と笠縫は、知りたがりの半なかばに溜ため息いきをついて、少しだけ困ったような、それでいて優しい顔をして、そして。たっぷりと溜まったツグミ貝の酒を、一息に干してから。
- 「……この玉たま串ぐしの言うたことは、幾つかは本当で、幾つかは間違いということ。例えば、かつて、今は名前も残らぬ大妖があったのは本当。けれど、その玉串とやらはその右腕……というのはこれは喩たとえではなく、そのままの意味なのだけれど、右の腕かいななどというのは誤り。本当は、もっと小さな一かけら」
- 「おいっ。あんたそんな身も蓋ふたもない、ていうか何で知って───?」
- もったいなくも杯の中身を幾らか振り零こぼしながら、身を乗り出した玉串に、年下に見えて大いなる心の深みを瞳ひとみに宿した笠縫は、そっと人差し指を唇に押し当ててやって、囁ささやきかけた言葉は、確かに半にも聞こえたのだ───
- 「───わたくしは……じゃから、さ───」
- ああ聞こえたのだ。玉串が呆ぼう然ぜんと呟つぶやいた通りに。
- 「今あんた、なんて……? そんなオオミズアオみたいな、薄緑色の綺麗な言葉、聞いたことがない」
- そう、聞こえた。笠縫の唇から、するすると水みず煙管きせるの煙のように滑り出た、薄緑青の音ね色いろを。
- 優しく嫋たおやかで、なのに深い事実と時間に晒さらされた色合いで、なんてわかりやすく目に映るのだろう、と半は陶とう然ぜんと見とれてそして、はっと我に返って愕がく然ぜんと押し出した言葉が、また。
- 「じゃあ君は……だって。なら、俺は。俺の…はだから……?」
- 自分の口から舞い出たのは、ぶわぶわとした薄茶色の、やや濁って、どうにも情緒に欠けた色の言葉で。
- ぎょっとして、つい手で払えばもわもわと夜闇の中に拡散していく。何がおかしいのか、膝ひざを叩たたきながら玉串が吐いた言葉は、浮かれた桃色だった。
- 「あははは…みてえだなあんた。ああそうだ、言葉っていろんな色があって…だから」
- 言葉、だけではなかった。
- いろいろの物音が、例えば泉の周囲に自生している羊し歯だ類の葉は擦ずれの音は優しい紫色の蔓つる草くさ模様として漂ったし、鳥たちの鳴き声はさながらカットされた青玉サフイア、紅玉ルビー、緑玉エメラルドの小さな星として、月影の中に周遊していて、ああ、と半なかばは恍こう惚こつと頷うなずいたのは、月の光はこんなにも雄弁で瀟しよう洒しやな秘密を毎夜語っているのだとその色から感得した故ゆえに。
- ───と、まあ、こんなのがツグミ貝の酒の酔い心ごこ地ちなのです───
- ───音と色の感覚が混ざり合う、と言えばお判りか───
- ……笠かさ縫ぬいがその言葉を半に伝え得たのは、杯持たぬ空の掌てのひらに、そっと指でなぞって教えたらで。
- だから結局、この夜の皆で口にして語り合った言葉は、その時は明めい瞭りように理解できたのに、後から思い出しても色合いと浮遊する動きの記憶としてあるのみだった。
- 九
- 翌朝。泉近くの朝あさ靄もやに濡れて緑匂うような羊歯類と野草の下した生ばえの中、むっくりと身を起こして頭を掻かく玉たま串ぐしや、半の声は酒精の名な残ごりやや掠かすれていたけれど、それでも昨夜呑のみ干した量を想えばツグミ貝の酒というのは、悪酔いもなく二日酔いも残さぬ、あと心地まで最上等の酒なのだった。
- 笠縫はといえば、既に一足早く泉の水で朝の身み繕づくろいを終わらせて、なんとも清すが々すがしくこざっぱりと。
- 「まあ、その、なんだ。おっかなかったし茹ゆで殺されるかと思ったけど、オマエら結構いいヤツだな。この辺りにまた来たら、その時は声かけてくれよ。今度は悪さとかしないからさ」
- 「お前な……まあ、いいか。昨夜の酒は美味うまかった。あまり後までぐちゃぐちゃ言わないさ」
- この変わり身の早さに半も呆あきれるが、まあツグミ酒の旨さにどうでもよくなりかけていたところ、笠縫がぴしゃりと。
- 一人こざっぱりしているだけに、言葉は清せい冽れつな張りを持って二人を撃った。
- 「お前、玉串、何を鷹おう揚ように物を言っておるのじゃ。半が言うたのは、酒を出せばお前の謝罪を容いれるかどうか考える、ということ。つまり半はこれで許したわけではないということ」
- 「え……え……そんなこと言われても、オレ……」
- 「え、いや俺もさすがにもうそこまでは責めるつもりはないぞ」
- 「お黙りあそべ。それにわたくしを煩わずらわせたことはまた別のお話……玉串とやら。お前の身柄、しばらくこの半に預けましょう。もう悪さしないと、反省が見えるまでのあいだ。さてどれだけかかるやら、ねえ」
- 「待ておい笠かさ縫ぬい、君、なにを勝手な」
- 「ねえ、だよな、そうだよな、あんたも思うよな、勝手って。だってそれってオレ、ここから離れるってことに」
- 「お黙りあそべ、とわたくしは申したはずですが聞かずにいたと───?」
- 笠縫は、あの白の杖の風鈴を、また一つ鳴らして、それは今朝は、判決を告げる槌つちのように響いた、という。
- なにを言いだすのか呆ぼう然ぜんとする半なかばと玉たま串ぐしだが、笠縫の目は酒精が上がった時よりも、彼女の元来の性しようの怖さが覗のぞいたか、凄すごいようなかぎろいを放つのみ。
- 十
- 後日。半の部屋を訪れていたまつ璃りは、不思議で美しい杯を土産みやげとして手渡され、深い色の緑ガラスのような杯状のそれを、ツグミ貝の貝殻なのだと聞かされた。
- そこにもなにやら曰いわくと逸話がありそうで、半があれこれ話をまとめようとして軽く唸うなっていたその時に。
- まつ璃の横で、部屋の押し入れの戸が開いて、
- 「あのさあ半、今晩の飯はオレ揚げ出し豆腐がいいな。こないだ食べたアレ、凄い美う味まかったからさ……って、客か」
- 押し入れの中から顔を出した玉串は、まつ璃をちらりと見て、じゃあまた後でと中に引っこんでまた戸を閉めたものだけれど。
- 到底それで納得できようものかで、まつ璃は半が止めるのも聞かずに強引に押し入れをこじ開ける。
- と───押し入れの向こうには深しん山ざん幽ゆう谷こく、そして樹海の景色が広がっていて、それは玉串の隠れ山なのだとか、笠縫がこことあそこを繋つなげていったのだとか、そんな事情は当然つゆ知らず、唖あ然ぜんとするばかりのまつ璃の前で半、ぱたりと戸を閉じる。
- それからもう一度開いてみれば、布ふ団とんが詰まっているばかりでなにもないし誰もいなかった。なんとも都合のよいことに。
- 「な? なにもないよ、まつ璃姉」
- 「わたし、目が変に? ううん、そうじゃない、今いたわよね、誰か。笠縫さんでもない誰かが押し入れの中? 山の中……?」
- 「まあいたのかもしれないし、いなかったのかも。後で説明するよ」
- 「なかちゃん……!?」
- 説明に窮きゆうじながら、半が思っていたのは、ツグミ貝の杯から呑のむあの不思議な酒は得も言われぬ美味だったけれど、なかでも格別だったのは、初めに一舐めした、笠縫の鎖骨の窪くぼみから掬すくい取った一滴だった、ということ───
- 第三話・了
- 一
- ローカル線の横座席の手すりから、若い娘のらしい、しなやかで形よく健康的な肌のふくらはぎだらしなく投げ出されている。足首をストラップで巻いた、涼しげなサンダルのつま先が、ぷらぷらとはしたなく宙を掻かいたさまがどうにもはしたない。
- 「んんぅ……半なかばぁ。オレ腹減ってきたよゥ。何か食い物ねえか?」
- とかかった声は、親指から小指まで、綺き麗れいに形の整ったつま先が肌色の振り子と右に左に揺れながら、だったので、まるでふくらはぎが退屈紛まぎれに口を聞いたのかのよう。
- 言うまでもなく顰ひん蹙しゆくもののお行儀だけれど、車内には見み咎とがめるような客は他に一人だけ。その一人だけの客というのも、二つばかり後ろの座席、呼びかけられた比ひ良ら坂さか半自身で、青年は呆あきれこそはすれ、注意するのも面倒と適当に相手する程度なので。
- 「ないよ。乗る時食ったパンが手持ちの最後だったよ。それだってお前が食ったじゃないか」
- 「あれはあれでお菓子みたいで美味うまかったけどさ、腹はあんまり膨ふくらまなかった」
- 「なんにしたって街中に降りるまでは我慢しろとしか」
- こっちだって我慢しているのだ、と半は、笠かさ縫ぬいのふくらはぎに覚えたかすかな飢えを抑える。笠縫ばかりか玉たま串ぐしにまでこんな食い気を覚えてしまうけれど、こちらはまだ抑えられた。
- とにかく玉串にぴしゃりと言い渡して車窓を見遣れば。
- 手を伸ばせば届きそうなくらい間近に迫った山林の、山腹のみっしり密度も濃く生い茂ったのが、列車の進むにつれ果てしなく後から後から流れていく。
- 変わり映ばえのない退屈な景色……いや、退屈どころか、山中は時には素す晴ばらしく開けた遠景を披露するし、激しくも清らかに駆け流れては岩肌を噛かみ、弾ける渓けい流りゆうをさっと見せたり、あるいは一世紀は経ているような古民家の数軒ばかりの集落を見下ろして今隠れ里かと驚かせたりと、なかなかに見どころというのが豊かである。
- この眺ながめこそが旅情というものだ、と感慨深く溜ため息いきを吐く向きもあろう───
- 東北地方のど真ん中に聳そびえ立っている奥おう羽う山脈という長大な山塊の景色である。
- そしてそんな大山脈であろうと、鉄道は縦貫して走るのだった。
- その車中、時刻は昼下がり。各駅停車の在来線で、横座席と長座席が混在した、地方でよく見られるローカル線である。
- ───間借り先に留まり続けるうちに、またぞろ半の精神的宿痾、食物の味がしなくなる、という奇病が頭をもたげてきていた。
- 二、三日は我慢がきいても、じっとしているだけでは解消されるものではないと誰よりよく理解している半は、また学校の講義やら身の回りのあれこれを打ち捨て飛び出してしまっていて、その道中のこと。
- このたび半なかばの傍そばに笠かさ縫ぬいの姿は見えず、一人の道中である……かと思われたのだが。
- 「なあ、どうして新幹線とかに乗らねえんだよ。この汽車、とろとろ走って鈍どんくさくって退屈ぅー」
- 「そうほいほいと新幹線なんて乗ってられるか。特急料金がばかにならないんだよ。金は節約するに越したことはないだろう」
- 「はぁん……今時貧乏旅行なんて流は行やらないんじゃねーの?」
- 今度は座席の手すりに仰あお向むけに首をもたせかけた、だらしない格好で呼びかけてきた玉たま串ぐしである。前回の旅先での一件以来、半のもとにずるずると居ついてしまっていた。
- 笠縫の姿は見えずとも、こちらの妖あやかし、玉串が半にくっついてきていたのである。
- 半としては閉口したのだけれど、玉串はいっかな聞かず、押し切られた形だ。
- 道中改札や検札などで、車掌は一向に玉串に気づいた様子もなかったのが、この娘の姿をしたモノもやはり妖の眷けん属ぞくということなのだろう。
- 「流行り廃すたりで腹はふくれないんだよ。だいたい山の中に引き籠こもってた人外の類たぐいに新幹線だ流行だの語られても違和感がある。……というか、お前、本気で俺についてくるつもりか」
- 「だってオレ笠縫様に言われてるしな。オレの身柄はアンタに預けるって。もうアンタに悪さとかするつもりあんまねえけど、許してもらえるかどうかは笠縫様次第だし」
- 「律りち義ぎというか変に生真面目な奴だな。彼女、ここしばらく姿を見せていないし、どこかよそに行っているんじゃないのか。そんなに気にすることもないだろうに」
- 立ち上がり、半の傍に寄ってくる玉串は、会ったばかりの時とは形なりを変え、ノースリーブのフレンチコットンのブラウス、細身の膝ひざ下丈のパンツにストラップ付きのサンダルと、いやに当世風に衣装替えしているけれど、実のところ全体の輪郭としては前とそれほど変わりがない。
- この衣装を見立てたのはこれがまつ璃りで、彼女は服装見た目にこだわらないようでいて、いざその気になればよい趣味を発揮する。確かに今の玉串は、元のつくりがいいだけに活発な可愛かわいらしさを浮き彫りにしていた。
- ……まつ璃は、玉串を笠縫の親類かなにかと思うことにして、その存在を受け容いれることにしたらしかった。
- 「そうは言うけどアンタさ……オレ驚かないよ? 例えばこうやってふっと眺ながめた窓の向こう……あの流れの岩の上に、あの方が腰掛けてこっちをキッて睨にらんでたって、ね」
- 「!?」
- 窓の向こうに展開されていく深山の景色、玉串が示した渓けい流りゆうの岩塊の上に、銀に艶つやめく髪の少女の姿したものが座しているのが見えたような気がして、ぎょっと目を凝らしたけれど、結局のところ何も見えず誰もいなかった。
- ただ、玉串にそう言われると、なんともありそうなことではある。この今も笠縫の視線が虚空から注がれているように意識されてしまい、半はあの妖への畏おそれと渇かつ仰ごうとがない交ぜになった複雑な気分で、襟えり足あしをすくめるようにして車内を見回したことである。
- 「それでさあ、アンタ、この汽車でどこまで行くつもりなんだ? 何か随分だらだら乗ってるけどよ」
- 「東北……日本海側。あの暑さのぶり返しにはやってらんない。とりあえず夜になったら涼しくなる場所に行きたい。そしたらあとはまあ、気分次第だな」
- 「ふうん。行き当たりばったりていうか暢のん気きっていうか」
- 「いや、これでもまだ理由めいたのがある方だ。場合によっちゃ、本当に何も考えずに衝動任せで電車か遠距離バスに飛び乗るし、サイコロで行き先を決めたこともある」
- 「変な奴だなあアンタ。ま、旅ってなるとオレも気分が変わっていいけど」
- 「どこまでついてくるつもりだよ……」
- ……そろそろ彼岸を迎えようという頃合いだったのに、長雨の後で暑さがひどくぶり返した。
- しかも湿気がひどく、だまって座っているだけでも薄い粥かゆの中に浸かっているような悪心ごこ地ち。
- そればかりかこういう時に限って部屋の空調が故障した。例の奇病の件も手伝い、東北の方にでも逃れようかという気分なのだ……玉たま串ぐしがどこまでついてくるやらが面倒であったが。
- 振動と傾斜の角度の圧がかかり、列車は斜面を上りながら、掩体スノーシエツドに覆おおわれた、深山中の無人駅へ進入し、折り返し線へと車体を進めていってから一時停車、バックで駅構内に戻っていってまた改めて停車した。
- なぜそんな面倒な手順を踏むのか一見奇異に見えるかもしれないが、これは急勾こう配ばい区間に設けられた駅に鉄道列車を停める際の、「スイッチバック」という方式であり、世界、日本各地で同様の機構を備えた駅はある。
- だが半なかばは、その時奇妙な違和感を覚えていた。何がどう、とは彼自身にもすぐさまは判別が尽き難く、心にもやもやとした影を落とす。奇妙なことに玉串も同様の感覚に囚とらわれていたようで、怪け訝げんそうな眼つきで鼻先を上げ、辺りの気配に五感を澄ましている様子だ。
- ややあって何事か捕えたように目を輝かせると、
- 「半! 何かいい匂いがする! 山ン中の方から。行ってみようぜ、すぐに、ほらもたもたしてんな!」
- 「なんだ急に、俺はこの駅で降りるつもりなんか……待てよ、引っ張るな、荷物が……っ」
- 玉串が何を嗅かぎつけたとしてもそれは半の違和感とは全く別のところだったようで、彼の都合など知ったことかと腕を引っ張る力の強さ、青年はたちどころに引っ立てられて、かろうじて荷物ばかりは掴つかんだけれど。
- 乗降口から引きずり降ろされてしまったところで、背後で扉が閉まってしまい、ついで電車は半たちをホームに残して発車してしまうのだった。
- 他に乗りこむ者も降りる者も駅員もおらず、ホームには半たち二人のみ。
- 「どうするんだよこんなところで降りちまって。次の電車が来るまで、この辺りの線だと下へ手たすれば二時間とかかかるぞ……いや、もっとだった」
- 「次来るのはもう四時半近くだ。どうやって時間潰つぶすかなぁ……」
- 万年の雪覆おおいに覆われたホームは梁はりも柱も剥むき出しで無骨で、無人で寂しかったけれど深山中の木こ立だちの中でがっしりと守ってくれるような頼もしい風ふ情ぜいが、肌を心ここ地ちよくくすぐるように募る。
- ちょっと戦前の小説中の景色に紛まぎれこんだような眺ながめ自体は半なかばの好みにそぐうところ、とはいえ時刻表をあらためて見てうんざりする。もとよりローカル線の過疎ダイヤは承知ではあったけれど、日に六本という運行本数の少なさは、あと数時間はこの秘境の駅とその周囲で暇を潰すことを半に余儀なくさせた。
- で、半を引きずり降ろした玉たま串ぐしはといえば、しきりにあの宙を嗅かぐ仕草で辺りを探りながらホームを降りて掩体スノーシエツドから駅前に出る。
- (考えてみれば、こいつ一人、勝手に降りるなりさせて、俺は乗ったままでもよかったんじゃないのか……?)
- 見た目は可愛かわいらしくても結局は玉串も妖あやかしなのである。
- どこへ勝手に行こうと己の身の処し方くらいは心得ているだろうと、憮ぶ然ぜんとした思いを抱えつつも、半とてこの無人ホームに立ち尽くしていたって仕方ない。
- 半は結局玉串の後を追うのだが、そこで、ふっとホームの暗がりを振り返った。
- どうにも何かが気にかかる───
- 二
- 峠の駅前の情景は、すぐ傍そばまで木立が迫った未舗装の広場の中に、駅に付随する施設と、家屋が二、三軒。そして駅前すぐには力餅もちと古びた看板を掲げた、茶屋というのが似つかわしい店が一軒。その程度。ただまあ食事処があれば腰も下ろせるだろうと、営業している様子がある茶屋の建物へと、とりあえず進んでみる。
- 辺りには、意外と手入れの行き届いた見事な盆栽やら植木が飾られるなか、布袋ほていさまの塑そ像ぞうあり、あけびの棚があり、岩いわ魚なを養殖する湧水池もある。そんな前庭を目で追いながら、茶店のやけに重そうなガラス扉へと手をかける。
- と山小屋のような店の中は、香ばしい醤油の匂いがほのぼのと漂っていた。看板の力餅の他に、蕎そ麦ばだのの食べ物も出しているようで、鼻から味覚がくすぐられる。寄宿先から遠く離れたここならば、食い物もちゃんと味がしそうだ……。
- 「なあなあ半。そっちじゃねえよ。もっと奥の方だって」
- 「お前の言う『いい匂い』の話は当てになるのかどうか。まあちょっとくらいは付き合ってもいいが、その前にまずここで軽く食べていこうじゃないか」
- 茶店にはかまわず進もうとする玉たま串ぐしを説き伏せ、半なかばは焼きお握りを四つ頼んだ。玉串はぶつくさ言いながらも、たちまちのうちに二つ平らげて、なおも物欲しそうな目。それを無視して半は自分の分は確保して、店の主あるじと会話を交わす。
- 「こちらは鉄道マニアや温泉巡りの人たちで、わりといつも客がいると聞きますが、今日は暇な方ですか?」
- 「まあこういう閑かん古こ鳥どりの日と半々くらいで」
- 話していくうちに、主人が朴ぼく訥とつながら人当たりよく、次の汽車が来るまでの暇つぶし、と言うにはちょっと時間がかかるかもしれないが、と勧めてきたのが郷土料理の店だった。
- 「この駅から道沿いに米よね沢ざわの方へ向かって進んでいきますと、渓けい流りゆうがあります。鰍かじか沢ざわというのですが、これを上流へ向かって進んでいくと、平べったくて大きな岩が生えている。大まな板という。この岩の根に、道祖神の石碑があります。その道祖神を、向かって右手、尾根側に進んでいって……」
- あれこれと身振り手振りを交えて道順を教えてくれる茶店の主人の人のよさ、客商売というより元がそういう性分と見えた。
- 「そこから一時間ちょっとも上っていくと、窪くぼ地ちが見えて、集落があります。ホロホロ窪、という」
- 「そこで郷土料理を出している民宿があるのです。菊きく乃の井いという。よろしかったら行ってみるといい。わたしの従兄弟いとこがやっている店で、何だったら連絡を入れておくが」
- ざっと値段を訊きけば、半が思っていたよりもずっと安い。道程にかかる時間と、食事の時間を合わせれば、次の列車どころか最終列車を逃す可能性が高いが、なんだったらその民宿に一晩くらい投宿してもいい程度の余裕は懐ふところにあった。
- 玉串は食うだけ食って床しよう几ぎを離れ、つまらなそうに茶店の中や前庭の生いけ簀すの周りをうろうろとしているし、もとより当てのある旅程ではない。半、主人が紹介してくれた宿に興を催もよおし、行ってみようと決めた。
- 「それじゃあ、せっかくお勧めしてくれたのだし、行ってみることにします。できれば紹介しておいて下されば有り難いです。ああ後、迷った時の念のため、電話番号も教えてください」
- 勘定を済ませ茶店の主人に別れを告げて、ふらふら落ち着かない玉串に声をかければ、まだ匂いがどうのとぶつくさ言っている。
- 「なんだったらお前は別行動でもかまわないが。俺はとりあえずその菊乃井さんに行ってみる」
- 「えー……ホントにアンタは判んないの、この匂い。ここだとまだ途切れ途切れだけど、すごく美味うまそうな匂いだぜ」
- 「生あい憎にく俺はお前ほどは鼻は利かないっぽいよ。一応訊いとくと、それはどっちからしてる?」
- 「あっちの方から」
- と指した先が、これから半なかばが向かおうとしている米よね沢ざわ方面だった。
- ならとりあえずは同じ道だ、と歩き出したところ、背後からからからぴしゃんと戸をたてる音。振り返ると、茶店ははやガラス扉を閉じ、シャッターを下ろしているところだった。
- 山中の茶屋の営業時間は長くはなかろうが、それでも半はこの店が日没まではやっていると聞いていた。自分たちが何かしでかしたわけでもあるまいが、と半は、茶店の主人の人当たりのよさに触れていながらも、自分たちを締め出すような店じまいにどこか不吉な念を覚えたことである。
- 三
- ……結局、玉たま串ぐしは半と別行動をとらずに、山中の道行きをともにしていた。どうやら玉串が嗅かぎ取る匂いは、半が目指すホロホロ窪くぼ方面から漂ってきているのらしい。
- 「どうやらお前が言ってるそのいい匂いってのは、例の郷土料理屋からなんじゃないのか?」
- 「そんなんオレには判らないよ。でもまあ、確かに向かう先は同じっぽいなぁ。匂いが前より濃くなってきてる。やべあんまり嗅いでると、どんどん腹が減ってくような気ぃしてきたぞ」
- 「よくよく食い意地の張った奴だな、このいやしんぼが……とか言いながら、実は俺もさっきからそれっぽいのが判るような、気が……なんだ、これは肉の匂いだ……? 確かになんともそそられる……茶店の店主は地鶏がメインだって言ってたが」
- 茶店の主人の子し細さいな案内があり、道は山中を切り分けていたといっても、初めて分け入る深山の、しかも道とは言いながらほとんど獣けもの道にも見まがう細道である。
- なのに二人は次々と主人が示した目印に行きあい、踏み越え、ずんずんと過あやまたず進んで、あまつさえ途中からはペースが増したようであったのは、まさしく匂いに導かれている、というのがふさわしかった。
- それでも山中の暮れは早く、木こ立だちに間に影が濃くなりゆき、日が落ちる前に行きつけるかどうか半が危あやぶみだしたころ、尾根を巻くような細道の肩が下がりいき、やがて二人は傾きかけていく陽に照らされた、窪くぼ地ちの集落を見たのだった。
- 「着いたようだな。迷わずに済んでよかったよ」
- 「あんないい匂いを見失うかよ。迷うわけなンかあるか」
- 見下ろす集落は、夕映ばえでサフラン色のぬるま湯に浸かっているような。
- 山中から流れ込んだ水が静かな川となって集落を鬱う金こん色の帯となって横切り、この流れのおかげで水豊かなのだろう。
- 窪地の斜面には棚田、平地部にも水田が多く切られ、これも黄こ金がね色に染まった稲穂の中に三、四軒ずつの古い民家がまとまって、それが窪地のあちらこちらと散らばって、さながら金の海に島々が点在するかに見える。
- ざっと二十軒程度の小村か。その民家というのも茅かや葺ぶき屋根の方が目立ってあちこち兜かぶとを伏せたかの佇たたずまい、いずれもがっしりと、年経てなお頑がん丈じようそうに、棟、柱や白壁にも傷いたんだ気配はない。
- 鉄道の車中からも時折深山に見かける、まるで時代に取り残されたかの小集落の一つをまさに今、二人は眼下にしているのだけれど。
- こうして間近に見ればちゃんと電線は引きこんであってあちらこちらに通っているし、商店らしき看板も何軒か掲げられ、集落内では道だって舗装されてある───そこに住む人々の営みが確かに感じられる。
- 「こういう山の中深くで、こういう小さな村に行き合うたんびに、ほんとに人間ってのはどんなところにも住むものなんだなあって毎回思うよ」
- 「あー、それな。オレの縄張りでもそうだった。むしろいないとこ探す方が難しかったさぁ」
- そんなことを言い合いながら半なかばと玉たま串ぐしが窪くぼ地ちへ下りていけば、山道はやがて手入れは悪いながらもアスファルトの舗装路に代わり、道端には農具小屋やら農業水路やらと、それまで潜くぐってきた山景色はいかにも草深い地方の集落の眺ながめへと転ずる。
- 「なー半、あれって学校か? なにか子供がいるけど」
- 「んー……学校にしちゃ門とか前庭とかもない。んん……ありゃ多分公民館とかそんな感じがするな」
- やがて道の脇に他より目立つ大き目な、その木造瓦かわら屋根、板壁の二階屋の、味わい深く古びた建物は、近づくにつれ『ほろほろ公民館』という看板がかけられているのが見受けられ、半の言葉が正しいことと、二人が山中を過あやまたず目的の集落まで辿たどり着いたことを示していた。
- で、半たちはただ子供たちが、跳んだり跳ねたりして遊んでいると見たのだが、こうして傍そばまで寄って見ると彼らは───ガラス引き戸の正玄関の前、案山子かかしとも田楽刺しの煮物とも取れる図形を道に描きつけ、けんけん跳び遊びの最中のようだ。
- それが二人の寄ったのに動き止やみ、皆して振り向いた顔が、黄緑で長い、目鼻口こそ開いているものの丸と横棒だけをくりぬいて、薄白い筋が走って、頭は獣けものの耳のように尖とがり───まあ、里芋の葉を仮面に被かぶっているだけの話であるのだが。
- とはいえ、携帯ゲーム機やスマートフォン端末、トレーディングカードゲームなど持ち寄って騒いでいるならまだいい。
- そんな草葉の仮面で古い遊び、暮れかけた陽の下では牧歌的というより、山村の景色にあまりにも嵌はまりすぎていてどこか不吉で妖あやしいくらい、玉串の心中は知らず、半は内心で身構えると、声は人懐こかった。
- 「こんばんはー!」「こ、こんばん、は……?」「まだ『こんにちは』でよくねぇ?」
- と仮面なぞ含みもなくぱっと取る。
- すれば皆純真そうな顔で、年が上の子で小学校の高学年くらいだろう、はにかむ子はいても意外にも朗らかに挨あい拶さつされ、半なかばは伝奇小説のように穿うがって見ていた自分をちょっと反省しつつ挨拶を返したことである。
- 「どうも、こんばんは。ここ、ホロホロ窪くぼってところだよな? 俺たちは峠とうげの駅で聞いてきたんだ。それで、この中で誰か、菊きく乃の井いさんって民宿を知ってるかな」
- 腰を屈め、目線を合わせ、子供扱いをしないし取り立てて下した手てに出るわけでもない、ニュートラルに話しかけるのが一番良いと、旅先で覚えたやり方で問うと、一番年かさの、挨拶も一番最初にしてきた利発そうな女の子が、得意げに頷うなずいて。
- 「わかる~。この道歩いてくと、左側にポストのある店があって、そこの角を左に曲がっていったところに看板出てる。あとは道ぞいでだいじょぶ」
- 「そうか。わかりやすいな、ありがとう」
- いつも通り、冴さえない、睡眠不足のような目つきながらも優しく笑いかけ、礼をする半を押しのけ、割り込んだのが玉たま串ぐしである。
- 「そんでオマエら、このムラの美味うまいものってあるだろ? なんだ? 地鶏か?」
- 「……うん、あの……ホロホロドリ」
- 「ホロホロドリ? ホロホロチョウのことかな?」
- ホロホロチョウならば半も知っている。白い斑点のある灰青色の、ガチョウのような体型で頭がちょこんと尖とがった鳥で、それなら食用にするし日本でも飼育している地域もある。
- 「うん……ホロホロドリは、ホロホロドリなの……」
- ただ、答えた子は気恥ずかしそうに俯うつむいてなにやら口ごもってしまい、ごにょごにょと。
- 子供たちは全体に人懐こい様子ではあったけれど、それでも外から来た相手とは、すぐには打ち解けきれないものもあるのだろう。
- あまり彼らにかまい続けてしまってはかえって警戒されそうで、半は子供たちに礼を述べて会話をほどほどに切り上げ、教えられた方へと歩きだす。
- ───ウッフフフ、フフフフフッ!────
- ───背せ筋すじをぎしりと冷たく凝縮させるかの、背後から忍び笑い。
- 子供の声、のはずなのにもっと別の、夜鳴く鳥の音じみた声色で、ぎょっと振り返れば、子供たちはまた里芋の葉の仮面をつけ直して、葉にあけた孔あな越しに半たちをまじまじと凝視している姿が、前屈みというのか、どこか獣けものじみた姿勢にも映る。
- 夕映ばえの弱い光と濃くなりつつある陰の中では余計に不気味で。
- 不意にぱっと踵きびすを返して散り散りに走り去って物陰に消えた。
- 猫か狐あたりの、あの跳ねるような身のこなしと駆け足で。忍び笑いをかすかに尾と曳ひいて。
- 「玉串、今の見たか? あの子たち、何かこう、おかしげな……」
- 慄りつ然ぜんとする想いで立ち尽くして、路面に残されたままの案山子かかしの図形だけが、子供たちがいたことを告げるよすがだった。
- 玉たま串ぐしに思わず縋すがるように語りかけても、本性が妖あやかしである彼女には、半なかばが覚えているこの気味の悪さは今ひとつ伝わらないらしい。
- 「ガキだろ、ただの」
- 「確かにそうだったけどさ……でも……」
- 「いいじゃんさ、今はそんなこと。さっさと食わせてもらおうよ、そのホロホロなんとか」
- それが玉串が言っていたいい匂いの源なのか、どうか。まだそうと決まったわけでもなし、それに今の子供たちの様子にもまた釈然としないものを残しつつも、ここで立ちっぱなしというわけにもいくまい、いよいよ宵よい闇やみが濃くなりつつある。
- 四
- 田舎道の宵闇の中に点ともりだした街灯は、笠付きの丸電球で光も弱く、それもぽつぽつ間遠で、とうてい夜道を照らすには足らずの闇の濃さ、山中の窪くぼ地ちの宵は残照も短い、もう四し囲いは完全に夜のとばりが下りた。
- 子供たちは『誑たぶらかす』という字面がなんとも似合いそうな風ふう体ていだったし、半は少々警戒していたけれど、彼らの案内自体に間違いはなかった。
- じきに辿たどり着いた『菊きく乃の井い』は、民宿というより旅館と呼ぶ方がふさわしい、玄関先には鳥の紋付の玄関灯の下がった瓦かわら屋根の車寄せが迫せり出した店構え。
- 建家は川に接して、流れに水車をかけてあるのも印象的な、間広く風ふ情ぜいのある佇たたずまいをしていた。
- 集落の窪地を囲む斜面を背とし、建てられた棟は法のり面めんに沿って幾棟にも分かれ、その間を屋根付きの渡り階段が繋つないでいる。
- 「こりゃまた……民宿と聞いたが、ちゃんとした旅館じゃないか。茶店のご主人、ちゃんと連絡してくれてあるだろうな……? そうじゃないと飛びこみで入ることになる。大丈夫か?」
- 「なんがよ? 旅館だかなんか知んねーが、寄せてくれないってことはねえだろ。ほらさっさと入ろうぜ」
- 半の逡しゆん巡じゆんなど玉串には察せられた機微ではなく、妖あやかしは青年の袖そでを引いてぐいぐい玄関内へ。広い上がり框がまちは上がり階段がかかって、その脇に荒格子窓の帳簿部屋、明かりも明るい。
- すぐに飛び出してきたのが、半、一瞬峠とうげの茶屋の主人が何かの術を使って先回りしてきたのでは、と疑うほどに彼かの人とそっくりな、どうやらこの『菊乃井』の主人なのだろう。
- 「やぁよくござってぇ! こんな山ン中まで。比ひ良ら坂さかさまとそのお連れ様でございますな?」
- こんな由緒正しげな民宿だか旅館だかに、果たしてちゃんと自分たちの話が通っているものかという懸念は、たちまちに吹き散らされた。
- 「賢けん司じから……あ、駅の茶店のもんのことです……話は聞いております。お食事ですな?」
- 「ええ、この通り、話がいっている通り、二名で」
- 「ええ、迎えに行った方がいいでねべかと話しておったですが、ほんにようござって。お食事はすぐに料理すっぺけんど、お客さま、その後どうされますか」
- それは半なかばとしては、この窪くぼ地ちに臨んだ刻限を見て、ほとんど肚はらが決まっていたことだった。
- 「それなんですが、こちら、宿もやっておられるんですよね? 飛びこみで申し訳ないのですが、宿泊もできたなら、と。どうでしょうか」
- 距離にしてみればそこまで長く歩いたわけでもないけれど、ただここで食事だけとなると帰りは街灯もない山道を懐中電灯頼りに歩くことになろう。
- そういう経験にも慣れてないでもない半だけれど、今回はまだ懐ふところ具合に余裕があった。
- 「ああそんなの。俺だの方はシーズン外で、部屋ならこの通りなんぼでも空いてます。泊まってて下っせ。というか山道暗いとこで歩くは、ハぁ危ないもの、こっちからも勧めます。賢司からの紹介だし、宿代も少し割り引かせてもらうんで、いかがですか」
- この辺りの訛なまり混じりだが聞き取れないほどでもない、宿の勧めを有り難く受け容いれて半は、予定の食事に宿泊を加えた。
- もともとが行く先の決まった旅程ではないし、寄宿先からこんなにも離れていれば食物の味が戻ってくることも経験上理解している。
- (問題はこいつだが───)
- と玉たま串ぐしを見れば、妖あやかしはさっさとサンダルを脱いで、脱ぎっぱなしにして廊下に上がって、あちらこちらと覗のぞきこんでいる気の早さ忙せわしなさの、その落ち着きのないこと色気のないことに、なにやら半の中ですとんと躊躇ためらいの箍たがが外れた、という。
- 「じゃあ泊まりということでお願いします。部屋は一つでいいんで」
- この、部屋を一つと決めて告げた際の半からは、若い男女のどうこういう水みず気け膏あぶら気けは一切脱落してあった次第である。
- 黒々と、濡れた黒御影石のように艶つやめくまで歳月と人の手の丹精を経た板張りの、こういう廊下というのは踏むと足裏に仄ほのかに温ぬくく柔らかい。
- 二人が案内された二階の部屋は、爪も立たないような上床の畳たたみで、年経て手入れの絶えない藺い草ぐさの、枯れたいい匂いがほんのかすかにゆかしく床上に漂った。
- 半がこれであの宿泊費は随分と安いと、思わぬ得をした心ここ地ちだったけれど、座ざ布ぶ団とんを尻で温めるより先に、山歩きの間我慢していた尿意が募った。
- 半が退出する前の主人を捕まえ、手洗いの場所を訪ね、用を済ませてから戻ってきてみれば、部屋はがらんと虚うつろで玉串の姿が見えない。
- (どこいったんだあいつ……)
- 予測がつかないのは妖怪も幼児も似たようなもので、宿のどこかでいらぬ悪さでもしでかしていないかと保護者じみた不安が芽め生ばえてきたあたりで、暢のん気きな声とともに戻ってきた玉たま串ぐしだったが。
- 「おーぅい半なかば~、こんなんどうよ~?」
- ぬい、と大おお盥だらいが出た。玉串の頭に、片手を添えられただけで載っていた。
- アジアの国々の市場なり港なりで荷運びがよくやるように、頭に載せてきたのが一抱えもあるような大盥で、下へ手たすれば戸口の幅より大きそうなのをよく通したものと半は驚くやら呆あきれるやら。
- 青年を尻しり目めに、玉串はするする部屋を横切って、窓際の広縁の、据すえられていた小卓子を器用かつ行儀悪く足でのけ、でんと降ろせばなみなみと張られたお湯がほんのりと湯気、水面を揺らしもせず雫しずく一つも零こぼさずやってのけたのだから、やはり人並み外れた化け物の面目、というところ。
- 「なんなんだこれは。人がちょっと目を離した隙すきに、訳の判らないことをするなと」
- 「まあまあ。オレたちが急な客だったんで、まだ温泉は熱くなってないってさ。まあでも風呂はまだでも、ちょっとは清せい々せいしたいよな。ほら、浸けろ浸けろ足」
- 少し声を尖とがらせた半をなだめるように、広縁の椅い子すに座って素足をたぷりと浸ける、もともとが丈の短いズボンなのでまくり上げる手間もない、ふくらはぎの肌が湯気を吸って瑞みず々みずしく、漏らした吐息も屈くつ託たくなかった。
- 「ふああ……いいよ、気持ちいい。半もやってみろって」
- 「またいきなりな。でも、じゃあ俺もちょっと試してみるか……」
- 向かいに座り、玉串にならって膝ひざ下剥むき出しにして沈めれば、やや熱めの湯が初めは肌に噛かんでくるようだったがすぐ馴な染じんで、じんわり沁しみてくるのが意外なほどの心ここ地ちよさ、山歩きの疲労がゆったり溶けゆくかに思われた。
- 「へええ。こりゃ思ったより悪くないな。山歩きで思ったより疲れてたみたいだ」
- 「だろー?」
- 今や古典中の古典となった幻想文学『指輪物語』にも、空の下に迸ほとばしる泉の響きは貴とうといけれど、それよりなお素す晴ばらしいのは脚に浴びせかける熱い湯の音、などいう戯ざれ歌も見られる。
- 人間と妖あやかしが向かい合って脛すねを晒さらし合っての足湯、くつろいで得意顔の玉串の、その意外な気配りに半は素直に感心するとともに覚えたのは、不思議な近しさだった。
- 旅路をともにする者同士の同類意識とでも言おうか。
- 黙っていれば、多少元気が良すぎるのを傷としても若く顔立ちも整った娘なので、考えてみれば今まではもっぱら一人旅ばかりだったのが、今回はこんな女連れ、とも言える。
- ただ騒々しく荷に厄やつ介かいばかりに思えていたけれど、二人ならではの愉快さと興が湧くというのもあるということか、と改めて感じ入りつつ窓の外を眺ながめれば、こちらとは別の棟との間に造られた庭の夜景が見下ろせた。
- あれは柏かしわの木だろうか、棟より高い、相当な古木が中心となって、築山を盛り池を掘り灯とう籠ろうを配し、半なかばには風流は判らないが、きっと名庭なのだろう。
- 茶屋の主人もここの主人も気易く民宿などと謳うたっていたけれど、この菊きく乃の井い、実は相当な名宿なのではあるまいか……と菊乃井主人がお手伝いさんとともに、食事の膳一式を運んできたのが、そんな頃合いだった。
- ご主人、広縁で足湯を使っていた自分たちに鼻白んだ様子で、半はいささかこりゃ勝手をしたかと焦あせったけれど、彼は別段大して咎とがめる風もなかった。
- 「鉱泉なもんで、はぁまだ湯は熱くなっていねけども、足湯くらいは風呂でも大丈夫でしたよ。もう少し浸かってから食事にしますか? それとも盥たらい、もう下げても?」
- 「あー、いいから。片づけもオレやっとく」
- 「いやいやそんな、お客さんにそんな手間を。ただ……」
- 主人は、窓を開けるとわざわざ雨戸を引き出し、庭の夜景を締め出すようにたてきった。
- 「この辺りは、もうこのくらいの時季でも夜になると随分冷える。うちは古いもんで全館のエアコンとかないから、雨戸をたてとかないと風邪を引きます。何だったら後で火鉢でも持ってきましょうか?」
- 「そこまで冷えるのか……我慢できないようだったらお願いするかも」
- 旅籠はたごの主人としての気遣いなのだろうし、有り難くも思うのだが、半がこの行為に何か含みがあるようにも感じられたのは、雨戸を閉める際に主人が一瞬だがこちらによこした横目に、少し奇妙な色合いが浮いていたからで───
- ともあれ、後は何事もなくお手伝いさんとともに食事の準備を整えて、主人は下がっていきしな、こんな断りを入れていった。
- 「ここの一番の名物はホロホロドリの肉でして、その大皿に串盛にしてある。炙あぶって食ってけらっしぇ。美味うまいこと、保証します」
- 「ご主人、来る途中それはちらりと耳にしてきたんですが、それはあのホロホロチョウの肉ということでいいんでしょうか?」
- 食えて美味ければ何でもかまわない、とまでは半も言わない。その食材が何であるのかくらいの興味はあって、だから訊たずねてみたところ、帰ってきた言葉は微妙に予想外な。
- 「そういう鳥もいて、肉にもするそうですな。ただ仲間内では、この窪くぼのホロホロドリは、この辺りでしか育たんと言い合っているので。なんにしても味は保証します」
- 主人にそんなつもりがあったのかどうか、微妙にはぐらかされた心ここ地ちではあったけれど、卓に並べられた料理の皿の数々は小さな満まん艦かん飾しよくの艦隊を思わせてたくさんで、野の香を強く残す山菜の和え物やおひたし、天ぷらがある、渓けい流りゆうの清冷な水に育った、岩いわ魚なの洗い造りもあれば鰍かじかの素揚げもある。
- いずれも深山の情趣を深く漂わせる皿ばかりだったけれど、やはりメインとして大皿にこれでもかと盛られてきたのが、塩、たれ、粗刻みのニンニクまぶし、新鮮なネギもたっぷり添えられた肉なのだ。
- ちょっと見には地鶏の肉にも見えるが独特な艶やかな色味があり、この辺りでしかいない鳥、というのもあながち本当のことなのかもしれずと、半なかばがしげしげ見やるうちにも玉たま串ぐしは臨りん戦せい態たい勢せい。
- しかし、先んじてさっさと箸を取って選び皿、ではなかった。なんとなれば玉串は地酒の一升瓶の栓を開けているところ。
- 主人の話では、茶屋の従兄弟いとこからの紹介とあれば酒の一本もつけないことには、とのことで、この志も料理に加えてなんとも嬉うれしいことであった。
- だが玉串は、ここまで勢ぞろいの、どこのお殿さまの夕ゆう餐さんかという豪勢膳に、いざ食べだすとなってちょっと首を傾かしげたのが、何が足りないのか、それ不満顔という。
- 「あのさ、そのコンロ、しょぼくねえ? せめて七輪とかさあ……ああそうか、この手の家にはそれよりもいいのがあるよな」
- ホロホロ肉の串は、膳とともに卓に載せられたお一人様用のガスボンベ式のグリルでそれぞれ炙あぶり焼きにして食べるという趣向なのだったが、玉串にはそれがご不満と見える。
- と立ち上がるや、その手は投げ銭を掻かき集める熊手より貪どん欲よくな、とうてい持ちきれないはずの盆と見えたのに、自分と半の分を器用に全部抱え上げたのには青年も魂たま消げたし、ばかりかさっさと部屋を飛び出していったのには呆あつ気けに取られるほかなく。
- とはいえすぐに我に返って追いかければ。
- 「なにやってんだお前、戻って来い、変な贅沢言うなっ」
- 「いいから。んー、こっちかねぇ。こういう屋にはきっとありそうなもんだけどなー」
- だが玉串は聞かず、廊下を小走りにとっとっと、角で折れたり曲がったり、と、とんとんとん、裸電球の下がるだけの薄明の渡り階段を辿たどり、とんとんとん、踏みこんでいった先が菊きく乃の井いの屋棟の中でも随分奥まったところだったろう。半たちの部屋から棟も違たがえて、隔へだたった。
- 「あったあった。こっちだって思ったさ」
- 「何探してるんだ一体……いやそう言うことじゃなく」
- しんと静まり返った広間に玉串は躊躇ためらいなく踏み入って、半も仕方なく後に続いて、で、広間の中央にあるものを見て青年にもぼんやりと理解された。
- 「ああ、囲い炉ろ裏り、か───」
- 部屋には囲炉裏が切ってあり、鋳ちゆう鉄てつの魚細工も施した、使いこまれた自在鉤かぎも下がっていたから───灰は柔らかで、囲炉裏枠も手ずれがしていて展示用でない、日頃に使っている形跡がある。
- グリルのガスの火より、こちらの炭火で焼こうというのが玉串殿の御趣向らしかったが、どうやってこの広間に囲い炉ろ裏りがあると見当をつけたものやら。その辺りは妖あやかしなりの勘働きというものなのだろう。
- ずらずらと囲炉裏端に料理を下ろし並べながら、玉たま串ぐしがまた得意げに。
- 「こっちの火であぶった方が絶対美味うまいって。な、アンタもそう思うだろ」
- 「ううむ、確かにそんな気もするな……とはいっても、勝手に使うのはまずいだろ。だいたい炭とかどうするんだ。炉の中のは……」
- とか火箸で灰の中を掻かき回し探り始めていたあたり、半なかばも好奇心と囲炉裏の誘惑にそそられつつある証拠である。
- 「うん、やっぱり燃え尽きたのしか残ってないし、見たとここの部屋に予備はないっぽいぞ」
- 広間の中を見回しても、炭すみ籠かごらしきものは見えず。
- 「え~……じゃあここまで運んできた飯なのに、また部屋まで持って帰るのオレ……」
- 「なにも考えずやらかすからだ。ただ───」
- 玉串の性向は、思い立ったが吉日の即決即実行、思い切りがいいと言えば言えるのが、軽けい挙きよ妄もう動どうとも言えて、その上この妖はどうにも詰めが甘い。
- はっきり言ってしまえばアホの子であると、半も徐々に気づきつつあった。
- とはいえ───半とて、品行方正聖人君子ではない。この年頃の青年なりの向こう見ずさ、勝手さ加減が枯れているわけでもない。
- こうして囲炉裏を前にしてみると、その炭火で串を炙あぶってみたい、さながら深しん山ざん幽ゆう谷こくの山小屋に籠こもる山人、杣そま人びとのように、と、惹ひかれる気持ちがむらむらと。だから。
- 「俺も囲炉裏で焼くってのには惹かれなくもない。ご主人に使っていいかどうか、炭はどこなのか聞いてくるよ」
- ───で、主人を求めて菊きく乃の井いの中を歩き回ってみたのだが、これが先ほどのお手伝いさんのような宿の者も、まして他の客も見えず、中は森しん閑かんと静まり返っているばかり。
- ここまで閑散としているとどうにも不自然で、なにやらうそ寒いものを覚えて、どうにか厨房まで探り当てて覗のぞいてみたのに、虚うつろな虚むなしさが流しや冷蔵庫の間に漂っているだけの。
- つい先ほどまで自分たちの料理の準備をしていたはず、なのに嘘うそのように人の痕こん跡せきも気配もない。
- (まさか、今宿にいるのは俺と玉串だけとか言わないよな……? なら、他の人たちは一体どこに行った……?)
- 思わず不穏なものを感じたが、厨房の隅に炭の積まれているのを見つけて、半はえいままよ、といり用な分を取り上げた。
- 後から咎とがめ立てされたなら、その時に言い訳すればいいとか考えたあたり、この青年もまた玉串に劣らず軽率のきらいがあるが───そうやって好き勝手に振る舞って、いわば自分を鼓舞しないことにはどこか背せ筋すじが寒々しくなりそうな、そんな不安定な空気が館内に漂い始めてあることを、半なかばは無意識理に感じ取っていたのだろう。
- ───囲い炉ろ裏りの火おこしにいささか手間取ったけれど、炭火はいったん据すわってしまえば後はたまに継ぎ足すか火箸で空気を入れるかすれば、特に障さわりもなくぱちぱちと懐かしく、そして頼もしく灰の中で赤らんだ。
- ひっきりなしにじゅうじゅうばちばちと、原始的なまでの露骨な脂の弾ける音は、言うまでもなく二人がホロホロ肉の串を炙あぶっては食いかつ炙りまた食らう、その伴奏である。
- 広間の明かりはいくつかの電球がぶら下がっていたけれど、二人はその内の囲炉裏端に近い一つだけを灯して、あとは周りを暗がりに泥なずませた。
- 光は穏やかな笠となって二人に物柔らかな影を投げかけて、深山中の古びた民家の懐ふところ深くに抱かれるという、得も言われぬ隠いん遁とん的な愉悦を与えている。
- 囲炉裏に燃える火もまた、その温ぬくもりと揺らめきで、二人をこの現代という時から隔離していくかのよう。
- そんな心ここ地ちの中で食べる山家の料理の滋じ味み深さ、町の料理にはない野趣に満ちた味わいといったら。
- こんな時期にも取れるのだろうか、コシアブラという山菜のお浸しの、癖くせが強い風味は慣れてしまえば後を引いたし、岩いわ魚なも凍るほどの水を惜しみなく用いて洗ったのだろう、コリコリとしっかりした歯ごたえから、やがて深い旨味が染みてくる。
- だがそれらよりなにより佳か味み絶ぜつ品ぴんだったのが、やはりホロホロ肉であった。
- 炙った端から脂が滴したたるようなそれをかじれば、確かに鶏肉のようでいて、やはり異なり、とにかく歯ごたえが印象的な肉だった。
- 肉質は絶妙の歯ごたえと脂の美味うまさを宿し、その炙り焼きの味わいは、絶品、いやそれ以上。
- 噛かみ口からは弾けるように肉汁が溢あふれ、舌の表面が勝手にじゅうじゅう吸いこんでいく。
- 噛むたびに歯の裏に一瞬肉が張り付き、剥はがれて肉汁とともに舌で踊る。
- 口の中で繰り広げられる香ばしさ、肉の旨味、塩の加減、あるいはたれの香味の宴は圧倒的なほどで、半は焼くためだけに手を動かし咀そ嚼しやくするためだけに口を動かす生き物となって、それがなんとも幸せなことであると夢中になった。
- ちらりと見れば玉たま串ぐしも同様で、二人前にしてはちと多すぎでは、と危あやぶまれた大皿の串がどんどんと減っていく。
- 舌に絡んだ脂を酒で洗えば、酒精が甘く濃こまやかに喉のどを流していって、さっぱりした舌がまた肉の旨味を求めて串を口に運ばせる、その繰り返しをどれだけしたのか、どれだけでもできそうな。
- それでもようやく一息ついて忘我境から戻って半と玉串は、顔を合わせて微笑ほほえんだ。美味いものを食えば誰でも状況がどうあろうと笑顔になり、この時の二人もまた然しかり、である。
- 「ふぅ……にしても半なかば、マジで美う味まいなこのホロホロ肉。いくらでも食えるよ。おまけにこの酒ともよく合いやがる」
- 湯ゆ呑のみに並々満たしたのをぐびりと大きく煽あおり、呑み下した喉のどの動きと、雫しずくに濡れた唇と、笑顔の、なんとも幸せそうなことといったら。
- 「少しは手加減してくれ。俺ももうちょっと呑みたいよ」
- 「手加減してるよ。いつもだったらラッパ飲みだ……な、半、やっぱ囲い炉ろ裏りでよかったろ?」
- 玉たま串ぐしの、言いながら半の湯呑みにも地酒を注ぎ足してやるのが、初めて会った時を思えば格段の進化で、むしろこの妖あやかし、意外に人懐こいと青年を奇妙な気分にさせる。
- 「……まあな。確かに」
- 「アンタたちはこういうの造るのは巧いよな」
- 「囲炉裏のこと……だけじゃなく、いろんな道具とか家の造ぞう作さとかのことか。まあなあ。その辺りは確かに人間と妖怪の違いなんだろう」
- 「まあオレらの中でも、特に力のあるのは、人間よりも凄すごい御殿とか造ったりすんのもあっけどさ、そんなのはちょっとしかいないんじゃないかな。オレ、他の妖のことはあんまり知らないし」
- 「じゃあ、笠かさ縫ぬいのことはどうなんだ?」
- そこで半がかの妖姫のことを口にしたのは、玉串の『力ある妖』という語からの連想だったのだろう。
- 「……笠縫様か……。正直オレにもよくわかんないよ。あの方って、妖気とか気配だけなら、生まれたての精とか憑つき物よりずっとずっと薄い。だから初めて会った時とか、全然同類とかって思わなかったんだぜ。それが───」
- 急に酒が渋くなったような顔つきとなる。それを流すようにまた一口呑み下す。
- 「あんなにおっかない、恐ろしい、逆らえない。もうこの国にはいなくなった大妖怪みたいだよ、ほんと。それにオレ、あの方のこと、前から知ってたのかなあ。なンかさ、懐かしいんだ」
- それには半も頷うなずけるところではある。あの妖姫は、人の中に混じってしまえばその際立つ美び貌ぼう以外は見えなくなる瞬間がある。
- だというのに半の前では様々に人間離れした振る舞いや業わざを見せる……。
- 「でもアンタも大概だよな。なにか見てるとアレなんだろ。あの笠縫様を食いたい食いたいって。よゥまあそういう恐ろしいことを言って、命たまも取られず済んでるもんだ。あの方、アンタになんかあんのかなぁ、因縁とか……ん~……わっかんねえ……」
- 胡坐あぐらに座って腕組みし、何事かさっと記憶の瀬をさらう風ふ情ぜいの玉串は、姿と態度としては色気も女らしさも欠けていたけれど。
- この時、半はそんな彼女に不思議な近しさと親しさ、言ってしまえば同胞意識を、酔い心ごこ地ちの中に覚えていたのである。
- ……そればかりではない。その剥むき出しのふくらはぎや肩に、こんなにもホロホロ肉の美味うまさを堪能している最中なのに、じっと視線が吸いつけられてしまって───駄目、食いたいとかそんなのはなしだ、と半なかばは軽く目を閉じた。
- しんしんと夜も耽ふけり、物寂しいような、それでいて懐かしいような情緒が深まりゆき、囲い炉ろ裏りの炭を足そうとした時。
- ふっと玉たま串ぐしが顔を上げ、怪け訝げんに思った半も同じくし、やがて二人は顔を見合わせ頷うなずき合った。
- 広間の外から、祭りの囃はや子しのような、いや、もっとしめやかな拍子の、雅楽のような曲の音がかすかに漏れ聞こえてくるのだ。
- この囲炉裏のある広間は棟の他の部屋からは長い廊下でやや離れ、半たちが宛あてがわれた部屋から見下ろした中庭からも遠かったのだけれど、音ね色いろはどうにもそちらから伝わってくるかに思われる。
- 聞き流してしまえばそれまでなのに、囲炉裏端を立って、二人、覗のぞきに行った足音を忍ばせていたのは、その時二人に既に何事か予感があったのかもしれない───
- 廊下に出れば黒い石のような床板が、さながら秘密の隧道トンネルのように延びて、果ての長廊下まで続いている。そこまで忍び足で進んで、半の間借り部屋と同じようなスクリュー式の鍵の古い窓枠の下に身を屈かがめ、中庭を窺うかがってみると。
- 灯とう籠ろうの古風な明かりが庭のあちこちをぼうっと黄色く明るませている他に、中央には赤々と燃え盛る松明たいまつの火と、そしてそこに築かれているあれ、神しん饌せんをのせる三宝をもっと大きくし、榊の葉やら松葉やらで飾り立てているあれは、祭壇ではないだろうかと半は推し量った。
- いや、測るまでもなく、その周りで、奇妙な、舞とも儀式ともつかぬ行為に没我している者たちを見れば誰でもそう思おう。
- ぐるりと取り巻いて、横笛やら手太鼓やら、鈴の棒やら、土俗的な楽器を手に、筒つつ袖そでの着物に括くり袴ばかま、手てつ甲こうと脚きや絆はんを着けて、毛皮の襟えり巻まきやら腰巻を巻いた、まるで伝説の絵巻物中の伝説から抜け出してきたような者たちだった。
- 大人もいる、女もいる、子供もいる。それぞれの鳴り物に興じながら、ゆったりと体を舞わせている。
- 彼らの異様な姿もさることながら、さらに衝撃的だったのは、祭壇の上に捧げられた供く物もつである。
- 屠ほふられているのかぴくりとも動きはしないが、その供物は、大きさは犬程度、山鳥のようでもあり、ムジナのようでもあり、半としては始し祖そ鳥ちようをもっと獣けものの輪郭に寄せたような姿に見え、とにかく正体不明の生き物───そこで、玉串が看破してしまったのが、よせばいいのにという奴で。
- 「なんだあれ。鳥でも獣でもねえな。───ん? なにかさ、半、これオレの勘なんだが」
- 「いや、皆まで言わないでくれ。その先はちと聞きたくないぜ」
- 「あの生いけ贄にえにされてるアレが、ここの『ホロホロドリ』なんじゃねぇの?」
- 「あ。言っちまいやがった」
- 二人、憮ぶ然ぜんと互いを横目を見合った。
- 「つまり、オレたちが美味うまい美味いと食い散らかしてたのはアレってことか?」
- 「そうなるな。肉になっていると判らんが、元の姿形はなかなかにアヴァンギャルドな」
- あんな得体の知れぬ生き物、はっきり言ってしまえば怪鳥の肉をあれほど意地汚く貪むさぼり食らったのかと、知ってしまえばじわじわと怖おぞ気けと吐き気がせり上がる……というのが正しい反応なのだろう。
- しかしこの時、ふっと笑みに口元をほころばせたのはどちらが先であったか。
- 「でも、なんにしてもとにかく美味かった」
- 「それには同意する。美味いは正義。それに俺は判るんだ。食っちゃまずいものはまずいと、なにかピンとくる。その意味ではあれは食って一向にかまわないものだ」
- あのような得体の知れないモノの肉を貪り食って美味いとまだ笑う精神性、妖あやかしである玉たま串ぐしはさておいて、半なかばも相当に箍たがが外れているけれど、彼なりの保証、というか自負として、食えるものを瞬時に見分けられるというあの直感がある。
- そしてそれは、時にはどれだけ食えそうに、美味そうに見えても食ってはいけないものがあることを青年に教え、彼は今までその直感に逆らうことはなかった。
- そんな直観も、妖姫の前ではどうしようもなく暴走するのだがそれはさておき。
- 「……便利な奴だなアンタ。変な天てん稟ぴんがある……」
- 「その天稟とやらが、笠かさ縫ぬいを喰ってしまえって全力で俺をそそのかすんだがな」
- 「うえ……」
- もちろん小声でやりあっていたつもりだったけれど、途中からはどうにも余計な無駄話。会話の途切れた隙すきが妙に静かなのに、二人がふっとまた中庭を見やれば。
- いつの間にか楽の音が止やんでいた。二人が注意を逸そらしていた隙に、中庭の者たちは、廊下の中の二人を目ざとくとらえて、妙にぎらつく視線を注いでいたのだった。
- 二人が慄りつ然ぜんとしたのは、彼らの顔には見覚えがあったということ、この菊きく乃の井いの主人でありお手伝いさんであり、集落ですれ違った人たちであり出会った子供であり───緊迫した瞬間が流れて、やがて彼らは顔を背そむけ、そろそろと筒つつ袖そでのたもとで顔を覆おおってそして。
- がばっと、バネ細工のようにまた向き直った時には、顔が怪しく異様に面変わり、の、皆異様な仮面を顔に着けていたのだった。大人たちは様々な鳥獣の、その特徴を奇妙に誇張させ、土俗的に戯画化カリカチユアしたような仮面を。子供たちはあの里芋の葉の仮面を。
- それまででも十分に異様であったのに、仮面を被かぶった後の気配はもうはっきり妖気と言ってよく、半はもちろん玉串までたじろいだほど。
- 「うぅ───っ!?」
- 「半なかば、アレやばい、なんかわかンねえがあれはまずい! 逃げろこっから!」
- 玉たま串ぐしはとっさに強く半を押しやりながら、駆けだしたが向かった方角が長廊下の先へ、宿の入り口へ、などではなく何を考えているのか元来た方、先ほどまでいた囲い炉ろ裏りの間へと。
- 押されてたたらを踏みながら、小声で、それでも強く怒ど鳴なりつける半。
- 「人には逃げろって言ってなんでお前は戻ってく!?」
- 「酒……っ。さっきの酒まだたっぷり残ってた、もったいねぇっ」
- 「そんな場合かあああっ」
- なるほど酒の一滴は血の一滴、とは大学の酒好きの先輩にとくとくと諭されたものだが時と場合によりにけり。
- この期においては玉串のお頭つむの中身を疑うほかなく、半はとっさにどちらに向かったものか逡しゆん巡じゆんした。荷物は惜しいが財布は身に着けている、なら出口へ? けれど玉串を残して自分だけ先に?
- ……彼女は妖あやかしであり、あの森の中で見せた跳ね脚もある、とこの時失念していたのは、先ほどまで親しい友のように酒を酌くみ交わしていたからか、ともかくこの躊躇ためらいが彼をさらに危あやうくした。
- ぱんぱんぱんと廊下に並ぶ襖ふすま戸引き戸が拍子木よろしく鳴って開いて、それまで無人だったはずの宿の中にわらわらと湧きだしたのが中庭の者たちと同様の仮面の者の、廊下の奥の方から、迫り来る、無言なのがかえって恐ろしい。
- 「うわわわああ!?」
- 玉串の方も同じ目を見たようだった。囲炉裏の間から一升瓶を抱えて走り出してきたはいいものの、その背後、囲炉裏の間の中からどっと湧きだし迫るは同じ、仮面の者たち。
- 「なんでぇ!? さっきまであの部屋、誰もいなかったろう!? ちょ、半もなんでぼさってしてるんだよ、逃げろっつったろうがバカ!」
- 「人のこと言えるかこのド阿あ呆ほう妖怪、あああもう!」
- 幸いにして、なのか───? 菊きく乃の井いの出口に向かう方にだけは仮面の者たちは見えず、玉串をぎりぎりまで待って駆けだす半だった。
- 五
- 部屋に荷物を取りに戻っている暇などあるものか、丹精に磨きこまれた廊下はこういう時には危なっかしく滑る滑る、二度三度足を踏み損ないそうになりながらもどうにか、廊下を辿たどり渡り階段を駆け下りる。
- 二人の背後には腕を振りかざして仮面の者たちが迫る迫る、玄関が見えてきた時にはただひたすらに、待ち伏せだけはなしにしてくれと祈った。
- こういう時だけ天が聞き届けたでもあるまいが、慌ただしく靴とサンダルを履くまで追っ手は間に合わず、玄関口から車寄せに駆けだした時にも外には誰もおらず。
- 間に合った、振り切った、逃げ切った、と半なかばも玉たま串ぐしも噛かみ締めた、安あん堵どはたちまちに驚きよう愕がくにと変わったのだった。
- 追っ手を振り切ったと思ったが、向こうはどうやら、宿の中から二人を追い立てればそれで事足りた、むしろそれが目的だったのだろう。
- なんとなれば───集落の姿は一変していた。
- 夕暮れには日本の山村の原風景のような、郷愁を誘う古民家が田畑と林の中に点在する景色を見せていたのに。
- この今は、月明かりの下で、水、水、どこまでも広がる暗い水───
- 集落を囲んでいたはずの窪くぼ地ちの法のり面めんも見えない。
- 月明かりに照らし出されていたのは、狭霧が妖あやしく漂う、夜の沼地。どこまでも広がって。
- 土臭く、泥臭い沼水のにおいが二人の鼻先を掠かすめ、空気にはむっと水気が籠こもり、生暖かくもなく、かといって寒いのでもなく、その温度のなさは放置した死肉を思わせた。
- 茅かや葺ぶきの家々は残っていたが、それは今は孤島のように暗い沼地のあちこちに散らばり、その間を粗末な板橋が延び、分岐し、合流しながら繋つないでいる……。
- 「いつの間にこんな……来た時と全然違ってるじゃないか……!?」
- 別れしなの子供たちの含み笑い。中庭を見せぬようにと雨戸を閉じた主人の振る舞い、その主人たちの奇き矯きような儀式と仮面、なにより祭壇上のホロホロドリ───いくつもの異様な事柄はあったけれど、だからといってそれらにこの集落のここまでの転変の前兆など読み取れたものか。
- 追っ手の迫るも一瞬忘れ、愕がく然ぜんと呟つぶやく半に玉串も、細い声で呟いた。
- 「ここ……オレの隠れ山と同じだ、幽世かくりよだよ……」
- 「そんなことだろうと思ったよ。でも、なあ玉串、そういうのってお前、入った時とかに判らないのか」
- 「どうなんだろう。オレ、自分とこの他の幽世ってよく知らないし。でもそう言えば、あの駅で汽車が後ろに下がっていって停まった時、なにかおかしかったような」
- あのスイッチバックの時か、と半は記憶を探って佇たたずんだ、青年の腕を、ぐいと引いた玉串の力は、やはり妖あやかし故ゆえか、彼の骨組みを軋きしらせるほどに強かったのだ。
- 「だからなにぼぅってしてんだってば半、逃げねえとマズいだろ、こいつらなんかどこかマズい!」
- 「痛い! わかった、もう気ぃ逸そらさないから、そんなにぐいぐい引っ張らないでくれ!」
- こうして駆けだすが、菊きく乃の井いにも続いていた板橋の上、月影で思いのほか明るくて、明かりもいらないほど。
- 暗い水面に逆写しに映る走る姿は、月の光の中で無声映画のような静かな騒がしさとでもいうべき趣おもむきだった。
- 二人の背後には、松明たいまつ翳かざした仮面の者たちわらわら追随し、火はこちらは不気味な鬼火として沼の面に揺れて、まさしく悪夢か妖怪画から百鬼夜行の抜け出してきた様さまかと、奇怪にして物もの凄すさまじい。
- 故に月の明るさなど仮面の者たちに追い立てられる半なかばと玉たま串ぐしにはなんの慰めにもならず、さらには新手が、あちこちで分岐し、合流する板橋から押し寄せて、こちらは鎌かまや短刀、鍬くわや鋤すきなどを構えた者もいて、その刃に弾き返る月光は、慰めどころかもう剣けん呑のんな限りであるのだから。
- 「なあ、あいつらオレたちをどうする気なんかな!? 〆しめて捌さばいて食うつもりかな!?」
- 変容前の集落は、せいぜいが二十軒程度の過疎の村だったのに、今は一体どれだけの大勢が繰り出されているのやら、数えられたものではなく。
- 「余計なこと言ってないで、走れ、こっちだ!」
- 「で、でも半、オレたち、なんかこれ、なんか……まずくないかっ?」
- ……玉串が危あやぶむのも半には理解されていた。
- 後ろから追い立てられ、板橋の分岐では一方から押し寄せる新手に、どちらに進むかの選択を潰つぶされ、自分たちはきっと、逃げているつもりが彼らの思惑通りに走らされている、と。
- ぎしぎしと軋きしむ板橋、沼水に何かが跳ねる低く籠こもった音、あちらこちらに群島のように点在する茅かや葺ぶきの家並みは今や明かりもなく海の底の古怪な貝のような輪郭を晒さらし、狭霧の中に浮かび漂う火は、追っ手のものか、それとも沼の瘴しよう気きが燃えたものか。
- 追っ手にあって然しかりの罵ば声せい、怒声がないのもまた不気味で、背後からの足音、板の軋みがなければ、二人はたびたび本当に彼らがそこにいるのかどうか振り返っただろう。
- こうやって幻妖な夜の沼の上を追いかけ回されるうち、半と玉串は板橋の先が、湖沼上の小島の一つにと繋つながっているのを悟った、というより自分たちがあの小島へと追い詰められていくのだと。
- それでもこの得体の知れない闇沼に飛びこんで逃れるのもご免で、やむなく駆けるうちに、二人が行き着いた小島は、幾いく許ばくかの杉や欅けやきの木こ立だちに取り巻かれ、その真ん中に大なる奇岩がでんと蹲うずくまっていたのだった。
- 巨大で夜目にも濃く苔こけむした、奇妙なくらいに丸い巌いわおの、半ばから根元にかけてが内側に大きく抉えぐれて窪くぼみこみ、この巨岩は半ば空洞となっているのだが、その窪みに、古い社やしろが嵌はめこまれている。
- 「……追い詰められたか、やっぱり……」
- 「だったら半、あの社の中に立て籠るとかは……?」
- これ以上先に進む道はなし、ひりつく喉のどに悲鳴を上げる肺腑、荒い息で囁ささやき交わす二人の背後から。
- 「神職でもないのがお社やしろの中に入るなどと、無礼にも程がある。ましてそこは、ホロホロ様のお社、ホロホロ様の塚だというのに」
- 仮面の追跡者の一人が初めて口を聞いた、声は菊きく乃の井い主人のものだった。
- 岩と社が融合したようなこの奇岩こそが、菊乃井主人の言葉によればホロホロ塚とやららしいが───
- 「なあおい、ホロホロって鳥の名前じゃなかったのか。するとあなたたちはこのホロホロ塚とやらの、ご神体でも俺たちに食わせたわけか?」
- 「ひでえよ、そっちから食わせておいて、後から怒って追っかけるとか。ダメならダメって言えばいいのにさ」
- 「…………」
- また無言に戻った菊乃井主人、追っ手たちに、じりじりと薄気味悪い社に追いやられていく半なかばと玉たま串ぐしの、その背後から響いた声は、夜や闇あんに昂然と、そして同時に艶つやめかしさも帯びて。
- 『ざわめかしいこと。おとなしゅう覚悟せよ、若人に小妖───』
- 声とともに奇岩中の社の扉が内側からたん、と小気味よく開いたとみるや、奥の暗くら闇やみから轟ごうと薄気味悪く暗い、青い炎が噴き出したのに、半と玉串は慌てて飛びのくも、火は彼らではなくホロホロ塚をめらめらと包み込む。
- やがて岩上まで燃え上がっていって、そこで一つのかたちに収束した。
- 青炎は、一人の女にと。岩上にすらりと佇たたずんだ女の姿は。
- 古い時代の武家の姫か上じよう臈ろうのような姿───羅うすもの、襲衣したがさね、下締めなし、裾すそを足元に引き、黒髪長く、丈に余る。
- まるで古い絵草紙の姫か御前のように美しい姿で、声で、鼻び梁りようは通って唇も赤く鮮やかなのに、その容よう貌ぼうは。
- 嘴くちばしを突き出した不気味な鳥の仮面で目元を覆おおった、異妖。
- 山の烏からすか天狗の姫か、驕きよう慢まんな美を満たした妙齢の女で、半が知る玉串よりも笠かさ縫ぬいよりも、人外の気配を強烈に発散してあり。明らかに妖あやかしにして、この沼地の、この幽世かくりよの主あるじなのだと凡俗の半にも知れた。
- それまで無言であった追っ手たちも、口々に『ホロホロ様』『ホロホロ御前様』などと呟つぶやき、首を垂れる様さまがいかにも敬けい虔けんな。
- つまりはこの妖女がやはりこの幽世の主『ホロホロ様』なのだ───ただ。半は。
- その出いで立ちや姿形はまるで異なるながらも、どこかしら笠縫と似通った印象を受けていたのである。
- 岩上より、暗くら闇やみに婀あ娜だな香りを撒まくような声で、妖女が衆目に呼ばわる。
- 「其その方等、しかとこの者たちを饗きよう応おうしたかえ? 肉と酒、魚に菜をば、存分に振る舞うてやったのかい?」
- 「お言葉通りに、ホロホロ様。ホロホロ窪くぼの本来の姿、ホロホロ沼の御前様。我ら、沼御前様のお望みのままに、お言葉のままに」
- 「なれば其の方、そこな若人、其の方はわたしへの供きよう犠ぎである。沼の主へ捧げられる栄えいに、存分に浴すがよい」
- 刃物を持っていた者はそれを下げ、無手の者はみな合掌してみな等ひとし並なみにかしずく中で、玉たま串ぐしがそっと半なかばの脇を突いて問うのが、これもよせばいいのにというやつで。
- 「半、この鳥顔女が言ってるのって……」
- 「要約すると、俺たちを生いけ贄にえして食ってやるとかそんなあたり……」
- 「ななな、なんでそんなことっ」
- 仕方ないとはいえ声を張った玉串に、妖女のその面の嘴くちばしの先を向けて、説き聞かせた。
- 「知れたこと。この沼を、わたしの領の護りをより強うするために。若人、其の方の気配、お山に入りし時より聴き取ってあった。其の方、俗人にしてはめずらかな気配を放っておる。嗅かぎ当てられるものは少なかろうが、な。ともかく、故ゆえに招いた」
- そこで半はようやく気づいた次第で、あのスイッチバックの時だと今さらの、思えばあの路線は、もうスイッチバック方式などとっくに排していた。
- あの辺りで既にこの妖女の網にかかっていたのだろう。同類の玉串にも感じさせないほどの隠いん微び陰いん湿しつなやり方で。
- 「其の方は、大おお阿あ闍じや梨り、聖の血肉、精魂に比すべき供犠……とまではまあ、届かぬとはいえ、それでもわたしを大いに養うてくれるだろうよ」
- 今度は半に嘴の先を向けて、鷹おう揚ような物言いの妖女だったが、半はその標的が自分なのだと、じわじわ理解しつつあったが、かといって納得いくものに非あらずして、なぜどこにでもいるような人間の自分が、と。
- 「え、俺……? 誰かと勘違いしてないか? 例えばこの玉串とかと」
- 「そこなちっぽけな小妖にはさしたる用はない。お前を招いたらついてきた、というだけ。とは申せ、もののついでともいう。其の方も私の糧かてにしてくれりょうぞ」
- 「とんだとばっちりだぁ! ううう半ぁ、アンタが恨めしいぞ」
- 恨み言を垂れても、半一人を置いて逃げだそうとしないあたりがこの玉串の性根の素直さを示しているのだろう……この期に及んでも酒瓶を離さず胸にしっかりかき抱き、それでいて膝ひざはガタガタとうち震わせているというみっともない姿だが。
- 奇くしき妖女の餌え食じきにされるという恐怖もあるにはあるが、それでも玉串の姿は情けないながらも共連れのある有難さを半なかばに感じさせ、そこで青年、ふと思いついたことがあり、小声で玉たま串ぐしに囁ささやきかける。
- (玉串お前な、そういやなんでわざわざ地べた駆けずり回ってるんだ? お前ほら、最初の追っかけっこの時、えらいこと跳ねたり飛んだりしてだろう)
- (だってそんなコトしたらアンタを置いてっちゃうだろ。そんなのもし笠かさ縫ぬい様にばれたらどうなるか)
- ここまでくると律りち義ぎと馬鹿の区別が曖あい昧まいになってきていよう───
- (それはわかるがそうじゃなくって、俺を抱えて跳ぶとかできないのか)
- (だって両手今、塞ふさがってるだろうが、酒瓶抱えるので! あんま強く握ると割れるし、そうしないよう一生懸命加減してたら、なにかもう手が強こわ張ばって離れなくなってきてるし───)
- ───半の中で、狭霧の異妖な沼も追っ手衆も妖女も、左手で描いたような輪郭にと崩れていくかのようだった。
- 半は大して世の中の役には立たぬ男だが、玉串もどちらとかいうと同類らしく、こんなのが初めはあれほど兇悪に自分と笠縫を脅おどかしてきたのが今となっては信じがたいくらい。
- 人は自分が人間であるなどと、常日頃から意識して生きているわけではないように、玉串も自分が妖あやかしだということをいつも自覚しているわけではないのかもしれないが、程がある。
- だから半は声を張り上げた。
- 「酒瓶を! 俺に! 渡せ!」
- 「ひゃ、ひゃい!」
- 半の怒声に撃たれて玉串が、反射的に緩ゆるめた手から一升瓶を奪い取り、それからまた一声。
- 「それから俺を抱き上げて!」
- 「こ、こうか……?」
- 小脇に抱える、肩に担ぎ上げる、そのいずれでもなく玉串がしたのは、横抱き、あのお姫様抱っこという奴なのが、この期に及んでだった。
- 「そして、思い切り───跳べぇぇぇ!!」
- そして玉串は、大きく跳んだ。呆あつ気けに取られていた追っ手衆よりの頭より高く、岩上のホロホロ様よりも上に、さらには塚を取り巻いていた木こ立だちをも越えて。
- 「玉串、あっちだ!」
- 「アレか。わかった!」
- 半が示したのは、沼の奥に浮かぶ一つの小島。そこにはなぜか板橋が繋つながっていない。あそこなら少しは時間稼ぎもできようと。玉串はいったん小島の木立の中でひときわ高い欅けやきの梢こずえに留まり、それからまた、より高く大きく跳ぶが、半の示したその小島へと。
- 生き物を大地に縛りつける重さから解き放たれる自在の境地、月夜の空に身を宙に放つ爽そう快かいさに、こんな時でも半なかばの目は晴れやかに瞠みはられたのも無理はない。
- 「やっぱり跳べるんじゃないんかお前、こんなに高く、遠く……」
- 「なんだって!? いいから、我慢しろ、ちょっとだけがくんっていうぞ」
- という玉たま串ぐしの警告に身構えしつつ、風を捲まいて後ろにその緒を靡なびかせて、二人が降り立ったのは、他の小島とはなんと趣きが異なっていたことか。
- その小島、と見えたのは、沼上に浮かぶ廃線路と小さな、待合室もないホームばかりの廃駅だった。まだ鉄道ばかりが物と人を遠くへ運んでくれるものだった時代の名な残ごりを濃く漂わせていたけれど、それでも廃されたもの特有の、侘びしさ、物寂しさを漂わせ月下に佇たたずむ。
- 残っていた駅名板を読めば、駅名は横書きで『いぬさか』とあった───
- 「犬かなんかに関係ある地名かな……いや、今はそんなことはどうでもいいんだ」
- 「なー半、この駅名って……」
- 「だから駅の名前なんてどうでもいいんだってば。そんなことより、こっから逃げられたりとかしないか……? 散々ぱら肉をドカ食いした代金に、自分が食われるなんてまっぴらだぞ」
- もし鉄道ならば外界に繋つながっているということも有り得るのではないかと半は一瞬考えたけれど、線路の端はどちらも水没している。これでは線路伝いに走っても、逃げ延びられるとは考えられない。
- 「線路を伝って逃げられないかと一瞬期待したけどな、こりゃ無理だろう……だいたいこの沼地に入っていくってだけでぞっとする」
- 「そもそもここ、オレがいた山よりも、ずっと境が強い。外からは入れないし、中からも出られない……オレには境が越えられないって判る」
- だんだんにっちもさっちもいかなくなってきて、手詰まりのいら立ちに半は業を煮やした挙句に、訪れたのはどうにも自じ暴ぼう自じ棄きな心ここ地ちである。
- 玉串から受け取っていた地酒の瓶を月光に透かせば、二人で何口か分は中で揺れていた。
- 「……どうせ逃げられないんだ、今のうちに呑のんじまおうぜ、玉串、半分ずつだ」
- 「そう、だな……じゃあオレから先に」
- ……こういう時くらい、遠慮と分別を見せるかと思った半がむしろ馬鹿なので、玉串が満悦の吐息で唇を拭ぬぐった時、残りを示す濃い色は色ガラスの中にわずかばかりと減っていた。
- 「半分ずつって言ったのに、こんなに減らしちまいやがって、七割がた呑んだな、おい……」
- まあ仕方ないと喇叭らつぱ呑みに煽あおれば、揺らされ続け玉串の体に温められ、変に伸びたような味わいだったけれど、渇いた喉のどにはそれもまたおつなもので一息に残りを───呑み干しはせず、半は錆さびたレールの上に残りを振り零こぼしたのである。
- 「一口二口ばかりだが、残りはこっちの線路にもお裾分けだ。毎日水気ばかり吸ってたってつまらないだろう?」
- 「よくわかんない理屈だな……アンタがいいなら別にいいけど」
- 追い詰められた焦あせりは奇妙な風流心となって発露したばかりではない。
- 半なかばは衝動的に空になった一升瓶をレールに投げつけて打ち砕いて、濃茶のガラスを煙水晶のかけらと錆さびた線路に散らしたのだった。
- なぜそんなことをしたのか、半自身にも無自覚の行為で、玉たま串ぐしもややぎょっとしたように線路上の破片を眺ながめていたけれど、その目がはっと背後へと振り向けられる。
- 沼上に、松明たいまつを掲げた小舟が幾いく艘そうも繰り出されていた。いずれも妖女とその手の者たちであることに間違いはなく、確かにこの廃駅には板橋は繋つながっていなかったとしても、半の思惑はその場しのぎにもならなかったらしい。
- じりじりと腹の底を炙あぶられる悪心ごこ地ちのうちにも舟は寄り来たり、その先頭の船の舳へ先さきに、打ち掛けの襟えりを取って掲げ、見上げるは沼の妖女の、獲物のあがきを愉たのしむ風すら漂った。
- (また跳んでみせろ、玉串……)
- (でもこれじゃ、すぐにまた追いつかれるぜ……)
- 二人の囁ささやきを聞いてか聞かずか、妖女は冷笑するのだった。
- 「このような小島……わたしの沼に、さてあったろうか。が、そんなことはどうでもいい」
- 「先ほどは虚を衝つかれ逃したが。其その方の飛んだり跳ねたりにはもう付き合わぬ。二度はないと、小妖も判っておろう」
- どういう動きをしたものか、小舟の縁に立ちはだかったはずの妖女は、次の瞬間にコマを中抜きにしたように半と玉串の前に立っていた。
- 有無を言わさず、羅うすものの肩を抜きざま、二人に多い被かぶせる───と、ざっと二人は風の音を聞いた、体が空を間切る感覚に包まれた。
- で、次に羅が引き剥はがされた時、半と玉串はホロホロ塚の前に立ち尽くしていた、あれだけ跳んだのに妖女の術で一瞬に引き戻されて、元の木もく阿あ弥みの。
- 「そもそも、もうヨモツヘグイしてしまった後では逃れられぬ」
- それは、冥界で煮炊きした食べ物を食べることを指し、そうした者はもう生者の世界には戻れないという概念で、妖女はきっと宿で供された食事のことを言っているのだろう。
- が、その宣言は二人には恐怖よりも、あのホロホロ肉の官能的なまでの美味の恍こう惚こつ境を思い出させていたという。
- 「……もっと食いたかった」
- 「ああ、全く同感だ。もっと食えるぞ」
- ……この二人、旅の道連れとして妙に似合いとなってきているような。
- 「あれだけ食らいかつ呑のみして、まだ足らぬと。これだから俗人に小妖は。呆あきれた話だこと。さて、そんな減らず口もどこまで続くやら、試してみようかねえ」
- とはいえ夕ゆう餉げの想い出がいかに幸せでも、妖女を阻はばむ盾たてになってくれるわけもなく、じわり、と仮面の美女から染み出したのは、胃の腑ふを掴つかみ上げ、せっかく食したものを吐き戻させてしまいかねない、重く鈍い鬼気。
- いよいよ追いかけっこはお終しまい、そして後は二人の末期、という際の、迫りきたる───
- 二人をじわじわと絶望が包む───
- この時突如として。
- 半なかばは異常なまでの。
- 強烈な飢えに見舞われたのだ。
- ホロホロ塚の社やしろの中、暗くら闇やみの奥に何かがあるのが、感覚外の知覚が把握した。
- それはホロホロドリの肉にも増した美味の予感。
- 匹敵するものはおそらくただ一つ。青年が笠かさ縫ぬいに抱く根源的な食い気。
- 笠縫のそれにも比すべき食い気を半に呼び起こすものがここに───?
- 「おい半、どうしたんだ、アンタふらふらと。逃げなくっていいのか、なんでそっち行く!?」
- 半はもはや、玉たま串ぐしも、我が身のことをも顧かえりみず。
- ふらふらと社へと吸い寄せられていき───
- 「其方、なんのつもりか、我が臥所ふしどに───無礼なる!」
- 妖女が袂たもとを打ち振れば、奇怪な寄生生物の咢あぎとのごとくぐわりと広がり拡大変容しつつ走り、半を呑のみこまんとするその布地、たとえ布地と見えてもその裡うちに包まれば肉は裂けて骨は砕けて、血汁は皆吸われよう。
- 「半───っ!?」
- 玉串の、迸ほとばしる悲鳴も虚むなしく半は背中からたちまちに呑みこまれる。
- かに見えて。
- 「───鬱うつ陶とうしい」
- 振り返りもせず、後ろ手で軽く払っただけ。
- 手を軽く、あっちに行けという風にひらめかせただけ。
- それだけで妖女の怪しき袂は力を失い、しなしなと崩れて地にたわみ───
- 誰より呆ぼう然ぜんとしたのは、追っ手衆でも玉串でもなく、ホロホロ様自身だったろう。
- 「───其その方、今何をした───?」
- 「は? ……え、なにが?」
- 力を失った袂を手た繰ぐり寄せて元に収める妖女に、振り返った半の眼まな差ざしは茫ぼう洋ようとして、今自分が何をしでかしたのか、彼自身理解していないらしかった。
- 「……いささか油断しておった。その気配の故ゆえか。何かの呪まじか術でも得ていると見た。それならばそれでよい。それでもやりようはいくらでも───これ。わたしの話を聞きやれ!」
- 妖女が声を荒げたのも当然で、半は皆まで聞かず、今度こそと奇岩の社の中に踏み入ろうとしていた。もう誰が止めようとしても間に合う機タイミングを逸し、半は社の中に───
- そこへ、声が、届いた。源定かではないが、居合わせた者の全ての耳に届く声。
- そして食い気に支配された半なかばの足取りさえ止める声。
- 『───お前さま。
- 見てはなりませぬ。触れるももってのほかじゃ。
- 見れば目玉が潰つぶれましょう。触れればお手が腐り落ちましょう』
- 「今の声は。ひどく癇かんに障さわる今の声は何」
- ホロホロ様が不快気に唇を歪ゆがめた時、沼地に鳴り響いた。汽き笛てきの音だった。蒸気機関車の。
- ざっと水音を立てて、沼地を割り、彼方かなたからホロホロ塚の水べりまで浮かび上がったものがある。線路だ。半にはそれが、先ほどの廃駅から繋つながっていることが無意識理に感じ取れた。
- 「───そして、なんじゃこれは。わたしの沼にこのような、無礼な───」
- 妖女が柳りゆう眉びを逆立てるうちにも沼の彼方で汽笛がまた鳴って、今度はそこに駆動音が続いた。幾重にも連つらなった動輪の。
- 沼の上を渡って重厚な機関車がどんどん近づいてくる。
- やがて動輪に制動の軋きしりをあげさせ塚の前に停車した、機関車の乗降口から降りてきたのは白しろ銀がねの髪の少女の形したもの。
- 笠かさ縫ぬいだった。
- 六
- 「今の世には覚えておる者とていなくなりました。
- したが半、それなるは塚でしての。今は名も失せた、古い妖あやかしの。
- ───その、ほんの一かけらの」
- 暗い足元にあの銀の光粒を散らしながら、危あやうげもなく降り立ち塚を眺ながめる笠縫は、いかにも全てを心得たように頷うなずいたものだけれど。
- その前に立ちはだかり強く咎とがめる、烏からす面めんの妖女がある。
- 「其その方は誰か。人ではあるまい。かといって妖というにも気配が薄すぎる。人にも妖にもなれぬ中途半端な混じり物のような。なぜそんなものが、招いてもおらぬのにわたしの沼に?」
- 「お酒を、供く物もつとしていただいたので、受け取りに来ただけのこと」
- 半が先ほど零こぼした酒のことを言っているのだろう。どうやら笠縫はその酒を辿たどってこの沼地に入りこんだらしかった。
- 「君の神しん出しゆつ鬼き没ぼつぶりは知っていたつもりだけど、それでもこのタイミングっていうのは……」
- 「だってお前さま、あそこはわたくしの駅だったのですよ。この幽かくり世よの沼に、わたくしの目印として残した。駅名にもちゃんと書いてありましたでしょうに」
- ああ、と今さらながらにあれは旧字体表記だったのかと、半なかばは了解した。つまりは青年は、笠かさ縫ぬいの名を冠した廃駅で、酒を捧げて、儀式のように瓶を叩たたき割り───
- 「さてお前さま、わたくしは確かに受け取りましたよ。ちぃとばかり控え目な量ではありましたけれど、じっくり味わうならあれくらいで十分。それで、わたくしに何を願われるのでありましょうや?」
- そう半と玉たま串ぐしに水を向ける笠縫に、激げき昂こうしたのがホロホロ様、沼御前、この幽世かくりよの主あるじである。
- いかに水際立って美しい笠縫だろうと、ホロホロ様からすれば己おのが領域への闖入者に過ぎないのだから。
- 「何を。許されぬ! その者たちは我が沼で肉を喫し酒を入れた、すなわちヨモツヘグイしたのじゃ。ここからは帰されぬ、帰れぬ、それが法というもの!」
- けれども笠縫はどこまでも平然と、臆おくしもせずに。
- 「その者たちにはヨモツヘグイなど意味を成しません。なぜなら玉串はそもそも幽世のものであるのだし。半は名前通り、冥めい途どに半ば足を踏み入れているもの」
- 「何を見透かしたような。わたしが其その方のごとき半端者の賢さかしら口を聞くとでも?」
- 「───額ぬか髪がみ。わたくしもままごと遊びに付き合うつもりはない」
- 名前───笠縫が呼びかけた言葉、それは名前。
- 「──────え───」
- 呼びかけられた途と端たんに、妖女は背骨に氷水、流しこまれたように身を烈しく震わせた。笠縫の言葉だけでひどく度を失っているのが、仮面を着けていても見て取れるほどの。
- 「わたくしは、かけらを埋めるに際して、ホロホロドリだのその肉で饗きよう応おうした捧げものなど、定めた覚えはない」
- ここでまた半はこれまで知らぬ笠縫に遭遇したのであった───
- 玉串を折せつ檻かんした時に幾らか似て、しかしその恐ろしさは桁が違った。
- 「のう半、お前さま。遠い昔に、一つの妖あやかしがありました」
- そんな笠縫に話しかけられて半は、どう答えたらいいものか見当もつかなかった。
- 「その時代にあってさえ、古い古い妖が。それは多くの姿をなし、様々な名を持った。けれど今ではその名は全て失われました───その妖が砕けて、散って、諸国の風土中に埋められ、封じられた時に」
- 「ただ、そんなかけらであっても、もとが古い妖だもの、時には悪性を発して、つまらぬ悪戯いたずらをするのです。その玉串のように」
- 「オレが……?」
- その場に遭って場の流れから取り残されていた玉串が、急に引き戻されたように、狼ろう狽ばいしてきょろきょろと自分を見回す。けれど彼女と出会った時、笠縫は呟つぶやいていなかったろうか。
- あれはどこのかけらやら、と。
- 「まあ、悪戯いたずら程度ならよろしい。けれど己が幽かく世りよに他者を引きずり込み、封じ込めて、供きよう犠ぎなど求めるようになっては目に余る。この、額ぬか髪がみのように」
- 「なぜ……其方ごときが、わたしの名を……」
- 「だってお前はわたくしの前髪だったのだもの。だから額髪。知らぬわけなどないだろうに」
- もうホロホロ様───額髪は完全に笠かさ縫ぬいに圧倒されて、妖姫が言葉を重ねるたびに、じり、じりと後じさる他知らず。
- 「そしてこの額髪の大元であった妖あやかしは、古い古い妖の名は、わたくしでさえもとうに忘れて、たまに心をよぎるくらい。今になってもまだ覚えている名前はね、半なかば、笠縫というのですよ」
- つまりは、それは。
- その古いにしえの大妖というのは、笠縫自身のことなのか。でもその妖は砕けて散ったと言った。
- 混乱する半に微笑ほほえみを投げて笠縫は、ホロホロ塚の社やしろのうちに手を差し入れ、何物かを闇の中から引きずり出した。
- それは何かの結晶の塊かたまりとも、艶つやめく万変の色合いの髪の束とも見えた。
- それを見た瞬間に半の食い気と飢えがまた発作のように襲いかかる。
- 「それだ笠縫、そいつを喰わせてくれ、一口でいい、お願いだ───!!」
- 半、妖姫の破片を喰わせてくれるよう懇願するも、却下されないわけがなく。
- 「お前さまはほんにぶれないこと。その芯はいっそ好ましくもありますが、なれど時と場合によりにけり、じゃ」
- 「ことに、これからこの額髪をとむらおうという時には」
- 「───わたしを滅ぼすおつもりか、貴女あなた───」
- 慈悲や容赦を見苦しく請いこそしなかったけれど、額髪は絶望の淵ふちに沈んで、ただただ沈痛に額ひたいを垂れるのみ。
- そんな額髪に、笠縫は───優しかったのである。
- 「何を今さら。滅ぼしていいのならとっくにやっています。とむらう、と言いましたよ、わたくしは」
- 「この幽世に誤って執着し、歪ゆがみ、悪性に堕したお前が、微笑んで彼岸に向かえるように、とむらうのさな」
- かくして───
- 始まるは───
- ───妖姫のおとむらい。
- あの白の杖、風鈴ライチを吊つるした杖を振るえば、夜の沼に響く鈴の音は、冴さえて、哀しく、けれど優しい。これは弔鐘であり、杖は弔とむらいの杖なのだ、と半は気づいた。
- 鈴の音に応じたように、沼の向こうから、先ほど半なかばたちを追い立てた小舟たちが戻ってくる。
- 笠かさ縫ぬいは軽やかに、額ぬか髪がみは沈ちん鬱うつな面持ちでこの舟に乗りこんで、そして暗い水の上を往く葬送が、今始まる。
- 「お前たちを流し遣りましょう───現世の汀なぎさから、彼世の岸辺へ、その先へ」
- 「お前たちは現世にあらざる者たち。お前たちの時は尽き、お前たちの居場所はもはや現世からは消えました」
- 「ああ、確かに生は言こと祝ほがれるものじゃが、しかしながら死すべき時に、ああ、よく生きた、と満足して死ぬるもまためでたきことです。だからお前たち───」
- 「おとむらいいたしましょうね、この笠縫が」
- 笠縫が舞い、踊り始める。
- 笠縫が拍子を踏むと、花が空間に生じて、舞い、さんざめく、その美しさ、儚はかなさ、清らかさは。浄化された哀しみというものの象徴のようだった。
- かつ、こちらも小舟に乗りこんでいたホロホロ沼の住人たちが楽器を鳴らす、鈴の棒を振れば、光の粒が舞い散り、躍る。
- 仮面を取り、宙に投げ上げればそれらもまた光の粒に化して昇華していって。
- 葬送だというのに、幻想的で、華やかで、まるで暗がりの中を喜びに満たされて進む、祝いの行列のようだった。
- 額髪ももう仮面を外していて、露あらわになったその双そう眸ぼうは、鼻び梁りようと唇に釣り合い、目も鼻も唇も、名工が大胆かつ丹念に仕上げたように彫りの深い美び貌ぼうだったけれど、船の上にはあっては死刑台に送られるがごとき表情で、それが次第次第に、朧おぼろ月づきが雲から出でるように、顔色明るく。
- いつしか笠縫の舞いに合わせて彼女もまた舞い始めていて、その唇にはやがて仄ほのかな、浄化されたものだけの綺き麗れいな微笑ほほえみが浮かび───そして葬列の船は、暗い沼の彼方かなたに消えていった。
- 七
- 山村は明けてみれば、窪くぼ地ちに繁はん茂もする緑の中にかろうじて形を残した、無人の廃集落だった。
- やがては自然の中に呑のみこまれていくのだろう。緑の中を流れている沢の脇に、朽ちかけている水車小屋が昨夜の『菊きく乃の井い』だったのだろうか。
- 半と玉たま串ぐしは、徹夜明けの目を擦こすりながら、窪地に下りていく細道から草に覆おおわれた廃屋を見下ろしていた。そんな半の傍そばに歩み寄る華きや奢しやな影一つ。
- 「どこか沢でも探して、お顔を浄きよめてきたらいかが、お前さま。随分と寝とぼけた顔をしていますよ」
- 「徹夜したんだか悪夢にうなされていたんだかよくわからない気分だよ、君。しかし、なんだ、その、あのまま彼岸まで行ってしまうかって思ったのに」
- 「あら。もしかして心配してくださったと」
- 「心配したんだか、厄やつ介かいなこととおさらばできると思ったのか、それもはっきりしない」
- 玉たま串ぐしも目をしょぼしょぼさせながら、笠かさ縫ぬいに問いかける。
- 「なー笠縫様。オレもアンタのひとかけだったってことだよな、昨夜の話だと。じゃあオレってどの辺りだったん?」
- 「はて爪の先やらどこかの肌のひとかけやら。あまりこまい分はいちいち覚えておらぬので」
- 「ひどい」
- 「なんにしても玉串、またおいたを致したりしたら、お前も流し遣ってしまうので、そのおつもりでいるように」
- 「ひぃぃぃぃ、しない、オレしない、オレおとなしくしてるから!」
- 「……なあ笠縫、君はここにかつての自分の『一かけら』が祀まつられていた、といったな? ってことは、ここ以外にもいろいろあって、同じような悪さをしでかしてるのか?」
- 「さて───」
- 笠縫がなんとも見やすく空っとぼけて山頂を見上げた時に、廃屋の方から一声だけ鳴り響いた、何かの、鳥のような獣けもののようなものの声。おそらくはホロホロドリの───
- 第四話・了
- 希
- Mareni
- 売文屋。好きな物。お酒。好きな飲み物。お酒。好きな食べ物。お酒。酒を呑んでは文を書き、文を書いては酒を呑む。そういう者に私はなりたい。(ただし書きながら呑んだりはしないようにする)
- 小学館eBooks
- 妖姫のおとむらい
- 2016年11月25日 電子書籍版発行
- 著 者 希
- 発行人 立川義剛
- 編集人 野村敦司
- 編 集 小山玲央
- 発行所 株式会社 小学館
- 〒101‐8001
- 東京都千代田区一ツ橋2‐3‐1
- s-ebook@shogakukan.co.jp
- 底 本 2016年11月23日 初版第1刷発行
- ⒸMARENI 2016 ISBN978-4-09-451641-8
- ※ご注意
- 本作品の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
- 個人利用の目的以外での複製など違法行為、もしくは第三者への譲渡をしますと著作権法、その他関連法によって処罰されます。
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement